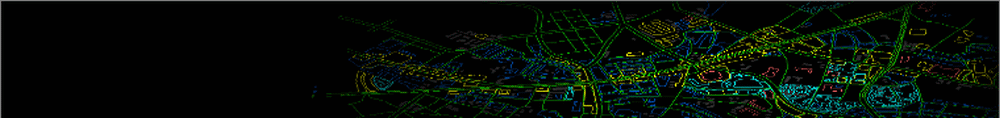アル・ジャズィーラ攻防戦5~
今回の海戦で、また海中の地形が大きく変わり、PLO軍のレーダーではポーツマスからドバイに帰るのも一苦労だろう。
一つ間違えたら、陸地をまた逆走した方が速いかもしれない。となると、今回の移動時間から見ても2日はかかる。
「まずは、ドバイに帰り、アッ・ザーリヤートを処理することにした。」
総旗艦バーンシュタインの円卓の中央で、いつになく冷たく言い放つアマンダの口調にそれぞれの艦隊長達はそれぞれの驚きの表現をしていた。第二艦隊長アレクセイなどは口笛を鳴らしてしまい、第三艦隊長の舘に机の下でつま先で足を踏まれ、逆に
「わっ!」
と大声を上げてしまい、皆の失笑を買ってしまった。
「理由はまぁ、それぞれあるが、まずは、導師が意外に今回の海戦で健闘したことが大きい。彼と、アッ・ザーリヤートが一緒になってもうまくやれるかは噂を聞く限りではかなり、疑問だが導師が主導権を持つようになればアッ・ザーリヤートもそれなりの戦略はたてられる人物だ。脅威となるに違いない。」
ビスファラシュの事件もある。妻からの一方的な離婚が認められないイスラム社会で、この義理の兄弟が大げんかをせずに仲良くできるかは疑問だ。
「次に、今回の海戦でも露呈したPLOのレーダーの質の低さだ。今回の海戦でまた海底が荒れた。導師は逆にポーツマスから動けまい。また、陸路を逆走するにしても二日はかかる。我々だとこの状況でなら1日で動くことも可能だ。」
第七艦隊長のアミル=マリナーズがここで質問した。彼の艦隊は今、今回の海戦の負傷者の看護と航行不能となった潜水艇の修理で追われている。
「では、我々が抱えている傷病兵と航行不能の潜水艇15隻はどうすればいいのですか?」
「俺たちの後をできる限りの速度でついてきてほしい。一応、アッ・ザーリヤートは導師と比べようがない程度の男だが、それでもわが軍にけが人は出るだろうからな。それなりの“病院”は必要だ。」
「しかし、北極の氷を溶かした後で、あのチャンネル男を処理してもいいのではないですかな。」
第五艦隊長のジャン=クローネが皆の心の中の意見を代表するようにこう言った。
アッ・ザーリヤートは陸戦を得意とする男である。その陸が無くなった後でゆっくり処理をしてもよいのではないだろうか?
とジャンでなくともショーンですら、思ったほどだ。
「ほう、諸君は、サウランドや、ロス島の悲劇をもう忘れたのかな?」
「…」
「俺は少なくともされたことの2倍は返す主義でね。アッ・ザーリヤートをコテンパンに産廃処理した後で、ドバイだのメッカだのを、水没させるのもまた一興だろうと思っているだけなんだかね。何しろ、あの戦争で、あの男はやりすぎた。地球上で数少ない快適な人が住める市街地を2つも居住不能にした。あの戦争で、親を亡くしたり、故郷を亡くした子供たちもいるし、そんな経験を持つ者も君たちの中にもいるはずだ。これは忘れてはならない。」
ポーツマスの導師の機嫌は悪くなる一方だった。
とにかく海図が不明で、演習すらできないらしい。
軽潜水艇がこんなところで活躍するとは思ってもいなかったが、やはり機械ではなく、人間の目での確認だ。完ぺきを求めるのもどうか、と思ってはいたが、それなりの海図が完成するのは2週間も先の話らしい。
(あの山猫に完全にしてやられたな)
PLO軍の頭の中には海戦などの選択肢など今までなかったのだ。
特にテロリストあがり、といわれるのを恐れ、嫌がる彼らは、当時の主流であった空軍の増強に特に力を注いできた。
今回のように150M以上空を飛んだら撃墜される事態などだれも想像していなかったのだ。PLO空軍の空母の中には縦幅のみで100Mをこえるものが多く、実質空など飛ぶことは不可能になった。
大体、第三次世界大戦の際、海に核爆弾を落としたり、南極の氷を人工的にとかして人が生活できるようにしたため、地球時代とは海流も海図も全く異なっている。
元々、イスラムの人々は不要と思われることに関しては関心を持たない人種だ。
宗教を持つ人たちに多い傾向なのだが、一つの価値観が個人の価値観を超えてしまい、個性的な考え方ができにくい背景があるのだろう。イスラム教はその冠たる宗教ではある。彼らが人口や、その教義の割には世界宗教になり得なかったのはその考え方や、閉鎖性も大きいだろうし、元から、あのシュケルですら、海戦は弱かった。正直、苦手分野なのだ。
これも宗教を信じる人に多い傾向なのだが、苦手な分野、都合の悪い分野になると覆い隠そうとする傾向が大きい。
通常なら、一応は調べておいておくべきことだったのだろうが、全く海底の変化何など興味のなかった彼らは、それすらもしていなかった。
恥ずかしながら、導師もその一人だった。ただ、その中で、間違いに気づき、軌道修正する速さはやはりさすがはアマンダの好敵手として歴史に名前を残すだけはあった。
だが、それにしても、と導師は思うのだ。なんで、こんなに皆の動きが遅いのだろうか?
当初感じていたよりもさらにさらに、いやな予感がしてきた。
それを振り払うためにも彼は戦線に立つことにしたのだが、もう遅いのではないか?
という恐怖と彼はこの先死ぬまで戦うこととなる。
元より宗教家である。元は楽天的で希望の人だ。その上、シャルマシュという彼にとっては唯一甘えられる女性もいた。だから最後まで人格のバランスを欠くことなく戦えたのだと思われるが、その恋人ともうわさされるシャマシュ=アル=ブルーシュは、このポーツマス以降、導師の最後まで、そばにいることになる。
身の回りの世話は十二分にできるこの男だから、特に必要なかったかもしれないが、話し相手になってやったり、お菓子を旗艦アル・アーディヤートの艦長室に持っていってやったり、なにくれとなく世話をしていた。
導師が何の気兼ねもなく話ができるのはなぜか女性に限られており、妹のビスファラシュと、このシャルマシュだけだった。そのため、そのころの導師の苦悩を物語るエピソードが彼女の日記につづられている。
「珍しく、洗濯をしていなかったので、全自動の洗たく機で乾燥も済ませてベットの上に置いておいた。
それを見て導師は感謝してくれたが、彼には珍しいことだったので、
『珍しいですね』
と尋ねたところ、このところ、考え事が多いので、それどころじゃない、という話だった。
以前はパスタを作りながら、来週の説教を考えていた人だったのに。」
という記述である。
おそらく導師という人物は何か手を動かしたり体を動かしながら色々考えたり、ひらめいたりするタイプだったのだろう。ある意味、アマンダより女性的な脳をしていたのかもしれない。
表面上、この男は、寡黙で厳格なイメージが付きまとうが、
意外におしゃべりが好きな兄だった、とのビスファラシュの証言もある。
しかし、PLO側の記述にはこういう証言はない。少々のこと、たとえばビシュファラシュの家出騒動の時もそういった記述はない。毎朝5時に起き、礼拝を終え、家事をした上で職務に入る。そういう人物が生活のリズムを狂わせるほどやはり、今回の問題は大きかったに違いない。
「どうだ、俺の方がいい男だろう」
と同じクラブで、カート=シュナイダーが導師の写真と自分の写真をおねぇちゃんたちに見せて、どちらがかっこいいか色々聞いているのをベケーレ=ミルは少々苦々しく聞いていた。
となりのフロアであるが、酒を飲むとこのカートという男は、驚くほど気前が良くなり、店中のおねぇちゃんに日給分のチップをやることで有名だった。その上、おそらくもともと声も大きいのだろうが、酒が入ると止まらなくなるらしい。
ベケーレ=ミルは意外にも、こういう高級クラブではお気に入りの美女と静かに酒を飲みたい気分なのだが、“元首さま”は違った考えの持ち主らしい。
元より華やかな男だ。
今は娘と目されるアマンダ=シュナイダー=ヨーゼフがユリウス=カエサルに例えられることも多いが、元はこの人自身もそう目されていた時代もある。
「ただ、借金王だった時代までだよ。アマンダは、そのあとのカエサルだよ。」
と自分で言っていたと、タブロイド紙には書かれていたが、大体、自分の娘が戦地にあるこの状態で、酒場のおねぇちゃんの嬌声の中にいる神経が理解できなかった。
このことはすでにラフマーンもカートには自重するよう注意していたはずだったのだが、カートとしては、娘の才能を信頼していたし、安心もしていた。
その上、自分までが戦時の状況にあると、月の経済にも影響する。
今のところ、裏では連合政府にかなりの出費はしているものの、それはあくまで、政治の世界からではなく、軍需産業という民間企業の名前を借りたものであり、彼としては毎日の生活まで変える必要性がなかったのだ。
「ちょっと、お話あるんやけどな。」
ベケーレ=ミルはバーボン片手に上機嫌のカートに近づいた。
セキュリティもつれていないのか、“元首様”はご機嫌なものである。
マフィア王と呼ばれたこの男に水割りを作って飲ませてやるように横のおねぇちゃんに指示した。
「あんた、自分の娘が戦地にいっとんやろ、えらい上機嫌みたいやけど、心配やないんか?」
「ああ、大丈夫だと思ってるよ。」
明らかに違う世界の住人の言葉遣いにも平然と答える“元首さま”だ。
長男のミケーレはああいった芸術家肌だ。二男のラフマーンは生真面目な男だ。で、娘のアマンダが一番こういう時に使える人材だ。
と、今までのアマンダの“武勇伝”を得々とマフィア王に自慢するかのように話す“元首さま”だ。
(この父にして、この子ありだな)
その程度の格言はベケーレ=ミルは知っていた。
それにしても、一度アマンダ=シュナイダー=ヨーゼフに会ってみたいものだ。
どんな女なのか?
今度アレクセイにでも頼んでみよう、と思ったその矢先に、“元首さま”はベケーレが思ってもいなかったことを聞いてきた。
「今度のカジノはいつ完成するんや。パチンコもそろそろ飽きたし、この辺はみんなカジノできるの待っとるで。」
自分が誰であるか、もうばればれらしい。
見事なやくざ言葉にももう驚きもしない。アマンダも酔えばこういう言葉になるという噂をアレクセイから聞いたことがあった。
「戦争が終われば、の話ですわ、旦那。カジノやパチンコは平和な時代にこそ皆に楽しんでもらえるもんやと俺は信じとるんでね。」
戦争の恐怖に耐えられなくなった不良兵たちに需要が最近高まっている麻薬関係のビジネスも細々とはしていたが、最近、ロス島のカジノが完全に破壊されたため、実入りが少ないという幹部連中の声もあったが、ベケーレは潤沢な資金もあるので、心配は必要ない、と常々話をしていた。
そのベケーレの襟を突然引っ張ったのがカートだった。一瞬、その場が凍りついたが、
カートの笑顔の方にベケーレは凍りついた。こんな経験はこの立場になって初めてに近い。
美男子だが、その笑顔にはある種の凄味があった。
「あんた、戦争は地球の話やろ。この月は平和なんや。安心して店だしたらええやん。何のために娘を地球にやっ取る思てるんや。あいつがおる限り、ここは平和や。それだけはわしが保証したる。ほやからはよう、こっちに本拠地移してこいや。」
月の”元首さま”と、地球のマフィア王との衝撃の初対面であった。
こののち、ベケーレはあらゆる意味で、このシュナイダー家とかかわりを持つことになるのだが、
あの”元首さま”そこまで言うのなら、と、ベケーレやその部下が調べた限りでは、カートの勧誘で、かなりの連合政府の優良企業が月に本社を移しているという事実が判明した。
地球の時代は、本当に終焉を迎えようとしているのだ、と、さすがにベケーレも思わざるを得なかった。“元首さま”は本当に策士で、非常に有能なビジネスマンの側面もお持ちであるらしい。
娘が地球で暴れていることに気を取られている間に、すっかり地球の経済は骨抜きにされてしまっていたのだ。
この時代、地球の役割は、あのドバイを除き、すでに戦場としての役割にしか、すぎなかった、とのちの歴史書にも書かれている。
© Rakuten Group, Inc.