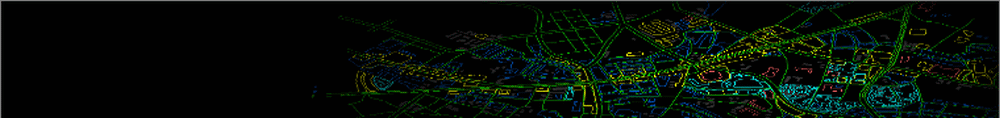アル・ジャズィーラ攻防戦7~
たとえば、もう少し導師の身辺を詳しく監視させることも可能だったし、また、足元をこれ以上すくわれないように彼にはできることはなかったのだろうか?
導師の注意深い性格と、一見約束を必ず守る”律儀”な性格と、時に“偽善”ともとられかねない行動が彼を惑わせたことも大きいが、アッ・ザーリヤート自身の性格の問題も大きかった。
人のミスを許さない割には自分や自分の仲間には寛大だった、という所が大きく作用したと思われる。
つまり、彼の周りにはいつもオブラートに包まれた現実しかなかったのだ。
導師との関係も、妹ビスファラシュの不貞の騒ぎもあり、借りを作っている、といった形で、“恩を着せていた”という。
まさか、導師とアマンダがこの時期、共闘関係にあったとは夢にも思っていなかったに違いない。
目の上のたんこぶが消えた、といわんばかりに、彼はドバイ王のようにふるまっていたといわれる。
連合政府側に、“チャンネル男”といわれ、小馬鹿にされていたことを知ったのは、本当にその一生の終わりの時だった。
「ほう、やりたい放題だな。」
カートならうらやましく思うだろう、とラフマーンが思っていた通り、彼の父はアッ・ザーリヤートを羨ましがっていた。
とにかく美女の宝庫といわれるエルサレムとドバイのいい女はすべてハーレムに入れているらしい。
「残り少ない人生を楽しんでいたらいいんじゃないのかな?」
可哀そうだが、昨日のアマンダとの会話で、アッ・ザーリヤートにこれから起こるであろう哀れな運命を知ったラフマーンは冷たくこう言い放つ。
昨日、ミケーレから同じく連絡があり、当世を代表する画家になっていた彼にアッ・ザーリヤートがなんと“自画像”を依頼してきたという話を聞いた。
ミケーレが誰の兄であるか、わかって言っているのだろうか?とこの話はアッ・ザーリヤートの周り1キロ圏外の人々が失笑するようなエピソードである。
それをラフマーンから聞いて苦笑するカートだった。
「まぁ、葬式のときは役に立つだろうよ。」
「それがミケーレは断ったらしいですよ。」
「バカだなぁ、引き受けてやればいいのに。チャンネル男の最期、とかな。」
その時、ちょうどあったアッ・ザーリヤートが写ったタブロイド紙にカートは鼻歌交じりで当世切っての人気画家の父とは思えない絵心の王冠を書きくわえ、その下に
“チャンネル男の最期”
と書いた。その新聞をそこらに放り出して、最近息子以上に孫娘にご執心の祖父はジョシュアと孫娘カメリアにお別れのキスをして家を出た。結局父親にはなれなかったがいい祖父にはなれた男だった。
あの例の“キス事件”の直後の話である。
恨めしそうに父を見送る息子だった。
毎朝、必ず出かけるときはキスをしてくれているはずのジョシュアだったのが、たまたま爪を伸ばしすぎていたのが発覚した原因だった。
さすがに顔を引っ掻かれ気づいたのだろう、一応ラフマーンは激怒した。
「今まで、ずっとそうだったのか!」
「だって恥ずかしいじゃないの!私の趣味じゃないもん。それにあなたももう、パパなのよ、パパ。ねぇ、カメリアちゃん。」
と一蹴されてしまった。かわいい娘を盾にされてしまったらさすがのラフマーンも何も言えない。ぶつぶつ言いながら私室に立てこもり、珍しく娘のカメリアを風呂に入れなかった。その程度の反抗しかできないラフマーンはやはり、後世の人が言うように“平和の人”なのだろう。時にさすがはアマンダの兄だ、と思わせるところはあったが、常に平和的で物腰も穏やかである彼の個性は謎に包まれたその母親の個性そのものなのかもしれない。とジョシュアなどは思うのだ。
一方、この3兄弟の中ではある意味一番個性的であったミケーレの息子はサルバトーレと名付けられた。
この子は、カートに非常によく似ていた。隔世遺伝。という言葉をミケーレは何度も思い出した。妻のマリーナと苦笑するほど、顔もそうだがやんちゃな性格もカートそのものだった。ミケーレもマリーナもおとなしい子どもだった、という話をそれぞれの幼少期に育ててくれた人々から聞いている。しかし、サルバトーレの夜なきの凄まじさは一時笑いどころではなかった。
いまだにやんちゃぶりはとどまるところを知らず、80歳を超えているもののまだまだ元気なカートとアマンダのの乳母が世話に行っているという話だ。
しかし、夜の世話までは無理は言えない上に、本当は自分達だけで育てたいという以降の強いマリーナの意向で、夜の間の世話は彼女とミケーレの交代制になっている。おかげでマリーナの女優への復帰の時期は未定のままだし、いまだに小学校の先生でもあるミケーレの寝不足も続いている。
「サルバトーレを見ていると父さんを良く思い出すんで。」
結婚前などはこちらが連絡しても返事一つよこさなかった長男だったが、何故か、最近よく連絡をくれるようになった。
何か心境の変化でもあったのか?とカートが聞いたところ、こういう答えが返ってきた。
ということはアマンダに似ている、ということだろうな。
最近、杉野にそう言われて、改めて実感したのだが、ますます、アマンダと自分の顔が似てきていることに気がついたばかりだ。今度、エルザにこっそりもう一度再確認をしてみようと決めたカートだった。
それにしてもあの”娘”はどんな孫を産むつもりなのだろう。
楽しみなような少々心配な”父”なのであった。
あと、明日はアル・ジャズィーラ側のドバイ基地攻略の軍議があるらしい。
その結果も気になる。
2081年5月18日。
第8艦隊の修理も終わり、第13艦隊が南極から引っ張ってきた深海に沈めた中古の宇宙ステーションには1万人の陸軍の精鋭が出撃は今かと待ちわびている。
その陸軍の元帥であるテンも出席して軍議が行われた。
この艦隊の軍議は一風変わっている。
大体がアマンダの頭の中で組み立てられていて、それぞれの艦隊はパーツパーツで分けられてその方向へ動くだけだ。
またしばらくしてアマンダの指示があればその方向へ向かい、その戦略のパズルの上を他の艦隊の邪魔にならないようにスムーズに動くことのみが求められる。
何か質問があれば、素直に質問すればすぐに答えは返ってくる。
全体の動きをまとめてもよくわからないことが多いが、それなり以上に戦果は上がっているので、今のところこのやり方に文句を言う隊長はいなかった。
ある程度の指示が終わり、質問の時間が設けられた。
意外に質問が多いのが、第七艦隊の隊長のアミル=マリナーズだ。
この艦隊の与えられた任務は他の艦隊とは違う。“赤十字艦隊”というあだ名を頂戴し、他の艦隊の負傷者や、航行不能になった潜水艇を補修するという仕事が待っていた。
そのため、その出撃するタイミングや、どこまでフォローすればいいのか?等聞くことは他の隊長達よりたくさんあったし、本来は勇猛な隊長ではあったが、その素直さ、率直さを買ってアマンダはこの男をこの任務につけることにしたのだ。
「もしかして、敵の捕虜が艦内で暴れ出したらどうしましょうか?」
「捕虜を保護する必要はない。」
他の隊長たちが目をむくようなことをアマンダは口にした。
「理由は数点あるが、彼らはおそらくは陸から動くことはないだろうし、彼らは彼らで負傷者の搬送ぐらいは考えておくべきである。今後我々の艦隊は捕虜を持つことは一切禁止する。たとえ、それが瀕死の重傷者であっても、だ。」
赤十字ができた時代はせいぜいあったとしてもダイナマイトぐらいの爆弾で、重傷者が隠すことができるものではなかった。
しかし、この時代は月ではすでにペン型の核爆弾が開発されている。
いくら科学的に遅れているPLO軍であったとしても、重傷者に爆弾を持たせることや、有毒な物質を持たせることは可能だ。
人道的には確かに問題であるかもしれないが、そんなものを持ち込まれてしまっては戦争にはならない。実際、シュケルも何度かそのような方法で暗殺されそうになったこともあるという。
「しかし、捕虜はどうしても出るでしょう?」
第三艦隊の舘が思わずこう口にした。
「捕虜は、武装解除した後、すぐに開放することだ。そこが放射能汚染地域であろうが、深海であろうが関係はない。何を持っているかわかったものではないし、狭い潜水艇で爆発されたり、ばらまかれては困るものが最近増える一方だしな。」
そのアマンダの言葉を聞いても嘆息したり、沈黙する隊長たちにテンはこう補足した。
「仕方がない決断ではあるでしょうな。
結局、一時は史上最強を歌われたシュケルの軍隊が崩壊したのも、ネクストアルカイダのあの豊富な富が枯渇したのも捕虜だか難民だかを山のように抱えてしまったからだ。我々にとって、シュケルの寛容さは、幸運につながった。
一見冷たいようだが、こうすることで、彼らにより大きな恐怖を与えることもできる。捕虜になれないと分かれば、逃亡者も増えるだろう。」
シュケルと同じ失敗をするわけにはいかない。ということをテンは経験から知っていた。
この話は、すでにアマンダが南極を出発する直前に杉野に伝えており、その考えはそのままテンに伝えられていたのだ。
「俺の言いたいことはテン元帥が代弁してくれた通りだ。元から厳格な軍隊として存在する連中ではない。それぞれの武装勢力が集まっただけの烏合の衆だ。何かあったら捕虜にしてもらって生きて帰れる、とぐらい考えているに違いない。それが無理なことだということが分かれば、彼らのうちのほとんどは脱走兵となり、必ず自壊する。」
アマンダの考えはいつでもシンプルだった。
捕虜を連れて移動するのはいつもリスクを伴う。その上、彼らは機械ではない。確実に毎日食料を減らしていくのだ。その上、捕虜を人質にして何かを交渉するほど、アマンダは困った経験をしたことも、今後もすることもない。ただ、少佐級以上のものは厳重なボディチェックの後捕まえておくように、と指示はした。彼らの情報はその一日分の食料を十分にフォローできるものだろう。その上、下の者は追い出されるのに、上の者のみが保護されるとなると、“内通者”という噂も出、もっと相手の士気に影響をもたらすことになるに違いない。
「しかし、我々の負傷兵が捕虜になった場合はどうすればいいのですか?」
「大丈夫。あの激戦の第一次ポーツマス海戦でもなかったことだし、今回もあり得ないことだ。陸軍兵は少々のリスクは伴うかもしれないが、そのための万端の準備をテン元帥には用意してもらっている。その上、海軍は、今回彼らと接触する機会はないだろう。」
言われてみればそうだった。
一見、どうすれば海戦になるのか、と言っていいほどドバイ周辺は大きな遠浅に守られているようだった。上からのレーザーやミサイル攻撃には万端の準備を整えているドバイにやって来るには、まず、陸軍が必要だろう、とアッ・ザーリヤート側は考えていた。統括軍側にそれだけの陸軍はいない、と思われている。事実敵の30万人に対して統括軍側はわずか1万人である。
ただ、その遠浅に苦しんだのは彼らの海軍である。そのわざわざイージス艦や潜水艇が出られるように運河を作ったぐらいだった。
その二つの状況に目を付けたのがアマンダだった。
相手の盲点が焦点となるゆえにだれもまねができない、とのちの歴史家に嘆息させた、といわれる、これがこの人の戦術である。
ついにドバイ攻略戦が始まる前の日の話である。
ドバイ側もそれなりに当時としては難攻不落と言っていいほどの要塞都市を形成していた。
連合国軍の戦車は、南極攻略の際のロス島を争う戦いで、ほとんど失っているはずだった。
その代りにアマンダが準備していたものは…まさかこんなものがこの時代に登場するとは、PLO軍側も思っていなかったに違いない。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- マンガハックさん閲覧数総まとめして…
- (2025-11-17 11:55:02)
-
-
-

- お勧めの本
- 「海のてがみのゆうびんや」海で迷子…
- (2025-11-16 19:10:04)
-
-
-

- 楽天ブックス
- HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY…
- (2025-11-18 10:54:57)
-
© Rakuten Group, Inc.