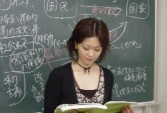問題1~25問
宅建 平成15年度試験問題
〔問 1〕 意思無能力者又は制限能力者に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはど
れか。
1 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,取消しの時点から将来に向かって無効となる。
2 未成年者が土地を売却する意思表示を行った錫合,その未成年者が婚姻をしていても,親権者が当該意思表示を取り消せば,意思表示の時点に遡って無効となる。
3 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,成年後見人は,当該意思表示を取り消すことができる。
4 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合,保佐人は,当該意思表示を取り消すことができる。
〔問 2〕 Aは,Bとの間で,E所有の不動産を溝入する売買契約を締結した。ただし,AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき,その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく,その他特段の合意もない。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。°
1 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効 力が生じていないので,Aは,この売買契約を解約できる。
2 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていないので,Bは,この売買契約を解約できる。
3 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に,Aが死亡して続が開始された場合,契約の効力が生じていないので,Aの相続人は,この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
4 Aが,A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して,故意に停止条件の成就を妨げた場合,Bは,その停止条件が成就したものとみなすことができる。
〔問 3〕 Aは,自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが,Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合,民
法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Cが,AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け,所有権移転登記を得た場合,CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。
2 Dが,Bを欺き著しく高く売りつける目的で,Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて,Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合,DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
3 Eが,甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても,その後Bが所有権移転登記を得てしまえば,以後,EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。
4 AとFが,通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し,所有権移転登記を得た場合,Bは登記がなくとも,Fに対して甲地の所有権を主張することができる。
〔問 4〕 A,B及びCが,建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)に関する次の記述のうち,民法の規
定によれば,誤っているものはどれか。
1 Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。
2 Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
3 Aが,その共有持分を放棄した場合,この建物は,BとCの共有となり,共有持分は各2分の1となる。
4 各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが,5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
〔問 5〕 Aは,B所有の建物に抵当権を設定し,その旨の登記をした。Bは,その抵当権設定登記後に,この建物を
Cに賃貸した。Cは,この契約時に,賃料の6カ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Bが,BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し,対抗要件を備えた後は,Cが当該第三者に弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。
2 Bの一般債権者であるDが,BのCに対する賃料債権を差し押さえ,その命令がCに送達された後は,Cが弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債椎を差し押さえることはできない。
3 Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は,Cは,Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。
4 Aが物上代位権を行使して,BのCに対する賃料償権を差し押さえた後,賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合,Aは,当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。
〔問 6〕 普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいも
のはどれか。
1 普通抵当権でも,根抵当権でも,設定契約を締結するためには,被担保債権を特定することが必要である。
2 普通抵当権でも,根抵当権でも,現在は発生しておらず,将米発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
3 普通抵当権でも,根抵当権でも,被担保債権を譲り受けた者は,担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
4 普通抵当権でも,根抵当権でも,遅延損害金については,最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。
〔問 7〕 Aは,Aの所有する土地をBに売却し,Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合,AがCに対して保証債務の履行を請求してきても,CはAに対して,まずBに請求するよう主張できる。
2 Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,AがCに対して保証債務の履行を請求してきても,Cは,Bに弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることを証明することによって,Aの請求を拒むことができる。
3 Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合,Cに対する履行の請求による時効の中断は,Bに対してもその効力を生ずる。
4 Cの保証債務にBと連帯して漬務を負担する特約がない場合,Bに対する履行の請求その他時効の中断は,Cに対してもその効力を生ずる。
〔問 8〕 Aは,Bに対して貸付金債権を有しており,Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で,Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき,BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。
2 Bが債権譲渡を承諾しない場合,CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは,CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
3 Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し,Cへは確定日付のない証書,Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で,いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき,Bへの通知の到達の先後にかかわらず,DがC
に優先して権利を行使することができる。
4 Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し,Cへは平成15年10月10日付,Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で,いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき,Bへの通知の到達の先後にかかわらず,EがCに優先して権利を行使することができる。
〔問 9〕 同時履行の関係に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
1 動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは,同時履行の関係に立つ。
2 目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは,同時履行の関係に立つ。
3 貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは,同時履行の関係に立つ。
4 売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。
〔問10〕 Aが,BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが,建物の主要な構造部分に欠陥が
あった。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。なお,瑕疵担保責任(以下この問において「担保責任」という。)については,特約はない。
1 Aが,この欠陥の存在を知って契約を締締した場合,AはBの担保責任を追及して契約を解除することはできないが,この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
2 Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締締した場合,Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる。
3 Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ,AはBに対して担保責任 を追及することができなくなる。
4 AB間の売買契約が,宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合,Bに対して担保責任が追及できるのであれば,AはCに対しても担保責任を追及することができる。
〔問11〕 借主Aは,B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し,敷金として賃料2カ月分に相当する金額をBに対して支払ったが,当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
1 賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず,Aの建物引渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。
2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で,Cが賃貸人の地位を承締したとき,敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。
3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で,Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき,敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。
4 賃貸借契約が終了した後,Aが建物を明け渡す前に,Bが建物をEに譲渡した場合で,BE間でEに敷金を承継させる旨を合意したとき,敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。
〔問12〕 Aが死亡し,それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B,C及びD(他に相続人はいない。)が,全員,単純承認し,これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
1 相続財産である土地につき,遺産分割協議前に,Bが,CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし,これを第三者に譲渡し,所有権移転登記をしても,CとDは,自己の持分を登記なくして,その第三者に対抗できる。
2 相続財産である土地につき,B,C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後,遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合,その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し,所有権移転登記をしても,
Bは,単独所有権を登記なくして,その第三者に対抗できる。
3 相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は,遺産分割協議が成立するまでは,相続人3人の共有に属し,3人全員の同意がなければ,その債務者に弁済請求できない。
4 Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合,CとDは,遺産分割協議の成立前でも,自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。
〔問13〕 Aが,Bに,A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し,Bがその土地上に乙建物を新築し,所有して
いる場合に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 Bが,乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は,甲地につき賃借権の登記をしていないときでも,甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し,甲地の賃借権を対抗できる。
2 乙建物が滅失した場合でも,Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは,Bは,甲地に賃借権の登記をしていなくても,滅失のあった日から2年間は,甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し,甲地の賃借権を対抗できる。
3 Bが,乙建物をEに譲渡しようとする場合において,Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず,Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは,Bは,裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。
4 Bが,乙建物を1年以上自己使用しておらず,かつ,他人に譲渡しようとすることもない場合,Aは,裁判所に,相当の対価の提供を条件として,自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。
〔問14〕 平成15年10月に新規に締結しようとしている,契約期間が2年で,更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。)に関する次の記述のうち,借地借家法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては,定期借家契約とすることはできない。
2 定期借家契約は,公正証書によってしなければ,効力を生じない。
3 定期借家契約を締結しようとするときは,賃貸人は,あらかじめ賃借人に対し,契約の更新がなく,期間満了により賃貸借が終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 定期借家契約を適法に締結した場合,賃貸人は,期間満了日1カ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば,その終了を賃借人に対抗できる。
〔問15〕 不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 不動産の登記申請において,申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には,申請人が即日にこれを補正したときでも,登記官は,理由を付した決定をもって,当該申請を却下しなければならない。
2 抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,申請書には,当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
3 登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人 は,過去に登記を受けた者でなければならないが,当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者は,保証人となることができない。
4 登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合でも,法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは,別に当該第三者の許可を証する書面を添付しなけれ
ばならない。
〔問16〕 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000 平方メートルの土地をBに売却する契約を,Aと,Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合,CはC名義により,事後届出を行う必要がある。
2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000 平方メートルの農地をEに売却する契約を,崖地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合,Eは事後届出を行う必要がある。
3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000 平方メートルの一団の土地を分割して,1,500 平方メートルをGに,3,500 平方メートルをHに 売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合,Gは事後届出を 行う必要はないが,Hは事後届出を行う必要がある。
4 甲市が所有する市街化区域に所在する面績3,000 平方メートルの土地をIに売却する契約を,甲市とIが締結した場合,Iは事後届出を行う必 要がある。
〔問17〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。
2 第一種住居地域は,低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり,第二種住居地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
3 高度利用地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
4 地区計画は,市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について,その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
〔問18〕 開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500 平方メートルの土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
2 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000 平方メートルの土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
3 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000 平方メートルの土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
4 準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした5,000 平方メートルの土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
〔問19〕 開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
1 開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,開発許可を受けた者は,工事用の仮設建築物を建築するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は,建築物を建築してはならない。
2 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,民間事業者は,都道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
3 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,民間事業者は,都道府県知事の許可を受けて,又は都市計画事業の施行としてでなければ,建築物を新築してはならない。
4 都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
〔問20〕 防火地域内において,地階を除く階数が5(高さ25m),延べ面積が800 平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で,その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 当該建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
2 当該建築物について確認をする場合は,建築主事は,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
3 当該建築物には,安全上支障がない場合を除き,非常用の昇降機を設けなければならない。
4 当該建築物は,外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
〔問21〕 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において,条例で,建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。
2 建築協定においては,建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は, 建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
4 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができる。
〔問22〕 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 換地処分は,施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
2 施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の毛地の上に存する。
3 換地処分に係る公告後,従前の宅地について存した抵当権は消滅するので,換地に移行することはない。
4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は,換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管轄に属する。
〔問23〕 農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合,農地法第5条の許可を得る必要はない。
2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合,あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要 はない。
3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合,農地法第4条の許可を得る必要はない。
4 遣産の分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条の許可を得る必要はない。
〔問24〕 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)に関する
次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法の指定都市等にあっ
ては,それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
1 規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ,現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合,当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
2 規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で,当該宅地に高さ1.5mのがけが生じ,かつ,その面積が600 平方メートルのときには,造成主は,あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 新たに指定された規制区域内において,指定の前にすでに着手されていた宅地造成に閲する工事については,その造成主はその指定があった日から21 日以内に,都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後,宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは,都道府県知事は宅地の所有者に対して,当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。
〔問25〕 次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 地すべり等防止法によれば,ぼた山崩壊防止区域内において,土石の採取を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 港湾法によれば,港湾区域内において,港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は,原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3 文化財保護法によれば,史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4 自然公園法によれば,環境大臣が締結した風景地保護協定は,当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては,その効力は及ばない。
© Rakuten Group, Inc.