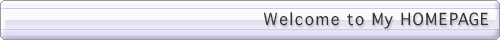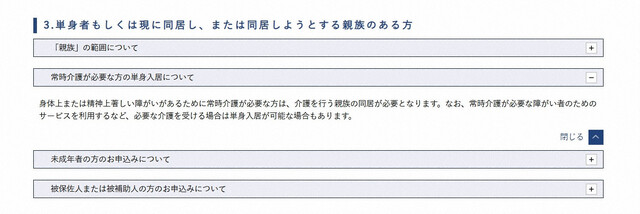けた違いのエネルギー
今夏の天候の大きな特徴は2つ。
6月以降に、高温の日が連続し多くの地域で暑さの記録を更新した。
もう一つは台風の発生数と日本への上陸数が多かったこと。
かつて、農業をはじめ経済活動に大きな被害をもたらした台風は、ともに15号。
洞爺丸台風や伊勢湾台風が有名。
1991年の「りんご台風」は19号で、青森県の農家を悲しませ、
翌年の受験シーズンでは合格リンゴで復活した。災い転じて福と成す農家の知恵。
台風は熱帯の海の膨大なエネルギーを温帯地方に運び、
暴風や大雨にともなう大きな被害を与える。
一方で、北太平洋地域の温度調節の役割を果たす。
昔から「台風一過の秋晴れ」が知られている。
厳しい残暑が続いている時に、台風が日本の太平洋沿岸沖を通り、
東海上に抜けるコースを進む時に起きやすい。
これは、シベリア大陸の秋の空気を運び込み、一気に涼しくなるからである。
逆に、台風が日本海を北上するコースでは、南の高温多湿の空気が流入し、
今年のように猛烈な残暑が続くこととなる。
熱帯の暖気を温帯に運んだり、
大陸育ちの冷涼な大気を引き出したりという大きな力を持っているのが台風である。
そのエネルギーは、中型で10の24乗エルグとなり、
広島に投下された原爆の2000個分に相当する。
伊勢湾台風級の超大型では、エネルギーのランクが1桁上がり、
各方面に甚大な被害をもたらす。
これらは台風本体のエネルギーであり、
9月になると台風に刺激された秋雨前線の影響が加わる。
秋台風の進行方向を的確に見極めて、
農作物の収穫や播種の対策を誤らないようにしていただきたい。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- みんなのレビュー
- 【レポ】便乗した、訳ありお得なザク…
- (2025-11-30 10:39:50)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 22歳Iカップグラドル カーディガン…
- (2025-11-30 23:00:06)
-
© Rakuten Group, Inc.