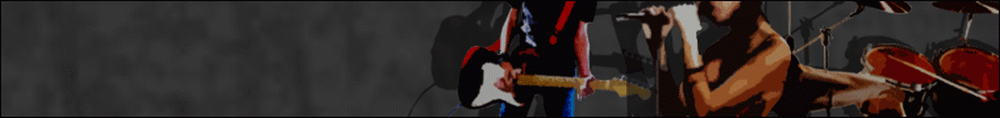トランペット
トランペットトランペットまいさんからのリクエスト

トランペットの歴史
そもそもの名前の由来は、ものの本によると「strombos」という貝殻の一種を意味するギリシャ語から来ているらしい
が、定かではない。そこから「trompe」に変化していったらしい。
要するに円筒の部分が多い楽器をトランペットという。
これに対して円錐の部分が多い楽器は現在のホルン、コルネットなどに代表される「corno」、つまり角とか牙 等を語源とする楽器である。
このトランペットとコルネットは現在では ほとんど同じ様なものとして扱われているが、両者は起源は異なっており、つい100年程前までははっきりと区別されていた。
バルブが発明されてから両者の関係は急速に近づいていった。
金管楽器全体の歴史は非常に古く、おそらく太古からあったと思われる。
打楽器に次に歴史のある楽器ではないだろうか。
昔々、あるところに筒状のもの(多分動物の骨)が落ちてましたとさ。
それを拾った古代人はそっと口に当てて息を吹き込んでみました。
すると あらびっくり!自分の唇がふるえて「ブー」と音が出たではありませんか!
これが金管楽器の始まりです。でもこの古代人は現在でいう中近東、ヨーロッパに住む西洋人の祖先だったのです。
我々の先祖達は少し骨格が西洋人とは異なっていました。
東洋人の祖先は 筒状のものを拾って口に当てても音は出ませんでした。
しかし斜めに息を吹きかけると「ピー」と音が出ました。これが笛(横笛)の始まりです。
というように基本的な骨格の違いから西洋人は金管楽器にむいているのです。東洋人は笛に向いているということになります。
西洋では金管楽器は高度に発達しました。
しかし東洋ではほとんど発達しませんでした。
]楽器もわずかに山伏がホラ貝を吹く程度で、しかもその演奏技術は基音と第2倍音位で、メロディを吹くというよりは「ボー」っとうなっているようなもので、信号用にしか使えませんでした。
この演奏技術は紀元前2000年位のエジプトのレベルと同じで、西洋はその後大きくレベルアップしましたが、日本では明治になるまでそのレベルを保っていたのです。保っていたというより進化しなかったのです。これはひとえに骨格の違いによるハンデがあるためと思われます。
トランペットの特徴
金管楽器の代表とも言えるトランペットは、華やかで勇ましく、強く輝かしいといった響きを持っており、曲がクライマックスに達したときには、多く主役を演じます。ピストンが発明される以前は自然倍音しか出せなかったため、作曲にも制約がありましたが、ピストンやロータリーが発明された後は音域内の全半音が使えるようになりました。ドイツのオーケストラでは多くロータリートランペットが使われ、少し暗く柔らかい響きになりますが、ドイツ曲などの重厚なアンサンブルには向いています。オーケストラではB♭管の他ほんのわずか明るい音色を持つC管も一番奏者には標準的に使われます。また、トランペットの音量の幅の大きさや表現力の広さはジャズの楽器としても重要で、ビッグバンドからソロ楽器まで大活躍します。同族楽器にはコルネット・フリューゲルホルン、1オクターブ高いピッコロトランペットなどたくさんの種類があります。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 洋楽
- ブルース・スプリングスティーン 「…
- (2025-11-20 22:49:15)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-
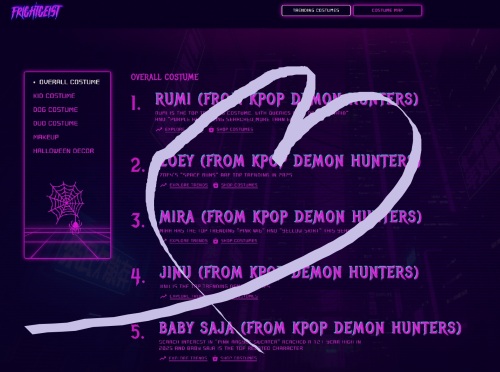
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
© Rakuten Group, Inc.