結城紬見学会 その2
きくやさん HP に会うのは2回め。しかも約10年ぶり。
わかるかしら、、の不安も何のその、、、、。エスカレーターを下りながら見えてきた雪駄(?)と野袴は、
どう考えても、、、、と思ったら、そのとおりでした。
懐かしい、、、、、。
話をしているうちに、☆☆さん御登場~。前回入手したという、結城紬をお召しです。
たてわくにお花を散らした素敵な着物。あまりに小花の柄がきれいに出ているので、うっかり
「後染め?」 と訊いてしまいました。そんなはずないのに、、、、。
帯も、優しい白地に、野菜がちりばめられた、大人の可愛さを感じさせるもの。
しまった、写真を撮り忘れました。
奥順さん HP から 鈴木さんという方がみえていて、車で案内してくれることに。
訳あって、予定より30分遅れての出発でしたが、車中はめちゃめちゃ盛り上がりました。
大阪弁、京都弁、茨詭弁(?)、秩父弁、標準語 ミックスで。
まずは機屋さんにお邪魔しました。3人の方が、いざり機に向かっていました。
初めて見る形の機です。同じ「いざり機」といっても新潟のそれとは違う形。
座るところに「足が付いていて」べったり座るのではなく低めの椅子に座る形です。
腰で縦糸を引っ張って織っているのは他の産地のいざり機と同じようです。
糸のすべりがきかないので、後からずらすことが出来ません。
(大島などは、糸がすべるので多少後からずらすことが出来るそうです)
なので、一本一本、厳密に柄合せをしながら織るそうです。
大変な作業で、「織っている時間より、柄の調整をしている時間のほうが長い」そうです。
杼は、樫の木で作られた大きくて重いもの。中に横糸を入れて杼で打ち込みます。

糸をくくるところも見せていただきました。
束にした糸をはって、図面(設計図)を正確に写して、木綿のカタン糸でくくっていきます。
そのとき、口にくわえて湿り気を与え、しっかりとくくります。
糸に湿り気を与えてしっかりと縛るのは、和裁でもやっていることなので共通点がありますね。

鈴木さんが、糸を取るところも見せてくれました。

「つくし」に掛けた真綿から、すーーーーーーーっと、同じ太さで糸を引き抜き、唾液でまとめます。
それを、丸い小ぶりな桶のような入れ物に、そぉ~~~っと、入れていきます。
よりを掛けていないので、雑に触ると糸同士がくっついてしまいますので、扱いは慎重に、
そぉ~~~っと、触らなければいけません。
その糸を織れる状態にするために、何度も糊付けを繰り返すそうです。
糊付けされた糸は、もう触っても大丈夫。ごわっとした感じで綛になっていました。
まだ、見学一軒目なのに、もう大興奮です。
お昼休みにかかってしまったのに、色々見せていただき、説明していただき、
ありがとうございました。
さて、次は、お楽しみの(?)お昼です。鴨汁蕎麦の大盛りをいただきました。
緑がかった、なかなか美味しいお蕎麦でした。鴨汁も美味。
蕎麦屋の2階の個室で、雰囲気もありました。

次は、「湯通し工場」です。結城紬は、糸に撚りをかけない分、強い糊を使うそうです。「うどん粉」。
なので、織りあがった後の湯通しも、専門の人が行います。
ぬるま湯で、何度も湯を換えながら、手触りで糊の落とし加減を見ます。
袷にするのか単衣にするのかで糊の落とし加減が違うそうです。
単衣にする場合の方がやや多めに糊を残すそうです。


糊を湯通しで程よく落としたら、天日に干します。
結城紬の染めの堅牢度は高いので、天日にさらしても色あせする事はないそうです。
左の写真は大島。結城と違って干していると皴がよるそうです。
右は結城。乾いてもぴんとしています。
天日干して乾いたら、たたんで、木綿の布(風呂敷)に包んで砧打ちをします。
何度も畳み直して繰り返します。それも、職人さんの加減だそうです。


さていよいよ次は、奥順さん。素敵な結城の街並みの中にあります。
「つむぎの館」 HP という資料館があり、見学しました。
「鳩子の海」の元になった建物(?)があり、その資料もありました。
結城紬の各種道具や、古い結城紬の着物、もんぺ、などなども展示してあり、見ごたえ十分。
2年前に結城に寄ったときは、残念ながら定休日で見られなかったので、念願の見学です。


その後、今製品として並んでいる結城紬をたっぷり見せていただきました。
手の届かないお値段も、途中の工程を見てきて、いかに大切に織られたものかを知ると、納得。
(というより、安すぎるぐらい)
本物の結城紬がこれだけ沢山見られる機会はめったにないと思うので、色々見せていただきました。
比べると、同じ結城の紬でも、いざり機で織ったものと高機で織ったものでは風合いが違います。
特に、無地ではわかりやすく、なるほどなぁ、と思いました。
でも、私、着物はすでにうんざりするほど持っているし、
良い物とわかっても、気軽に買えるものではないので、宝くじでも当たったら、買いに来ようかしら??
帯も奨められたけど、半幅帯しか締めないし。。。。。
てな事で、何も買えるものがありませんでした。
(と、日記には書いておこう。)
実は、、、、。 小さな買い物だけしました。結城紬の本とちょっとしたコモノです。


ここで知ったのは、結城紬の縦糸は、一本おき(下側の糸)に糸が結んであって、右足でロープを引っ張ると下側の糸が上に上がる仕組みになっています。
ロープを戻すと引かれた糸は下に戻ります。
一般的な「高機」は綜絖を使って、上になる糸と下になる糸を交互にしていくのですが、結城紬では仕組みが違うので、これも結城紬のいざり機の風合いの特徴になります。
(((( 書き込み中です。 だんだん増えます。 )))))
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 運気をアップするには?
- 最新グッズは「パワー磁気ブレス」と…
- (2025-11-27 17:13:18)
-
-
-
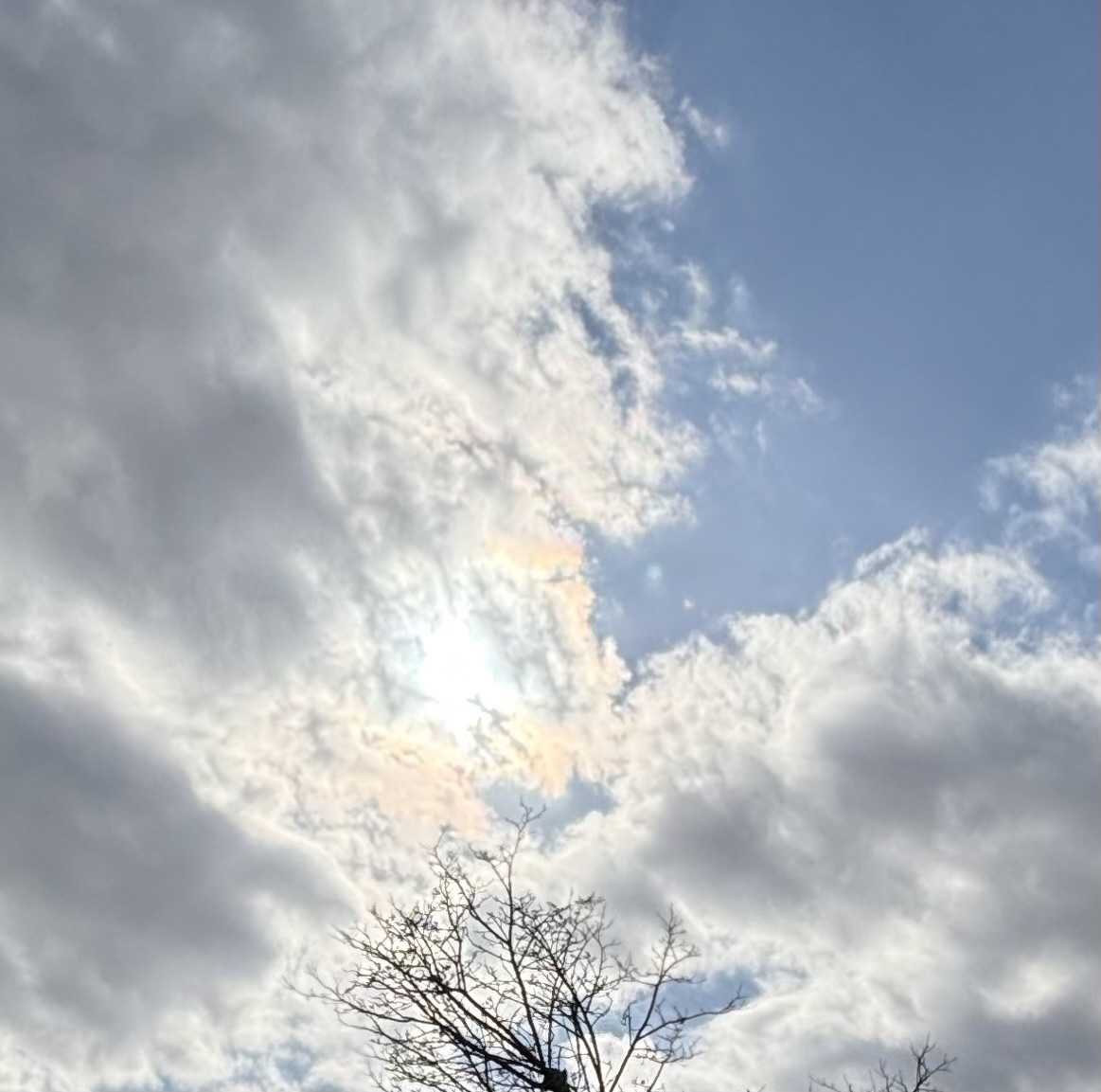
- 日常の生活を・・
- 娘の送迎でトータル3時間も運転して…
- (2025-11-28 21:31:25)
-
-
-

- ささやかな幸せ
- 【ドンク】フランスパンの日
- (2025-11-28 18:15:06)
-
© Rakuten Group, Inc.



