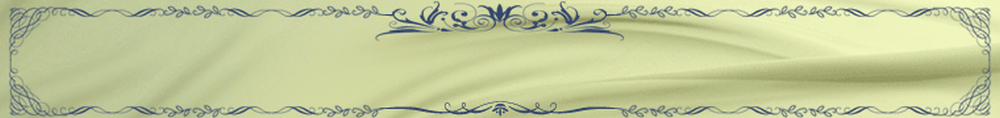チューリップのすごさ
さて、今回はチューリップのスゴさについてです。もう、なんら公共性の無い記事を延々と書いてますけど、ふ~んって感じでお付き合い下さい。
で、いろいろあると思いますが、とりあえず、「サウンド」、「ライブパフォーマンス」、「バンドの雰囲気」、「その他」と言う4点で考察してみたいと思います。
あ、その前に、チューリップはデビューした1972年から1989年の解散までの17年間のうちに構成メンバーがたびたび変化していて、それを目安に3つの期に区分しているようなんですが、「第一期でチューリップは終わったと言う人もいれば、「第二期以降はチューリップじゃない」と言う人もあり、また「第三期ももちろんチューリップさ。高橋君や丹野君、よかったよね」なんて言う人もいるわけです。僕としては全期及び解散後に再結成した現在のメンバーの時代までも通じて「チューリップ」と言うことにしたいと思います。バンドは生き物ですからね。若くて勢いのある時期がもちろんいいんでしょうが、だんだんとたんたんとしてきて、ついに老いさらばえてくる時期もなかなかいいもんだって思ってますから。そうは言っても、夢中だった第二期までのイメージが強いんですけどね。
それと、いまから書くことは、チューリップのスゴさのホンの一部ですし、僕自身に知識が無いって事もあって、物足りなく思われるかもしれませんが、ご容赦下さい。
さて、それではまずはサウンドです。サウンドといってもいろんな切り口があるんですが、例えば、「コード進行の斬新さ」、があげられると思います。つまり、普通の歌謡曲やフォークソングには無いコード進行の曲が多いわけです。「へぇ、こんなところにこんなコードを使うんだ」と言うさりげないものから、「なんじゃこりゃ?」っていうものまであって、また、使われているそれぞれのコード自体も決して単純なものではなかったりするわけです。さらに、ごく普通の進行だと思っていたのが途中で転調する曲が多く、ギターの初心者にとっては結構きついわけです。
あ、「コード進行が斬新だったりコードが単純じゃなかったりするのが何がそんなにいいの?」って思われるかもしれませんが、そういう伴奏によってメロディーがより「映える」訳です。歌バンドですもん、歌(主旋律)のための伴奏なので、難しいコードや普通にはめったに無いコード進行で、伴奏に深い響きを持たせ、それでメロディーをぐっと引き立たたせるわけです。
チューリップの作曲方法は、以前財津さんがラジオか何かで、メロディーに伴奏をつけていくタイプのものと、コード進行からメロディーを導き出すタイプのものがあると言ってたと思うんですが、たとえばオフコースなんかでもNHKで放送された「若い広場」でみると、最初にコード進行を作っておいてそれを何度か演奏しながらメロディーを作っていましたから、ああいう感じで作った曲も多いんだろうなと想像しています。
作曲というか、楽曲と言うことで言うなら、童謡や演歌や歌謡曲やフォークソングなどのいわゆる「歌」の場合、その多くは歌詞のメロディーの終了時点で曲が完結しているのが普通なんですが、ポップスやロックの場合、歌詞が終わった時点では完結感がなく、完結するための演奏が必要と言う曲があるわけです。つまり、歌が主体ではあるけれど、演奏のメロディーも歌のメロディーと同様に楽曲を構成しているというタイプの曲で、チューリップにもそういう曲があるわけですが、千春さんを聴きなれてきた僕にとっては、歌と伴奏で曲のメロディーを作っているというのがとっても斬新に聞こえました。
で、その伴奏です。大雑把には、初期の頃は多くの曲がギターが主で、だんだんとキーボードの比重が多くなっていった、と言う感じだと思うんですが、細かく言えばメンバーの交代による時代区分やアルバムの作風によってそれぞれの特徴があるわけです。ただ、全期を通して、それぞれの楽器が実によく考えられて演奏されていると思います。
音色や演奏のテクニックはチューリップよりもうまいミュージシャンがたくさんいますが、チューリップの場合は、それぞれの楽器のメロディーのとり方が秀逸で、伴奏にきらめきと彩り、そして深みを作り出しています。アンサンブルがいいわけですね。それぞれの楽器が自分をじゅうぶんに主張しつつ、しかも他との調和を保っているという感じで、さっと聞くと気がつかない場合でも、よく聞いてみると音の入れ方とかタイミングとか音色とかがすごくこってるなぁ、と感心してしまうわけです。特に感じるのがベースラインのとり方なんですが、これは宮城さんにも言えますが、特に吉田さんのベースラインは、曲によっては賑やかに、あるいはさりげなく、印象深いフレーズのとり方がしてあって、バンドでのベースの重要性を、僕はチューリップによって知りました。
プレイヤーとしての彼らについては、またいつか書きたいと思っていますが、とりあえず、サウンドについてはもう1つ、コーラスのこともはずせません。
チューリップのコーラスは、よくビートルズっぽいと言われてるわけですが、それは、古いフォークソングや歌謡曲によく見られるような、たとえばC長の曲ならド、レ、ミ、というメロディーに対してミ、ファ、ソと言うようにコーラスを入れると言うような感じではないと言う意味で、そういう音のとり方しか知らない人にとっては、「あれ、なんじゃこのハモり?」と聞こえるコーラスの入れ方な訳です。
う~~ん、このあたりは具体例を書くといいんでしょうけど、文章だけではうまく書けないので、、、どうしようかな?・・・そうだ、たとえば、ビートルズでもチューリップでもないんですが、比較的皆さんがよく知ってらっしゃる歌で言うと、「まんが日本昔話」のオープニングの「ぼ~や~よいこでねんねしな」って言う歌がありますでしょう?あの歌の中の「い~まもむかしもかわりなく~~~」の「かわりなく~~~」のところのコーラスの入れ方みたいなコーラスが特徴といってもいいと思うわけです。(この例え、ちょっとはずしたかな?)あれは二人で歌ってるわけですが、そういう感じの、なんだか不思議な、そして感性をくすぐるような「へぇ~~~」ていう音の入れ方を3人、4人、5人で入れてる訳です。
で、そのコーラスの入れ方もいいんですが、声質がまた特徴があるわけです。例えばオフコースだと、小田さんと鈴木さんは声はもちろん違いますが、にごりのない柔らか系と言う共通点がありますでしょう?声の質が似てるわけです。そういう場合、まあ、普通にきれいに聞こえるわけですが、チューリップの場合、財津さんの柔らかっぽい声質に対して、第一期の場合ではちょっと硬い感じの姫野さんや、更に硬くて高音の上田さん、低音の吉田さんの声がかぶさるわけで、これがまた、他では聞けない魅力となっていたわけです。僕は初めてレコードを聴いたときには、そのコーラスに「壊れそうな切なさ」を感じました。第二期以降の財津さんと比較的声質が似ている宮城さんとのハモりもよかったですけどね。
なにしろ、メロディーと伴奏の作り方、楽器の音作りと入れ方、ハモりかた、これが日本のミュージックシーンではチューリップでしか聞けないものだったわけです。
昔それを真似ようとがんばったんですが、真似るだけでも難しかったですね。ましてや作るとなると・・・たとえば、クイーンなんかはぱっと見でも「難しいわ、これ、ぜんぜんできんぞ」ってわかるんですが、チューリップのヒット曲はポップポップしていて、ぱっと見簡単に聞こえるわけです。で、コピーなんて簡単だよ、やろうやろう、ってことになるんですが、やってみると実は奥が非常に深くて音楽の難しさを思い知らされる、と言うことになるわけです。で、逆にチューリップってすごいなぁ、と見直すことになるわけです。
「自分を主張しつつ他者と調和する存在のあり方」、「細かいことでも凝ってみると全体がよくなる」、「簡単に見えるもんでも実際にやってみると奥が深い」・・・チューリップを聞くと、そういうことまでも知ることができたわけです。・・・あ、ちょっと公共性が出てきた・・・でしょう?
次回はチューリップの「ライブパフォーマンス」ということで、書いて見たいと思います。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 心の病
- 深淵なる聖堂 (Remastered)
- (2025-10-18 14:20:02)
-
-
-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- 目指せ絶対的健康体 AIに訊いてみた…
- (2025-11-16 05:16:04)
-
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/15(土)・=七五三=・「1…
- (2025-11-15 08:00:00)
-
© Rakuten Group, Inc.