2025年06月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

稲のピンチはジャンボタニシことスクミリンゴガイがもたらす
早々と真夏の天気になったのに、違和感を感じてその元を考えてみて、思いついたのはクマゼミの鳴き声が無いこと。例年だと7月中旬に梅雨が明けるとともに、一斉にクマゼミが羽化しセミの大合唱が始まる。 余りにも早い梅雨明けで、ある一定の積算温度を経て羽化が始まるので、それが足りずに土中から出てこないのだろう。ククマゼミがいつ鳴き始めるか気を付けていようと思う。 28日土曜日は朝にヤマモモを採取し、その加工に半日以上かかってしまった。しかも何時もアバウトで加工してしまうので、結果が思い通りにならないこともある。もう終わりが近いヤマモモでもう一度ジャム作りにチャレンジするため、30日の朝も4㎏ほど採取して加工した。結果はまずまずだった。 ヤマモモは公園によく植えられていて、多くは実が小さい野生種が多く、大きい実の栽培種は少ない。木によって熟す時期にずれが有り、一旦熟すと早々に落果し採集時期が短く、何らかの理由で熟さずに終わる木もある。採取しても使えるのはせいぜい40%ぐらいで、選別は手間がかかる。生食用の大きい実は鮮度が落ちやすいことが災いして高価で、店頭で見ることもほとんど無い。 この厄介なヤマモモに高知県人は執着するのは何故か。熟れて路上に多数落ちているのを見ると、じっとしておられない。手に負えない量を採取しても、手間を度外視して加工する羽目になる。 29日は朝から糸島半島を巡り、有り余る時間の浪費に手こずりながら、日没まで粘って二見ガ浦の夫婦岩の間の落日を見た。6月27日唐泊へコッパグレを釣りに行った。手の平レベルを14匹。夕方小戸へ夕日を見に行く。28日朝は雲が多かった。選別前のヤマモモ左が加工用に選別したもの。右は廃棄するもの。延々と手作業で選別と果柄を除去する。果柄が付いている。左が野生種に近いヤマモモ1cm程。右は栽培種2cm以上ある。紛れ込んだナミテントウはアブラムシを食うので益虫といえる。ヒメアカホシテントウはカイガラムシ類を食うので益虫。29日水田のカブトエビ。全長3~4cm。ひしめくほどいるスクミリンゴガイ。1980年代に食用に南米から持ち込まれ、食用にはならず、野生になって各地に氾濫した。このような例は過去に多発している。アメリカザリガニ、ウシガエル、ブラックバス(オオクチバス)、コクチバス、ブルーギル、アメリカオオナマズ、ミシシッピアカミミガメなど何れも在来種に悪影響をもたらしている。多くの苗が消えている。苗を食っているリンゴガイ。苗を植えて間が無い水田を見て気付いたが、苗の本数にばらつきが大きく、少ないものが多いのがリンゴガイの食害を助長しているように見える。兼業で稲作をしているのか、食害にあった水田で植え直ししている例は無い。米不足で大騒動の御時世で、いかにももったいない。梅雨明け前の降雨で水位が上がった農業用ため池。水に浸からない位置に産卵するリンゴガイの卵塊も水没したものがある。トンボ類も増えて来た。カラスアゲハなど大型のチョウも増えて来た。クロアゲハカラスアゲハの雌ムラサキシジミ。表には鮮やかなブルーの鱗粉がある。上から下がって来た毛虫。糸を手繰って何メートルもよじ登る。アカメガシワの花の蜜を吸うイシガケチョウ。このチョウとテングチョウが異常に多い。ベニカミキリの飛翔。クマバチの1種ヒメヒオウギスイセン糸島市志摩の彦山の山道を行く。芥屋大門の大きい海食洞が見える。可也山麓の溜池ではチョウトンボが多くいた。雌は単独で産卵する。ギンヤンマもいたがうまく写せなかった。サシバが頭上を横切った。離れた所にもう一羽いたので番だろう。野北の磯野北港内のアマモ。セイヨウニンジンボクかムクゲ野北で時間を潰し、日がだいぶ西に傾いた5時過ぎに、日の入り位置が良くないので野北から帰り方向の二見ガ浦へ向かった。日の入りまでまだ1時間半の二見ガ浦夫婦岩の夫岩の上にミサゴが営巣していてもう飛べるほどに成長した幼鳥3羽が見えた。日頃は観光客が多く、止まって見ないので気が付かなかった。太陽は右にスライドしながら沈んで行く、この時期でも蔓を延ばすクズ。獰猛な植物の代表格。レンズのような太陽。太陽の下には壱岐があり、ここでは海に日は沈まず島の山に没する。30日ヤマモモを採取した帰り道に通った水田地帯。せっかく植えた苗が消失している。ここはほぼ壊滅。再度田植えをしないのか。植えてもまた食害に合うのか。 比較的早い時期に植えられた苗は食害が少ないようで、高温を好むリンゴガイの活動が気温に左右されるためではないか。スクミリンゴガイを農薬で駆除するなどは、過去の過ちを繰り返すことになるので、田植え時期や水の管理などで、被害を軽減できる栽培方法を研究する必要がある。 田植えさえ終われば勝手に米が出来るという認識を改める必要がある。8時頃の帰り道は通勤の渋滞がひどかった。車社会は通勤や、現場への移動、帰宅などで1日に何時間の無駄な時間を浪費しているのか。車無しでは成り立たない社会は、大きい負の一面を抱えている。
Jun 30, 2025
コメント(0)
-

もう梅雨は明けてしまい、長い夏が始まる。
25日まで数日雨が降って、それを最後に早い梅雨明けになった。例年よりかなり早く、災害に繋がる大雨も無く、梅雨末期の水害が例年のように何処かで起こってので、今年は良かったと言える。長い夏がどう推移するのか見ていきたい。 25日は雨の中でヤマモモの採集をした。今年はビワと同じく豊作で、春先に低温期が長くあったことで害虫のチャバネアオカメムシがかなり駆除されたせいかも知れない。例年になく個体数が少なくなっている。 海の方と言えば、海水温は上昇してコッパグレ釣りも佳境になるはずが、低調のままで個体数の減少がひどく先行きも期待できないレベルで、ボラも全く見ないし、アイゴも釣れるほどいない。半面増え続けているのはスズメダイとトウゴロウイワシ、サバゴとお邪魔虫ばかり。そのせいか、加齢のせいか、釣りへの意欲がすっかり減退している。6月23日 唐泊で釣る。わずか6匹のコッパグレに終わる。野生化した外来の多年生アサガオ。野生化し始めて長くなるが、思ったより勢力は伸びていない。クズと競合して勝ち切れていないのが原因か。24日 この日も唐泊で釣って、コッパばかりでさらに悪く2匹だけに終わった。巣立ったばかりのハシボソガラスだろうか、道路に落ちて動けなくなっていたが生きている。頭上の電柱で親だろうか2羽のカラスが大騒ぎをしていた。車に轢かれない所に移動した。車がほとんど無い。ここまで少ないのは滅多に無い。レジャーボートの釣り人もいないのだろう。新月の大潮1日前で潮位が高い。夜光虫が発生している。 25日 ヤマモモを採取してから、小田へハスを見に行った。かなり強い雨になったが傘を持っていたので何とか写せた。ハスの葉に溜まった雨は、ある段階になると茎が傾いてするりと流れ落ちて、また水を溜め始める。葉上の水は水銀か溶けた鉛のように見えた。ヤマモモシロップを製造。選別するのに数時間を要した。ヤマモモジャム加工。26日 すっかり天気が回復したので、まず室見川中流付近の西部運動公園へハグロトンボを見に行く。その後西へ向かい、伊都菜彩へ魚を見に行き、北上して例のハスを再度見た。夏の到来を告げるネジバナが咲いた。広大な休耕田。トウモロコシ畑の向こうに九州大学伊都キャンパスウスバキトンボより赤味が強いハナハマセンブリかカラスアゲハ。気温が上がると吸水して、水を排出して温度を下げる。アガパンサス倒木で山道が塞がれた。数年前からひどくなったナラ枯れ。糸島半島ではマテバシイが被害に遭っている。ツマグロヒョウモン雨の日のハスに比べると白けて見える。今夏はテングチョウが多い。ガのベニスズメ。初めて見た。イシガケチョウキマダラセセリベニシジミまだ青いホウズキ
Jun 26, 2025
コメント(0)
-

明日は夏至、戻り梅雨の予想で太陽は見られないだろう。
梅雨が明けたかのような天気が数日都度浮いて、20日は雲が増えて蒸し暑くなり、数日ぐずつくという。鳴かず飛ばずの日々は、釣りの不調と、気温は真夏ながら野山はまだ夏の手前の半端さで、いたずらに過ぎて行く。 西浦港内でのコッパグレ釣りに見切りをつけて、唐泊のテトラで2度釣ってみたら余りの釣れなさで、遂に釣り場所が無くなってしまった。こんな状態ならもう落胆することも無くなったので、唐泊の港内で釣ってみたら20cm余りのコッパグレが7,8匹釣れたのは、救いの神、救いの場所だった。小型ばかりの中にわずかに20cm以上がいる。足裏サイズも見られるが、これは餌に見向きもしない。見えるだけでも希望が持てる。6月15日 背振り山系の林道へ行って見た。早良区脇山から脊振山系を望む。室見川の支流の椎原川を遡って林道に入る。林の中に廃屋が1軒あり、放置されて相当な年月が経過しているように見えた。何を夢見て息の詰まるようなスギ林の中に建てたのか。別荘としても寂し過ぎる。装飾花がピンク色のベニガクウツギ二ホンカワトンボ雄マムシグサの種、秋には真っ赤になる。有毒植物。林道上のカワラヒワアザミの1種マタタビの葉は花期には表が白くなる。雄花外来のキキョウソウ。タラノ木。葉の付け根にも棘がある。キカラスウリの花花粉団子を付けたハナバチクロセセリ毎年見る野生のヤマアジサイ。アカタテハアケビは9月中旬に熟す。2mmほどの花。クマノミズキ。もう少し標高が高くなるとミズキに変わる。イチゴのような実で甘い。初めて見るようで、調べると紙の原料になるコウゾ。オカトラノオの咲き始め。ルリシジミ北の遠くに志賀島と能古島。路肩のヤマウド林縁のヤマウド。癖が強い味なので若芽は採らない。ムカシヤンマ。古い型のトンボ。何か虫を捕食している。秋の花ハギ坊主が滝へ向かうフタスジサナエタツナミソウミヤマカワトンボ雄ムカシヤンマ17日クロツラヘラサギは4羽田植え前の水田で餌を探すハシボソガラス。産み付けられて間がないリンゴガイの卵塊。アジサイはもう終わるハマナデシコ梅雨明けを思わせる夏空19日瑞梅寺川河口のミズクラゲクロツラヘラサギは2羽農道の縁に隠れるヒバリニンニクの花大賀ハスはもうすぐ咲き始める。田植え間もない水田のリンゴガイ。苗を食害するのか。唐泊の港内で釣ったグレ。20日
Jun 20, 2025
コメント(0)
-
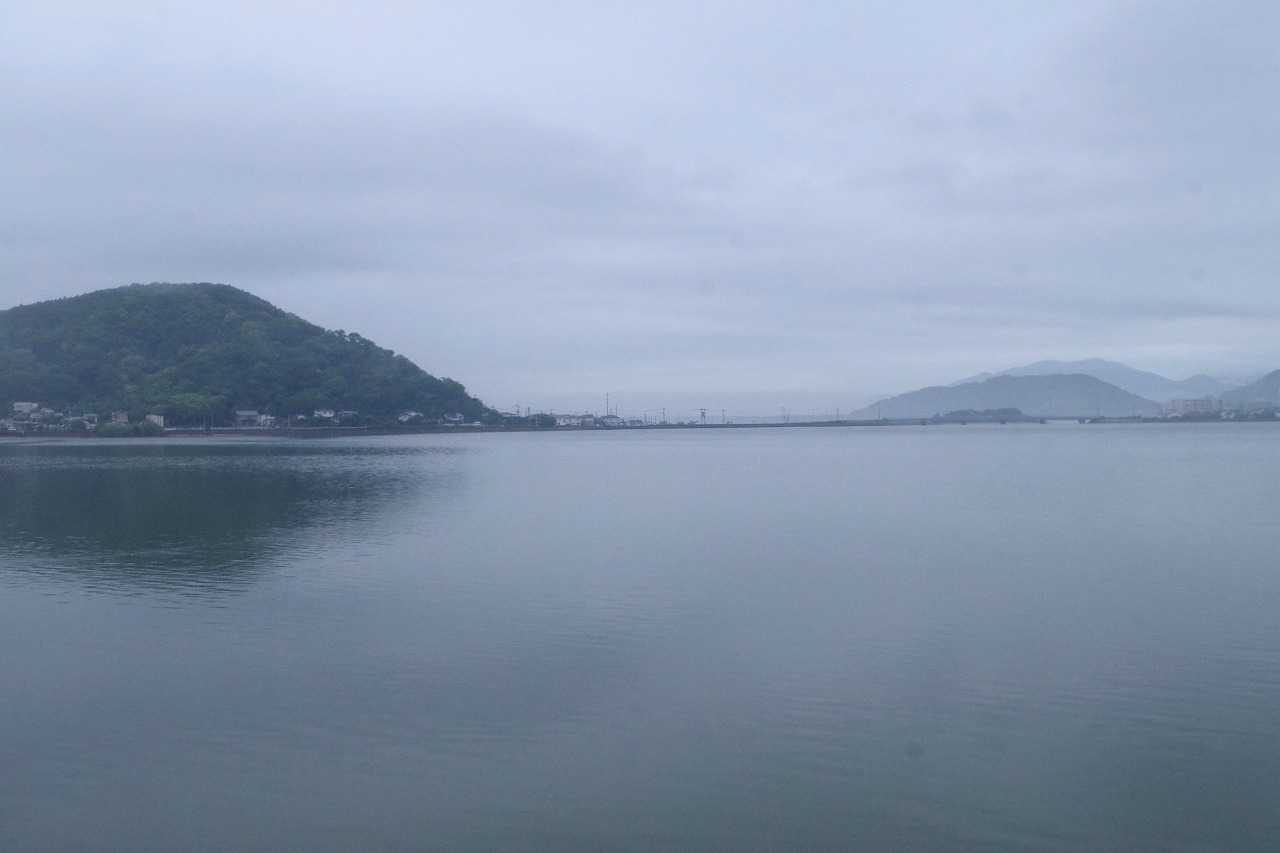
梅雨が思ったより早く明けそうな気配
今年の梅雨は梅雨らしいと思っていたのに、どうやらそうでもなさそうな雲行きになって来た。14日は朝から西から、やって来た熱低崩れの低気圧と梅雨前線が雨を降らせた。予想ほどの大雨にはならず、昼頃には止んで、南からの高温多湿の空気にすっかり覆われて梅雨末期の蒸し暑さになった。 低気圧が東進するにつれて梅雨前線も短くなって東へ移動し、天気図的には梅雨らしくなくなった。来週はさらに高温になって、関東など梅雨明けのような天気になる見込み。 13日 13日は何故か金曜日が多い気がする。すっきりしない天気ながら大降りも無さそうで、不調の西浦を止めて唐泊でコッパグレを釣ってみた。テトラから始め、まず延べ竿で釣ってみたら10cm余りの小型グレばかり数釣れる。埒が明かないので反転籠で遠投して釣ってみた。サバゴとトウゴロウイワシがわんさかやって来て、籠から出た撒き餌に群がり特にサバゴはパン粉アミ団子の付け餌に喰いついて邪魔をする。 試験操業と思っていたので辛抱して釣り続けていると、コッパグレも現れる場面もあり手の平大も少しは釣れる。しかし、サバゴの勢いに気圧されてすぐに見えなくなり、1時間余り釣って手の平大を5匹持クーラーに入れた。せっかくの試し釣りなので、港内の船の間でも釣ってみた。何時も1~3人は釣っているのに雨が降る予報のせいか、釣れないせいか誰もいなかった。しばらく延べ竿で釣ってみると小型のグレが入れ食いで20匹釣って手の平サイズは1匹だった。 どうやらテトラでの反転籠釣りを辛抱してやるのがましとの結論を得た。鈍色に覆われた今津湾。帰りの道草でムラサキシジミを何匹か見た。オオバギボウシの花。花壇のユリ斑入りの葉のカラー筍シーズンも終わり。遅れて生えたマダケ。靄で煙る志賀島海岸近くのタイトゴメ。ヤマモモがやっと色付き始めた。高知県の木。福岡では那珂川市の木。14日 雨が降る中、雨が最も似合う花を見る為、室見川を遡って曲淵まで行った。雨中での撮影には雨傘が必須なので、紐で縛り竿と同じように背負った。アジサイは標高差からかまだ少し早かった。
Jun 14, 2025
コメント(0)
-

今年の梅雨は梅雨らしい梅雨、今日も雨が降る。
和歌山から帰ってもう4日になる。そして毎日雨か曇りのぐずついた天気が続いていて、ここ数年来の典型的な梅雨の天気になっている。毎年のように降る梅雨末期の大雨は、今年もあるのだろうか。 梅雨グロと言ってこの時期はグレ(クロ)が良く釣れると福岡では言われてきたが、年々グレが減り今年は一段と少なくなって、この言葉は既に死語になっている。我が雨釣も雨降りでの釣りをしなくなった今は、改名しないといかんとも思う。 梅雨の花アジサイは、例年入梅までに盛りを過ぎていたのに、今年は春先の低温の影響で開花が遅れ、今やっと見頃に向かいつつある。 世界情勢は相変わらず暗雲が立ち込めたままで、大雨続きで見通しも効かず、見たくもない狂気の独裁者の顔を見るたびに、心は重く何処までも沈んで行く。6日 晴れたので出掛けた。小田川のボラゴは5cm位まで成長していた。前年10~11月に産卵された。小田川の横の草の上に、先日助けたと思われる亀の死体があった。元気よく泳いで行ったので良いことをしたと思い込んでいたのに、悲惨な姿を見るとは。それも川に沢山いたハゼの撮影をしようと、わざわざ行って目にしたもので、見るはずもない偶然のことで、世の中にはこれに類することが多々あるのかも知れない。偽善的行為がいつもハッピーエンドになるとは限らない。結果を知らない方が良いこともある。モンシロチョウのカップルに横恋慕する雄。海岸でスナガニを見た。警戒心が強いカニで、気配を消してじっと待っていると穴から出て来る。目に付いた砂を小顎で綺麗に拭う。カニとはいえ目は良いようで掃除をする。左右とも綺麗にする。食事をするスナガニ。砂を小さい方のハサミで口に運び、素早く餌分を濾し取った後、砂を丸めて落とす。やがてカニの周りは吐き出した砂の団子だらけになる。ハサミは右が大きいものが多いが左が大きいものもある。巣穴を掘る時に、両ハサミで砂を抱えて穴から出て来て、放り投げるシーンは見られなかった。刈られた草の中にニンニクの花らしいものが転がっていたので持って帰った。姪浜の興徳寺でタイサンボクの花を見た。11日西浦へ釣りに行った。西浦近くの道路脇のアジサイ。小物ばかり釣って早々に帰る。本来の子殺し雨釣に戻っている。数日が過ぎて花が咲いたニンニク。12日雨が小降りになった時に、ちょっと外に出た。花に見えるのは装飾花で花ではない。裏側に花が咲いた時が開花というらしい。斑入りのガクアジサイ。テイカカズラの雨粒。水滴の中に映った景色にピントが合うと水滴の輪郭がボケる。水滴の輪郭にピントが合うと中の景色はボケる。鏡に映った映像が2倍の距離になるのとのと同じ理屈。
Jun 12, 2025
コメント(2)
-

和歌山旅行(2)
和歌山での2日目は南紀であちこち過ごして午後2時までに関西空港へ戻り、夕方7時の便で福岡に帰る予定だった。 7時に朝食をホテルで食べた。おかずに干物が出て、自分で焼くシステムでカマスとサゴシは塩干、小アジとキハダマグロは味醂干しだった。さすがに漁業が盛んな串本の近く、海産加工も盛んなのだ。味はかなり良くて、干物を自作する私にとっても良い出来と思えた。 太地のクジラ博物館が開館するまでの間の時間で、那智の滝を見に行った。日光の華厳の滝と双璧をなす名瀑でぜひ見たかった。 生憎天気が悪く、光が無い暗い背景での滝はかえって白く際立っていた。130mの落差を一気に落ちる水の束は速かった。滝が近い場所に降りる前から滝は見えた。長い石段を下りながら振り返ると、杉の大木と苔が悠久の時を体感させた。滝は神社と一体化したご神体と見られている。那智の滝を後にして、勝浦港へ立ち寄った。ここは近海マグロ漁が盛んで、生のマグロが多く水揚げされる。セリは既に終わり、キハダマグロ、ビンナガマグロ、シイラが少し残されていた。体長2mの大型雄シイラ。港内を廻ると、中型マグロ延縄漁船が停泊していて、船籍に室戸市とあった。懐かしい故郷の地名で、衰退の一途を辿っているマグロ延縄漁業が、まだ生きているのを異郷の地で知った。こちらは高知県の東端、東洋町甲浦の船。太地町へ引き返してクジラ博物館へ向かう。ザトウクジラ親子のモニュメント。古式捕鯨の模型仕留めたクジラは2艘のもっそう船で浜まで運ぶ。祖母から幼い時に聞いた記憶がある。鯨一頭七浦潤うと言われた鯨の話を詳しく聞いておけば良かったと、思ってももう叶わない。セミクジラの模型。古式捕鯨ではセミクジラが獲物として多かったようで、子連れ背美鯨を殺したら祟ると言っていた。ゴンドウクジラの餌やり。イルカの捕獲と、と殺食用が世界の保護団体に批判された太地だが、今でも食用の漁業は続いている。捕鯨のキャッチャーボート。 じっくり見たかった博物館は時間が足りなかった。南紀と言えば景勝地橋杭岩。ちょうど干潮時の昼近くで、陸に並ぶ巨岩群だった。多くの観光客が訪れていた。大岩が多数転がっているのは、過去の大津波で運ばれたものだという。底板は石畳のようになっている。小さい亀裂が入っている岩は火成岩だろうか。溶岩が冷える時にガラスのように割れたものか。大仏のような岩。懐かしいハマアザミ。新芽と根は天ぷらにすると美味い。ここで、あちこちで買い揃えた和歌山の寿司を昼飯にした。和歌山は寿司の文化があるのは高知と似ている。最後の見物で海中展望塔を訪れた。時期が早く、うねりがあって濁っていた。ヤマトカマスだろうかヘラヤガラ餌を撒いて飼い付けているグレ(メジナ)は池の鯉状態で、40cmの大物だった。赤いのはオジサン。併設された水族館帰途の機内から見えた微かな夕焼け。 和歌山県は予想を超える広さで、現地に行って見たい場所も増えたのに、時間が足りなかったのが心残りだった。
Jun 10, 2025
コメント(0)
-

遠路はるばる和歌山に出掛けた。(1)
6月7日~8日の1泊2日で福岡からは決して近くない和歌山へ、家族で観光と言える旅行をした。 黒潮にまつわる文化の発祥の地と、かねがね思っていた和歌山に一度行って見たかった。高知在住の時は、海を隔てた隣県だったが、その海ゆえに70歳を過ぎてこれまで行ったことが無かった。漁業や海産の食に関して共通することが多く、紀州和歌山から伝来したことが多いと親などから子供時代に聞いていた。 子供の頃に色々なサメの鉄干しを父が加工して和歌山に送っていた記憶が有り、私が鹿児島県で水産関係で勤めていた時は、ウツボ(鹿児島ではキダカと呼ぶ)の干したものを和歌山に輸送されていたのを知ったし、黒潮文化圏の中心として注目していた。 古式捕鯨の発祥の地としての紀州は日本全国の捕鯨の先駆けとして、その技術を各地に伝えている。私の祖父は高知県室戸の浜に水揚げされたクジラの商売が原点だったし、何やらつながりの深さを感じる。 先に無くなったムツゴロウこと畑正憲さんの随筆に外川の鯛というのがあって、かつて江戸時代に房総外川に漁法を伝えたと読んだことがある。幼少期には親から、和歌山から漁船で遠く出稼ぎにきた漁師が漁法を室戸で教えて、地元漁師から紀州さんと呼んで尊敬されていたと聞いた記憶がある。 1年前に読んだ和歌山出身の作家、故中上健次の枯れ木灘が引っ掛かっていた。 それやこれやで和歌山へ家族で行くことになった。福岡から遠く、1泊では時間が足りず、大阪まで飛行機で行き、そこからは広大な和歌山の南部を目指して道草しながらレンタカーで向かった。 梅雨が間近で天候の不安があったが、曇りながらも辛うじて雨はほとんど回避出来た。 朝7時半発の大阪行きは、折からの大阪万博の客で満席だった。搭乗するまでの移動距離はかなり遠く、膝が悪い老人にはかなりの負担だった。運転は子供がしてくれるので楽だったが、和歌山県の広さは行って初めて実感することになり、かつては関西圏ながら陸の孤島と呼ばれたのも納得できる。幸い高速道路もあって、片道200km以上の行程をこなした。7日福岡空港離陸前搭乗機と同型機。紀の川を渡る。有田漁港の道の駅で見たハナシャコ。ヤツシロガイがスガイという名で売られていた。オウムガイが殻を磨かれて売られていた。美しい。有田は大阪に近く、シラスのバッチ網漁が盛んらしく多くの漁船が係留されていた。多くのリヤカーはシラスを運ぶためのものか。有田で昼飯にシラス丼を食った。なかなか美味かった。その後、高速道を南下して南紀へ向かった。 道の駅の横に併設されていたエビカニなどの水族館へ立ち寄った。トラウツボとウツボ。黒潮沿岸にはウツボがいる。冬が旬で子供の頃に干物をよく食った。独特の味で美味い。カノコイセエビ。イセエビはかつての産地伊勢や紀州は衰退して常磐辺りまで北上している。外国産のサンショウウオ。外鰓がある。串本近くの浜が白いので行って見ると、造礁サンゴの骨格が多数打ち上っていた。奄美レベルの多さ。串本漁港南紀の小型漁船はカツオの引き縄漁が盛んで、ケンケン釣りと呼ぶ。2本の竿を張り出して、片側2~3本の擬餌針を潜行板や飛行機で動かしてカツオを誘う釣り方で、南紀が発祥の地で全国各地に広まっている。串本の先には南に飛び出た本土最南端の潮岬がある。今回は時間不足で訪ねられなかった。近くには紀伊大島が橋で繋がっている。串本節に、ここは串本向かいは大島仲を取り持つ巡航船、と歌われている。 1日目の日程を終えて更に東へ走った太地町の白鯨というホテルに泊まった。夕飯ではクジラ料理が出た。太地はかつては古式捕鯨発祥の地で、その技術は各地に伝えられた。紀伊水道を挟んだ高知室戸、遠くは長崎平戸の生月島、山口長門の青海島。
Jun 9, 2025
コメント(0)
-

海が駄目なら山で収穫する縄文人もどき
爽やかな好天続きで出掛ける。釣りやら山やら相変わらずの多目的で、あちこち徘徊する。 すっかり西浦港内でのグレ釣りが不調になって、わずかな漁獲を求めて4,5日とも小メバルをした。小潮の上にスズメダイとトウゴロウイワシ、サバゴと手強い餌取が増えてコッパグレどころか小メバルすらあまり釣れない。 2時間も釣りをすればもう十分で、帰りながら背後の山をあちこち訪ねては、マダケの筍を探したりしながら道草を楽しんでいる。このまま釣りが不調なら、筍も終わりこのまま昆虫も少ない状態が続いては、日々の過ごし方が思いやられる。6月4日朝から素晴らしく晴れている。西浦で2時間釣っての寂しい釣果。イノシシに食われたマダケの筍の残骸。帰りに通った道端でバイクを止めてパンを食っていて、ふと見た地面に黒い小さい木の実が多数落ちているのに気付いた。見上げると間にやら見覚えのある実が付いた木がある。実はクワのようだが葉が以前見たのとは違う。実を採って食ってみると甘く、間違いなく桑の実だった。 どうやら野生のクワの木らしく、以前見たのは栽培種で葉が大きかったと思われた。そうと分かれば付近はどうかと歩いてみると、道を挟んで山裾に数本のクワの木が有って、どれも実が熟していた。土産に少し採取してみたら、実は小さく、熟れたものは触れただけでぽろぽろこぼれ落ちるし、指は果汁で紫に染まりベトベトして多くを取るのは難しかった。田植えが終わったばかりの水田の向こうにペイペイドームなどが見える。田舎都会の福岡らしい風景。今津浜崎から南を見れば、女原山とその先の脊振山系雷山が見える。夕方小戸公園へ行って見た。ヨットハーバーより北になり夕日の位置も変わる。雲が太陽を隠していたが、低高度は雲が薄く、夕日は見られると予想して待った。燃えないゴミに出そうとして思い止まって復活させた望遠レンズで写した。20年ぐらい前に新聞広告で買った、500mm~1000mmレンズ。大口径なら中古の車1台買えるほどのレンズだが、小さい光景の暗いレンズでオート機能も無い単純なものだが、使いようではデジタルカメラでもそれなりに写せることが分かり、捨てなくて良かった。主に使っているデジカメ用50~500mmレンズは絞り機能が壊れていて、何時も開放の状態で写している。この為ピントの合う範囲が狭く、視力の低下と運動神経の低下でほとんどピンボケになる。5日 久し振りに唐泊で釣ってみようと、去年の夏にヒイラギを釣った港内の一角で撒き餌を撒いてみた。数回撒いて様子を見ていると、突然10cm位のサバゴが大挙押し寄せた。これでは釣りにならないと諦めて、竿を出す前に前日と同じ西浦へ場所を変えた。 わずか小メバル9匹を釣ってから、1時間で釣りを切り上げてJF志摩の四季へ向かった。自然薯の葉とガクアジサイ。唐泊港と灘山。 志摩の四季では小さいイサキを3匹とトマトを3個買っただけ。売っている魚は少なく高い。イカ類はかなり多く出ていたが、相変わらず高価で、開店から1時間過ぎていたが多く売れ残っていた。 今話題のコメの価格も同じだが、売りたい側の希望価格と、買う方の買える価格とが乖離すれば売れ残るのは当然のこと。米のようにすぐに売れずとも品質の低下がない物と違い、時間単位で鮮度が落ちる魚介とでは比較にならない。売れ残ることを見越して高値で売ろうとするのは本末転倒だと思うのだが。クロセセリ店からブラブラしながら帰る。遠く唐津の浮嶽が見える。林内のマダケの筍林縁の筍。桑の実のジャムをどうしても食ってみたかったので、頑張って採取した実は300g。採取した筍はすぐに先端部を切り落とす。魚の活け締めと同じ。2日分のメバルは甘露煮にした。まずガスのグリルで素焼きする。川魚と同じ方法。圧力釜で30分水煮にした後、醤油、味醂、酒、砂糖、生姜を加えて煮詰めると完成。小骨は柔らかくなっている。
Jun 5, 2025
コメント(0)
-

遅れに遅れたマダケの筍を探す。
例年この時期には食用筍の最後のマダケを採取している。筍を待っている人々がいるので、どうしても採取するノルマがある。殆どの竹林は放置されていて、古い竹林は枯死した竹が縦横に倒れて進むことすら困難になっている。モウソウチクは売り物の筍を採取する為に管理されている場合もあるが、マダケは地産地消で少し出回るだけで、一般の人は食べない。 今年は春先の冷え込みで何もかも遅れていて、マダケも例年より10日程も遅れてやっと生え出した。初めは林縁に小さいのが生えて来て、それが枝を出す頃にやっと林内に食用になる大きさの筍が生え始める。釣りに出掛けたり、徘徊する時にはまめに竹林を覗いているが、いつもながらイノシシの食害が激しい。 今年のモウソウチクが極不作でイノシシは十分に栄養をつけられず、ハチクは開花で滅亡の縁にあり、待ちに待ったマダケは伸びる暇もなく食われている。マダケの筍は地下茎が浅く、地上に出てある程度伸びないと可食部が無いにもかかわらず、待ちきれないイノシシは伸びる前に筍を食ってしまう。 可食部が少ない為、本数で空腹を満たそうとするのでことごとく食い尽くし、それが夜な夜なの事なので人間の取り分は無くなっている。 6月と言えば全国的にアユ漁が解禁になる。今はアユ釣りと言えば友釣りを指すが、我が釣りの原点でもある釣りはアユの餌釣りで、今でも解禁日を待ちかねて釣りに興じたのを思い出す。アユを見ればすぐ分かることで、体形はマスやサケに似ている。元々は肉食魚で、川での安定した成長と、水温が上がる時期に過ごし寿命が1年というサイクルを有効にするために、川の石に生える珪藻や藍藻を餌にするように進化した。 しかし川は大雨で増水し、濁流は岩や石の表面に生えている藻を根こそぎ流してしまい、水が澄んで数日経過しないと藻は再生しない。その間は餌が無く空腹に晒される。この時に過去の肉食の記憶が蘇って餌で良く釣れるし、虫を模した毛バリでも釣れる。 動物の多くは草食でも動物性の餌を食う場合があるのは、種の存続のための策だろうが、肉食動物が草食性を持つ場合もある。哺乳類ではイタチの仲間やイノシシ、アライグマ、イヌ科のタヌキ等多いし、鳥類も多くが雑食性。 雑食性ゆえに畑の作物を食害するので人との軋轢も生ずる。陸でも水中でも動物の雑食性こそが生きる有効手段になっている。31日カンムリカイツブリ夏羽北東の風が強く吹くと博多湾側は波が出る。池の周りには夥しい小ガエルがいる。オオスズメバチはとにかく大きい。休むジャコウアゲハの雌ガの1種キナミシロヒメシャク6月1日クロツラヘラサギが7羽残っている元岡の水田にアマサギが渡って来ていた。田植えの時期にやって来る。白い羽毛のアマサギもいる。ダイサギの半分の大きさのアマサギ。糸島市のとある溜池。風下に吹き寄せられた水草。水面が隠れアメンボが浮草の上を歩いている。コフキトンボ水の表面張力で浮かぶアメンボ。雄雌重なったアメンボは多い。去年の初冬が温暖で、受粉が順調で豊作のビワ。放置ビワの木にも多く実が付いている。サトキマダラヒカゲ今年のウメは不作で、早咲き程悪い。アマサギトラクターの後を付いて行って餌を探す。水辺ではほとんど見ない。大物のカエルを捕らえた。ミシシッピーアカミミガメの甲羅干し。モクレン科のタイサンボク。小戸にて2日テイカカズラキキョウソウは北アメリカ原産。外部と接触が無さそうな山道で見かけた。帰り道の姪浜の興徳寺で見た。雪が積もったような花はティツリーというらしい。ザクロの蕾興徳寺には珍しい植物が沢山ある。 連日のように米が話題になっている。安いコメに出来る長蛇の列。主食を巡る異様な高まりを横目で見る。武士は食わねど高楊枝を決め込む。
Jun 2, 2025
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 日帰り温泉あれこれ
- 【温泉】岩井温泉 #温泉,#日本,#共同…
- (2025-11-12 13:35:25)
-
-
-

- 今日は何処へ行きましたか?
- 曇天のよこやまの道を散策
- (2025-11-12 08:31:11)
-
-
-

- ★自然の中で感じること★
- 今日も少ないわぁ
- (2025-11-13 17:00:09)
-







