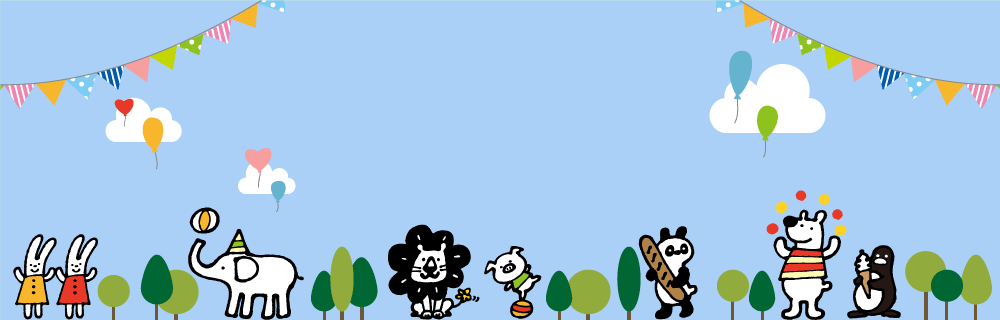時間と時計(11)~(21)
さて、江戸時代に、広い範囲で、時報や寺鐘が時を告げていたのですが、ここに一つ考えるべきことがあります。
時の鐘は、いったい正確だったのだろうかということです。とりわけ、17世紀中期以降は、世界最大の都市となっていた江戸(18世紀の初めには、100万都市となっています。続くは北京。ロンドンは19世紀に入った1801年で96万人、1701年はようやく50万人です)の場合、1626(寛永3)年に日本橋石町(今の日銀本店の近く)に鐘楼堂が建てられたのは皮きりで、町の拡大に合わせて、城を巡る高台に次々に時鐘が設けられ、計9箇所もになっていました。
また寺も数多くあり、そのほとんどが鐘楼を持っていたのです。それらがバラバラに鳴ったのでは、様になりません。しかし、江戸の川柳にも寺鐘がバラバラになって困ったという話はでてきません。
いったいどうやって、時報の時間を決めていたのでしょうか。しかも、相互に電話連絡など出来ない時代にです。何で時を計っていたのでしょうか。しかも不定時法の時代です。
まず、正午の時間は、太陽の南中時で良いとして、日の出、日の入の時刻を決めねばなりません。太陽が顔を出すとか、沈むとかすると、高台と低地では違ってしまいます。そこで、眼の前に手をかざして薄明かりで見える時刻、見えなくなる時刻と決めました。
それでも、天候によって、明るさは違います。そこで、自然条件に影響されない、1種の時計を用いていました。勿論機械時計ではありません。日本人の発明した機械時計も、実を言うと江戸時代にあったのですが、そのことは後に書きます。大阪の釣鐘屋敷や江戸石町の鐘楼堂など、そして寺などが使っていたのは、1種の大きな香時計でした。
その香時計なのですが、1間四方の大きな香時計が利用されました。香時計は1種の火時計です。四角い大きな香炉の中に、粉末の香でコの字型の線を書いて行くのです。己の字の跳ねがない感じで、繋げて行きます。
ご自宅の蝋燭か線香で確かめていただけると分かりますが、風が入らないようにしておくと、仏壇などで燃える速度がほぼ一定であることが、お分かりいただけると思います。ですから、大きな香炉のようなものの中に粉末の香で描いた線の端に火をつけると、それが一定の速度で燃えて行きます。この燃える速度に合わせて、時刻点に記しを打ち、その時点毎に子、丑、寅……と記した香串を立てておき、そこを眺めて時刻を確認するのです。
しかし、夜通し寝ずの番というのも、辛いものです。そこで、香串に火がまわると、大きな鈴が鳴って落ちる仕掛けが考案され、確実に時刻が分かるように工夫されたのです。
欧米でも、例えば奴隷の競り市等では、蝋燭の火が消えるまでが、競りの時間であるなどと、一定の時間を計るために、蝋燭が用いられたことは、多々あったのですから、当時としては、香時計はとても正確であると、認識されていたのです。時報や時鐘は、かなり正確に時を告げていたのです。
明日は江戸時代の、日本産の機械時計のことを記す予定です。
続く
時間と時計 (12)
ところで、ヨーロッパの機械時計は、いつ頃日本に齎されたのでしょうか。現存する最古の機械時計は、時計搭に掛ける掛け時計ではなく、16世紀の後半に誕生した置き時計です。
西欧世界でも僅かしか現存していない、16世紀の置き時計が、静岡県久能山の東照宮に保存されています。1581年にスペインのマドリッドで作られた旨の銘が入っている金メッキ製の時計です。
この時計はスペイン国王から、1610年に徳川家康に送られたものなのです。当時スペイン領であったフィリピンの総督ドン・ロドリコが、1609年に任期を終えて帰国の途についた時に、折りからの嵐にあって漂流し、房総半島の白浜海岸近くで座礁してしまったのです。報告を受けた家康が救助を指示し、ロドリコ一行は無事スペインに帰りつけたのです。この報告を受けたスペイン国王が、翌年感謝の意を込めて家康に贈ったのが、自ら愛用していたこの時計だったのです。
この置き時計は時針が1本だけの時計で、国の重要文化財に指定されています。そのため、直接に時報を聞くことはできないのですが、私が拝観した1992年には、テープで録音した時報が定時毎に館内に流されていました。毎時毎に時を打つ時計でした。
ところで、日本に最初に機械時計を齎したのは、私がお名前を拝借しているザビエル神父その人でした。1549年に来日したザビエル神父は、鹿児島から山口に趣き、時の西国の権力者大内義隆から布教の許しを得ようと、13種類の品を献上しました。その中に機械時計(まだ置き時計はありません)があったのです。
続いて、ローマ法皇庁へ派遣された少年使節団が、遥かローマで厚遇を受けて1590年に帰国した時に、帰国の土産として秀吉に献上したのが、自鳴鐘と呼ばれた置き時計でした。ただ、この2つの時計については現存していませんので、どんな時計だったのかは、分かりません。
さて、江戸時代の前半は、1種の香時計によって、時を計り鐘や太鼓の時報を鳴らしていたことは、昨日記しました。ところが江戸も中期に入る頃から、和時計と呼ばれる日本独特の機械時計が作られ、利用されるようになっていったのです。
続く
追記。 大航海の時代、アフリカ南端経由のアジア貿易はポルトガル、ブラジルを除く中南米貿易はスペインと分けられました。それはローマ教皇の調停を受けての合意でした。なのに、何故16世紀末のフィリピンがスペイン領になっていたのか。これは、スペインとポルトガルの王家が姻戚関係を結んだ結果、1580年に両国が合併し、60年後にまた分離するまで、統一スペイン王国になっていたからです。
時間と時計 (13)
日本人は、手先が器用なことで知られています。種子島に齎された鉄砲も、半世紀足らずで世界でも5指に入る鉄砲量産国になるほどに、短期間で自前の技術に作り変えているのです。戦国末期の日本は、世界でも有数の鉄砲生産国でした。日本の技術水準は、決して世界にひけをとってはいなかったのです。
そんな日本でしたから、西洋から入手した機械時計の技術もまた、独自の機械時計の製造に昇華させていったのです。それが和時計でした。西洋の機械時計は、昼夜の別なく一定の時を刻み、人工の時間を創り出す定時法の時計です。これに対し和時計は、不定時法である日本の時刻制度に合う様に改良された不定時法の機械時計です。言うまでもなく、定時法の時計よりも遥かに難易度の高い時計でした。
不定時法の下では、昼よ夜の長さが異なります。ですから、昼と夜で1時間という単位時間の長さを替える必要がありました。さらに、四季を通じて、昼の時間と夜の時間は日々替わって行きます。日の出、日の入の時間も日々変わります。それらを調整する必要もありました。
現代のハイテク技術があれば、解決不能ではないでしょうが、江戸時代にこれを解決するのは、さすがに困難でした。そこで、和時計の技師達は、時間の正確さをトコトン追及することを諦め、自然の時間に合う機械時計を作る方を選びました。世界広しと言えども、不定時法に適合的な時計を発明したのは、日本だけです。このことは、もっと誇りにされて良いように私は思います。
残念な事は、和時計の多くは、明治期にそのほとんどが海外に流出してしまった事です。不定時法が明治6年(1873年)に廃止され、定時法に変えられてから、実用性を失った和時計は次第に姿を消し、その機械技術の価値を知った西洋人の手に、次々と渡ってしまったのです。今では、国立博物館外、幾つかの博物館が所有するだけになっているのではないでしょうか。皆さんの地元の博物館はいかがですか。
ところで、和時計は各地の藩や名門の大寺などが、お抱えの技師に作らせたものですから、夫々に特徴を持っていたのですが、大まかにやぐら時計、尺時計、枕時計の3種類に分けられるようです。このうち、やぐら時計が最も早く元禄時代の初め(17世紀末)に、出現していますので、香時計に替わって、城下の時報装置と連動して、時を告げる役割も担ったのでしょう。美術工芸品として、藩主の威光を示すと共に、実用の役も果たしていたことになります。
続く
時間と時計 (14)
やぐら時計は、はかま型をした木製の台座の上に、四角い箱型の機械時計を据えつけた時計です。袴の形の台座の中には、時計の動力となる錘が下がっています。その錘が落下する速度を調節する役を果たすのが脱進装置で、この脱進装置を調節すのが、テンプとかバランスと呼ばれるものです。
このテンプの部分が、昼用と夜用の2つつけられていた時計が、「二挺テンプ式和時計」と呼ばれたものです。これが17世紀末~18世紀の日本で、最も進んだ時計と言われていたのです。
尺時計は、戦後しばらくまでの間、木造家屋に良く掛けられていた短冊型の柱時計に良く似た形をしています。「大きな、大きな古時計、おじいさんの時計…」今は動かなくなったおじいさんの時計は、この形をした、しかし定時法で時を刻む振り子式の時計なのでしょう。昨日も記しましたように、明治6(1873)年以降、日本も定時法に切替えていますから、以後不定時法の時計が各家庭で使われることはなくなっていたからです。
尺時計は構造的には簡単なもので、動力が錘である点では、やぐら時計と同じです。異なっているのは、錘が垂直に落下して行く際に、錘に取り付けられている針が、時刻を示す文字盤を通ることです。その時に針が示す記号によって、時刻を知る仕組みです。
ですからこの尺時計の工夫は、文字盤を季節毎にとか、1ヶ月毎にといった目安で、何枚も取りかえることが出来るようにしてあったことでした。錘の落下速度は一定ですからこうしないと、1年中の時刻の調整をする術がなかったのです。
やぐら時計と違って錘は一つでしたから、彼岸時を除けば、日々の昼夜の長さの差も文字盤の入れ替えで対応するしかありません。毎日、そして毎月文字盤を調節するとなると、これは大変です。ですからやぐら時計に比べて、手間はかかるし、その割りに時刻の正確さには劣りますから、ファッションとしてはともかく、あまり普及するには至らなかったようです。
最後に枕時計です。この枕時計は、昨年春からお付き合いいただいている尊敬するブログ仲間のkopandaさんが、過去にコレクションなさったことがあり、いくつもお持ちのようですから、彼のブログに載せていただけないかとお願いしておきました。
この枕時計は、今までの2種の時計が錘を動力としていたのに対し、ゼンマイを動力とした置き時計です。非常に精巧で豪華なものが多く、ゼンマイなどの部品の製造に、高い技術を必要としていました。初めて製造された時期は、特定できていないのですが、その技術的な完成度の高さからして、おそらく幕末になって作られたものだろうと、考えられています。
なお、幕末に近づくと、西欧伝来の懐中時計も、日本に輸入されており、武士や大地主、大商人の中には、この輸入物の懐中時計を、印籠に埋めこんだ印籠時計を所持するようになったと言われています。
機械の部分は輸入品ですが、日本人の時間の観念と、時間への関心は非常に高かったように思われます。こんなところにも、アジアで日本だけが19世紀段階での近代化に成功した、隠れた原因の一つがあるように思います。
続く
時間と時計 (15)
ところで、日本にもからくり時計は存在しました。からくり人形は17世紀後半には、かなり知られた存在で、井原西鶴も座敷で茶運び人形を見て、感動した様子を綴っています。
このからくりと時計との結合も自然のことでした。西欧よりは時期的に遅れますが、こうした技術は幕末には大きく開花しています。
つくば研究学園都市の近くにある谷田部町の住人だった飯塚伊賀七は、幕末に木製の大時計を作った人物として知られています。高さが2メートル以上もある木枠の中に、大小の歯車をいくつも取りつけた時計だったようです。
1985年につくば科学万博が開かれた時に、隣の谷田部町でも「幕末の科学展」を開いて協賛したそうで、この時の目玉が飯塚伊賀七の大時計の復元・展示だったそうです。私は残念ながら、その年日本を離れていて見逃してしまったのですが、しっかり見学した友人からの情報で、およそのことを知りました。
この時計には、太鼓や鐘の装置がついていて、日の出、正午、日の入りの時刻になると、自動的に鐘や太鼓が鳴るように工夫されていました。自動時報装置つきの時計だったのです。しかも町中に(最も江戸時代の谷田部町は、小さな村だったでしょうが)音が響き渡る公共の時計搭が、幕末の地方農村に備わっていたことになります。
伊賀七は、村人から「からくり伊賀」と呼ばれていたようで、彼の家は代々名主を務めた地方名望家だったようで、その屋敷の1部に、彼の遺品が残っています。
彼の家の筋向いに「玉川屋」と呼ばれた酒屋があったのですが、その酒屋へ酒を買いに行く人形を彼が作ったそうです。人形は家を出ると道路を横断し、酒屋の前にくるとピタリと止まる仕掛けになったいたそうです。主人が酒ビンいっぱいに酒を注ぐと、人形はぐるりと向きを替えて帰っていったというのです。面白いのは、これは酒屋の話なのですが、主人が技と酒の量を少なめに入れると、人形は帰ろうとしなかったというのです。秤の機能も併せ持っていたのでしょうね。
残念ながら、こうした話が残っているだけで、この酒買い人形は現存しないのですが、人形が持ち歩いたという備前焼の酒ビンは、伊賀七の屋敷に残されています。正六角形で、高さがおよそ20センチ、約4合(720ml)入りのビンです。
幕末にはもう1人、からくりの天才技術者がいました。後に田中久重と名を改めたのですが、からくり儀右衛門と親しまれた、田中儀右衛門ですが、彼の話は、明日にさせていただきます。
続く
時間と時計 (16)
田中儀右衛門(後久重)は、1799年久留米の鼈甲細工屋、田中弥右衛門の長男として生まれました。幼い時にからくりの硯箱を作って、寺子屋の先生を驚かせたと言いますから、早熟的な天才だったようです。
15才で久留米絣に花模様を織り出す発明に成功し、22才の時には「風砲」という火薬を使わない空気銃を発明、地元で大変な評判を取りました。また発明のための資金作りのために、全国を回るからくり人形の一座を作って、約10年ほど全国を巡演、大変な評判もとりました。
36才で大阪に出ましたが、丁度大塩平八郎の乱(1837年)に遭遇し、家屋を焼失したことから、京都に移り住み、そこで空気ポンプを利用した「無尽燈」を発明して評判を取り、学者仲間と親しくなります。30代後半にして、なお向学心旺盛な儀右衛門は、ここで戸田久左衛門の紹介で、天文暦学の権威土御門家に入門し、その道を極め、天皇から一流の御用時計師に与えられる「近江大掾」の称号を賜っています。
京都で「機巧堂」という店を構え、さまざまな機械や高級時計を作製しました。この高級時計の最高傑作が1851年製造の「万年時計」です。正式名称は「万年自鳴鐘」と言うこの時計は、上野の国立科学博物館に展示されています。それは、和時計の粋と西欧の時計技術を融合させた、当時の最高傑作の一つとして、世界的にも注目された作品でした。
六角形の六面には、夫々に時刻を示す洋式文字盤、和式文字盤、月日、七曜などが取りつけられ、頭部には日本地図が描かれていて、その上に太陽と月の運行を現す模型がセットされています。このハイテク技術の粋は、しかし買い手がつかず、儀右衛門はからくり興行に使っていました。
黒船の襲来と開国によって、幕府も諸藩も西洋の技術を取り入れて、海防を強化することに熱心になり、1854年の開国の年に、儀右衛門は佐賀藩に招かれて、藩の精錬所の技師長となり、船のボイラーや銃砲の製造に携りました。この時期に、日本で最初の蒸気機関車の模型も開発しています。
長命だった儀右衛門は、69才で明治維新を迎えます。廃藩置県後、70代の儀右衛門の才能に注目した、明治政府の進めで東京へ出、1875(明治8)年に、銀座に田中製作所という日本で最初の民間機械工場を開きました。今後は電気の時代がくることを見越す慧眼を持って、電気の研究も進めていたのですが、1881(明治14)年83才で他界しています。
彼の起こした田中製作所は、2代目田中久重に受け継がれ、彼の下で飛躍的に成長し、やがて東芝と名を代え、今日にいたっています。
なお蛇足ですが、江戸時代のからくり人形が発展したものが、現代のロボットです。現在世界で使われているロボットのおよそ90%が日本製であるといわれているのですが、その土台に流れているのは、西欧の模倣ではなく、日本独自のからくり人形の技術であると知るのは、ちょっと良い気分ですね。
続く
時間と時計 (17)
シンデレラの話に戻りましょう。
シンデレラの話は、シャルル・ペローが民話から採取した童話のの一つで、これもお馴染みに「赤頭巾ちゃん」や「眠れる森の美女」といった作品と共に、1697年出版の『ペロー童話集』に納められています。
話の筋はご存知の通りですが、シンデレラと魔法使いの約束は、深夜の12時を過ぎると魔法が解けるということでした。そこで、こういうシーンがあります。最初の日、シンデレラは11時45分の時計の音を聞いて、王子様とお別れします。ところが、初日より少し慣れた2日目は、この音を聞き漏らし、12時の鐘が鳴り始めたところで、慌てて王子様を振りきり、走って門へ向かいますが、ガラスの靴の片方を落としてしまうという、有名なシーンです。
靴のお蔭でハッピー・エンドになるのですが、ここでの注目点は11時45分の時計の音を聞いたという、初日の記述です。お城の舞踏会の会場に、いくら高価な品だからとはいえ、柱時計をかけておくほど無粋なことはありません。シンデレラが聞いた時の音は、徳川家康がスペイン王から寄贈された類いの置き時計だったと考えられます。
その置き時計、定時でもなく、30分でもなく、15分と45分も知らせる精巧なものが、17世紀末には、既に出来ていたことになります。その証拠がシンデレラの話ということになります。物語の記述は、空想も含みますが、現実に体験しない事には、書けないし、想像もできない事もあるのです。
実際にアメリカの博物館などには、ドイツの古時計を展示しているところがあるのですが(本国でないところがミソですね)、その古時計の時の告げ方を記してあるものもありますから、それを見ると15分毎と1時間毎に時を打つと記されたものが、1部にあることが分かります。
何の必要で、15分の時を告げる時計が開発されたのか、この解明に、明日は『ガリバー旅行記』の冒険家、ガリバー氏に登場していただくことにします。
続く
時間と時計 (18)
ジョナサン・スイフトの『ガリバー旅行記』は、1715年頃に書き始められ、1726年に完成した作品です。空想の国に題材を取りながら、当時のイギリス社会を風刺した作品です。面白いのは空想譚でありながら、出発の日付や空想上の島での日付などは、しっかりと記録されていることです。
ここで取り上げるのは、小人国への漂流譚ですが、この旅立ちの日は1699年の5月4日、イングランド西岸の港町ブリストルを出発したと記されています。そしてインド洋海域で嵐に遭って難破、小人国へ漂着したのが、その年の11月5日。小人国を出発したのは、1701年の9月24日と記されています。
この時、漂流中に気を失ったガリバー1人が、ふと気がつくとそこが小人国だったという設定です。気付いたガリバーは身動きできないように縛られていたのですが、大勢の小人に取り囲まれていて、彼の持物が逐一検査されるのですが、小人達が最も驚き、かつ関心を示したのが、上着のポケットに大切にしまってあった銀の懐中時計でした。
小人国の役人の、皇帝への報告を引用すると、
「耳元に近づけると、あたかも水車のように、絶えず音を響かせています。おそらくこれは、私達が知らない動物か、それとも彼等が礼拝する神ではないかと思われます。彼等の日常の行動は、この機械の作る時間に指示されていると、本人は言っております。」とあります。
この懐中時計、何故ガリバーは未知への航海に、懐中時計を携えて行ったのか。ここにシンデレラが出会った15分を打つ置き時計の謎を解く鍵があります。持っていた時計は1ケだけ、しかも上着のポケットにしまっていたのですから、これは商品ではなく実用のためのものであることが分かります。
いったい何のために。コロンブスが初めて大西洋横断の航海に乗出したのは、1492年の事でしたが、彼の航海にも大きな砂時計が据えられていたことが、『コロンブス航海誌』に記されたいます。即ち航海と時計は切っても切れない関係にあったのですね。ガリバーもまた航海に欠かせぬ道具として、懐中時計を肌身放さず、持ち歩いていたのですね。
それではいったい時計で何を計っていたのでしょう。
続く
追記
懐中時計も、17世紀の後半から作られるようになっていましたが、当初は誤差が大きく、日に30分程の遅れが当たり前の製品でした。そのため、当初は貴族の装身具のように扱われていたのですが、1675年頃にオランダで、精度が飛躍的に高い時計が開発され、一躍オランダがヨーロッパ時計工業の中心地に踊り出たのでした。ここに1日の誤差は5分以内となり、修正可能範囲に落ち着いたのです。1699年出航のガリバーが持っていたのも、このオランダ製の懐中時計と考えて良いように思います・
時間と時計 (19)
実は時計は距離を測る上で、欠かせない重要な道具だったのです。砂時計のコロンブスも、○○の方向へ○ノットで、○時間進んだという調子で、航海日誌を記しているのです。
元禄3年から5年(1690~92年)にかけて日本に滞在した、オランダ東インド会社の医師ケンペルという人物は、日本滞在記という日本の紹介記録を残しているのですが、この記録はオランダで『日本誌』として出版されました。その中に、彼が将軍を表敬訪問するために江戸に上った時の記録「江戸参府日記」も含まれています。
この旅に、ケンペルは完成後間もない懐中時計を大事に持って出かけました。江戸城で将軍綱吉に拝謁した時の情景もあります。大奥の女性達にも見学が許されたこの席で、ケンペルは西洋の剣やタバコのパイプなど、日本人が珍しがりそうな品を見せて気を引いているのですが、最も皆が興味を寄せたのは、小人国の小人同様懐中時計だったと記しています。大奥の女性達は時計を部屋の外まで持ち出し、不思議そうにためつすがめつ眺めたり、耳にあてて音を聞いたりしていたと、なかば得意気に記しています。
さて、ケンペルはこの時計で何をしていたのかが、確認出来ると、ガリバーが懐中時計を大事に持っていた理由も分かります。ケンペルの旅日記を引用しましょう。
「3月2日金曜日。我々一行は籠に乗って京都を離れた。一緒に宿を出た主人は、京都から1時間程の距離にある町外れの料亭に、我々を招いた。……ここで我々は1時間を過ごし、長々と続く日岡村を過ぎると、15分で岩茶屋村に至り、それから間もなく追分村に着くが、この村は400ケ程の長い町並みを有し、通り過ぎるのに半時間ばかりかかった。」
お気づきと思いますが、京都から1里の距離という表現を用いず、距離を時間で現しているのです。今でこそ不動産の広告には、「駅から○分」がありますが、江戸時代の日本には、距離を時間で表現する習慣はありませんでした。ケンペルは籠に揺られて旅をしながら、懐中時計を常に見ながら、夫々の地点の距離を時間で表現していたのです。それも15分単位で時間をはかっていたことが、この記録から読み取れるのです。
そして彼は時間を距離に換算していました。おそらくガリバーも同じことをしていたことになります。時報の1時間の他に、15分という時間が大切だった理由が、仄見えてきましたね。
続く
時間と時計 (20)
さて、ガリバーの話に戻りましょう。遭難地点はこう書かれています。
「我々の船は、ブリストルから東インド(当時インドは東インド、アメリカ大陸とその周辺は西インドと記述されていました)とへの航海中、ひどい暴風雨に遭って、バン・ディーマンズ・ランド(これはタスマニア島の当時の呼称だったと考えられています)の北西方まで流された。天体観測の結果、我々の位置は、南緯30度2分にあることが分かった。」と。
現在の地図で、タスマニア島の北西、南緯30度2分を見れば、これは海上ではなく、オーストラリア大陸の上になります。ですから、実際にはそんなことはありえないのですが、何しろ18世紀初頭では、クックによるオーストラリアの「発見」や領有宣言は、まだ行なわれていないのです。それゆえ、空想冒険小説では、こういうことが起きるのは、不思議でも何でもないのです。
ここでは、ガリバーが船の位置を示すのに、緯度だけを記し、経度を記していないことに注目して欲しいのです。緯度だけでは船の位置は決められません。船の位置が決まらないとすれば、当然危険も増えます。
何故緯度があって、経度がないのか。それは古来からの天体観測の発達によって、緯度は早くから比較的正確に測定できたのですが、経度の測定が難しかったからなのです。未知の大陸や島々が沢山あった時代に、不正確な地図や海図で航海することが、いかに危険をともなうものであったかが、ここから理解できます。
ガリバーや、これも皆さんご存知のロビンソン・クルーソーが出会ったような海難事故は、当時は日常茶飯な事柄だったのです。それは海軍の軍船でも、起こりうることでした。
西洋史でお馴染みのスペイン継承戦争(1701~1713年)の最中、1707年のことです。ジブラルタルを通って、帰国途上にあったイギリスの地中海艦隊が、11月22日夜に英仏海峡を通過中に、西からの強風にあおられて進路を誤って座礁、軍艦4艘を失い、2千人の乗組員が全員死亡するという、大事故を起こしたのです。
この事故はイギリスのみでなく、ライバルのフランスやオランダにも強いショックを与えました。いつ我が艦隊にも、同じ事が起こるかもしれないからです。事故は、正確な経度の測定が出来ないが故に起こったことは、間違いのないところでしたから、この時から経度の測定への関心は、いっそう高まったのです。
スペイン継承戦争が終った翌年の1714年に、イギリス政府は、正確な経度測定法を考案したものに、2万ポンドの賞金を出すと発表しました。フランスも負けては1715年に1万リーヴルの報奨金を出すと発表しました。オランダも負けじと、1万ギルターの賞金を出したのです。
早くに経度の測定法を入手した国が、世界の海を支配できる。当時の海洋国家は、競って経度の測定法の取得を目指したのです。
理論的には経度の測定法は分かっていました。標準経線を設定して、それと船が位置する地点の、ローカルな時間との時差から割り出すことが出来るからです。問題はそうした時差を測る誤差の少ない正確な時計がなかったことです。
また、仮にそうした時計が開発できたとしても、その時計を常に揺れていて、動揺の激しい船の上でも、正確に時を刻んでくれるかは、難しい問題でした。時差の誤差が仮に1分だとしても、それは地図上では大きな差になるからです。こうして、まずは時報の外に、15分単位で時を打つ時計が開発され、さらに、掛け時計でも、置き時計でもない、人が身につけている懐中時計が製造されたのです。
続く
時間と時計 (21)
ガリバーが服のポケットに、大切に懐中時計をしまっていたわけは、船の進んだ距離を測るためでした。それも正確さにやや欠けるとしても、経度を測るためでした。コロンブス一行が、大型の砂時計を積み込んでいたのも、未航海の海を行くために、出来るだけ正確に我が船の位置をしるためだったのです。
やがて、18世紀後半になって、より正確に経度を測る道具として、マリン・クロノメーターが発明され、懐中時計は、海上での役割りを終えるのですが、その頃から、イギリスでは産業革命が始まり、やがて時計はなくてはならないものになって行くのです。
ここで、ガリバーの話しは終えますが、日本で最初に懐中時計を手にした人物の話をさせていただきます。私事ですが、私の父方の従弟が川越に済んでいます。この従弟が、私のブログを覗いて、川越市多賀町にある「時の鐘」について記された『川越市史』の1部をコピーして送ってくれたのです。
実は、ペリーの黒船が来航した1853年に先立つ事7年、1846年にも米国は2艘の黒船を日本に派遣しています。東インド艦隊所属のコロンブス号とビンセンス号でした。この時の記録は、詳しくは残っていないのですが、ペリーの『日本遠征記』(岩波書店から翻訳が出ています)に7年前のことが1部記されています。
この時幕府は、沿岸警備艇で2艘の軍艦を遠巻きにして様子を見たのですが、1人の血気にはやる侍が、2艘のうちの1艘、ビンセンス号に近づき、投錨した錨をスルスル上って、ビンセンス号の甲板に降り立ったのです。
川越藩士、内池武者右衛門でした。内池は英語が出来たわけではないのですが、面白がった米軍水兵と身振り手振りで応待し、帰り際に、何と懐中時計をお土産にして戻ったのです。
しかし当時は、なお海禁政策が続けられていた時代ですから、お土産に貰った懐中時計については、誰にも話さず、勿論主君に献上する事も出来ず、密かに家宝として、自宅にしまっておいたのです。
やがて開国した日本は、幕末の動乱を経て、明治維新を迎えます。文明開化を掲げた新政府は、時刻制度の刷新にも思いを致さざるをえません。こうして明治6(1873)年1月1日をもって、不定時法を定時法に改め、1日を12刻制から24時間制に改めること、暦法も太陰暦から太陽暦に改める旨を決したのでした。
時刻はともかく、太陰暦と太陽暦では日付が違います。ですから移行に伴っては、経過措置が必要になります。このため、明治5(1872)年は12月2日を持って終りとし、12月3日を、明治6(1863)年1月1日とすることになったのです。こうして、明治5年には、12月は2日しかない、変則的な1年になっています。除夜の鐘を撞く方も、気分の出ない年の瀬だったでしょうね。
それはともかく、夫々の地方では、江戸の昔から慣れ親しんだ、時の鐘をどう撞くかが大問題となりました。和時計もどこにでもあるというシロモノではなかったのですが、不定時法の和時計で、時を告げるわけには行かなくなりました。かといって西洋時計は、大都会はともかく、地方都市や農村には無縁のシロモノだったからです。
事情は旧川越藩、当時の入間県川越市でも同じでした。
続く
© Rakuten Group, Inc.