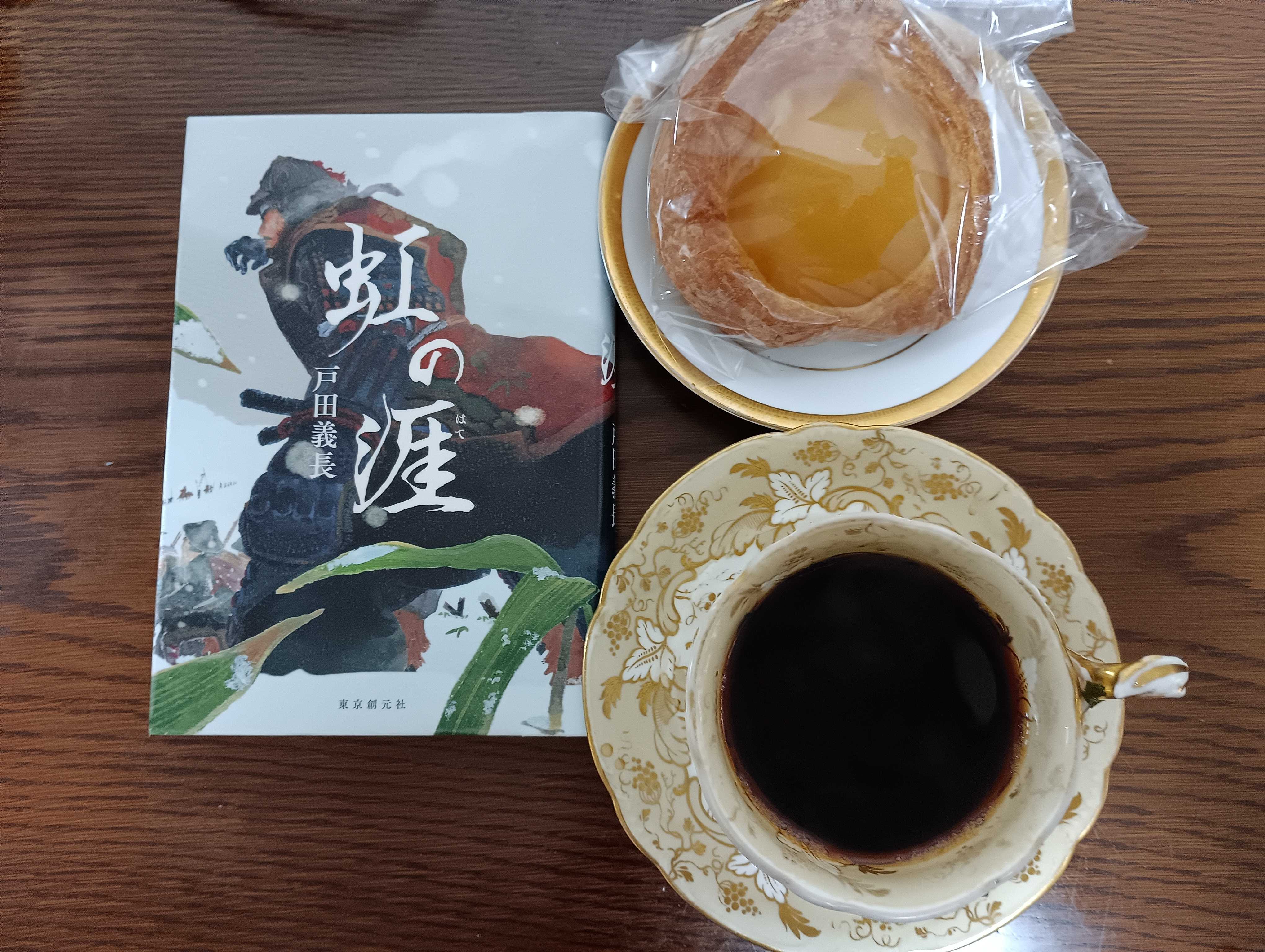2016年10月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
田中一村の「富貴図」と「幽蘭賦」の衝立
私は、2004年6月に鹿児島市の山形屋文化ホールで開催された「田中一村展」に鑑賞に出掛けたが、会場に入ると「富貴図」の衝立がどんと置いてあった。この絵は一村が1929年3月に衝立に描いたものだが、彼が従来描いていた南画の傾向とは異なり、その精緻な描写と濃密で華麗な彩色は、写意よりも写実を重んじる中国の院体画の影響を受けて描かれたもののように思われる。 しかし、円山応挙に有名な「孔雀牡丹図」があり、一村はどうも円山応挙のその絵から孔雀の姿を除き、太湖石と牡丹の配置を変えて写し取り、それを一村流にかなりデフォルメして描いたようにも思える。 この「富貴図」の衝立画は、その一番手前に描かれた赤色の牡丹の花とその少し奥にある薄紫色の牡丹の花を斜めに寝かせる配置の仕方や、かなり形状をデフォルメして鮮やかな青色に彩色された太湖石の存在は予定調和的な絵画的構成を意図的に打ち壊そうとしており、一村が画家としての新境地を切り開こうとする意欲を強く感じさせるものがあった。しかし、残念ながら絵画的に成功しているとは言いがたい。 さらにこの「富貴図」の衝立画の裏に「竹と蘭」の水墨画が描かれているが、この水墨画には風雅さが欠けており、なんとも不気味である。そして、この水墨画の左上に楊炯の「幽蘭賦」の詩句全文が小さな字で画賛としてびっしりと書かれている。この衝立を一村はどのような精神状態のなかで描いたのであろうか、非常に気になるものがあった。 それで、上海商務印書館から出版された四部叢刊集部所収の明刻本影印版『盈川集』を調べてみたところ、そこに楊炯の「幽蘭賦」が載っていた。この「幽蘭賦」は、「惟うに幽蘭の芳草、天地の純精を稟(さず)かり、青紫の奇色を抱き、竜虎の嘉名を挺(ぬ)く」と幽蘭(ひそやかにけだかく咲く蘭の花)の素晴らしさを讃えている。 また大矢鞆音『田中一村 豊穣の奄美』(日本放送出版協会、2004年4月)は、世田谷郷土資料館の武田庸二郎氏がこの「幽蘭賦」 について、「楊烱はこの中で屈原の名を挙げており、全文にちりばめられた修辞は、屈原の『離騒』に似た表現がある」と指摘していることを紹介するとともに、また渡邊明義氏の『水墨画の鑑賞基礎知識』(一九九七年二月、至文堂) の一節に、「蘭は香草で、深林に生じ、辺に人無くとも芳香を発つ。このことから、君子の修道して徳を立て、困窮しても節を変えないことに喩えるのである。讒言に遇い、ついには汨羅に身を投じた、楚の忠臣屈原の『離騒』には蘭が度々登場し、祀りごとにも尊重された香草であるが、蘭を縄で結んで腰に帯びるようなこともあったのである。このことから蘭は遠く屈原を想うことに繋がるのである」との記載があると紹介している。 確かに「幽蘭賦」中に「若夫霊均放逐」という詩句があり、この「霊均」とは屈原のことであり、彼の長編詩「離騒」で「余を字(あざな)して霊均と曰う」としている。また、「幽蘭賦」中の詩句「結芳蘭兮延佇」は、「離騒」の「結幽蘭而延佇」から採ったものであろう。 さらに「含雨露之津潤、吸日月之休光」という詩句が出てくるが、これは魏の思想家で竹林の七賢の一人でもあった嵆康の「琴賦」中の詩句「含天地之醇和兮、吸日月之休光」から採ったものと思われる。なお、この人物はその批判精神が魏王朝で権勢を掌握していた司馬氏の憎悪の的とされ、死刑に処せられている。さらに、「幽蘭賦」には、「雖處幽林与窮谷、不以無人而不芳」(幽林と窮谷に處るといえども、人無きを以て芳しからざるとはせず)との句があり、これは『孔子家語』の「芝蘭生於深林、不以無人而不芳」から採ったものと思われる。 この「幽蘭賦」には、自らが説いた政治理念を生前には為政者から採用されることなく各地を弟子たちと流浪した孔子、讒言を受けて放逐されて汨羅に身を投げた屈原、司馬氏の憎悪の的となって処刑された嵆康が隠されており、そんな「幽蘭賦」の作者の楊炯自身が則天武后打倒の企てに連座して左遷されたことのある人物であった。 当時21歳の一村は、どのような思いからこの衝立の裏に「竹と蘭」の絵を描き、そこに画賛として「幽蘭賦」を書き込んだのであろうか。衝立の表の「富貴図」に描かれた奇怪な形をした青い太湖石から受ける印象も含めて考えるに、そのとき彼の心には「幽蘭賦」の最後に詠まれている様に、「鴻歸り鶯去りて紫莖歇(やす)み、露往き霜来たりて緑葉枯れ、秋風之一敗、蒿草とともに芻(か)らるるを悲しむ」(雁が歸り鶯去って紫色の蘭の茎が枯れ、露の季節が終わって霜が降りるころに緑の葉が枯れ、秋風がこれをヨモギとともに枯らしてしまうのは悲しいことだ)とするような寂寥感が存在していたのではなかろうか。この寂寥感は、画家としての才能に強い自負を持ちながらも、他方でこれまでの自分への画業への確信が揺らぎ始め、新たな境地を切り開こうと模索を開始したときに必然的に生じる不安と焦燥感に由来するものではなかろうか。 なお上記のことは、拙サイト「やまももの部屋」の「田中一村の遊印」のつぎのページに詳しくアップしています。 ↓ http://yamamomo02.web.fc2.com/poem.htm
2016年10月27日
コメント(0)
-
田中一村の千葉時代
1938年に一村は千葉市千葉寺に転居し、姉の喜美子、妹の房子、祖母のスエと生活することになり、奄美に移住するまで同地に20年間暮らすことになる。当時の千葉寺は、田園が広がり、竹薮や杉、栗の樹木が生い茂る自然豊かな農村地帯であり、一村はそれらの豊かな自然を対象に絵画制作にいそしんだのである。 1941年に太平洋戦争が始まり、一村は1943年 船橋市の工場に板金工として徴用され、体調を崩して闘病生活に入ることになる。日本の敗戦直前になって一村の病もやっと癒えたが、その頃に彼は盛んに観音菩薩の像を描き始める。健康を回復し、また戦後の解放感のなかで一村の創作意欲は大いに燃え上がる。 画家としてのアイデンティティを模索し、複雑にも重なり錯綜する山や川を越え、目指すべき路を見失って彷徨うことも幾たびかあったであろう一村であるが、戦後まもない1947年、宋の詩人・陸游が七言詩「遊山西村」で「山重なり水複なって 路無きかと疑えば 柳暗く花明かるく 又一村あり」と詠んだように目の前にぱっと明るい視界が広がったのである。その年、彼は「白い花」と題する日本画を描き上げるとともに、画号を一村と改めている。朝の陽光を受けて瑞々しい緑の葉のなかに無数の小さな花を咲かせるヤマボウシの清楚な姿を見事に描き上げたこの絵は、一村の最高傑作の一つに数えられるものであろう。 私はこの「白い花」の絵の実物を鹿児島市立美術館で「田中一村 新たなる全貌」展(2010年10月5日~11月7日)で初めて見たのであるが、近くに寄ってよく見ると岩絵具で描かれた緑の葉がとても厚くこってりと塗られていることに意外な感じを受けた。しかし、かなり離れて見ると、朝の光を浴びたやまぼうしの葉とその白い花がとても清々しく爽やかに感じることができた。 1947年、「白い花」を描いて以降、彼は画号を「一村」に改め、南画も再び描き始める。しかし、それらの南画には「倣蕪村」、「倣木米」、「倣鐵斎」といったように先達の作品を倣っているということを明確にしている。 1953年には襖8枚に「花と軍鶏」という絵を描いており、岩絵具による筆遣いも「白い花」よりさらに洗練されたものになっている。この襖絵の軍鶏は一村の自画像と評されている。 しかし、一村が本道と信じる道を歩いて目的の場所にたどり着くまでにさらに10年以上の歳月が必要だったようである。 千葉時代は一村の絵画制作を考える上で重要な雌伏の時期と言えるが、無名の日本絵画の画家として経済的には非常に苦難の時期であった。 中野惇夫「奄美に逝った孤高の画家、田中一村」(『季刊銀花』1992年春第八十九号)に1959年3月に一村が中島義貞氏宛てに書いたつぎのような手紙が掲載されている。「東京で地位を獲得している画家は、皆資産家の師弟か、優れた外交手段の所有者です。絵の実力だけでは、決して世間の地位は得られません。学閥と金と外交手腕です。私にはその何れもありません、絵の実力だけです。」 また千葉時代の田中一村の生活状況を知る上で、『田中一村作品集―NHK日曜美術館 黒潮の画譜』(日本放送出版協会、1985年8月20日)に掲載されている一村が岐阜の児玉勝利氏宛に書いたつぎのような内容の手紙の下書きがとても興味深い。なおこの手紙の下書きに奄美の「紬工場で五年働きました」とあることから、1967年頃に書かれたものと推測される。「細工場で五年働きました。細絹染色工は極めて低賃金です。工場一の働き者と云われる程働いて六十万円貯金しました。そして、去年、今年、来年と三年間に90%を注ぎこんで私のゑかきの一生の最後の繪を描きつつある次第です。何の念い残すところもないまでに描くつもりです。 画壇の趨勢も見て下さる人々の鑑識の程度なども一切顧慮せず只自分の良心の納得行くまで描いています。一枚にニケ月位かゝり、三ケ年で二十枚はとてもできません。私の繪の最終決定版の繪がヒューマニティであろうが、悪魔的であろうが、畫の正道であるとも邪道であるとも何と批評されても私は満足なのです。それは見せる為に描いたのではなく私の良心を納得させる為にやったのですから……。 千葉時代を思い出します。常に飢に駆り立てられて心にもない繪をパンの為に描き稀に良心的に描いたものは却って批難された。 私の今度の繪を最も見せたい第一の人は、私の為にその生涯を私に捧げてくれた私の姉、それから五十五年の繪の友であった川村様。それも又詮方なし。個展は岡田先生と尊下と柳沢様と外数人の千葉の数人のともに見て頂ければ十分なのでございます。私の千葉に別れの挨拶なのでございますから.....」 一村のように「学閥と金と外交手腕」を持たない無名の画家は、千葉時代に姉の喜美子や岡田藤助氏等数人の友人たちの支援を受けながら、「常に飢に駆り立てられて心にもない繪をパンの為に描き稀に良心的に描いたものは却って批難された」としている。 南日本新聞編『アダンの手帖 田中一村伝』には、「飢駆我」(飢え我を駆る)という遊印が一村にあり、それが陶淵明の「乞食」(こつじき)という詩の冒頭の「飢来駆我去」に由来していること、一村はその遊印を幾つかの絵に落款として押していることが書かれている。 それで、陶淵明の「乞食」という詩のことを調べてみたところ、角川書店から「鑑賞 中国の古典」シリーズの第13巻として出された都留春雄・釜谷武志『陶淵明』(1988年5月)に「乞食(食を乞う)」の詩の原文とそれについての解説、口語訳が127頁~130頁に載っていることが分かった。参考のために、同書の陶淵明「乞食」の口語訳を下に紹介させてもらうことにする。 食物がなくなってひもじくなると、いても立ってもいられずに家を出る。 いったい自分はどこへ行くつもりなのか。 歩いて歩いてこの村までやってきた。門をたたいて(食物を乞おうとするが) その言い方はまことにつたない。 家の主人はわたしの気持ちを理解してくれて、物を恵んでくれた。 ここまで来たかいがあったというものだ。 話が弾んでいるうちに日が暮れ、出された酒は遠慮なく飲んだ。 新しい友人ができたことを心から喜びうたって詩を作った。 あの洗濯ばあさんのようなあなたの思にいたく感じ入るが、 自分に韓信のような才能のないことを恥ずかしく思う。 胸にしまった感謝の気持ちをどう表現すればいいのだろう。 死後あの世からでも恩返しをせねばなるまい。 なお『田中一村 新たなる全貌展図録』、2010年10月)に拠ると、1960年頃に描かれた色紙「紅梅丹頂図」にこの「飢駆我」の遊印が押印されているとのことである。このとき一村は、奄美から1960年 5月に岡田藤助氏の襖絵制作依頼を受けて千葉に戻っている。おそらく奄美でこの「飢駆我」の遊印を篆刻し、千葉に戻ったときに描いた色紙「紅梅丹頂図」に押印し、支援者の岡田藤助氏に贈呈したものと想像される。なお同上図録に「昭和30年代に描かれた色紙」として「マダラハタとフジブダイ」にも「飢駆我」が押印されていることが指摘されている。 前掲書の南日本新聞編『アダンの画帖 田中一村伝』で中野惇夫は、遊印に「飢駆我」と彫った当時の一村の心境をつぎのように内在的に理解しようとしている。「この陶淵明の『乞食』の詩を読むと、なぜか一村の気持ちが切々と伝わってくる。この詩に託して、自らの気持ちを、表していたと思われてならない。故なく人の援助を受けることは、衿持が許さなかった。しかし絵を売らず、定収もなく、絵の探究を続けるには、不本意ながら人の恩を受けざるを得ない。人に受けた恩は、いつも心に重く負担となってのしかかった。絵かきとしての一村は、絵をかいて報いるよりほかに道はなかった。千葉時代は、絵は売らなくとも、ささやかな恩に報いるために絵をずいぶんかいた。それがまた心の傷として残ったのではないか。いくつかの絵に『飢駆我』の落款が押してある。絵を受け取った側が、一村の意をどこまでくみとってくれたのか、いささか心もとない。」 そうなのであろうか。勿論この「飢駆我」の遊印には支援者からこれまで援助を受けてきた画家の「心の傷」も刻み込まれていることは間違いなかろう。しかし、この「飢駆我」の遊印がいつ頃篆刻されたのかおおよその見当がついたとき、私はこの遊印に込められた一村の思いが分かったような気がした。前掲書の『田中一村 新たなる全貌展図録』(2010年10月)によると、この「飢駆我」の遊印は1960年頃に色紙に描かれた「紅梅丹頂図」に押印されているとのことである。 1958年に奄美に渡った一村は、そのとき「絶対に素人の趣味なんかに妥協せず自分の良心が満足するまで練りぬく」(前掲の大矢鞆音『田中一村 豊饒の奄美』に引用されている1959年3月に奄美から千葉の知人に宛てられた手紙)ことを決意しており、支援者の経済的援助なしに独力で生活していくことを決意している。そう決意したとき、生計を立てるために支援者の個人的趣味に妥協に妥協を重ねて来たこれまでの自分を振り返りつつ、支援者たちからの非常な解放感を覚え、「飢駆我」の遊印を篆刻したのではなかろうか。 一村は、50歳のとき住みなれた千葉から奄美大島に渡り、これまでとはまったく異なる自然と対峙して新たな美を創造することになるのであるが、それら奄美で描かれた作品は支援者の意向から解放された状況において創作されたものだということも忘れてはならない。
2016年10月21日
コメント(0)
-
田中一村と東京美術学校
田中一村は、1926年4月に東京美術学校(現在の東京藝大美術学部)の日本画科に入学している。同期の入学生に加藤栄三、橋本明治、東山魁夷、山田申吾などがいた。たが、その3ヶ月後に退学している。 その頃、日本美術界では横山大観、安田靫彦、小林古径、前田青邨、速見御舟、川端龍子、土田麦僊、村上華岳等が活躍していた。 ところで、田中一村は東京美術学校の日本画科に何を学ぶつもりで入学したのであろうか。彼がもし幼い頃から親しみ、また優れた能力を大いに発揮して来た南画の道を志し、美校でそのための研鑽を積むつもりであったとしたら、彼は大いに戸惑うことになったであろう。一村が入学した東京美術学校には南画を学ぶ環境などは存在しなかった。東京美術学校はアーネスト・フェノロサや岡倉天心が創設の準備にあたり、1889年に開校しているが、開校当初の日本画科の教員スタッフとして、主任教授に橋本雅邦、教授に結城正明、狩野友信、川端玉章、巨勢小石が迎えられている。なお、近藤啓太郎『日本画誕生』(岩波書店,2003年4月)は開校当時の教員スタッフについてつぎのように述べている。「雅邦、正明、友信はいずれも狩野派、玉章は四条派、小石は土佐派であって、フェノロサが嫌っていた南画(文人画)の画家は一人もいなかった。当時の南画はきわめて俗化していたということもあるが、フェノロサは一種の漫画として見ていたようなところもあった。」 フェノロサが1882年に『美術真説』で南画(文人画)を批判して、「文人画卜称スル一種ノ画風ヲ以テ真ノ東洋ノ画術トナシ、之ヲ奨励スルト謂フ説ニシテ熄(や)マズソバ、真誠ノ画術起ルノ期ナシ。之ヲ譬フルニ、油絵ハ磨機ノ頂石ニシテ文人画ハ其底石二等シク真誠ノ画術其間ニ介(ハサマ)リテ連(シキ)リニ磑砕セラルカ如シ」とし、文人画こそが真の東洋の画術なりとするような謬説が存在する限り「真誠ノ画術」の発展などは期待できない、「真誠ノ画術」は西洋画と文人画とが挽き臼の上下の石のようになって粉々にされている、と語ったことは有名である。では、フェノロサにとって文人画のなにが問題だったのであろうか。彼は『美術真説』でつぎのように語っている。「文人画ハ、天然ノ実物二擬スルヲ主トセザルノ一点二就テハ稍賞スべキモノアルモ、其目的トスル所ノ妙想ハ画術ノ妙想ニアラズ。其実文学美術ノ妙想二外ナラズ。諸美術妙想ノ形状ハ各同ジカラズ。詩文ノ妙想ハ必ズ画ノ妙想卜同ジカラズ。文人画ニ就テ人心ヲ感ズルハ、畢竟文学上ノ関係二由ルモノニシテ、毫モ画ノ善美二関セズ。殊二文人ノ毎ニ磊落疎率ヲ喜ブモノハ、果シテ何ノ由アルヤ。是レ蓋シ画二係ルノ故ニアラズ、別二其源因アルヤ明ケシ。文人画ヲ目シテ真誠ノ画トナスハ、画ヲ目シテ音楽卜云フト何ゾ択バソヤ。」 すなわちフェノロサは、南画(文人画)について、天然自然をそのまま模倣するものではないという点において些か評価していいが、それは「画術の妙想(アイディア)」ではなく「文学の妙想(アイディア)」に過ぎず、文人画を本当の絵だというのは絵画を音楽だというのと同じことだと批判している。 さて、一村が入学した当時の日本画科の教授は、小堀鞆音(1864―1931)、川合玉堂(1873―1957)、結城素明(1875-1957)、松岡映丘(1881―1938)であった。小堀鞆音、松岡映丘はともに土佐派の手法を継いで歴史画を得意としていた。川合玉堂は狩野派の流れを継いで情緒豊かな風景画に優れていた。結城素明(1875-1957)は最初は四条派の川端玉章に師事し、さらに円山応挙の写生の精神を受け継いでいた。 湯原かの子『絵の中の魂 評伝・田中一村』は、一村入学当時の東京美校についてつぎのように解説している。「教授陣には小堀鞆音、川合玉堂、結城素明、松岡映丘等を擁していた。このうち小堀 輌音と川合玉堂は帝国美術院の会長、結城素明と松岡映丘は審査委員と、いずれも東京 画壇の有力者であった。美校での指導は、主として結城と松岡があたっていた。両者とも、院展離脱後の文展に不満をもつ新進気鋭の画家が、芸術の自由な研究と個性の表現を求めて結成した『金鈴社』というグループの同人で、素明は洋風の写生を日本画のなかに積極的に導入する道を開き、映丘は歴史画と古典の研究から、大和絵の伝統を新時代に生かす新興大和絵を起こした。ともに大正から昭和にかけての東京画壇に新風を吹き込むと同時に、教育者としても辣腕をふるった。(中略)当時の美校では大和絵を中心に、基本のデッサンに重きをおいた技術指導がなされていた。とくに結城素明は、外遊の体験から、客観的描写にすぐれ独創性を重んじる西洋絵画に対抗していくには、これからの日本画は素描力と独創性が大事だと主張していた。 授業内容は、一、二年生では植物写生が主で、厳密に緻密に写生し彩色をほどこした作品を、一週間に一枚提出することが義務付けられていた。三年生になると鳥の剥製の写生や風景写生が取り入れられた。画学生たちは、こうしてみっちりと鍛えられたのだった。」 このような東京美校に入学した一村はどのようなことを思ったのであろうか。湯原かの子『絵の中の魂 評伝・田中一村』はつぎのように想像している。「画壇を代表する有力教授、厳格な技術指導、将来の日本画壇を背負って立つべき画家の卵である級友たち。米邨にとっても、希望と誇りにあふれて始まった美校生活のはずだった。ところが米邨は間もなく、自分の目指すべき画道と美校の校風との問に相容れないものを感じ始めた。それまで研鑽を積んできた南画は画壇の趨勢ではなく、美校には南画を専門にする教授はいなかった。それに級友たちも、多くは家から仕送りを受けている比較的裕福な家の子弟たちで、自分とは別世界の住人に思われた。」 一村は結局、美校に入学して三ヶ月後に退学してしまうのであるが、美学入学の体験は梁井朗氏が「ギターを持った流しの歌手的職人」の世界と評した昔風の南画等の絵描き世界からさらに視野を大きく広げる機会を間違いなく与えたことであろう。 湯原かの子『絵の中の魂 評伝・田中一村』は、「美術学校でたとえ短期間といえども新しい日本画の潮流に直接触れたことは、大きな体験だったに違いない」とし、美校同期入学の若林景光の一村についてのつぎのような興味深い証言を紹介している。「学校に長く居らず、在学中も学校の教育など問題にしていないような態度だったのに、奄美の絵を見ると学校で習った厳密な写生を踏襲しています。それを非常に大切に守り、ますます深め、高めていってますね。みんなが卒業後はそれから離れていったのとは対照的で、たいへん珍しいタイプです。写実の厳格さは見事なもので、同期生の中でもあれだけの技術を持った者はいないでしょう。」 では、田中一村はなぜ東京美校に入学してすぐに退学したのであろうか。その理由として3つの説がある。すなわち、(1)修学困難説、(2)修学不要説、(3)美校からの追放説、以上の3説である。 まず第1説の修学困難説であるが、南日本新聞社編『田中一村伝 アダンの画帖』は、美校に入学後、「梅雨の期間に、結核が再発、安静を命ぜられた。家庭の事情も美校生活を続けられる状態になかった」としている。家庭の事情というのは、「大正十二年九月の関東大震災で麹町の家が焼失し、米邨の家族は南画家の小室翠雲の家の離れに身を寄せ世話になっていた。父稲村も病に倒れ、姉喜美子はまだ女学校を卒業(大正十二年)したばかりで、琴の名取を目ざして師匠のもとに習いに通っていた。長男孝は一家を背負って立たねばならなかった。美校に通っている余裕などなかった」というものである。 第2説の修学不要説は1926年12月に開かれた田中米邨画伯賛奨会の趣意書に書かれている。南日本新聞社編『田中一村伝 アダンの画帖』に紹介されている同賛奨会の趣意書には、一村の美校退学を説明して、「画伯今年四月東京美術学校に入学す。しかるに教授らも驚嘆していわく、〝この天才児すでに南画の妙域に達せり、何ぞ美術学校等の平凡課程を修するの要あらんや〟と。ここに於て退きて独自おおいに東洋絵画の淵源を探究して、さらに自家の新機軸を発揚せんともっぱら研究に没頭す」としている。 第3説の美校からの追放説は、加藤邦彦『田中一村の彼方へ 奄美からの光芒』(三一書房、1997年10月)で紹介されている。加藤邦彦は、1996年1月に細谷達三(一村と同期に美校日本画科に入学)にインタビューしているが、そのとき細谷達三は、加藤邦彦につぎのような衝撃的な話を語っている。「入学しても、すぐに学校をやめさせられた生徒が三人いた。学校の方針に合わなかったのか、個性が強すぎたのかよく分からないけど、田中君もその一人だった。自分は、田中君が『君の絵はとても良くできていて学校としては教えることはもうないので……』といわれたと聞いている。つまりデッサンとか絵の具、色の使い方が学校のそれに合わなかったからでしょう。」 また、加藤邦彦は鈴木草牛(一村と同期入学。1988年死去)の夫人にもインタビューしている。そのとき夫人は、鈴木草牛から「田中君は日展系ではなく、派閥もちがうから、学校に受付けられずに退学した」と聞いていたということを加藤邦彦に語っている。 興味深いことは、第2説の修学不要説と第3説の美校からの追放説とは一枚のコインの表と裏の関係にあるように思われることである。コインの表を「教授らも驚嘆していわく、〝この天才児すでに南画の妙域に達せり、何ぞ美術学校等の平凡課程を修するの要あらんや〟と」だとして、コインの裏側には、美校が一村を「君の絵はとても良くできていて学校としては教えることはもうないので……」という婉曲な表現で追放したことが不鮮明ながらも刻まれているように思われる。 こうして美校を退学した一村は、胸に複雑な思いを抱きながら、「ここに於て退きて独自おおいに東洋絵画の淵源を探究して、さらに自家の新機軸を発揚せんともっぱら研究に没頭す」ることになる。一村が「本道と信じる絵」のために南画から離脱するのは、彼が美校を退学してから4年後のことである。
2016年10月06日
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1