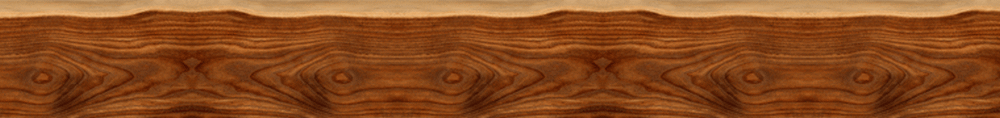[本にまあ] カテゴリの記事
全114件 (114件中 1-50件目)
-

どの本も暇を埋めるに余りある
今回の入院で私は7冊ほど病院に本を持っていき、退院までにすべて読了しました。7冊の内訳は入院に備えて新たに購入したのが2冊、読みかけていたのが3冊、買ったものの読み始めていなかったのが2冊です。入院したのが11月4日、手術が6日、そして退院が11月22日。つごう19日間の入院生活でしたが、入院から手術までに2日あり、しんどくもなくすることもなかったのでまず7冊のうち2冊を読んでしまいました。手術前に読んでしまったのは「養老先生再び病院に行く」と「論語の教え」でした。手術直後はさすがに読む気がしなかったのですが、術後3日目にもなるとかなり動けるようになり体に繋がれた管もはずれたので読書を再開。ただし、頭を使う本は疲れるので軽く読める「佐藤愛子の孫は今日も振り回される」から読み始めました。その後、読みかけていた本2冊を読み最後に手をつけていなかった2冊を読みました。どの本も私の退屈な入院生活に刺激を与えてくれ、選択に誤りはないものばかりでした。なかでも、買ってはいたもののなぜか少しも読んでいなかった2冊「ルビンのツボ」と「沖縄のことを聞かせてください」が一番印象に残りました。もっと早く読めばよかった。入院中に読んだこれら7冊の本について、感想は明日から順次載せていきたいなと思っています。
2024年11月23日
コメント(0)
-
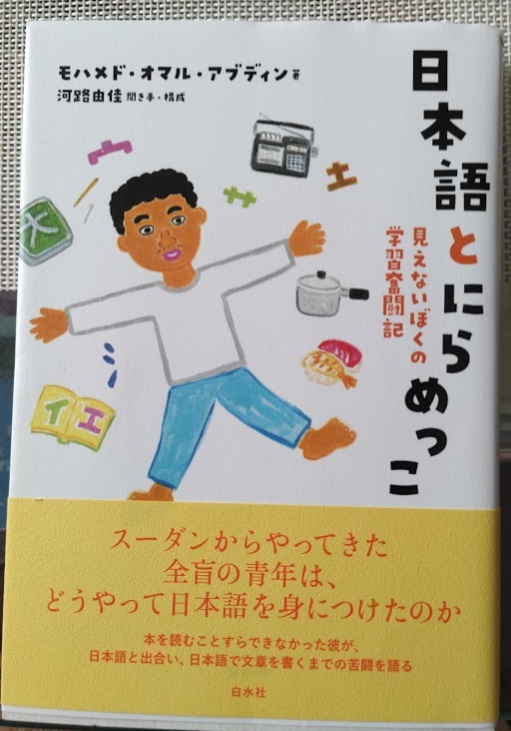
楽しんでやるからこその「奮闘」記
「日本語とにらめっこ:見えないぼくの学習奮闘記」(モハメド・オマル・アブディン著、白水社)を読みました。入院用図書(明日から数週間入院するわたしの暇つぶし用に買った図書)のはずが面白すぎて、入院する前に読み終えてしまいました。困ったこっちゃ。著者のアブディンさんは全盲のスーダンからの留学生。19歳で日本に来て日本語を覚え、鍼灸の資格を取り、大学院に進学。現在は大学の教員、研究員として、またエッセイストとして活躍しています。本書は、全盲かつまったく日本語を知らなかった彼がいかにして自分で日本語の本を出すまでになったのか、彼の日本での「奮闘記」です。「奮闘記」は副題にもなっています。しかし「奮闘記」と言われると何か違和感を覚えます。面白がりな彼のキャラクターもあって、奮闘記というより周りの人に可愛がられながら楽しく日本語を覚えていった感じがしてなりません。奮闘はたしかにしているし並大抵の努力ではないほどの体験はしているのですが、苦労したことも大変だったこともすべてを糧にしプラスにしていく彼のポジティブな性格のゆえ、そんなに奮闘しているように見えないのです。アブディンさんのおやじギャグが大好きなところも災い(?)しています。それは同音異義語の多い日本語の特徴をうまく理解して、会話に応用していくということなのですけれど。たとえば鍼灸の仕事でいきなり全盲のアフリカ人がやってきたのでびっくりする日本人の客から、「出身地スーダンはどんなところですか」と聞かれ、「スーダンは日本より数段広くて、数段暑いです」と言ってすぐに距離を縮めてしまったりします。初対面人との少しの会話からすぐに出身地を当ててしまうほど方言にも造詣が深いのは全盲ゆえの耳の良さがあるのかもしれません。が、やはりそこには彼の強い探究心があるのだと思います。たくさんの親切な日本人たちに囲まれていたのもよかったのでしょう。私自身、盲人の学習の手伝いをしたり留学生の勉強に関わったりした経験があるので、アブディンさんの学習環境がいかに恵まれていたのかはよく分かります。盲学校や鍼灸の学校以外にもボランティア的にホームステイやホームビジットを受け入れてくれた人たち、また彼の入学後、点字にする機械や盲人用パソコンを要求に応じてすべて準備してくれた筑波大学。やはりこうしたサポートがないと彼の努力だけでは難しかったところもあると思いました。それにしても大人になってから日本に来てこれだけ日本語を扱えるようになったアブディンさんはやはり稀有な存在。いくら環境に恵まれていたといっても、それは彼の努力があってこそ環境も整っていったということ。熱心に勉強し「奮闘」したことがよく分かる本でした。遊び心というか、本書を読み進めていくと何でも楽しんでしまう彼の前向きの性格が随所に見えました。やはり盲人とか留学生とか関係なく、どんな分野であっても勉強は楽しんでやること、好きになることが大事。それはスポーツや習い事などでも同じ。そんなことを思わせてくれる、とっても気持ちのいい読後感をいただきました。
2024年11月03日
コメント(0)
-
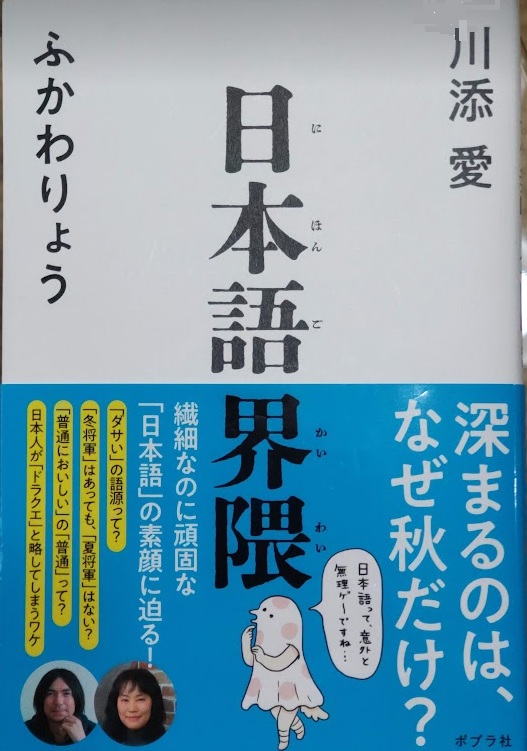
芸風はよく分からない人だけど
「日本語界隈(にほんごかいわい)」(川添愛、ふかわりょう著、ポプラ社)を読みました。著者の川添さんは言語学者、ふかわさんはご存じ、芸人の方です。「ご存じ」と書きましたが、私自身は容貌は知っていますが、あまり芸については存じません。本屋の棚で見たこの本のタイトルに引かれ、無作為にめくって読んでみたページがあまりにも面白く、購入することにしました。衝動買いのようなものですが、通読してみて正解だと十分に思い知りました。川添さんはもちろんですが、ふかわさんがこんなに日本語の表現に造詣が深い方とは。お見それしました。本書は二人の対談形式で、さまざまな日本語にまつわる話題を語り進めていきます。読み始めは「川添さんにもっと解説して欲しいな、ふかわさん素人の割りに口を出しすぎて、うるさすぎじゃないか」と思っていたのですが、途中からは考えが変わりふかわさんの言葉に対する感覚の鋭さにすっかり魅了されてしまいました。川添さんはあくまでも学術的な観点から言葉を語り、ふかわさんは感性の部分で言葉を捉え、どんどん話題を拡げていきます。ふかわさんの疑問はみな現代に生きる一般の我々の疑問になっていて、思い当たることばかり。表紙の帯に書かれたいくつかの疑問はほんの一部、「そう言えばそうだな」という言葉に関する疑問がふかわさんの口から無限に溢れ出し、いかに彼が言葉に敏感なのかがよく分かります。しかもそんな疑問を次々と、楽しそうに語ります。それは対談後の川添さんの言葉によく表れています。「言葉について語るときのふかわさんの楽しそうなこと!お話ししていると、ふかわさんの「たのしい!」という思いが波のように押し寄せてきて(中略)私の頭のなかの堤防もいつしか「たのしい!」の波に呑み込まれ、気がついたらあっという間に時間が経っていました。」(同書234ページ)この気持ち、よく分かります。私もどちらかというと川添さんの側の人間です。でもそんな「凝り固まった頭」(同書)はふかわさんにかかると軽~くほぐされてしまいます。よくこんなに次から次と話題が出てくるものだと感心しますが、ふかわさんはそれだけ言葉を愛し、言葉に敏感で、言葉と楽しく遊んでいる人だとよく分かりました。来週入院するベッドの上で読もうと思っていた本なのに一気に読んでしまい楽しみがひとつ減りました。
2024年10月29日
コメント(0)
-

したたかな沖縄人がここにいた
「ナツコ 沖縄密貿易の女王」(奥野修司著、文春文庫)を読みました。本書が最初に単行本として発行されたのは2005年、その後2007年に文庫本になりました。著者の奥野はこの本で「大宅壮一ノンフィクション賞」を受賞しました。本土ではあまり目にしませんが、沖縄の書店ではいまでも郷土本コーナーだけでなく、平積み台にもよく置かれています。前々から気になっていた本ですが500ページ近くあるボリュームに圧されてしばらく「積ん読」していた本でした。読んでみるとその展開の速さとしっかりした事実の裏打ちに、どんどんと読み進めていけました。沖縄は第二次大戦後、日本から切り離され米政府の政権下に置かれ、経済も本土とは切り離されていました。アメリカのお粗末な占領行政の下に置かれた沖縄はアメリカからも日本からもまともな物資が入ってこない状態が続き自分たちで「何とかしなければならない」立場に置かれます。そこで生きるためにやむなく行ったのが「密貿易」でした。密貿易と聞くと私腹を肥やすのが目的のような悪印象が強いですが、当時の沖縄ではそれが生き残りの手段でした。そこで若くして才覚を現したのがナツコこと金城夏子でした。夏子は商売の才能や情報収集能力に長け、若くして沖縄の「密貿易」の中心人物になっていきます。20代の若い小柄な女性でありながら、大男達は彼女の手下か子分のように働き、誰ひとり文句ひとつ言わなかった、言わせなかった。それだけの才覚があった人物でした。本書は、それまでほとんど記録にも残っていなかったこの夏子の生涯を、家族や関係者を丁寧に調べ上げ、多くの証言を得たうえで再構築しました。本書によって戦後の沖縄の経済活動の礎を築いたと言ってもいい「密貿易」の実態が、夏子という女傑の生涯を通じて明らかになりました。本書はウチナーンチュ(沖縄人)が誰にも支配されず主役となって活躍した時代を、夏子を通じて描き出した歴史書としての価値をもっています。と同時に、夏子と娘達の家族の物語でもあります。夏子が晩年、といっても30代後半ですが、娘達に見せた深い愛情を描いた第10章と終章は、ノンフィクションでありながら涙なしには読めませんでした。物語としての味わいを持ちながら沖縄の戦後の庶民史を知れる好著です。
2024年10月21日
コメント(0)
-

戦った者だけが知るモンスター
「怪物に出会った日」(森合正範著、講談社)を読みました。モンスターというニックネームを持つボクサー、井上尚弥と「出会った」対戦相手へのインタビューで構成された本です。著者の森合はスポーツ記者で、けっしてボクシングを見る眼がないわけではありません。しかし、井上がなぜこれほど強いのか、何が強いのかはわかりませんでした。そこで井上に負けた相手にインタビューすればそれがわかるかもしれないと思ったのがきっかけで、インタビューを始めました。最初は当然、負けた試合のことを尋ねるのは失礼ではないかとかなり迷い、逡巡したそうです。ところがインタビューを申し込むと、敗者たちはみな快くOKしてくれ詳しく試合の様子を話してくれました。井上戦について話すことを楽しんだりする者さえいました。井上に敗れ引退したもの、さらにそこから自らを奮い立たせリンクの上で進化したもの、対戦の「その後」は様々ですが誰もが一様に井上との対戦を喜び、それを糧にし、勲章にすら思っているという事実がありました。私と本書の出会いは最初ひとつの章をネットで読んだことでした。感動し、全部を読みたいと思って本を買いました。ネットで読んだのは若い井上に敗れ、またそこから再起するメキシコのボクサーの話でした。それだけでも十分惹きつけるものがありましたが(だからこそ本を買ったのですが)、実際に読んでみると一つ一つの対戦、一つ一つの章には井上と対戦したそれぞれのボクサーの人生が描かれていました。敗者たちの人生をこれだけ変えてしまうという事実がモンスターと呼ばれる井上のとてつもない強さを表しています。技術的なことなどはわかっていないボクシング素人の私ですが、それでも十分に読んで楽しめる本でした。
2024年10月03日
コメント(0)
-

賭け事の好きな理由はこれだった
「人はなぜ負け続けても賭けてしまうのか? 本当は怖い行動経済学(博学こだわり倶楽部編、KAOKAWA夢文庫)」を読みました。本屋さんに並んでいるのを見つけ、タイトルにつられてちょっと読んでみると内容が腑に落ちることが多く、文章も平易で読みやすいのでつい買ってしまいました。タイトルにある行動については、「負債があると人はギャンブラーになる」や「つぎ込んだ分は取り返さずにいられない」「どんな方法で得た収入かによって、お金の使い方が変わる」などの説明があります。たとえば「負債があると人はギャンブラーになる」に関してこんな実験結果が紹介されています。実験1 被験者に次のA、Bのような条件を提示してA、Bどちらを選ぶか聞く。 A.100万円が無条件で手に入る B.コインを投げて表が出れば200万円手に入る、裏なら何も手に入らないすると圧倒的な人数の人がAを選びますが、少数の人(ギャンブラー)はBを選ぶそうです。これに似た実験が次です。実験2 あなたは200万円借金を負っているとします。次のA、Bどちらを選びますか。 A.100万円無条件で返済減額される B.コインを投げて表が出れば200万円減額、裏なら減額なし今度はBを選ぶ人が圧倒的に多くなるそうです。Aは負債が減額されるものの、まだ100万円借金がある状況、Bは借金がなくなる状況で、多くの人は後者がより魅力的と感じるそうです。実は、実験1と2はほとんど同じ質問なのですが、借金のあるなしで人の行動が変わってくることを示唆しています。このように本書は、実験に基づいた研究の成果を紹介しながらある状況下で人はどのように行動するのかを豊富な行動経済学の知見によって分析し、わかりやすい言葉で綴られています。おかげで私のように経済学や社会学の予備知識のない素人にとってもとっつきやすい本でした。ギャンブルや投資で損をし続けている人は、一度本書を読んで頭を冷やしてみることも必要でしょうね。
2024年09月29日
コメント(0)
-

沖縄の本のおすすめ歴女にも
「さきがけ!歴男塾」(賀数仁然=かかずひとさ=著、沖縄タイムス社)を読みました。このシリーズの第4巻「慶良間ぁー見ーしが、まち毛ー見ーらんの巻」です。と聞いても、沖縄に関係のない人にとってはもう何が何やらですね。しかもこれは子供向けの本なんです。第4巻とあるとおり、これまで1~3巻までが発行されていて私は全部持っていますが、各巻ともすべて沖縄の歴史についてさまざまなエピソードが書かれていて、沖縄のちょっとした裏歴史から正式な歴史までが学べる仕組みになっています。本書は沖縄タイムス社発行の子供新聞「ワラビー」に連載されていたものが数年後に本になったので首里城は燃えていません。タイトルの歴男は近年はやりの歴女と、沖縄の古い呼び方であるレキオをかけたものでしょう。また第4巻のサブタイトル「慶良間ぁー」は沖縄の格言で「慶良間諸島は見えても自分のまつげは見えない」つまり「灯台下暗し」の沖縄版です。実際晴れた日には那覇空港などから慶良間諸島がよく見えますが、よほどのつけまつげでもしていない限り自分のまつげは見えません。本書は1~3巻同様、沖縄に特化した歴史的エピソードが並んでいますが、小学生対象なので理解しやすい内容になっています。第4巻では沖縄の紙すきや鶏の固有種、軟弱地盤に建てられた座喜味城とそれを作った英雄護佐丸のすごさ、などなど民俗文化から歴史上の人物のことまでが取り上げられ、ユーモア溢れる文章を通じて沖縄通になれる仕掛けになっています。沖縄県以外でこの本をみかけたことはありませんが、県内の本屋さんにはたいてい置いてあります。子供向けだけあって軽く読めますが内容はきちんとしているので、沖縄に興味のあるナイチャーにはお勧めの一冊です。
2024年09月23日
コメント(0)
-

そのよさを何とか分かりたいけれど
「なんくるない」(よしもとばなな著 新潮文庫)を読みました。本棚を整理していると十数年前に著されたこれが出てきました。読んだ記憶がありません。家族の誰かが買ったものかとも思いましたが、この文庫本が発売された2007年に私は独り暮らしでした。なので私自身が買ったものでしょう。「キッチン」でデビューしたよしもとばななのことは何となく知っていたし、タイトルから沖縄に関係していると推測して購入したのでしょうか。私は小説というものをあまり読みません。それでこの本も長く手つかずになっていたのでしょう。せっかくなので読んでみました。本書は4つの全く異なる物語をあわせた短編集です。第1話「ちんぬくじゅうしい」から順に読みました。最初の物語は中学生の少女が両親と最後の沖縄旅行をする話です。その独特の文体に慣れるのに私は苦労しました。以前もこの文体のせいで途中で読むのを休んでしまったのでしょう。なに分、心象風景の描写が多い。それに、この物語も含めてとにかく主人公への感情移入が私には難しい。およそ現実には、そのようなセリフを発する人に会ったことがない主人公ばかり出てくるのです。第4話の「リッスン」に出てくる14歳らしき女の子(主人公の30代男性の推測)がしゃべる内容は20代から30代の女性としか思えない内容で、しかもまわりくどい説明台詞を延々と述べています。またこの話でも第3話「なんくるない」でも、旅先で偶然出会った人が実は知り合いだったというちょっと都合がよすぎる話が展開し、小説は事実より奇をてらうのかと思ってしまいました。第2話の「足てびち」は「あとがき」の中で半分エッセイみたいなものと書いていてこの物語だけはある程度ストーリーを追っていけるのですが、あとの3話は何かご都合主義的なファンタジーに終始していて理解しようとしてもなかなか頭が追いついていきません。ガラにもなく小説を読もうとした私が間違っていたのか、よしもとばななさんの作風がそうなのか。大衆小説と純文学の違いはよく分かりませんが、よしもとさんは小説のスタイルで純文学を書いてしまったのかな、というのが私の印象でした。いずれにしろとっても世俗的な価値しか持ち合わせていない私には文学は向かないことが分かった作品でした。それではいけないと思うのですが、本書を読んでますます、よしもとさんの作品と文学作品に距離を感じてしまったのでした。
2024年09月09日
コメント(0)
-

手にとってすぐに購入決めた本
「介護ヘルパーごたごた日記」(佐東しお著 三五館シンシャ発行)を読みました。訪問介護ヘルパーという職業、つい最近まで家庭介護を受けていた両親のもとにも来てくれていたので私にはとてもおなじみです。著者の佐東さんは重度の障害のある子どもがいますが、子どもが支援学校を卒業し生活介護事業所に勤め始めて少し手が離れたので、この仕事を始めたのだそうです。現在は勤務10年の還暦のヘルパーさんです。両親の介護をしていたのも同年代の人が多かったなと、読みながら彼女たちの顔が思い浮かびました。入浴やおしもの世話の大変さ、認知症患者とのつきあい、そして利用者本人や家族からのハラスメントも経験している佐東さん。そのいくつかは両親の介護ヘルパーさんも直面していたことで、彼女たちと毎日顔を合わせていたのでその苦労は分かります。しかし本書を読むまで、これだけ働いていてこんなに給料が少ないとは知りませんでした。佐東さんの働いているところでは利用者宅訪問への行き帰りの交通費も出ないとか。両親のヘルパーさんは15分以上かけて車で来ていたけれど、往復の30分は勤務時間になっていたのかな。ガソリン代は?生でヘルパーさんたちと接していて、その働きぶりには頭が下がり高齢化社会ニッポンを支えているのは彼女たちだと実感しました。ただ、トイレのたまり水で雑巾を洗うヘルパーさんや行きたくない利用者の場合に無断で欠勤しそのまま辞めてしまう困ったヘルパーさんの話も出てきます。が、ほとんどのヘルパーさんは飲食の供応を受けない、個人情報の守秘義務を守る、などきちんとルールを守って働いていることが分かります。他のヘルパーに迷惑をかけるので決まった範囲を超えた仕事はやらないようにもしているそうです(「あのヘルパーはやってくれたのにあなたはしてくれないの」などと言われるから)。そうしたことは重々分かった上で、それでも仕事を離れた個人的つきあいまでやってしまうのが佐東さんのやさしいところ。認知症の入った利用者さんと二人、ヘルパーという立場を離れ友達としてお花見に出かける最後のエピソードには佐東さんの暖かさとプロのヘルパーの矜持が見えてほろりとさせられ、ちょっと感動してしまいました。
2024年08月31日
コメント(0)
-

その時代あらわす貴重な証言が
「わたくし大画報」(和田誠著 ポプラ社)を読みました。和田誠さんは数年前に亡くなったイラストレーター。料理研究家の平野レミさんの旦那で和田明日香さんのお舅さんでもあった人ですが、私としては大好きなSF作家、星新一の本の挿絵画家としての印象が一番強くあります。もちろんそれ以外の仕事もたくさんなさっており、ひと目見ると「あ、和田誠の絵だ」とすぐに分かる特徴的なイラストを描く人でした。この本は和田誠さんが1970~80年代にいくつかの雑誌に執筆されていたエッセイを集めた本の復刻版です。そのため話題は当然、その頃の出来事に限定されます。再ブレイクする直前の中尾ミエのショーを見た話から、台湾の航空機事故で不慮の死を遂げた向田邦子と会談した話、ブレイクする前のタモリの話まで。今となってはどれもこれも芸能界や文壇の昔話の範疇に入ります。すでに鬼籍に入った人の話も多く出てきます。ご本人も5年前にそちらに行かれてしまいましたが。4、50年ほど前の本ですから取り上げている人だけでなく、取り上げ方が昭和的です。ハウス食品の「私ツクルヒト、僕タベルヒト」のCMをきっかけに始まる男女の家事分担の話やトイレの便座を上げておくか下げておくかの話、ご自身の子どもの誕生から子育ての話など、和田さんの率直なコメントが詰まっています。エスカレーターの片側をあけない人に腹を立てていたりもします。今なら「不適切」と思われることでも素直な性格の和田さんならではのストレートな物言いが見られます。ただこう考えるのは和田さんだけでなく、そういう時代だったこともあるのでしょう。よく昔の映画の再放送で最後に「この映画には現在では差別とされる言動が出てきますが、原作者の意図を忠実に描くためそのまま放送しました」と注意が出てくる場合があります。本書でも「これは今の時代にはどうだろう」という表現がままあり「大丈夫かな」と思いましたが、編集者はやはり「今日の観点から見ると差別的表現ととられかねない箇所がありますが、著者がすでに故人である等の事情に鑑み、原文どおりとしました」と断り書きをつけていました。和田さんの広い交友シーンも含めて50年前の日本文化を記録したドキュメンタリーのような本でした。
2024年08月27日
コメント(0)
-

続編はちょっと違ってこれもヨシ
「オバァの渇(カーツ):続・沖縄オバァ列伝」(沖縄オバァ研究会、双葉文庫)を読みました。第一遍の「沖縄オバァ列伝」と同様、こちらも約20年前に発刊されたオリジナルを復刊した本です。そのため登場するオバァの年齢や情報は当時のままとなっています。私は第一遍のオリジナル版が出た当時にすぐに購入して読んだ覚えがありますが、こちらの続編は読んだことがなく、今回復刊されて初めて目にしました。どちらもいま沖縄の書店では平積みされていてよく売れています。こちらの続編にも生命力にあふれ、周囲を圧倒しながらも愛されているオバァがたくさん登場します。ただ第一遍に比べて周りを振り回す荒唐無稽なふるまいをするオバァの描写が減り、大変な世の中を立派に生き抜いてきた人物が多く描かれています。最後のほうに、2015年に亡くなった「ちゅらさん」のオバァ役でおなじみの平良とみさんの話が出てきます。彼女は方言で演じられる沖縄芝居の中心的存在として、また超モテモテ役者平良進さんの奥様として、苦労を重ねながら、役者として人としてそしてオバァとして超一流の地位を築いた方。第一遍にみられるギャグのようなおもしろ話と同時にじっくり読めるオバァ話も多く、第一遍よりも読みごたえがありました。
2024年08月12日
コメント(0)
-

難解な本ではないが用語がね
「『指示通り』ができない人たち」(榎本博明著 日経プレミアシリーズ)を読みました。あちこちの書店に平積みになっているのを目にし、タイトルに興味を抱いて購入してみました。著者は心理学者。企業の管理職や先輩社員からみた「指示通り」ができない若い社員に関する悩みを分析し、解決するために書かれた本です。著者は「指示通り」にできない人たちの問題点を3つに分けて説明します。1.認知能力のない人 2.メタ認知能力のない人 3.非認知能力のない人 です。著者は「ない人」などという言葉は使わずに「改善の必要な人」というソフトな言い方をしていますが、まあ言っていることは同じかと思います。そこで気になるのが「認知能力」という言葉です。あまり一般的でないと思われるうえ、そこに「メタ」や「非」が付くので「何か専門的で難しい本なのかな」と身構えてしまいます。本書を読んで、私は3つの能力について次のように理解しました。1.認知能力:仕事そのものやコミュニケーションに関する能力 2.メタ認知能力:自分の能力を過大に評価したり過小に評価したりせず客観的に把握する能力3.非認知能力:仕事周辺の状況をコントロールして、やる気や粘り強さ、集中力を持続させる能力いま開催中のオリンピックを見ていて、これはスポーツの場でも言えることのように思いました。1.競技力そのものを高めること、2.自分の能力を過信したり逆に自己不信に陥らないこと、そして3.いい準備と最後まで諦めずやり抜く精神力をもつことが結果につながる。と。新入社員のどこに「問題」があるのか。それを見極めるヒントが得られる良書だと思いました。
2024年08月02日
コメント(0)
-

私には到底できないワザを見た
「書店員は見た! 本屋さんで起こる小さなドラマ」(森田めぐみ著 大和書房)を読みました。タイトルそのままの本です。書店で働く森田さんが、お客さんとのドラマチックな出会いを経てその人にお薦めの本を紹介するエピソードが一杯出てきます。森田さんのやっていることは本の紹介を通じた人生相談ですが、「なんでそんなに」と思うほど様々なトラブルを抱えたお客さんと出会い、そしてその客にぴったりの本を紹介していきます。そもそも書店員と客は、本の所在を尋ねる以外にそんなに親身な話をしていますか?私は残念ながら森田さんのようなフレンドリーな書店員さんにまだお会いした機会がありません。森田さんは客の「悩み」を聞いてすぐにその人に合う本を選び出し、紹介することができる「カリスマ」書店員さん。本を紹介された人は一様に喜び、次回の来店時には「悩み」が解決されています。もう、ちょっと森田さんのファンタジーが入っているのではないかと思いたくなるほどです。ただもしこの通りの書店員に出合ったら私はちょっと苦手かも知れません。本を選んでいる間はあまり話しかけて欲しくないし、それになにより本は人から紹介されたくありません。それに私の方から誰かに紹介もしたくないのが私のポリシー。人はひとりひとり育ちも興味も異なり、同じような悩みに出合ってもそれを解決する道はその人なりのものだと思っています。私も人に「お薦めの本」を聞かれることがありますが、具体的な書籍や著者を薦めることはめったにありません。その割りにこのブログには読んだ本の感想を書いていますが、それはあくまでも自分の感想。誰かに薦めているのではないつもりです。我が家に来た人が私の蔵書を見て「これ読んでみたい」と言う場合は「必ず読まなければならないと思わないでください」「少し読んでみて興味がなければ読まなくていいです」などと言います。人から本を借りると「読まなければならない」「感想を言わなければならない」というプレッシャーがかかります。読んで面白ければいいですが、そうでない場合は読了すること自体が苦痛でしかありません。私の興味の範囲は誰とも違います。私が読んで面白いと思った本は誰にとっても面白いわけではありません。そのような理由で私はめったに本を人に薦めません。なので、逆にその人に合った本がパッと思い浮かび、どんどん薦められる森田さんはすごいなーと思いました。
2024年07月19日
コメント(0)
-

この表紙ホントはすごく怖いのよ
「国道沿いでだいじょうぶ100回」(岸田奈美著、小学館)を読みました。岸田さんの本は「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」以来、欠かさず読んでいます。それにしてもタイトルが長い。岸田さんの本を読んだのは同名のテレビドラマ(NHK-BS)をたまたま見て、それが何とも言えず面白かったので原作も読んでみようと思ったのが最初でした。「家族だから~」はドラマも原作もどちらにも変な面白さがありました。今度読んだ本にもそれは共通しています。岸田さんは中学生の頃に父親を亡くし、弟はダウン症で母親が大動脈解離から車椅子生活になり、助けてもらっているはずのおばあちゃんが認知症という「不幸ネタ」満載の家族です。でも彼女はヘレン・ケラーが言った「(障害は)不幸ではなく不便」そのものとして捉えています。それは彼女のどの著書にも共通に出てくる考えです。「国道沿いで~」にもそうした考えが随所に出ていて、不便ゆえに起こる様々な出来事を独特のユーモアで描きます。笑いながら読んでいると、不便ゆえ不幸になりそうなことをとても真剣に語っていて、感動的なエピソードにいつしか引き込まれていたりします。とくに私の心に残るのは次の二つのエピソードでした。「『死ね』といったあなたへ」(p.97~p.110)「魂を込めた料理と、命をけずる料理は違う」(p.170~p.178)前者はブログでそんな衝撃的なコメントを受けた経験の話、後者は急に大きく値上げしたラーメン店の話。この二つのエピソードを通じて彼女は、表面だけで即座に物事を判断し決めつけてしまう危うさを語ります。そう言わざるを得ない人、値上げをせざるを得ない店にはそれぞれそれなりの理由がある。最初は怒りや驚きをもって反応したけれど事情を知っていくといずれも深い理解に至る。「神は細部に宿る」を地で行く、一見どうでもいいようなところの彼女の細かな表現が実際は説得力を高めています。本書の著者紹介で初めて知りましたが、岸田さんはForbesの「世界を変える30歳未満の30人(30 UNDER 30 Asia 2021)」に選ばれていたんですね。さもありなん。彼女なら世界を変えられるでしょうし、すでに変えつつあるのは間違いありません。BSで放送されていた「家族だから~」は、NHK-Gでも放送が始まりました。以前見逃した方は是非ご覧ください。
2024年07月13日
コメント(0)
-
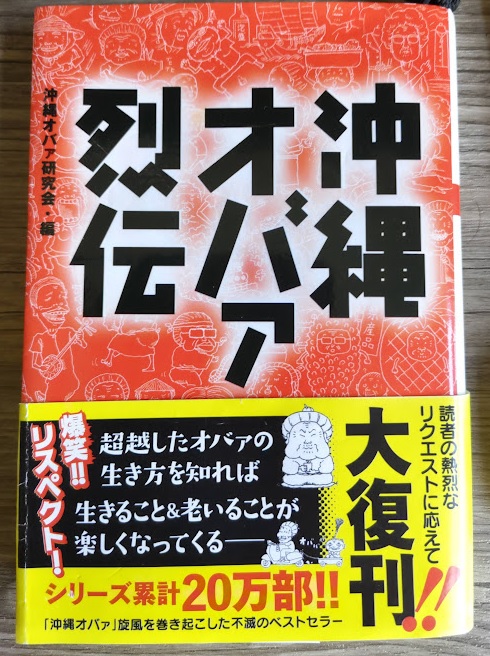
20年経ってもオバァはオバァです
「沖縄オバァ列伝」(双葉文庫 沖縄オバァ研究会・編)を読みました。この本を読むのは2回目になります。1回目は20年以上前、最初にこの本が出版されたときでした。そのときはまだ沖縄に住んでおらず沖縄を訪ねたのも1、2回しかなくて、この本に書かれているオバァがほんとにいるのか半信半疑で、デフォルメして面白おかしく書かれているのではないかと思っていました。しかし沖縄に住むようになり知れば知るほどオバァはこのまま本の通りだという気がしてきました。今回20年ぶりの復刊。迷いなく買いました。私は本を一度読むと二度読みすることはほとんどありません。誰かにあげてしまったりすることもよくあります。この本もたぶん誰かにあげてしまったのか、手許にはありませんでした。でも、20年経って書店に並べられた復刊された本を見たとき、もう一度読みたくなり、迷いなく買ってしまいました。内容は覚えていましたが、見方が少し変わりました。本書の内容は全然デフォルメでも何でもなくフツーに真実です。行動は若干違ってきているような気もしますがオキナワン・スピリットは今のオバァも変わりありません。沖縄に親戚や高齢の友人・知人がいない私は、日常生活で「列伝」中のオバァのようなオバァにはなかなか会えませんが、たまたま居合わせただけなのに人なつっこく話しかけてくるオバァやリサイクルゴミの日は集積所からアルミ缶だけ「収集」していくオバァ、90歳前後になっても市場で現役のお店をやっているオバァなどはまだまだ見かけます。若い人もオバァを自然に愛し敬っていてだからオバァはオバァでいられるのだろうと感じます。続編も買わなくちゃ。
2024年07月12日
コメント(0)
-
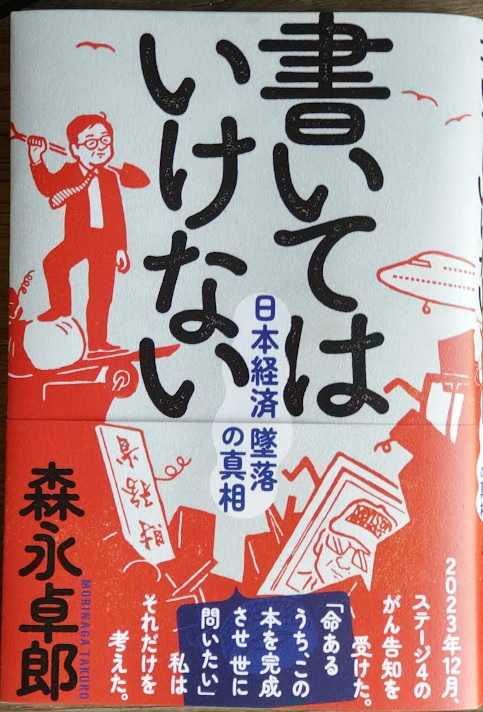
もしかして「読んではいけない」本だった?
「書いてはいけない:日本経済墜落の真相」(森永卓郎著、三五館シンシャ)を読みました。とてもにわかには信じがたい内容でした。財務省は事実上、日本の三権分立の上に立っていること。そして、日航機墜落の真相は自衛隊の誤爆によるものだということ。それは多くの人が承知している事実であるにもかかわらず知っている誰もが口をつぐんでいること。その理由はメディアや関係者の、我が身を守ることを優先した忖度であること。しかし、衆人承知の事実でありながら誰もが表向き触れなかったもう一つ大きな問題「ジャニー喜多川事件」はBBCの報道や勇気を持って告発した被害者らによって真相が明るみに出ることになりました。そこで森永さんは、ジャニー喜多川事件と同様に、財務省や日航機事件の真相も勇気を持って告発しなければならないと考えました。森永さんはいまステージ4の癌患者であることを公表しています。まえがきで森永さんは言います。これらのことを書くことによって「大きなリスクがあるのは承知だ。逮捕されるかもしれないし、命を狙われるかもしれないし、訴訟を起こされるかもしれない」(同書10ページ)。それでも「命あるうちに」真実を知らせたかったことを思うと、本書の伝えたかった事実の重みを感じます。発行社はあの日記シリーズで有名になった三五館シンシャ。驚いたことにここは社長が一人で経営するひとり出版社だそうです。この、忖度無用な二人がタッグを組んだからこそ実現できた企画なのかも知れません。実際、森永さんは本書の企画を多くの出版社に持ちかけ断り続けられたと書いています。関西空港で飛行機に乗る前にふらりと寄った本屋さんでふと目に入ったこの本。暇つぶしにと思った本でしたが、重たいものをつきつけられました。
2024年04月21日
コメント(0)
-
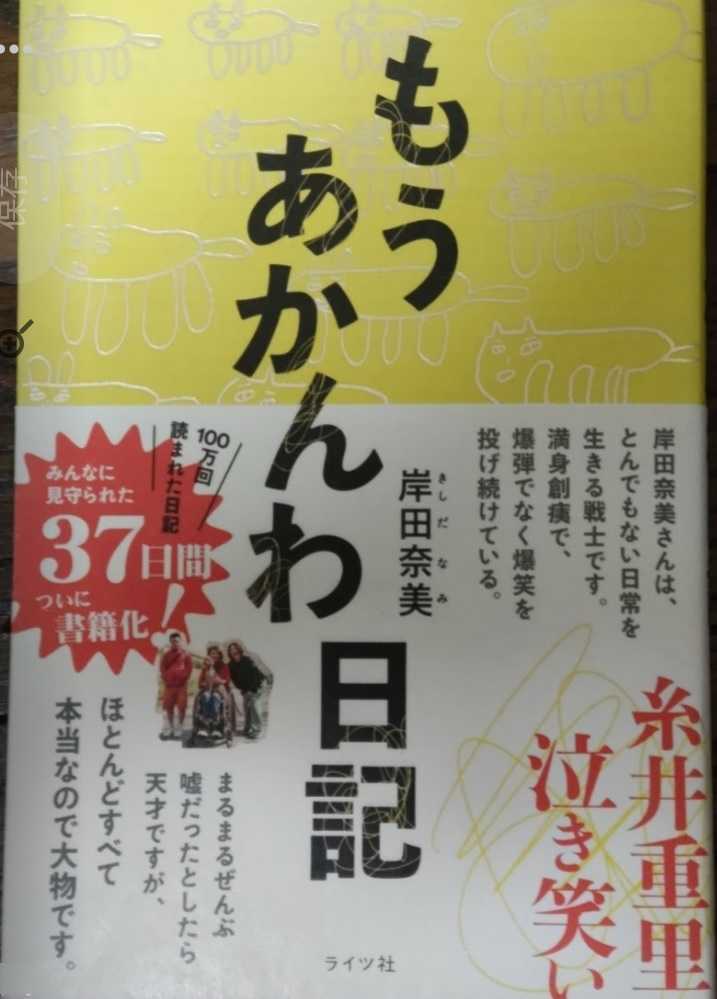
「もうあかん」言ってしまうと楽になる
「もうあかんわ日記」(岸田奈美著、ライツ社)を読みました。以前NHKで「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」というドラマを見て著者のことを知り、それからドラマの原作本をはじめ著者の本はすべて読んできました。何せドラマの印象が強烈。主演は「不適切にもほどがある」でブレイクした(私の中では『愛したのが・・・』でブレイクしたと思っていますが)河合優実。関西弁が完璧で「絶対関西の子」と思っていたら東京出身で驚いた、のはまた別の話。タイトルにあるとおり、この本は著者岸田さんの日記。どう考えてもフィクションだろうと思われるあり得ない日々の連続を綴ったものです。そもそも岸田さんは若くして父親を亡くし、その後もお母さんが病気で車椅子生活になり、弟がダウン症、おばあちゃんが認知症と、たくさんの「もうあかん」になりそうな要素を抱えています。次々と襲いかかってくる、思わず「もうあかんわ」とつぶやきたくなるできごとが連続する日々。と書くと壮絶な話のように思えますが、それを彼女のユーモアあふれる文章で軽く読ませてしまいます。いや、本当は軽くはなく重い話ばかりなのですが、全然そんな感じはありません。前述のドラマ「愛したのが・・・」もこうした家族の話をドキュメンタリー風に描いた軽妙なタッチのもので、だからこそ岸田さんのファンになりました。岸田さんは「もうあかん」と思ったことを文章にし誰かに読んでもらうことを自らのエネルギーにしてきました。私も「もうあかんわ」と言いたくなることもあります。彼女に比べれば全然たいしたことではないことがほとんどですが、それでもこうして日々のできごとを綴ることが何かの救いになっているのかなあと思いました。いま深刻な状況に陥っていて「もうあかんわ」と思っている人に読んでもらいたい本です。
2024年04月16日
コメント(0)
-

巡りきてバカがバカども批判する
「バカ老人たちよ!」(勢古浩爾著、夕日書房発行)を読みました。書店に並んでいたこの本、表紙の絵と帯のことばが気になって手に取ってみました。適当なページを開いて読むとなかなかおもしろそう。実際に買って読んでみることにし、一日ですぐに読了しました。さて、読後の感想ですが、ちょっと評価が分かれそうな気がします。共感できる部分もあれば、ただの年寄りのたわごとのように思える部分も(著者は70代後半)あるからです。プーチンや習近平らをクソミソに書いているところは胸がすきます。これぐらいの歳になるともう怖いものはないのかという気がします。一方で、老人に関するたくさんの書籍の書評では的確なものもあれば単なる言いがかりのような論も目につきます。いわゆる街で見かけるバカ老人、昭和を引きずって周囲に老害をまき散らしているリタイヤ老人に関する批判はそれほど問題がありません。でも、書評の中には難癖をつけているような、やや強引かなと思える箇所も。著者自身がちょっとそんな老人のひとりになっているところが見える部分もあります。本書の帯に「ひとのバカ見てわがバカ直そう」と書き、「まえがき」で自分もそのバカ老人に入るとおっしゃっているのは免罪符のつもりでしょうか。そうした謙虚な気持ちからでた「老人批判」であれば問題はなかったでしょうが、自分を棚の上に置いておいて大所高所から見下ろす部分がなきにしもあらずだったのは、全体としてはおもしろかっただけに少し残念な気がしました。と、こう書いている私も人のことは言えないバカ老人のひとりなのではありますがね。
2024年03月25日
コメント(0)
-

実際に食べたら羊肉だった
「障害者支援員もやもや日記」(松本孝夫著、三五館シンシャ発行)を読みました。本書もその一つである三五館シンシャの日記シリーズを私は好きでよく読むのですが、最近のシリーズでは「看板に偽りあり(いい方に)」の本が多くなってきたように思います。シリーズの「〇〇日記」の〇〇部分には「よれよれ」「へとへと」「こそこそ」など否定的なことばが入り、本書でも「もやもや」となっていますが実際にはそれほど「もやもや」した話ではありません。著者はもやもやしながらではなく信念を持って働いており、読後感はむしろさわやかなものでした。著者は経営していた会社が倒産した後、家庭の事情もあり70歳になって非常勤として障害者支援施設で働き始めます。高齢者施設のつもりで応募したのが障害者支援施設だったとの偶然の出会いはありましたが、元々好奇心旺盛で仕事熱心な著者は障害者支援の仕事に前向きに取り組み、間もなく80歳の大台を迎えようとする今も働く意欲は衰えません。たしかに本の帯のような大変なこともありますが、それでも彼が支援員を続ける「理由と意味」はあるのです。本書を通して障害者を取り巻く環境、家庭や社会、授産施設などの実態、国の取り組みなどを私たちは詳しく知ることができます。精神障害、知的障害とは何か、またその当事者に対してどのように接すればよいか。彼らの人権への配慮や性の問題にも踏み込んでいき、読者は著者の軽い筆致を通してしかし実際は重い問題に向き合わされることになります。「羊頭を掲げて狗肉を売る」ということばがありますが、狗頭を看板にして羊肉を売る、そんな印象の本でした。
2024年03月23日
コメント(0)
-

幼児からおとなも涙止められず
「もう一度読みたい 教科書の泣ける名作」(編者 Gakken、発行 Gakken)を読みました。「ごん狐」「かわいそうなゾウ」「ちいちゃんのかげおくり」など各世代にとってなつかしい、教科書で読んだことのある名著にあふれる本です。「泣ける」話ばかりではなく、考えさせる内容であったり、教室で子ども同士意見をたたかわせる内容であったりと、まさに教科書掲載にふさわしい名作が揃っています。「ごん狐」と「かわいそうなゾウ」は自分自身子どもの頃に読んだ気がします。「ちいちゃんのかげおくり」は子どもの教科書で見たように思います。「ちいちゃんの・・・」は最初に読んだときから涙があふれ、いま読み返してみてもまた目頭が熱くなってしまうのですが、こんな物語を授業で読んだりしたら教室中が大泣きしてしまって授業にならないのでは想像してしまいました。ある知り合いに、ことばが出るのが大変遅い子どもを持ったお母さんがいました。お誕生を過ぎればたいていの子どもはひと言ふた言しゃべりはじめ、2歳にもなれば2語文や3語文が出てくる子どもが大半ですが、その子は3歳近くまで自分から話すことが全然なかったそうです。上におしゃまなお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんが彼の要求を全部分かって代わりに話してくれたことも影響していたのだろうと言っていました。でもその彼、聞いて理解することはしっかりできていたのです。それが分かったのが「ごん狐」でした。自分から全然話そうとしないときから彼は母親に本を読んでもらうのが大好きだったそうです。そして「ごん狐」を読んでもらうと必ず泣いてしまっていたというのです。全然しゃべらないくせに「ごん狐」のお話を聞かせると必ず泣く。それがおもしろくてお母さんは何度も何度も「ごん狐」を彼に読んで聞かせたとか(悪い親です)。それを笑って私に伝えてくれました(悪い親です)。ことばがまだ出ない子どもにも「ごん狐」の悲しさはしっかりと届くのだとある意味感心しました。本書に収録されたお話は、上記の3編以外にも心に残っていてるものがたくさんあります。お話の中には読んだはずだけど忘れてしまっていたもの、初めて読むものもありました。知っている話も知らない話もひとつひとつどれも心にしみるもので、教科書を通じて子ども達がこんな話を学んでいれば日本の情操教育は安心だと思いました。ちなみに「ごん狐」を読んで涙した、ながくことばが出なかった彼はいま小学校の先生をしています。
2024年03月19日
コメント(0)
-

あらためてペンの力を考えた
「母という呪縛 娘という牢獄」(齊藤彩著、講談社)を読みました。内容は写真にある通りです。母親の学歴信仰の呪縛にがんじがらめになった医学部志望で9浪をした娘が、「モンスター母」から自由になるために母を殺すしか解決方法を見いだせなかった事件。発売当初から各方面で話題になっていて私も数ヶ月前には購入していたのですが、内容の重さからなかなか読めませんでした。奈良にいるときは沖縄で、沖縄では奈良で読もうと、この本は何度も飛行機で往復をしました。なかなか読めませんでしたが読み始めると一気に読んでしまうんだろうなと思っていました。いつかは読まないといけないし読みたいとは思っていたので、昨日意を決して読み始めることにしました。すると、やはり止まりません。話の展開が気になって、途中でやめるきっかけが見つかりません。一つの章を読み終えて小休止はするのですが、結局すぐにまた次の章に取りかかってしまう、の繰り返し。結局数時間の後には300ページ弱を読了していました。娘はなぜ母を殺さなければならなかったのか。母はなぜここまで娘の学歴や人生にこだわったのか。それが元共同通信社の記者、齊藤彩さんの丁寧な取材によって明らかにされていきます。留置場や刑務所での『娘』との面会の様子、娘から受け取った手紙も多く掲載されていて「これは私と彼女の合作だ」とも述べられています。本書には子どもの頃から事件を起こすまで、そして殺人を否認し続けた1審の供述を覆して第2審で殺人を認めるまでの娘の心の動きが詳細に示されています。周りの人たち、弁護士、裁判官、父親をはじめ彼女の人生にかかわった関係者の証言から、彼女が事件を起こすに至った経緯を読者は理解していきます。しかし死人に口なし。母親がどうしてそこまで娘を牢獄に閉じ込め監視してしまったのか。それは分かりません。「この程度」の学歴信仰や子ども支配は世間にはよくあることなのか。子どもを縛り付けるやり方を見ると彼女が飛び抜けてエキセントリックな性格だったのか。それは彼女が死んでしまった今となっては分からない部分も多々あります。ただ、客観的に見ても娘に対する折檻や精神的支配にはかなり度を過ぎたところがあるのは事実です。何とか児童相談所や警察が関われていたらここまでの悲劇にはならなかったでしょう。殺人を否定し続けて出された1審の18年の刑期が、2審では殺人を認めたにもかかわらず10年に短縮されました。そこには事件に至った「娘」の人生に対する裁判官の理解の深まりがあったからでしょう。本書を通じてそのことは深く伝わってきます。犯罪者には事件に至るストーリーが、それこそ犯罪者の数だけある。それはこのような忌まわしい事件についても同じ。そう教えてくれるノンフィクションを書き上げた齊藤さんには一読者として敬意と感謝を捧げたいと思います。素晴らしい本でした。
2024年03月08日
コメント(0)
-

やばすぎる面白すぎるやばい本
「東大教授がおしえる やばい日本史」(本郷和人監修 ダイヤモンド社)を読みました。売れ筋本が平積みで並ぶ書店の本棚にあるのを最初みたときは汚いマンガだなあと思って「読まず嫌い」を決め込んでいましたが、ちょっと手にとってパラパラと眺めてみると内容が秀逸でした。取り上げ方といい、全体解説といい、とても分かりやすい。分かりやすいだけでなく、面白すぎました!私には信号待ちをしている車で読書する(よい子はまねをしないでね)習慣がありますが、そのときに読む本は2~30秒でもインパクトのある短編と決めています。この本は日本史に登場する人物をマンガつきで見開き2ページほどで解説していて読むところはとても少なく、信号待ち読書に最適です。ところが信号待ちだけでは物足りず車をとめて続きを読み、最後は家に持ち帰ってしまいました。取り上げられている人物は卑弥呼から始まって、聖徳太子やいま話題の紫式部、信長、家康から西郷隆盛、伊藤博文、そして吉田茂、太宰治まで。歴史に登場する有名人40人弱について、ひとりひとり「すごいところ」と「やばいところ」を取り上げています。それぞれは歴史の上で「すごい」ことを成し遂げた人ばかりですが、一方では人間として「やばい」ところもあったと面白おかしく解説しています。たとえば葛飾北斎は世界の画壇に影響を与えた天才画家だった反面、家はゴミ屋敷だったとか。こんなエピソードを人物ごとにそれぞれ2~4ページを使って解説。しかもそれを子どもにも分かりやすく現代の風潮になぞらえて説明しているので、日本史を学び始めた子ども達の興味を引くことは間違いありません。そう。この本は子ども向けなのです、たぶん。その証拠に読みがながついていますし、「芸者」のように大人にはわかりきった用語の簡単な解説も載っています。この本を読んで思い出したことがあります。子どもの頃から「マンガで見る日本の歴史」みたいな本が好きでした。歴史だけで無く、あらゆる教科についてマンガつきの学習書をいつも図書室で借りて読んでいました。小学校で読書カードというのがあって一年を通して読んだ本がリストになっていましたが、あるとき友達が「どんな本を読んでいるの?」と言って私の読書カードをのぞいてきました。そこにあったのは全てマンガ。文字だけの本はリストには一冊も無くちょっと恥ずかしかった記憶があります。私はマンガ大好きな子どもでした。大人になり文字だけの本も読むようになりましたが、やはり原点はここだったようです。
2024年02月20日
コメント(0)
-
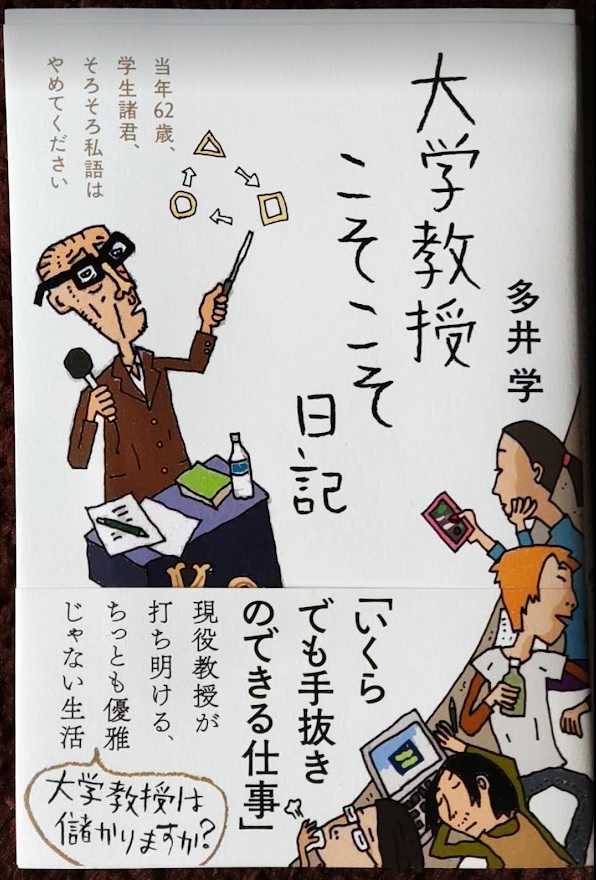
これからは過酷な業界 仲間入り
「大学教授こそこそ日記」(多井学著 三五館シンシャ)を読みました。この日記シリーズは好きで、結構読んでいます。たいていはその業界の過酷さが描かれています。しかし、本書に出てくる大学教授の仕事はそれほど過酷に見えません。私も知らない業界ではないのでどんなことが暴露されているのか興味津々で読みましたが、世間によくある職業の一つ程度に描かれていました。著者が大変だと書いている長時間にわたる会議や全員参加の慰安旅行は他の業界でもあること。大きな問題が発覚した場合は長時間会議はあり得るし、全員参加の慰安旅行も小さな企業ではある話です(さすがに最近は減ったでしょうが、本書の話も数十年前の話)。タイトルの「こそこそ」も、こそこそ仕事をやるのではなく本書を出して身バレしないかが気になる「こそこそ」です。多井教授の仕事ぶりは何もこそこそしていません。むしろ堂々と研究や教育に邁進する姿は立派ですし、帯に「いくらでも手抜きのできる仕事」と書かれている割りには全然手を抜くこともなくしっかりと立ち向かっています。研究業績にちっとも関心がない教授の話も出て来ますが、それはむしろ例外です。ただ最近は教授も業績を上げることが必須になったとか博士号があっても就職できないとか、業界が厳しさを増しているのは事実。文部科学省は教授も含めて毎年業績を上げ報告しろと締め付け、文系学部でも就職するために博士号は必須となり、博士号があったところで教授職に就けるのは宝くじに当たるようなものになっています。その意味では大学教授という職業は若者にとって目指したい職業でなくなってしまいました。大学教授はあまり過酷ではないようだと最初に書きましたが、それは小規模短期大学→地方国立大学→関西大規模私大と多井さんがたどってきた、これまでの過去の話。今後は教授を目指す人にとっても教授になった人にとっても、いずれも厳しい世界になることは覚悟しておかなければなりません。少子化が進むなか大学の数は減らないどころか増えている実態を見ると厳しくなるのも当然でしょうね。
2024年01月27日
コメント(0)
-

マリさんに向う側へと誘(いざな)われ
「扉の向こう側」(ヤマザキマリ著、マガジンハウス)を読みました。漫画家でエッセイストのヤマザキさんの経験談をご自身のイラストつきで掲載した短編集です。元は雑誌の連載だそうですが、私は本書で初めて読みました。絵のスペースを含めて4~5ページずつのショートストーリーが30編弱。ヤマザキさんの子どもの頃から最近までの色んな人との出会いが時間を前後しながら描かれています。沖縄に移動する機内の2時間で読めるとふんでいたのですが、読んでいると一気に読んでしまうのがもったいなくなりました。短編ながら一つ一つの物語に透明感があり、何気ない日常が描かれているようでいてドラマがあり、良質の短編映画を見ている気分です。新たなストーリーを繰るとそれまでとは全く別の世界に誘われます。どんどん読み進めないで一つ一つをじっくり味わった方がいいと思い、沖縄に行く飛行機では半分ほどで本を閉じました。沖縄にいた2週間の間は読まず、昨日、関西に戻る飛行機のなかで「満を持して」残りの半分を読みました。初めてひとり旅をした少女時代のイタリア、ブラジル移民日系一世の人との機内の出会い、幼い頃の祖母との短い同居生活、ボランティアで訪れたキューバで会った貧しい大家族。ヤマザキさんは軽々と国境を越えさまざまな世界に生きる人々を読者にとって身近な存在にしてくれます。そして、本の帯にあるように「自分に見えてる世界なんてほんのちっぽけ」だと私たちに気づかせてくれるのです。おかげで沖縄から関西への2時間の飛行機の旅があっという間でした。
2024年01月24日
コメント(0)
-

思春期の子どもと親に向けた本
「思春期のトリセツ」(黒川伊保子著 小学館新書)を読みました。私には孫が4人います。そのうちの一人、中学生男子がもうすぐ誕生日を迎えます。私は孫達が誕生日を迎えるたびに、毎年その子に合う(と私が思う)本を一冊ずつ送ってきました。小さいときは文字のない絵本だったり、少し大きくなると日本や世界の名作だったり、また子ども向けの図鑑だったり。孫の顔を思い出しながら本屋さんであれこれ吟味するのが楽しい時間の過ごし方でした。そして最年長の孫はいま思春期まっただ中。大人向けの本でも読む年齢です。そこで今年送ることにしたのがこの本。本の題名からしてこれは思春期の子どもを持つ親に向けた本ではあります。たしかに親である私の息子と嫁にも読んでもらいたいと思います。でも、同時に中学生が読んでもいい本ですし、私としてはどちらかと言えば彼に読んでもらいたいと思いました。著者の黒川さんも親子で読めばいいと記しています。黒川さんは脳科学、そして人とAIの会話の専門家。その立場から男性脳や女性脳の特徴を踏まえた本を著しています。内容は科学的知見に基づいて書かれているためにどれも胸にストンと落ちるもので、しかも人にあたたかいのです。トリセツ、すなわち取扱説明書の体裁を取りながら読んでいて私には感動の連続でした。たとえば思春期を迎えた子どもに対する性教育を扱ったところでは、女性の身体的特徴を科学的に説明した上で、思春期男子に「一生をかけて命がけで相手を守る」ことがなぜ大切なのかを述べます。倫理や道徳の教えではありません。それが人類のオスとしての役割であるということを知識として伝えているのです。とかく思春期の子どもは扱いにくい。でもそれが彼らの発達段階において当然やってくることであり、否定することでもない。どんなに理不尽な行動をとっていても、とんでもない要求をしてきても、それが子ども脳から大人脳への変化の過程で起こる一時的な現象なのだとする著者の物言いにはとてつもない説得力があります。思春期の子どもを持つ親にも子どもにも是非読んでもらいたい一冊だと思いました。
2024年01月20日
コメント(0)
-

ひしひしと伝わる校閲プロ意識
「くらべて けみして:校閲部の九重さん」(こいしゆうか著 新潮社)を読みました。一風かわったタイトル「くらべて けみして」は校と閲の漢字の訓読みだそうで意味は最後まで読めば分かります。新頂社という架空の出版社の校閲部に勤める九重さんが主人公のコミック。コミックという体裁はとっていますが、出版社の中での校閲者の立場や仕事を淡々と描いた、仕事紹介エッセイのような印象の本です。私は校閲という仕事にも携わったことがあるので興味深く読みましたが一般の読者はそれほど興味がないのではないですか。紹介されている校閲者の日常もまた、オタッキー(死語?)で変化のないもの。一日中だれとも話さないこともあり第一声を発するのに声が枯れるエピソードもありました。ライターの書いた文章の誤字や事実の誤りなどを、あらゆる知識を総動員しながら探していく、一種のあら探しというか重箱の隅をつつくというか、校閲者は見方を変えれば意地悪な人。それも読者に正しくライターの意図を伝えたいがための高い職業意識ではあります。私自身、本や論文を執筆したり、また校閲したりする経験があるので、この仕事の大切さが分かります。地味で根気の要る仕事ですが、まさにこうした表にあらわれてこない人たちが縁の下の力持ちになって出版文化を支えているのは事実です。ただ登場人物はみんな暗めで変人ばかり。彼らのプロ意識をリアルに描いているのだとは思いますが、これでは読者は九重さんはじめ丹沢君やとっとこちゃんたち濃ゆいキャラたちになかなか感情移入ができません。彼らを単なる変人ではなくもう少しコミカルに描いた方が、この世界を知らない読者にもっと興味を持ってもらえるのでは思いました。ただ、読み進めていくと段々とじわじわしてくる本ではありました。
2024年01月14日
コメント(0)
-
審美眼養えお金もかからない
「パブリックアート入門」(浦島茂世著 イースト新書Q」を読みました。パブリックアート、すなわち駅や公園など公共空間に置かれている彫刻や絵画を紹介したものです。パブリックアートは「ハチ公」の銅像や太陽の塔、ロダンの像など有名なものもありますが、全国にはそれと知らず触れているものがかなりあって、本書を通して日常的に知らずに通り過ぎているものも多いと気がつきました。この本ははそんな全国に散らばるパブリックアートの紹介が中心ですが、単なる紹介ではありません。たとえば銘板。多くのアートには銘板が近くに据えられていてアートの名前や作者、説明などがあるので、周りにあるそれを探してみることも勧めています。変わったものと言えば(だいたいパブリックアートは変わったものが多いのですが)水木しげるロードの妖怪達や長野県立美術館の霧の「彫刻」、東京オペラシティギャラリーの音の「彫刻」なども紹介されています。最後の章ではちょっとしつこいくらいに「パブリックアート」の楽しみ方が語られ著者のパブリックアート愛が見られます。本書には取り上げられていませんでしたが、沖縄には家の門柱や屋根の上によくシーサーが乗っています。ゆいレール牧志駅の近くの広場や読谷村の残波岬には巨大なシーサーがあり、これらもパブリックアートの一種でしょう。どちらも何度も目にしたことがありますが、銘板を見たこともありませんしあまり注目していませんでした。そう言えば那覇空港近くの瀬長島に巨大なカニがいたり漫湖公園にはクジラがいたりします。あれは遊具かとも思いますが、パブリックアートと言えないことはないでしょう。こうして考えていくとパブリックアートは意外と近くに潜んでいそう。脚の痛みが引いたらウォーキングを再開する予定ですが、パブリックアートを見て回るとより楽しさが増すかも知れませんね。
2024年01月11日
コメント(0)
-

運悪い人必読の書になるか
最近話題の本を読みました。「新版 科学がつきとめた運のいい人」(中野信子著 サンマーク出版)。この本を手に取ったのは、運がよくなりたいとかといった動機では無くて(今でも自分は運が悪いと思っていませんから)、科学がつきとめたという部分が気になったのが理由です。「運」というものをどう科学的視点から料理するのかに興味が沸きました。簡単に言うと「病は気から」や「幸せは自分の心がけ次第」を脳科学の点から説明しようとした本です。5章構成のこの本の章題を書き出すとこうなります。「運のいい人は世界の中心に自分をすえる」「運のいい人は『自分は運がいい』と決め込む」「運のいい人は他人と『共に生きること』をめざす」「運のいい人は目標や夢を『自分なりのものさし』で決める」「運のいい人は祈る」人生の教訓や啓蒙の書としてはありふれたテーマです。それを脳科学という視点から説明したところがこの本のミソ。ただ、素人にも分かりやすく説明しようとしたからなのか、ちょっと物事を単純化している気がしないでもありません。「こう考えればこんな脳内物質が出る。だから、そういうふうに生きましょう」といった具合。「運の悪い人」はそれができないからいつまでも幸せになれないのだと思いますが、そういう人がこれを読んでどれだけ考え方を変えられるかそれは分かりません。この本は啓蒙書ではなく「運」を客観的で科学的な分析に委ねたものですから。私のこれまでの生き方を振り返ってみると、だいたい著者の言う「こうすれば運が向く」的な生き方の通りに生きてきたように思います。そういう意味で私は運のいい人生を送ってきているのかなあと思います。そういう楽観的な人生観を持っていることが運を向かせているのか、運がいいからそう思えるのか。こうした、卵が先か鶏が先かのような雰囲気が本書にも漂っているように思ったのは私の読み方が浅いのでしょうか。
2023年12月29日
コメント(0)
-

ちょい前に生きた男のことみたい?
「よかれと思ってやったのに:男たちの『失敗学』入門」(清田隆之、双葉文庫)を読みました。「男たちの失敗学」とあるとおり、世の男性の女性に対する数多の失敗や取り扱い方の間違いを列挙し、分析した本です。各パートのタイトルには「モヤモヤさせていること」「軽く引かれていること」「迷惑だと思われていること」「悲しい気持ちにさせていること」「理解できないと思われていること」と、女性に対して男性が犯している数々の「罪」が並びます。私も男性として本書に書いてあることは思い当たる部分はあることもあるのですが、ちょっと違うなと思うことも少なくありませんでした。帯の裏には次のようなことが列挙されています。男性あるあると思う方もたぶん多いのでしょうが、私にはどれも当てはまりませんでした。 女性を悩ませる男性たちの“謎”行動 ・飲み物やトイレットペーパーをちょい残し ・周りを無視してガンガン冷房を効かせる ・「ありがとう」「ごめんなさい」を言わない ・黙り込んで話しかけるなオーラを出す ・イキってムリめな約束をするが結局守れない ・不健康自慢 etc・・・これって単に子どもなだけではないですか?男だから、というのにはやや無理がある気がします。ただ、我が国の男は子どものままでいて許されてきたというのがあるのでしょうか。本書に出てくる「ホモソーシャル」の男性社会の話も、私には縁遠い話に思えました。著者が言う男社会のなかで生きてきた覚えが私にはあまりありません。著者は千人を超す女性からもらった意見に基づいて本書を著しており、上記のようなことはよく当てはまるとか。ということは私が例外で、子どものような、男同士でつるんでいる輩が世の男どもなのでしょうか。私も色々な面で昭和を引きずっている人間ですが、仕事のなかでジェンダー問題を扱ったり、また20年近く前から独り暮らしとなり「自立」した生活をせざるを得なくなったりといった環境にいたのが、本書に見られる男性の典型からズレてしまった原因なのでしょうか。本書に書いてあることが今もそっくり当てはまるなら、我が国の男にはもっと大人になってもらわなきゃと思ってしまいました。私もどれだけ人のことが言えるのか、わからないんですけどね。
2023年12月12日
コメント(0)
-
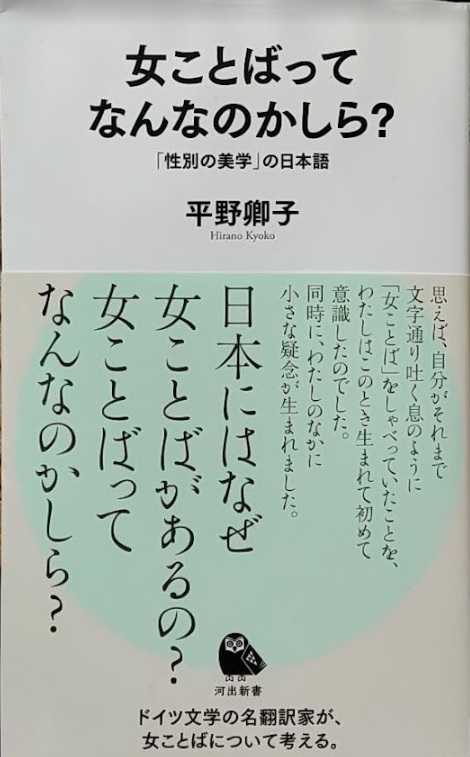
日本語が元から差別してるのよ
「女ことばってなんなのかしら?-性別の美学の日本語」(平野卿子著、河出新書)を読みました。翻訳家である筆者が、いかに日本語の中には男女の役割分担が深く根ざしているかを広く語っています。嫉、妬、媚、奸など女偏の文字にはネガティブなものが多いことは一般にも知られていますが、そういった分かりやすいところだけでなく女性を下に見ることば遣いは日本語にいくらでも見られる、と筆者は山ほど例を上げて説いたのが本書です。読んで驚いたことが三つありました。 1.現代知られている女ことばと言われるものができたのは比較的新しい。 2.女ことばは共通語に見られるもので、方言にはない。 3.女ことばは実際の場面ではそれほど使われていない。語尾に「~だわ」や「~よ」「~かしら」などをつけるのは明治時代に女学生の間で始まったものだそうです。それまでは語尾の違いにそれほど男女の区別がなかった。また、これが東京で始まった共通語での男女の言い方の違いなので、方言にはこうした違いは見られないとか。たしかに関西弁の男性話者である私は「~してしまったのよ」とか「それはちがうわ」とかの語尾は当たり前に使います。LINEなどでも同様の言い回しをするので、関東出身の嫁(息子の妻)は最初のうち戸惑ったと言っていました。また、こうした語尾はたとえば外国語を翻訳するときなどに女性の発言であることが分かるように敢えてそう訳すことがあります。これはおじいさんが語尾に「~じゃ」をつけたり関取が「~でごわす」と話したりするのと同様、役割語というものだそうです。そう話させることで誰がしゃべっているかを分かりやすくします。でも現実の場面で、実際にそのように話している人を見かけることはあまりありません。私たちはこうした「典型的な」女ことばをドラマで聞いたり本で読んだりすることに慣れてしまっているため違和感を持たないのだとか。でも実際3次元の人間に目の前でそうした話し方をされると、きっと演技のように感じるでしょうね。こうした例をたくさん上げながら、平野はいかに日本語が私たちにジェンダー意識を植え付けているか警鐘を鳴らします。読後私は、日本語ということばのなかに見られる無意識の女性差別をこれからは見逃さないようにすることが必要と感じました。そうは言っても日常当たり前に使っている母国語は、意識のとても深いところまで入り込んでいるので、そこからジェンダーバイアスを見つけ追放する作業はそう簡単なものではなさそうですけれど。
2023年11月20日
コメント(0)
-
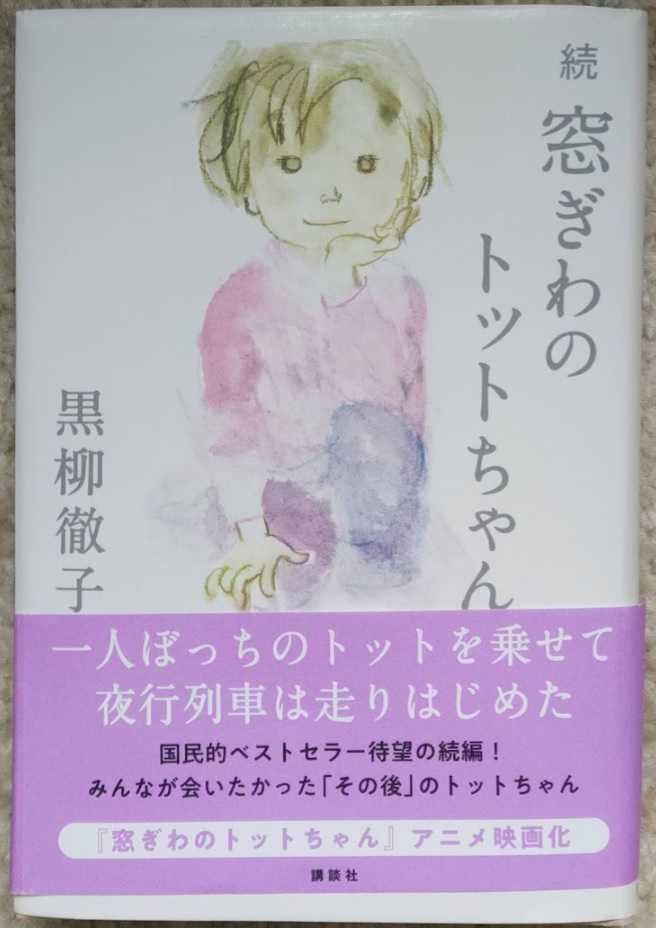
今だから余計読みたいトットちゃん
40年待ちました。そう思うと阪神タイガースの優勝より長かったわけです。待ったのは「窓ぎわのトットちゃん」の続編。いまどの本屋にも平積みで並んでいるこの本、発売と同時にとは言いませんが割りと早い時期に買いました。トモエ学園の印象が強烈だった前作を読み、最近の黒柳さんの活躍を見て「この後トットちゃんはどうなって今の黒柳徹子さんになったのだろう」と思っていました。今作は前作のような、強烈な個性を持つ子どもがその個性をさらに周囲に引き上げられた、ただあっけらかんとした楽しい話ではありません。黒柳さん自身がまえがきで書かれているとおり、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけにして書くことを思い立った、戦時下の子どもを思って戦争体験を描いた本だからです。東京空襲の話、それを避けるべく青森に疎開する話、お母さんの奮闘、そしてお父さんの戦争・抑留の体験。昔の話だと思いながらどうしても今の黒柳さんを思い浮かべてしまうので、どの話もそんなに悲惨な感じが伝わってこないのですが、客観的に読むと実際は相当な苦労をしていたはず。一生歩けないかも知れない病気になったり、次々と重い病気にかかったりしたこともサラッと書かれています。同様、戦後の自身の就職活動の苦労話もあまり苦労のように聞こえません。天性の天真爛漫さで窮地を切り抜けているように思えるのはあの、「徹子の部屋」でのあまり感情がこもっていないように思える黒柳さんの受け答えのせいかもしれません。しかし感情の起伏が激しくそれが表にも出ていたならば、後のユニセフの親善大使の大役などこなせなかったかも知れないですね。最近また、40年前の「ザ・ベストテン」での黒柳さんの涙の訴えが話題になっています。私はそのときの映像を鮮明に覚えていますが、最初わたしは子どもからのシャネルズへの質問「シャネルズは黒人のくせになぜ香水の名前をつけているんですか」を何とも思わず聞き流していました。ところがCMの後、黒柳さんが涙ながらに「国籍が違うからといって『~のくせに』と一段高いところから見下ろすような言い方はしないで」と訴えていたのを聞いて、ハッとしました。考えてみれば「黒人のくせに」というのはすごい偏見ですし、明らかに蔑視した発言です。しかし、それを何となく聞き流してしまった自分。言い訳ではありませんが、そういう時代だったかも知れません。男性への性加害が大問題となっていますが、あの頃はテレビやマスメディアでは男色を面白おかしく取り上げるのが常でしたし、人種問題にも世間は疎かったように思います。しかしそんな時代にも人権意識をしっかりと持ち、おかしいことはおかしいと言った黒柳さん。こんな黒柳さんを育んだ家族や周囲など、彼女の生い立ちを本書は伝えてくれています。前作とあわせて是非たくさんの人に読んでほしい一冊だと思いました。
2023年11月15日
コメント(0)
-

沖縄の変わらぬゆったりシマ時間
「沖縄:時間がゆったり流れる島」(宮里千里著、光文社新書)を読みました。2ヶ月ほど前に第一牧志公設市場の前にある「市場の古本屋 ウララ書店」でふと目にとまったのが本書。題名にゆったりとあるからではありませんが、自動車の助手席に置いて信号が赤になったときにだけ読んでいたので、読了までに長い時間がかかってしまいました。タイトルからはのんびりした島で観光客が癒やされる類いのガイドブックを思い浮かべるかも知れませんが内容は全然違います。著者の宮里千里は自身が古書店を経営し、沖縄に関するエッセイも書き綴っている発信者でもあります。宮里は沖縄の言葉や暮らしを生活者の視点から見て論ずる、郷土歴史家ならぬ郷土民俗研究家と呼べそうな人で、沖縄民俗関連の書物をたくさん著しています。内容は沖縄に現代も残る風習、民俗関連の行事中心で、第一章は地元紙に載る死亡広告欄をめぐるあれこれ。続けてさまざまな角度からウチナーンチュ(沖縄人)の特性を語ります。沖縄の人々は予約より当日券を求め、台風でも結婚式には万難を排して参列し、清明(シーミー)や十六日(ジュールクニチー)で先祖と一緒にご飯を食べ、オバァたちは他県にはない独特の名前を持ち、民謡からジャズまでを愛します。それはもはや「県民性」のレベルを超え、ナイチャーから見ると異文化、異国の様相を示しています。これまで県内外の人がさまざまな視点から沖縄を語ってきましたが、ナイチャーにとっては知っているようで知らないウチナーンチュの特徴が分かり、この一冊で沖縄の魅力をかなり知ることができるのではないでしょうか。ただし、人によっては以前から抱いていた沖縄への違和感を強めることになるかも知れません。しかし、ここに描かれた沖縄はただありのままにある沖縄の姿です。ナイチャーが魅力に感じようが違和感を持とうが、沖縄は普通にそこに存在しているだけ。昔からの伝統を守り、新しいものを付け加え、あるときは内地と距離を縮め、あるときは距離をとり、あるがままに存在し続けていることが本書を通じて伝わります。沖縄の風習を面白おかしく取り上げるのではなくウチナーンチュである著者が地に足をつけて、自らも属する世界を丁寧に描いています。発行が20年前のためそこに出てくる統計の数字などは今とは異なっていたり、雰囲気が若干違っている場合もありますが、底に流れるウチナーンチュのスピリットや伝統は変わりません。気軽に読めて現代の沖縄を知れる好著だと思いました。
2023年11月04日
コメント(0)
-

哲学と認知症はうりふたつ?
「おやじはニーチェ」(高橋秀実著、新潮社)を読みました。60代の著者が父親を介護する話。若干私とシチュエーションが似ていると、興味を引いた本だったので手に取ってみました。しかしそれはよくある、単に介護に苦労した顛末を述べている本ではありませんでした。認知症の父親の言動を、著者は「人間とは何か」との哲学的問いに結びつけざるを得なかったからです。認知症と診断された父親との会話を通じて著者は知症とは?認知とは?人間とは?と考えさせられます。父親との会話の中に著者は人間の認知に対する根源的な疑問を見出し、ニーチェをはじめとする古今東西の哲学者の言葉に答えを見つけようとします。哲学者達の引用部分は著者が分かりやすい言葉で言い直してくれてはいるものの、やはり難しい部分もあり正直言って読み飛ばしたところもありました。しかし読み進めていくうちに古今東西の哲学者達こそが実は認知症だったのかという気にさえなってきます。いつしか「ニーチェおやじ」ワールドに引き込まれ、著者の軽妙な筆致にも支えられて最後まで読書意欲は衰えませんでした。著者と父親の交流は心温まるものがありながらときには迷走していると言った方が適切な表現だと思うときもあります。が、途中から頻繁に登場する著者の妻の視点がそこに加わり、方向性は定まります。というか、妻に方向性を教えられていきます。副題に「認知症の父と過ごした436日」とあることからこの話には最後があることが分かっています。手を焼きつつも愛のある親子の交流、「ぼけているのか、とぼけているのか」分からない父親と著者との日々はしかし突然に終わりを告げます。それを分かりつつ読み進めていっていたはずですが、一読者としてあのニーチェおやじと会えなくなる場面はしんみりしてしまいます。とぼけていた分、より寂しく、悲しくなりました。私の両親も101歳と98歳。元気そうに見えても別れはいつやってくるか分かりません。本書が方向性を示してくれている通り、淡々としかし楽しんで日々交わっていきたいと思います。悔いが残らないように。というわけで、明日から帰省します。
2023年10月26日
コメント(0)
-
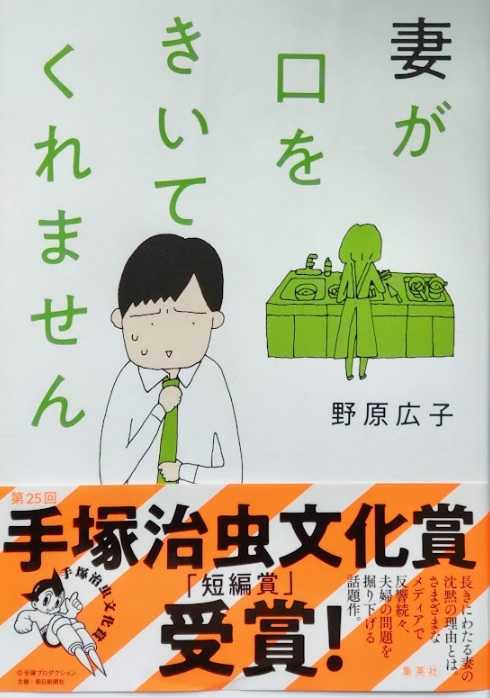
ちゃんとある口をきかないその理由
「妻が口をきいてくれません」(野原広子 集英社)を読みました。サラリーマンの旦那からの目線で描かれた夫婦間のいさかいを扱ったコミックです。サラリーマンの誠はある日を境に、妻の美咲から無視されるようになってしまいます。一切口をきいてくれません。しかし、誠にはまったく思い当たる節がありません。原因をあれこれ考える誠。口はきかないけれど家事やパートは続け、弁当は毎日作ってくれる妻。子どもや近所の人たちとはにこやかに接する妻。ただ、夫とだけ口をきかないのです。理由が見当たらず日だけが過ぎていきます。懐柔しようとしたり、強く出てみたりしますが効果は無し。口をきいてくれない期間は1日が3日になり、1週間になり、1ヶ月になり、さらに延びていきます。5年が過ぎたところまで読み進めていくと、今度は妻の目線からの物語が始まります。夫の目線でのみ話が進んで行くと思っていた私には意外でしたが、目次を見ればわかったことでした。なのでネタバレは嫌いな私ですが、この話の展開だけは記しておくことにします。妻の目線で物語が始まり、今度は妻の心理が描かれていきます。彼女が口をきかなくなった理由もすぐに分かります。内容についてはこれ以上触れません。長期にわたって口をきかない夫婦。いわゆる仮面夫婦です。程度の差こそあれ、誰にも思い当たる節のある話。だからこそ多くの人の共感を呼びベストセラーにもなったのでしょう。また「なぜ」口をきかないのかを夫、誠といっしょに考えるところが謎解きのようになっていて、ミステリー的な面白さで読み進めていく読者もいるのではないですか。この手の話はナゾ解きが納得でき、大団円に至るプロセスが論理的に構築されていないと一気にしらけてしまいます。その点は、帯にもある「手塚治虫文化賞」を受賞したことが保証しています。妻や夫がいる(あるいは過去にいた)読者は誰もが身につまされるストーリーです。一読の価値あり。楽しく読ませていただきました。
2023年10月20日
コメント(0)
-

前提になるのは生きていく力
「97歳母と75歳娘 ひとり暮らしが一番幸せ」(松原かね子 松原惇子著、中央公論社)という本を読みました。超高齢の母親と娘が二人の格闘の日々を綴ったエッセイで、我が家の状況と似たところがあるかと思い、本屋で手に取りました。そしてちょっと読んで爆笑。これは是非買わねば、と思いました。何しろお母さんの方がパワフルすぎます。そして、母も娘も超がつくぐらいの独立心のある人たち。母親が97歳、娘が75歳、そして弟が一人。家族構成的にも年齢的にも我が家とよく似ています。購入の際は我が家と似ているから参考になるかもと期待したところはあるのですが、似たところもありながら全然ちがうところも多々ありました。我が家とちがうのは母娘がとにかく独立独歩の精神を持っているところです。やむを得ない理由で娘が40年ぶりに実家に戻り二人で同居生活を始めるのですが、とにかくリズムが合いません。二人の生活パターンが全く違っていて、知らず知らずお互いが迷惑をかけ、かけられてしまいます。同居し始めたとき母親は80歳半ば、娘は60歳半ば。世間の多くの親子ならもう少し妥協し合い、うまく同居生活をこなしていきそうなものですが、この親子はとにかく個人主義が徹底しています。数年の間は我慢して暮らしますが、結局はまた別居する道を選びます。それができるのも母親が高齢にかかわらずスーパーパワフルだからです。二人は決して仲が悪いのではなく互いが相手の生き方を尊重している、本当の個人主義者たちなのです。しかし母親が怪我をしたりしていよいよ施設に入るときが訪れます。同居生活は合わないけれども互いの信頼は深いこの母娘。母は娘の判断を信じて何ら施設に関する希望を出さず、娘の提案してくれた施設にすんなり入居。実はこの母、家が大好きでいつもぴかぴかに掃除をして料理も上手でオシャレな人でした。そんな自分の城である家を離れ、施設に入るのは無念だろうと娘は思っていました。しかし、母は渋ることもなく入居。最初から喜んで施設の生活にとけ込みます。そういう潔さや切り替えの早さ、決断力というパワーも母にはあったことに娘は感心します。本書は娘の言い分と母の言い分のパートに分かれて、それぞれが自分の心境や意見をかわりばんこに述べ合う形で構成されています。同世代の親を持つ私としては、この母親の頭がしっかりしていることに驚くばかりです。母親のパートはおそらく談話で話したものを編集者がまとめたのだと思いますが、話がとても論理的で出てくるエピソードがとにかく面白いんです。私の家族と似ているかと思って買ったのですが、とても似ているとは言えませんでした。その意味では介護や対処の仕方の参考にはなりませんでしたが、内容が面白くて読んで元気を一杯もらえる本でした。帯にある通り「この97歳、すごすぎる」お母さん。私もしっかりと生きる力を身につけて、こんな超高齢者を目指します。
2023年10月13日
コメント(0)
-

挑戦は楽しむものと心得て
「君が校長をやればいい」(柴山翔太著、日本能率協会マネジメントセンター)を読みました。30歳にして高校の校長になった柴山さんの自伝、というか報告書のようなものです。柴山さんは赴任2年目にして30歳という若さで福岡女子商業高校という地方の私立高校の校長になりました。校長になったことは色々なタイミングが重なったひょんなことからですが、赴任1年目の年にはそれまで誰も思いもよらなかった(期待していなかった)商業高校の生徒を国公立大学に20人も進学させるという「偉業」をやっています。そして、その偉業によって校長に推薦されたわけでもありません。国公立への多数の進学に代表されるように彼は、生徒のチャレンジを後押しする教育観を持っていました。1年目から生徒を大量進学させるというチャレンジを行ったことから分かるように、彼自身がチャレンジの重要性を体現する人でした。その年度末、彼のチャレンジを認めてくれていた校長が退職することになり、それを食い止めようと理事長にひとり掛け合った結果、「それなら君が校長を」という流れになりました。元々チャレンジャーであっても野心家ではない彼は大いに悩み悪戦苦闘して要職に就くことを受け入れていきます。ひとたび校長になるとその立場を最大限利用して、学校を大改革していきます。彼の挑戦は生徒ファースト(そういう言葉は使っていませんが)の精神の上に置かれた、シンプルですが説得力のあるものでした。高校生の子どもを持っている親はこんな学校に子どもを通わせたくなるのではないでしょうか。2021年に校長になったばかりの彼のチャレンジは今もリアルタイムに続いています。これからはどのような展開を見せ、学校が彼の下でどう変化していくのか。学校のホームページを見ながら楽しみにしています。
2023年09月29日
コメント(0)
-
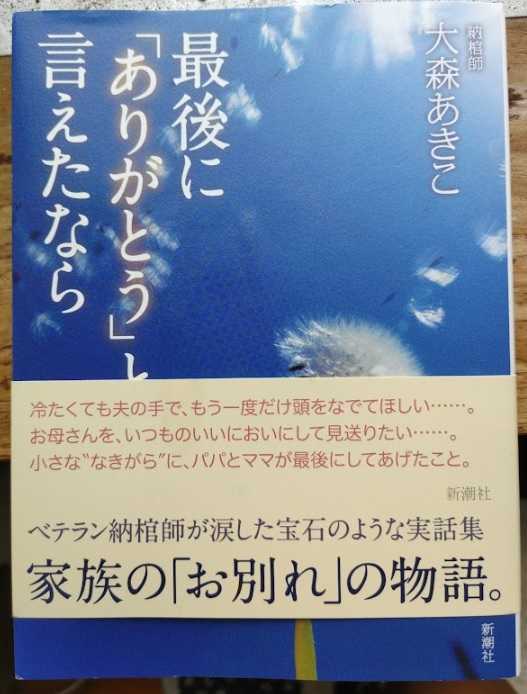
最後まで読めるか心配だったけど
「最後に『ありがとう』と言えたなら」(大森あきこ著、新潮社)を読みました。お父さんの死をきっかけに40歳手前で転職し、納棺師になった方のエッセイです。納棺師の経験から見た、たくさんの家族との別れの話が出てきます。この本は少し前に購入していたのですが、「はじめに」を読んだだけでつらくなり、読むことを躊躇してしばらく開いていませんでした。でも読みたくて買ったのだからいつまでも「積ん読」にしていてもと、勇気を振りしぼって読むことにしました。最初のいくつかの話を読んだだけでやはり胸が詰まってしまいます。急な別れになった旦那さんにもう一度「いい子、いい子して欲しかった」奥様の話。可愛い盛りの2歳のハナちゃんを突然奪われたお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの嘆き。遺族の一番近くにいる納棺師の語りは続きます。そしてそれぞれの話に救いはあります。ひとつひとつのエピソードを読みながら、自分自身が経験してきた家族の死と重ね合わせてしまいます。そう言えば、あのときも体をきれいにしてくれたり着替えさせてくれたりした人が来ていたなあ。あれが納棺師という方だったのか、とおぼろげっだった記憶が蘇ってきます。あのときの納棺師さんも私たち遺族に様々な言葉を語りかけ、気持ちに寄り添ってくれていたことを思い出しました。半年以上も寝かせていた本ですが、読み終えて「読んでよかったな」と思える本でした。
2023年09月15日
コメント(0)
-
いたずらも 言葉が消えれば 許される?
「三省堂国語辞典から消えたことば辞典」(三省堂、見坊行徳編)を読みました。私には人にはおススメできない、信号待ち読書の習慣があります。車を運転しながら信号待ちの数十秒間にちょこちょこ本を読むのですが、そのためにはじっくりと読み込む本を持ち込むと信号が変わっても気がつかず後ろの車に迷惑をかけてしまいます。その点、この本は一応「辞典」ですから一つ一つの項目が短く信号待ち読書に最適。言葉はときとともに変わっていきますから、辞書に載る言葉も変わっていくのは世の習い。言葉の意味が変化したり説明内容が不適切と判断されるものもあれば説明対象そのものがなくなってしまう場合もあります。自分ではまだ生き続けているという言葉が辞書からなくなるのを知り切なくなることもあります。パッと開いてみるとちょうど200ページでした。まみむめもの最初のページ。そこからちょっと拾ってみます(カギ括弧で示す引用はすべて同書200~201ページより)。そこにある消えた言葉のひとつが「マイナスイオン」。かつては「これをふくむ空気は健康によいといわれる」とも説明されていたそうですが「正式な用語ではないとして廃項」となりました。次の項目は「まえうた(前歌・前唄)」。まえうたとは「主役の歌手が出る前に歌う歌手」や「中心部分に先立つ歌」を指すそうです。その次が「まえばり(前張り・前貼り)」。説明は「はだかで演技する俳優が、陰部を隠すためにはりつけるもの」となっています。ページの最後は「まくり」。これもなくなったそうです。私にとってはなじみ深いものばかり。どれもなくなったと聞くと驚いてしまいます。いま、エアコンや空気清浄機は「マイナスイオン」効果を謳ってないのですか?歌謡ステージでは主役が出る前に歌う前座歌手というのはいなくなったのでしょうか。それに「はだかで演技する」俳優は前貼りをしなくなったのですか。ま、今なら映像技術で何とでもできるようになるのかも知れません。「まくり」はたしかに最近は見ませんが、海草を原料とした回虫駆除を目的とした飲み薬です。まくりに関してこれまで誰にも話したことはありませんでしたが、子どもの頃の文字通り「苦い」思い出があります。ある時ちゃぶ台の上に置いてある茶碗に入った茶色の液体を見て私はきっとコーヒーだろうと思い、周りに誰もいないことをさいわいにひとくちだけいただこうと思ったことがありました。ところが、ひとくち口にしただけでその飲み物は私の意に反してものすごく苦かったのです。言葉が辞書から消えたということは「まくり」を飲む人もいなくなってしまったということでしょう。周りに回虫を持っている人なんて、聞きませんものね。私には忘れられない思い出ですが、言葉と一緒に私のいたずらもフェイドアウトしていく運命のようです。あのまくり、誰が飲むんだったのでしょう。いまでも謎です。
2023年08月19日
コメント(0)
-

抜きましょう肩の力を60代
黒川伊保子さんの「60歳のトリセツ」(扶桑社)を読みました。自身も60歳代の黒川さんが60歳代の生き方、とらえ方を彼女の専門である脳科学の視点から描いていて、イチイチ納得出来ることばかり。読んでスッキリする胃薬みたいな本です。曰く、若さと競争する必要はない、子ども(いてもいなくても)を気にする必要はない、老いや死を受け止めて人生の達人になる、夫(妻)や友人と適度な距離を取ってつきあおう、などなど。どれも精神論や経験に基づく自分勝手な主張ではなく、あくまでも科学的に理詰めでおっしゃっているのでよく理解できます。物忘れやも体の衰えはなぜそうなるのか、どう前向きに捉えるかが分かり、生きやすくなります。NHKラジオで肩に力を入れず小気味よく話される黒川さんの口調や姿勢がそのまま文章にも表れていて、60代になって「もう若くない」と嘆いている人にも「自分が60になるなんて考えられない」と若さを謳歌している人にも、一読の価値がある本だと思いました。
2023年07月29日
コメント(0)
-

悲しめのネタがあるほど燃える人
岸田奈美さんの「傘のさし方がわからない」(小学館)を読みました。テレビドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」を見て、同名の本を買って読み、以降わたしの中に岸田さんのブームが来ています。ドラマはNHKーBSでやっていたのでBS放送が受信できない沖縄にいるときは見ることができません。そこで録画しておいて奈良で遅れ遅れで見ています。放送としてはすでに終了しているのですが、私は最終回をまだ見ていません。映画にしても小説にしてもネタバレが嫌いな私は基本、原作はドラマが終了するまで読みません。でも「家族だから・・・」は、あと1回を残して我慢できずに読んでしまいました。早めに本を買っておいたのがよくなかったのかも知れません。そして、一緒に買った「家族だから・・・」に続く岸田さんのエッセイ集「傘のさし方・・・」は「家族だから・・・」を読み終えるとすぐに何の躊躇もなく読んじゃいました。しかし、なんで岸田さんには人の十倍、二十倍増しぐらいでこんなに色んな出来事が起こるのでしょう。ちょっとタイトルを見ただけでもそのすごさが分かります。「歩いてたら30分で6人から『ケーキ屋知りませんか?』ってたずねられた」話とか「深夜、タクシーで組織から逃げる」話とか。似たような話は一般の人にも起こっているかも知れませんが、岸田さんの感性がそれを何倍にも増幅させて「これは絶対ネタになる」と面白おかしい文章をひねり出していくのでしょう。でもそれだけでなく、この本にはこれまでの彼女の失敗談や感動譚なども収録されています。自己肯定感が低かったり他人にさまざまな迷惑をかけたりした話もあけすけに書き綴り、でもそうして書いてきたことが「作家」として実を結びその仕事を通じて自分は救われたと素直に表明しているところがまた岸田さんの魅力でもあります。関西人は自ギャグ的(自虐的から連想して作った私の造語)なところがありますから、多分これまでの岸田さんの人生はそれほど悲惨な経験に満ちているわけではないのではないですか。自分をギャグにしておとしめて、面白く語るのは関西人の得意技。岸田さんは、その関西人の特性を素晴らしくうまく楽しく表現できる作家さん。この本を読んで岸田さんをかわいそうに思った関西以外の方、それが彼女の作戦ですからいい意味で「話半分」に読むのが彼女のエッセイを楽しむコツですよ。
2023年07月26日
コメント(0)
-

歴史好き沖縄好きの暇つぶし
「沖縄の事件史100のナゾ」(比嘉朝進著、風土記社)という本を読みました。1989年に発行された本で、グスク時代から第二次大戦前までの沖縄で起きた「事件」を書き綴っています。版を重ねた様子もなくおそらく古本屋でしか手に入らない本です。私も古本屋(牧志公設市場前にあるウララ書店)で、偶然見つけて何となく面白そうだと思い購入しました。正直、あまり学術的な期待はできません。ナゾでも何でもなく各時代の史実(?)を収録したものです。どちらかというと歴史こぼれ話的な内容だと言った方がいいかもしれません。筆者もまえがきで「本書は史話として、気軽に沖縄史を楽しめるように書いた」としているとおり、寓話のようなものが並んでいます。内容は第一、第二尚王朝の王様の話から北谷村の村長の某が悪政を施していたといった話まで多彩。とにかく参考文献として扱ったものがたくさんあり、中山正譜から市町村史まで種々雑多。単にそれらの一部を抜き出しただけの(に見える)ものも多く、ナゾ解きというよりも歴史おもしろ読み物として(おもしろいかどうかは別として)読んだ方がいいかもしれません。これを読んで琉球・沖縄の歴史を知ろうとはしない方がいいです。ある程度歴史に通じている人が読めば得るところもあるかな、程度でしょうか。この本、四半世紀以上前に定価1000円(税込み)だったものが900円の値付けで売られていました。おそらく初版が多く見積もっても千部程度だと思われるので欲しい人が探してもなかなかないでしょうから、そういう意味では希少価値はあるのかも知れません(そもそもこの出版社、今でもあるのでしょうか)。でも一度読めばもういいかな。手許に是非とも置いておきたいほどでもないのでまた売りに行くか。さて今度はいくらで買ってもらえるでしょう。
2023年07月21日
コメント(0)
-

読んでみてわかるようになったのか?
養老孟司さんの「ものがわかるということ」(祥伝社)を読みました。ランキングとかにも入っていて、よく読まれているようです。この本を読んでものがわかったということはありません。でも、何かスッキリするんです。ものがわかるということについて考える姿勢がわかった、というか、腑に落ちた感じがするからです。養老さんの饒舌な説明のおかげで、何がということは言えないのですが、デトックス効果みたいなものを感じます。全然、読後の感想になっていませんね(笑)。養老さんは言います。「わかる」とはどういうことなのか、「それが分からない」と。でも「分かっていなくても説明ならできる」。この本を読んでいると会得するとか体得することと知識として理解することとは全然別のことだという気がしてきます。都会化した場所で情報としてものごとの意味を理性で理解するのではなくて、自然のなかで体験しながらひとつひとつ体が納得していくことが「わかること」につながるのかな、と思いました。「分かること」そのものではないにしても。うーん、言葉を重ねたところでこの本をうまく説明できません。でもひと言いえるのは、「養老さんってわかっているな。」
2023年07月13日
コメント(0)
-

読みながら泣いて笑って元気出て
今日は先日生まれた孫と初の対面をしに東京へ。その道中、往復の新幹線で本を一冊読了しました。「家族だから愛したのではなくて、愛したのが家族だった」(岸田奈美著、小学館)本屋で平積みにされているのを見かけて以前からタイトルが気になっていたのですが、NHKのBSプレミアムドラマになったのを見てようやく内容が分かりました。こんな話だったんだ。ご存じの方も多いでしょうが岸田家を次から次へと襲う「不幸」にめげず、それをすべて笑いに変えてしまう岸田奈美さんの実生活を元にしたお話です。「不幸」のはじまりは弟がダウン症で産まれたこと。その後、岸田さんの父親が著者が中学生の時に急死。そして母親が脳梗塞で車椅子生活に・・・。これらの「不幸」をことごとく乗り越えて(と言っていいのかどうかよくわかりませんが)障害をプラスに捉えていくユーモアいっぱいの家族の物語。岸田さんが創業メンバーの一人になって起業したミライロ(ドラマではルーペ)ではバリア・フリーならぬバリア・バリューという概念が出てきます。障害には健常者にはない、独自の視点をもたらしてくれる、ある種の価値があるということです。私の知り合いにアメフトの試合中に脊髄を損傷し、車椅子生活になった若い人がいます。その彼からも「障害を負ってよかった」という言葉を聞いたことがあります。もちろん、その境地に至ったのは障害を負ってから何年も経った後のことですが、その言葉は強がりから出たわけでもなく、心の底から本気で言っているのが分かります。彼も何にでも挑戦し、車椅子でダイビングをしたり本場のアメフトの選手と交流したり。車椅子生活になっていなかったらできなかったこと、出会えなかった人たちと出会えたこと、その一つ一つに彼は「よかった」と思っているのです。彼からもらうのと同様、岸田さんの本やドラマからも元気や希望、新しい物の見方などをいっぱいもらいました。今度の日曜日でドラマは第10回の最終回を迎えます。本は少し前に購入し、ドラマが終わってから読もうと決めていたのですが、ついつい我慢できなくてフライングしてしまいました。京都から新横浜の新幹線の往復があっという間でした。
2023年07月12日
コメント(0)
-
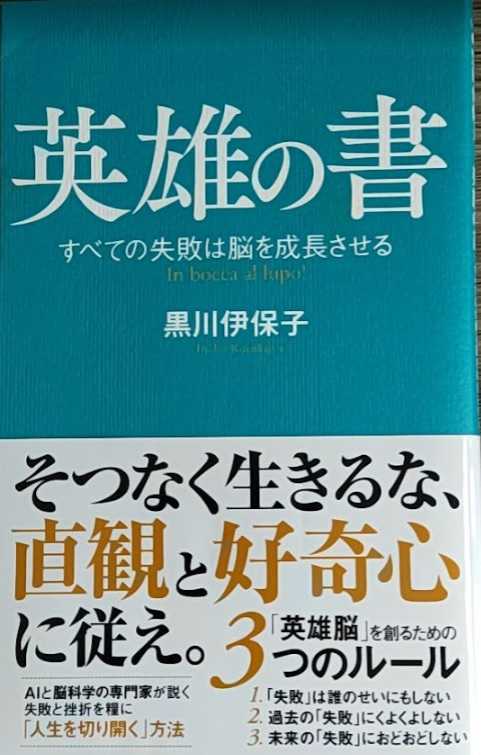
失敗はなぜ「成功のもと」なのか
黒川伊保子著「英雄の書」(ポプラ新書)を読みました。いわゆる啓蒙書のたぐいですが、他の啓蒙書と違う点は彼女の専門の脳科学やAI研究の成果を主張の根拠としているところ。そのために言っていることに説得力があります。副題の「すべての失敗は脳を成長させる」も古くからの言い伝え「失敗は成功のもと」を科学的に裏付けているものです。この本は「失敗の章」「孤高の章」「自尊心の章」「使命感の章」「餞の章」の5章構成です。それぞれ失敗は脳の進化に必要だ、創造するには孤高であれ、自己愛ではない自尊心を持て、使命感は他者を思うことから生まれる、上質な異質になれと説き、英雄になろうと謳い上げます。これだけ見ると一般の啓蒙書のようですが私が気に入ったのは、それぞれの主張がちゃんと納得できるところでした。いま生成AIが大きな話題になっていますが、あのAIの進化にも失敗が必要で、失敗を含めて多く学習することでより高次の発達が可能になると言います。人間の脳の進化も同じような性質を持っているので失敗をどのように進化に結びつけるかが重要で、失敗を他人のせいにしたり過去の失敗をいつまでも引きずるのはいかに「もったいないことをしている」かを彼女は説明します。本書を読んでいると、結論がスッと腑に落ちる上質なSF小説を読んでいるような錯覚に陥りました。世の中には強引につじつまを合わせているだけの説得力のないSF小説が多くて、最後まで読んでも何か納得できないもやもやしたものが残ることがよくあります。それと同じように啓蒙書でも「なぜそうなのか」を突き詰めないで「ああしよう」「こうしよう」というものが目につきます。その点、「英雄の書」はただ単に「失敗を恐れるな」ではなく「失敗はなぜ成功のもと」なのかを分かりやすく教えてくれる、好著だと思いました。
2023年05月24日
コメント(0)
-
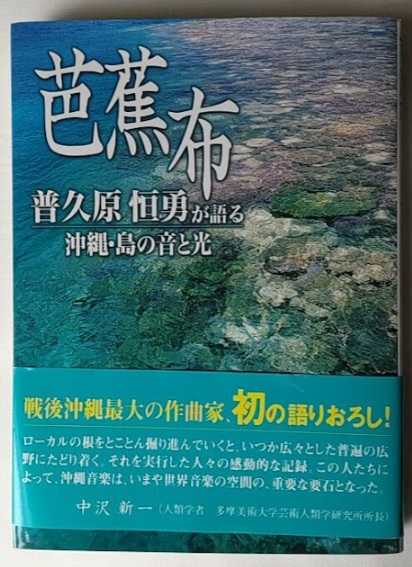
職人や芸術家を越え天才に
「芭蕉布:普久原恒勇が語る 沖縄・島の音と光」(ボーダーインク社)を読みました。以前普久原本人が書いた「僕の目ざわり耳ざわり」を読み、面白かったので普久原のことをもっと知りたいと思ったのが本書を読もうと思ったきっかけ。残念ながら普久原が著した本は「目ざわり」しかなく、本書は普久原へのインタビューをまとめた読み物となっています。普久原の作曲家としての才能は万人の知るところですが、その生い立ちや写真の腕はあまり知られていないのではないかと思います。それがこの本では余すところなく述べられています。第1章が生い立ち、第2章が写真家としての普久原、第3章が音楽関連の交遊録、そして第4章が作曲してきた数々の音楽の解説という構成です。第1章では大阪で育った少年時代から沖縄に戻ってきた後の作曲家になるに至る様子が本人の口から語られます。驚くのが音楽プロデュースをしながら写真家としての彼の活躍。レコードジャケットは彼の作品とか。第3章の、名だたる沖縄の唄者や音楽家らとの交友の話もとても面白く、沖縄音楽の生き字引と言ってもいい人です(残念ながら普久原は昨秋亡くなりましたが)。それでいて全く飾らない人柄がインタビューの中に感じられて好感が持てます。言葉の端々からは彼のもつ天賦の才が感じられますが、本人は芸術家というよりも職人だと自己を表現しています。代表曲「芭蕉布」にしてもその他の曲にしても、内からあふれ出したり上から降りてきたりして出来上がったというよりも「作曲を依頼されたから作ったまで」との姿勢を崩しません。世界各国の古今の音楽に精通していた普久原は、沖縄民謡にクラシックの要素を注入したりジャズやロックを取り入れたりして新しいジャンルを作った人でした。私にはまだまだ知らない普久原の曲がたくさんあります。この本を参考にしながら少しずつ彼の歌を聞き、普久原恒勇の世界を堪能するという新しい楽しみができました。
2023年05月08日
コメント(0)
-
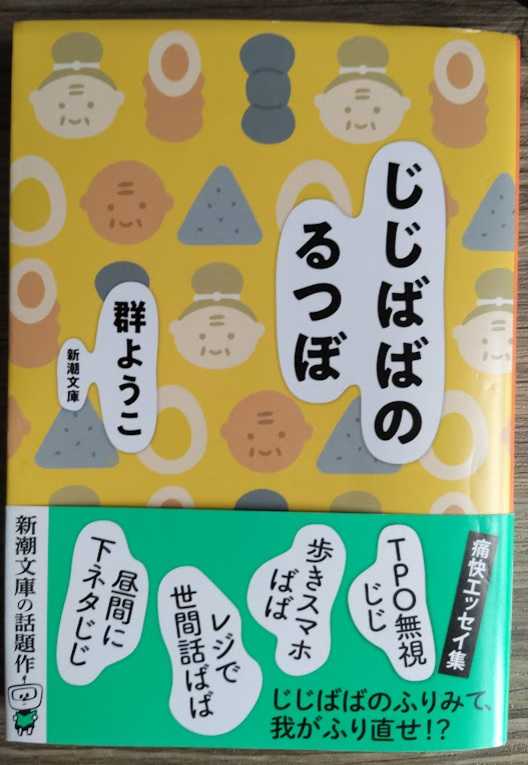
正論に 反論させない 群ようこ
群ようこさんの「じじばばのるつぼ」(新潮文庫)を買ってきました。本屋さんで最初の方を立ち読みし、面白そうと思い即購入。ご本人も高齢者枠に入った群さん、もう少し上の後期高齢者の方の困った行動を観察しています。目次を見ると「ばばと乳首」「情けないじじ」「レジ前のばば」など刺激的な見出しが並んでいます。齢を重ねて何かと厚顔無恥になってくる老人の行動を取り上げているようです。いわゆる「お年寄りあるある」が並んでいて、色々と共感できそう。寝る前の読書は気楽に読めるものがいいので、重いものよりこれがぴったり。そう思って読み始めたのですが・・・。読んでいるうちにだんだんとつらくなってきました。そこには誰が見ても困惑し迷惑する老人の行動がたくさん出てきます。群さんの言っていることに間違いはありません。ですが、群さんの文章からはこれらの非行老人に対する愛が感じられないのです。群さんの意見は正論ですが、大所高所から一刀両断して当の老人達に弁解の余地を与えません。群さんは第三者的、客観的観察者の立場に立っていて具体的な非難行動はとっていません。高みから見下ろして、ときにあきれときに哀れみ、軽蔑そのものの目で見ます。そして心の中で困った老人達に言葉を尽くして罵詈雑言を浴びせかけます。ここには一歩踏み出しさえすればマスク警察になってしまう危うさがあります。高齢者たちへの非難が延々と書き記されているのを読み、疲れてしまいました。たしかに、ここに描かれている高齢者達は困った人たちであるのは間違いありません。でも個々に事情がありそうな人もいるのに群さんは自分のもつ最悪の想像をそこに加えます。もうちょっとあたたかい目で見てやれないものかなあ。いくらページをめくっても高齢者に対する非難は止みません。読んでいるうちに群さんがだんだんとのぞき見趣味のいやなおばさんに思えてきました。多分そんなことはないと思います。高齢者達の行動に本気でNGを出しているのだと思います。でもこの本、私には合わない。私にしては珍しいことですが、読了せずに読むのをやめました。群さん、ごめんなさい。
2023年03月20日
コメント(0)
-
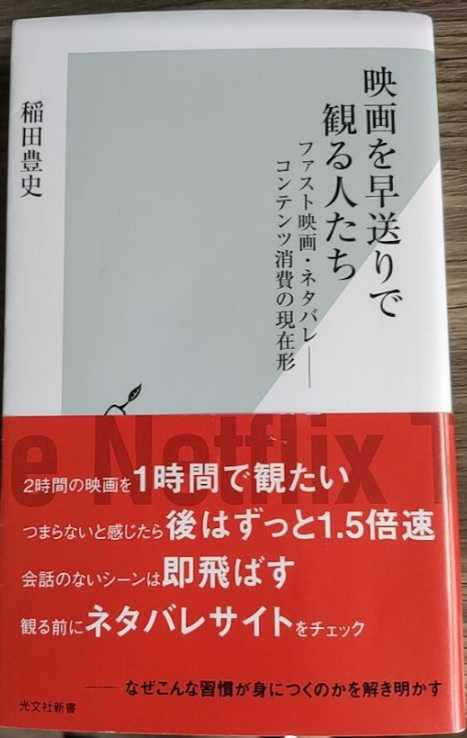
ネタバレを先に見るのに理由あり
私は映画やドラマを見る前に内容を知るネタバレが嫌いで、極力避けるようにしています。自分が見た映画の感想をここに書くときも、ストーリーの展開や結末は書きません。でも、世の中にはネタバレというか結末を知っておいてから映画やドラマを見る人が多くいます。それが私にはどうしても理解できなくて、不思議でなりませんでした。「映画を早送りで観る人たち」(稲田豊史著 光文社新書)を読み、理由が納得できました。この本には「ファスト映画・ネタバレ-コンテンツ消費の現在形」という副題がついています。映画を倍速で見る、10秒飛ばしで見る、予めネタバレを見る、には共通の理由があると言います。映画やドラマを見る目的が、一種の「コンテンツの消費」だからです。私は映画に「感動体験」を求めます。最後の最後に、いい意味で作者に裏切られる快感を求めます。しかし早送りで見る人は話のネタを仕入れるために流行のものは見ておかなくては、と考えます。したがって「コンテンツ」は、できるだけ効率的、合理的に消費することが優先されます。また、他人によって裏切られることで快感を得るのではなく、自分の「好き」を補強しようとします。他者の視点よりも自分の視点を最優先し、自分の価値に合うものかどうかを基準に映画を見ます。だから早送りをし10秒飛ばしをしネタバレサイトで結末を予め知っておかないといけないのです。そうしないでまるまる2時間を費やしたあげく価値に合わない映画を見てしまうのは「失敗」です。ここでは映画に感動を求めるのではなく、自分の「好き」を補強してくれる快感が求められています。ただし、筆者はこうした傾向を否定しているわけではありません。曰く、技術の進歩は常に”良識的な旧来派”によって不快感をもって論じられてきた、と。いま世間を見渡すと、この早送り視聴は旧来派にはあらがえない流れになっている。コンテンツの作り手も、それに合わせた作品作りをするようになっている。旧来派が何を言っても、それが世の中の流れなのです。この的確で説得力のある文章を見て、ネタバレサイトを先に見る人たちの気持ちが分かりました。ただ、私は映画に感動を求め、どんでん返しを求め、もう少し旧来派のままでいたいなと思います。いやー、映画って本当にいいものですね(死語)。
2023年03月16日
コメント(0)
-

方言は顔も含めていっちょまえ(知らんけど)
「関西人vs関東人 ここまで違うことばの常識」(博学こだわり倶楽部 編)を読みました。よくある豆知識本の一種かと思って購入。最初のうちは関西弁と関東弁の違い「あるある」ネタが多く出てきてそれなりに楽しめます。途中からはより学術的な考察や関西のなかの京都と大阪、神戸などの違いが増えてさらに面白い。ふと最近全国的にはやっている「知らんけど」は関西アクセントで言われているのか気になりました。関西人は「知らん」にアクセントを置き「けど」を付け足します。それによって「いま言うた話は話半分に聞いといて」と責任逃れをします。「知らん」より「けど」にアクセントを置くと不確実なことを認める発言になります。関西弁の「知らんけど」はあることないことべらべらしゃべってから付け加える免罪符。関西人のコミュニケーションは事実の伝達よりもその場のノリや盛り上がりが大事。「知らんけど」はそのために使う小道具、というような意味合いのことを本書に書いてあります。まさに関西コミュニケーションの神髄。ところで、朝ドラ「舞いあがれ!」の主人公母娘の関西弁が気になります。二人(福原遥、永作博美)は関西人ではありません。しかし、イントネーションはかなり完璧に近く関西人と同じような言葉づかいをしています。耳で聞いただけでは関西人と間違うレベルかも知れません。でも気になるのは、話をするときの二人の表情。音を消してしゃべっているときの表情や動作を見ていると関東弁をしゃべっている感じなのです。(永作博美は茨城県、福原遥は埼玉県出身)大阪出身のくわばたりえはあのような表情をしません。関西人は二人のような意味深な(後を引くような)表情はあまりしないのではないでしょうか。永作博美の役は長崎県出身とのことなので、もしかしたらああいうことがあるかも知れません。でも福原遥は生粋の大阪人の役どころ。主役ということで力が入っているのか、関西人にしては「きばりすぎ」な演技に見えますね。二人ともセリフのイントネーションに関してはよく頑張っていると思います。でもあの表情が関西人に見えないのがちょっと残念。関西弁方言指導の方も表情指導までは任されてないのでしょうね(知らんけど)。
2023年03月06日
コメント(0)
-
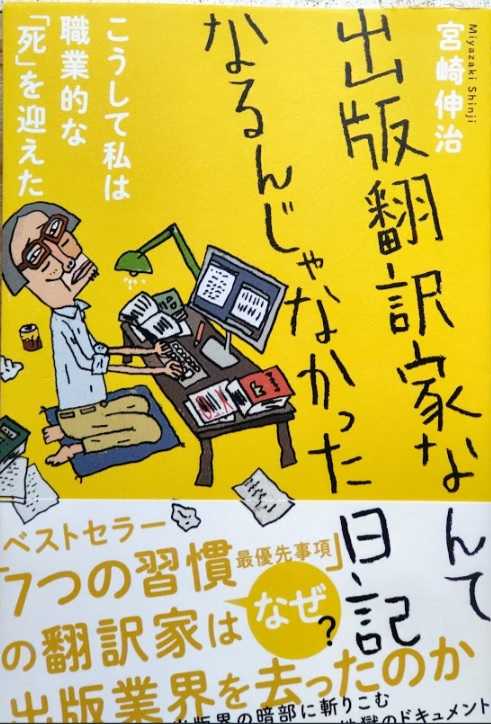
そんなにも出版業界こわいとこ?
「出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記」(宮崎伸治著 三五館シンシャ発行)を読みました。この本、「交通指導員ヨレヨレ日記」や「マンション管理員オロオロ日記」と並んでおかれていました。表紙も「日記」シリーズに類したものだったのでそのようなものを期待して読み始めたのですが。シリーズの他の本と似ているところもあるものの、他とは少し内容が違います。基本このシリーズは不平不満が中心なのですが、なかでも宮崎氏の不満は飛び抜けています。それだけ彼が訴えている出版業界は執筆者を軽く見ている不良業界、ということでしょうか。私も多少出版社とかかわった経験がありますが、宮崎氏が被ったような「被害」はありません。私はおもに書籍や論文の執筆を行ってきましたが、宮崎氏は翻訳が専門。執筆分野の違いが根本にあるのでしょうか。宮崎氏によると翻訳の仕事はなかなかスケジュール通りに行かないことが多い。訳書でなくても分担執筆をしていると締切を守らない人がいた場合予定が遅れることはあります。しかし、丸ごと一冊を1人で書いていると予定通りのスケジュールが遅れることはありません。少なくとも私がかかわってきた書籍の場合はいつもそうでした。宮崎氏の話では、訳者はいつも超特急で仕事を仕上げているのに発売延期になることの多いこと。そして、延期になった理由をごまかし続ける出版社、編集者の多いこと。裁判を起こすことすらあるというのですから、出版業界は相当こわいところとの印象を持ちます。私もいくつかの出版社とはご縁がありましたが、知る限りそのような経験はありません。雑誌原稿の内容が問題になって、編集者が東京から奈良まで来てくださったことがありました。私ひとりのためにわざわざご足労くださったのもあり、私は差し替え原稿を書きました。それでも発売延期もなく、月刊雑誌は通常通り発行。定期刊行誌だからまあ当然でしょうが、個人で執筆した書籍も発売延期になったことはありません。印税も当初の約束通り支払われ、宮崎氏のように発売直前になって値切られたこともありません。翻訳本の業界は事情が異なるのか、宮崎氏がたまたま不運な目にばかり出合ってしまったのか。本当のところはよく分かりませんが業界に対する印象が宮崎氏と私は違うなと感じた一冊でした。
2023年02月07日
コメント(0)
-
伝えたいときは短くきっぱりと
いま各地の書店に平積みされている「日本史を暴く」(中公新書 磯田道史)を読みました。内容が面白く、しかも読みやすい文章だったのですぐに読み終えてしまいました。磯田さんはかつて朝日新聞土曜版「be」に連載していた歴史コラム以来のファン。どちらかというと歴史の表舞台に出てこない話を取り上げ、説得力を持って解説していました。今回の本も「闇歴史」をきちんとした史料をもとに分かりやすく語っています。内容だけでなく磯田さんの書くものは文章の読みやすさに定評があります。無駄な修飾を除いて、核心を短い言葉でズバリと書く。しかも一つ一つのコラムが短く、すぐに読み切れるのが特徴です。適当にページを開いて、そこから少し引用してみましょう。(同書p.162 「龍馬の遺著か『藩論』の発見」より 1~3行目)そうなのである。この『藩論』という本は極端に残存数が少ない。原著は太平洋戦争で消失したとされる。200部限定で出版された木版本も同志社大学人文科学研究所に、ただ一冊残るのみである。この100文字に満たない文章の中に5個の句点があります。つまり、5つの文章があるということです。一つの文が平均20文字足らずで、読点も最後の文のなかに一つあるだけです。最初の文を除けばすべて主語と述語が表され、当然ながらきちんと対応しています。これだと歴史にあまり興味がない人でも読みやすさに惹かれて、ついつい読み進めてしまうのでは。私は歴史の専門家でも愛好家でもないのですが、磯田さんの文章は好きで思わず読んでしまいます。私自身文章を書いたり人に教えたりすることがある時、磯田さんの姿勢はとても参考になります。私ももっと短く、もっと分かりやすく書きたいのですが、どうしても説明的になってしまいます。このブログはできるだけ短く書こうと、すべての文章を1行45文字以内に収めようとしています。でも、なかなかうまくいかないことも。そんなとき磯田さんの文章を思い出し、参考にし、自分を戒めている私です。
2023年02月04日
コメント(0)
全114件 (114件中 1-50件目)