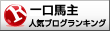2025年10月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
ミラーレスカメラを始めるなら、中古の OM SYSTEM がお勧めです。
今日はハロウィーンですが、今夜は雨模様でコスプレして騒ぎたい方達には少々残念かもしれませんね。でも、お巡りさんには幸いかもしれません。こういうイベントは本来嫌いではないので私も後40歳ほど若ければコスプレしていたかも?。と言いつつ、今回は撮影される側ではなく撮影する側で使うカメラについてのお話です。普通の人ならスマホのカメラで十分でしょうし、別にカメラが欲しいなんて思わないでしょう。個人的にも、動画撮影に興味があるなら、今どき流行りの「小型アクションカメラ」の方が魅力的だと思います。今回は「レンズ交換を楽しみたい」「予算は安ければ嬉しい」「でも性能であまりに劣るのは嫌」「大きくて重いのも嫌」という人に向けたご案内です。そんな用途に「OM SYSTEM」のカメラはお勧めできます。では、何故 Panasonic ではなく OM SYSTEM なのでしょうか。答えは簡単で Panasonic はAFが弱くて、ボディに手振れ補正を搭載していないからです。もちろん、最新の上級機はその限りではありません。と言うか価格や、大きさ、重さを無視した「絶対性能」なら Panasonic の方が勝ると考える方も多いでしょう。私も動画撮影や Leica レンズの魅力を考慮すると賛成です。ですが「レンズ交換を楽しみたい」「予算は安ければ嬉しい」「でも性能であまりに劣るのは嫌」「大きくて重いのも嫌」と言う条件だと Panasonic ボディは除外した方が良いのです。まず、マイクロフォーサーズの中古カメラボディを選ぶ上で重要となるのがボディ内手振れ補正の有無です。パナの小型ボディは G100 が田式手振れ補正を搭載していますが、静止画では有効とは言えず、既にディスコンですがGFシリーズもボディ内手振れ補正を搭載していません。パナ純正のレンズにはズームレンズの多くが手振れ補正を内蔵していますし、単焦点レンズもある程度なら手振れ補正を内蔵していますが、全てではないし、MFの中華レンズでもボディ内手振れ補ならば有効です。何よりも、パナの現行モデルでは唯一、小型の G100 以外は全てボディ内手振れ補正を搭載している事を考えても、ボディ内手振れ補正が良いのは間違いありません。次に、マイクロフォーサーズの中古カメラボディを選ぶ上で重要となるのが画素数です。選択するべきは現行モデルに代表される2000万画素機、少し前の1600万画素機で、どちらを選ぶかは「予算」と「画質への思い」によります。とにかくボディは低予算で、レンズに多くの予算を使いたいなら 1600万画素機です。画質への思いとなると難しいです。何故なら高画素=高画質とは言い切れないからです。スマホやタブレットで拡大やトリミングせずに鑑賞するだけなら1600万画素でも不満を感じる事は少ないでしょう。今回は 2025年も年末に差し掛かった時期と言う事で 2000万画素機に絞って中古カメラサイトの「CAMERA fan」に掲載されていた価格を参考価格として、おすすめポイントを紹介しています。現在 OM SYSTEM の2000万画素センサーには大きく2種類に分類されます。●初代OM-1で初採用された、裏面照射積層型 Live MOS センサー。 OM-1. OM-1Mk.Ⅱ. OM-3. だけが搭載しています。画質最優先なら此方が本命です。●従来の Live MOS センサー。 OM-5. OM-5MkⅡ. E-M10Mk.Ⅳ. E-M1Mk.Ⅲ. E-P7. に搭載されています。小型・軽量なら こちらが本命となります。次に中古価格の安い順に記載していきます。⓵E-P7(現行モデル)TruePicⅧ ¥68,000-~81,800- 名機 Pen シリーズにつらなるボディです。EVFは搭載されず、後付けも出来ません。ですが 「CPボタン」の先駆けともいえる「プロファイルコントローススイッチ」を搭載しています。 一時期 E-P7 が高騰しましたが今は落ち着いたようですね。サブ機にお勧めですがEVFが不要 ならばメインとしても十分です。②E-M10MarkⅣ(現行モデル)TruePicⅧ ¥72,800-~94,000- E-P7 のベースモデルです。一時期 E-P7 が高騰した事が在りましたが今は落ち着いたようです。 メイン機にするならEVFを搭載した本機の方が良いと思います。防滴性能を必要としないなら 本機で十分です。③E-M1MarkⅢ TruePicⅨ ¥79,800-~115,000ー 二世代前とは言え最上級機がこの価格はお値打ちかも。センサーにこだわりが無ければ、上質な 感触を楽しめるし、画像処理エンジンも新しいので「鳥撮影」を安価に始めるならお勧めです。④OM-5(初代)TruePicⅨ ¥81,000-~110,000- 防塵・防滴が必要ないなら②との価格差と実機の質感の違いで選べば良いでしょう。二世代前の E-M5MarkⅢも選択肢に入れても良いと思います。既に手放してしまいましたが、私は OM-5 の スペックを十分に吟味して、あえて E-M5MarkⅢを選びました。⑤OM-5MarkⅡ(現行モデル)TruePicⅨ ¥135,000-~148,500- 欧州からの輸出規制に対応する為 USB-C になった。と同時に「CPボタン」が搭載されました。 今なら USB-C 対応と「CPボタン」搭載、TruePicⅨ の搭載を考慮して OM-5MkⅡを選ぶかも しれません。一般的には OM-3 の評価が高いですが、センサーは良くてもEVFが駄目なので、 「ライブGND」より「中古価格」と「小型軽量」を選べば、私的には「アリ」なのです。以上が Live MOS 搭載機です。個人的には従来型の m4/3 型センサーでは 2000万画素と 1600万画素で「大きな優劣」は無いと考えます。画像処理エンジンの進化で従来型センサーでも 2000万画素センサーを実用レベルとしましたが、後述の裏面照射積層型 Live MOS センサーと比較できるレベルには至らないです。所有する OM-1 と所有していた E-M5MarkⅢ と所有する E-PL8 での比較で、あくまで私個人の JPEG 撮って出しをメインとした感想ですけどね。センサーだけではなく、画像処理エンジンの新しさ、ボディ内手振れ補正の方式と段数も、画質に大きな影響を与えます。手持ち撮影に限った話をすれば中望遠程度まではボディ内手振れ補正が優勢で、超望遠になるほどレンズ内手振れ補正が有利になりますけど、現在ではボディとレンズの協調補正が超望遠レンズのトレンドになっています。ボディ内手振れ補正には3軸と、より強力な5軸が有ります。レンズ内手振れ補正は基本的に2軸です。故に超広角から中望遠まで有効で、撮影レンズを選ばないボディ内手振れ補正が、より有効であり、中級機以下でボディ内に手振れ補正を持たないPanasonic 機を除外しているのです。例えば、安価で描写の楽しい「MF中華レンズ」でも、ボディ内手振れ補正なら有効なのです。また、メーカーの修理対応が終了した機種はどんなに安くてもお勧めしません。みんな大好きなPEN-F は 2000画素機ですが修理対応が終了しているので、私に言わせれば限りなくジャンク品に近しい物件です。1600万画素機では、E-M1. E-M5Ⅱ. E-PL5. 6. 7. E-M10. E-M10Ⅱまでは修理サービス期間が終了していますけど、一部部品が残っている製品で、修理・点検サービス・診断サービスが可能な場合があります。これより古い機種は、修理サービス期間が終了し部品も残っていないので、修理・点検サービスだけでなく診断サービスも受けてもらえません。私が所有する E-PL8 ですが 2024.9.9-11.29 に行われていた「シャッター交換キャンペーン」にてシャッターユニットを交換しました。料金は通常の約 50%OFF、返送料は先方負担というお得なキャンペンーンで、しかも、シャッター交換の上、各部点検、清掃、ファームウェアのバージョンアップまで実施。ウチもそうでしたが、現時点でシャッター故障が発生していない場合でも希望があれば交換してくれました。修理保証と同様の 6カ月間保証も付きます。対応機種は PEN-F \15,400-. E-PL8. E-PL9. E-PL10. E-P7 \13,200- と「お値打ち」で、おかげでウチの E-PL8 はグッドコンディションです。このキャンペンから予測できるのは「旧オリンパス製品」のサポートは早々に終了したいと言う考えです。なので中古とは言え現行機種か、古くても2世代前までが「妥当な選択枝」です。現在、2000万画素機で唯一 PEN-F のみ、修理対応が終了していますが、今ならシャッターユニットがまだ残っているかも。 PEN-F のユーザーさんは、シャッター回数がボディで確認できますから現時点で故障していなくても部品が有る間に交換した方が良いと思います。但し、修理料金は通常料金の31,350 円の可能性が高いです。各自で確認して下さい。此処からは裏面照射積層型 Live MOS 搭載機。「PROレンズ」を使って撮影すれば「ボケ量」の差以外で画質の違いを簡単に見分ける事は難しいでしょう。予算が許せば「本命」はこちら。⓵OM-1(初代) ¥136,000-~159,800- 最新センサーを搭載した一世代前の最上級機がこの価格は「お値打ち」だと思います。 「ライブGND」とAIAFに興味がなければ、本機で無問題だと思います。②OM-3(現行モデル) ¥188,100-~214,800- やっと市場に出回り始めたって感じで、まだ高値安定ですからキャッシュバックキャンペーン等 を利用して新品を購入した方が良いかもしれません。コンピュテーショナルフォトを気軽に切り 替えてさつえいしたいなら「CPボタン」はマストな装備かもしれません。個人的にはEVFが 現行の最下位モデルと同じなので、現在の中古価格では魅力を感じません。③OM-1MarkⅡ(現行モデル) ¥196,900-~240,000- 中古価格が20万を超えてくると Panasonic の上級機も選択肢に入ってくるのが悩ましいです。現在の私はメインが OM-1(初代)で、サブが E-PL8(1600万画素)です。この2台では使用するレンズも全く異なります。今回はミラーレス入門と言う事で、色々な意味で入手し易い「中古ボディ」を紹介していますが、本来は「使いたいレンズ」を決めて、そのレンズが使い易いボディを選ぶのが本筋だと私は思っています。例えば「野鳥撮影」を本格的に行いたいのなら、必ず、レンズを先に選んでください。40-150 / 2.8 Pro や 300 / 4.0 Pro あと 100-400 / 5.6-6.3 IS なら中古の球数も多くそれなりに選択肢の幅がありますし、ボディも E-M1MkⅢ で問題ありません。ですが、最新にして最良と思われる 50-200 / 2.8 IS Pro を選ぶなら、レンズ性能を最大限発揮させるためにも、ボディは最新センサー搭載機を選ぶべきでしょう。M.ZD 300mm F4 IS PRO(中古)+ E-M1MarkⅢ(中古) ¥296,800-M.ZD 50-200mm F2.8 IS PRO (新品)+ OM-1(中古) ¥549,820-どちらも参考例ですが、ほぼ「最安値」だと思います。フルサイズ機なら「100万コース」でガチの「野鳥撮影」とはこう言う世界です。金持ってそうな「オッサン」が多いのも納得。何より、ボディの購入金額よりレンズの購入金額の方が、下手をすれば数倍にもなるのですから、ボディを後回しにするのは当然だと思うのです。普通の「Proレンズ」を選んでも「RAW撮りPC現像」が前提なら、ボディは 2000万画素機から選んでも特に問題ありませんが「JPEG撮って出し」なら最新センサー搭載機を選ぶべきです。パンケーキズームや小型単焦点レンズを選ぶなら、ボディも小型・軽量な方が良いですね。そして、実際に中古で購入する場合「レンズセット」が別々に買うよりお得な事も少なくないので検討してみてください。では、良い m4/3 デビューをお祈りしています。(^^)
2025.10.31
コメント(0)
-

ファームウェア 「1.8」がアップされていました。
気が付いたら、初代OM-1の新しいファームウェア「1.8」がアップされていました。基本的には M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO への対応がメインですけど「安定性の向上」も「お題目」として記載されています。OM SYSTEM のサイト情報によるとVer.1.8(2025/9/10)M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mmF2.8 IS PRO使用時のSH2 50fps連写に対応しました。動作の安定性を向上しました。とのことです。この「動作の安定性を向上しました」と言うのが「何の」安定性を向上させているのかが、とても気になります。個人的には「顔・瞳検出」の安定性が向上していたら嬉しいです。同様の文言は Ver.1.6 でも使われていました。Ver.1.6(2024/4/11)動作の安定性を向上しました。スマートフォン接続のセキュリティレベルを選択可能にしました。Wi-Fi接続できない場合には「WPA2」を設定してください。取扱説明書を更新しましたのでご参照ください。OM-1取扱説明書ダウンロード私はOM-1のファームウェア Ver.1.7 登場時に中古価格は「底値」だと判断して Ver.1.6 仕様の中古OM-1をゲットしましたが、全く使わずに Ver.1.7 にアップデートしてしまったので Ver.1.6で、どの程度「動作の安定性が向上」したのか知りません。予想出来るのは中古市場の価格に影響が無かったと言うか、変わらずに中古価格が下がり続けたので、ユーザーは納得できなかったのでしょう。当時はケースバイでしたが E-M1 Mk.Ⅲの中古価格の方が高かったと記憶しています。上記アップデート項目に対して Ver1.7 のアップデートは下記の通り。Ver.1.7(2024/8/29)S-AFとC-AFの(オールターゲット) 時の、主要な被写体に対するAF性能を向上しました。撮影時の(消去) ボタンでのメニュー操作に対応し、右手でのメニュー操作を可能にしました。[ MENU > (歯車タブ) > 1.操作 > ボタンの設定 ] から設定可能です。「消去ボタンに MENUボタン機能を割り当て、撮影時に右手でメニューを呼び出す方法 (OM-1)」をご参照ください。また、取扱説明書(ver1.7)の347ページにも掲載しています。OM-1取扱説明書ダウンロード手持ちハイレゾショットの合成アルゴリズムを改善しました。その他カメラの動作安定性を向上しました。このアップデートで一番評価が高かったのは「S-AFとC-AFの(オールターゲット)時の、主要な被写体に対するAF性能を向上しました。」です。少なくとも、他メーカーと比較できるレベルに追いついただけですが、今まで搭載されていたAF性能は「Mk.Ⅱ」並みになった。と言う事で、中古市場で「初代」の評価がゆっくりとですが向上しました。また E-M1 Mk.Ⅱや Mk.Ⅲユーザーから好評だったのは「撮影時の(消去) ボタンでのメニュー操作に対応し、右手でのメニュー操作を可能にしました。[MENU > (歯車タブ) > 1.操作 > ボタンの設定 ] から設定可能です。」ですね。コレで、ようやく「初代」は非常に多かった E-M1 Mk.Ⅱユーザーの理解を得られたと思います。個人的には「手持ちハイレゾショットの合成アルゴリズムを改善しました。」も嬉しいです。最終的には「その他カメラの動作安定性を向上しました。」と合わせると「ライブGND」が不要なら「初代」でも「実用に耐える」という評価に収まりました。まぁ E-M1 Mk.Ⅲと同等か、少しマシな程度ですが、オールターゲットのAF性能向上で差別化が出来たのかなと言う感じです。今回の「動作の安定性を向上しました。」は、現行モデルであるOM-3との位置関係にあったと「CPボタン」や「ライブGND」は別として「基本性能」でOM-3から大きく劣るのでは問題アリとの判断がメーカー内で浮上したのではないでしょうか。OM-1Mk.Ⅱに、性能が近づいてしまうとしても、既に廃番モデルで「炎上騒ぎ」が収まった処でのアップデート。おそらくですがOM-1Mk.Ⅲでは「CPボタン」を搭載してくるでしょうから、AF性能のさらなる向上は当然として、今後 OM SYSTEM のミラーレスは「CPボタン」が、一つのキーワードになるのかなと愚考しています。であれば「CPボタン」を持たないOM-1Mk.Ⅱも「初代」共々「過去モデル」と言う扱いとしてしまえば、今さら「初代」の性能が多少 Mk.Ⅱに近づいても問題なし、それよりもOM-3との差別化が重要だと考えても不思議はないのかなと愚考します。今更「初代」のAIAFに「人物」を入れるのは無理だと思いますけど、今回のアップデートで「顔・瞳AFの性能・安定性」が向上していたら嬉しいです。と言う事で「初代」OM-1のファームウェア Ver.1.8 登場のお話でした。
2025.10.29
コメント(0)
-

SPスタンド LS-EXA3 をゲット♪
本来、このSPスタンドは EX-A3の為に作られたもので、現在は同じ品物が LS-EXHR99 の型番で販売されています。対象機種は EX-HR9. EX-HR5. EX-N1 / N5 / N50. EX-AR7.EX-AR3. EX-AK1. EX-BR3. EX-BK1. SX-WD30. X-WD9VNT. の為に作られたオプションなのですけど EX-S1 のSPを縦にした時の寸法が 122x155x236 で、このSPスタンドの寸法が 120x43mmx232 で横幅で 2mm と奥行で 4mm ほど出ますが、ほとんどジャストサイズになっているのです。で、本来このスタンドは一万円前後ほどのお値段なのですが、某オークションで半値以下で落札出来てしまい、ウチにやって来る事になったのです。まさか落札出来るとは思わなくてラッキーって言うより「えっマジ?」って感じでした。(;^_^Aまぁ、SPスタンドと言っても 30mm 厚のMDFボードに、真鍮製インシュレーターを組み合わせ、設置側はフエルトが、SP側にはインシュレーター上にコルクスペーサーが貼ってあるだけなので、見た目を意識しなければ、もっと安価に作成する事も可能なのでこの値段で間違って落札出来たら市販のインシュレーターを色々試すより良いかな?って感じで入札したのです。インシュレーターなんで、安く済まそうと思ったら、片側に5円玉を3枚、ペアで \30-から実現可能ですが、専用品としてチューニングされている安心感が有りますし、何より実勢価格で一万円前後する品物ですから、見た目が奇麗で素敵ですね。単体での姿。SP置いたら見えないけど中央にプリントされた「Victor」のロゴが素敵。重量はカタログスペックだと、単体で約 760g との事で、ウチの設置環境だと、MDFボードのご利益がありそうだと思っています。(実際には真鍮製インシュレーターの効果が大きかった)まずは直置きで縦位置に設置して違いを確認してみました。縦置きにしただけでも全体に重心が下がり、音場定位が向上する事を確認できたので、横置きは設置場所の影響を受け易いと言う事かもしれません。最後に今回のSPスタンドを設置してみました。元は横置きSPとは思えない姿に感じます。横幅が 2mm ほど大きいはずなのですが、前面が緩やかなラウンド形状になっているので上記画像だと逆に細く感じるほどですね。実際には「丁度良い」感じで、本当に良い雰囲気です。知らない人が見れば「専用品」と思う事でしょう。奥行も良い感じで、正にジャストサイズ。側面の「ゴム脚」はご愛敬と言う事で。(;^_^A気になる実際の効果ですが、ウチの環境では「効果絶大」でした。入手して大正解です。このスピーカーはヘッドユニットとの見た目のマッチングを無視できるなら、縦置きが「正解」だと思いました。縦置きにしただけでも、低域がの質が向上しつつも量感が増え、音場定位も向上し、人のの声が背景の音に全く埋もれず、とても聴き易くなりました。更に本SPスタンドを介在すると、生々さに拍車がかかります。まるで対面で歌ったり話したりしているような臨場感です。また、真鍮製の脚の成果と言いますか中高域から高域にかけては、美しい響きを伴って奇麗に伸びる雰囲気で、大げさに言えばソフトドームツィーターだけではなくてホーンツィーターまで足した様な奇麗な高域です。(あくまでイメージです)ヴォーカル域でのウッドコーンの艶っぽさに美しい高域を乗せて、低域はバランスを取る為、量感を増やしたような感じです。Apple Music のハイレゾロスレスで聴く Jazz はピアノの高域やシンバルの響きが奇麗ですし低域も向上した中高域とバランスが取れる良い塩梅で量感が増しているので、ウッドベースも良い感じに響きます。小さな 8.5cm SPだと思えばこれ以上ない結果だと思いました。フルレンジSPなのでモニタースピーカーの様に定位が良いのは、ある意味で当然ですけど、JPOP ではヴォーカルに掛けた、リヴァーブやエコーの量とか質まで感じる事が出来ますし、ブレスの吐息までしっかりと聞き取れます。。そして音場は欧州系SPの様にSPの外と奥に広がる感じとなりました。はっきりと言えば「まるで別物」のSPかと錯覚するほどに全てが向上しました。ですが、弱点もあって「ぼっち・ざ・ろっく」の「あのバンド」では、ボッチちゃんが奏でる冒頭のギターソロでエフェクターの効きが強調され、何だかグシャっとして聞こえました。Apple Music のロスレスより Prime VIDEO でアニメを視聴した方が良い塩梅です。では、「ロックが苦手」なのかと言えば「ロックはレディの嗜みでして」のOPは AppleMusic で視聴してもドラムもギターも良い感じで、しかもヴォーカルが埋もれない良い塩梅でした。でも、全般的にアニメの楽曲は Apple Music で聴くよりも Prome VIDEO だったりYouTubeで視聴した方が良好な結果になる事が多いです。今回の設置方法では、ソースのクオリティに対してシビアになってしまったかもしれません。録音が良いとされるアルバムでは非常に良い感じですし、クラシックやJAZZも良いです。ピアノ、女性ヴォーカル、アコースティックギター、ヴァイオリン、金管楽器全般などなど、実に良い。SPスタンド(と言うか一体型インシュレーター?)を足しただけなのに3時間近く、色々な楽曲を改めて聴いてしまいましたし iPad の小さな画面で音楽が印象的なシーンを視聴したり YouTube の 1st Take を視聴したりしたのですけど新たな発見があったりして楽しかったです。正に「聞き惚れる」ってヤツですかね。家には音楽を聴く用と映画やアニメを視聴するようにシステムが複数あるのですけど、今までボンヤリしていたウッドコーンシステムが「ガチで音楽を聴く」為のシステムとして確立したなって感じです。このSPを縦置きする機会を与えてくれただけでも、このSPスタンドを入手した価値があったと思いますし、それだけ元の設置環境が悪かったと言う事かもしれませんが、SPの設置環境に自信が無ければ、手に入れる価値は「アリ」だと思います。若干ながら低域の量感を増やし、中高域には「ウッドコーンらしさ」と言われる艶感を足してくれるのですから、SPの設置について自信が無かったり、色々と考えるの事が面倒ならば、お高いですけど「専用品のご利益」は有ります。ウッドコーンスピーカー専用の艶っぽさや、色っぽさを意識してチューニングされたSPベースです。と言う事で、あまり宜しくない設置環境では優秀な結果を出すと思いますが、音に対する評価も設置環境も千差万別で基本的に「同じ環境」と言うのは有りません。ウチは偶然にも最大級の効果が出ましたが「以前から使ってた安価なインシュレーターの方が良いじゃん」って思う人も居るでしょう。私は良い物だと思いましたが、導入は「自己責任」でお願いします。正直な話をするとヘッドユニットを換えた事で音質が向上して、逆に欲が出てしまって9cmユニットのウッドコーンSPシステムに入れ替えようかと真剣に悩んでいました。まぁ、それ故の前回のブログだったりする訳ですが、今回のSPスタンド LS-EXA3 の導入で「もう、これで良いかな」って気になり始めています。今後も9cmユニット搭載システムの物色は時々行うと思いますが、よほどの「出物」に出会わない限り、ウチのシステムは「コレで決まり」かもしれません。と言う事で、落札出来なくても良いかなぁ位の気持ちで安価な価格で入札したのに何故だか落札出来てしまった LS-EXA3 ですが、本当に良い品物でした。
2025.10.27
コメント(0)
-

OLYMPUS 本革ボディジャケットを改造してみた♪
私が m4/3 のサブ機としている E-PL8 ですが、去年の11月にメーカーキャンペーンを利用してシャッターユニットの交換を行ったので絶好調です。で、この E-PL8 のケースとして使っているのが、メーカー純正の本革ボディジャケットなのですが、ストラップ取り付け部を利用した固定方法だとケースとボディの固定が甘くて気に入りませんでした。それにケースの上からクイックシューを取付て使用したいのですよね。ですが、クイックシューを付けてしまうとケースを外すのが面倒になり、今度はバッテリーや記録メディアへのアクセスが面倒になってしまいます。 ULANZI F38 / F22 共用クイックシューの取付も苦労しました。完成当初は専用USBケーブルを使用してPCにデータを取り込み、バッテリー交換は面倒ですがその都度クイックシューを外してケースも外していました。データの取り込みは特に問題を感じませんでしたが、やはりバッテリー交換が面倒です。なので、サードパーティ製ケースで採用されているケース底面のバッテリー部をフラップ化する改造を施してみました。コレでケースを付けたまま、バッテリーと記録メディアにアクセスできます。現物合わせで加工を開始したのですが、読みが甘くて追加加工をしながら仕上げたので、結構な時間を要してしまいました。また、底板に厚みが有ったのでバッテリー交換時にはクイックシューの向きを90°回さなくてはなりません。それでもケースを外したり戻したりするよりは楽になったし、メディアの出し入れなら普通に出来るので良しとします。(;^_^A何とか仕上がりましたが、合皮で問題を感じなければ初めから完成されているサードパーティ製品を入手した方が良いですね。私の場合は中古の純正ボディジャケットをも安価に入手したので改造してみました。まぁ、自分で使う分にはギリ合格ですかね。。。
2025.10.26
コメント(0)
-
JVC Victor のウッドコーンスピーカーについて
ウチでは 8.5cm 横置きバスレフ型エンクロージャーである JVC EX-S1 のSPを現在はiPad(Youtube/Apple Music)⇒ Hip-Dac(DAC) ⇒ AIYIMA A07 MAX(AMP)と言うセットで鳴らしています。純正ヘッドユニットで鳴らしていた頃と比べるとウッドコーンらしさと低域の量感は薄れ、その代わりワイドレンジなSPになったと思います。まぁ、ワイドレンジと言っても 8.5cm シングルコーンですから限界は有りますけども、定位の良さとウッドコーンの艶っぽさを残す、私にとっては好ましい音楽を聴かせてくれるシステムになっています。純正の組み合わせとの違いを端的に言えば、よりモニターライクになったと思います。ウッドコーンはそれなりに人気があるらしく現在 PARC Audio さんから単体フルレンジユニットが販売されていますが、今回は JVC Victor さんから販売されたフルレンジSPについて書いてみたいと思います。現在、新品が購入出来るのは Victor EX-HR10000 / HR99 と JVC EX-S55 の3機種に限られますが、今回は初代 EX-A1 から続くウッドコーンSPをフルレンジ 8.5 / 9 cmに限定して書いてみました。まずSPユニットの種類ですが、サランネットの違いまで考慮すると15種類でした。なお、縦型エンクロージャーのサランネットにはSPユニットのサイズに関係なく互換性があります。●縦型エンクロージャー用8.5cm 最初期モデル。唯一の防磁型。 個人的には中古でも割高なのでお勧めしません。サランネットは四角形。 EX-A1. 120x161x239 1.6kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第二世代。サランネットは四角形。 キャビネットが天然無垢チェリー材の AK1 と、MDF材ピアノブラック仕様の BK1 が 存在する BK1 の重量表記は誤りだと思われる。第二世代より奥行が短い。 EX-AK1. 120x161x239mm 1.7Kg EX-BK1. 120x161x239 2.0Kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第三世代。サランネットは円形。 防磁仕様を排しマグネットを大型化、エンクロージャー(箱)も大型化された。 EX-N1/N5. 120x161x246 1.7Kg ・N5 はヘッドユニットがブラック。 キャビネットのフロント、天板、底板にチェリーの天然無垢材を採用した上位モデル。 EX-S1000. 120x161x246 1.7Kg●縦型エンクロージャー用8.5cm 第四世代。サランネットは円形。 ウッドブロックが採用されました。縦型8.5cmユニット採用SPの最終モデルで、 奥行きが一番長く、結果、重量も一番重い。 EX-N50. EX-HR5/HR55. 120x161x248 1.8Kg 初代 A1 だけ、箱がやや小さいです。世代を経るごとに重量が100gずつ重くなっている ので、それなりに進化しているのだと思うけど、中古市場の C/P を考えると個人的には 微妙な存在です。音色の違いは確実にあるようで HR5/HR55 のSPが 8.5cm ユニット ではベストかもしれません。●横型エンクロージャー用8.5cm 第一世代。 チェリー材の響棒とともに補強板や補強桟が組み込まれています。私も使っていますが、 安価に入手できる可能性が高いので悪くない選択肢だと思います。 EX-S1. 155x122x236 2.0Kg●横型エンクロージャー用8.5cm 第二世代。 ウッドブロックと補強桟、四方留め構造でキャビネットの合成アップ。OFCワイヤー採用。 チェリー材の響棒を排し、代わりにウッドブロックが採用されました。 EX-S5/S55. 140x110x276 2.0Kg こちらはコスト削減の為か重量は変わりませんけど S5 / S55 ではエンクロージャーが長く なっています。SPユニットは専用設計の新型で、個人的には EX-S1 のSPは EX-A1 比較 でも決して悪くないと思っています。寸法的にも EX-A1 のSPを横置きにしたサイズに近い のでSPユニットが新しい分だけ良いのかもしれません。 エンクロージャーの容量的には縦型が勝り、重量的には横型が勝ると言う図式になってます。 横型SPはヘッドユニットのクオリティが低いので単体運用する事で化けるSPです。 現行モデル以外では EX-HR5 の修理期間が 2027.12 までで、その他の機種は全てメーカー 修理が出来ません。●縦型エンクロージャー用9cm 第一世代 進化したフルレンジウッドコーン、との記載があり、天然無垢材のフラッシュサーフェス ・スピーカーキャビネットが採用され、サランネットは円形。 EX-A3. 120x161x267 1.8Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第二世代 低音の質感を向上する竹響板を採用した天然無垢チェリー材キャビネットになりました。 重厚な低音と高解像度を実現するメイプル材による木製吸音材も採用されています。 どちらもサランネットは円形。 EX-AR3. 120x161x267 2.0Kg EX-BR3. 120x161x267 2.0Kg キャビネットがMDF材のピアノブラック仕様*同一世代としたがエンクロージャーの仕上げが全く異なるので鳴り方は違うと思う。●縦型エンクロージャー用9cm 第三世代 異方性振動版とウッドボイスコイルが採用されましたが、ウッドブロックはまだです。 なお EX-A3Ltd のサランネットは円形で EX-AR7 のサランネットは四角形。 EX-A3Ltd. EX-AR7. 120x161x264 2.0Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第三世代上位モデル。 第四世代SPへ更にポールピース上部メイプル吸音素材、不均一コルゲーションダンパー、 スプルース縦目響棒を採用した上位モデル。サランネットは AR7 と同じく四角形。 EX-AR9. 120x161x264 2.0Kg●縦型エンクロージャー用9cm 第四世代 異方性振動版に次いで、ウッドブロックが追加された最終モデル。 ウッドブロックの材質にメイプル材と、レッドオーク材の違いがある。 EX-HR11/HR10000. 120x161x264 2.2Kg ウッドブロックがレッドオーク材。 EX-HR9/HR99. 120x161x264 2.2Kg ウッドブロックがメイプル材。上記システムは、全てヘッドユニットとセットで音響特性を決められていて、ヘッドユニットを一般なAMPに変更すると、安価なモデルやDVD搭載のAV対応モデルほど、ウッドコーンらしさを残しつつモニターライクな音に変わります。逆にヘッドユニットを一般的な小型SPに繋ぐと、人の声をを中心として音楽性豊かに響く傾向となりますが、好みが別れる癖のある音作りと言えるかもしれません。初期モデルはDVDに対応したAVモデルなので音作りも人の声を意識して作られているのだと思います。中期のネットワーク対応モデルや、搭載ドライブがCDに変わってからのモデルは純粋に音楽を意識していると思われるのでヘッドユニットとセットで音楽を楽しむのであれば考慮した方が良いかもしれません。古い機種を選ぶ場合はメーカー修理がほとんど終了しているのでDVDドライブやCDドライブを搭載しないモデルを選ぶと言う選択肢もあるのですが、その場合はSPユニットが 8.5cm か2ウェイSPに限定されてしまうのが悩ましいです。JVC Victor のウッドコーンスピーカー製品群は総じて「楽器」としての意識が高く「響き」や「余韻、艶」といった感性に訴える部分を重視しています。ですので自宅に近い環境で、好みの音楽を聴いて確認するのがベストですが、個人的には欧州製品に似た、音楽性豊かな製品としてお勧めしたいです。オマケとしてウッドコーン搭載2ウェイSPについて書きますと、2ウェイ2SPモデルにバイアンプ対応型とネットワークの入った通常モデル。AV向きと思われる2ウェイ3SPモデルが存在します。ウッドドームツィーターには大変興味があるのですけど設置スペースが無いのでウチへの導入は考えていません。フルレンジウッドコーンシステムは音楽再生に妥協はしたくないけど、ガチでオーディオに予算を費やしたくないライトユーザーには良い選択肢になると思います。
2025.10.24
コメント(0)
-

音の良い USB-C マグネットアダプター。
先日 iFi-Audio Hip-Dac の別売 USB-C ケーブルをゲットした訳ですが、経由するマグネット接続のアダプターもアップグレードしました。何故かと言えば、マグネットアダプタ無しの状態と比較して明らかな劣化を感じたからです。とは言えL型アダプタ無しでは設置に支障が有るので音質に与える影響が少なそうな製品を改めて探す事にしたのです。と言う事で、今までは円形コネクターの 9Piin 型を使用していたのですが、今回は 24Pin 設計で8K@60Hz 映像にも対応した物を選んでみました。どちらもL型ですが、材質が異なります。画像中央はアルミニウム合金製で画像右は亜鉛合金製です。事前の予想では金額も高め出し亜鉛合金製の方が良さそうだと思っていたのですが、実際にはアルミニウム合金製では、ロスを全く感じる事なく、亜鉛合金製では S/N は若干向上したように感じましたが、ローパスフィルタを掛けたような感じに思いました。外部ノイズを拾うような環境では亜鉛合金製が良いと思われますが、家ではアルミニウム合金製を Hip-Dac で使う事にしました。亜鉛合金製の方はBGM用SPで使います。こちらはTONEコントロールが有るので低域を少しブーストしてバランスを取りました。結果的にどちらも音質向上を果たしたので大満足です。
2025.10.17
コメント(0)
-

ULANZI FALCAM F38 / F22 システム導入。♪
この ULANZI FALCAM F38 / F22 システムは俗に言う「クイックシュー」の部類ですが、従来と異なるのはシステム化されている事です。クイックシューはフィルムカメラ時代に HAKUBA のクイックシューだったり、ハッセルのクイックシューを使っていましたけど、デジカメは高感度ISOが気軽に使えるので三脚の出動機会が激減しクイックシューも使わなくなっていました。まず ULANZI FALCAM F38 システムですが、一般的なクイックシュープレート以外にクイックリリースショルダーストラップタイプV2、カメラホルダーバックパッククリップキャプチャー型更に新型のバックパックストラップクリップ カメラホルスターV2、クイックリリース折り畳み式ハーフケージキット、動画撮影用ケージ、ジンバル用プレート等、様々な製品とオプションが登場しています。また、似た構造で小型機材用の F22 と、主にビデオ機材向けの F50 もあります。ショルダーストラップタイプV2とninjaストラップの組み合わせ。自転車でカメラを持ち歩く時に便利そうなので、ショルダーストラップタイプV2とninjaストラップをセットで導入しました。ですが、考えてみたらカメラを「むき出し」で持ち歩く習慣が無いのでショルダーストラップタイプV2と ninja ストラップは無駄だったかもしれません。(;^_^AF38 のベースは新型1個と従来型1個を購入しそれぞれを比較しました。結果として、屋外で使用するメインの三脚にはプレートロックの使い易さと安心感で新型を選びました。ですが、私の運用方法では価格ほどの差は感じなかったので、安価な従来型を2個追加して、小型三脚とミニ三脚に取付けています。新型の方が良く出来ていて安心感があります。屋外運用メインなら新型をお勧します。屋内ではプレートロックしないで使ってますが、従来型では数mmリリースボタンが押されるだけでロックが解除されてしまいますので屋外運用ではプレートロックが絶対条件でしょうね。対する新型は、プレートロック自体も楽ですが、ある程度シッカリとリリースボタンを押さないとロック解除されないので、万が一プレートロックを忘れても安心感があります。私が F38 で使用するボディは OM-1 と E-PL8 で、どちらもケースの上からクイックシューを取り付けています。特に E-PL8 の純正ケースは、運用していてケースの「遊び」が気になっていたのでクイックシューが付くように加工する事でカメラとケースがしっかり固定できるようにしました。OM-1 の TP Original ハーフケースにはサクッと取り付けできました。クイックシューを取り付けてもバッテリーへのアクセスは問題ありませんでした。流石の造り込みだと思います。このケースは小指の遊びが解消され持ち易くなるのも気に入っています。E-PL8 の純正ケースに F38 / F22 共用クイックシューを取付けるのには苦労しました。背面液晶の「自撮りモード」を生かす為には純正ケースしかない訳ですが、このケースの取付方法は「遊び」が多いのが気に入りませんでした。ケース自体はフェイクレザーではなく本革ですので質感は非常に良いのにケースとボディの取付に微妙な「遊び」が有るのが嫌だったのです。この加工でボディとしっかり一体化したので個人的には満足していますが、バッテリーやメディアへのアクセスは面倒になったので、PCへのデータ移動はケーブル接続で対応しています。バッテリー交換は「諦めモード」です。それでも、ケースがボディにシッカリ保持されたし、私は手が大きいのでケースがあった方が使い易く、そのケースを固定する方法としてクイックプレートをケースの上から付ける加工を行いました。ですが F38 のクイックシューでは前後に飛び出してしまうので F38 / F22 共用クイックシューを使用しました。そのままでは長さが足りなかったので取付ネジを交換・加工しています。このクイックシューは共用なので F38 と F22 の両方で使用できるのが便利です。今回の様に一般的な F38 シューよりも奥行きを短縮できるのが便利な場合もあると思いますし。ケージや小型三脚では F38 を使い、ミニ三脚で F22 を使うって感じで、コンパクトな E-PL8 には良い選択になったと思います。若干シューが邪魔ですが自撮りモードがそのまま使えます。まぁ E-PL8 で自撮りモードを本当に使うかは何とも言えないところですが、せっかく搭載されている機能をスポイルするのも嫌なので加工を頑張りました。主に小物撮影や動画撮影に便利そうなので「折りたたみハーフケージ」も入手しました。LED照明や外部マイクをハーフケージに取り付ける為 F22 を使う事になります。この、折り畳み式ハーフケージは、手持ちの OM-1でも E-PL8 でも使える優れもので、汎用性と利便性に優れるのが良いと感じて購入しました。仮に、機材に変更が在っても継続して使用出来る可能性が高く F38 システム対応で簡単に脱着が出来るのも非常に良いのです。このハーフケージを使う場合は F22 接続が一番楽で確実なので F22 もある程度揃えました。動画撮影で、外部マイク、外部モニター、ビデオライト、等をカメラに付けるにはケージが無いと始まりません。外部マイクは必須として、バリアングル液晶でもモニター出来ますが外部モニターも有ると無いとでは利便性が大きく異なりますし、ビデオライトも同様です。小型のビデオライトは自撮りから、せいぜい1m程度の距離が限度なのでモニターとビデオライトを同時に付ける事は多くないですが、外部マイク+ビデオライト、外部マイク+外部モニター、と言う組み合わせは多いのでミラーレスで動画撮影するならケージがあった方が良いです。まだ機材が揃っていないので、とりあえずケージだけを付けてみました。現在 iPhone や iPad を外部モニターとする機材を物色中で、およそ決まりつつあるのですけど、お財布事情で先送りしている状態です。それに動画撮影機材としては SONY ZV-1. DJI Pocket 2. DJI Action 2. が有りますし撮影頻度も多くは無いので、まぁ良い「出会い」があれば入手しようかなと思っています。とは言え、動画撮影にも使える 8-25 / 4.0 Pro を入手しましたから、テストはしたいですね。このように F38 と F22 には多種多様な周辺機器が揃っていて、かつ「ワンプッシュ」で着脱可能なのに、しっかりと取付できる優れモノです。
2025.10.16
コメント(0)
-
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO について。
今回は M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO を「広角寄りの標準ズーム」と考え、 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROⅡと比較してみたいと思います。まずフィルターサイズですが 12-40 / 2.8 Pro は Φ62 で 8-25 / 4.0 Pro は Φ72 と、1サイズ大きいです。この1サイズの違いは価格にそれなりに影響しますので、特殊効果フィルターを揃えようと思うと地味に辛いかもしれません。次に大きさと重さは 12-40 / 2.8 Pro の φ68.8 x 84mm 382g に対し φ77.0 x 88.5mm411g とほんの少し大きく重いですが、実際に手にしてみれば誤差の範囲ですかね。先端部は太いですが、手に持つ分部が同形状と言う事もあると思います。専用フードを逆付けした収納状態では本当に誤差の範囲で特に問題はないです。で、収納時のサイズがコンパクトに収まっているのは「沈胴式」を採用したからです。世の中には沈胴式を嫌う方も少なからずいらっしゃいますけど、本レンズの沈胴機構にはロックレバー等が無く、ズームリングを回転させるだけなので、個人的には持ち歩く時にズームが勝手に伸びないズームロックと考えれば全く気になりません。むしろ「沈胴式」とした事で収納時のサイズをコンパクトに収めてくれた事に感謝しています。また 12-40 / 2.8 Pro の望遠端である 40mm F2.8 はフルサイズ換算で 80mm F5.6 となってしまうのでボケ量に期待は出来ませんし個人的には全く魅力を感じません。ですので、よりコンパクトな 12-45 / 4.0 Pro を選んだのですが、本レンズを入手した事で、実は標準ズームの地位が危うくなっています。本レンズは望遠側が 25mm までカバーされているので画角的には標準レンズ相当であり、換算 16-50mm の超広角寄りの標準ズームと言えますし、デジタルズームを使えば、換算32-100mm となり、望遠寄りの3倍標準ズーム域をカバーする事となります。なので個人的には標準ズームをとして十分に実用的であると思うのです。運用面でも、最短撮影距離がズーム全域で 0.23m ですから標準ズームとして全く不足が無いのです。一般的には 12-100 / 4.0 IS Pro が万能標準ズームとして扱われていますが、広角好きな私には本レンズが万能標準ズームとなりそうな気がしています。
2025.10.15
コメント(0)
-
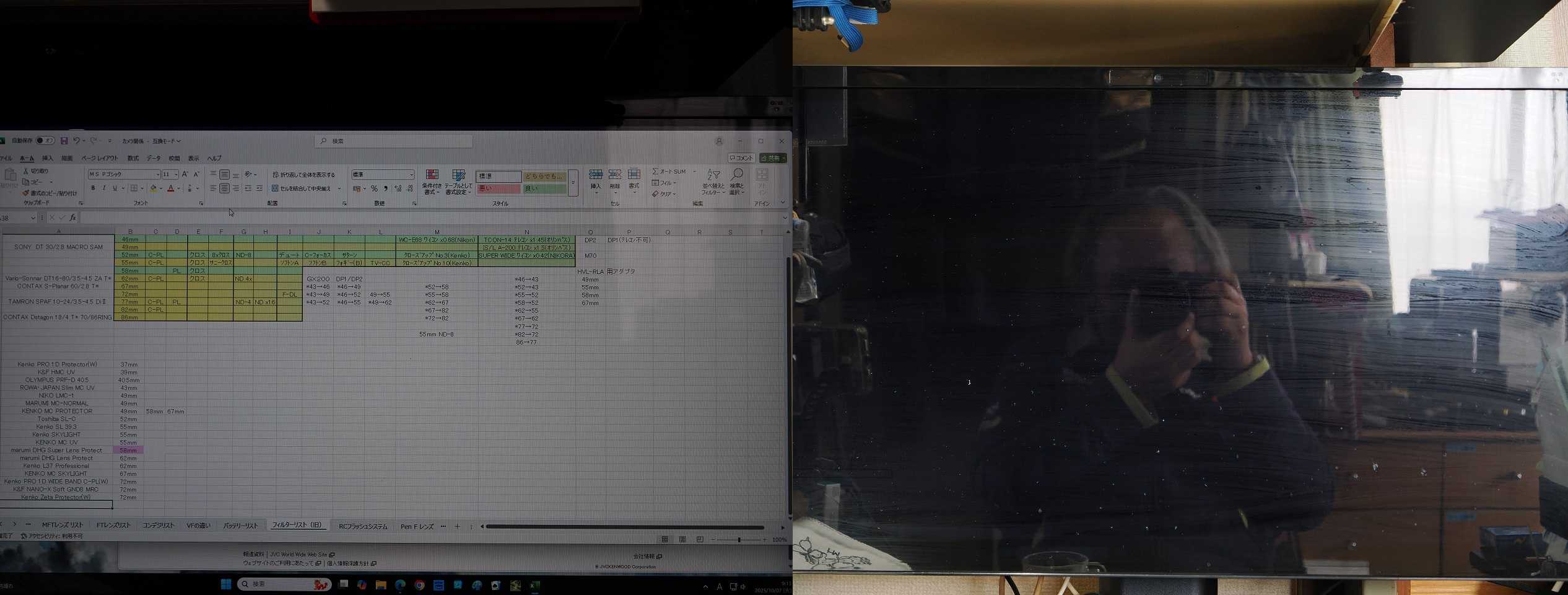
Kenko PRO1D WIDE BAND C-PL (W) 72mm(中古)をゲット♪
この夏に、ライブGND機能を持たないウチの OM-1で使う為に「ハーフNDフィルター」をゲットした訳ですけど、やはり風景撮影にはPLフィルターだろうと言う事で、ネットにて物色していました。と言うのもPLフィルターには多くのグレードがあるからです。で、色々と考慮した結果、タイトルの様に Kenko PRO1D の中古を購入しました。価格的にはK&F の一番安い C-PL フィルターと同程度か少し安い感じです。それなりに汚れていたので、シッカリとクリーニングしました。海外製品ですと短期間で変色したり、そもそも色被りしていたりするようなので、中古でも国産でそれなりのグレード品を選んでみました。中古とは言え定評 Kenko PRO1D シリーズですから撮影結果には満足しています。反射を消す事も出来ますが、その逆も可能です。ディスプレイを消したわけではありません。あくまでフィルター効果です。太陽の向き的に効果が弱いですが、それなりに雲の陰影が出ています。夕焼けなんかはハーフND一択ですが、通常撮影ではやはりPLフィルターの方が使い勝手が良いように感じました。まぁ、慣れているせいもあるとは思います。C-PL フィルターは経年劣化で変色したり色被りを起こすのが宿命ですが、多分、私が生きている間くらいは使えるのではないかな。国産の中古を選んで良かったと思います。
2025.10.12
コメント(0)
-
2025 夏アニメの感想。
かなり以前に「ひかりTV」を解約して以来、TVは完全に視聴しなくなったので、私のアニメ視聴環境は Amazon プライムのみです。なのでリアルタイムでも視聴しますけど、特に録画する必要も無いので、お気に入りを何度も視聴したりしています。で 2025 夏のお気に入りだったアニメは⓵その着せ替え人形は恋をする(シーズン2) ホスト回も良いですが「あまね君」の回も好きだし、寿叶様姉妹が登場する「棺」回も良い ですね。コスする「元ネタ」への造り込みが凄くて素晴らしい。今シーズンは海夢ちゃんの 微妙にズレた初心な感じが初々しくて良いです。シーズン3も期待しています。②サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと 初回が素晴らしく引き込まれました。背景や音作りも良かったです。③転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます(シーズン2) 好みは分れるかもしれませんがシーズン2も良作でした。④ふたりソロキャンプ 理解できない人には無理でしょうけど、16歳差の彼女と12年過ごした私としては「アリ」 でした。クオリティが低いのでお勧めはしませんけど、2クールモノだったのですね。秋も 続けて視聴します。⑤瑠璃の宝石 「石」の作画が素晴らしかったです。元気だったら「石拾い」に出かけていたかもね。 クオリティの高い良作だったと思います。⑥水属性の魔法使い 私は嫌いではありませんが「なろう」の原作には劣ります。作画も音も「並」です。⑦よふかしのうた(シーズン2) シーズン2が始まってから、シーズン1から見始めました。キャラデザに癖は有りますが 良作ですね。ラテンな感じのOPも好きです。他にもいくつか視聴していましたが「次週が楽しみ」だと思えたのは上記くらいかな。ダンダダン(シーズン2)は、まだ視聴していません。そのうちまとめて観ると思います。今年の夏は、過去作品の「異世界のんびり農家」や「転生したらスライムだった件」を視聴する事が多かったです。後は「魔法科高校の劣等生」とかね。改めて書き出してみますと、今年の夏は「鬼滅~」の映画も観に行っていないですし、体調悪化の影響は視聴作品にも影響しているように感じました。また「水属性の魔法使い」のような「なろう原作」の作品を視聴して原作を読み始めたりはしています。視聴環境がアマプラ(+Dアニメストア)オンリーになってしまったのも影響ありますね。HDに録画したら「視聴しなくては」と思いますが「何時でも観れる」と思うと視聴する気にならないって感じでしょうか。オーディオ環境が変わって音楽鑑賞の時間も多かったように思います。
2025.10.10
コメント(0)
-

INIU 大容量 モバイルバッテリー 20000mAh をゲット。
10月になって、やっと涼しくなってきた感のある、今日この頃ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は抗癌剤の副反応が少し酷くなったようで、引き籠りに拍車がかかっています。10月初めのお話は「モバイルバッテリー」についてです。昨年末に中古の Dynabook U63(Win 11 & MS Office 2019 インスト済)を入手しましたが、薄型軽量モデル故か内臓バッテリーが着脱不可でしたので、専用のモバイルバッテリーとしてUGREEN PD3.1 145W 25000mAh を同時に購入したのですが、なんと10回も使っていないのに充電不可になり廃棄しました。今までも、マイナーメーカーのモバイルバッテリーを3個ほど購入していますが他は全て現在でも使用しています。大容量、大出力と言う事で奮発して、それなりに知名度のある UGREEN を選んだのですけど、所詮は中華製と言う事でしょうか。まさか一年以内に使用不可になるとは思いませんでした。今回の事で、私の中で UGREEN 製品への信頼度は下方修正されました。とは言え同時期に購入した UGREEN Nexode 65W 急速 充電器は今も元気に動作していますので、定評ある充電器はある程度信頼しても良さそうです。とりあえず、二度と UGREEN のモバイルバッテリーは購入しませんけどね。仕方ないので再び Dynabook U63 用のモバイルバッテリーを物色してタイトルに記載の製品をAmazon プライム感謝祭の開始を待ってゲットしました。下一桁が充電時は点滅していて画像では表示されていませんが46%の残量でした。今回、このモバイルバッテリーを選んだ決め手は二つあり、一つは出力だけでなく入力も高出力に対応している事。コレで充電時間が大幅に短縮されます。二つ目は内臓セルがリチウムイオン電池ではなくリチウムポリマー電池と記載されていた事。分解して確認する訳にもいかないので記載を信じるしかないのですが、本当にリチウムポリマー電池内臓だとしたらかなりのお値打ち価格でした。容量表記が少なくなった分、小型軽量になったし、何より、無名メーカー故なのか本当に安かったです。かなり昔の話ですが「ソニータイマー」という言葉がささやかれていた時期が有りました。保証期間が終わるタイミングで故障する個体が多かったようで、そのような言葉が生まれたらしい。今時の中華製デジタル系ガジェットは一時期の返品期間が過ぎると故障するとか、ハズレ個体が多く、正しく検品されていないのではないかとか、そういう時期は過ぎ去り、それなりに信頼性が増してきたように感じます。それでもネット購入する中華製デジタルガジェットは今回の様に未だ「ハズレ」が存在します。まぁ、その分、安価なので一概に文句を言うのも違うような気もしますけどね。対策としては「充電したまま放置しない」と言う事でしょうか。充電したまま放置して外出したり就寝したりするのは危険と言う事です。後は自分の手元に「ハズレ個体」が来ない事を祈るだけです。(;^_^A
2025.10.07
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1