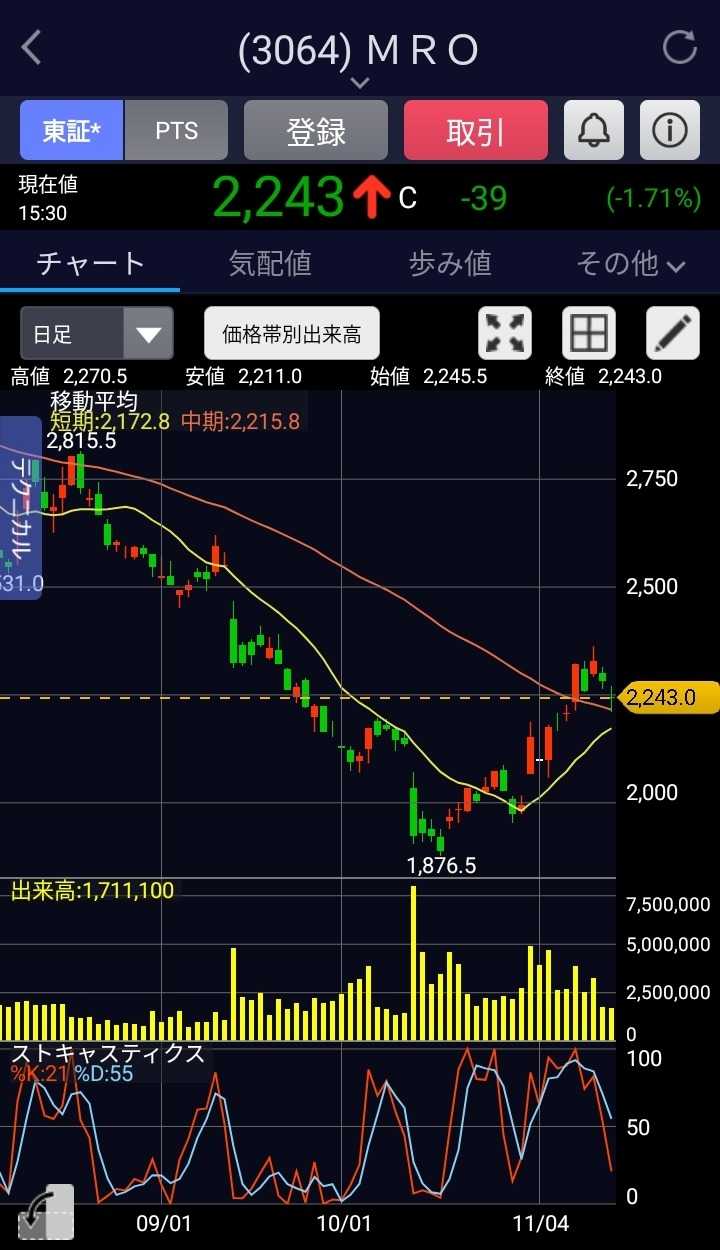2017年09月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

御香宮神社
つづき大手筋通を東へ歩いて、京阪と近鉄の線路を過ぎると、御香宮神社の赤い鳥居。左の白塀の奥、緑多き所が境内。いい香りの水が湧き出たことから、862年に清和天皇によって、御香宮と命名された。重要文化財の表門。1622年に徳川頼房によって、旧伏見城大手門から移築。表門をくぐると、大きな鳥居と参道。秋晴れの青空がすがすがしい^o^緑いっぱいの参道の先に、鮮やかな彫刻のほどこされた拝殿。同じく徳川頼房によって、1625年に寄進された。拝殿の彫刻を間近で見上げる。豪華絢爛きらびやか、めっちゃキレイ☆〃拝殿の奥に、徳川家康によって建立された、重要文化財の本殿。本殿にも極彩色の装飾がほどこされ、屋根のカーブも美しい♪全景を撮ろうとすると、この角度しかなくて、逆光なうえにソテツが邪魔ですが^^;本殿の右手に御香水の石碑。御香水の井戸は明治時代にいったん枯れたが、その後復元され、今も霊水が湧き出ており、名水100選に選定されてる。以下はお知らせ、といっても重大発表ではなく。10月2日のどこかの時間帯で、画像保存先がサーバメンテするので、その時は写真が表示されないかもしれません。
2017.09.30
コメント(12)
-

酒どころ伏見の街並み
黄檗山萬福寺2のつづき黄檗駅(宇治市)から中書島駅(京都市伏見区)まで電車移動して、酒蔵の建ち並ぶ伏見の街並み散策。ここは月桂冠大蔵記念館、近大化産業遺産に認定されてる。入館してないけど、立派なたたずまい☆〃道をはさんで反対側に月桂冠本社があり、付近には月桂冠関連施設が多数点在。さすが京都の酒どころ、趣ある古い街並みを歩いてると、古風な飲食店の出入口に。「伏見の清酒」と「月桂冠」の酒樽が^o^今度は黄桜。ここはキザクラカッパカンパニー、付近には黄桜関連施設が建ち並ぶ。坂本龍馬ゆかりの寺田屋。慶長2年(1597年)創業の宿で、慶応2年(1866年)に坂本龍馬が滞在中、幕府役人に襲撃された所。当時の建物は鳥羽・伏見の戦いで焼失し、現在は史跡庭園になっており、となりに旧宅にならう形で旅籠が建つ。旅籠・寺田屋を正面から。明治時代築、創業からの歴史を考えると、比較的新しい建物になるけど、じゅうぶん古くてステキ♪少し西へ歩いて、土手沿いに松本酒造。寛政3年(1791年)創業、現在の建物は大正11年築、近代化産業遺産に認定されてる。圧倒的な存在感ある建築群、レンガ造りの煙突が青空に映えてた!!つづく
2017.09.29
コメント(8)
-

飛鳥坐神社と最後に有名な古墳
つづき飛鳥寺の近くに鎮座する、飛鳥坐神社。2月に行われるおんだ祭という奇祭が、ちょっと有名な神社。どんな祭りかというと、御田植神事なのですが、種まきつながりで、天狗とおかめのお面をかぶった夫婦役が、公衆の前で〇〇〇して(もちろん所作だけです^^;)、終わったら服の上からティッシュで股間拭いて、そのティッシュは公衆に投げられ、ゲットするとご利益があるとか^o^拭くの紙=福の神だそうです!鳥居をくぐって石段を上がり、拝殿を正面から。奥に本殿、向かいに神楽殿がある。神楽殿の窓の外に山景色。こちらの舞台でおんだ祭が行われるのでしょうか^^拝殿右手の階段を上がっていくと、飛鳥山口神社。左手前が拝殿、右奥が本殿。まつられてるご神体。ここにもマラ石が^▽^以上は稲渕に行く前に立ち寄った所で、以下は帰り道に行った所。上は高松塚古墳、下はキトラ古墳、ともに国の特別史跡。めっちゃ鮮やかな青空に、緑のこんもり♪話が前後しましたが、飛鳥駅~鬼のせっちん~鬼のまないた~亀石~川原寺跡~酒船石~飛鳥坐神社~マラ石~稲渕の棚田~高松塚古墳~キトラ古墳~壺阪山駅と歩いて、近鉄電車で帰ってきた。
2017.09.27
コメント(12)
-

明日香村の不思議な石造物めぐり
つづきせっかくここまで来たので、明日香村の謎多き石造物めぐり。鬼のせっちん(上)、鬼のまないた(下)。7世紀に作られた古墳の石室の一部で、もとは1つの古墳だったが、盛り土がなくなったうえ、バラバラにわかれたもの。この地域には鬼が住み、通行人をだまして食べたという伝説があり、鬼がまないたの上で調理し、せっちんで用を足した、という言い伝えの石^^;亀石。いつ何の目的で作られたのか不明ながら、川原寺の四方の境界を示す標識ではないか、という説がある。川原寺跡(手前)と弘福寺(左奥)。飛鳥寺・薬師寺・大官大寺(大安寺)とともに、飛鳥の四大寺といわれた寺院、跡地は国史跡。当時は非常に栄えたが、のちに廃寺になり、今は弘福寺が継承。酒船石遺跡の酒船石。作られた目的も時期も不明で、酒をしぼる槽、油や薬を作る道具、庭園の施設、といった複数の説がある。遺跡は国史跡、背後の竹林もいい感じ♪マラ石。マラというのは、そうです、あのマラです!昔はまっすぐ立ってたらしいw横から見ると角張った形で、あまりソレっぽくないけど。上から見ると。あ、ソレっぽいかも、でも、直方体+鈴カステラに見えなくもないwつづく
2017.09.25
コメント(10)
-

稲渕の棚田と彼岸花とかかし2
つづき燃えるように赤い彼岸花。奥にそびえ立ってるのは、忍者のジャンボかかし^o^ちがう角度から、右奥にジャンボ忍者を入れて。左手前のかかしは、たぶん老夫婦。おじいちゃんとヘルパーさんに見えなくもないけどw胸ポケットに彼岸花を入れた、マネキンみたいなリアルなかかし。リアルなうえに色白美形(鈴〇その子レベルの白さ!)、ちょっと怖い?でも、青空には映える^^田んぼの黄緑、木の深緑、空の青、かかしの白、彼岸花の赤、色のコントラストが鮮烈でキレイ☆〃7人のこびと。これも・・・かかし?棚田を見下ろすロケーション、いいながめ♪彼岸花は赤い花のほか、白と黄色も咲いてた。白い彼岸花と棚田。色がちがうと雰囲気も変わり、白花には落ちつきと気品を感じる*^^*奥に赤い花が点々と咲き、右端に黄色い花も少し写ってる。黄色い彼岸花。クリーム色ではなく、ハッキリした鮮やかな黄色!!つづく
2017.09.24
コメント(14)
-

稲渕の棚田と彼岸花とかかし1
明日香村の稲渕地区に行ってきた。ここは日本の棚田100選にも、日本の里100選にも選ばれており。見事な棚田、すばらしい山里風景☆〃手前に彼岸花を入れて、棚田をのぞむ。わ~い、絶景\(^o^)/かかしロードをゆく。稲渕では只今、かかしコンテスト実施中で、棚田の農道沿いに、さまざまな手作りのかかしが並ぶ。秋晴れの青空の下で、かかしと彼岸花のコラボ♪定番から変わったものまで、いろんなかかしが立ってた。農作業中のオッチャン・オバチャン。オッチャンの笑顔がカワイイ^▽^なぜか三味線を弾く、へのへのニャンコ。珍しいかかしのつづきは次回へ。つづく
2017.09.22
コメント(9)
-

彼岸花3色inナイト
秋らしくなり、近所で彼岸花が出現。昼間に目星をつけてた所へ、夜に行ってフラッシュ撮影w咲いてる所が田んぼのあぜ道ではなく、普通の住宅街で風情ないから、周囲の風景見える必要ないしw赤い花アップ。わ~い、満開\(^o^)/白い花も。暗闇の黒背景だと、白くても赤くても彼岸花のあやしさ全開で、ちょっといい感じかもw闇夜に紅白コラボ。ダーク感満載、紅白で縁起いいのか悪いのか、どっちやねんな雰囲気w色味のちがう白っぽい花。さっきのが白でこちらは薄黄色なのか、こっちが白でさっきのが薄ピンクなのか?アップで見ると、ゆりの花に少し似てる。車道だけ街灯に照らされて、歩道は真っ暗な所で、歩道から車道に背を向けて撮影してたら、だんだん目が慣れてきて、猫目になった気分で感動♪視界に車道の光が入ってくる限り、なかなか目が暗順応しなくて、ふだん夜歩く時は、何も見えない歩道を歩くか、明るい車道の端っこを歩くか、の2択になる。歩きなれた道なので、見えなくても歩けますが、問題は人とすれちがう時、その人がワンコを連れてる場合。人が来るのは気配でわかるけど、大型犬も近づいてくると息使いでわかるけど、小型犬の存在がまったく把握できず、正面からぶつかるスレスレの所でバッタリ出会ってしまい、おもいっきり吠えられることが^^;きっと私以上にワンコのほうがビックリだと思う(汗)かといって、人が来た=犬の散歩と思って大幅に避けて通って、もしも犬がいなかった場合、何避けとんねん!ということになるので、人の気配を感じたら車道を歩くか、車道に下りるタイミング失ってすれちがう時は、仮に犬がいても踏んだり蹴ったりしないように、スリ足でソロソロ~ッと通過。ちなみに、懐中電灯は足元をピンポイントで照らすにはいいけど、ワンコ発見には役に立たずorz非常に助かるのは、光る首輪や光るリードで散歩されてる方がときどきいて、あれめっちゃイイ!!
2017.09.20
コメント(10)
-

黄檗山萬福寺2
つづき大雄寶殿の左横から左手をのぞむ。灯籠がいっぱい下がった回廊が、これまた美しい☆〃回廊を曲がったとこに見えるのは禅堂、となりに祖師堂・鼓楼とつづき、天王殿に戻る。大雄寶殿の奥に法堂。説法をする場所、左右に西方丈・東方丈がつづく。大雄寶殿の右手(禅堂の反対側)に斉堂。僧侶が食事をする場所、となりに伽藍堂・鐘楼とつづき、やはり天王殿に戻る。斉堂の前に魚型の開パン。時を知らせる法具♪来た道を戻りながら、天王殿と三門の中間左手の門。やっと逆光から解放された。門をくぐると、隠元禅師をまつる開山堂。卍モチーフの柵デザインが中国的^o^屋根をアップで。やはり一般的な日本の寺院建築とは異なる。ちなみに、有名どころでは長崎の国宝・崇福寺も、同じ黄檗宗。萬福寺では建築様式のみならず、建築材も南アジア・東南アジア原産のチーク材が使用されてるとか。壮大で豪華絢爛で見どころ満載、すばらしいお寺さんで感動した*^^*つづく
2017.09.19
コメント(12)
-

黄檗山萬福寺1
つづき宇治市の黄檗は「おうばく」と読み、禅の一宗派である黄檗宗の大本山・萬福寺がある。黄檗宗は中国の明の様式を残した禅で、開祖は隠元禅師、あのインゲン豆を日本に伝えたお方!萬福寺では毎月8日(2月と8月以外)、ほていまつりが開催され、その時は拝観無料になるので、9月8日に行ってきた。これから登場する建造物は、日本の江戸時代中期に中国の明時代末期頃の様式で建てられたもので、すべて国の重要文化財。いかにも中国的な総門。ほていまつり開催日につき、縁日が出てにぎわってた♪屋根の左右にほどこされてるのは、シャチではなくマカラという魔よけの架空生物。総門をくぐってしばらく行くと、立派な三門。ここから三門-天王殿-大雄寶殿-法堂が一直線に配置され、左右に膨大なお堂が建ち並び、境内は広くて壮大。三門のまっすぐ先に天王殿。中国寺院では玄関として見られるお堂。ほてい様などがまつられてる。天王殿のほてい様。めっちゃ金ピカ\(^o^)/☆キラリ天王殿のさらに先に大雄寶殿。萬福寺の本堂に相当するお堂。ご本尊の阿弥陀如来様などがまつられてる。屋根は三門に似ており、左右にマカラ・中央に宝珠・鬼瓦も個性的。大雄寶殿の出入口の前から。赤い丸~い窓が異国的*^^*伽藍はすべて屋根つきの回廊で結ばれてる。大雄寶殿に入ってすぐ、中央にご本尊の阿弥陀如来坐像。右に大きな木魚が写ってますが、木魚は黄檗宗が日本にもたらし、他宗に広まったそうです。つづく
2017.09.17
コメント(9)
-

朝の宇治の神社と仏徳山からの展望
京阪電車の宇治・伏見1dayチケット(大阪から1日乗り放題で900円ポッキリ♪)を使って、チャリは大阪の駅前駐輪場に置いて、京都の宇治と伏見を徒歩散策してきた。まずは宇治神社へ。鳥居の奥に中門、朝日がまぶしい☆〃中門の奥に本殿、ななめから撮影。右の渋い建物が本殿、鎌倉時代前期築、国の重要文化財。次は世界遺産の宇治上神社へ。朝早すぎて、有名な観光地に誰もいない^▽^国宝の拝殿。鎌倉時代前期築、屋根の形が美しい☆〃拝殿の奥に、同じく国宝の本殿。平安時代後期築、なんと日本最古の神社建築!このあとハイキングコースを歩いて、仏徳山(標高131m)の展望台へ。南西のながめ。手前に宇治川が流れ、右端に宇治橋、中央付近に赤い朝霧橋、その奥に平等院が見える。宇治川と朝霧橋と平等院をアップで。かの有名な平等院鳳凰堂、今回は拝観してないけど、仏徳山からよく見えて、ここからなら混雑とは無縁\(^o^)/北西のながめ。奥に北摂の山並みが見える。下山して宇治駅まで戻り、次は黄檗へ。つづく
2017.09.15
コメント(8)
-

マリーナシティ2黒潮市場と夕暮れ
つづき同じ和歌山マリーナシティ内に、新鮮な海産物の集まる黒潮市場。大阪からチャリで来て、すでに閉園時間がせまってるので、ザーッとだけ見てまわる。中に入ると。天井から巨大魚がこんにちわ\(^o^)/マグロ祭と生マグロの文字が目を引く♪反対側に目をやると。やはり天井からマグロ、鯉のぼりみたい^▽^魚屋さんが延々とつづく。ここにも天井からマグロ、なんか見慣れてきたw干物屋さんも。ポルトヨーロッパと黒潮市場のほか、新鮮な果物・野菜の紀ノ国フルーツ村などもあるけど、これにてタイムオーバー^^;日の沈みゆく海をのぞむ。右手に片男波、左奥に淡路島が見える。ここから1番近い駅は海南駅かな?紀三井寺駅でもいいかな?と思いながら、結局は紀三井寺の前を通過して、ターミナル駅の和歌山駅(海南駅より4駅・紀三井寺駅より2駅大阪寄り)から輪行して帰った。
2017.09.13
コメント(14)
-

マリーナシティ1ポルトヨーロッパ
つづき海南市に近い和歌山市南部にあるマリーナシティは、大阪に近い加太から少々はなれてるけど、少し前にマリーナシティ内のポルトヨーロッパが入園無料になったことを知り、せっかくここまで来たので、加太からさらにチャリこいで行ってきた。やっと着いたぁ&さっそく異国情緒満載^o^夏休み明けの9月早々の平日、すいてる時をねらって正解だった♪反対側の広場。ポルトヨーロッパはヨーロッパの街並みを再現したテーマパーク。それではヨーロッパの街並みをご覧ください。この路地裏の感じ、めっちゃステキ!!路地を抜けて、1枚目と2枚目の連結部分に出て、軒下から撮影。思ってた以上に本格的で、大阪の箱作から加太をへて、チャリこいで来たかいあった^^vつづく
2017.09.11
コメント(9)
-

加太淡嶋神社
つづき休暇村から65号線を3kmほど南下して、次は淡嶋神社へ。加太の海岸近くに鎮座する、仁徳天皇の時代に創建された神社。観光客が多すぎず少なすぎず、ちょうどいい感じににぎわってた^o^人が途切れた瞬間に、本殿を正面から。全国にある淡島(淡嶋)神社・粟島(粟嶋)神社の総本宮。人形供養の神社として有名で、3月3日には雛流しの神事が行われる。本殿にズラリと並ぶ、大量の人形・人形・人形・・・∞ちょ、ちょ、ちょっと怖い?^^;上段に人の人形、下段に動物の人形。人以外の人形も並んでるし、本殿以外の所にもいてるし。招き猫の大群=^・^==^・^==^・^=境内のいたる所に、ものすごい数の人形が整然と並び、圧巻!!淡嶋神社の向かいは漁港。周辺の路地は古いお宅が多く、昔ながらの漁村の雰囲気の残る、ステキな所だった♪つづく
2017.09.09
コメント(12)
-

小島から加太休暇村へ
つづきとっとパーク小島の海釣り場。海の向こうに見える陸地は、もちろん淡路島^^引きつづき65号線を走って、大阪府から和歌山県へ。大川トンネルは通らず、徒歩とチャリのみ通行可の旧道に入り、大川峠を越える。峠道は展望良好という事前情報があったんですが、今は緑が生い茂りすぎて、ながめはビミョー^^;ミンミンゼミが鳴き、バッタが跳ね、ハチと蚊が飛びかう、動植物(雑草と虫)が豊かな道だったw65号線に合流してまもなく、休暇村紀州加太に到着。散策路を歩いて、由良要塞の第一砲台跡へ。かつて榴弾砲の砲台があった場所で、砲台は残ってないけど、トンネルの通路と地下の弾薬庫が残ってる。トンネルの中。右下に地下の弾薬庫。地下への階段を下りて、暗い弾薬庫の前でフラッシュ撮影。反対側にも弾薬庫が並ぶ。歴史と廃墟の探検隊になった気分で、めっちゃ楽しめた♪近くの展望台からは、海の絶景が。手前の島は地ノ島、すぐ左奥の小さな島は虎島、その奥は沖ノ島、ここまでは無人島で、これらを総称して友ヶ島。友ヶ島から紀淡海峡をへて、最も右奥に淡路島の由良が見える。つづく
2017.09.07
コメント(7)
-

岬町サイクリング
大阪府下にある市町村のうち、大阪最南端の岬町と阪南市だけ、チャリで走ったことなかった。ってわけで、阪南市の箱作駅までミニ号輪行して、岬町を通って大川峠を越えて、和歌山の加太とマリーナシティまで走ってきた^o^まずは箱作からチャリこいで、せんなん里海公園へ。阪南市と岬町にまたがる公園で、阪南市側はぴちぴちビーチ、岬町側はときめきビーチという海水浴場になってる。ときめきビーチから真西をのぞむ。正面に見えるのは淡路島、ちょうど洲本の中心部のあたりだと思う。水は透きとおってキレイ☆〃北西の神戸方面をのぞむ。左に淡路島北部、右に阪神工業地帯が見える。海辺をあとにして、少しだけチャリこいで、淡輪の船守神社へ。鳥居の奥に見えるのは拝殿。割拝殿のようになっており、ここで参拝。奥に本殿が鎮座する。本殿は豊臣秀頼の命令で造営されたもので、国の重要文化財。淡輪の古い街並みを抜けて、みさき公園の前を通過して、深日からしばらく65号線を走る。※淡輪は「たんのわ」、深日は「ふけ」と読みます。ところで、深日港と淡路島の洲本港を結ぶフェリーが、運行するようになるとかならないとか、何年も前に聞いたんですが、あの話はどうなったのだろう?今か今かと待ち望んでるのですが^^;現在の淡路島へのアクセスは、島の北部に限られてるため、車のない私にとって、広い淡路島の中南部は日帰りでは行きにくい。もしも深日~洲本便が就航(かつてあった航路なので、厳密には復航)したら、洲本・南あわじ日帰りサイクリングに行きたい!話を戻して、65号線をずっと走っていくと、道の駅とっとパーク小島。大阪・和歌山の府県境の600mほど大阪側にある、海釣り公園をかねた道の駅。当初の目的(阪南市と岬町をチャリで走る)は達成し、これにて大阪の全市町村踏破^^vつづく
2017.09.05
コメント(16)
-

清荒神清澄寺
9月になり、入道雲の浮かぶ夏の青空が去り、すがすがしい秋晴れの青空が到来。あまりにも天気がいいので、午前のうちに往復できる所まで、午後からの仕事前にプチサイクリング。宝塚の清荒神参道にやって来た。右下にMTB入れて記念撮影。阪急清荒神駅から清荒神清澄寺まで、長々と参道商店街がつづく。この写真は帰りに撮影、来た時は朝早すぎて、まだ閉まってる店が多かったので^^長い坂道の参道商店街の先に、清荒神清澄寺の山門。平安時代初期に創建されたお寺で、火の神様・かまどの神様として信仰されてる。お寺だけど神様♪境内は広く、山門からずっと奥の正面に本堂があり、それより手前の左手に赤い橋があって。赤い橋の先に鳥居、その奥に見える建物は拝殿、まるで神社^o^拝殿の奥に神社の本殿のような感じに、ご本社と呼ばれる護法堂。このあと山内をぐるっと時計まわりでめぐると、本堂に着いた。石段を下りて、正面に本堂を入れて撮影。左手前に池苑、右手に登廊みたいのがある。池のとなりに建つ資料館横から、池苑越しに本堂をのぞむ。さるすべりが咲き、池には黒っぽい鯉が泳いでた。緑に隠れて、本堂はチラッとしか見えませんが^^;本堂と登廊(?)の間の道を奥へ進み、鉄斎美術館の前を通過すると。突き当たりに龍王滝。今回はチャリだったので、駐輪してた所まで戻って、ピストンで帰宅したけど、清荒神から中山寺奥の院をへて中山寺へ下山するコース、奥の院から中山最高峰をへて山本方面へ下山するコース、中山最高峰から満願寺へ下山するコースなど、縦走ハイキングも可能。
2017.09.03
コメント(10)
-

世界の貯金箱博物館2
つづく昔の日本の貯金箱。下駄や般若の貯金箱まである~^▽^日本の貯金箱、まだつづきます。招き猫の貯金箱=^・^=ジャリン子チエの小鉄や、大阪のオバチャンが好きそうな柄も。ヒョウ柄はベンガル猫なのか、招きヒョウなのかw小鉄のとなりの猫は、京大合格祈願の京大招き猫だそうです^^ほかにも縁起物いろいろ。福がいっぱい来そうな陳列^o^おもしろいと思ったのは、お城とお寺の貯金箱。次は階段を上がって2階へ。再び海外の貯金箱。ドゴール、サダト、ガンジー、めっちゃリアル@o@こんな貯金箱が部屋にあったら、夜ちょっと怖いかもwいろんな動物の貯金箱。博物館は1階と2階で構成され、入館無料にしては見ごたえあって、館内の写真撮影も自由で、かなり楽しめた♪
2017.09.01
コメント(10)
全17件 (17件中 1-17件目)
1