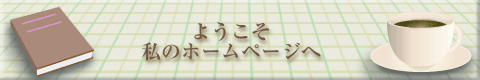[2]-1,2
本論[2]では、[1]で予告したように、事例として(「幻肢痛」を含む)「幻影肢」のメルロ=ポンティによる解釈を取り上げる。さらに、「クオリアの問題圏」から出発してメルロ=ポンティの存在論へと到る道筋を経由した上で、患者に対する介入実践の現在および近未来における困難な課題としての「生体工学的介入の問題圏」へと議論を接続する。
第1章 「要素還元主義」批判あるいは意味の全体論
「患者に対する介入実践の倫理学序論」[1]の議論を経ることによって、われわれは、始原的習慣としての「自己の身体」という次元が、いかにしてそれ自身のあるべき場へと向かっていくのかという根源的な問いに遭遇した。この問いの探究に際して、われわれは、まず、メルロ=ポンティの身体論の骨格を成す「要素還元主義」批判を取り上げる。ここで「要素還元主義」とは、何らかの観察または測定によって定量的に同定可能な「刺激-興奮」という「要素=単位」の特性(要素的属性)を想定し、それらを足し合わせた(すなわち数値化されたそれら特性を一定の演算により計算した)「総和」を一義的に導出できるという図式だといえる。なお、ここでの「要素=単位」は、「入力-出力」という観点から測定=数値化されたニューロンネットワークの機能的単位(「活動電位action potential」すなわち膜電位の変化の単位)と言い換えることができる。ただし、議論のこの導入的段階においては、現時点での脳神経科学研究――あるいは計算機上でニューロンネットワークの機能特性をシミュレートした「ニューラルネットワークモデル」、とくにその「並列分散処理モデル」に依拠するいわゆる「コネクショニズム」――において、どこまで上述の「要素還元主義」が乗り越えられているのか否かといった二次的な問いは括弧に入れている。
「意味論を捨象した情報理論」をベースとした機能主義(としての要素還元主義)は、一般に以下のような問題を抱えている。茂木健一郎(1998,1999)から引用する。
「クオリアとは、「赤の赤らしさ」や、「バイオリンの音の質感」、「薔薇の花の香り」、「水の冷たさ」、「ミルクの味」のような、私たちの感覚を構成する独特の質感のことである。(略)機能主義者は、しばしば「情報」(information)という概念に言及する。ここで言う「情報」とは、意味論を捨象した、シャノン的な意味での情報概念である。シャノンの情報概念は、統計的描像に基づいており、情報の意味論には何ら関与しない。それにも関わらず、シャノン的な統計的猫像に基づく情報概念が、脳の情報処理を解析するために用いられて来た。私たちのある事物の認識は、その事物にだけ選択的に反応する性質(反応選択性、response selectivity)を持つニューロン群の活動(一般には、時空間的なパタ
ーン)によってもたらされるという考え方が典型である。反応選択性は、統計的にしか定義され得ず、個々のニューロン群の活動の時空間的なパターンがいかにして私たちの心の中にある一定のクオリアを生むのかという心脳問題の核心には答えることができない。(略)クオリアが脳の中のニューロンの活動からどのように生まれてくるかということは、デジタル・コンピュータにおけるコーディングと同じ思想に基づいている「反応選択性」(response selectivity)の概念では説明できない。私たちは、認識におけるマッハの原理(Mach's Principle in Perception)から出発しなければならない。クオリアは情報の意味論的側面と深く関連する。クオリアは、シャノン的な情報理論では全く解明することができない。」(茂木健一郎1998,1999.http://www.qualia-manifesto.com/index.j.html)
メルロ=ポンティは、この「刺激-興奮モデル」を批判的に再考する。メルロ=ポンティによれば、そういった刺激-興奮の「総和」以上のものとしての、あるいはそうした「総和」を超越するものとして、われわれにとっての「意味」がある。逆にいえば、そうした「総和」の測定=計算を可能にする「刺激-興奮」という「要素=単位」も、またそうしたものの「要素的属性」も、それ自体としてはわれわれにとって「意味」のあるものではない。このわれわれにとっての「意味」は、上記の「クオリア」とも言いかえることができる。すなわち、もし「刺激-興奮」という何かが、われわれにとって「刺激-興奮」という「図」として現われてくるとするなら、そのときのその「図」に対する「地」としての「状況の意味」、あるいはその「刺激-興奮」がわれわれにとってある固有な「意味」として現われる得るためのいわば「可能性の条件」のレベルを探究の対象とするのである。この「地」としての「状況の意味」、あるいは可能性の条件のレベルは、また「世界内存在」とも呼ばれる。
したがって、例えば「反射は客観的な諸刺激から帰結したものではなく、逆にそれらの諸刺激の方へとふり向き、それらの諸刺激に対して、それらが一つ一つとしては、また物的諸要因としてはもたなかったような意味を、付与するのである。(略)状況の意味にまで己れを開いている限りでの反射と、まだはじめには認識対象を措定しないでわれわれの全体的存在の指向性にとどまっているその限りでの知覚とは、一つの前客観的視界の諸様相であって、この視界こそ、われわれが世界内存在と呼んでいるところのものである。(略)してみると、諸刺激からは相対的に独立して、われわれの<世界>の或る種の持続性というものがあるわけで、これが世界内存在を単なる反射の総和として扱うことを禁じているのだ。また同じく、われわれの意志的な思考とは相対的に独立して、実存衝動の或る種のエネルギーというものがあるわけで、これがまた世界内存在を一つの意識的な作用として扱うことを禁じているのである。世界内存在とは前客観的な視界であればこそ、あらゆる第三者的過程、延長体res extensa のあらゆる様相からも、また同じくあらゆる思考作用cogitatio 、あらゆる第一人称的認識からも区別され得るのであり、そうであればこそそれは、<心的なもの>と<生理的なもの>との接合を実現することもできるわけであろう。」(メルロ=ポンティ 1945=1967.pp.94-95.訳 第1巻pp.143-144. 原文における強調を斜体文字化した。)
さらに、メルロ=ポンティは、「基本的障害」または「質的な変容」(行動の新しい<意味>)としての「病的変化」について以下のように述べている。
「基本的障害は(略)知覚され・理解され・演じられた全体を、「図」という形で、無記的に見える「地」のうえに鮮明に浮かび上らすことの不能と定義されうるであろう。病的変化は、より未分化でより非組織的な、より全体的でより無定形な行動にむかう方向に起こるのである。(略)疾患は直接に行動の内容にかかわるのではなく、その<構造>にかかわるということ、したがってそれは観察されるような何ものかではなくて、むしろ了解される何ものかだ、ということが明らかになる。患者の動作は、正常者の動作から単なる部分の引き算によって演繹されるのではなくて、質的な変容をあらわすのであり、そして或る行為が選択的に障害をうけるというのも、彼にとってはもはや不可能な態度が要求されているかどうかによるのである。したがって新しい種類の分析が、ここではっきりしてくる。それはもはや諸要素を切りはなすことにではなく、全体の態度と、それに内在する法則とを了解するところに成りたつのである。(略)病的な活動(略)は多くの症候群に共通な、行動の新しい<意味>なのである。」 (メルロ=ポンティ 1942=2006. 訳 pp.106-107. 原文における強調を斜体文字化した。)
すなわち、メルロ=ポンティは、前客観的(潜在的)レベルにおける「意味の全体論」を主題化する。この「意味の全体論」のパラダイムは、「意味論を捨象した情報理論」を「クオリアの解明」には無力であると位置づける先の引用文における「認識におけるマッハの原理 Mach's Principle in Perception」が共有するものである。この「認識におけるマッハの原理」に関して、茂木健一郎は、「認識において、あるニューロンの発火が果たす役割は、そのニューロンと同じ瞬間に発火している他の全てのニューロンとの関係によって、またそれによってのみ決定される。ニューロンは、他のニューロンとの関係においてのみある役割を持つのであって、単独で存在するニューロンには意味がない。」(茂木健一郎1998,1999.http://www.qualia-manifesto.com/mach-p.html)と説明している。
上記引用における「多くの症候群に共通な、行動の<意味>」は、メルロ=ポンティによって「行動の構造」とも呼ばれる。ここで「病的変化」「疾患」「病的な活動」と記述された「多くの症候群に共通な、行動の<意味>」としての「行動の構造」を分析する際に、『知覚の現象学』のメルロ=ポンティが取り上げるのが、「幻影肢」という固有な「経験」あるいは「現象」である。以後本発表では、メルロ=ポンティの身体論を検討する上での事例として、「幻影肢」のメルロ=ポンティによる記述を取り上げる。
第2章 固有な「経験」あるいは「現象」としての幻影肢
事故や戦闘で酷く負傷したり、あるいは腕の切断手術を施されたりした人において、その腕がかつてあった場所に、例えば腕を炸裂させたその砲弾の破片をしばしば感じることがある。幻影肢とは、このように切断された四肢を自己の身体経験のなかで保持し続ける症例――より正確にはその人にとって固有な経験としての現象――である。さらに、その炸裂の衝撃の感覚といった「痛み」を経験する場合、幻肢痛と呼ばれる。幻影肢がつねに幻肢痛を伴うというわけではないが、しばしば伴うということがある。この幻影肢という「経験」あるいは「現象」は、現在においてもそのメカニズムや原因が十分に解明されているとはいえない。しかし、これまでの記述からも了解されるであろうが、その「メカニズム(機能的説明)」や「原因」の解明は、固有な「経験」あるいは「現象」としての幻影肢へとわれわれをみちびくわけではない。というよりむしろ、「メカニズム(機能的説明)」や「原因」から「経験」あるいは「現象」への道は途絶えていると考えるのが通例であろう。例えば、中枢神経系の可塑性変化(再構築)に注目するアメリカのUCSDサンディエゴ神経科学研究所のV.S.ラマチャンドランは、幻影肢について、以下のように述べている。
「幻肢体験は、少なくても二つの情報源から出る信号に依存している。一つは地図の再配置である――顔面や上腕からの感覚入力が「手」に対応する脳領域を活性化するという、あの話だ。第二に、運動指令の中枢が失われた腕に信号を送るたびに、身体イメージをもつ頭頂葉にも指令に関する情報が送られる。この二つの情報が収束して、動的でいきいきとした幻肢のイメージがどんなときにもできあがる――そのイメージは、腕が「動く」たびに、たえず更新される。」(ラマチャンドラン 1999.訳 p.80.)
そしてこの二つの情報の収束という「機能的メカニズム」が、この私の、またはある特定の個人の固有な「経験」あるいは「現象」へと到達できないことは、ラマチャンドラン自身の次の記述からも認めざるを得ないだろう。
「NIH(米国立衛生研究所)では、眼が見えない人の視覚皮質を磁気で刺激して、視覚路が衰退あるいは再編成をしているかどうかをみる研究が行われているし、私もここUCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)でいくつかの実験を開始している。しかし私の知るかぎりでは、人がその人にとってまったく新しいクオリア、すなわち主観的感覚を感じるかどうかという特定の問題が実験的に探究されたことはまだない。」(ラマチャンドラン 2003. 第12章 原注4)
言うまでもないが、「探究されたことはまだない」というよりむしろ、そういった「実験的探究」は原理的に(再現)不可能である。その人にとっての「クオリア」は、つねに同時に、「その人にとってまったく新しいクオリア、すなわち主観的感覚」であるほかない。すなわち、そうした探究においては、「同一なものの反復可能性」が原理的に成立不可能であるだろう。言い換えれば、そうした探究は、たとえあり得たとしても、つねに先送りされる(不在の)「再現」を目指す終わり無き(不可能な)プロセスであり続ける。この点に関して、意識の「難題 hard problem」としての「クオリア問題」を論じたチャーマーズは、「人はたとえば「学習は脳から生じてくる」とは言わない傾向にあり、仮にそう言ったとしても、それは時間的経過を表わす<生じてくる>ということになるだろう。それよりもむしろ、人はもっと当然のこととして、学習は脳内の過程であると言う。心は脳から生じてこなければならないという事実こそが、まだその先に何かが起こっているということを示している。」(チャーマーズ 1996. 訳 p.166. 強調の斜体文字化は引用者による。)と述べている。
この「まだその先に何かが起こっている」という論点に関して、茂木健一郎は、「方法論的に重要なのは、クオリアの質感そのもの(例えば、「赤」という色の質感そのもの)が、クオリアを感じる枠組みである主観性の構造そのものに依存するかどうかを明らかにすることである」(茂木1998,1999.http://www.qualia-manifesto.com/manifesto.j.html)という課題を提起している。この「クオリアを感じる枠組みである主観性の構造」(という仮想的存在)の探究という問題に関して、ラマチャンドランは、「心理学のある分野では、実行あるいはコントロールのプロセスが一般に脳の前頭前部や前頭部に局在すると考えられている。私は、クオリアが何かのために書き込まれている、その「何か」とは、「もの」ではなくてプロセスではないか、すなわち前部帯状回を含む、辺縁系と結びついた実行プロセスではないかという意見をもっている。このプロセスは知覚クオリアを特定の情動や目的と結びつけ、あなたが選択をすることを可能にする――これは伝統的に自己の役割と考えられてきたことそのものである。(略)知覚や動機に関与している脳領域が、たとえば運動出力の組み立てに関与している領域などの他の領域の活動に影響をおよぼす、そのプロセスなのだ。この観点に立つと、書き込みは、それらの領域が辺縁系と適切に相互作用をできるようにするために、クオリアを用意しているのだと言える。クオリアが書き込まれる必要があるのは、ギャップがあると実行系の働きがじゃまされて、適切な反応をする効率や能力が減少するからだと考えられる。(略)では辺縁系のどこにコントロールのプロセスがあるのだろうか? 扁桃体が情動に中心的な働きをもち、前部帯状回が実行の役割をもっているらしいことを考慮すると、それは扁桃体と前部帯状回からなるシステムではないかと考えられる。(略)前部帯状回や辺縁系の組織は、髄板内核(視床にあるニューロン集団)からの投射も受けており、その髄板内核は脳幹の複数の核によって駆動されている。(略)この脳幹と視床の回路が、意識やクオリアにおいて重要な役割をはたしているのは確かだ。しかし単にクオリアを「支えている」だけなのか(支えていると言えば、肝臓や心臓だって支えている)、それともクオリアや意識を組み込んでいる回路の構成成分なのかは、まだわかっていない。」(ラマチャンドラン 1999. 訳 pp.315-317. 強調の斜体文字化は引用者による。)と述べている。
すなわち、ラマチャンドランによれば、少なくても現状の脳神経科学において、先の茂木の問いに対する回答は存在していない。言い換えれば、「特別な神経回路を使って感覚表象や運動表象のメタ表象を生みだす能力――言語を促進し、また言語によって促進される能力――が、本格的なクオリアの進化にも自己意識の進化にも不可欠だったのかもしれません。先にも述べたとおり、クオリアを経験する自己をともなわない自由な立場のクオリアをもつことは不可能ですし、いっさいの感情や感覚を欠く孤立化した自己をもつことも不可能です。」(ラマチャンドラン 2003. 訳 p.152. 強調の斜体文字化は引用者による。)とされるように、何らかの「主観性の構造」が「クオリアの質感そのもの」にとっての必要条件であることが推定されるとしても、その仮説的な構造それ自身が、「クオリアの質感そのもの」とのギャップを埋める――すなわち「心が脳から<生じてくる>」ための――<構成的条件>でもあるのかどうかは、依然として謎にとどまる。
ここで、メルロ=ポンティにしたがって、探究の方向を「実践的領野を保持しようとする世界内存在の一般的運動」へと向け換えてみよう。この一般的運動の一つの様態としての「欠損の拒否」について、メルロ=ポンティは次のように語っている。
「われわれにあって手足の切断や欠損を認めまいとしているところのものは、物的ならびに相互人間的な或る世界のなかに参加している<我れ>であって、これが手足の欠損や切断にもめげず今までと同じく自分の世界へと向かい続けているのであり、その限りで欠損や切断を断じて認めまいとしているわけだ。欠損の拒否とは、一つの世界へのわれわれの内属の裏面でしかない。つまり、われわれをおのれの仕事、おのれの関心事、おのれの状況、おのれのなれ親しんだ地平へと投げ入れている自然的な運動に対立するようなものは認めまいとする、暗々裡の否認にほかならないのである。腕の幻影肢をもつとは、その腕だけに可能な一切の諸行動に今までどおり開かれてあろうとすることであり、切断以前にもっていた実践的領野をいまもなお保持しようとすることだ。」(メルロ=ポンティ 1945=1967.pp.97.訳 第1巻 pp.147.強調の斜体文字化は引用者による。)
したがって、探究の焦点は、「幻影肢」という事象を「腕の幻影肢をもつ」という固有な「経験」あるいは「現象」として可能にする基盤である「身体図式」のレベルへと移行することになる。言い換えれば、「身体図式の一つの様態である幻影肢は、世界内存在の一般的運動によって了解される。」(メルロ=ポンティ 1945=1967.p.117.訳 第1巻 p.176.)
メルロ=ポンティによれば、「習慣的な運動感覚の構成法則」としての「身体図式」とは、以下のことを意味する。すなわち、「幻影肢の現象を解明しようとしてこれを患者の身体図式と結びつけようとする場合、大脳痕跡や再生感覚による古典的説明に何者かを付加するためには、身体図式が単に習慣的な運動感覚の残滓たることをやめて、それの構成法則となるのでなければならない。もしも人がこの新しい言葉を導入する必要を感じたとすれば、それは身体の空間的・時間的統一性、相互感覚的統一性、あるいは感覚=運動的統一性がいわば正当な権利を持っていること、この統一性は単にわれわれの経験の過程で実際に偶然連合した諸内容だけに限定されはしないこと、この統一性は或る意味ではそれらに先立ち、まさにそれらの連合を可能にするものであること――こうしたことを表現するためであった。(略)身体図式はダイナミックなものだと心理学者はしばしば語るけれども、この言葉をその正確な意味で捉えてみると、それは私の身体が現勢的または可能的な或る任務に向かってとる姿勢として私に現れる、という意味である。そして実際、私の身体のもつ空間性は、外面的諸対象のもつ空間性や<空間的諸感覚>と同じような、一つの位置の空間性ではなくて、一つの状況の空間性なのである。」(メルロ=ポンティ 1945=1967.pp.115-116.訳 第1巻 pp.174-175. 原文における強調を斜体文字化した。)
したがって、「身体図式」とは、「私の身体が現勢的または可能的な或る任務に向かってとる姿勢として私に現れる」という事態(経験)そのものを可能にしている、私の身体経験の可能性の条件(構成的条件)である。ここで「現勢的または可能的な或る任務」という場合の「可能的」というのは、また「潜在的」ともいえるわけで、「身体図式」とは、あらゆる可能的状況、そしてそのつど現実化する状況に対して、臨機応変に(潜在的に)身構えて――すなわち「私の身体」として――反応できるという意味において、あらゆる可能的な刺激に対して反応できるような<経験のシステム>だといえる。
そして、まさにこの意味における身体図式という経験のシステムにとって、さらにそのシステムの<生成母胎>となるのが――したがってそれ自体は(例えば任意の身体イメージの生産機能を持つ一定のニューロンネットワークといった)システムではない――始原的習慣あるいは「世界内存在の一般的運動」としての<自己の身体>なのである。
第3章 始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>の経験へ
これ以降、始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>をテーマ化する。まず、われわれは、最も基礎的なレベルにおける導入として、以下の諸テーゼを提示する。すなわち、
[1] 端的にそれ自体存在すると同時に、世界あるいは状況のただなかで私の意識が出会う他者という<両義的な存在>に対する介入実践とは、身体図式としての経験のシステムのさらなる<生成母胎>すなわち始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>の経験であり、それは「この私の身体」と「他者の身体」との相互交錯的反復の経験として現象する。
[2] 始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>と「この私の意識」は、[1]の相互交錯的反復の経験における同時的かつ相互的な関係性のうちにある。
[3] 始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>と「この私の意識」は、これら両者を結び付ける何らかの因果性のうちには位置しない。すなわち、始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>が、(原因としての)「この私の意識」の超越論的構成物(結果)ではないのと同様に、「この私の意識」は、(原因としての)始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>の因果的効果(結果)ではない。言い換えれば、始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>は、「この私の意識」の因果的成立条件という位置づけを持たない。
[4] 始原的習慣あるいは世界内存在の一般的運動としての<自己の身体>は、そのシステムまたは機能的メカニズムが分析可能な何らかの「主観的構造」とは異なったレベルに位置づけられる。もし何らかの「主観的構造」の機能的メカニズムが完全に分析され得たとしても、そうした任意の「主観的構造」は、可能的経験の条件としての<経験のシステム>であるとしても、この「主観的構造」がそれ自体として「クオリアの質感そのもの」という固有な経験あるいは現象の構成的条件でもあるのかという問いは、どこまでも決定不可能なものにとどまる。
Copyright(C) Nagasawa Mamoru All Rights Reserved.
© Rakuten Group, Inc.