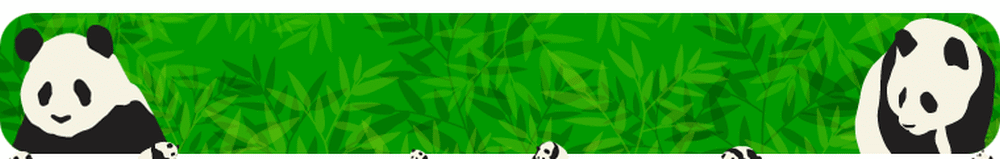秘密小説『告白』1~3
秘密 「告白」
「たすけて、たすけて、たすけて・・・」
悲痛な叫びが聞こえる。
真夜中の残業で薪の寝言を聞いた青木は心配になって、
薪に近づいた。
第九に二人きり残って、仕事をしていたのだが、いつの間にか
薪はデスクに座ったまま居眠りをしてしまい、自分の腕を枕にした
うつ伏せの状態で眠っていた。
薪はまた悪い夢でも見たのか涙でスーツの袖を濡らしている。
この人はいったいどんな夢を見ているのだろう?
親友を殺したことをいつまでも後悔して、苦しんで、
夢の中で泣いている。
俺には理解できないと青木は思った。
「薪さん、薪さん、起きてください。」
青木が肩を掴んで揺らすと、薪はハッと目が覚めて顔を上げた。
「うなされてましたよ。かわいそうに。」
青木はそう言ってハンカチを薪に差し出した。
「かわいそう?」
薪は大きな濡れた瞳を見開いて信じられないものでも見るように
青木を見た。
そして、ゴシゴシと自分のスーツの袖で目をこすって
涙を拭いてしまった。
また一言多かった。と青木は思った。
プライドの高い人にかわいそうとは言ってはいけない言葉だった。
たとえ、見るに見かね聞くに堪えない状態でも同情する言葉は
不適切だった。
薪は自分の醜態を取り繕うように青木を無視して、
デスクに広げたままの書類を手に取り、読み始めた。
青木は差し出したハンカチを黙って自分のポケットに
しまうしかなかった。
「データの修復は終わったのか?」
薪は青木と目線を合わせないで聞いてきた。
「後もう少しです。」
「さっさと仕事しろ。」
薪は冷たく言い放った。
青木はしぶしぶMRIコンピューターの前に戻り、可愛くないなぁ
と思った。顔は可愛いのに・・・
薪は極度のストレスから睡眠障害に陥っていたのだが、
夜眠れないため、やたらと昼寝をする。
無防備にソファーに横たわり、聖書を抱えて幸せそうに眠る薪を
青木はいつも眺めていた。
夢の中で鈴木に会って、あんな第九の誰にも見せない安らかな
顔をするのかと思うと、時折、腹立たしく感じることさえあった。
結局は寝顔が最初、幸せそうであればあるほど、
最後は泣くはめになるのだが・・・
寝ながらポロポロ涙を流し、「鈴木」とつぶやく薪に青木は
やるせなさを感じていたのだった。
また、寝起きの悪い薪が寝ぼけて鈴木と間違え、青木に
しがみついてきたこともあった。うるうるのすがるような瞳で
「もう離さない。」
なんて言われたら、男として我慢できない。
数日前にも薪の色香に迷わされて押し倒す寸前までいったが、
岡部が飛んで来て、二人を引きはがした。
岡部は常に見張っていて、薪を守るように何かあるといつも
すっ飛んで来るのだが、今日はその岡部がいない。
真夜中の第九という密室に青木は薪と二人きりだった。
時計が1時をさした頃、青木の隣に薪がスッとやって来て、
体が触れ合うか触れ合わないかくらいの至近距離に立ち、
真剣なまなざしで青木の顔を覗き込んで聞いてきた。
「寝ている間に何か喋ったか?」
青木は蛇に睨まれた蛙のように答えにつまったが、
すぐに気をとり直してこう言った。
「薪さん。泉鏡花の『外科室』ってご存知ですか?薪さんはまるで
うわ言を言うかもしれないからといって、麻酔なしで胸の手術を
うける伯爵夫人みたいですよ。想いが強ければ強いほど無意識
のうちに言葉を発してしまうのは当たり前のことなのに、
薪さんはどうしてそれを秘密にするんですか?」
薪は一瞬、眉をつりあげて、何か言い返そうとしたが、青木は
「つらい思いをしてまで、守る秘密なんかどこにもないんです。
俺は知ってます。薪さんが鈴木さんを好きだってことを!!」
薪は驚いて、青木の頬を平手打ちした。
薪は自分がたたいたのに、まるでたたかれたような顔をしていた。
薪は蒼ざめて泣きそうだった。青木は薪の腕をつかんでひっぱり、
体を引き寄せて抱きしめた。
「薪さん。もっと現実を見てください。鈴木さんはもうこの世に
いないんです。死んだ人の事をくよくよずっと考えていても何も
はじまらないですよ。それなのに薪さんは何年も後悔し続けて
誰にも言えず、独りで苦しんで聖書を抱えて眠っている。
教会へ行っても祈るばかりで懺悔しなければあなたの罪は一生
消えない。一生独りで罪を背負って生きていくつもりですか?
あなたの罪を俺にわけてください。
あなたの苦しみを俺にください。
あなたの声を俺にください。
俺があなたを幸せにしてみせますから。」
青木は薪にくちづけした。
そして、瞳からあふれて頬を伝う涙をそっと人差し指でぬぐいとり、
長い濡れたまつげに接吻した。
「幸せにします。」
青木は愛を誓ったのだった。薪はただ黙って泣いていた。
青木がもう一度、薪を強く抱きしめると、薪は素直に年下の男の
胸に顔をうずめて、子供のようにすすり泣いた。
青木はしばらく薪の頭を優しく撫でていたが、ゆっくりとこう言った。
「薪さん、もう泣かないでください。これからは俺がずっとそばに
いますから。あなたの笑顔をみせてください。
俺はあなたの笑顔が欲しい。」
薪は潤んだ瞳でまっすぐに青木を見つめて、やがて、
はにかんだように微笑んだ。
「青木。」
「薪さん、あなたに泣き顔は似合わない。あなたは笑顔が素敵
な人だ。やっと俺に笑顔を見せてくれましたね。」
青木は写真でしか見たことのない薪の笑顔を自分のものにできて
うれしかった。照れたように笑う薪の顔を青木はいつまでも
見つめていた。もう言葉は何もいらない。
至福の時が二人を包んでいた。
(完)
秘密 「告白」 2
「青木、そろそろ別れないか?」
突然の薪の言葉に青木は我が耳を疑った。
「な、何故ですか?なんでそんなこと言うんですか?」
「このままズルズル付き合っていたってしょうがないだろう。」
青木はショックだった。あの感動的な告白をしてからたった1ヵ月
で別れ話を切り出されるとは思ってもみなかったのだ。
この1ヵ月間、青木は毎日、薪のマンションに通い、夕飯を食べ、
テレビを見て、風呂に入り、寝て、翌朝、一緒に出勤するといった
生活を送っていた。
何がいけなかったんだろう・・・青木は必死に考えた。
幸せにしますと告白したのはいいけれど、デートはいつもマンション
で夕飯を食べて寝るだけで、仕事が忙しくて休みが取れないから
という理由で映画にも遊園地にも行ってなかった。付き合ってすぐ
半同棲生活というのもやはりまずかったか・・・でも、薪さんが夜
眠れなくて俺が添い寝してあげたら眠れたから・・・それから毎晩
泊まるようになって、今日もいつものようにコンビニで買ってきた
弁当を二人で食べてテレビを見ていたのに・・・あ、そうだ。
テレビばっかり観てて会話がなかった・・・薪さんああ見えて
寂しがりやさんだから、拗ねちゃったのかな。うん。きっとそうだ。
青木はポジティブな性格だった。
「薪さん、何怒ってるんですか?」
青木は機嫌をとるように薪の肩に腕をまわして作り笑いを浮かべて
聞いた。しかし、薪は青木の質問に答えようとはせず、黙って腕を
ふりほどいた。そしてしばらくうつむいていたが、やがてこう言った。
「帰ってくれ。青木。もうここには来ないで欲しい。」
「薪さん、なんで、なんでなんですか?」
「見たくないから・・・青木の顔。」
再び青木はものすごいショックを受けた。
室長は初恋の人が忘れられなくて恋人をつくらないでいる
と第九の誰かが言っていたことを青木は思い出した。
また、薪は恋人はつくらないが、毎夜、ゆきずりの男とベッドを
ともにしているとか総監や長嶺と寝ているとかあらぬ噂が絶えない
人でもあった。最初、青木も半信半疑だったのだが、1ヶ月前
はじめて薪のマンションに行った時、ベッドに押し倒したら、
拒絶されて、誰とでも寝るという噂が嘘だと分かり、安心した。
だが、一方で鈴木に対する想いがそれだけ強いのかと思うと
せつなかった。
青木はこの1ヶ月間キス以上のことを薪にしていない。
相手がその気になるまで待つつもりだった。
大切にしていたのに・・・
夜眠れないとか怖い夢を見るとか言うから、毎晩、添い寝して
慰めてあげたのに・・・
初めて泊まった日も貝沼の夢を見て夜中に悲鳴をあげたから、
薪さんの震える体を抱きしめて朝までずっと一緒に寝てあげた。
薪さんはまだ貝沼の呪縛から逃れられないでいる。
人を殺した罪悪感が自らに無意識のうちに罰を与えているのか。
それとも好きだった人がそんなに忘れられないのか。
薪さんはいつも遠い目をしている。
俺のことをじっと見つめているかと思えば、目が合うと急に目を
そらして、体裁の悪そうな顔をする。
きっと鈴木さんに似ているから、俺に鈴木さんの面影を重ねて
見ているのに違いない。いや、顔が似ているから一緒にいるのが
つらくなったのかもしれない。 俺は鈴木さんのことが忘れられる
まで待とうと思った。毎日好きだよってキスするだけで、
薪さんの嫌がることは何一つしなかったのに・・・
そういえば、まだ一度も薪さんに好きって言ってもらってない。
青木の怒りが爆発した。
「薪さんは俺のことを利用していただけなんだ。そうなんでしょう?」
「そうだ。」
薪のそっけない答えに青木はついカッとなって薪の肩をつかんで
押し倒した。
「じゃあ、見なければ良い。」
青木はそう言うと自分のネクタイをほどいて薪の瞳をふさいだ。
「青木。何するんだ。やめろ。」
「目隠しですよ。薪さん、こうゆうの好きでしょう?」
「ばか。」
薪は手を振り上げたが、青木がそれをつかんで床に押さえつけた。
青木は荒々しく薪に口づけした。強引に舌を入れ、舌を絡ませて
薪の唇をむさぼるように味わった。薪は必死に抵抗したが、所詮、
力でかなうわけもなく、なすがままにされた。
息苦しいほどの長いキスの後、青木は薪のワイシャツに手をかけ、
ボタンを外そうとした。
「何をする。やめろ。青木、頼むから、やめてくれ。」
薪は泣きそうな顔で懇願した。その時、薪の顔に冷たいものが
ポタポタと落ちた。それは青木の涙だった。
「薪さん、俺は鈴木さんの代わりでも良いって思ってました。
でも、もう限界です・・・」
「青木、泣いているのか?どうしておまえが泣くんだ?」
「薪さんに拒絶されて、鈴木さんの代わりにもなれない。
もう、どうしたらいいのか・・・」
「青木、何を言っている?意味がよくわからないな。」
薪は青木が手を放したすきに目隠しをはずして、ゆっくりと
起き上がり、冷静に青木の目を見つめて、こう言った。
「鈴木に対する好きはおまえに対する好きとは違うんだ。鈴木は
親友で恋人じゃない。」
「薪さん。」
「僕は鈴木を殺したことをずっと後悔していた。だから、悪夢を毎晩
見るのだと思う。これ以上青木に迷惑かけたくないんだ。僕は最近
甘えてばかりいたから、このままじゃ青木なしで生きられなくなる
んじゃないかと思って・・・今までずっと一人で生きてきたから・・・
生まれて初めて人を好きになって、ちょっと怖くなったんだ。」
「薪さん、今まで誰かと付き合ったことないんですか?」
「ない。」
「一度も?じゃあ、女性とも男性とも経験がないんですか?」
「あたりまえだ。」
「え、まさか、ひょっとして、キスも俺が初めてだったりして・・・」
「はじめてだ。」
薪は顔を赤らめて言った。青木は嬉しくなって薪を抱き寄せた。
そして、この年上の可愛らしい上司を一生大切にしようと思った。
「俺、別れませんから。もう、薪さんに何か言われても絶対に別れ
ないです。一生そばにいます。」
「うん。」
薪は照れたようにうなづいた。青木は薪の手を握りしめて言った。
「俺、今、すごく幸せです。」
「僕も・・・」
言葉少ない恋人は大きな瞳を輝かせて幸せそうに微笑んだ。
青木は薪のことを天界から舞い降りた天使のようだと思った。
その純粋無垢な天使は幸せを青木に運んでくれた。
幸せとは愛する人のそばにいて愛する人が幸せになること。
青木は天使のような微笑を浮かべる薪の手をいつまでも握りしめて
いた。夜が更けて、朝が来るまで二人はずっと手をつないでいた。
その日、薪は怖い夢を見なかった。
青木が呪縛から解き放ってくれたのだ。
闇の底に沈んでいた堕天使は温かい光に救われて、翼を広げて
飛び立ち、陽のあたる場所へとたどり着いたのだった。
(完)
秘密 「告白」 3
「まずい。」
僕は青木の作った手料理を一口食べただけで箸をおいた。
「薪さん、そんなこと言わずに食べてくださいよ。」
テーブルの上には青木が作った野菜いためらしきものが置かれて
いた。どうやったらこんなに真っ黒にこがすんだか・・・
あきれてものも言えない。しかも、失敗したにもかかわらず、
青木は平然とそれを食べ、僕にも食べることを強要するのだ。
「見た目は悪いけど、美味しいですよ。ほら、この辺ならこげて
ないから、もう一口食べてみてくださいよ。」
「いらない。」
僕は青木が箸でつまんで僕の口元に持ってきた肉を手ではらった。
肉はテーブルの上に落ちてしまったが、僕は肉を拾おうともせずに
横を向いた。青木は慌てて肉を拾い、ティッシュでテーブルを拭い
たが、テーブルクロスには油染みが残ってしまった。青木の作る
料理はいつも油が多すぎる。僕は買ってきたものを食べてれば良い
と言っているのに、青木は栄養のバランスを考えて自炊したほうが
良いとか言って、黒コゲのまずい料理を作りだした。青木が僕の
マンションに毎日やって来るようになって2ヶ月が過ぎた。青木は
最初は大人しくしていたのだが、だんだんまるで世話女房のように
あれこれと世話をやきだしてからはうっとうしくてしょうがない。
やはり1ヶ月前に別れておけば良かった。僕はずるずるとあいつの
手の中に落ちて行く自分が嫌いだった。
「薪さん、明日のクリスマスイヴは何が食べたいですか?薪さんの
ために一生懸命作りますよ。」
「青木、頼むからもう何も作らないでくれ。」
「じゃあ、久しぶりに食べに行きますか?フレンチとイタリアン
どちらが良いですか?」
「どっちでもいい。お前の手料理以外なら。」
「はいはい。わかりました。あ、そうそう、約束、覚えてますか?
クリスマスプレゼントは薪さんの処女を俺に・・・」
「ばか。」
僕は耳まで顔が赤くなった。青木が勝手に言ってるだけで僕は
承諾した覚えはない。こんな奴の側にいると馬鹿がうつりそうだ。
「風呂に入ってくる。夕食はもういらない。そのまずい料理は
捨てておけ。」
僕は青木にそう言うと席を立った。
風呂に入ると鏡に映る自分の姿が嫌いだった。痩せすぎて鎖骨が
くっきりと浮き出た身体。そして、昨日の名残の赤い小さな痕が
花びらを散らしたようにいくつもついている。青木はこの身体が
自分の所有物である証を毎晩つけたがる。青木に刻み込まれた
刻印は白い肌に赤く浮かび上がる薔薇の花びらのようだった。
こんなんじゃうかつに外で着替えられない。仕事柄、泊り込みで
徹夜することが多かったのだが、青木と付き合うようになってから
第九に寝泊りしなくなった。いや、できなくなった。キスマークを
つけるなと言っても、青木はちっとも言うことを聞かない。あんな
年下の自分の部下になすがままにされている自分が嫌いだった。
青木は水と同じだ。無味無臭。何の価値もない。人畜無害な顔を
して僕の身体を支配しようとしている。人間は水なしでは生きられ
ないとわかっていたから、僕は青木と別れようとしたんだ。それな
のに青木はそんなことおかまいなしで僕の心に入ってくる。砂漠の
ように乾いた僕の心に水を浸み込ませて、大地に雨を降らせるが
ごとく愛情を降り注ぎ、僕の身体に潤いを与える。僕は青木に満た
されて、青木に侵食される。もう、青木なしでは生きていけない。
明日の晩、僕は青木に食われるのだろうか・・・
「薪さん、電話です。」
その時突然風呂の扉が開いて青木が携帯を持ってやってきた。
「俺が出るわけにいきませんから、薪さん、早く出てください。」
僕は青木が差し出した携帯を呆然と受け取り、電話に出た。
「もしもし・・・」
岡部だった。
「薪さん、犯人らしき人物が特定されました。明日の朝一番に
逮捕状をとってください。」
「ああ、わかった。」
「明日は大捕り物になりますよ。」
岡部はクリスマスイブが仕事でつぶれるのを嬉しく思っているかの
ような声だった。
僕は手短に電話を切ると青木に携帯を渡してこう言った。
「明日の予定はキャンセルだ。」
風呂から出てすぐ寝室に入った。明日は早いからもう寝ると言って
ベッドに横になった。明日はまた徹夜になるかもしれない。急な
仕事が入って先延ばしにしていた青木との関係をもうしばらく延長
できることに僕はほっとした。だが、クリスマスを二人で祝う楽しみ
を失って、なんだか寂しい気もした。そういえば、ここ数年、毎年
クリスマスは仕事だった。岡部はなぜか毎年クリスマスが近づくと
異様に仕事熱心になり、必ず第九にひきこもる。今までは僕も一人
だったから、さほど気にせず岡部の仕事に付き合っていたのだが、
今年は違った。毎日、岡部を一人残して青木の待つマンションへ
帰宅していた。こんなこと初めてだ。仕事よりも青木を優先させる
なんて・・・僕はどうかしている。
「薪さん、もう寝ちゃいましたか?」
パジャマに着替えた青木が僕のセミダブルのベッドにもぐり込んで
聞いてきた。
僕がわざと答えずに寝たふりをしていると、青木は後ろから僕を
抱きすくめ、僕のパジャマに手を入れてきた。
「うん、やめ・・・」
「反応良いですね。やっぱり起きてました?」
青木が耳元でささやく、そのまま耳たぶを甘噛みされ、ねっとりと
舐められた。
「あ、やめろ・・・」
僕が首をよじって青木を見ると、青木は僕の唇に口づけした。とろ
けるようなディープキスに僕はまた抵抗することを忘れてしまった。
青木の手が僕の身体を狂わせる。舌と舌を絡め合わせ、快感を
むさぼるように何度も唇を合わせた。
「口でしてあげましょうか?」
青木が意地悪く僕に聞いてきた。青木はいつもベッドでは意地悪
になる。僕は少し照れたようなしぐさで目を閉じて青木が服を脱が
せるのを待っていた。僕はいつも何もしない。青木が与えてくれる
快楽を味わうだけ。快楽は甘い蜜のように僕を溶かし、トロトロに
溶けた僕を青木は美味しそうに舐め上げ味わうのだ。
「薪さん、もう1本指入れていいですか?2本じゃキツイかもしれ
ないけど、慣らさないと俺のが入らない。」
「あ、ダメ、やだ、いっ、痛いっ。」
「薪さん、ローションって知ってます?これつけると滑りがよくなるん
ですよ。明日のために買ってきたけど、今日、使っちゃいますね。」
「あ、やだ、やめろ、青木。」
「また、痛いのヤダって泣くんじゃないでしょうね?もうこれ以上待
てませんから。」
「あああああああああああ~」
青木が僕の身体に入ってきた。信じられないほどの激痛が僕を
襲った。僕は身体をのけぞらせ苦痛に耐えた。身体の中で青木が
動くたびに僕は悲鳴をあげ、青木にしがみついた。
「薪さん、痛いですか?すみません。」
「ばか。あやまるなよ。」
「薪さん、好きです。愛してます。」
青木は僕にくちづけした。愛してるという言葉は魔法の言葉だ。
どんな苦しみも愛があれば乗り越えられる。僕に再び快感の波が
押し寄せた。僕の悲鳴はいつの間にか嬌声へと変わり、愛の高波
が僕を更なる高みへと押し上げ、僕の思考回路は津波にさらわれ、
頭が真っ白になった。
「薪さん、大丈夫ですか?ちょっと切れちゃいましたね。でも、
薪さんが感じてくれて良かった。」
青木はティッシュで僕の身体を拭いながらそう言った。
僕はぐったりとして何も答えなかった。
とうとう一線を越えてしまったけど、不思議と後悔はなかった。
「薪さん、メリークリスマス!開けてみてください。」
青木は可愛いリボンの付いた小さな箱を差し出した。
「青木、クリスマスイブは明日だぞ。」
僕がそう言うと青木はくすっと笑って、こう言った。
「薪さん、時計を見てください。もう夜中の2時ですよ。薪さんが
ベッドに入った時にはすでに12時まわってたのに気づかなかった
んですか?」
僕は時計を見て、今日が24日であることにようやく気づいた。
「さあ、早く開けてみてください。」
青木にせかされて僕は包み紙を破って小箱を開けた。指輪だった。
シルバーリングかと思ったが、プラチナだった。
「プロミスリングです。ステディに贈る。」
青木は僕の手をとり、左手の薬指にそっとはめた。
「結婚してください。」
「ばか、僕は・・・」
「籍を入れるのは無理だってわかってます。でも、一緒に暮らしま
しょう。一生俺のそばにいてください。俺は死ぬまであなたを愛し
続けます。」
青木は僕を抱き寄せた。僕は青木の腕の中で、それも悪くないと
思った。僕はまだ青木に愛してると言ったことがない。今まで誰も
愛したことがないから、これが愛なのかわからないからだ。青木は
勝手に僕が照れて何も言わないだけだと勘違いしている。僕は
青木のそんな傲慢で強気なところが好きだった。愛とはただ単に
好きの延長上にあり、一緒にいて幸せと感じることであるなら、
100%僕は青木を愛してる。でも、まだそれは確かな定義では
ないのだから、確信できるまで黙っておこう。いつか僕は青木に
愛を告白する時が訪れる気がする。それまで僕の思いは秘密に
しておこう。僕はまた何も答えずに青木の腕の中で寝りについた。
(完)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 【中古】エースをねらえ! <全10…
- (2024-11-26 12:28:12)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 陽だまりの月 2巻 読了
- (2024-11-25 21:41:16)
-
-
-

- アニメ!!
- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…
- (2024-11-14 14:54:38)
-
© Rakuten Group, Inc.