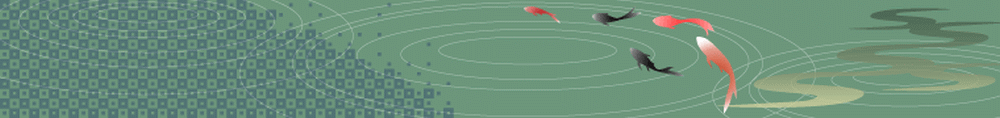スペイン史(2) 近現代
スペインの歴史(4) 「無脊椎のスペイン」
スペイン・ハプスブルク家最後の王カルロス2世が1700年に嗣子なく死んだ時、その後継者をめぐって国際紛争となった。共にスペイン王家と縁戚関係にあるフランス(ブルボン家)とオーストリア(ハプスブルク家)の双方が継承権を主張する。フランスの「太陽王」ルイ14世はヨーロッパでの覇権を確立すべく自分の孫フィリップを後継者に据えようとしたが、それに反対するイギリスやオーストリアが包囲網を形成した。ここにスペイン継承戦争が勃発するが、この戦争は1945年まで度々起こる欧州大戦の最初のものといっていい。
スペインは両陣営の戦乱の巷と化した。この間イギリスは海軍根拠地としてジブラルタルを占領し、1713年のユトレヒト講和条約で領有が認められた。双方痛み分けのこの戦争で結局王位はルイの孫フィリップが継承したが(フェリペ5世)、スペインの属領だったベルギーやイタリア南部はオーストリアに割譲された。
こうしてスペインでのブルボン朝による支配が始まった。ブルボン朝は進んだフランスの行政制度や重商主義をもちこみ、フランス人やイタリア人官僚によって近代国家への改革が進められる。汚職の追放、産業の振興、税制の一本化などであるが、教会勢力の排除は敬虔な国民の抵抗もあってなかなか実現しなかった。
フェリペの子カルロス3世の治世に改革はさらに進んだ。同族のフランス王家が繰り返す無益な対英戦争に度々巻きこまれ、また多くの改革が机上の空論に終わったものの、国家の独占していた中南米との貿易が自由化され、またフランス式の政教分離が進んで教会のもつ特権(10分の1税など)が廃止されイエズズ会が追放された(1767年)。彼の治世の末年(1788年)にはスペインの人口は1000万人を越えた。スペインの代名詞である闘牛が現在の形となり、大衆娯楽として定着したのもこの時代である。
1788年、カルロス4世が即位する。彼は無能な人物でその妃マリア・ルイサに牛耳られ、その愛人であるマヌエル・デ・ゴドイが先王の功臣を排除して実権を握った。折しも隣国フランスでは革命で王政が倒されたが、同族のブルボン家を戴くスペインは傍観するのみだった。1793年に元国王ルイ16世が処刑されるとスペインはフランスに宣戦したが、無能な戦争指導によって逆侵攻を許し、ゴドイの意向もあって実質的にフランスの属国となる条約を締結した。
1801年、ゴドイはイギリスと結ぶ隣国ポルトガルを攻撃したがイギリスに逆襲され、カリブ海のトリニダード島を割譲、中南米の植民地は不穏になりまた財政が逼迫した。ナポレオン・ボナパルトが皇帝となったフランスへの従属は続き、トラファルガー岬沖の海戦(1805年)ではスペイン・フランス連合艦隊がホレイシオ・ネルソン提督率いるイギリス艦隊と戦ったが、今や見掛け倒しのスペイン艦隊は無様に敗走する。
島国イギリスを封じこめるべくナポレオンは大陸封鎖令を出したが、イギリスに経済的に従属するポルトガルはこれを無視した。ナポレオンはフランス軍をスペインに進駐させてポルトガルを占領し(1807年)、その南半分の王にゴドイを据えようとした。翌年ついにアランフェスでゴドイに対する反乱が起きゴドイは亡命、カルロス4世は息子への譲位を強いられた。これを機にナポレオンはスペイン王家を呼び寄せて退位を迫り、ナポレオンの兄ジョゼフ(当時ナポリ王)がホセ1世としてスペイン王位に即いた。
フランスの横暴に憤激した国民はジョゼフの即位を認めず反乱を起こした。これに呼応してアーサー・ウェルズリー将軍率いるイギリス軍がポルトガルに上陸しフランス軍を攻撃する。業を煮やしたナポレオンは自ら30万の軍を率いスペインに侵攻してマドリードを奪還した。しかし教皇領を併合しローマ教皇を幽閉したナポレオンへのスペイン国民の反感は強く、各地でフランス軍に対する攻撃を続けた(「ゲリラ戦」の語源)。カルロス4世の宮廷画家だったフランシスコ・デ・ゴヤは、このゲリラ戦に取材した作品を多く描いている。
1812年になると反乱軍やイギリス軍は勢いづきマドリードを奪還、ジョゼフは逃亡した。ナポレオンがロシア遠征に失敗した後の1813年になるとフランス軍はスペインから一掃され、イギリス軍はフランスに逆侵攻する。この功によってウェルズリー将軍はウェリントン公爵の称号を授けられた。スペインはフランス支配から解放されたのである。
王位に復したフェルナンド7世(カルロス4世の子)だが、彼を迎えたコルテス(国民政府)が対仏闘争中に定めた憲法を認めず、逆にコルテスを解散させ絶対王政の反動政治を行った。1820年にはカディスで軍の反乱が起き、ラファエル・デル・リエゴ大佐ら自由派が国王に憲法を承認させたが、ブルボン朝が復活した隣国フランスの軍隊が介入して自由派は処刑され(1823年)、絶対王政が復活した。
一方ナポレオンによる占領や王政復古による混乱の間、中南米のスペイン植民地にあるクリオージョ(現地スペイン人)たちは次々と本国からの独立を宣言し、鎮圧に向かったスペイン軍も撃退された。既に1819年にはフロリダをアメリカ合衆国(1776年独立)に売却しており、中南米のスペインの植民地はキューバを除き全て失われた。絶対王政で一切の改革が封じられ、また植民地を失ったスペインは、同時期の西ヨーロッパで進んでいた産業革命に完全に乗り遅れることになる。
1833年にフェルナンドが死ぬと、王妃マリア・クリスティナの意向で娘のイサべル(2世)の王位継承が決められた。しかしヨーロッパ王家の相続はゲルマン人の昔から男系相続が原則であり、王弟のドン・カルロスが継ぐべきであった。保守派を主体とするカルロスの支持者(カルリスタ)はカタルーニャを拠点に反乱を起こし、自由派の支持を得たイサベルと摂政マリア・クリスティナに対する内戦となった(第1次カルリスタ戦争)。内戦は6年で終わりイサベルが1843年に正式に即位したものの、将軍によるクーデターが続発、1847年には第2次カルリスタ戦争が勃発し内政は安定しなかった。
1868年にはプリムとセラノの両将軍によるクーデターが発生し女王は亡命、コルテス(国民政府)はイタリア王子アメデオを国王に迎え立憲君主制の樹立を目指したが安定せず(この王位をめぐる争いが1870年の普仏戦争の遠因となる)、1872年に第三次カルリスタ戦争が勃発、匙を投げたアメデオが退位し、初めて共和制が宣言された。しかしこの共和国政府は全土を実効支配することは一度もなく、セラノ将軍のクーデターでコルテスは解散、共和制は1年で崩壊した。
1874年にイサベルの息子アルフォンソ(12世)が王位に迎えられて事態の収拾が図られ、内戦は終結した。新憲法が制定され、制限選挙が導入され言論の自由が保障されたが、教会(同時に大地主でもある)の影響力は依然強く、また保守派と自由派、それに社会主義者は激しく対立し、経済先進地域でもあるカタルーニャやバスクの分離独立運動が活発化、暗殺やストライキが頻発した。19世紀の100年間に産業革命の進んだ西ヨーロッパ各国の人口は2倍から3倍増しているが、スペインでは僅か6割増の1600万人に過ぎない。
1895年、スペインが中南米に唯一維持していた植民地・キューバで反乱が起きた。カリブ海対岸のアメリカではキューバ産砂糖の9割を輸入していたこともあり、この独立運動を支持する者が多かった。アメリカの新聞は発行部数拡大のため、住民の強制収容を行うスペイン当局の残虐ぶりを書きたてて、国民の反スペイン感情を煽った。
1898年、ハヴァナ港に入港していたアメリカ軍艦メイン号が爆沈するとアメリカの新聞はスペインの仕業と決め付け、アメリカ国内では戦争を望む声が強まった。アメリカ政府はキューバ独立などの要求が拒否されるとスペインに宣戦する。太平洋への進出を図っていたアメリカは海軍増強を進めており、旧式なスペイン海軍は敵ではなかった。数ヶ月で戦争はアメリカの圧勝に終わり、キューバの独立(=アメリカの保護国化)が認められる一方で、スペイン領のフィリピン、グアム島やプエルト・リコはアメリカの植民地になった。
スペインは北アフリカの飛び地や西サハラ、赤道ギニアを除いて海外領土を全て失った。この敗戦はスペイン国民に大きな衝撃を与え、芸術や文学界に自省的な「98年世代」と呼ばれるグループを形成する(作家ミゲル・デ・ウナムノや哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセトなど)。内政では労働者や農民の不満が高まり、過激な社会主義思想が広まることになる。政府は国民の不満をそらすため海外進出に乗り出してフランスと共同で地中海対岸のモロッコを保護国化したりしたが(1905及び11年)、1909年にはバルセロナで無政府主義的な労働者蜂起が起きている。こうした不穏な国情を嫌ってアメリカに移住する国民も多かった。
一方でこの時代はスペイン(カタルーニャ)を代表するモデルニスモ(近代主義)の建築家アントニ・ガウディの活躍した時代でもあり、彼がバルセロナの聖家族教会の設計を引き継いだのは1883年のことである(現在も建設中)。またフラメンコ舞踊が大衆化したのも、カフェなどの外食産業が発達したこの時代のことであるといい、その歴史は存外浅い。
1914年に始まる第一次世界大戦ではスペインは中立を保ち、軍需資源を輸出して一時的な好景気に沸いたが、経済格差が大きく国民の多くはその恩恵に与れなかった。資本流入によるインフレーションといった社会不安やロシア革命の影響もあり、保守派(大地主、教会、軍部)と労働者・社会主義者との対立が激化し、1917年からの6年間で内閣が13回替わるという混迷ぶりだった。
1921年、モロッコ北部でのアブド・エル・カリムの反乱に対して、議会の承認なしに鎮圧に向かったスペイン軍がアヌアルで逆襲され1万人以上が戦死した。軍部の責任を問う声が高まり、政情はますます紛糾する。1923年、ミゲル・プリモ・デ・リヴェラ将軍がクーデターを起こし全権を掌握、国王アルフォンソ13世の承認を得て、1876年の憲法は停止された。治安回復で一定の支持を得た軍事政権(1925年、文民政権に移行しプリモ・デ・リヴェラは首相に就任)は道路・鉄道・水道建設や行政・税制改革を推進し、フランスと協力してモロッコ支配を回復した。
しかし暫定政権を標榜しながらも約束した総選挙をいつまで経っても行わず、また教会保護政策で知識人の、特権廃止で貴族層の、社会制度改革で財界の、そして軍制改革で軍部の支持を失い、プリモ・デ・リヴェラは1930年に辞任に追い込まれ、フランスに亡命した。軍部独裁を許した国王の責任も問われ、翌年の総選挙では共和派が勝利して第2共和制が宣言され、国王は国外に亡命した。
同年リベラルな共和国憲法が制定され、政教分離や婦人参政権、カタルーニャ、バスク両地方の自治などが定められた。しかし共和制に移行して社会問題が解決されたわけではなく、対立はさらに先鋭化、とりわけ頻発する急進社会主義者の活動は脆弱な連立政権を揺るがした。連立政権内の対立で改革は遅々として進まず、また反教会的な政策(教会財産の国有化など)は敬虔な貧農層の共和制への支持を失わせていく。1932年には早くも軍部のクーデターが起きるが失敗に終わった。
同年、保守派が結集してCEDA(スペイン独立右派連合)を結成、1933年の総選挙で中道右派が勝利したが、折からの世界経済恐慌の影響もあって左派勢力によるテロやストライキが頻発し、連立政権は幾度と無く窮地に立たされた。右派では1933年にファランヘ党が設立されており、鉱山労働者蜂起を武力鎮圧したフランシスコ・フランコ・バハモンデ将軍もその一人だった。
1936年2月の総選挙では、共和派・社会主義者・共産主義者からなる人民戦線(ソヴィエト連邦肝いりのコミンテルンによる反ファシズム統一戦線結成の呼びかけに応じたもの)が勝利した。右派は選挙不正を糾弾して暴力的な対立が激化、7月の保守派議員の暗殺事件をきっかけに軍部は各地で反乱を起こし、スペインは左右両派の内戦に突入していく。
2006/10/05
スペインの歴史(5) Plus Ultra
1936年7年、軍の一部が人民戦線政府に対して起こした反乱でスペイン内戦が始まった。反乱軍はフランコ将軍を首領(カウディージョ)として、年内には国土の西半分を制圧することに成功した。しかし軍の全てが反乱軍に投じたわけではなく(フランコの弟も政府軍に留まっている)、また内紛続きだった人民戦線政府が反ファシズムで結束したため、内戦は長期化の様相を呈する。
この内戦に国際社会の取った対応は様々だった。スペインに投資しているアメリカ、イギリス、フランスは政府側に好意的だったとはいえ共産勢力の台頭を嫌い、何よりこの内戦が欧州大戦に発展することを恐れ、不介入の姿勢をとる。ソヴィエト連邦は人民戦線政府を支持し、武器・資金援助を行った。また世界中の共産主義者や知識人(作家のアーネスト・ヘミングウェイやアンドレ・マルローなど)からなる国際義勇旅団が組織され、政府軍に投じる。
一方ファシズム政権の隣国ポルトガルは反乱軍を支持、また反共主義を標榜するナチス・ドイツとイタリアも、反乱軍に陸上・航空部隊を送って公然とこれを支援した。特に再軍備を進めるドイツにとって、この内戦は格好の兵器実地試験となった。1937年4月26日、ドイツ空軍の「コンドル軍団」はバスク地方の小都市ゲルニカを無差別爆撃し、一般市民の死者1600人に上った(但しこの数には2日後の地上戦の犠牲者も含まれている)。この惨禍に対して当時フランスにあった画家パブロ・ピカソは抗議の怒りを込めて大作「ゲルニカ」を描いている。
内戦は膠着状態が続いたが、反乱軍でファランヘ党と保守党が統合したのとは対照的に、政府内ではソ連の威を借りる共産党と他政党の間で内紛が発生、やがてそのソ連がドイツと接近して援助を控えると政府軍は劣勢となった。1939年3月に首都マドリードが陥落、内戦は反乱軍の勝利に終わった。米英仏などもフランコ政権を承認した。
3年に及ぶこの内戦での死者は双方による処刑も含めると60万人(当時のスペインの人口の2%)に上るといい、スペインに大きな傷跡を残した。この内戦を通じて迫り来る第二次世界大戦の陣営(独伊枢軸対連合国の構図)が固まることを思えば、1700~13年のスペイン継承戦争と共に、この内戦は欧州大戦の一部であったといっていい。
内戦の余燼の中で成立したフランコ独裁政権は、早速ドイツやイタリア(及び日本)と防共協定を締結したが、その半年後に第二次世界大戦が勃発する。翌年ドイツは電撃戦でフランスを降し、ドイツのヒトラー総統とフランコはフランス・スペイン国境の町アンダイで会見する。枢軸国(独伊)側での参戦を要求するヒトラーに対し、フランコは内戦の痛手を理由に言を左右にして応じなかったが、本音は地中海になお強力なイギリス軍があってイタリアを圧しており、かつドイツ空軍がイギリスを制圧出来ないのを見たためだった。
会見後ヒトラーは部下に向かってフランコを「小物」と罵倒したが、その「小物」の方が、むしろ生存戦略に長けた先見の明があったというべきだろう。翌年独ソ戦を開始しまたアメリカに宣戦した枢軸国は次第に劣勢となり、1943年にはイタリアが降伏、ドイツも1945年に破滅的な敗北を喫した。その間スペインは独ソ戦に義勇兵を送った以外は決して動かず、最後まで中立を維持した。
大戦は終わったが、かつて枢軸国と友好関係にあり、今もファシズム政権が続いているスペインは微妙な位置に立たされた。戦勝国(連合国)主体で結成された国際連合はスペイン非難決議を採択して締め出した。孤立するスペインは国内での自給自足経済を志向したためヨーロッパの最貧国に転落、国内では抵抗運動が徹底的に弾圧された。
こうした状況が変化したのが、戦勝国アメリカとソ連による東西冷戦だった。アメリカにとって、地中海西端を扼する戦略上の要衝、かつ反共国家であるスペインを取り込まない手は無い。1953年、スペインはアメリカと軍事・経済援助と引き換えに基地協定を締結し、そのアメリカの後押しで1955年には国連加盟を果たす。しかしフランコ独裁政権はなお続いていた。
1956年、北アフリカでモロッコが独立、スペイン領モロッコも併合された。時を同じくして、検閲制度に反対し言論の自由を要求する学生運動が活発化する。1958年にIMF(国際通貨基金)に加盟したスペインは翌年に経済を自由化、観光客(特にドイツから多い)や外資の誘致、そして外貨獲得のため西ドイツなどへの出稼ぎ労働者派遣に転じ、驚異的な経済成長を実現したが、同時に根強い民主化運動を招くこととなった。1966年には検閲が一部緩和されたが、信仰や家族といった伝統的価値を強調するフランコ政権はなお磐石だった。
しかしフランコが老衰するにつれ、その政権も動揺する。1969年、フランコは元国王アルフォンソ13世の孫であるフアン・カルロスを後継者に指名して王党派取りこみを図る。さらに1970年には翼賛政党ファランヘ党を解散して「国民運動」に改組、1973年には政権奪取以来初めて首相ポストを置いてルイス・カレロ・ブランコを任命した。しかし民主化運動はおさまらず、さらにフランコの統一化政策に反対するカタルーニャやバスク地方の分離独立運動も活発化、ETA(「バスク祖国と自由」)によるテロが横行し、カレロ・ブランコ首相は就任半年で暗殺された。政府は1970年に廃止した死刑を復活してこれに応じた。
1975年11月20日、危篤状態だったフランコは82歳で死んだ。即座にフアン・カルロス(1世)が即位し、44年ぶりに王制が復活した。フランコは王を中心とした独裁体制維持を想定していたが、フアン・カルロスの下、スペインでは急速に民主化が進められていくことになる。戦前から40年近く続いたフランコ独裁政権はようやく終焉した。
翌1976年、フアン・カルロスの政府はまず西サハラを放棄(フランコの死の直前にモロッコが侵入し西サハラ紛争が始まっていた)、既に1968年に赤道ギニアが独立していたため、スペインの海外領土は全て失われた。7月には政治犯(共産党やETA)に対する大赦を発表、さらに左右両派によるテロが横行する中、12月に国民投票が行われ、スペインを議会制君主国とすることが定められた。翌年には「国民運動」が解散すると共に共産党を含む政党結社が解禁、1936年以降初の自由選挙が行われ、国民の88%の支持で新憲法が制定された。また極度の中央集権が改められ、地方分権も進められた。
こうした民主化に反対する軍部や治安警察の一部は1981年2月23日、議会に乱入して議員や新首相を人質に取りクーデターを画策したが、国王は軍最高司令官として民主化支持を断固表明、騒ぎは一晩で収まり、スペインの民主化は揺るがなかった。翌年スペインは北大西洋条約機構(NATO)に加盟、第12回サッカー・ワールドカップも開催され(優勝はイタリア。なおワールドカップ常連のスペインだが、現在に至るまで優勝経験が無い)、国際舞台への復帰を印象付けた。
1986年にはポルトガルと共にヨーロッパ共同体EC(のちヨーロッパ連合EUに改編)に加盟し、「孤立と貧困のスペイン」からの脱却を果たした。なおイギリスとはジブラルタル領有権を巡って対立し、1969年以来封鎖を続けていたが、EC加盟直前の1985年に解除している。その後もイギリスとの協議が続いているが、2002年の住民投票ではイギリス残留派が98%を占めている。
1992年にはセヴィージャ万博とバルセロナ・オリンピックという国際的な二大行事を成功させたことはもはや記憶に新しいだろう(万博に合わせて新幹線AVEも開業している)。なお故郷バルセロナへの五輪誘致に尽力し、財政破綻寸前の五輪を商業主義に転換、1980年から21年もの間国際オリンピック委員会会長の座に君臨したフアン・アントニオ・サマランチは、フランコ政権でスポーツ長官を務めていた。
1982年以来社会労働党のフェリペ・ゴンサレスが4期14年の長きにわたって首相の座にあったが、長期政権につきものの不正蓄財疑惑で1996年の選挙に敗北、中道右派国民党のホセ・マリア・アスナルが首相に就任した。アスナルはアメリカでスペイン語を母語とするヒスパニック系が増えていることに鑑み、アメリカや中南米諸国との友好を重視する。これには順調な経済成長が続いて国内総生産が世界第7位(当時)に踊り出たスペインの国際的地位向上の狙いもあった。
2003年初頭にそのアメリカが対イラク戦争に踏み切るとき、アスナルは国民の大部分の反対にも関わらずアメリカを全面支持、折しも国連安全保障理事会の非常任理事国だったこともあり、マデイラ諸島で米英首脳と会談を行ってアメリカ支持を鮮明にし、同じEUのフランスやドイツがイラク戦争に反対したのとは好対照をなした。当然イラクにも派兵している。
2004年3月11日、マドリード郊外の通勤列車で複数の爆弾テロが発生、死者191人の大惨事となった。事件直後アスナルはこのテロをETAによるものと決め付けたが、実際はイスラム過激派によるものと判明する。そのせいか2日後行われた総選挙では、事前の予測に反してイラクからの撤兵を公約に掲げた社会労働党が勝利し、ホセ・ルイス・サパテロが首相に就任した。サパテロは公約通りイラクからスペイン軍を撤兵させ、独仏などEU諸国との関係強化を目指している。70年代以降テロを繰り返してきたETAは2006年に再停戦を発表、政府は対話に乗り出した。
EU開発計画や補助金を活用し好調な経済成長を続けたスペインは、EU共通通貨ユーロ導入にも参加(2002年に流通開始)、2005年には国民投票でEU憲法を批准(ただしこの憲法はフランスやオランダでの否決で暗礁に乗り上げている)、独英仏伊に次ぐ人口や経済規模を擁することもあり、EU内で確固とした地歩を得ている(イタリアと共に独自の地中海政策をもち、大国主導外交に走りがちな英独仏へのブレーキ役でもある)。かつて農業中心だった経済構造はサーヴィス業中心に変化し、EU内でもっとも高かった失業率は近年改善されている(10%前後)。なおスペインはフランスに次ぎ世界第2位の外国人観光客受入国である。
かつて西ドイツやアメリカに移民を送り出してきたスペインだが、現在はアフリカや中東から流入する移民への対処に苦慮している。サパテロ政権はEUの要請により不法移民の取締りを強化すると共に、既にスペインに居る不法移民の滞在を合法化した。マドリード同時多発テロ事件は移民系のイスラム過激派がヨーロッパで起こした最初の大規模テロ事件だったこともあり、アフリカからのヨーロッパの窓口にあたるスペインの移民対策は今やEU全体の問題となっている。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 韓国!
- 釜山ビジネスホテル~西面のロッテホ…
- (2024-11-27 13:40:20)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- 暖かい伊豆・貸別荘・スターヒルズ
- (2024-11-27 11:14:07)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- コストコのホノルルクッキー★パイン…
- (2024-11-06 10:12:11)
-
© Rakuten Group, Inc.