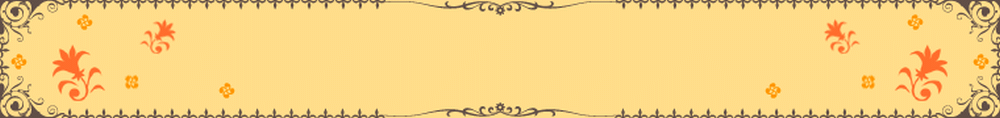遠い猫
わたしの家はそれほど道路に近くは無かったので、立ち退きをする必要はなかった。
何年もかけて、住宅街の端に住む人たちはいろんな地域へ引越しをして行った。
道路の大工事は10年もの歳月をかけ粛々と進み、その間にわたしは結婚して実家を離れた。
そして気がつくと、道路はすっかり完成していた。
わたしは都会で暮らすようになった。
中途半端な都会ではあるが、まぁ大きな地方都市ではあった。
駅に程近い広めの3LDKのマンションの9階にわたしは暮らしていた。
南側に開かれた大きな窓からは市内を縦断する大きな川が見えた。
天気の良い日は、わたしは洗濯物を干しながら、飽かずに川の流れを眺めていた。
こどもはなく、夫もわたしも働いていた。生活は潤っていて、問題は何もなかった。
ある日の夜、わたしはふと目を覚ました。寝つきの悪いわたしは、ちょっとした物音でもすぐに目覚めてしまうのだった。
カサカサカサ、にゃーん。カサカサ、カリカリ。にゃーん。
猫がいる。家の中に。
猫がいる音がする。どうしてだろう?
わたしは暗闇の中でむっくりと起き上がり、耳を澄ませた。
隣か、上下階の音かと思ったのだ。
しかし、ここは鉄筋コンクリートの分譲マンションで、防音効果は良いほうだ。
実際、これまで隣や上下の音など感じたことがなかった。
カツカツ、カリカリ。にゃーん。にゃーん。
間違いない、猫だ。猫が家の中にいる。猫が、誰かを探している。
わたしの実家の母は大変な猫好きだったので、家の中に猫を切らしたことはなかった。
祖母もそうだったらしい。だからわたしも猫には馴染んでいる。
猫の鳴き方で、猫が何を欲しているのか、大体のことはわかる。
この鳴き声は、誰かを探している声だ。寂しがっている声だ。
しかし、なぜ、家の中で猫が鳴くのか。
今現在わたしはは猫など飼っていない。まさか、夫が突然連れ帰って来たのだろうか。
その可能性もある、と思って、わたしはゆっくりと寝室のドアを開けた。少し怖かったが、ほうっておくわけにもいかない。
寝室のドアを開けると、廊下がある。玄関にまっすぐ向かっている。
廊下に猫はいなかった。
わたしは猫の気配のするほうへ、そっと歩き出した。
そこは、夫が寝ているはずの部屋だった。
カリカリ、カリカリ、夫の寝室の内側から猫が引っ掻いているらしい音が響いていた。間違いない。猫はここにいるのだ。
わたしはそっとドアノブを回した。夫がいれば、鍵がかかっていることの方が多い。しかし、すぐに開いて、中から、背中が黒くてお腹が白い、ぽっちゃりと太った大きい猫がゆらりと出てきた。
わたしは息を呑んだ。やはり猫がいたのだ。
中を覗くと、夫はいなかった。そうだ、とわたしは思い出した。夫は出張に行くと言い残してここ二週間くらい留守にしているのだ。
にゃーん、にゃーん。
猫は甘えたような声で鳴き、わたしの足元にすりすりと体を擦り付けた。わたしは猫を抱き上げた。ずっしりと重い、丸い顔をした可愛い猫だった。
「うんち」
猫ははっきりと言った。そしてまた、にゃーん、と鳴いた。
「え、うんち?」
わたしは慌てた。家の中には当然ながら、猫のトイレや猫砂なんてない。
「困ったな。ちょっとまって!」
わたしは急いで新聞紙を持ってきて、その場に引いた。
「ここにして」
そういうと、猫は、にゃーん、と言いながらぶるぶると体を震わせてうんちをした。
わたしは新聞紙をくるくると巻いて、うんちを片付けた。
「ねえ、おまえ、日本語が話せるの?」
猫は知らん振りで、にゃーん、と鳴いた。
時計を見ると、夜中の3時過ぎだった。まだ辺りは暗い。
お腹が空いているのじゃないかと思って、キッチンの戸棚を開けてあちこち探したけれど、何もなかった。仕方ないので、鰹節をごはんに混ぜて少し与えてみた。
にゃーん。
猫はお腹が空いていたのか、かっかっ、と舌を鳴らしながら喜んで食べていた。
わたしは猫の姿を眺めながら、この子はどこかで見たことがあるなあ、とずっと考えていた。実家で飼っていた猫なら、すぐに思い出せるけれど、そうではなかった。もっと関わりは薄い、けれど、見知っている、そういう気がした。
とりあえず、わたしは明日のために寝ることにした。猫はわたしの部屋に入り込んで、ずしっと重い体をわたしの体の上に横たえ、わたしと一緒に眠った。
次の日、わたしは半日休むことにして、午後から出社することにした。そして車を出して郊外のホームセンターへ出かけ、猫用品を買い揃えた。猫のトイレ、猫砂、猫缶、猫の水のみ機、猫キャリー、爪とぎ板。そして急いで家に帰り、猫用品をセットした。これで安心だ。
そしてわたしは猫にいい子にしているようによく言い聞かせ、会社に行った。
夜はなるべく早く家に帰ろうと思っていたのだけれど、急な打ち合わせが入った上にそれが長引いて、すっかり遅くなってしまった。息せき切って家に戻ると、テレビの音がした。夫が帰っているのだ。
「ただいま」
リビングに入ると、夫がちら、とわたしのほうに振り向いて、不機嫌そうにチャンネルを変えた。
「おかえり。っていうか、どういうことだよ?これ」
「え?何のこと?」
「いきなり猫なんか飼ってさ。相談もなく」
「何言ってるの?この猫を連れて来たのはあなたでしょ?わたしだって昨日の夜びっくりしたんだから」
「二週間ずっと秋田にいたんだ。猫なんか連れてこれるわけないだろう」
「え、じゃ、どういうこと」
「聞きたいのはこっちだよ。道具までそろえてさ」
「だって・・・。用意しないと、もう家にいるんだし」
「だから、どうしているんだよ」
「そんなに怒ることないじゃない。そんなに猫が嫌いなの?」
「家の中が汚れるのが嫌なんだよ。猫って毛が散るし、爪を研いだりするだろ」
夫は本当にいやそうに目を細めた。冷たい雰囲気の細い目がますます細くなった。
「でも・・・・」
わたしは何を言ったらいいのかわからなくなってしまった。
ぽっちゃりと太った丸い顔の可愛らしい猫が、急にとてもかわいそうに思えて、悲しくなった。
「じゃあ、どうしたらいいの?」
「誰か、貰ってくれるひとを探すとかさ。お前は仕事で知り合いが多いんだから誰かいるだろう」
夫はテレビを消し、今度はゲームを始めた。話は終わり、と暗に言われたような気がした。
夜、寝室にはやはり猫が入ってきた。柔らかくて重い。わたしは猫を撫で回した。
「どうしよう。家で飼っちゃいけないんだって。ところでお前はどこから来たの?」
猫はわたしを見つめている。猫に見つめられるのは不思議な感じだった。
「でもわたし、お前には見覚えがあるんだあ。ね、教えてよ」
わたしは記憶を辿った。
とろとろと眠りに落ちそうになったそのとき、わたしは思い出した。
そうだ。
立ち退きになった住宅街の端の家の猫だ。
その家では、おじさんとおばさんが二人きりで暮らしていた。
わたしよりもずいぶん年上の息子が一人居て、息子は自立して家を出たらしくもう長いことその家にはおじさんとおばさんと猫が暮らしていたのだ。
おじさんとおばさんとは言っても、もう二人ともかなり年を取っていて、おじいさんとおばあさん、に近い雰囲気だった。
わたしが猫目当てに遊びに行くと、おばさんが飴をくれたりした。おじさんはいつも静かにテレビを見ながら座っていた。おばさんがときどき、古いポットでお茶を入れて、おじさんの前に出したりしていた。
おじさんとおばさんは痩せているのに、猫は良いものを食べているのか、ぽっちゃりと太って、とても人懐っこいのだった。
おじさんとおばさんの家は、かなり最後まで立ち退かないでその場にあった。
子供を育て上げ、30年以上過ごしたであろうその家を、二人は離れたくなかったのかもしれない。
しかし、その家は段々、近所の人に疎まれていった。
どこも行くところがないらしいとか、保証金の問題でゴネているとか、とにかくあまり良い噂を聞かなくなった。
わたしも子供ながらその家の側にはあまり寄り付かないようになった。
猫にも会わなくなった。
時が流れた。
そしていつの間にか、道路は完成していたのだ。
「そうか、お前」
猫はそっとベッドから降りた。そして、ドアをカリカリと引っ掻いた。
「どこへ行くの?」
わたしが寝室のドアを開けると、猫は玄関のほうへ行き、玄関のドアをカリカリと引っ掻いた。
「どうして?」
わたしは悲しくなった。
「どこへ行くのよ?」
猫はわたしを見つめている。そして小さな声で、にゃーん、と鳴いた。
わたしはドアを開けると、猫はするりと外へ出た。そしてマンションの外廊下をすべるように歩いていった。
「チャぺ」
わたしは思い出した名前を呼んだ。すると、猫は一度だけ振り向いた。そして、すぐにまた歩き出して、暗闇の中へ消えて行った。
わたしはその場にしゃがみこんでしばらく泣いた。
© Rakuten Group, Inc.