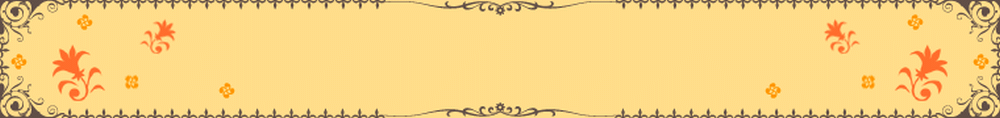アスラエル
かといってただ座っていることもできない。
前屈みになっているような状態がいくらかましだが、その姿勢そのものが苦しいので全く楽ではない。
そしてずっと鼻から酸素を吸っている。
入院してから、鎮痛剤のおかげか胸の痛みはずいぶん収まったが、ただひたすら、息苦しい。そしてそれは日に日にひどくなっていく。
息苦しさ、というのはどうやら薬ではそれほど軽減しないものらしい。個人差もあるのだろうが。
ヘビースモーカーだった俺は、使えない薬、効かない薬が多いらしい。
まるで犬みたいに首輪をつけられ、それが日に日に少しずつ締まっていくような感じだ。
この苦しさは、胸に水が溜まっているせいだと聞いたが、実感としては息の通り道がどんどん塞がっていくような気がする。
そしてそれは緩くなることはない。
おそらく死ぬまで、この苦しさは続いていくのだろう。
入院したのは二ヶ月ほど前だった。
しばらくずっとイヤな咳が続いており、血の混じった痰も出るので、家の近くのクリニックに通っていたのだが、大きな病院での検査をすすめられ、そこで肺がんと診断されたのだった。
俺にとっては寝耳に水で、まさかそんなことだとは全く思っていなかった。
すぐに入院になった。
その後、医者が妻だけを呼び出した。
妻とは結婚したときから、こういうときにはお互い正直に言い合うように約束していたので、俺は妻に医者との話がどんなことだったのか訊ねた。
妻は動揺し泣いていたが、俺はもう手術しても意味のない末期の状態で、余命は三ヶ月から半年であることを教えてくれた。
数日前に、俺はこの大部屋に移って来た。
ここはどうやら、要観察の肺がん末期患者が集められているところのようだった。
大部屋とはいっても、誰とも会話はない。
みな息苦しいので、しゃべるどころではないのだ。 酸素マスクをつけて寝たきりだ。
がんが脳に転移したのか、わけのわからないことを言っている男もいる。
その男は四十五歳の俺よりも若く見えた。
それだけになかなか死ぬに死ねず苦しいのに違いない。
若いのは俺とその男だけで、あとはみな高齢者だった。
その若い男はベッドに手を縛り付けられていた。
点滴や酸素マスクをむしってしまうからということらしいが、たまに正気に戻ることもあるらしく、縛った手をほどいてくれだの、苦しいから起き上がりたいだのと言うので哀れだった。
起き上がりたいという気持ちは俺にもよくわかった。 息苦しいときというのは、とても横になって寝てなどいられないのだ。
横になっているとひどくなってくるので、少しでも楽になれるよう、いろんな姿勢を取りたいはずだ。
しかしそいつは縛らなければならないからなのか、仰向けにされているのだ。
さぞつらいだろう。
まぁ、俺が哀れんでも仕方がないのだが。
明日は我が身なのかもしれない。
そういえば最近、妙に頭がふわふわする感じがある。 俺の頭にもすでにがんは転移しているのかもしれない。肺がんというのは脳に転移しやすいらしいから。
年寄りの患者たちは、みな静かなものだった。
暴れる気力もないのか、そこはもう通り過ぎてしまったのか、ただぐったりと息だけをしている感じだった。
高齢になればなるほど、それほど苦しくも無いのか、強い薬を使っているからかなのか、ぐっすりとよく寝ている患者もいた。
俺は息苦しさと背中の痛みが強く、良く眠れない日々が続いている。眠っても、すぐに目が覚めてしまう。
薬の量は増えているのだが、段々効かなくなっているような気がする。
眠れない夜、俺はベッドでケータイをいじってばかりいた。
病院内では禁止だとばかり思っていたのだが、それは外来だけで、入院病棟ではそうでもないようだった。 自分のベッドの上で使うだけなら特に制限はなかった。
ノートパソコンを持ち込んでいる患者もいた。それで自分の病気のことを調べて、一喜一憂したりしていた。
俺も最初の頃は、ケータイでそういったページを見たりしていた。が、見れば見るほど、自分がどれだけ希望のない状況なのかを知ることになるだけだったので恐ろしくなり、今はそういったページは一切見ていない。
本や雑誌は頭と目が疲れてしまうし夜の消灯の後は読めなくなる。
ケータイは消灯のあと、眠れないときに暇が潰れるので良かった。
主にゲームをすることが多かったが、妻や友人たちにメールをするのも日課になった。
友人たちには見舞いに来て欲しくないと強く伝えてあるので誰も来ない。
俺はもう、入院する前の俺ではなかった。
こんな姿を友人たちにさらす気にはならなかった。 寝ているだけなのに二ヶ月で十五キロ以上体重が減り、顔貌が変わった。
だからメールが一番良かった。メールなら以前のように話せる。
俺は三十五歳のとき脱サラしてコーヒーショップを始め、最近ちょうど二店舗目を出したところだった。
妻は店に通って来ていた客のひとりだった。結婚したのは三年前だ。
俺にとっては初婚だったが、小学校で教師をしている妻は再婚で連れ子がひとりいた。連れ子とは言っても、もう大学生で、親元を離れて生活しているのだが。
俺は三男坊で、高校生のときに母親をがんで亡くしている。
母親は胃がんだったのだが、俺は体質が似たのかもしれない。
父親は生きているが、認知症が始まっており、一緒に住んでいる兄貴は俺の病気のことを伏せておいているらしい。
俺もそれでいいと思う。
自分の息子がもうすぐ死ぬなどということがわかったら、余計に認知症が進んでしまう可能性もある。
俺はこれまでよくやってくれていた店員に店の権利を譲ることにした。
場所もよく上手くいってる店なのでまだまだ続けられるはずだ。
そんなわけで、俺はもう後の人生は死ぬだけになった。
普通は誰だって死ぬのは嫌だろう。
俺だって嫌だ。
自殺するやつに、寿命をわけてもらいたいと真剣に思う。
この息苦しさもわけてやりたいと思う。
調子が悪いときは苦しみに耐えるだけで何もできない。
いくら胸水をとってもすぐに溜まる。
薬や点滴でいくらか楽になるとはいっても、すべてが消えるわけではない。
俺はもう助からないということは理解したのでせめて楽に死にたいのだが、医者にそう訴えても、
「だいぶ緩和されるはずですがやはり多少はつらいらしいですよ」
などと慰めにもならないようなことを言われる始末で、気分が荒れることも増えた。
俺は孤独だった。
妻は毎日のように病院へ来てくれるが、俺の気持ちや体の辛さは、妻になどわかるわけがないと思った。
現に妻は、一時退院したいという俺の希望を汲んでくれなかった。
酸素の機械を持ち込めば一週間くらいならなんとかなりそうだったのに、仕事も休めないし家で世話をする自信がないというのだ。
俺は心底がっかりした。
まぁでも妻だって、本当は仕事を休みたいのに休めないのかもしれないし、病院での俺の様子を毎日のように見ていれば、家でひとりこんな状態の俺の世話をすることに恐れをなす気持ちもわからないでもない。
そう思えば仕方のないことなのだ。
俺はそう思うことにしたが、妻との間に心の距離ができたことは確かだった。
俺が入った部屋は末期の患者だけを集めたところらしいが、噂ではもう一段階あって、危篤に近い状態になると個室に移されるという話だった。
言われてみれば、俺がこの部屋に入ってから、何人かがすでにどこかへ移動していっている。
交流もないからあまり関心もなかったのだが、行ってしまった患者がここへ戻って来ることはなかったから、おそらくそういうことなのだろう。
そんなある晩、いつものように目が覚めてしまい寝付かれず、ケータイでゲームをしていた俺は、薄明るい病室の中でふと人の気配を感じた。
病院なのだから看護師の見回りもあるし、夜中だってひっきりなしになにかしら動きはある。
人の気配があること自体は全く不思議でもなんでもない。
でも、なんだか妙に気になった。
その晩は、消灯のあたりから静かだった。
いつも夜中に騒ぎがちな同室の若い男は、昼間になにやら大掛かりな処置を受けたらしく、強い薬を飲んででもいるのか、ずっと眠っているようだった。
俺はゲームに夢中になっていたので、最初は気がつかなかったのだが、どうやらその男のところに誰かが来ているようなのだった。
そして小声で、何やら会話をしていた。
男は普通に話していた。
男が普通に話をするのを、俺は初めて聞いたような気がした。
俺はちょっと様子を見てみたくなった。
大部屋だが、ひとつひとつのベッドはカーテンで区切られており、昼間は開け放しにしておくが夜は閉めることが多かった。
俺はそうっとカーテンをつまみ、隙間からのぞいてみた。
男のベッドは斜め向かいにある。
この部屋はスペースを広く取ってあり、斜め向かいといってもわりと離れている。
しかし見えないことはない。
男のベッドのカーテンは一部開けられた状態で、看護師の後ろ姿が見えた。
(なんだ、見回りか)
そう思ったが、ふとなんだかいつもと様子が違うような気がして、俺はもう一度よく見てみた。
そして気がついた。
看護師の、白衣の色が違うのだ。
この病院の看護師たちは、薄いベージュ色の白衣を来ている。そして同じ色のキャップも被っており、足元は白のスニーカーだ。
しかし、目の前で背中を向けてる看護師の白衣の色は、一瞬白に見えたのだがよく見ると、薄いグレーだった。
そして靴は黒いローヒール。
そんな看護師は見たことがない。
少なくともこの病院では。
俺が不思議に思いながら見ていると、その看護師がくるりと振り向いて、俺を見た。
(音は立てていないはずなのに、どうして気がついたんだろう)
俺は慌ててカーテンを閉めた。
すると靴音が近づいて来て、カーテンがめくられた。 薄いグレーの白衣を来た看護師は、若いきれいな女だった。
薄暗いところで見たせいかもしれないが、ずいぶん肌の色が白く見えた。
目の色も薄く、全体的に色素が薄い感じ。でも、ナースキャップにまとめられた髪の毛は、黒く艶があった。
この病院では初めて見る顔だった。
が、なぜか初めて会ったという気はしなくて、昔どこかで会ったことがあるように感じた。
「何してるんですか?」
看護師は明るい調子でたずねてきた。
「ゲームですよ」
「どんなゲームですか?」
「こういうのですよ」
俺はケータイの画面をその看護師に見せた。
「あ、これ知ってます。楽しいんですよね、ガーデニングとか農場経営のゲーム」
「今ちょうど、バラの花が咲くところなんですよ」
「あっ、咲いた!バラってけっこう時間かかるんでしょう。三十時間くらいですか?」
「三十六時間らしいですよ。でも肥料をやって短縮してるんですけどね」
このガーデニングゲームというのは、ケータイの中で花を育てるというものだ。
種をまき、ゲームの設定に従って水や肥料をやっているうちに花が咲く。ただそれだけといえばそれだけのゲームだ。
俺は看護師とそんなどうだっていいことをしゃべっていて、不意に気がついた。
苦しくない。
痛くない。
こんなはずはないのに。
いくらでもしゃべれる。
俺はうれしくなりしゃべり続けた。
「でもね。俺、このゲームやってて花が咲くたび、最近時々思うんですよ。何しろ三十時間くらいかかるから、ああ今回も花が咲くまで俺は生きていたんだなぁって」
看護師はにこにこ笑って聞いていた。
普段は、あまりこういうことは言わないことにしているのだが、なぜかこの看護師には気軽に話せた。
「まだ、大丈夫ですよ。もうしばらく」
「そっか。もうしばらく、大丈夫なんですか」
「うーん、もうちょっと、かな」
「しばらくじゃないんだ。ちょっと、なんですね」
俺はなんだかおかしかった。
こんなことを言う看護師は今までいなかった。
でもほんとうは、こんな風に普通に、残り少ない日々のことを誰かと話したかったのだと俺は思った。
「それじゃ、おやすみなさい」
看護師はカーテンを閉めると、再び斜め向かいの男のところに戻っていった。
俺はなんだか気になって、またそっとカーテンの隙間からのぞいた。
看護師は男になにやら話しかけると、男の頭のほうに回った。
すると、部屋の中にゴトン、という重い音が響いた。
看護師は、ベッドを壁から外したのだった。
どこでもそうなのか、ここだけなのかは知らないが、この病院のベッドは簡単に壁から外すことができ、手術のときなどは、患者たちはみな寝ていたベッドごとコロコロと運ばれて行くのだった。
しかしこんな夜中に手術というわけでもあるまいし、と思ったが、
(そうか、あいつは個室に移動させられるのかもしれない)
そう気がついた。
看護師が男の寝ているベッドを押し、廊下まで出ていくのを、俺はカーテンの隙間からずっと眺めていた。
次の日の朝検温にきたいつもの看護師に、俺は昨夜のことを話してみることにした。
が、夜にはあんなに体調が良かったのに、朝になったら体中の倦怠感や痛みがひどく、ろくにしゃべることもできなかった。
俺の話はわかりにくかったと思うが、看護師は一応最後まで聞いてくれた。
「グレーの白衣?そんなのこの病院にはありませんよ。それに、黒いローヒールの看護師なんかいるわけないですよ。ここは、わたしたち看護師はベージュで、ドクターや技師さんたちは真っ白って決まってるんです。それに、斜め向かいの大谷さんなら、今もこの部屋にいますよ。夢を見たんですね」
看護師は忙しいのか、せわしなくそう言った。
きっと俺の話など、夢でも見たか幻覚だろうと思っているんだろう。
そういえば医者も、そろそろ少し強い薬を使うと言っていたから、そのせいだとでも思っているのだろうか。
そうなのだろうか。
夢なのだろうか。
そういえば本当は、俺はここ何日も、ケータイなど触っていない気がする。
なんだか最近、時間の感覚がちょっとへんだ。
ケータイの充電なんかはどうなっているんだろう。
斜め前の男は、やはり今朝もいるようだった。
が、昼過ぎころおかしな声がしたと思ったら暴れ始め、看護師や医者が集まりちょっとした騒ぎになった。
そして男は本当に、その日のうちにこの部屋からどこかへ運ばれていってしまった。
男は戻って来なかった。
俺もそのあとしばらくして、個室へ移された。
その頃から、本当に時間の感覚がへんになってきていて、妻がいつ来て帰っていったのか、よくわからなくなった。
兄貴たちやその家族も訪れるようになった。
起き上がることができず寝たきりになり、持続的な息苦しさが例えようもなくつらかった。腹に穴をあけられ、水も栄養もそこから入れられていた。
いつのまにかつけられていた酸素マスクがうっとうしく外したかったが、あるときから俺の手は動かなくなっていた。
ベッドに縛り付けられたのだ。
ろくに声も出ないのに、
「助けてくれ、ほどいてくれ、苦しいんだ」
と何度も俺は叫んでいた。しかし妻はほどいてくれるでもなく、隣で泣くだけだった。
それに喉が渇いて仕方がなかった。
そばにいる妻に水をくれと頼んでも、霧吹きで唇を湿らせてくれるだけだった。
俺がいくら水が欲しいと訴えても、
「口から水を飲んだら死んでしまうのよ」
などと妻は涙声でいうのだった。
全然わかっていない。
どうせもうすぐ俺は死ぬっていうのに。水を飲んだら死ぬっていうけど、飲まなくたってもうすぐ死ぬんだ、それでも飲ませてもらえないのか。
しかし俺にはもう、妻にそんなことを訴える体力も気力もなかった。
眠っている時間が多くなった。
起きてもただ目を開けているだけだ。
目を閉じていれば眠っているようにしか見えないらしく、あるとき、見舞いに来たらしい兄貴と妻の会話が聞こえてきた。
「式場の下見なんかは済ませましたか」
「ええ、昨日行ってきました。旦那さんの写真を準備してくれって言われたんですけどなかなかいいのがなくって」
なんだ、俺の葬式の相談か。気が早いな。
いやそうでもないのか。
目が覚めたら夜だった。側には誰もいない。
いつかのように、静かな夜。
俺はただ、ぼうっと目を開けた。
すると、どこからか足音が聞こえてきた。
その足音は俺のいる個室の前でピタリと止り、ドアが開いた。
静かだが、はっきりとした足音だった。
その足音は俺の方に近づいてくる。
そしてカーテンがすうっと開けられた。
グレーの白衣に、ナースキャップ。色白の顔に黒い髪。
あの看護師だった。
彼女は、俺の手の拘束をほどき、酸素マスクを外してくれた。
「具合はどうですか?」
「いいわけないでしょう」
そう言いながら俺は驚いた。
あのときと同じだ。
不思議と、つらくない。
へんに体が軽い。
しゃべることができる。
「それはそうですよね。あ、そうそう。そろそろ、別のお花が咲いてるんじゃないですか?あの、ケータイのゲームで」
「ああ、どうなりましたかね。最近具合が悪すぎて見てなかったんですけど」
彼女はベッドサイドのテーブルに置いてあった俺のケータイを開いた。
「わあ、咲いてますよ」
彼女はうれしそうに言った。
俺もつられてのぞき込んだ。
咲いていたのは、白いユリの花だった。
「きれいですね」
「あはは。ゲームですけどね」
俺は久しぶりに笑った。
どうしてだろう。不思議で仕方がなかった。
どうして苦しく無いんだろう。笑うことができるんだろう。
そうこうしているうちに、彼女は俺の腕についていた点滴の針も、
「このほうがすっきりするでしょ」
などと言いながらすべて外してしまった。
そして言った。
「そろそろ、いいかしら。ちょっと、苦しいかもしれないけれど」
彼女がにっこりしてそう言った途端、いきなり激しい発作が起った。
発作というか、息が全く吸えなくなったのだ。
急に俺の回りから、空気がなくなったみたいだった。 俺は苦しさのあまり必死で暴れまくった。
そして回りから空気が消えたと思ったら、俺はビニールに包まれており、そばには巨大な掃除機が現れた。 それがものすごい勢いで、まるで布団でも圧縮するみたいにビニール内の空気を吸い込むので、俺はあっという間に真空パックにされてしまった。
もう限界だ。
痙攣しながらそう思った時、彼女が大きなハサミでビニールを切り裂き、俺を救い出してくれた。
「ごめんなさいね。つらかったでしょ」
彼女はすまなそうに言った。
そうして、俺をゆっくりとベッドに寝かせた。
俺はもう苦しくも痛くもなかった。
「ほんとにごめんなさいね」
そう言いながら彼女は俺の胸にそっと手を当て、何度も優しく撫でてくれた。
すると苦しかった胸がすうっとして、まるで健康だったときのように楽になっていくのがわかった。
俺は彼女を見つめていた。
そのとき、俺はふと気がついた。
(母さん)
誰かに似ている、どこかで会ったことがあると思っていたのだが、彼女は母親とよく似ていたのだった。 高校生の時、がんで亡くなった母親に。
「さあ、一緒に行きましょうね」
彼女はそう言うと、俺の頭のほうへ移動し、壁からベッドを外した。
月明かりだけの暗い部屋に、ゴトン、という重い音が響いた。
そして、押しながら歩き始めた。
まるでベビーカーでも押しているみたいに、その足取りは軽やかだった。
俺はベッドごと部屋から出た。
そして、夜の病院の中を、どこまでも運ばれていった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- アニメ!!
- 【中古】 幻魔大戦(Blu-ray…
- (2024-11-14 14:54:38)
-
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 電脳お絵描の館...第103の扉
- (2024-11-30 06:30:11)
-
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 経済用語イラスト図鑑 改訂版
- (2024-12-01 00:00:29)
-
© Rakuten Group, Inc.