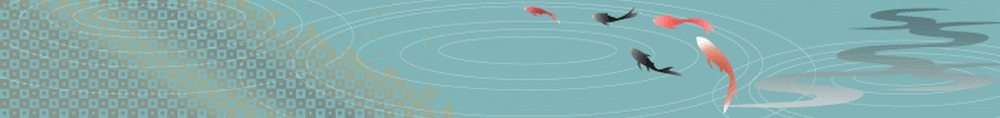小説「赤い呪縛」
『赤い呪縛』
クラスメイトの相馬光子嬢が不良にからまれていた。どうするべきか考えていたら俺までからまれた。軽く腕を払っただけなのに、相手が勝手によろけて転倒。その先に、窓。そして、がしゃん。
ガラスもサッシも壁も床も相手も、駆け寄って床に膝をついた俺の制服も掌も指先も、一面の赤。
出血のワリにはずいぶんと軽いケガだったらしい。だからと言って、それで俺の気が晴れるわけじゃない。後味はかなり悪い。
何度洗っても、指先の汚れがとれない。肉と爪の間の赤黒い汚れ。あの、血。シャープペンシルの先で浚ってみる。それでも、まだそこに赤いものが溜まっていた。
フェンスにもたれかかる俺の前に相馬嬢が立っていた。
「爪、大丈夫?授業中、ずっと気にしていたでしょう?」
「まだ血が残っているような気がするんだ」
苦笑する俺の手をとり、相馬嬢はゆっくり身を屈めた。
「剥いでしえばいいのよ、爪」
唇から真珠のような歯がこぼれ、俺の爪を噛む。
「貴方の血が洗い流してくれるわ」
冗談よ。笑いながら相馬嬢は体を離し、胸ポケットから小さな瓶を取り出した。赤いマニキュア。
「これで見えないでしょ。これがあたしの呪縛。血の呪縛より強力な呪縛」
ブラシが爪の上を走る。その爪と同じ、赤い唇が笑みを浮かべる。
「あたし、まだ言ってなかったわね」
「何?」
「助けてくれてありがとう。嬉しかった」
そう言ってくるりと身をひるがえす。走り出す相馬嬢の長い髪が風に泳ぐ。
空を見上げると単調な青しかなかった。なんだか物足りなくて赤い爪を空にかざしてみる。澄みきった青と鮮やかな赤のコントラスト。キレイすぎて、眩しすぎて目を閉じる。
それでもまぶたの裏に赤い色があった。相馬嬢の唇の、赤。
気がつくと爪の間の血なんかどうでもよくて、第一もうどんな色だったかも思い出せなくなっていた。
「なるほど、大した呪縛だ」
だけど俺の心は完全に相馬嬢の色に侵食されていた。この呪縛はどうしたら解けるのだろう。
© Rakuten Group, Inc.