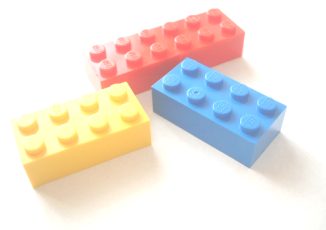アンコール
彼女は優雅に会釈をして、舞台の袖へと退出していった。
いつもながら、鮮やかな演技。
私のあの人を奪った時も、今のように完璧な一人芝居だったのでしょうね。
小さな素人劇団の団長と、衣装係の私。
いつの間に恋人になっていたのかなんて、本人たちにもわからないくらい自然に。
ブツブツと台本読みをして台詞を検討しているあの人の傍らで、
私は無津に針を動かし続けていた。
その頃の私、デザイナーという夢に挫折していて。
あと半年で終わるはずの学校にも、あんまり行かないで、
あの人の部屋の片隅にじっとしていた。
ささやかな幸せ。
彼女が来るまでは。
大学で本格的な演劇を学んでいるという、
容姿も艶やかな彼女が何故うちの劇団を選んだのか、今でも納得できない。
けれど、彼女は入団した。
そして、当然のように主役を得た。
稽古ではそう目立つこともなく、ただのお嬢さん役者なのだと、
団員の誰もが思っていた。
だが、舞台に立った彼女は、まるっきりの別人。
ひらひらと舞い、踊り、セイレーンのように歌って観客をひきつけた。
いいえ観客だけではない。
団員の中の男性は、すべて彼女に魅了された。
本物のセイレーン。
私はそう感じた。
でも、あの人だけは、彼女を見なかった。
その事実に私は満足し、彼女を引き立てる美しいドレスに、針を通し続けた。
けして表舞台に立つことのない、不美人の私にふさわしい役回り。
裏方を演じることに、不満は持っていなかった。
ある日、部屋の洗濯物の間に、女物のピアスが刺さっていた。
うちの劇団で、こんな高価そうなダイヤのピアスをしている女なんて、彼女以外にいない。
それが、彼女の宣戦布告だった。
あの人を問い詰めたりはしなかった。
熱くなったほうが負け。
今は信じるしかない。
しがない三流劇団の団長にいつまでも固執するほどに、
彼女が情の深い女だとは思えないから。
彼に飽きて離れるまで、じっと待ち続ければ終わること。
自分に言い聞かせながら、外泊の増えていくあの人を、
針を動かしながら待ち続けた。
彼女のためのドレスは、血の色に染まっていった。
ある公演で、彼女の演技が一流プロデューサーの目に留まり、
TVドラマの準主役に抜擢されることになった。
彼女が退団の挨拶をしに稽古場に現れた時、あの人は詰った。
何故ここの劇団ではいけないのか。
TVなどという薄っぺらなメディアに賭けるのか。
その様子は、あからさまに恋する男の狂乱だった。
私は見るに絶えず、扉をそっと明け、稽古場から逃げ出した。
彼女は優れた演技と存在感で、一躍脚光を浴びた。
映画にも出たし、大劇団の客演も務めるようになった。
私は、あの日からあの人の部屋には帰らなかった。
荷物も作りかけの衣装も、すべて置き去りにして。
彼女に捨てられた男が、身代わりに私を求めるのか、
さもなくば私すら捨て去って逃避していくのか。
どちらの結論も、見たくはなかったから。
劇団にも行かなかった。
もともと私の役なんて、いくらでも代役がいるのだ。
無理して落ちぶれていく姿を見に行かなくてもいいはず。
セイレーンからの電話。
私も魅力にとりつかれた。
「今度、一人芝居をやるのよ。だから、演出も好きなように出来るの。
私の衣装をお願いできるかしら」
今の彼女なら、有名なデザイナーに衣装を特注させたところで、
スポンサーに困ることはない。
それなのに、地味にお針子生活をしている、私に白羽の矢を立てるなんて。
断らなくちゃいけないと思いつつも、セイレーンの声は理性を遠ざけた。
打ち合わせをし、デザイン画を起こし、白い優美なドレスを縫い上げた。
彼女と会う機会は何度もあった。
その度にあの人のことを訪ねようとしては、言葉を呑み込んだ。
劇団の公演の噂すら聞いていないのだもの。
もう演劇を辞めてしまったのかもしれない。
あの人から劇団を取ったら何が残るのかは知らない。
セイレーンの声は魔女の声。
魅せられた船乗りたちは、座礁すると知りつつも
彼女めがけて船を漕ぎ続ける。
水面に沈むその瞬間まで、セイレーンは優しく歌うのだ。
歓喜の表情のまま、船乗りは永遠の国へと旅立って行く。
衣装は監督たちにも好評を博し、舞台の上の彼女を彩っている。
ウェディングドレスを身にまといながら、一人で舞台に立つ彼女。
彼女の夫は、数多の俳優たち。
脚本たち。
舞台たち。
決して一人の男のものになる日は来ない。
もしも私が彼女だったら。
セイレーンの歌をあの人に歌えただろうか。
あんなにもひたむきに、自分の小劇団を愛している人に。
取り返しのつかない深手を負わせる程、自分を愛せただろうか。
セイレーンの愛するのは自分一人。
それを知っているのに、私は彼女の衣装を作る。
もう、自分の意思はない。
女神と運命を共にする以外、残された道はないのだ。
拍手はいつの間にか、アンコールへと変わった。
偉大なる女優へと、魅惑の魔女へと。
アンコールの声は響き渡る。
つかの間の、仮初めの舞台だから、観客はセイレーンの歌声に気づかない。
彼女の人生のステージに立たされたものだけが、彼女の本性を知っている。
そして、逃れられない魅力に自分を失っていく。
もう、あの人がどうしているのかなど気にかけることもない。
私は楽屋に飛び込んできた彼女に、新たな舞台衣装を着せると、観客の前へと送り出した。
私のセイレーン。
いつまでもアンコールを続けよう。
あなたが望む限り。
© Rakuten Group, Inc.