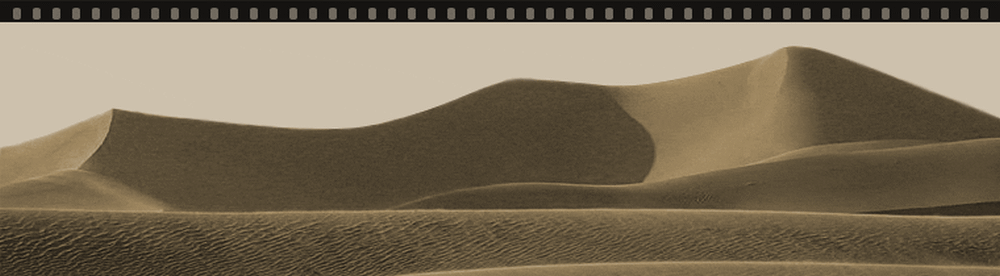■24節気名称■
★24節気名称★日本には季節を24に分けて表す美しいことばがある。
それが24節気である。
春夏秋冬の移ろいに恵まれた風土である喜びを感じる。
24節気とは太陽年を太陽の黄経に従って24等分して季節を示す言葉である。
その等分点の中で日の一番長い日を夏至、一番短い日を冬至とし、等しい日を春分、秋分と名付けている。
これは月に2回ずつあり、例えば1月は小寒(1月6日頃)、大寒(1月20日頃)、2月は立春(2月4日頃)、雨水(2月19日頃)、3月は啓蟄(3月6日頃)、春分(3月21日頃)である。
啓蟄とは冬ごもりの虫がはい出る頃という意味である。
見事に季節感を表している。
この24節気も暖冬が続くと、小寒、大寒はなくなってしまう。寒さがこないと虫も冬ごもりしなくなるかもしれない。
24節気は春夏秋冬がはっきりしていればこその名前である。
松下電器産業株式会社環境保護推進室室長 吉村孝史
01.立春(りっしゅん)
・・・・・立春とは,もうこれ以上は寒くならない。これからは春の気配が感じられるようになる。(2月4日)
02.雨水(うすい)
・・・・・雨水とは、雪や霙(みぞれ)に変わって雨が降る様になる季節と言う意味です。(2月19日)
03.啓蟄(けいちつ)
・・・・・啓蟄とは、土中にこもっていた虫たちが春の陽気を感じ取って姿を現す頃とされています。(3月6日)
04.春分(しゅんぶん)
・・・・・春分とは、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。この日を中日にして、前後3日を合わせた7日間を春の彼岸と言います。「暑さ寒さも彼岸まで」(3月21日)
05.清明(せいめい)
・・・・・清明とは、草木清風に逢い桜花爛漫、風光明媚になり、万物清新の気満つる季節の儀。(4月5日)
06.穀雨(こくう)
・・・・・穀雨とは、「雨が降って百穀を潤す」という意味から来ている言葉で、この時期は春雨が降る日が多くなり、田畑をうるおしてその成長を助け、穀物には適した時期。(4月20日)
07.立夏(りっか)
・・・・・立夏とは、山野に新緑が目立ち、吹く風もだんだん爽やかになって夏の気配が感じられる時期。(5月6日)
08.小満(しょうまん)
・・・・・小満とは、陽気が良くなって草木などの生物がしだいに成長して生い茂る時期。(5月21日ごろ)
09.芒種(ぼうしゅ)
・・・・・芒種とは、芒のある穀物、すなわち稲を植えつける時期。(6月6日ごろ)
10..夏至(げし)
・・・・・夏至とは、北半球で昼間の時間が年間で最も長い日(6月2日)
11.小暑(しょうしょ)
・・・・・小暑とは、本格的な暑さが始まる時期(7月7日ごろ)
12.大暑(たいしょ)
・・・・・大暑とは、一年のうち最も暑いときと言う意味。
13.立秋(りっしゅう)
・・・・・立秋とは、暦の上で秋が始まる日。秋の気配が感じられる。(8月8日ごろ)
14.処暑(しょしょ)
・・・・・処暑とは、暑さも峠を越え収まる頃。 (8月23日ごろ)
15.白露(はくろ)
・・・・・白露とは、草木に露がおり始めるころ。 (9月8日ごろ)
16.秋分(しゅうぶん)
・・・・・秋分とは、秋の彼岸の中日。昼と夜の時間が同じ (9月23日ごろ)
17.寒露(かんろ)
・・・・・寒露とは、晩秋から初冬にかけて草木の葉に結ぶ露のこと。(10月9日ごろ)
18.霜降(そうこう)
・・・・・霜降とは、夜間の冷え込みが厳しくなり、霜が降り始めるころ(10月24日ごろ)
19.立冬(りっとう)
・・・・・立冬とは、冬の気配を感じられるようになるころ。雪の便りも聞かれる(11月8日ごろ)
20.小雪(しょうせつ)
・・・・・小雪とは、寒さがまだ深まらず、雪もまだわずかなころ(11月22日ごろ)
21.大雪(たいせつ)
・・・・・大雪とは、北風も次第に強く降雪が多くなるころ(12月7日ごろ)
22.冬至(とうじ)
・・・・・冬至とは、昼の長さがもっとも短く、夜るが長い(12月22日ごろ)
23.小寒(しょうかん)
・・・・・小寒とは、寒気が激甚とまではいかないが、寒さの厳しいころ(1月6日ごろ)
24.大寒(だいかん)
・・・・・大寒とは、一年中で一番寒さの厳しいころ(1月21日ごろ)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- M.シュナとの生活♪
- シュナウザー保護活動ボランティア
- (2023-07-02 18:37:16)
-
-
-

- ☆動物愛護☆
- 1周年(⋈◍>◡<◍)。✧♡(⋈◍>◡<◍)。✧♡…
- (2024-04-12 02:08:31)
-
-
-

- MIX(雑種)だってかわいい!
- 今月も美味しく予防だ ▼・。・▼」」」」ーワ…
- (2024-06-06 12:12:07)
-
© Rakuten Group, Inc.