[欧米露の本] カテゴリの記事
全57件 (57件中 1-50件目)
-

「日本の弓術」 【オイゲン・ヘリゲル 述】
再読。 初めて読んだのは20年近く前だったと思う。 覚えていることもいくつかあった。 「述」というのは、書いたものではなく、講演したものだから。 ドイツ人哲学者が、大正末から昭和にかけて五年間滞在し、東北帝国大学で教える一方、道場で弓道を学んだ経験から、日本文化の一端を紹介したもの。 技術論ではなく精神論であり、文化論である。 ただ、最初から「禅」の文化が日本を覆っているという先入観があるようで、合理的精神では理解できないものとして受容しようとしている。 たとえば、日本人は、自分でそれを説明できるかどうかは別として、禅の雰囲気、禅の精神の中で生活している。(p17)というところにそれを感じる。 あるいは、ヨーロッパ人には理解できない論理を「禅」と呼んでいるだけなのか。 絶望的な気持ちになるのは、言葉だけ翻訳してもその本質を知ることはできない、というところ。 わたしは、日本語以外の言語で書かれたものは、翻訳したものでなければ読めない。 しかし、それは表面を置き換えただけのものであり、それによって本質を理解することができるかどうかというと、単に技術を説明したものででもないかぎり、おそらくできないのだろう。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2013.03.24
コメント(0)
-

『図説「最悪」の仕事の歴史」 トニー・ロビンソン
日暮雅道・林啓恵 訳。 ヨーロッパ、特にイギリスにおける、「最悪」と思われる仕事の歴史。ローマ時代から19世紀の終わりまで。 汚物の処理であったり、動物の皮革の処理であったりというのが多い。 ヨーロッパ裏面史を書こうとしているのかというとそうでもない。 全体の「のり」が、テレビのバラエティ番組のようなのだ。 イギリスのテレビ番組やタレントが引き合いに出されることが多い。 こっちは「モンティ・パイソン」ぐらいしかしらないのに。 最後まで読んでやっとわかった。 もともとがテレビ番組なのだ。 なるほどなあ。どうもイギリス人の考えることはわからない、と改めて思ったのだった。 子供の時に読んだ「水の子トム」のことがちょっと出てくる。 この本の中では、「水の子どもたち」となっている。 昔は理解できなかった社会背景のある話のようだ。 読み直してみたくなった。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2012.01.18
コメント(0)
-

「たのしい川べ」 【ケネス・グレーアム。石井桃子 訳】
初めて読んだ。 不思議な話である。 最初に出てくるモグラが主人公なのかと思うと、そうではない。川ネズミやガマガエルやいろいろな生き物がその時その時で中心になる。 強いて何に似ているかというと「水滸伝」に似ている。 前編を杏がレルテーマがあるわけでなく、行き当たりばったりに話が進む。 モグラは、川根済みのボートをこいでみようとして軽はずみな行動をとったりするのだが、終わりの方では思慮深く有能になっている。 しかし、それを不自然に感じさせない。 動物だけが出てくるわけではなく、人間も出てくる。 人間と動物が共存していて言葉も通じるのだが、同じ世界にいるようでもない。 簡単には説明のできない不思議な世界の物語なのだ。 「訳者のことば」によって、その成り立ちを知ってやっと納得できた。 終始一貫している必要はない話なのだ。 2002年初版ということなのだが、石井桃子の訳文はやや言葉が古い。一分は一分と、ヒキガエルは、むしゃくしゃしてきました。(p293) この「一分は一分と」という表現は初めて目にした。二か所出てくる。 子供も大人も読める非常に興味深い本である。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2011.11.03
コメント(0)
-
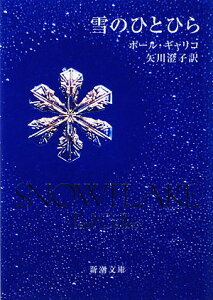
「雪のひとひら」 【ポール・ギャリコ。矢川澄子 訳】
雲から水となり海に注ぎ再び雲となる水の循環を擬人化したものは多いことだろう。 わたしが子供に読んでやったものでは、「しずくのぼうけん」が記憶に残っている。 この本も、そういう系統のものなのだが、大人向けの本だ。そして、際立っているのは、主人公が女性に設定されていることだ。 雪として地上に舞い降り、水になって川を流れる。 それだけではない。結婚出産まで経験する。 夫となる「雨のしずく」の言動はいかにもアメリカらしい。 キリスト教的な創造主の存在を感じてはいるが「神」とは言わない。 「再生」を予感させつつ物語は終わる。 水を擬人化したものではなく人生を水になぞらえた物語なのだ。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2011.06.25
コメント(0)
-

「ぎざ耳ウサギの冒険」 【シートン。藤原英司 訳】
いわゆる「シートン動物記」。もっとも、本人はそんなシリーズものとして書いたつもりはないらしい。 「ぎざ耳ウサギの冒険」「黒いくり毛」「あぶく坊や」「ビリー」が収録されている。 このうち、「ぎざ耳ウサギの冒険」と「あぶく坊や」は読んだ記憶がある。ほかの二作も読んだのかもしれないが何も覚えていない。 イノシシがガラガラヘビの毒に対して耐性を持っているというのはよく覚えている。(事実かどうかは判らないけれど) 解説によると、「黒いくり毛」は、発表された後、その馬に関わった女性からの手紙を受け取ったりしたそうだ。 擬人化するのではなく、動物を動物としてそのまま描くということが斬新だったのではないだろうか。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2011.05.13
コメント(0)
-

「不思議な少年」 【マーク・トウェイン】
地震で本棚の本が散乱した。片付けていたら出てきたのがこの本。 30年ぐらい前に古本屋で130円で買った旧版。 元々の定価は「☆☆」で200円。その昔、岩波文庫は☆と★で値段を現していた。 表紙もパラフィン紙。 実は、買ったまま読んでなかった。思わぬ再会を機会に読んでみた。 1590年のオーストリアが舞台。 少年たちの前に現れた謎の少年。なんと「サタン」と名乗る。 少年たちを幸せな気持ちにさせるのだが、人間の「良心」をあざ笑い、人間の非人間性を否定する。 その特別な力で村人にも影響を及ぼすが、不幸にしたように見えてもそうではないということもある。 何が幸福なのか、人間らしさとは何か、宗教には価値があるのか。 ほとんどの人が疑いもしなかったことに疑いの目を向け、否定する。 人間の「進化」もそうだ。キリスト教と文明とが、いつも手を組んでやってきたことはよくわかった。そして、「そのあとには、つねに飢饉と死と荒廃と、そのほか(さたんの言葉によれば)すべて人類の進歩の証拠であるものをのこしてきた」のである。(p144)と言い切っている。キリスト教と文明の否定である。 よくこんなことを書いて無事でいられたな、と思ったら、解説によると、生前には発表していなかったのだ。 最後は非常に観念的に結ばれている。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2011.03.26
コメント(2)
-
「初恋」 【ツルゲーネフ。米川正夫・訳】
初恋 有名な小説だが初めて読んだ。 中年男性が、自分の初恋を思い出して記したもの、という体裁になっている。 それを人に読ませたということなのだろうが、読んだ人の感想があるわけではない。 年上の女性への初恋と、その女性の恋人を知った時の衝撃。その後の複雑な思い。 印象的な物語ではある。 19世紀のロシアの貴族の生活というのがどういうものなのかさっぱり想像がつかないので映像としては浮かんでこない。 作者が詩人であることからすると、おそらく、詩的な文章を味わう小説なのだろう。 岩波文庫は表紙に紹介文が書いてあるのだが、そこではっきりとネタバレになってしまっている。主人公が衝撃を受けるところはさほど重要ではないということなのだろうか。 読んだのは、1933年4月15日第1刷、1960年8月5日第14刷改版、1995年7月15日第64刷のもの。 もう70年以上前の訳なのだ。 やや古くは感じるが、自然な訳文だ。 「弄媚女《コケット》」(p71)は訳者の造語だろうか。 「痙攣的《けいれんてき》に」(p88)は珍しい表現だ。「痙攣しながら」ではなく「痙攣的に」と訳したくなるような原文なのだろうか。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2009.02.18
コメント(0)
-
「恋のかけひき」 【マルキ・ド・サド。澁澤龍彦・訳】
角川文庫。1983.9.20初版。1978.4.20第9版。 サドの短編小説集。 宗教を否定してはいるが、欲望のままに生きることを肯定しているわけではない。 その結果不幸になることだってあるし、かえって幸福になることもある。 世の中、理論の通りにはならないのだ。 真実はそれぞれの人間の中にある。 肉体を描いているようであって魂を描いているのであるが、その方法が過激なのである。 収録作品「ファンクスランジュ あるいは 野心の罪」「ロドリグ あるいは 呪縛の塔」「オーギュスチィヌ・ド・ヴィルブランシュ あるいは 恋のかけひき」「寝取られ男 あるいは 思いがけぬ和解」「司祭になった男」「ロンジュヴィルの奥方 あるいは 仕返しをした女」「二人分の席」「プロヴァンス異聞」「哲学者の先生」「復讐」「エミリー・ド・トゥールヴィル あるいは 兄の惨酷」「司祭と臨終の男との対話」 訳文が凝っている。ゴエ氏は平静に見せようと努力する。自制する。従妹の手に接吻を与えると、失意の気持ちをいだいて、家を出る。(p16)というところなど、原文がどうなのか知らないが、読ませる訳文である。 もともとが古いものなので、訳文もそれにあわせたものか古い言い回しが目立つ。 たとえば「恋のかけひき」には、「宗旨変え」「初物《はつもの》」「こすっからい」「手入らず」「つと立ちあがり」「こよなく」「男を見やりつつ」という表現が出てくる。 訳者にとっては自然な表現だったのかもしれない。・「刺[月各]《しらく》」(p173) 腕から血を抜くこと。治療法でこういうのもあったというのを何かで読んだような気がする。ただし、ここでは治療ではない。・「譫言《せんげん》」(p223) 「うわごと」のこと。音読みではあまり見られない。イエスがマホメットよりすぐれているのでもなければ、またマホメットがモーゼより優れているのでもなく、はたまたこれら三者が孔子より優れているというのでもないんです。なにしろ孔子は、前の三人が屁理屈をこねまわしていた間に、まがりなりにもある善訓則を口授していたのですから、それだけましと言うべきでしょう。(p228) 18世紀にすでにフランスでは孔子の言葉が知られていたらしい。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ クチコミblogランキング TREview
2008.02.21
コメント(0)
-

「サテュリコン」 【ペトロニウス。国原吉之助】
岩波文庫。1991.7.16第1刷。1993.9.6第4刷 副題は「古代ローマの風刺小説」。 「風刺」といわれても、わたしには古代ローマに関する知識がないので、何を風刺しているのかさっぱりわからない。 まさに酒池肉林の饗宴があったということはわかったが、主人公が何をして生活をしているのかというようなことはさっぱり理解できない。 男も女も欲望最優先という設定であることはわかる。 欲望といっても、出世欲などというものではない。 ほとんど性欲である。男同士と男と女はあるが、女同士というのはないらしい。 ほかの欲望は食欲ぐらい。 セネカの風刺短編「アポコロキュントシス」というのも収録されているが、これまたよくわからない。 古代ローマというと暴君ネロぐらいしか思い浮かばないのだが、「解題」によると、そのネロに関わりのある作品なのだそうだ。 読んでいてずっと気になったのは、これを訳した「国原吉之助」という人は、どういう人なのだろうか、ということだ。 描かれている風俗や、何を風刺しているのか、ということについて、40ページ近い「訳注」が施されている。 これが書かれた時代のローマに精通していなければできないことだ。 ざんねんながら、この本には訳者の紹介がない。 いったいどうしてこういうものを訳せるようになったのか、そちらに興味がわいた。←映画になっているが、見たことはない。 どこまで映像化したのだろう。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ クチコミblogランキング TREview
2008.02.08
コメント(0)
-
「わたしが子どもだったころ」 【ケストナー。高橋健二・訳】
わたしが子どもだったころ。1962.8.18第1刷。1973.10.30第10刷。 ケストナーが、両親の祖先のことから説き起こし、1914年8月、戦争が始まる「わたしの子ども時代《じだい》はおわった」(p238)というところまでの思い出がつづられている。 楽しい思い出よりも、「子どもにも心痛《しんつう》があるという章のように、その内面に陰を残したできごとのほうが多い。 両親は息子を愛している。父も母も、自分のプレゼントの方が息子を喜ばすに違いないと競い合う。しかし、その両親の中がどうだったのかについては触れていない。 母が、結婚前に、姉たちに、「でもわたし、あの人はぜんぜん愛《あい》していないわ!」(p52)と語ったということが述べられているだけだ。 母は一人息子にすべてを注ぎ込む。教師にするために。もちろん本人も教師になることを望んでいる。しかしこれでは、斉藤学の問題にする母親像そのものだ。 その母に向かって、「ぼくは教師《きょうし》にはなりません!」(p93)と宣言することは、ケストナーにとっては必要なことだったのだろう。それがなければ母親におしつぶされていたのかもしれない。(しかし、その宣言も受け入れられてしまうのだから逃げようがない) 「おわりにひとこと あとがき」で、書いたものの削った章があることが述べられている。 そして、思い出を書き記《しる》すには二つの法則《ほうそく》がある。第《だい》一の法則《ほうそく》は、たくさんのことをはぶくことができいる、いや、はぶかなくてはならない、というのである。(p244)と述べている。わざと書かなかったことがたくさんあるはずだ。(第二の法則は、何も付け加えてはならない、ということ) たとえば、衛生参事官チンマーマン先生が、何の説明もなく唐突に登場する感じがするが、この人物についてはいろいろとはぶいてあるのだろう。 表紙に、三歳の時の写真が載っている。その写真の中で履いているのが「編み上げ靴」。「紐付きブーツ」とでも言った方がわかりやすいだろうか。(12月24日読了) 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2008.01.03
コメント(0)
-
「五月三十五日」 【ケストナー。高橋健二・訳】
岩波書店。1962.6.16第1刷。1973.10.30第9刷。 「算数のできる子は空想力がないに違いない」という教師の思いこみによって、南洋についての作文を書かなくてはならなくなったコンラート少年が、リンゲルフート叔父さんと、偶然知り合った馬とともに、ドラえもんのタイムマシンのような装置で、南洋への半日旅行。 その途中で、なまけものの国、偉大な過去の白、さかさの世界、電気の年、赤道を通って南洋にたどり着く。 全体としては荒唐無稽で楽しいものにしたかったのだろうが、まとまりにかける。 最後の作文は、活字ではなく手書きで、誤字もある小学生の作文として訳せればよかった。 巻末に「詩集から」として詩が収録されている。 そのうち「子どもと親」の3作はいかにもケストナーという感じがする。 中でも「最初の絶望」と「マッチ売りの少年」は実話だという。 そもそも、ケストナーの記憶の最初に「絶望」があったのかもしれない。だからこそ、「希望」に目を向けるのだろう。 こういうものを読むと、翻訳は難しい、とつくづく感じる。 訳されてから40年がたち、今では使わない言葉、ほかの言い方の方がわかりやすい言葉が目につく。 「球軸受《たまじくう》け」(p46)は「ベアリング」 「露台《ろだい》」(p53)は「バルコニー」 「心おぼえ」(p111)は「メモ」 「小アジア」(p65)は最近は聞かない語だ。 「あみあげぐつ」(p107)は、子どもの頃から、ヨーロッパの小説に出てくるのを読んで、どんなものか不思議に思っていたもの。 今では、どういうものかわかるが、何かもっと違う呼び方がないのだろうか。(12月21日読了) 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.12.30
コメント(0)
-
「ライラックの花の下」 【オルコット。松原至大・訳】
角川文庫。1958.6.10初版。1994.12.10第33版 「若草物語」のオルコットの小説。 サーカスから逃げてきた、身寄りのない少年が、彼を受け入れた人々の愛の力によって、穏やかな生活を手に入れ、成長する物語。 「愛の力」とはいっても、ただ愛を与えるだけではなく、紳士に育てるための教育も行われるのである。 また、養子として迎えられるわけではなく、家族同様に扱われながらも、給料をもらう住み込みの使用人という形になっている。 1958年の訳なので、訳文になじむまでに時間がかかる。 特に台詞は時代がかったように感じられる。たとえば、あの方は、いつも夏になると、一人お雇《やと》いになるんだが、まだおきまりでないようだから。坊や、牛追いができて?(p49)という具合。 楽しいことばかりではなく、悲しいこともあるし、嫌な思いもする。 しかし、「善」の心を持つ少年として誇りを持って生きている。 最後は何もかもがめでたしめでたし。 フィクションなのだからこれでいいのだ。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.11.03
コメント(0)
-

「カンディード」 【ヴォルテール。吉村正一郎・訳】
山あり谷あり波瀾万丈の物語なのだが、結局のところ何が何だかよくわからない。 作者は17世紀末にフランスに生まれた人物で、「解説」を読んでも、哲学者なんだか小説家なんだかよくわからない人物なのだが、おそらく、そういうものが「職業」としては成り立っていない世界において、思索と文筆によって生活していた人であるらしい。 あらすじだけ見れば、ジョットコースター小説である。 新だと思ったら生きていた、まさかこんなところで偶然に再会するとは思わなかったの連続である。 家柄主義や宗教者の権威というものに対する疑問が提示されているのはわかる。 しかし、「ソチン教徒」「マネス教徒」「痙攣派」「テアト派」などといわれても何が何だかわからない。 おそらく、執筆当時の、柔軟な頭脳を持ったヨーロッパの知識人なら抱腹絶倒するようなことが書いてあるらしい。 そういった、理解できない部分をのぞいても、物語は壮大で、読むものを飽きさせない。 中国の紹介小説のようなところがある。 そして、その結果がどうなるかというと、次の台詞でしめくくられる。「何はともあれ、わたしたちの畑を耕さねばなりません。」 薄い本である。すぐ読める。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.10.24
コメント(0)
-
「あしながおじさん」 【ウェブスター。中村佐喜子・訳】
旺文社文庫。1970.7.1。 昔、旺文社文庫の名作100冊セットのような「特装版」というのがあって、それが我が家にあった。 その中の一冊。 定価210円と書いてある。 最近は聞かないが、今でも、子どもが読むべき定番の一つなのだろうか。 アニメ化されたのは記憶しているが、あまりにも、現代とはかけ離れた世界で、今の子どもには理解できないかもしれない。 「あしながおじさん」は「Daddy-longlegs」という「あしながぐも」そっくりだというところから、主人公が勝手につけた呼び名。その「あしながぐも」のイラスト(著者による)をみて初めて知ったが、これは「ザトウムシ」らしい。へええ、そうだったのか。 遠い昔に読んだ記憶はすっかり消えていて、ほとんど覚えていなかった。 今回読み直して、14歳年下の17歳の少女を見そめて、ということなのかと思ったが、そんなわけはなく、ちゃんと対面して話したことがあれば、主人公は正体にとっくに気づいていたはずだ。 ただ、成績優秀だが、捨て子だったために孤児院にいて、進学ができない少女がいることを知って援助した相手が、あまりにも自分と気が合うので、ということなのだ。 これが書かれたのは1912年。 当時の社会に疑問を抱いた人たちは社会主義に希望を見いだしていたらしい。 社会主義国になったからといって、貧富の差がなくなるわけではないことは、今の世界を見れば分かるが、心ある人なら不条理に思うほど格差があったのだろう。 そして、今でも格差は残っているのだろう。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.09.03
コメント(0)
-
「ガリヴァ旅行記」 【スウィフト。中野好夫・訳】
新潮文庫。1951年7月30日発行。1981年5月15日47刷 子どもの時に、子ども向けの本でリリパット国と巨人国の話を読んだだけなので、その後はどんな話なのか知りたいと思っていたところ、先日、古本屋で見かけたので買って読んでみた。 なるほどこれでは、子どもには巨人国の話までしか読んでも理解できまい。 そもそも、子ども向けに書かれたものではなく、大人、それもかなり自分を客観視できる大人に向けて書かれたものなのだ。 簡単に言えば、「価値観の相対化」なのだが、第2章までとその後ではずいぶん様子が異なる。 第二篇までは、自分が巨人になったら、あるいは禦人の中で暮らしたら、という、視覚的な相対化なので子ども向けに書き直すこともできるのだ。 しかし、第三篇からは、観念的な相対化なので、子どもに理解させることは難しい。 読み進めていくうちに、作者の憤りは諧謔を超えて怒りの爆発になっていく。 もはや、「批評」や「風刺」などどいうレベルではない。「罵倒」である。 スウィフトが見聞した、実社会でのことを当てこする話が多いらしく、訳者による、モデルの説明や、版によって内容が異なるところがあることの説明など、詳細な注釈がついているが、それは無視して読んでいい。 訳者自身も「一般読者諸子にはにはかかる時代のトピック的言及には一切無関心で読んでもらうことを希望する」と述べている。 この小説は、特定の時代から切り離されても価値を失わないということだ。 日本人としては、たびたび日本に言及しているばかりか、実際に日本を訪れたことになっているのが興味深い。本物の旅行記らしく見せるためにそうしたのではないだろうか。 訳文は、今日となっては古めかしく感じられるが、かえって原書の雰囲気に近いのかもしれない。 出てくる言葉には、今日ではお目にかからないようなものもあった。 それについては、いずれ稿を改めて。 楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2007.05.10
コメント(0)
-

「モモ」 【ミヒャエル・エンデ。訳・水島かおり】
1976年9月24日第1刷。1985年七月10日第22刷。 こういうものをちゃんと読んだことがないので、最近、児童文学を続けて読んでいる。 さて、この「モモ」だが、果たして児童文学なのだろうか。 国は異なるが、トーベ・ヤンソンの「ムーミンパパの思い出」を読んだときにも同じことを感じた。ヨーロッパの子供たちは、こんな観念的な話を好むのだろうか。 副題は、「時間どろぼうと、ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語」。挿絵も作者が描いている。 収入を得るためにあくせくすることは悪であり、のんびり「今」を楽しむのがあるべき姿だ。子供は、純真無垢とまではいかなくとも、善だ。 同じドイツのケストナーの言うように、大人は子供だったことを忘れてしまってはならない。そういう話だ。 物語は壮大で、モモという少女が世界を救うのである。 しかし、そのモモの出自はわからないし、重要な登場人物であるマイスター・ホラが何者なのかもわからない。 作者が人に聞いた話、という体裁を取っているので、それでも不都合はない。 むしろ、説明がないからこそ、印象に残るのだろう。 全てが合理的に説明されてしまったとき、物語は、「そんなものを使ってもほんとうの遊びはできないような」(p98)「子どもがじぶんで空想を働かせる余地がまったくない」(p99)ものになってしまうのだろう。 今から30年以上も前に訳されたものなので、訳文はやや古めかしい。「視聴者」ではなく「聴視者」(p230)、「えりもえって」(p232)などという表記が時代を感じさせる。 観念的な物語を子どもにも理解できるように訳すというのは、大変な仕事だったろう。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2007.03.09
コメント(0)
-
「サーカスの小びと」 【エーリヒ・ケストナー。高橋健二・訳】
岩波書店。1964年8月20日 初めて読んだ。 不思議な物語である。 いわゆる児童文学ではあるのだが、むしろ大人向けの小説なのではないだろうか。 子供が読んでも理解できないのではないだろうか。 主人公のメックスヒェンについては、合理的な説明は何もない。ただ、そういう存在なのだ。 我々とは異なる官製で生きている人たちの物語だった。 検索してみたが、「飛ぶ教室」とは違って、各社から出版されて版を重ねるということはないようだ。 「うーむ、世の中にはこういう小説もあるのか」というのが正直な感想である。 けっして退屈な小説ではない。 その後の展開が全く読めないので先が気になる。 事件が解決してハッピー・エンドではあるのだが、「では、この後、どうなるのだろう」と思ってしまう。 子供はそんなことを考えない、というわけではない。メックスヒェンは、自分と同じような少女がいてくれたら、と思っていることが、将来への不安を感じさせるのだ。 今から40年以上も前のものなので、訳文も時代を感じさせる。 今なら「ぐあい」と書くところが、「ぐわい」になっている。 「よりによって」ではなく「えりにえって」(p37) 「わたしあの人にすっかりチャームされましたわ」(p159)の「チャーム」は子供に理解できたのだろうか。 「まさに奇想天外《きそうてんがい》より落《お》つ」(p263)は本来の表現。 原文でどうなっているのか気になるのは、一座の「竹の家《や》一家《いっか》」(P16)、「おとうふのように、ふるえていました」(p211)。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2007.03.06
コメント(0)
-
「チップス先生さようなら」 【ヒルトン/菊池重三郎訳】
新潮文庫。1987年改版 冬休みの間に、NHK-BSでイギリス制作のドラマを見て興味を持ったので読んだ。 ドラマと小説ではずいぶん違っている。 伝統的なパブリック・スクールで長い間教鞭を執った「チップス先生」と呼ばれた人物が、晩年に、過去の様々な出来事、出会った人物達のことを回想する。 何しろ長く関わったので、親、子、孫の三代にわたって教えた生徒もいる。 時系列で書かれたものではなく、断片的に思い出したことを並べているので、話は前後する。 それによって、様々な面から主人公の人物像を浮かび上がらせようとしている。 チップス先生は、決して理想的な人物ではない。 むしろ頑迷である。 自分の教え方が、いかに旧式であろうと、変えようとはしない。 衣服には注意を払わない。 それでも、長く一つの学校で教え、頑迷であるからこそ生徒に対する態度を変えず、学校に変化をもたらさないようにすることで、いわば「校風」の象徴ともいえるような人物になったのである。 私立の全寮制学校という特殊な空間でのことで、どこの国にもあるような普遍的な話ではない。 パブリック・スクールが舞台のものは、小説を読んだり、映画を見たりしたことはあるが、自分では経験しようがないので、雰囲気はわからない。 最近の映画でいうと、「ハリー・ポッター」に出てくる学校が、パブリック・スクールを摸しているのだろう。 舞台となっているのは、一流ではないらしく、ブルックフィールド学校と同様、チップスは、立派ではあるが、別して優秀《ゆうしゅう》というほどの人物でもなかった(p13)ということである。 ただし、パブリック・スクールというものについていえば、翻訳者による解説によれば、ブルックフィールドという仮名の学校に、英国のパブリック・スクールのあり方を集約しているもので、どの学校でも同じような雰囲気らしい。 「良家の子弟が集まる」ことを前提としているので、どこも同じようになるのだろう。 もちろん、問題はいろいろあるようだ。 例えば、生徒達は以前から見ると余程《よほど》礼儀《れいぎ》正しくなった。よわいものいじめはやらなくなった。が誤魔化《ごまか》しや毒づくことは巧《うま》くなった。(p91)というところに、その一端をかいま見ることはできる。 また、自由競争試験によって入学した者に与《あた》えられる奨学《しょうがく》資金制度(p93)という記述からすると、ほとんどの生徒は家柄や財力によって入学するものらしい。 訳文は読みやすい。 表記では、「ズボラな者」「トガメない」「存外ウルサイ」と、カタカナが混じるのが目についた。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へどうぞ。
2007.01.24
コメント(0)
-
「エピソード科学史 1 化学編」 【サトクリップ】
現代教養文庫。1971.10.15第1刷。1985.5.15第33刷。(古本を探す) 科学者が、科学に親しんでもらおうと、さまざまなエピソードを紹介し、科学的に考証し、軽い読み物としたもの。 「ガラス作りの技術」から時代順に「錬金術――三百年ごとの事件」まで二十二話。 錬金術なんて昔の話だろう、と思ったら、1925年にも起こっているのだ。 伝説を取り上げているので、どのように伝説が作られるのか、という面でも面白い。 たとえば、「ハンニバル,アルプスを溶かす」では、発音の似た語を混同したために生まれた伝説だろう、と述べている。 「アンチモンの名のおこり」に、「大寺院に雷がおちて壁がくだけおち、原稿が出てきたのだ!」(p45)というのは、岳飛像から拳譜が出てきたという、形意拳の伝説を思わせる。 科学とは関係のない豆知識も。 競馬用語の「ダービー」「オークス」とは、ダービー卿の名と、その屋敷の名に由来するそうだ。(p72) 1962年にある科学者の書いた文の中に、(イギリスは)「キハダやベニバナの無規制代用品を、これらの植物を現在生産している中国や日本などへ送るだろう」とあるという。(p94) 幕末になってあっという間に世界に広まったのだろうか。 錬金術のところに「卑金属」という語があった。初見。 これを見て、「そうか、卑金属があるから対義語として貴金属があるのか」と、値段の高低で卑金属だったり貴金属だったりするのか、と思ったが、念のために辞書を引いたら、空気中で参加しやすいのが卑金属、科学変死しにくいのが貴金属だそうだ。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください
2005.12.30
コメント(0)
-

「飛ぶ教室」 【ケストナー】
講談社「青い鳥文庫」1992年9月18日。第1刷) 先日、新聞のコラムがこの本にふれていたので、家にあったのを読んでみた。 小学生の時に読んだことがあり、三十年以上の時を経ての再会だ。 例によって、ほとんど覚えていない。 覚えていたのは、劇で北極の地軸を見るのと、旅費のない少年の話のところだけ。 ドイツの寄宿舎のある学校を舞台にした物語。主人公たちは寄宿生。 クリスマスを目前に、うきうきしている。 驚いたことに、わずか数日間の物語だったのだ。 長い時間の中で子どもたちが成長していく過程を描くのではなく、ある短い一時期を描き、それぞれの悩みや悲しみ、その子どもたちを支える大人を描いている。 解説によれば、主人公たちは十六歳らしいが、もっと子どもなのかと思っていた。 日本で言えば高校生に当たる生徒たちがたばこを吸っていたりして驚く。 子どもたちが信頼している正義先生は舎監で、学校に住み込んでいる。独身なのだろうか? そのあたりはわからない。 物語は、この話を書くに至る作者の「まえがき」の「その一」と「その二」から始まり、「あとがき」で、登場人物の一人に出会い、本に書いたことを話して終わる。 作者の考えは「まえがき」にはっきり書かれている。「おとなというものは、どしてこうも、けろりと、自分の子どものころをわすれて、子どもだって、ときにはずいぶん悲《かな》しく、不幸《ふこう》なことだってあるのだということを、まるでわからなくなってしまうのでしょう。(この機会《きかい》に、わたしはみなさんに心からおねがいします。みなさんの子どものころをけっしてわすれないで、と。約束《やくそく》してくれますか。誓《ちか》って?)」(p16) そして、子どもたちが信頼を寄せる大人である、正義先生と禁煙さんは、クリスマスのお祝いの席で子どもたちにこう訴えかける。「わたしは諸君《しょくん》におねがいしたい、きみたちの子どものころをわすれるな! と。」(p233) 「あとがき」で、作者は、禁煙さんと正義先生の友達だ、と言う。すなわち、禁煙さんと正義先生は作者自身なのである。 主要な登場人物の性格がきちんとかき分けられていて、それぞれの背負っているものを感じさせる。 中でも、父に棄てられたジョーニーの境遇は目を引く。 ジョーニーのキャラクターから、萩尾望都の「トーマの心臓」「訪問者」を連想したが、「飛ぶ教室」の影響というわけではない。 「飛ぶ教室」の子どもたちは、自分たちはいつか大人になって世の中に出ていくんだ、ボクサーになったり、画家になったりするんだ、と思っている。 1932年に書かれ、翌年出版されたものだそうだ。 もう70年もたっているので、「子ども」というものへの見方も変わってきているのだろ。 また、ヨーロッパ(ずいぶん乱暴なくくりだが)と日本とでは「子ども」に対する考え方も違うはずだ。 私には、はたして大人は自分が子どもだったときのことを忘れているのだろうか、という疑問もある。 しかし、そういう壁を越えて「これはいい」と思わせられる作品である。楽天ブログランキング←よかったらクリックしてください
2005.12.22
コメント(2)
-
「マーフィーの黄金律《ゴールデン・ルール》」 しまずこういち
三笠書房・知的生きかた文庫。1998.1.10第1刷。2004.7.4第8刷。 最近妻がマーフィー博士の理論に凝っていて、すすめられたので読んでみた。 不思議な本である。 理論を生み出したジョセフ・マーフィーという人のプロフィールは次のようになっている。精神法則に関する世界最高の講演者の一人。神学、法学、哲学、薬理学、化学の博士号を持っている。テレビやラジオを通じて、またヨーロッパ、オーストラリア、日本など各国において精力的に潜在意識の活用についての講演を行うかたわら、多数の著書を執筆し、世界的にその名を知られている。1981年没。 どこの国の人なのかもわからないし、没年だけで生年がないので、何歳まで生きたのかもわからない。 「精神法則に関する世界最高の講演者の一人」というが、「精神法則に関する世界最高最高の講演者」って、世の中にそんなに何人もいるのだろうか。 マーフィー博士も謎なのだが、この本を書いた「しまずこういち」という人がどういう人なのかはどこにも紹介がないのも不思議だ。 どこからどこまでがマーフィー博士の言葉で、どこからどこまでが著者の言葉なのかわからない。 例えば、「私は次のような例を知っています。」(p101)の「私」がどちらなのかもわからない。 日本人向けに書いているのではあるが、どうも事例は日本らしくない。 たとえば、「ここに法律家を目ざすA君がいるとします。」(p163)という例を出しているのだが、日本に「法学者」や「弁護士」ではなく、「法律家」というものが存在しているのだろうか。 さて、「黄金律」について述べると、潜在意識に刻印したことが現実化する、という理論。 「こうありたい」と思い、そうなると潜在意識が信じ込めば、それが実現する、というのである。失敗するんじゃないかと思っていれば失敗し、成功すると思っていれば成功する。 よいことを考えればよくなり、悪いことを考えれば悪くなる。つまり「人生はよくも悪くもその人の思い描いた通り」(p50)のものだというのである。 潜在意識の力によってそうなるのだが、その潜在意識は「聖者善悪の区別はなく、同情も憐れみもない」(p50)。したがって、心のそこからの悪人が、悪事をはたらいて成功しようと心の底から願えば、それが実現してしまうのである。 どんなに善人でも、潜在意識を正しく利用できなければ、悲惨な目にあったりする。 まさに「信じるものは救われる」のである。 こういう本を一概に否定する気はない。 心の持ち方を変化させることによって、精神的な安定が得られれば、生活はよりよいものになるはずだ。現世利益の強調が目立つのが気になるが、精神的な安定を求めるための本である。 「子供は親のいう通りにはしないが、親のする通りにはする」(p138)というのはまさにその通りだろう。 興味深かったのが、過度の飲酒癖(要するにアルコール依存症だろう)の克服の事例。(p127) マーフィー博士は、「お酒を飲むときは、自分にとってはいまがそれが必要なんだと思いなさい。」とアドバイスする。 酒を飲むためならどんな理由でも考え出せるのだから、逆効果だろうと思ったら、それに続けてこうあった。「罪悪感だけは持ってはいけません」 アルコール依存症の人は自分の飲酒に罪悪感を感じることが多いという。 罪悪感は飲酒の結果である。ここでは、結果をかえることによって原因を変えていこうとしている。 こういうことが可能かどうかはわからないが、罪悪感を感じないためには飲まないしかないのだから、飲酒量が減っていくという理屈だろうか。
2005.06.22
コメント(0)
-
「悲しみよ、こんにちは」 【サガン】
朝吹登水子・訳。新潮文庫。1955.6.25発行。1985.11.15百二版改版。1998.1.15百三十版。 中年になってから読むとは思わなかった。 たまたま目についたので読んでみた。 筋立てが複雑なわけではない。 少女の目から、父と愛人、父の妻となろうとする人、自分の恋人などが描かれ、主人公の屈折、大人への反感、大人になる不安などが克明に描かれる。 人間は単純な好き嫌いで行動するものではないし、同じ人間でも違う角度から見れば、評価は変わる。 簡単にあらすじだけ知りたい人は、訳者による「あとがき」の最初のところを読めばいい。 著者が十八歳の時の処女作だそうだ。 年若い作者の作というと、「肉体の悪魔」を思い出す。 民族性なのか、時代のせいなのか、登場人物の感覚には驚くしかない。 そう言えば、「危険な関係」も感覚的には理解しがたい話だった。 この作品は、十八歳の感性によって書かれた、という点が重要なのである。 同じ物語でも、中年になってから書いたのでは違う印象のものとなるだろう。 それだけに、翻訳者は苦労したのではないだろうか。 日本の十八歳が使わないような言葉にしか訳せないような文章もあったことだろう。かといって、橋本治が使った桃尻語というわけにもいかないし。今では桃尻語も古くさい言葉になってしまっている。(もちろん、この本が出た時にはまだ桃尻語はない) 従って、普遍的な言葉を使わなくてはならないのだ。 翻訳って、大変な仕事なんだなあ、と思いながら読んだのである。
2005.06.08
コメント(2)
-
「料理人」 【ハリー・クレッシング】
料理人(著者:ハリー・クレッシング /一ノ瀬直二|出版社:ハヤカワ文庫) おそらくイギリスと思われる国の田舎町に自転車で現れた男コンラッド。 名家に住み込みの料理人として雇われ頭角を現していく。 料理を通じて主人一家、もう一つの名家をコントロールするようになる。 といっても金銭的な野心があるわけではない。両家を実質的に我がものにし、富を手に入れるが、結局何をするかというと城にこもって延々とパーティを開くという結末。 料理を作ること、食べることにとりつかれた人間たちの物語でもあるのだが、グルメ小説ではない。旧家乗っ取りの成り上がり小説でもない。 何とも言いようのない不思議な小説なのである。 コンラッドが人々を操っていく様は見事だ。 主人一家の体重をコントロールし、じゃまになりそうな執事は病気にして追い出す。 料理の力で主人の娘も手に入れる。 主人はそれまで執事の仕事だった飲み物の調合に、その妻はテーブルセッティングや皿洗いに、息子はコンラッドの弟子として料理に、それぞれ嬉々として取り組むようになり、常にコンラッドの指示を仰ぐ存在になってしまう。 訳者あとがきによると、これは悪魔物の一つなのだそうだ。 人間の欲望を刺激し、人間を意のままに操る。悪魔とはそういう存在であるらしい。 一箇所誤植発見。「喚起設備の貧弱」(p145)は「換気設備の貧弱」だろう。
2004.08.19
コメント(0)
-

「ムーミン谷の彗星」 【トーベ・ヤンソン /下村隆一】
ムーミン谷の彗星(著者:トーベ・ヤンソン/下村隆一|出版社:講談社文庫) 解説によると、1946年に書かれたものを1968年に書き改められたものだという。 シリーズとしてはムーミントロールたちがムーミン谷に住み着いてから最初の話ということだそうだ。 偶然ながら、「ムーミンパパの思い出」を先に読んだが、時間軸では、次にこれを読むのが妥当なわけだ。 スニフは最初から一緒にいて、冒険の途中でスナフキン、スノーク、スノークのおじょうさんに出逢う。 スナフキンはギターではなくハーモニカが得意で、すのーくのおじょうさんには名前はない。 冒険譚ではあるのだが、この夜の終わりが来るかもしれないという時に、どのような精神でそれを受け止めるのかという心理的な面に重点が置かれている。 「ムーミンパパの思い出」もそうだったが、哲学的なのだ。 北欧の児童文学ではこういう理屈っぽいのが一般的なのか、あるいは、特殊なシリーズだから人気があるのか。 そのあたりは全く分からない。 不思議な世界である。
2004.05.10
コメント(0)
-

ムーミンパパの思い出 【トーベ・ヤンソン/小野寺百合子】
ムーミンパパの思い出(著者:トーベ・ヤンソン/小野寺百合子|出版社:講談社) 最近、スナフキンの父親のことを知って、確認のために読んでみた。 たしか、3度アニメ化されていて、最初の2度は同じ設定になっていた。これが印象に残っていて、ずいぶんムーミンの世界を誤解していたのだ。 3度目のテレビ東京でのアニメ化は原作に近かったようだ。 さて、スナフキンのことなのだが、原作のファンには常識なのだろうが、なんと、ミイの異父弟なのだ。スナフキンの父親はヨクサルという。ミイの父はでてこない。 最後まで読んでさらに驚いたのは、ヨクサルもミイの母親もまだ生きているのだ。冒険を続けていてずっと子どもたちをほったらかしにしているのだ。 北欧と日本の風土の違いというのはあるにせよ、登場人物の考え方は新鮮だ。 精神的自立を目指す話なのである。これ、童話ではあるが、大人のために書かれたのではないだろうか。
2004.05.07
コメント(0)
-
「パレアナの青春」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
パレアナの青春( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社:角川文庫 )" 『少女パレアナ』の続編。 ベタな通俗小説になってしまっているのだが、それでも面白い。 それまで全く登場していなかった一家と関わりを持ったり、途中であっという間に六年たって、パレアナが二十歳になってしまったりして、物語はどんどん進む。 続編というよりも、これは『少女パレアナ』と分けられない、一つになったものなのだ。 おそらく、作者は、『少女パレアナ』を書いているときから、最後にはこうなる、というのが、頭にあったのだろう。 『少女パレアナ』に比べれば、伏線のはり方が甘いが、それでも、一体どうやって決着をつけるのだろう、という興味で読み進まずにはいられなかった。 訳文で気づいたこと二つ。 「おまえの舌(した)にはついていかれないよ」(p37)。初版は1962年。「いかれない」という表現は今は珍しくない。訳した当時は不自然ではなかったのだろうか。裕次郎の「赤いハンカチ」に「いかれたものを」という歌詞があり、聞くたびに引っかかるものを感じていたのだが、どうやら、広く使われていたらしい。 「患家先(かんかさき)」(p194)。初めて見た言葉だ。患者の家、という意味なのだが、英和辞典にはこういう言葉が載っているのだろうか。
2004.03.17
コメント(0)
-

「少女パレアナ」 【エレノア・ホジマン・ポーター】
少女パレアナ改版( 著者: エレノア・ホジマン・ポーター / 村岡花子 | 出版社: 角川文庫) 子どもの頃に、子ども向けの文学全集で読んだことがあったが、たまたま家にあったのでちゃんとしたものを読んでみた。 大人の目で読んでみると、大衆小説のつぼを心得ていて、話の展開が実にうまい。 貧困から裕福へ、かたくなな親族、と、『小公子』や『秘密の花園』などのパターンを踏襲し、主人公の明るさで周囲のものが救われていく、というハッピー・エンド。叔母の昔の恋人は誰か、など、あとで考えると、ちゃんと伏線が張ってあったのに、ついだまされてしまった。 作者は、子どもの時から作家になりたいと思っていた、という人ではないそうだが、物語とはどういうものかがよく分かっている人だったのだろう。 出版されたのは1913年で、すでに開拓時代ではないのだが、西部と東部というのはだいぶ異なるらしい。それもまた、主人公とまわりの人物とのギャップになっているようだが、そこはよく分からない。 読んでいて、何かに似ている、と感じたが、何に似ているかといえば、『非凡なる凡人』と、『富士に立つ影』の「主人公編」の主人公だ。特に、物語としてもおもしろさから言えば、『富士に立つ影』に似ている。 こういうものを読むたびに感じるのは、翻訳の難しさだ。 児童文学、ということで、ですます調で訳してあるのだが、「懇望(こんもう)していた」などという言葉が出てきたりする。 また、訳されたのが40年近く前であり、言葉遣いが随分違う。
2004.03.15
コメント(0)
-
「あなたに似た人」 【ロアルド・ダール】
あなたに似た人(著者: ロアルド・ダール /田村隆一 | 出版社: ハヤカワ・ミステリ文庫) 書名は知っていたが、初めて読んだ。 短編集だが、書名になった作品があるわけではない。 不思議な味わいがある。こうなるだろうと予測させておいて、それをはずすのがうまい。 一つだけ、「兵隊」はなんだかよく分からなかった。 ただ、こういうものを読むといつも感じることだが、訳文がどんなに良くても、日本語の論理で書かれたものではないために、どうしても隔靴掻痒の思いをしてしまう。 かといって原文で読む能力はないし。少し残念。
2003.12.20
コメント(0)
-
「誰がために鐘は鳴る」 【アーネスト・ヘミングウェー】
誰がために鐘は鳴る(上巻)改版誰がために鐘は鳴る(下巻)改版( 著者: アーネスト・ヘミングウェイ。大久保康雄・訳 | 出版社: 新潮文庫 ) 下巻になり、戦闘が始まるとあとは一気に読み進むことができた。 正直なところ、上巻は読み通すのに忍耐を要した。 時間としては、物語は四日間ぐらいしかないのだが、台詞や回想、心理描写が長い。 饒舌ですらある。 最後は、こうなるのかな、と思った通りの最後になったが、感銘は残る。 それにしても、翻訳は難しい。 野卑な言葉を話す連中のせりふが特に難しい。 短い例を挙げれば、「あのワイセツな橋を吹き飛ばし、それからおれたちはワイセツにもこの山から出て行かなきゃならねえっていうじゃねえか」(上巻p86)「わしらは奇跡のおかげで、ここに巣くっていられるだ。ファシストのやつらの怠慢と愚かさの奇跡のおかげだて。」(上巻p283)「雌のやつが、夜明け前に、雪のなかで、何かドタンバタンやってたんだ。やつらが、どんな放埒(ほうらつ)なことをやらかしてたか、とてもおまえさんにゃ想像がつくめえて。」(上巻p90)などという台詞がある。日本語の世界なら、野卑な言葉を使うものがいいそうにないことをいうから不自然なのだ。 翻訳の問題というよりも、全く異なる文化のなかで書かれたものを日本語で読む、というところに無理があるのだ。 文学は何が書かれているかではなく、どう書いてあるかだ、という高島俊男さんの言葉を思い出す。 しかし、日本語で書かれたものしか理解できない身としては、翻訳で読むしかない。 翻訳家は大変だ。
2003.10.06
コメント(0)
-
「黄金の壺」 【ホフマン/神品芳夫】
黄金の壺(著者:ホフマン/神品芳夫|出版社:岩波文庫) 久しぶりに訳の分からない小説を読んだ。 作者はドイツ・ロマン派というものに属する人なのだそうだが、その「ドイツ・ロマン派」というのが何かも分からない。最近『ホフマン短篇集』を読んだのがきっかけで読んでみたのだが、『ホフマン短編集』の内容もさっぱり覚えていない。 現実の世界と幻想の世界が入り交じった世界で物語が進んでいく。 アトランティスやら火の精やら出てくる。たぶん何かを意味してはいるのだろうが、理解できない。 主人公の大学生アンゼルムスに思いを寄せるヴェロニカの最後の選択が非常に現実的で、主人公の住む幻想的な世界よりも、現実世界のことの方が印象に残った。
2003.03.31
コメント(0)
-
「中世騎士物語」 【トマス・ブルフィンチ/野上弥生子】
中世騎士物語改版(著者:トマス・ブルフィンチ/野上弥生子|出版社:岩波文庫) 名高い、アーサー王とその回りの騎士たちの物語。 一つのストーリーがあるのではなく、銘々伝である。 ガウェインの話、カラドクの話、ラーンスロットの話、と個別に語られる。 リア王の話がこのなかに含まれていると走らなかった。 最も印象に残るのは、やはり、ラーンスロットとアーサー王と王妃ギニヴィアの物語である。 ラーンスロットはギニヴィアを恋い求めながらもアーサー王に対しては忠誠を誓い、その危難を救いたいと思っている。 読むと、かつてのイギリスは小国割拠の状態であったこと、民族同士のせめぎ合いがあったらしいことがわかる。単純に「イギリス」などといるものはないのだ。 訳者の野上弥生子は1985年生まれ。この文庫の初版は1942年。 P197に「耳ざわりのよいことを言うな!」とあるが、「耳ざわりがいい」という用法はかなり昔からあったようだ。(「耳ざわり」は「耳障り」で聞いて不快に感じるという意味のはず)
2002.12.13
コメント(0)
-
「愛の妖精」 【ジョルジュ・サンド /宮崎嶺雄】
愛の妖精(著者:ジョルジュ・サンド/宮崎嶺雄|出版社:岩波書店・岩波文庫) これも子供の頃に読んだ記憶はあるのだが、大人になってちゃんとした翻訳で読むと、ずいぶん印象が違う。 サンドはバルザックとほぼ同時代の人だが、こちらには、退廃的なフランス人は出てこない。みんなまともである。バルザックやモーパッサンを読むと、フランス人には貞操などという観念はないのかと思ってしまうがそんなことはないようだ。 解説によれば、「温和な物語によって人心を慰める」という目的を持って書かれたと言うことだが、確かに人の心をいやす小説である。 終わりの方で、貯蓄があったことが出てくるのは蛇足のような気がするが、あるいは、自分でもずっと知らなかったが、実は裕福だった、という型の嚆矢なのかもしれない。 自分自身がこうありたい、周りのみんなにこうあって欲しい、という願いが込められた小説である。 ファデットはランドリーに「手を握らせても手首より上は握らせなかった」(p180)というのだが、手首より上を握る、というのは何か意味があるのだろうか。
2002.11.16
コメント(0)
-
「ホフマン短篇集」 【ホフマン】
ホフマン短篇集(著者:ホフマン/池内紀|出版社:岩波書店) 「クレスペル顧問官」「G町のジェズイット教会」「ファールンの鉱山」「砂男」「廃屋」「隅の窓」 よくこんな話を考えつくものだ、というような不思議な話ばかり。 正気と狂気との境界はないのだ。 自分にとっては現実でも、他者にとっては現実ではない。 現実とはどこに存在するのか。それぞれの人間の中にのみ存在するのである。 何事もなければ、共同幻想としての現実の中で、それを現実と感じて生きていくのだが、ひとたび、自分の中にのみある現実に入り込んでしまい、そこから出られなくなってしまうと、他人からは破滅としか思えないような結末を迎えることになる。 「廃屋」だけは、主人公が、かろうじてそれを避けることができた話であるが、主人公に、自分の中にしかない現実の中で生きる人間はそれはできずに終わる。 「隅の窓」は、ほかの作品とは作風が違っているが、自分で勝手に他人の人生を拵えて楽しむ、ということが会話でなされ、やはり、自分の中にある現実に目を向ける話である。 1984年の訳で、昔の翻訳にありがちな不自然な堅さはなく、読みやすい。「生きざま」(p68)という語が使われているあたり、いかにも新しい訳という感じがする。
2002.11.13
コメント(0)
-
「危険な関係(上)(下)」 【著者:ラクロ/伊吹武彦】
危険な関係(上)危険な関係(下)(著者:ピエール・アンブロワーズ・フランソア・コ/伊吹武彦|出版社:岩波文庫) 書簡体小説の長編。 十八世紀フランスの社交界に渦巻くスキャンダル、という内容ではあるのだが、描かれているのは、心理的駆け引きが中心。色恋沙汰に事欠かぬ華やかな社交界、という世界ではあるのだが、結末に至っては、無常観を感じさせる。 社交界の人間は、ほかにすることがないのか、と思いたくなるが、日本の源氏物語だって、こういう一面がないわけではないし、どのような社会にあっても、ある階層においては、起こりうることなのだろう。 モデルはあったらしいが、登場人物それぞれの個性がはっきりしており、心理的駆け引きの描写が巧みで、心理小説と呼ばれるに恥じない。 特に、ほとんど主人公といえるヴァルモンとメルトイユの二人の関係には緊張感がある。 直接顔を合わせることはほとんどなく、それでいながら互いに強く意識し、それぞれの思惑に基づいて策略をめぐらし、牽制し合うさまが、書簡体という婉曲な表現で巧みに描かれている。 書簡体小説というのはほかに読んだ記憶がないが、登場人物それぞれが一人称で語る、というのに近い。したがって、一つのできごとが、語り手によって違う意味を持つことにもなる。 こんなに緻密な小説を書くのには、大変な技量が必要だと思うのだが、作者はほとんどこれ一作のみによって後世に名を残しており、本職は軍人。 もしかして、ほんとうに手紙を手に入れて整理しただけなのではないかとさえ思える。
2002.11.06
コメント(0)
-
「風車小屋だより」 【アルフォンス・ドーデ/桜田佐】
風車小屋だより(著者:アルフォンス・ドーデ/桜田佐|出版社:岩波書店・岩波文庫) 子供の時にこの中の何編かは読んだことがある。 やはり最も印象に残っているのは「コルニーユ親方の秘密」だ。 ほかに、「老人」も話だけは覚えていたが、この「風車小屋だより」の一遍だっとは記憶してなかった。 南仏プロバンスというと、昨今はやりの土地のようだが、これを読むとひなびた土地である。プロバンスにも都会も農村もあって、その農村の方に住んでいるからなのだろうが。 モーパッサンなどと同時期の人なのだが、同じフランスとは思えないくらい描かれる人々の様子が違う。「女の一生」などは、爵位を持つ上流階級の話だが、こちらは、社会の底辺に生きる貧しい人々の暮らしぶりも描かれる。 豊かな自然を求め、都会から離れて暮らし、その土地での見聞を記す。これは山本周五郎の「青べか物語」ではないか。 古今東西、こういうことをしたがる人はいるわけだ。 訳者あとがきによると、訳は、最初に1932年に訳され、1958年に改訳した、ということだ。P85の俗謡の訳、「いいえ、とのさま もったいない、 お律(りつ)は村ァで わび住(ず)まァい……」など、訳者の技量を感じさせる。しかし、何分古いので、所々、現在ではわかりにくい部分もある。 たとえば、「この果物(くだもの)は、砂糖菓子や有平糖(あるへいとう)の仲間である」(p155)、「一スー」という通過についての訳注の「邦貨の五銭ぐらい」(p221)など。 初めて知ったのは、プロバンスには、フランス語とは異なるプロバンス語がある、ということ。「フランス語でお話ししてみようと思います」(p90)、「ミストラルはプロヴァンス語をもって筆を励ましている」(p137)という記述がある。
2002.10.25
コメント(0)
-
「人形の家」 【イプセン/原千代海】
人形の家(著者:ヘンリク・イプセン/原千代海|出版社:岩波文庫) 初めて読んだが、わかりやすい話だった。 わずか三幕で、舞台は変わらない。 女性が自分の意志で行動し、一人の人間として生きる道を探るのだが、大仰な決意を披瀝するわけではなく、軽い気持ちでしたことが自分を追いつめ、その結果、夫に庇護される存在としてではなく、精神的に自立した存在として生きていくことを求める。 古くて新しい、洋の東西を問わないテーマなのである。 ただ、魯迅ではないが、気になるのは、ノーラは家を出てからどうなったか、だ。 踏み出すことは勇気があればできる。しかし、踏み出した後はどうなるのか。現実にはそこが問題なのだが。
2002.10.12
コメント(0)
-

「モーパッサン短篇選」 【ギ・ド・モーパッサン /高山鉄男】
モーパッサン短篇選(著者:ギ・ド・モーパッサン/高山鉄男|出版社:岩波書店・岩波文庫) 短編十五を収録。「水の上」「シモンのパパ」「椅子直しの女」「田園秘話」「メヌエット」「二人の友」「旅路」「ジュール伯父さん」「初雪」「首飾り」「ソヴァージュばあさん」「帰郷」「マドモワゼル・ペルル」「山の宿」「小作人」。 このうち、「シモンのパパ」と「首飾り」は、子供の時に、子供向けの文学全集で読んだことがあり、内容はよく覚えていたが、どちらもモーパッサンの作とは知らなかった。 「首飾り」のように落ちのついているのもあれば、「帰郷」のように、これからどうなるんだろう、で終わるのもある。 「シモンのパパ」のように救いのある話もあれば、「椅子直しの女」「田園秘話」のように、ああ、人間とはこういうものだろうな、と思わせられるのもある。 話の展開で読ませるのではなく、人物の造形で深い印象を残すものが多い。 恋愛の関係する話が多いのはフランス人ならではなのか、モーパッサンの特長なのかは知らないが、バルザックの「ゴリオ爺さん」を読んだときの印象に共通するものがあるので、近代フランス文学の特徴なのか。調べたら、モーパッサンはバルザックの死んだ一八五〇年に生まれている。 モーパッサンのほかの小説も読んでみよう、という気になった。 訳は、新訳で、自然な訳文。日本語の状況がかわっていくのだから、翻訳も新しいものを出していく必要があるわけだ。
2002.10.07
コメント(0)
-
「デーミアン」 【ヘルマン・ヘッセ】
デーミアン(著者: ヘルマン・ヘッセ|出版社:講談社文庫) 自己追求の青春小説。かなり観念的。 主人公が、友人のデーミアンの導きによって自我を確立していくのだが、おそらく、デーミアンというのは現実には存在しない友人なのだろう。 どうしてとどいたかわからない手紙や、夢の中に現れた女性が、デーミアンの母親にそっくりだったことなどから、そう考えられる。 自我が確立されたとき、主人公の姿はデーミアンとなっている。 自我は自分の外に求めるべき物ではなく、自分の中にあるものなのだ。 これは誰もが経験することではない。この小説で言えば、「しるし」を持ったものでなくては経験できないことなのだ。 したがって、周囲からは孤立することになる。 近代的な自我に目覚めた鴎外や漱石が経験したのは、こういう苦悩だったのだろう。(講談社文庫は絶版。岩波文庫と新潮文庫から出ている)
2002.06.29
コメント(0)
-

「この輝かしい日々」 【ローラ・インガルス・ワイルダー】
この輝かしい日々(著者:ローラ・インガルス・ワイルダー/小玉知子|出版社:講談社) ローラの青春の物語。 好意を示してくれる男性が現れた時点で、両親からは、大人と同じように扱われはじめる。ローラにとって最も幸福な時期だったのだろう。 ただ、なぜアルマンゾがローラを好きになったのかは全くわからない。何のきっかけもないということはないとおもうのだが、本当はローラの方から気を引いたのかなという気もする。 こうして子どもから大人になっていくという過程が描かれている。 話を読んでいるだけだと、だいぶ西部にきたように書いてあり、東部に帰りたいという人物も出てくるのだが、地図で見ると、大陸のまんなかあたりで、ロッキー山脈よりだいぶ東側である。「西部」というのは、特定の地域を指しているわけではなく、開けた大西洋側から見て相対的に西側にある開発地をさしているらしい。
2002.06.28
コメント(0)
-
「ゴリオ爺さん」 【オノレ・ド・バルザック】
ゴリオ爺さん(著者:オノレ・ド・バルザック/平岡篤頼|出版社:新潮文庫) 実に読み応えのある小説だった。 人物の造形が重厚で、読み流せない本だ。 二人の娘を溺愛し、その幸福のためと信じて金を作り、自らは困窮するゴリオ爺さん。同じ下宿に住まっている若い二人の学生。そのうちの法律を学ぶ学生が主人公になっている。 自分のことしか考えていない娘達の存在と、苦悩する青年との対照が印象に残る。 「人間喜劇」というシリーズの一つであり、これに登場する人物はほかの小説にも登場するらしいが、これはこれとして完結したものとして読まなくてはならないだろう。 書かれたのは、日本で言えば天保年間。個人の資質というものもあるのだろうが、描かれている世界があまりにも日本とは異なる。 ゴリオ爺さんは、青年が銀行家に嫁いだ娘の恋人になることを望み、二人を結びつけようと努力するのだが、そういう心理が理解できない。 バルザック自身も、人妻の恋人がいたというし、当時のフランスでは普通のことだったのだろう。 文章は、どうしても饒舌に感じられる。 描写が多いのではない。とにかくセリフが長いのだ。二ページぐらいずっとしゃべり続けていたりする。 こういうところは、慣れるまで時間がかかった。
2001.06.29
コメント(0)
-
「知られざる傑作 他五篇」 【オノレ・ド・バルザック/水野亮】
知られざる傑作 他五篇(著者:オノレ・ド・バルザック/水野亮|出版社:岩波文庫) 初めてバルザックを読んだ。 「人間喜劇」というものがあることは知っていたが、その中の六篇収録。 「砂漠の情熱」 物語が、その体験の主から聞いた話、として語られる趣向が面白い。 「ことづけ」 これが最も面白かった。 年上の既婚女性を恋人にしているというあたり、「三銃士」の時代そのままだ。 「恐怖時代の一插話」 時代背景がよく分からなかった。訳注を読んでやっと理解した。 「ざくろ屋敷」 物語の部分は少なく、冒頭は屋敷の描写が延々と続く。 登場人物の置かれている環境は明瞭にはかかれていないが、どういうことなのかはわかる。 「エル・ベルデゥゴ」 重要なせりふが語られる場面があっさり書かれているので、最初は何がなんだかよく分からなかった。 訳注なしでは理解できなかったろう。 「知られざる傑作」 ある芸術家の物語。表現が屈折しているので、女性の心理がよく分からない。
2001.04.23
コメント(0)
-
「復活(上・下)」 【トルストイ/木村浩】
復活(上巻)・復活(下巻)(著者:トルストイ/木村浩|出版社:新潮文庫) 昔々子供向けの世界文学全集で読んだことがあるはずだが、ほとんど覚えていない。 そもそも、子供に読ませるような話ではない。 心理描写がやたらと長い。冗長に思える。おまけに、登場人物の名前が理解しにくい。 主人公ネフュードフはドミートリイ・イワーノヴィッチで、マースロワはカチューシャでもある。 ロシアでは当然のこととして理解されることなのだろうが、どうもよくわからない。 上巻は慣れるまで時間がかかった。しかし、下巻になると、だんだん話が分かってきた。 ネフリュードフの疑問はトルストイの疑問であり、社会への憤りをストレートに出した小説なのだ。 主人公はマースロワの救済のためではなく、自分の魂の救済のために行動している。 しかし、それは利己的な気持ちからの行動ではない。 キリスト教とはほとんど無縁の者には理解できない原理によって行動しているのである。 解説によれば、トルストイ自身の体験がこれを書かせたものらしい。 しかし、問題はこの後だろう。続きを書きたいと思ったそうだが、ぜひ書いて貰いたかった。この後に来るはずの、苦悩、失敗、それを読みたかった。 もっとも、作品としては、何をすべきか、という新の目的を見いだすまでが重要だったのだろうが、これでは、読者としては結末がないまま終わられたような気になってしまう。
1999.11.04
コメント(0)
-

「ティファニーで朝食を」 【トルーマン・カポーティ/龍口直太郎】
ティファニーで朝食を(トルーマン・カポーティ/龍口直太郎|出版社:新潮文庫) 映画の原作。原作の小説があることは知らなかった。 むかし、こういうタイトルの映画があることを知った時、てっきりティファニーというのはレストランに違いないと思いこんでいた。実は宝石店であるということを知ったのは大学を卒業してしばらくたってからのことだ。 映画は見たことがない。しかし、どうしてこれを映画化しようとしたんだろう。 ほかに、「わが家は花ざかり」「ダイヤのギター」「クリスマスの思い出」の三編が収められているが、この三編のほうがよほど映画化しやすいだろう。 「わが家は花ざかり」は表題作と同じような状況で育った女が主人公なのだが、結末は全く違う。「ダイヤのギター」は、話はよく分かるし、印象にも残る。 中でも、「クリスマスの思い出」は、泣かせる話だ。欧米のものによくある、貧しいながらも幸福だった幼少期の思い出ものなのだが、欧米の人って、子供の頃は貧しくても幸福なのに、大人になると、どんなにお金があっても不幸になってしまうのだろうか、とさえ思わせる。 訳者は、この本が出版されたときニュー・ヨークにおり、ディファニーに食堂があるかを確かめに行ったという。訳者にとっては、映画化されたのは原作を知ったずっと後のことであり、映画に対してはいろいろと故障を申し立てているのが面白い。映画と原作とはだいぶ趣が違うようだ。
1999.09.09
コメント(0)
-
「青い麦」 【シドニ・ガブリエル・コレット/堀口大学】
青い麦(著者:シドニ・ガブリエル・コレット/堀口大学|出版社:新潮文庫) 「ふ・た・り・は、あーおいむぎ」というのは遠い昔に聞いた伊藤咲子の歌だ。当時、『青い麦』というタイトルの小説があることは知っていて、それから取ったのだな、とは思っていたが、読むのは今回が初めて。 読んでいるうちに『肉体の悪魔』を思い浮かべ、フランス人というのはよくもまあ、こんな事ばかり考えていられるものだ、とも思ったが、重要なのは何が書いてあるかではなく、どう書いてあるか、ということなわけで、翻訳を通してではあるが、日本人との違いをいろいろ考えさせられた。 例えば、「夜明け方から、やがて熱した地表が、耕した畝(うね)の、脱穀された麦の、湯気を立てる堆肥(たいひ)のにおいを、爽(さわ)やかな海の風に吹き払わせる時刻になるまでここ数日の八月の朝には、秋の匂いがしみていた。生垣(いけがき)の裾(すそ)には、いつまでも消えずに露が光っていた。」(p35) などという文章だけでも、感覚の違いが伝わってくる。 物語は、十六歳の少年と十五歳の少女の恋愛の物語なのだが、混乱・当惑・嫉妬というものが詳細に描かれている。こういうのを翻訳するのは大変だろう。
1999.07.07
コメント(0)
-

「人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ」 【ロバート・フルガム/池央耿】
人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ(著者:ロバート・フルガム/池央耿|出版社:河出文庫) ああ生きろ、こう生きろという本かと思ったら全くそう言うものではなかった。日常生活の中のありふれた出来事をどのように捕らえるかという、ものごとの受け止め方の本だった。 解説には『徒然草』に似ているとあるが、宗教者としての面がはっきりでている点は『方丈記』に共通すると感じた。
1999.05.07
コメント(0)
-
「肉体の悪魔」 【レーモン・ラディゲ/新庄嘉章】
肉体の悪魔(著者:レーモン・ラディゲ/新庄嘉章|出版社:新潮文庫) 20歳で死んだ男がこんなものを書き残していたとは。主人公には反省や罪悪感などというものは全くないが、どうも社会階層がはっきりしている時代のようなので、「自分はこういうことが許される人間なのだ」と割り切ってしまえば、何でもないことだったのだろうか。 フランス人の考えることはわからないな、とも思ったが、考えてみると、明治の日本人の小説にもこういうのはあったかもしれない。 現代で言うと、萩尾望都のマンガに近いものを感じた。
1999.01.18
コメント(0)
-
「外套」 【ゴーゴリ/平井肇】
外套(著者:ゴーゴリ/平井肇|出版社:岩波文庫) 「外套」は昔子供向けの本で読んだが、「鼻」は初めて。 こういう話だったのか。どちらも150年以上前に書かれたものだが、諧謔を帯びた描写に驚かされる。それまでロシアこういう小説の伝統があったわけではないようなので、これが登場した時にはみんな驚いたことだろう。 解説によれば、ドストエフスキーは「われわれは皆ゴーゴリの『外套』の中から生まれたのだ!」と言っているそうだが、内容といい、描写法といい、斬新なものだったのだろう。 訳は1938年のものをもとに1965年に少し手を入れたものということで、下宿の女主人を「主婦」と書くなど、今からみれば古めかしいところもあるが、わかりにくいというところはない。 ただ、仕立屋がハンカチに外套を包んで来たのには驚いた。「ハンカチ」とは風呂敷のような大きなものまで含まれるものだったのか。
1999.01.13
コメント(0)
-
「東京に暮す 1928~1936」 【カサリン・サンソム】
東京に暮す(著者:カサリン・サンソム/大久保美春|出版社:岩波書店) 1928年から1936年にかけて東京で暮らしたときのことをもとに、イギリス人に日本を紹介する目的で書かれたもの。 冷静に日本文化を見ており、イギリスの文化とは異なる文化も尊重する態度をとっている。 昭和初期の日本では、そこかしこでしゃがんでいる姿が見られたこと、列を作って並ぶ習慣がなかったことなど、興味深い。 列は作るようになったが、礼儀正しさ、謙虚さなどは失われてしまった。 旅行好きであること、通勤風景など、今と変わらない。 「跪く」という訳が頻繁に出てくるが、なぜ「正座する」と訳さなかったのだろうか。正座とはまた別の姿勢なのだろうか。
1997.10.14
コメント(0)
-

「わが家への道」 【ローラ・インガルス・ワイルダー】
わが家への道(著者:ローラ・インガルス・ワイルダー/谷口由美子|出版社:岩波書店) マンスフィールドを目指した時のローラの日記を中心に、その前後に、娘のローズが、自分の記憶をもとに当時のことを書いている。 結婚してから10年ほどたっている。 ローズの目から見たローラが、普通の主婦なのでややがっかり。アルマンゾにくってかかることもあったそうだ。 しかし、この後は幸福だったようで、よかった。
1996.01.11
コメント(0)
-

「はじめの四年間」 【ローラ・インガルス・ワイルダー】
はじめの四年間(著者:ローラ・インガルス・ワイルダー/谷口由美子|出版社:岩波書店) 夢のような新婚生活のはずなのに、毎年毎年自然の力によって収穫がだめになる。2度の出産、火事、乳児の死と、つらいことばかりが続いている。 作り話なら、幸せな結婚で終わりにすることもできるが、現実は結婚してからの生活の方が長いし、一人の大人として行動しなくてはならないのだから、常に現実に直面し、自分で問題を処理していかなくてはならない。 アルマンゾの不屈の精神には感心するが、ローラはつらかったろう。 これでは、あまり人に読ませようとは思わないわけだ。 読者としては、幸せな結婚をした、というところで終わりになっていれば、つらい生活を知らずにいられたのだが。
1996.01.10
コメント(0)
全57件 (57件中 1-50件目)
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 紅旗の陰謀/濱嘉之
- (2024-11-09 15:43:18)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 変な家2〜11の間取り図〜 雨穴
- (2024-11-10 20:34:23)
-
-
-

- 楽天ブックス
- 【特典】MASU Styling log(イラスト…
- (2024-11-10 21:32:36)
-








