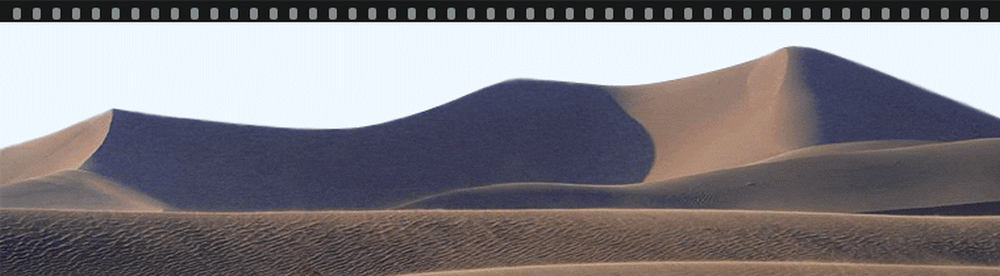PR
Keyword Search
Calendar
 New!
ひでわくさんさん
New!
ひでわくさんさん大相撲【幕下】楽し…
 New!
ほしのきらり。さん
New!
ほしのきらり。さんwestern peppermint … tougei1013さん
サウジで水着のファ… snowshoe-hareさん
surfersparadise☆2 ☆rokogirl☆さん
Comments
Freepage List
インドには、 カースト制度
が、まだ現存しています。日本で言えば、江戸時代の
士農工商
を、もっと 厳しくした
ようなものでしょう。
カーストとは、ポルトガルの casta(血統)
に由来するようです。インドでは、
古来から、 バルナ
と言われる身分・階層があったようです。
このバルナの元は、紀元前に遡り、前1500年頃に、中央アジアからインドや
イランへ移住した 古代民族アーリア人
に、あります。
彼らは、支配層を ラジャーニャ
、被支配者、平民を バイシャ
と呼んで差別して
いました。
現在のインド社会で、バルナは、下記の四大身分を言います。
バラモン
最上位の身分で、司祭者。祭式と教育を独占する特権階級。
クシャトリア
第2位の身分。王侯及び武士階層。
バイシャ
第3の身分。古くは農業、牧畜、商業に従う庶民をさしたが、のちに
商人のみに限られた。
シュードラ
第4の身分。隷属民で最下層。
この下に、アウト・カーストと呼ばれる、カーストにさえ入れない、 ハリジャン
(不可触民)
と言う階級があります。
今でも、すごい 宮殿に住む王族
もいれば、 ぼろいテントに生活する集団
も、
バスの中から、何度も見ました。バス通りからでも何度も見られるほどですから、
実態は、もっとすごい人数になるのでしょう。
ハリジャン
は、そのカーストを嫌って、 仏教や、モスリムに改宗
する人も
多いと聞きます。(アウランガーバードで)
何故、このような身分階級が、 延々と2千年も3千年
も続くのでしょう?
何故、身分格差のない、他の宗教に、もっと多くの人たちが 改宗しないのでしょう?
生まれた時から、そのように差別されて生きて育つと、それが、当たり前で、
そこに居る方が居心地が良いのでしょうか? 確かに、その集団に属していれば、
職業は、継承出来るようなので、何とか生きて行く事も出来るのでしょう。
バルナとも関連しますが、 ジャーティ
と言うのも、 インドの社会集団
を指します。
ジャーティとは、 ヒンドゥー教のなかにみられ、通婚と共食を許され 特定の
職業と結びついた集団
であります。
その職業の区分は、 3000余り
あり、さらに、それが、 25000種
にも細分化
されているそうです。これでは、その中から抜け出すのは、難しいでしょう。
子供達を見ると、どの子も、素敵な笑顔をしています。 乞食の女の子
に、すごく
利発そうな、素晴らしい笑顔の子
もいました。僕の行く先々に現れて、にっこり
笑うので、絶対に乞食に物を上げない主義の僕としても、心を動かされたほどです。
きちんとした教育さえ受ければ、きっと素晴らしい女性に成長するでしょうが、
乞食のまま一生を終える
と思うと、やはり心が痛みます。
その子達の、 ほとんどは裸足
です。汚い、洗った事のないような服を着ています。
服を着ているのは、まだ良い方で、小さい子は、パンツもはいてません。
その足も尻も、砂や泥で、汚れています。
一方で、町や、バスで、着飾った子供達も見かけます。両親と一緒に、観光旅行に
来ている子供達もいます。 格差が激しい
のですね。
今後、インドも益々、経済成長して行くでしょうが、僕は中国のように、急激な
経済成長は、難しい国ではないかと感じます。 もっとゆるやかな成長となるのでは
ないでしょうか?
何故なら、 カースト制度に安住
する多くの人たちがいるからです。
中国の場合、金儲けなら何でもすると言う、生きる力のようなものを、どこでも
感じますし、恐ろしくさえ思います。それはインドでも感じますが、中国に比べると
それが、小さいように思えます。
インド国外に住むインド系の人たちは、商売上手で、いい生活をしている
人も多いです。根は変わらないのでしょうから、やはり宗教の力は絶大です。
日本にも身分制度があり、江戸時代には、 士農工商
にも入れない 、「非人」、「えた」、
と言う最下層に位置づけられた賤民がいました。
生産的職業に就くことを許されず、 牢獄や処刑場での雑役
、 卑俗な遊芸
などに
従事、「えた」は、 死んだ牛馬の処理、罪人の処刑
、 皮革の製造
などに従事し、
特定の地域に居住させられました。
この制度は、明治になってすぐ、4年に廃止されました。
しかし、昭和の戦後になっても、あそこの地域には行くな、などと言われ、
その制度が事実上、あるかのような 差別が継続
していたやに聞いたりもします。
日本のように、宗教とは関係なく、制度化された身分制度、それが解除されても、
尚、60年も70年も残る身分制度です。
インドのように、宗教と職業、さらに居住区に結びついた身分制度が、簡単に
解消するとは、思えません。
インドが、今後、どうなって行くのか、 関心 があります。