1
片岡家の災難 1
災厄というものは突然やってくる。
いや、この災厄には前触れがあったのかもしれない。沈着冷静を絵に描いて額に入れ、毎日磨きこんでいるかのような片岡が、その日に限ってティーカップを落として割るという失態をやらかしたのだ。
「まずい。ばあさんのお気に入りだったのに」
片岡は淡々と言った。全然まずそうに聞えない。しかしこの出来事は、彼にとって大型の台風が直撃することを意味しているはずだった。猛烈な勢いの、である。
「げっ。極妻のお気に入りだったのかっ」
ぼくは片岡の部屋の襖を開け、廊下に立ち尽くしていた彼に言った。片岡の足元には小さな茶色い水溜りができており、十秒ほど前までティーカップだったと思われる残骸が散らばっている。
「人のばあさんを捕まえて極妻と言うな。うちはカタギだ。知らない人が聞いたら誤解するだろう」
「聞かなくても、見たらみんな誤解するから大丈夫」
「つくづく明代と同じことを言うな。本当はお前があいつの兄貴なんじゃないか。とても俺の妹とは思えん。あ、片付けはひとまずいいから、こっちを持っててくれ」
片岡は、破片を拾おうとしていたぼくを制し、持っていたお盆をぼくに預けると、雑巾を取りに階段を下っていった。カップの残骸は、この家の二階にある片岡の部屋の前に散らばっているのだ。
ぼくがお盆を受け取って部屋の中へ戻ると、赤松が心配そうに顔を上げた。
ぼくと友人の赤松はこの日、学校帰りに同学年の片岡篤史の家に寄っていた。通っている高校こそ同じだが、クラスも出身中学も違い、同じクラブに所属しているわけでもない三人が、何故この日に限ってここに集結することになったのかはよく分からない。ただ、鬼のように厳しい片岡のおばあさんの留守が要因の一つであることは間違いなかった。彼女には一度会ったきりだが、ぼくはその時、蛇に睨まれた時のカエルの気持ちが分かったような気がした。
赤松は廊下に出てくると、陶器の破片に手を伸ばした。
「二人とも怪我してない?」
「大丈夫。赤松も手、切らないように気をつけて」
ぼくが言ったそばから、彼女は「痛ッ」と悲鳴をあげた。赤松が拾い上げようとしていた大きめの破片がまた床に落ちて更に分裂する。彼女の指から赤い小さな玉が出現した。
だから言わんこっちゃない。ぼくは大きくため息を吐いた。
「赤松、頼むから動くな。お前が動くと仕事が増える」
「ごめんなさい・・・・・・」
赤松は切った指をくわえて小さくなっている。ぼくは片岡の学習机の上にお盆を置くと、自分の鞄から絆創膏を取り出して、彼女に手渡した。
「ありがとう。用意いいね」
「ま、ね」
誰のために用意してると思ってんだか。
わたしもちゃんと用意しといた方がいいな、と言いながら、大切そうに絆創膏を受け取る赤松を見て、そうだお前が自分で用意しとけよ、と思う今日この頃である。
そうこうしている内に、片岡が雑巾とビニール袋、それに新聞紙を抱えて戻ってきた。そして、それから一分とかからない間に、その場は元通りに片付けられた。
『ドジ、鈍感、鈍臭い』の三大看板を掲げ持つ赤松が手を出さなければ、事は迅速に運ぶのだ。もっとも、鈍感については、異論がなくもない。ぼくは時々、彼女がわざと鈍感を装っているのではないかと思うことがあるのだ。
しかし、赤松が鈍感だろうと敏感だろうと、この話にはあまり関係がない。どちらにしても、この時点で事を食い止めることはもう不可能だったのだから。
「とりあえず、おばあさんが留守で良かったな。でも、片岡の小指も今晩までの命か」
ぼくは、片岡が淹れなおしてくれたコーヒーをのん気に飲みながら、彼の手元を見つめた。
この時、この家の中でさっきと違っているところといえば、マイセンのティーカップが一つなくなって、代わりに破砕ゴミの塊が一つできたことくらいのはずだった。
「勝手に指詰め決定にするな。うちは極道じゃない」
「でも、すごく怒られちゃうんでしょう? マイセンなんてとっても高価だもん」
赤松は心配そうな面持ちだ。
「高価って、どれくらいするわけ?」
「私もよく知らないけど、一客が一万とか二万とかするものもあるらしいよ。安くても五千円は下らないんじゃないかな」
ぼくの疑問に、赤松が考えながら説明した。表情こそ不安げだが、こいつの喋り方はどうにも緊張感に欠ける。コギャル特有のあの話し方とは違うのだが、なんとなく語尾が間延びしているのだ。
「そんな高いの、なんで出しきたんだよ」
ぼくは片岡に向かってぼやいた。片岡は無表情に、なんでだろなと呟いて、窓の外へと目を向けた。
「まぁ、今晩は風呂場に宿泊だろうな」
ぼくは畳に膝をつき、床から一メートル程の位置にある窓を開けて、外へ身を乗り出した。彼の家の風呂は、家の外にあるのだ。
ひんやりした秋の風が心地良い。
「あれが風呂場?」
窓の下の方からは、一階部分の瓦屋根が張り出している。その屋根の端から一メートルも離れていない所へ小さな小屋があった。
「そ。今夜は冷えそうだから、毛布出しとかないとな。カイロも調達しとかないと。お前らを送っていくついでに買ってこよう」
「あ、明代ちゃんが帰ってきたぞ」
風呂場の小屋の横にある松の木の隙間から、この近辺の中学校の制服を着た髪の長い女の子が見えた。少しして、ただいまー、という元気のいい声が、古い家屋を震わせる。
「あいつが来たらうるさいから、そろそろ送っていこうか」
片岡が財布を握り締めて、腰を上げようとした時だった。
「うっきゃーっっっ!!!」
今度はここが崩れるかと思うほどの大音響が、家屋を揺るがした。
「ばあさんの部屋か」
反射的に片岡が立ち上がった。ぼくと赤松もそれに続く。
明代ちゃんの声がした一階の角部屋の襖は、開け放たれたままだった。四畳半の和室の真ん中に佇んでいた明代ちゃんが、ぼく達の気配に振り向いた。
「お兄ちゃん、おばあちゃんの部屋が・・・・・・どうしよう・・・・・・」
ビリビリに破れた障子紙。畳に転がる一輪挿し。散乱しているティッシュペーパーの山。
極妻、もとい片岡のおばあさんの部屋は、大型地震にでも見舞われたかのような惨状を呈していた。
――午後四時三十分。事件発生。
- つづく -
災厄というものは突然やってくる。
いや、この災厄には前触れがあったのかもしれない。沈着冷静を絵に描いて額に入れ、毎日磨きこんでいるかのような片岡が、その日に限ってティーカップを落として割るという失態をやらかしたのだ。
「まずい。ばあさんのお気に入りだったのに」
片岡は淡々と言った。全然まずそうに聞えない。しかしこの出来事は、彼にとって大型の台風が直撃することを意味しているはずだった。猛烈な勢いの、である。
「げっ。極妻のお気に入りだったのかっ」
ぼくは片岡の部屋の襖を開け、廊下に立ち尽くしていた彼に言った。片岡の足元には小さな茶色い水溜りができており、十秒ほど前までティーカップだったと思われる残骸が散らばっている。
「人のばあさんを捕まえて極妻と言うな。うちはカタギだ。知らない人が聞いたら誤解するだろう」
「聞かなくても、見たらみんな誤解するから大丈夫」
「つくづく明代と同じことを言うな。本当はお前があいつの兄貴なんじゃないか。とても俺の妹とは思えん。あ、片付けはひとまずいいから、こっちを持っててくれ」
片岡は、破片を拾おうとしていたぼくを制し、持っていたお盆をぼくに預けると、雑巾を取りに階段を下っていった。カップの残骸は、この家の二階にある片岡の部屋の前に散らばっているのだ。
ぼくがお盆を受け取って部屋の中へ戻ると、赤松が心配そうに顔を上げた。
ぼくと友人の赤松はこの日、学校帰りに同学年の片岡篤史の家に寄っていた。通っている高校こそ同じだが、クラスも出身中学も違い、同じクラブに所属しているわけでもない三人が、何故この日に限ってここに集結することになったのかはよく分からない。ただ、鬼のように厳しい片岡のおばあさんの留守が要因の一つであることは間違いなかった。彼女には一度会ったきりだが、ぼくはその時、蛇に睨まれた時のカエルの気持ちが分かったような気がした。
赤松は廊下に出てくると、陶器の破片に手を伸ばした。
「二人とも怪我してない?」
「大丈夫。赤松も手、切らないように気をつけて」
ぼくが言ったそばから、彼女は「痛ッ」と悲鳴をあげた。赤松が拾い上げようとしていた大きめの破片がまた床に落ちて更に分裂する。彼女の指から赤い小さな玉が出現した。
だから言わんこっちゃない。ぼくは大きくため息を吐いた。
「赤松、頼むから動くな。お前が動くと仕事が増える」
「ごめんなさい・・・・・・」
赤松は切った指をくわえて小さくなっている。ぼくは片岡の学習机の上にお盆を置くと、自分の鞄から絆創膏を取り出して、彼女に手渡した。
「ありがとう。用意いいね」
「ま、ね」
誰のために用意してると思ってんだか。
わたしもちゃんと用意しといた方がいいな、と言いながら、大切そうに絆創膏を受け取る赤松を見て、そうだお前が自分で用意しとけよ、と思う今日この頃である。
そうこうしている内に、片岡が雑巾とビニール袋、それに新聞紙を抱えて戻ってきた。そして、それから一分とかからない間に、その場は元通りに片付けられた。
『ドジ、鈍感、鈍臭い』の三大看板を掲げ持つ赤松が手を出さなければ、事は迅速に運ぶのだ。もっとも、鈍感については、異論がなくもない。ぼくは時々、彼女がわざと鈍感を装っているのではないかと思うことがあるのだ。
しかし、赤松が鈍感だろうと敏感だろうと、この話にはあまり関係がない。どちらにしても、この時点で事を食い止めることはもう不可能だったのだから。
「とりあえず、おばあさんが留守で良かったな。でも、片岡の小指も今晩までの命か」
ぼくは、片岡が淹れなおしてくれたコーヒーをのん気に飲みながら、彼の手元を見つめた。
この時、この家の中でさっきと違っているところといえば、マイセンのティーカップが一つなくなって、代わりに破砕ゴミの塊が一つできたことくらいのはずだった。
「勝手に指詰め決定にするな。うちは極道じゃない」
「でも、すごく怒られちゃうんでしょう? マイセンなんてとっても高価だもん」
赤松は心配そうな面持ちだ。
「高価って、どれくらいするわけ?」
「私もよく知らないけど、一客が一万とか二万とかするものもあるらしいよ。安くても五千円は下らないんじゃないかな」
ぼくの疑問に、赤松が考えながら説明した。表情こそ不安げだが、こいつの喋り方はどうにも緊張感に欠ける。コギャル特有のあの話し方とは違うのだが、なんとなく語尾が間延びしているのだ。
「そんな高いの、なんで出しきたんだよ」
ぼくは片岡に向かってぼやいた。片岡は無表情に、なんでだろなと呟いて、窓の外へと目を向けた。
「まぁ、今晩は風呂場に宿泊だろうな」
ぼくは畳に膝をつき、床から一メートル程の位置にある窓を開けて、外へ身を乗り出した。彼の家の風呂は、家の外にあるのだ。
ひんやりした秋の風が心地良い。
「あれが風呂場?」
窓の下の方からは、一階部分の瓦屋根が張り出している。その屋根の端から一メートルも離れていない所へ小さな小屋があった。
「そ。今夜は冷えそうだから、毛布出しとかないとな。カイロも調達しとかないと。お前らを送っていくついでに買ってこよう」
「あ、明代ちゃんが帰ってきたぞ」
風呂場の小屋の横にある松の木の隙間から、この近辺の中学校の制服を着た髪の長い女の子が見えた。少しして、ただいまー、という元気のいい声が、古い家屋を震わせる。
「あいつが来たらうるさいから、そろそろ送っていこうか」
片岡が財布を握り締めて、腰を上げようとした時だった。
「うっきゃーっっっ!!!」
今度はここが崩れるかと思うほどの大音響が、家屋を揺るがした。
「ばあさんの部屋か」
反射的に片岡が立ち上がった。ぼくと赤松もそれに続く。
明代ちゃんの声がした一階の角部屋の襖は、開け放たれたままだった。四畳半の和室の真ん中に佇んでいた明代ちゃんが、ぼく達の気配に振り向いた。
「お兄ちゃん、おばあちゃんの部屋が・・・・・・どうしよう・・・・・・」
ビリビリに破れた障子紙。畳に転がる一輪挿し。散乱しているティッシュペーパーの山。
極妻、もとい片岡のおばあさんの部屋は、大型地震にでも見舞われたかのような惨状を呈していた。
――午後四時三十分。事件発生。
- つづく -
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 2024/W24 ノマ通信(0610-0616)
- (2024-06-17 07:04:21)
-
-
-
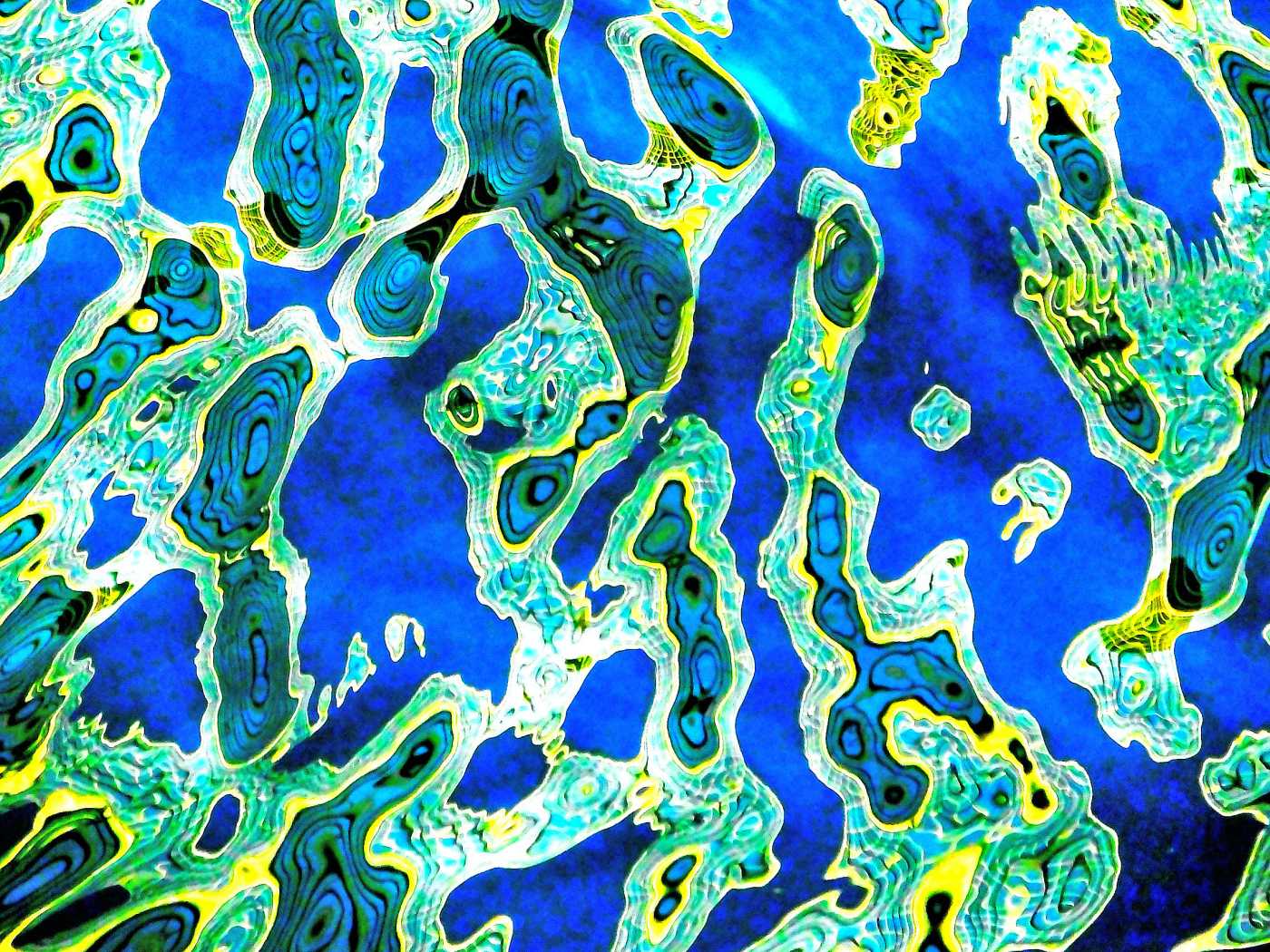
- 楽天写真館
- 1232 水の都 大阪ならでわの 光時…
- (2024-06-17 10:05:38)
-
© Rakuten Group, Inc.



