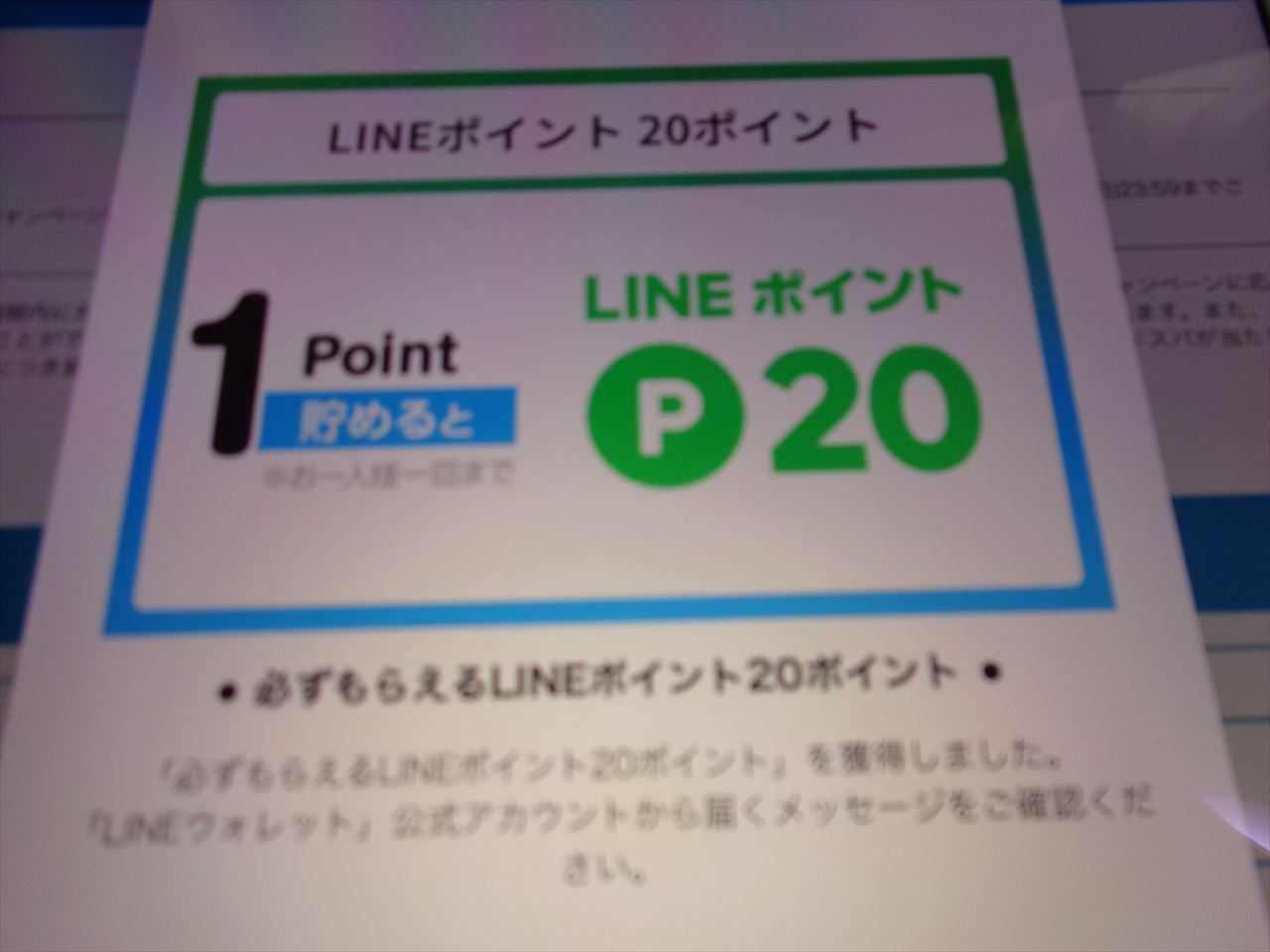2
ポケットの秘密 2
そのカッターを手に入れたのは、中学一年の時。
体育が終わって教室に帰ると、何故か私の筆箱の中に入っていた。私の物でないことは明らかだった。
私はカッターなんて持っていなかったし、カッターにシールを貼ったこともない。
誰かが嫌がらせに入れたのかもしれない。そう思った。
その頃、クラスでは一人の男の子がハブにされていた。その子は、表立っていじめられてはいなかったけれど、誰とも口をきいてもらえない日が続いていた。
私とは別の小学校から来た子だったので、どういう子なのかはよく知らなかったけど、足の速さを鼻にかけている嫌味な子だという噂だった。でも、体育祭などでも自慢だったという俊足を披露することはなかった。小学校の頃に活発だったという面影もどこにもなく、教室の片隅でひっそりと息を潜めて生活していた。
私が彼の声をまともに聞いたのは、中学三年生になってからだった。
私は誰かの嫌がらせなら、その人物を除く全ての人に、このことを知られないようにしようと思った。知られてしまえば、たちまち私はあの男の子と同じ立場に立たされるような気がした。
誰かに嫌われている子は、全てのクラスメートに嫌われる。
誰かに疎まれる存在だという噂は、梅雨の雨水が水溜りを作っていくように急速に広まり、気付いた時には暗い影の中に取り残されるだろう。陽の当たらない場所に閉じ込められた水溜りは、乾くことなく広く浅く浸透していく。学校という閉鎖された空間に。
私はこのことは誰にも言わず、カッターをポケットに入れて持ち帰った。
「あんな言い方したら、余計誤解を招くだろ」
昼休み。ぼくは人気のない旧校舎の一角で、自分の行動を棚に上げて、赤松に説教をたれていた。テーマは、先ほどの噂の否定の仕方について。
「ごめんなさい・・・・・・・」
赤松は地球儀の隣で小さくなっている。
旧校舎の最上階にあるこの教室の扉の上には、『多目的教室』というプレートが掲げられている。ここはかつて視聴覚資料を観るために使われていたらしいが、その役割は南校舎にできた新しい視聴覚教室に移行しており、現在は物置のような扱いをうけている。
クラスの違うぼくと赤松はいつも、この教室で昼休憩を過ごしていた。定位置は南窓際の真ん中あたり。地球儀の置かれている机の隣の席だ。埃っぽい教室の中で、ぼく達の利用する机だけが、表面を薄っすらとした白いものに覆われていなかった。
開いた窓からは、湿気を含んだ生暖かい風が流れてくる。まだ制服の衣替えが済んだばかりだというのに、すでに汗ばむほどの気温だ。
「別に俺に謝ることないけど。困るのは赤松だし」
赤松のデコピンをお見舞いしてやりたいという衝動を必死に抑えながら、彼女から視線を逸らせる。
赤松は「ごめんなさい」が多い。これは、彼女が自分の存在自体を「ごめんなさい」と思っている表れのようなもので、ぼくはそれが気に入らない。
少し前までは、「ごめんなさい」一回に付き、デコピン一回という取り決めをしていたのだが、それではぼくが赤松よりも上の存在であるというような感覚を彼女に植え付けてしまいそうなのでやめた。もっとも、やめたのはぼくの中だけで決めたことなので、赤松は現在もデコピンをされる危険を感じている。その証拠に、今、彼女は自分の額を両手で押さえていた。
「うん・・・・・・」
やっとデコピンをされる心配がないと確信したのか、赤松が両手を下ろして頷いた。
「それにしても、うまい言い訳考え付かなかったのかよ? まがりなりにも小説家だろ? ホラ話作って儲けてんだろ?」
「そんなに儲かってないよ」
俯いたまま赤松が言う。
赤松はぼーっとしている割に、とてつもなく内気な自分の将来を冷静に見据えているらしく、早々に普通の勤め人になる道を諦めていた。専業主婦になるのも相手が見付からないだろうと思った彼女は、文章を綴ることで生計を立てることにしたらしい。幸いそちら方面に才能があったらしく、中学の時にデビューして、現在は二冊の本も出版されている。
ちなみに、このことを知っているのは、この学校ではぼくを含めて二人くらいしかいない。
「いや、儲かってるかどうかじゃなくて。あの男は親戚だったとか、兄貴だったとか、なんとでも話を作っちゃえば良かっただろ」
ともすれば、論点のずれてしまいそうな赤松との会話をもとに戻すべく、ぼくが言った。
「あ、そうか! 頭いいなぁ。わたし、トロイから、とっさに思いつかなくて」
なんで思いつかないんだ、それくらいのこと。もっとも、こいつがうまく嘘を吐き通せるわけがないので、とっさに浮かばなくていいのかもしれないが。
「そんなんで、よく小説なんて書けるな」
思わずため息が出る。
「編集者の人に助けてもらってるから」
赤松は照れたように笑った。褒めたんじゃないっての。
編集者の人。それが藤田の言っていた『中年の男』だ。
赤松がファミリーレストランでその編集者と話しているのを、藤田の彼女が目撃したのが去年の秋。それは接点の全くないぼくと話し始めた頃でもあり、一時期は、冷やかしに混じって、聞くに堪えないような噂も囁かれていた。
ぼくは作家であることを公表してみてはどうかと提案したこともあるが、恥ずかしいから絶対に嫌だ、という赤松にしては珍しいくらいの断固拒否態勢を取られたので、その案はすぐに取り下げた。
そんな噂もだいぶ前にたち消えていたのだが、まさか藤田がまだ引きずっていたとは思わなかった。
「なんか、悪かったな」
藤田の言葉を思い出して、ぼくは謝った。
「え? なんで謝るの?」
赤松はきょとんとした。
「藤田があんなこと言うとは思わなかったからさ」
「ああ、あのこと。いいよ。もう覚えてない」
覚えてないはずがない。でも、ぼくはそれ以上突っ込むのをやめた。
援助交際の噂が広まった頃のことを思い出す。
あの時も赤松はいつもどおりぼーっとしていて、彼女の耳には噂が届いていないのかもしれないと思ったものだった。もちろんそんなわけはなく、赤松はしっかり噂を耳にしており、気に病んでもいた。後に、何故それを表に出さなかったのかと訊ねると、赤松はいつものように俯いてこう言った。
聞こえていない振りをしていれば、みんなから軽蔑されていることを認めずに済むでしょう?
今回も同じだ。言われたことを忘れたのではなく、なかったことにしようとしているのだろう。
軽蔑の視線は見ていないこと、ひどい噂は聞いていないことにして、彼女は自分を守っているのかもしれない。全ての感覚を仮死状態にして。
結果、無表情に俯いている少女が完成する。しかも自分に自信のない彼女の行動はいつもおどおどとしており、周りに暗い印象を与えてしまう。
「そういえば、今はなんか書いてんの? 小説」
ぼくはいたたまれなくなってきて、話題を変えた。あまりこのことについて考えていると、嫌なことを思い出しそうで怖くなったのだ。
赤松は少し驚いた顔をした。ぼくはが彼女の副業に関することを訊くことは、ほとんどなかったからだろう。ぼくは自他共に認める活字嫌いなのだ。
「今は、宝物をテーマに話を考えてるところ。すごく大切にしてる宝物ってある?」
急に質問を振られて、ぼくは咄嗟に頭に浮かんだ答えに、赤面しそうになった。
現在の宝物なら、目の前にいる。
もちろんそんなことを口にできるはずもないので、少しの間、頭の中の古い抽斗を開ける作業に勤しんだ。覗きたくない抽斗を開けないように用心しながら確認していくと、一つだけそれらしきものを取り出すことができた。
「カッター」
「カッター?」
赤松が復唱する。
「いや、正確に言うと、カッターに貼ってたシールだ」
「シール?」
「うん。どんなのだったかよく覚えてないけど、レーシングカーのだったと思う。従兄がF1の神様のだぞって言うから、なんかすごい貴重なもののような気がしてたんだ。それで、そのシールを貼ってたカッターをずっと持ち歩いてた。なんでカッターに貼ったのかは覚えてないけど」
「それ、今も持ってる?」
赤松は興味を持ったようだ。しかし、彼女の期待には応えられない。
「残念だけどもう持ってない。無くしたんだ。中一くらいまでは持ち歩いてたと思うけど」
「そう」
赤松は肩を落とした。ぼくは少しだけ申し訳ない気持ちになりながら、読みかけていた漫画雑誌に目を落とした。
「F1の神様って、アイルトン・セナとか?」
昼休憩も終わりに近づいた頃、本を読んでいた赤松が、ふいに口を開いた。
「誰それ?」
「F1の神様ってその人じゃないの? あ、セナは音速の貴公子だったかな」
「知らない。本当は、従兄が適当なこと言ってただけかもしれないし」
「F1に興味があったんじゃあ・・・・・・」
呆気に取られたように赤松が口ごもる。ぼくは漫画雑誌を閉じて、後を引き取った。
「ないよ。ただ速いものに興味があっただけ」
「速いもの?」
「うん。一番とか最速って言葉に弱かったんだ。ガキの頃は」
従兄には、このことをネタにいろいろとからかわれたものだ。本当は、F1の神様のマシンだなんて嘘っぱちで、あのシールを貼ったカッターを後生大事に持ち歩いていたぼくを見て、笑い転げていたのかもしれない。
「そうなんだ」
何故か複雑な表情を浮かべて、赤松は本を閉じた。
窓から見える空は、今にも雨を降らせようとしているような厚い雲に覆われていた。
- つづく -
そのカッターを手に入れたのは、中学一年の時。
体育が終わって教室に帰ると、何故か私の筆箱の中に入っていた。私の物でないことは明らかだった。
私はカッターなんて持っていなかったし、カッターにシールを貼ったこともない。
誰かが嫌がらせに入れたのかもしれない。そう思った。
その頃、クラスでは一人の男の子がハブにされていた。その子は、表立っていじめられてはいなかったけれど、誰とも口をきいてもらえない日が続いていた。
私とは別の小学校から来た子だったので、どういう子なのかはよく知らなかったけど、足の速さを鼻にかけている嫌味な子だという噂だった。でも、体育祭などでも自慢だったという俊足を披露することはなかった。小学校の頃に活発だったという面影もどこにもなく、教室の片隅でひっそりと息を潜めて生活していた。
私が彼の声をまともに聞いたのは、中学三年生になってからだった。
私は誰かの嫌がらせなら、その人物を除く全ての人に、このことを知られないようにしようと思った。知られてしまえば、たちまち私はあの男の子と同じ立場に立たされるような気がした。
誰かに嫌われている子は、全てのクラスメートに嫌われる。
誰かに疎まれる存在だという噂は、梅雨の雨水が水溜りを作っていくように急速に広まり、気付いた時には暗い影の中に取り残されるだろう。陽の当たらない場所に閉じ込められた水溜りは、乾くことなく広く浅く浸透していく。学校という閉鎖された空間に。
私はこのことは誰にも言わず、カッターをポケットに入れて持ち帰った。
「あんな言い方したら、余計誤解を招くだろ」
昼休み。ぼくは人気のない旧校舎の一角で、自分の行動を棚に上げて、赤松に説教をたれていた。テーマは、先ほどの噂の否定の仕方について。
「ごめんなさい・・・・・・・」
赤松は地球儀の隣で小さくなっている。
旧校舎の最上階にあるこの教室の扉の上には、『多目的教室』というプレートが掲げられている。ここはかつて視聴覚資料を観るために使われていたらしいが、その役割は南校舎にできた新しい視聴覚教室に移行しており、現在は物置のような扱いをうけている。
クラスの違うぼくと赤松はいつも、この教室で昼休憩を過ごしていた。定位置は南窓際の真ん中あたり。地球儀の置かれている机の隣の席だ。埃っぽい教室の中で、ぼく達の利用する机だけが、表面を薄っすらとした白いものに覆われていなかった。
開いた窓からは、湿気を含んだ生暖かい風が流れてくる。まだ制服の衣替えが済んだばかりだというのに、すでに汗ばむほどの気温だ。
「別に俺に謝ることないけど。困るのは赤松だし」
赤松のデコピンをお見舞いしてやりたいという衝動を必死に抑えながら、彼女から視線を逸らせる。
赤松は「ごめんなさい」が多い。これは、彼女が自分の存在自体を「ごめんなさい」と思っている表れのようなもので、ぼくはそれが気に入らない。
少し前までは、「ごめんなさい」一回に付き、デコピン一回という取り決めをしていたのだが、それではぼくが赤松よりも上の存在であるというような感覚を彼女に植え付けてしまいそうなのでやめた。もっとも、やめたのはぼくの中だけで決めたことなので、赤松は現在もデコピンをされる危険を感じている。その証拠に、今、彼女は自分の額を両手で押さえていた。
「うん・・・・・・」
やっとデコピンをされる心配がないと確信したのか、赤松が両手を下ろして頷いた。
「それにしても、うまい言い訳考え付かなかったのかよ? まがりなりにも小説家だろ? ホラ話作って儲けてんだろ?」
「そんなに儲かってないよ」
俯いたまま赤松が言う。
赤松はぼーっとしている割に、とてつもなく内気な自分の将来を冷静に見据えているらしく、早々に普通の勤め人になる道を諦めていた。専業主婦になるのも相手が見付からないだろうと思った彼女は、文章を綴ることで生計を立てることにしたらしい。幸いそちら方面に才能があったらしく、中学の時にデビューして、現在は二冊の本も出版されている。
ちなみに、このことを知っているのは、この学校ではぼくを含めて二人くらいしかいない。
「いや、儲かってるかどうかじゃなくて。あの男は親戚だったとか、兄貴だったとか、なんとでも話を作っちゃえば良かっただろ」
ともすれば、論点のずれてしまいそうな赤松との会話をもとに戻すべく、ぼくが言った。
「あ、そうか! 頭いいなぁ。わたし、トロイから、とっさに思いつかなくて」
なんで思いつかないんだ、それくらいのこと。もっとも、こいつがうまく嘘を吐き通せるわけがないので、とっさに浮かばなくていいのかもしれないが。
「そんなんで、よく小説なんて書けるな」
思わずため息が出る。
「編集者の人に助けてもらってるから」
赤松は照れたように笑った。褒めたんじゃないっての。
編集者の人。それが藤田の言っていた『中年の男』だ。
赤松がファミリーレストランでその編集者と話しているのを、藤田の彼女が目撃したのが去年の秋。それは接点の全くないぼくと話し始めた頃でもあり、一時期は、冷やかしに混じって、聞くに堪えないような噂も囁かれていた。
ぼくは作家であることを公表してみてはどうかと提案したこともあるが、恥ずかしいから絶対に嫌だ、という赤松にしては珍しいくらいの断固拒否態勢を取られたので、その案はすぐに取り下げた。
そんな噂もだいぶ前にたち消えていたのだが、まさか藤田がまだ引きずっていたとは思わなかった。
「なんか、悪かったな」
藤田の言葉を思い出して、ぼくは謝った。
「え? なんで謝るの?」
赤松はきょとんとした。
「藤田があんなこと言うとは思わなかったからさ」
「ああ、あのこと。いいよ。もう覚えてない」
覚えてないはずがない。でも、ぼくはそれ以上突っ込むのをやめた。
援助交際の噂が広まった頃のことを思い出す。
あの時も赤松はいつもどおりぼーっとしていて、彼女の耳には噂が届いていないのかもしれないと思ったものだった。もちろんそんなわけはなく、赤松はしっかり噂を耳にしており、気に病んでもいた。後に、何故それを表に出さなかったのかと訊ねると、赤松はいつものように俯いてこう言った。
聞こえていない振りをしていれば、みんなから軽蔑されていることを認めずに済むでしょう?
今回も同じだ。言われたことを忘れたのではなく、なかったことにしようとしているのだろう。
軽蔑の視線は見ていないこと、ひどい噂は聞いていないことにして、彼女は自分を守っているのかもしれない。全ての感覚を仮死状態にして。
結果、無表情に俯いている少女が完成する。しかも自分に自信のない彼女の行動はいつもおどおどとしており、周りに暗い印象を与えてしまう。
「そういえば、今はなんか書いてんの? 小説」
ぼくはいたたまれなくなってきて、話題を変えた。あまりこのことについて考えていると、嫌なことを思い出しそうで怖くなったのだ。
赤松は少し驚いた顔をした。ぼくはが彼女の副業に関することを訊くことは、ほとんどなかったからだろう。ぼくは自他共に認める活字嫌いなのだ。
「今は、宝物をテーマに話を考えてるところ。すごく大切にしてる宝物ってある?」
急に質問を振られて、ぼくは咄嗟に頭に浮かんだ答えに、赤面しそうになった。
現在の宝物なら、目の前にいる。
もちろんそんなことを口にできるはずもないので、少しの間、頭の中の古い抽斗を開ける作業に勤しんだ。覗きたくない抽斗を開けないように用心しながら確認していくと、一つだけそれらしきものを取り出すことができた。
「カッター」
「カッター?」
赤松が復唱する。
「いや、正確に言うと、カッターに貼ってたシールだ」
「シール?」
「うん。どんなのだったかよく覚えてないけど、レーシングカーのだったと思う。従兄がF1の神様のだぞって言うから、なんかすごい貴重なもののような気がしてたんだ。それで、そのシールを貼ってたカッターをずっと持ち歩いてた。なんでカッターに貼ったのかは覚えてないけど」
「それ、今も持ってる?」
赤松は興味を持ったようだ。しかし、彼女の期待には応えられない。
「残念だけどもう持ってない。無くしたんだ。中一くらいまでは持ち歩いてたと思うけど」
「そう」
赤松は肩を落とした。ぼくは少しだけ申し訳ない気持ちになりながら、読みかけていた漫画雑誌に目を落とした。
「F1の神様って、アイルトン・セナとか?」
昼休憩も終わりに近づいた頃、本を読んでいた赤松が、ふいに口を開いた。
「誰それ?」
「F1の神様ってその人じゃないの? あ、セナは音速の貴公子だったかな」
「知らない。本当は、従兄が適当なこと言ってただけかもしれないし」
「F1に興味があったんじゃあ・・・・・・」
呆気に取られたように赤松が口ごもる。ぼくは漫画雑誌を閉じて、後を引き取った。
「ないよ。ただ速いものに興味があっただけ」
「速いもの?」
「うん。一番とか最速って言葉に弱かったんだ。ガキの頃は」
従兄には、このことをネタにいろいろとからかわれたものだ。本当は、F1の神様のマシンだなんて嘘っぱちで、あのシールを貼ったカッターを後生大事に持ち歩いていたぼくを見て、笑い転げていたのかもしれない。
「そうなんだ」
何故か複雑な表情を浮かべて、赤松は本を閉じた。
窓から見える空は、今にも雨を降らせようとしているような厚い雲に覆われていた。
- つづく -
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 2024/W24 ノマ通信(0610-0616)
- (2024-06-17 07:04:21)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-
© Rakuten Group, Inc.