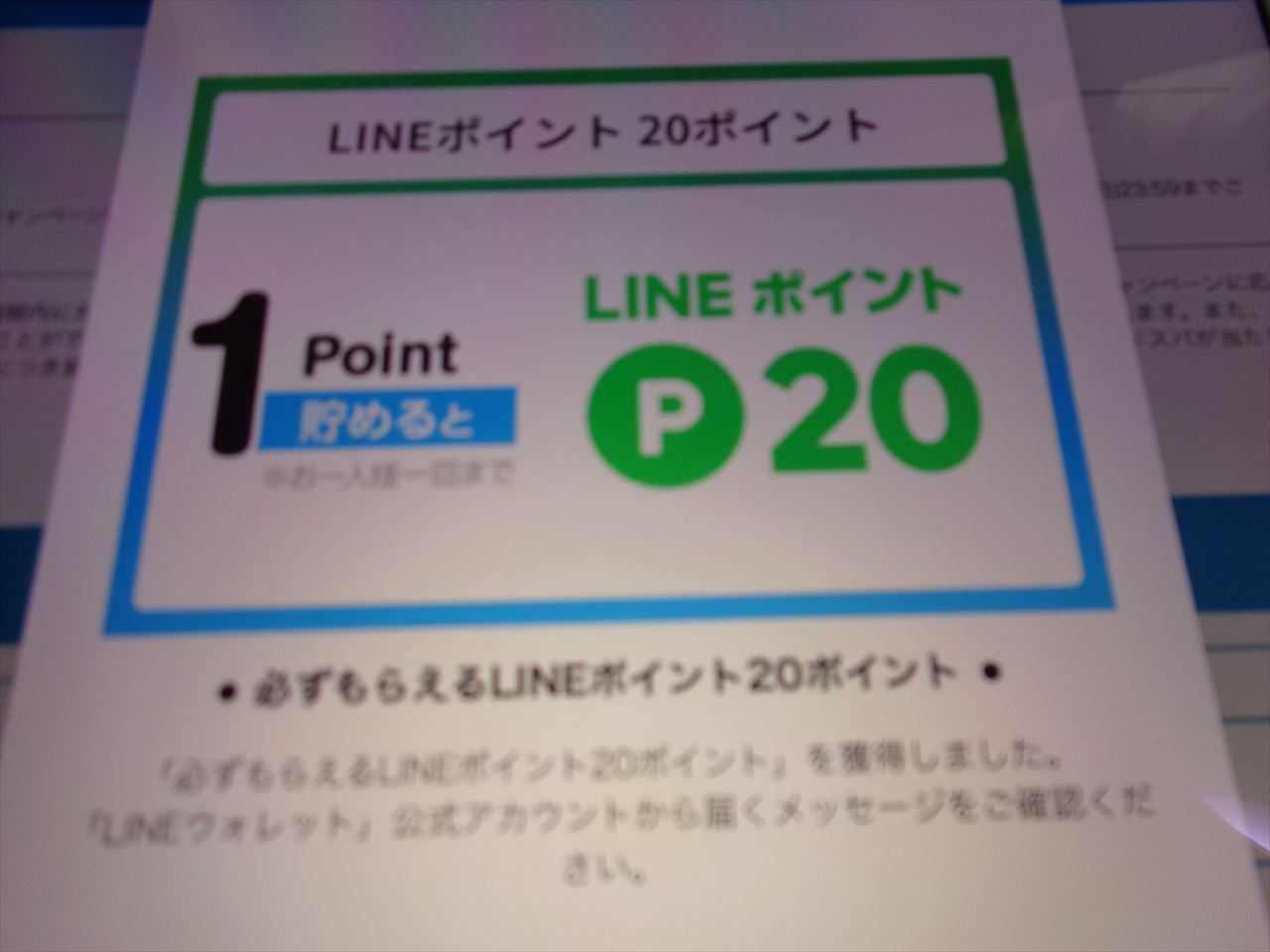6
ポケットの秘密 6
「ただいま」
返事のないことは分かっているのだけど、一応口にしてから家に入る。台所の前を通ると、アルコールの匂いが鼻をついた。薄暗いキッチンの中、テーブルに突っ伏している母の姿がある。手にはビールの缶をしっかりと握り締めている。
キッチン・ドランカー。考えたくはないけれど、母はそうなりつつあるのかもしれない。
いつもなら母に一言声を掛けるところを、そのまま通り過ぎて二階の自室へ向かった。とてもそんな気になれなかったから。
彼の話を聞いてからの記憶があまりない。
幼馴染とは家の前で別れた。彼女の家はこの三軒先にある。でも、彼らと別れて、彼女とどんな話をしたのか、全く覚えていなかった。
自室に入り学習机の横に鞄を下ろすと、私はベットに寝転んだ。
スカートのポケットからカッターを取り出してみる。握ったり刃を出してみたりしてしばらくもてあそんでいたけれど、いつもの安堵感は伝わってこなかった。
じめじめした空気が体にまとわりつく。校舎特有の、カビと埃とチョークの粉を混ぜ合わせたような臭いがいつもより濃い。雨が降り出すのかもしれない。この地域が梅雨入りしたのは、昨日のことだった。
三限目は視聴覚室での授業だった。ぼくは日直だったので、授業が終わった後もそこに残り、後片付けを手伝っていた。
「あ、そのプロジェクターは出したままにしておいて」
振り向くと、開け放していた扉の前に杉本瑞葉が立っていた。ぼくは持ち上げていたプロジェクターを教卓の上に戻した。
「次はあんた達のクラスだったのか」
「そ。私、今日日直だから、それ出しておくように言われてたの。出してあったなんてラッキー」
彼女は扉を閉めると、プロジェクターとぼくの所へ近寄ってきた。近くに来ると、彼女の背の高さがよく分かる。百六十五センチは越しているだろう。
「俺も片付けずに済んでラッキー。じゃあ」
ぼくが自分の教室へ帰ろうと、彼女の横を通り過ぎようとした時だった。
「赤松さんと仲良しなのは、同類相憐れむってやつ?」
突然の言葉に、背筋に緊張が走った。誰もいない空洞のような教室。出入り口の扉がやたらと遠くに感じる。ぼくは平静を装って答えた。
「何それ?」
「同じ中学だったって言ったでしょ?」
嫌な奴と知り合ってしまったもんだ。
「同族嫌悪ならしたことあるけど。第一、赤松が俺を同類だと思う理由がない」
「中学の時のこと、話してないの?」
足元に穴が開いて、どこかへ急降下しているような気持ち悪さを覚えた。エレベーターやジェットコースターに乗ったとき、体は下へ落ちているのに、内臓はその速さへついていけず、もとの場所に留まろうとしているような、あの気持ちの悪さだ。
「『自分は嫌われ者でした』なんて、わざわざ言って歩く奴がいるかよ」
「赤松さんなら、一人ぼっちで寂しそうな人に『私も同じよ』って声をかけてあげると思うけど」
「生憎と俺はそこまでお人好しじゃないんで」
杉本は何が言いたいのだ。彼女はぼくを追い詰めるために現れたのだろうか。開けないようにしている記憶の抽斗をこじ開けるために。
「あなたの過去を知ってるから、赤松さんも普通に喋れるんだと思ってた」
杉本は静かに言った。鳥肌が立つほど優しげに聞こえる声で。
「彼女が人と普通に話してるところを見たの、昨日が初めてだったから。あなたとは喋れるんだって思ったら、自分と同じだと思えるから話しやすいのかもしれないって考えが浮かんだの。同じ理由で、あなたも彼女と一緒にいるのかなって」
「単なる慣れの問題じゃない? 俺は何も話してないし、そういう理由で一緒にいるわけでもない」
そう思うなら、傍になどいない。面倒な感情など抱かない。
「じゃあ、なんで一緒にいるの? やっぱりかわいそうだから?」
「あんたはかわいそうだから赤松に声をかけたわけ?」
彼女はかぶりを振った。
「違うわ」
「俺も違う。ただ自分のしたいようにしてるだけ」
「嫌悪感があるのに?」
「今はない。あいつと俺じゃ全然違うから。苛々することはあるけど」
「どういう意味?」
「さあ?」
困惑の表情を浮かべてぼくを見ている杉本を残し、再び歩き出そうとすると、また呼び止められた。
「中学の靴切り裂き事件の犯人、本当に覚えていないの?」
真っすぐにぼくの目を見て訊いてくる。
「ああ」
「本当に見たの?」
「さぁな。白昼夢だったのかも。夢に見るほどの興味もなかったんだけど」
「そう」
彼女が自分から目を逸らせたのを期に、ぼくは逃げるように視聴覚室を出た。シャツが背中に張り付いていた。
視聴覚室を出ると、今度は田口加奈子に会った。仲の良い杉本が日直で先に行ってしまったので、一人で移動していたらしい。
「あ、ちょっといいかな?」
「早く教室帰りたいんだけど。次の授業あるし」
「ちょっとだけだから」
「まぁいいけど」
ぼくは渋りながらも、ここら辺でうろうろしていれば赤松に会って、午後にある英語の授業のノートを借りられるかもしれないという打算の為に、田口の話に付き合うことにした。
彼女がジュースを奢ってくれると言うので、自動販売機のある場所へ移動する。赤松がそこを通るかどうかは少し不安だったが、ぼくが気を付けていれば、姿を見止めて声をかけることくらいはできるだろう。
ぼくがアイスコーヒーのボタンを押すと、唸るような声を上げながら紙コップへ茶色い液体が注がれる。それを覗き込んでいる田口は、小さな子供のようだった。実際、彼女の身長ときたら、百五十センチもないんじゃないかと思うほどなのだ。背の高い杉本と一緒にいるせいで低く見えるのかと思っていたが、どうやら本当に小さいらしい。
「話って?」
ぼくは田口からコーヒーを受け取りながら促した。彼女は周囲を見回し、人影がないことを確認してから切り出した。
「うん。あのね、中学の靴紛失事件の犯人、本当に覚えてないの?」
「ああ、そのこと。うん、覚えてない。現実に見たのかどうかさえ怪しい気がしてきたところ」
「本当に?」
「うん」
何度も聞き返してくる田口を訝しみながら、ぼくはコーヒーをすすった。
「どうしてそんなこと訊くの?」
杉本にもしたかった質問を、田口にぶつけてみる。しかし、ちょっとね、の一言で片付けられてしまった。
「赤松さんとは本当に付き合ってないの?」
話題を変えようとしたのか、田口がわざとらしい声を出した。杉本と田口の頭には、ぼくイコール中学の靴泥棒目撃者プラス赤松、という図式しかないらしい。
「別に」
「じゃあ、どうして彼女とよく一緒にいるの? 中学も違ったし、去年も同じクラスじゃなかったよね?」
「さあ? なんとなく」
「ひょっとして好きなの?」
「別に」
こういう質問は、赤松と話し始めた頃よく耳にした。好きなのだろうと確信したように言われれば動揺もするが、疑問系で訊かれるぶんには平常心でいられる。
面倒臭いので、こんな感じでのらりくらりと受け答えしているうちに、冷やかしたり質問してきたりする奴もいなくなった。その代わり、恋人同士だと誤解してくれている人間も少なくないらしい。藤田はその代表格だ。彼にはきちんと訂正しているのに、全く聞く耳を持たない。赤松には悪いが、今更他の奴にまで弁解しようという気は、ぼくにはない。
しかし、勘違いしている人間を見ると、嬉しいというよりも悲しくなってしまうのは、どこかおかしいのだろうか。
「私ね、赤松さんに女子の友達が少ないのって、あなたのせいもあると思うの」
「え?」
あまりに不当ではないかと思える言葉に、ぼくはコーヒーをこぼしそうになった。
「なんで俺のせいなの?」
彼女は思案顔で自販機にもたれかかった。
「あなた、いつも藤田君と追いかけっこしてるから、結構有名人じゃない? 背も高いし運動神経もいいから、憧れてる女の子もチラホラいるのよ。だからあなたと仲良くしてると、そういう子から妬まれちゃうんじゃないかな」
褒められてんだかけなされてんだかよく分からない。追いかけっこなんかしたくてしてるわけじゃないし、自分が有名だなんて初耳だ。しかも迷惑だ。ぼくは穏便な学生生活を営みたいってのに。
「だから俺にどうしろと?」
「どうしろってこともないけど・・・・・・」
彼女は俯いて、自分のスカートの裾あたりを見つめた。膝より少し長い丈のスカートは、背の低い彼女には少し長すぎる気がした。
遠まわしに、赤松に関わってくれるなと言いたいらしい。
そういえば田口も同じ中学だったことを思い出し、苦いものがこみ上げてきた。ぼくのような人間と仲の良い友達は、欲しくないといったところか。
過去というはやっかいなものだ。どこまでも追いかけてきて、人の恋路まで邪魔しやがる。
「悪いけど、人に言われて知り合いやめるつもりないから」
ぼくはコーヒーを飲み干して、空の紙コップをゴミ箱へ放った。それはきれいな放物線を描き、燃えるゴミ用の籠の端に当たって床に転がった。
どこから見ていたのか、タカヨシが駆け寄ってきてそれをくわえる。ぼくは犬の口からそっとそれを取り上げると、ゴミ箱へ入れた。
「私もその一人なの」
田口の思い切ったような物言いに、タカヨシから彼女へ視線を移す。
「私も憧れてる女の子の一人なの。覚えてない? 中学の時のこと。あなた、言ってくれたじゃない。私はあれで救われたの」
田口は、中学時代にぼくが言った言葉とその状況について説明した。彼女の顔は覚えていなかったが、その言葉はしっかり覚えていた。
それこそ、憐れみから出たものだったからだ。
「悪いけど覚えてない」
ぼくは彼女を残してその場を離れた。タカヨシが後をついてくる。犬の爪音に混じるように、くぐもったテレビの砂嵐のような音がする。いつの間にか雨が降り始めていた。
赤松に会う気は、もうなくなっていた。
- つづく -
「ただいま」
返事のないことは分かっているのだけど、一応口にしてから家に入る。台所の前を通ると、アルコールの匂いが鼻をついた。薄暗いキッチンの中、テーブルに突っ伏している母の姿がある。手にはビールの缶をしっかりと握り締めている。
キッチン・ドランカー。考えたくはないけれど、母はそうなりつつあるのかもしれない。
いつもなら母に一言声を掛けるところを、そのまま通り過ぎて二階の自室へ向かった。とてもそんな気になれなかったから。
彼の話を聞いてからの記憶があまりない。
幼馴染とは家の前で別れた。彼女の家はこの三軒先にある。でも、彼らと別れて、彼女とどんな話をしたのか、全く覚えていなかった。
自室に入り学習机の横に鞄を下ろすと、私はベットに寝転んだ。
スカートのポケットからカッターを取り出してみる。握ったり刃を出してみたりしてしばらくもてあそんでいたけれど、いつもの安堵感は伝わってこなかった。
じめじめした空気が体にまとわりつく。校舎特有の、カビと埃とチョークの粉を混ぜ合わせたような臭いがいつもより濃い。雨が降り出すのかもしれない。この地域が梅雨入りしたのは、昨日のことだった。
三限目は視聴覚室での授業だった。ぼくは日直だったので、授業が終わった後もそこに残り、後片付けを手伝っていた。
「あ、そのプロジェクターは出したままにしておいて」
振り向くと、開け放していた扉の前に杉本瑞葉が立っていた。ぼくは持ち上げていたプロジェクターを教卓の上に戻した。
「次はあんた達のクラスだったのか」
「そ。私、今日日直だから、それ出しておくように言われてたの。出してあったなんてラッキー」
彼女は扉を閉めると、プロジェクターとぼくの所へ近寄ってきた。近くに来ると、彼女の背の高さがよく分かる。百六十五センチは越しているだろう。
「俺も片付けずに済んでラッキー。じゃあ」
ぼくが自分の教室へ帰ろうと、彼女の横を通り過ぎようとした時だった。
「赤松さんと仲良しなのは、同類相憐れむってやつ?」
突然の言葉に、背筋に緊張が走った。誰もいない空洞のような教室。出入り口の扉がやたらと遠くに感じる。ぼくは平静を装って答えた。
「何それ?」
「同じ中学だったって言ったでしょ?」
嫌な奴と知り合ってしまったもんだ。
「同族嫌悪ならしたことあるけど。第一、赤松が俺を同類だと思う理由がない」
「中学の時のこと、話してないの?」
足元に穴が開いて、どこかへ急降下しているような気持ち悪さを覚えた。エレベーターやジェットコースターに乗ったとき、体は下へ落ちているのに、内臓はその速さへついていけず、もとの場所に留まろうとしているような、あの気持ちの悪さだ。
「『自分は嫌われ者でした』なんて、わざわざ言って歩く奴がいるかよ」
「赤松さんなら、一人ぼっちで寂しそうな人に『私も同じよ』って声をかけてあげると思うけど」
「生憎と俺はそこまでお人好しじゃないんで」
杉本は何が言いたいのだ。彼女はぼくを追い詰めるために現れたのだろうか。開けないようにしている記憶の抽斗をこじ開けるために。
「あなたの過去を知ってるから、赤松さんも普通に喋れるんだと思ってた」
杉本は静かに言った。鳥肌が立つほど優しげに聞こえる声で。
「彼女が人と普通に話してるところを見たの、昨日が初めてだったから。あなたとは喋れるんだって思ったら、自分と同じだと思えるから話しやすいのかもしれないって考えが浮かんだの。同じ理由で、あなたも彼女と一緒にいるのかなって」
「単なる慣れの問題じゃない? 俺は何も話してないし、そういう理由で一緒にいるわけでもない」
そう思うなら、傍になどいない。面倒な感情など抱かない。
「じゃあ、なんで一緒にいるの? やっぱりかわいそうだから?」
「あんたはかわいそうだから赤松に声をかけたわけ?」
彼女はかぶりを振った。
「違うわ」
「俺も違う。ただ自分のしたいようにしてるだけ」
「嫌悪感があるのに?」
「今はない。あいつと俺じゃ全然違うから。苛々することはあるけど」
「どういう意味?」
「さあ?」
困惑の表情を浮かべてぼくを見ている杉本を残し、再び歩き出そうとすると、また呼び止められた。
「中学の靴切り裂き事件の犯人、本当に覚えていないの?」
真っすぐにぼくの目を見て訊いてくる。
「ああ」
「本当に見たの?」
「さぁな。白昼夢だったのかも。夢に見るほどの興味もなかったんだけど」
「そう」
彼女が自分から目を逸らせたのを期に、ぼくは逃げるように視聴覚室を出た。シャツが背中に張り付いていた。
視聴覚室を出ると、今度は田口加奈子に会った。仲の良い杉本が日直で先に行ってしまったので、一人で移動していたらしい。
「あ、ちょっといいかな?」
「早く教室帰りたいんだけど。次の授業あるし」
「ちょっとだけだから」
「まぁいいけど」
ぼくは渋りながらも、ここら辺でうろうろしていれば赤松に会って、午後にある英語の授業のノートを借りられるかもしれないという打算の為に、田口の話に付き合うことにした。
彼女がジュースを奢ってくれると言うので、自動販売機のある場所へ移動する。赤松がそこを通るかどうかは少し不安だったが、ぼくが気を付けていれば、姿を見止めて声をかけることくらいはできるだろう。
ぼくがアイスコーヒーのボタンを押すと、唸るような声を上げながら紙コップへ茶色い液体が注がれる。それを覗き込んでいる田口は、小さな子供のようだった。実際、彼女の身長ときたら、百五十センチもないんじゃないかと思うほどなのだ。背の高い杉本と一緒にいるせいで低く見えるのかと思っていたが、どうやら本当に小さいらしい。
「話って?」
ぼくは田口からコーヒーを受け取りながら促した。彼女は周囲を見回し、人影がないことを確認してから切り出した。
「うん。あのね、中学の靴紛失事件の犯人、本当に覚えてないの?」
「ああ、そのこと。うん、覚えてない。現実に見たのかどうかさえ怪しい気がしてきたところ」
「本当に?」
「うん」
何度も聞き返してくる田口を訝しみながら、ぼくはコーヒーをすすった。
「どうしてそんなこと訊くの?」
杉本にもしたかった質問を、田口にぶつけてみる。しかし、ちょっとね、の一言で片付けられてしまった。
「赤松さんとは本当に付き合ってないの?」
話題を変えようとしたのか、田口がわざとらしい声を出した。杉本と田口の頭には、ぼくイコール中学の靴泥棒目撃者プラス赤松、という図式しかないらしい。
「別に」
「じゃあ、どうして彼女とよく一緒にいるの? 中学も違ったし、去年も同じクラスじゃなかったよね?」
「さあ? なんとなく」
「ひょっとして好きなの?」
「別に」
こういう質問は、赤松と話し始めた頃よく耳にした。好きなのだろうと確信したように言われれば動揺もするが、疑問系で訊かれるぶんには平常心でいられる。
面倒臭いので、こんな感じでのらりくらりと受け答えしているうちに、冷やかしたり質問してきたりする奴もいなくなった。その代わり、恋人同士だと誤解してくれている人間も少なくないらしい。藤田はその代表格だ。彼にはきちんと訂正しているのに、全く聞く耳を持たない。赤松には悪いが、今更他の奴にまで弁解しようという気は、ぼくにはない。
しかし、勘違いしている人間を見ると、嬉しいというよりも悲しくなってしまうのは、どこかおかしいのだろうか。
「私ね、赤松さんに女子の友達が少ないのって、あなたのせいもあると思うの」
「え?」
あまりに不当ではないかと思える言葉に、ぼくはコーヒーをこぼしそうになった。
「なんで俺のせいなの?」
彼女は思案顔で自販機にもたれかかった。
「あなた、いつも藤田君と追いかけっこしてるから、結構有名人じゃない? 背も高いし運動神経もいいから、憧れてる女の子もチラホラいるのよ。だからあなたと仲良くしてると、そういう子から妬まれちゃうんじゃないかな」
褒められてんだかけなされてんだかよく分からない。追いかけっこなんかしたくてしてるわけじゃないし、自分が有名だなんて初耳だ。しかも迷惑だ。ぼくは穏便な学生生活を営みたいってのに。
「だから俺にどうしろと?」
「どうしろってこともないけど・・・・・・」
彼女は俯いて、自分のスカートの裾あたりを見つめた。膝より少し長い丈のスカートは、背の低い彼女には少し長すぎる気がした。
遠まわしに、赤松に関わってくれるなと言いたいらしい。
そういえば田口も同じ中学だったことを思い出し、苦いものがこみ上げてきた。ぼくのような人間と仲の良い友達は、欲しくないといったところか。
過去というはやっかいなものだ。どこまでも追いかけてきて、人の恋路まで邪魔しやがる。
「悪いけど、人に言われて知り合いやめるつもりないから」
ぼくはコーヒーを飲み干して、空の紙コップをゴミ箱へ放った。それはきれいな放物線を描き、燃えるゴミ用の籠の端に当たって床に転がった。
どこから見ていたのか、タカヨシが駆け寄ってきてそれをくわえる。ぼくは犬の口からそっとそれを取り上げると、ゴミ箱へ入れた。
「私もその一人なの」
田口の思い切ったような物言いに、タカヨシから彼女へ視線を移す。
「私も憧れてる女の子の一人なの。覚えてない? 中学の時のこと。あなた、言ってくれたじゃない。私はあれで救われたの」
田口は、中学時代にぼくが言った言葉とその状況について説明した。彼女の顔は覚えていなかったが、その言葉はしっかり覚えていた。
それこそ、憐れみから出たものだったからだ。
「悪いけど覚えてない」
ぼくは彼女を残してその場を離れた。タカヨシが後をついてくる。犬の爪音に混じるように、くぐもったテレビの砂嵐のような音がする。いつの間にか雨が降り始めていた。
赤松に会う気は、もうなくなっていた。
- つづく -
© Rakuten Group, Inc.