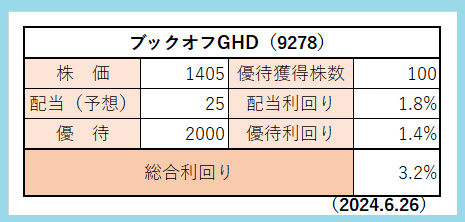12
ポケットの秘密 12
昨夜のことだった。
私が帰宅した時には寝室に引きこもって出てこなかった母が、私の部屋を訪ねてきた。最近やっとアルコールの臭いが消えてきたけれどまたいつ飲み始めるかと油断ならなかったので、一人にしてほしいと思いつつもドアを開けた。
母は部屋に入ってくると嵌め込み式の棚の所へ行き、そこに飾っていた写真を手に取った。それは、中学の修学旅行で撮った学年全体の集合写真だった。
「ごめんね、勝手に転校のこと決めちゃって」
ポツリと、母が言った。
「どうしたの? 急に」
私はベッドに腰掛け、いつものように明るく返した。
「お母さん、自分のことばかりで、あなたのこと考えてあげてなかったよね。あなただって、お友達と別れたくないわよね。今日ね、言われちゃった」
母は目を写真に落としたまま語った。
私が帰宅する前に幼馴染がうちに来たこと。そして、昼休憩に私が喋ってしまった弱音を母に伝え、もっと私のことを考えてほしいと訴えて帰ったこと。それでいろいろ考えてしまったこと。
私は苦い思いで聞いていた。無意識にシーツを強く掴んでいた。彼女にぶちまけてしまったことが悔やまれた。
「本当にごめんね。あなたを信頼してなかったわけじゃないの」
母は写真を棚に戻して私の前に来ると、床に膝をつけてこちらを見上げる格好になった。彼女の顔は泣きそうになっていた。
「いいのよ。気にしないで。私が子供だっただけだもん」
私は励ますように微笑んだ。母に見付からないように、そっとシーツから手を離す。その手を母の手が包んだ。
「ううん。あなたは十分支えになってくれてた。あなたに相談せずに決めてしまったのは、あなたに甘えてたからだわ。自分のことばかり考えて、あなたはお母さんについてきてくれるって、勝手に決め付けてた。あなただって、離れたくない人達や生活があったのに。本当にごめんね。こんなお母さんでごめんね」
謝罪の言葉を繰り返しながら、私の手を強く握り締め、顔を伏せて泣き崩れる母に、私は必死で声をかけた。
「もういいよ、お母さん。分かったから。私の方こそごめんね。そんなつもりで言ったんじゃないの。お母さんを傷つけるつもりで言ったんじゃないの」
母と同じように床に座り、目の高さを合わせる。すると母は顔を上げ、懇願するような目を私に向けた。
「こんなお母さんでも、見捨てないでいてくれる? 一緒に行ってくれる?」
「当たり前じゃない・・・・・・」
「ありがとう・・・・・・」
母は私を抱きしめて、そう繰り返した。私は母の背中をさすりながら、彼の顔を思い浮かべていた。
幼馴染に感謝するべきなのかもしれないけれど、素直にそんな気持ちにはなれなかった。
彼女は何を思って、母に私の気持ちを伝えてしまったのだろう。単純に、私のことを想ってしてくれたのかもしれない。でも、そんな見方をできない屈折した自分がいる。
幼馴染はうちの事情を知っていた。母がどういう精神状態にあるのかも全て。幸い昨日は考え込んでもお酒に手を出さなかったようだけど、母にあんなことを言うというのは、うちを引っ掻き回したいからではないか。私の重荷が増えるのを楽しんでいるのではないか。
考えすぎだとは思いつつ、彼女を見る目が疑いの眼差しになってしまう。
放課後、彼女が私に「一緒に帰ろう」と言わずに教室を出た時には、正直ほっとした。昼休みは周りに他の生徒がいたから大丈夫だったけど、今二人きりになってしまったら、何を言ってしまうか分からないから。
教室は、今日も赤松さんの話で持ちきりだった。
今度は、犯人であるはずの彼女の靴が盗まれたというのだ。自分から疑いを逸らせる為の狂言ではないかという人もいた。靴が盗まれたことが分かってから、彼女を見た生徒はいない。姿をくらませていることこそ、彼女自身が犯人である証拠だということらしい。
私は特に危機感を覚えることもなく、教室を出た。彼女の靴を盗んだのは私ではないけれど、本当はまた靴を切りたいと思っていたし、赤松さんが身代わりになっている今もやめる気はなかった。でも、今日は無理だ。
無責任な噂話を耳にしながら昇降口へ向かう。溜息を吐きながら靴に履き替えようとした時だった。凄い勢いで昇降口へ駆け込んできた人がいた。その人物は、私の後ろで立ち止まった。
私は振り向かなくとも、それが彼であることが分かった。何故なのかは分からない。でも、とうとうその時が来たのだと、頭のどこかで悟っていた。
「杉本、話があるんだけど」
彼の呼びかけに、私はゆっくりと振り向いた。
杉本瑞葉はゆっくりと振り向いた。
ぼくはざっと辺りを見まわした。昇降口には、いくつかの集団がまだ帰る様子もなく話し込んでいる。田口もぼくを追っているはずだ。
「ちょっと、こっち」
ぼくは彼女を急ぎ足で南校舎まで引っ張っていき、視聴覚室に連れ込んだ。この教室は防音になっているので、人に聞かれたくない話をするには好都合だった。
「何? 話って」
杉本が静かに問いかけてくる。ぼくは一呼吸置いてから答えた。
「思い出したんだ。中学の時のこと」
ぼくが中腰の姿勢で田口のスカートの裾を見た瞬間、手の先にあった紙くずは、レーシングカーのシールが剥げかけているカッターナイフに変貌した。ぼくはやはり見ていたのだ。あの時の犯人を。
あの残暑の厳しい放課後、ぼくはクラスメートの盗まれた靴を探していた。地面に伸びる影が、とても濃い色をしていた。探していたというのは形ばかりで、ぼくは適当にほっつき歩いているだけだった。
ところが、涼しそうだと思って入って行った体育館の裏手で、懐かしいものを見てしまったのだ。
それは二年前に失くした宝物だった。
顔をあげると、ぼくより少しだけ背の低い女子生徒が、無残に切り裂かれた靴を持って立っていた。
「靴泥棒の犯人の顔とか?」
杉本の声が光のない空間に響く。
ぼくと杉本は、教室の電気を付けることさえせず、向き合っていた。遮光カーテンを閉めた部屋はほとんど闇に近い。
「いや、顔はぼんやりとしか覚えてない。でも、間違いなく犯人は女子で、カッターを持ってた」
「だから?」
「それで、犯人が誰だか分かったんだ」
杉本が体を震わせたのが分かった。しかし、彼女は次の言葉を穏やかに発した。心なしか、いつもの突っかかってくるような感じも少ない気がする。
「誰? 犯人って。私の知ってる人?」
「ああ。あんただ」
「私?」
「そう。犯人の持ってたカッターには手で擦って貼り付けるタイプのシールが貼ってあった。あんたは知らないかもしれないけど、あれは俺のものだったんだ」
カーテンの隙間から弱い光が入って、杉本の体が薄闇に浮かぶ。彼女はスカートのポケットに左手を入れようとしていた。ぼくは続けた。
「俺はずっと、あのカッターはどこかで落としたと思ってた。でも違った。そう思い込もうとしてただけだったんだ。本当は、あれは盗まれたんだよ。中一の時に」
当時、ぼくはクラスの連中から総無視をくらっていた。要するに、地味にいじめられていたわけだ。それは本当に無言の攻撃で、面と向かって殴りかかられるようなことはなかった。しかし、一度だけ盗難という別の形を取られたことがあるのだ。
ぼくがレーシングカーのシールを貼ったカッターを大事にしていたことは、同じ小学校の出身者はみんな知っていることだった。それと同じくらい、ぼくの傍若無人ぶりも知れ渡っていたので、いじめはそういった小学校で一緒だった連中から始まったようだった。
そして無視だけでは飽き足らなくなった彼らは、ぼくの宝物を盗んでクラスの女子のペンケースに隠すことを思い付いた。それも一番人気のある女の子を選んで。
何故ぼくがそれを知っているのか。誰かが気の毒に思って教えてくれたわけではない。彼らが聞こえよがしに話していたからだ。
ぼくはそれを聞いてピンときた。そのようにぼくに聞かせるということは、ぼくがカッターを取り戻すために、彼女に話しかけるよう仕組もうとしているのだと。
きっと彼らは、ぼくが彼女に話しかけたら分不相応だと言って冷やかそうと思っていたのだろう。何せ相手はクラスだけでなく、学校中から可愛いと噂されている少女だ。嫌われ者が声をかけられる存在ではない。
「あの時奴らが話していた女子の名前は、杉本、あんたの名前だった」
中学一年の時、杉本とぼくは同じクラスだったのだ。
ぼくはもちろん、彼女に声をかけなかった。カッターは盗まれたのではなく失くしたのだと諦めた。物を盗まれたということが、いじめがひどくなることを示唆しているようで、認めたくなかったのも事実だ。
そしてぼくは、自分の記憶を改ざんした。それに関係する全てのことをも忘れることにした。ちょうど今の赤松のように。記憶の抽斗に鍵をかけて。
「あなたはそれで、私がそのカッターを持っているから犯人だと思ってるのね。でも、本当に私が持っている確証はないじゃない。彼らは口では私の名前を出していても、他の人のペンケースに入れていたかもしれない」
「いや、俺はあんたがペンケースからカッターを見付けて首を傾げてるのを見てたんだ」
「でも、私から他の人の手に渡ってるかもしれないわ。加奈子とか」
「田口は違う」
「どうしてそんなに即答できるの?」
「中学の犯人は、左足の腿に大きな傷があったんだ」
杉本の表情は見えない。ぼくは続けた。
「見たのは一瞬だったし、前も言ったように俺は次の日には忘れてた。おまけに事故で一生消えない傷ができた女子がいるって聞いたのはあのかなり後だったから、その時は事件の犯人とは結びつきもしなかったんだ。田口は確かに事故に遭ってた。でも、彼女の足には傷がない。さっきも会ったけど、あれだけ短いスカートを穿いていたら、あの傷は見えてるはずなんだ。だけど、彼女の足には痣すらなかった」
そう。先ほど焼却炉の前まで来て踵を返した足には、どこにも傷などなかった。今まで長いスカートを穿いていたせいで、ほとんど日焼けもしていない白い足。
ぼくは遠ざかろうとする田口を呼び止め、杉本の居場所を訊いた。
「瑞葉なら、まだ教室にいると思うけど。どうかしたの?」
ぼくは余程恐ろしい顔をしていたのだろう。田口は完全に怯えていた。
「ちょっと話したいと思って」
「何を?」
「田口には関係ない」
ぼくは怯えながらも訝しげに問いかけてくる彼女を振り切り、水溜りを飛び越えて駆け出した。
「待って!」
後ろから田口の追ってくる気配と、旧校舎の最上階の窓が開く、軋むような音がした。ぼくは構わず走り続けた。昇降口で杉本を捕まえるまで。
カーテンの隙間から斜めに差し込む弱々しい光が、ぼくと杉本の空間を分断するように床に落ちている。
「それに何より、あんたがここで俺に言った言葉が、あんたが犯人である証拠だ」
「私の言葉?」
空気が揺れた。教卓にもたれていた杉本が、姿勢を正したのだ。
「あんたは俺に、本当に犯人を覚えてないのかって聞いてきた時、『靴切り裂き事件の犯人』って言ったんだ。あの時盗まれた靴は、結局一足も見付からなかった。だから、盗まれた靴がどうなってるかなんて知ってる奴はいないんだ。なのに、あんたは靴が切り裂かれたと知っていた。俺と犯人しか知らない事実を」
杉本が息を飲む。
「それで、私にどうしろっていうの? あの時盗んだ人達に謝って回れって?」
そう問いかける声は、意外と落ち着いていた。
「いや、あの時の被害者にじゃない。藤田と赤松に謝ってほしいんだ」
「中学の時の犯人だったからって、今回の件の犯人だとは限らないじゃない。何か証拠でもあるの?」
ぼくは少し言葉に詰まった。はっきりとした証拠は何もなかった。
「・・・・・・強いて言えば、靴の切り方が似ていたってことかな」
「でも、あなたは中学の時の犯人と今回の犯人は別人だと言ってたじゃない」
「ああ、あの時点ではまだ別人しかいなかったんだ。あんたは藤田の靴しか盗んでないからね。そうだろ?」
杉本はぼくの質問には答えず、逆に問いかけてきた。
「じゃあ、もう一人の犯人は?」
「タカヨシだよ」
「え? 犬の?」
「そう。あんた気付いてなかったのか?」
彼女の頷く気配がした。
「そうか、気付いてなかったのか・・・・・・。だから赤松を犯人と思わせるようなメモを、藤田の机に入れたのか」
考えてみれば、犬のタカヨシが犯人だと知っていれば人間に罪を着せる必要はない。全て犬の仕業にしてしまえばいいのだから。
逆に人に罪を着せることは、真犯人にとって危険なことになる。もう一人の犯人が人間なら、赤松を全ての犯人にすることでそいつも盗みを止めるかもしれないが、噂を理解できない犬が犯人では、犯行が続く可能性が高いからだ。そうすると、赤松犯人説はいつか崩れることになる。
「証拠はそれだけ?」
「あとは赤松だ。最初俺は、タカヨシを庇うために、あいつが罪を被ることにしたのかと思った」
タカヨシは保健所送り寸前になったことがある。そんな犬が生徒の靴を自分のコレクションの為に持って行ってしまっていることが教師達にバレたら、きっと今度こそ無事では済まないだろう。だから赤松は、タカヨシがやっていることを誰にも気付かれないようにしようと思った。そして、タカヨシのやっていることに気付いてからは、盗まれた靴をこっそり返していたのだ。
最近タカヨシが赤松に攻撃的なのは、餌をくれる人から自分のコレクションを盗んでいくとんでもない輩へと、認識を改めたせいだろう。
ゴミ集積場の裏には直径五十センチ、深さ一メートルくらいの穴があり、タカヨシのコレクションが放り込まれていた。そのほとんどは赤松によって回収されていたようで、今朝は二・三足しかなかったが、不思議と片方だけの靴はなく、左右両方ともを咥えてきているようだった。サイズがまちまちながらも小さめの靴ばかりが消えていたのは、運び易かったからだろう。
あの日、赤松の鞄から盗まれた靴が出てきたのは、彼女がそれらを昇降口に並べようと穴から持ち出してきていたからだったのだ。
「でも、赤松が庇ってたのは、タカヨシだけじゃなかったんだ。あいつは友達少ないから、自分のせいで親しい人間に害が及んで迷惑を掛けることを心底恐れてる。だから、タカヨシの為だけに自分が全部の罪をひっかぶるようなことはしない」
助けなければならない対象がタカヨシだけなら、保健所に連れて行かれないように飼い主を探すとか引き取るとか、もっと別な方法を取るだろう。
「じゃあ、どんな奴なら友達まで白い目で見られても庇うか。その友達自身が犯人だった場合だ」
「それでどうして私なの? 前科者だから?」
「赤松が今現在大切に思っている友人といったら、あんたと田口だろうと思ったんだ。あいつは犯人だと言われた時、真っ先にあんたらの反応を見たからな。あの時、田口は挑発的な表情をしてたけど、あんたは怯えたような顔をしてた。さっきあんたが中学の時の犯人だって思い出して、これはおかしいと思ったんだ。他の奴ならともかく、あんたの場合は過去に自分もやってたことだ。靴を切るくらいの人間なんて、怖くもなんともないだろう。それで思い当たったんだ。あんたが怯えてたのは赤松じゃない。自分のやったことがバレてしまうことだったんじゃないかって」
「赤松さんは、どうして私だと思ったのかしら」
杉本が力なく呟く。左手はスカートのポケットに入れたままだ。
「さぁ? ゴミ集積場の裏手で靴を回収してた時にでも、あんたが焼却炉の前でしてたことを見たんだろう」
「赤松さんがそう言ったの?」
「あいつは何も言わない。それどころか、俺まで泥棒の仲間だと思われるから自分に近づくなってさ」
ドアの上部に嵌めてあるすりガラス部分から、四角い光が落ちている。いつの間にか廊下の蛍光灯がついたようだった。薄ぼんやりと見える杉本の表情は、少し困惑しているように見える。
「何でまた靴なんて切ろうと思ったのか知らないけど、そこまでして庇おうとしてくれるような人間に罪を着せて、良心痛まないわけ?」
「あなたにはあるの? 良心」
「一グラムくらいはあるつもりだけど」
「あなたのせいよ」
「は?」
急に話が飛んだような気がして、ぼくは聞き返した。
「靴を切ろうと思った理由」
「え?」
今度は自分の耳を疑った。なんでぼくのせいなんだ。
「何で俺のせいなわけ?」
ぼくは思ったままを口にした。
「あなたが忘れていたから。あの時、あの中学の焼却炉の前であなたに見付かった時、私はもう終わりだって思った。でもあなたは誰にも言わないでいてくれた」
「それは・・・・・・」
「分かってる! 忘れてたからでしょ?」
杉本が、今日この教室に入って初めて、感情のこもった声を発した。いつもの冷静さや穏和さをかなぐり捨てた激しさが、そこにはあった。
ぼくは黙って頷いた。忘れてたから。忘れるほどに興味がなかったから。それに、思い出したくない過去の鍵があの現場にはあったから。全ての理由は心の中だけで打ち明けた。
「でも、私はそんなこと知らなかったから、庇ってくれてるのかと思ってた。許されたって思った。守られてるって。それからずっと、あの出来事を支えにしてきた。まさか次の日には忘れられてるなんて思ってもみなかったから・・・・・・。私は周りからしっかりしてるとか優しいとかって言われてるけど、そういう自分を演じてるにすぎいわ。本当の私はあんなに醜いのに。親でさえ、演技してる私が本当だって思ってる。私は必死に演技してるのに、それにも気付かないで勝手に離婚して。でも、あなただけは醜い私も受け入れてくれたんだって思ってた。それが・・・・・・。やっぱり誰も私の支えになんてなってくれないのよね。本当の私なんて・・・・・・」
ただ、思い出して欲しかったの・・・・・・。震える声でそう呟く杉本を、ぼくはただ見ていることしかできなかった。
そのうちに見ているのも辛くなり、四角い光の影へと視線を落とした。時折、廊下を通る人の影で、床に落ちた明かりが点滅する。カーテンの隙間から入っていた外の光は、もう薄明るい筋を落としてはいなかった。
「でも、私じゃないわ」
しばらくの沈黙の後、彼女が言った。
「え?」
先ほどとは打って変わって、あまりに静かな声音に、ぼくは一瞬聞き逃しそうになった。
「あのメモを藤田君の机に入れたのも、切った靴を赤松さんのロッカーに入れたのも私じゃない。切った靴は、焼却炉に入れたんだもの」
「じゃあ誰が・・・・・・」
言いかけてぼくはハッとした。そうか、そうだったんだ。
「なんだ、いるじゃん」
「え?」
今度は杉本が戸惑う番だった。ぼくは勢い込んで宣言した。
「俺なんかを支えにしなくても、本当のあんたを知って、なおかつ庇おうとしてる人間が、あんたの傍にはちゃんといる」
- つづく -
昨夜のことだった。
私が帰宅した時には寝室に引きこもって出てこなかった母が、私の部屋を訪ねてきた。最近やっとアルコールの臭いが消えてきたけれどまたいつ飲み始めるかと油断ならなかったので、一人にしてほしいと思いつつもドアを開けた。
母は部屋に入ってくると嵌め込み式の棚の所へ行き、そこに飾っていた写真を手に取った。それは、中学の修学旅行で撮った学年全体の集合写真だった。
「ごめんね、勝手に転校のこと決めちゃって」
ポツリと、母が言った。
「どうしたの? 急に」
私はベッドに腰掛け、いつものように明るく返した。
「お母さん、自分のことばかりで、あなたのこと考えてあげてなかったよね。あなただって、お友達と別れたくないわよね。今日ね、言われちゃった」
母は目を写真に落としたまま語った。
私が帰宅する前に幼馴染がうちに来たこと。そして、昼休憩に私が喋ってしまった弱音を母に伝え、もっと私のことを考えてほしいと訴えて帰ったこと。それでいろいろ考えてしまったこと。
私は苦い思いで聞いていた。無意識にシーツを強く掴んでいた。彼女にぶちまけてしまったことが悔やまれた。
「本当にごめんね。あなたを信頼してなかったわけじゃないの」
母は写真を棚に戻して私の前に来ると、床に膝をつけてこちらを見上げる格好になった。彼女の顔は泣きそうになっていた。
「いいのよ。気にしないで。私が子供だっただけだもん」
私は励ますように微笑んだ。母に見付からないように、そっとシーツから手を離す。その手を母の手が包んだ。
「ううん。あなたは十分支えになってくれてた。あなたに相談せずに決めてしまったのは、あなたに甘えてたからだわ。自分のことばかり考えて、あなたはお母さんについてきてくれるって、勝手に決め付けてた。あなただって、離れたくない人達や生活があったのに。本当にごめんね。こんなお母さんでごめんね」
謝罪の言葉を繰り返しながら、私の手を強く握り締め、顔を伏せて泣き崩れる母に、私は必死で声をかけた。
「もういいよ、お母さん。分かったから。私の方こそごめんね。そんなつもりで言ったんじゃないの。お母さんを傷つけるつもりで言ったんじゃないの」
母と同じように床に座り、目の高さを合わせる。すると母は顔を上げ、懇願するような目を私に向けた。
「こんなお母さんでも、見捨てないでいてくれる? 一緒に行ってくれる?」
「当たり前じゃない・・・・・・」
「ありがとう・・・・・・」
母は私を抱きしめて、そう繰り返した。私は母の背中をさすりながら、彼の顔を思い浮かべていた。
幼馴染に感謝するべきなのかもしれないけれど、素直にそんな気持ちにはなれなかった。
彼女は何を思って、母に私の気持ちを伝えてしまったのだろう。単純に、私のことを想ってしてくれたのかもしれない。でも、そんな見方をできない屈折した自分がいる。
幼馴染はうちの事情を知っていた。母がどういう精神状態にあるのかも全て。幸い昨日は考え込んでもお酒に手を出さなかったようだけど、母にあんなことを言うというのは、うちを引っ掻き回したいからではないか。私の重荷が増えるのを楽しんでいるのではないか。
考えすぎだとは思いつつ、彼女を見る目が疑いの眼差しになってしまう。
放課後、彼女が私に「一緒に帰ろう」と言わずに教室を出た時には、正直ほっとした。昼休みは周りに他の生徒がいたから大丈夫だったけど、今二人きりになってしまったら、何を言ってしまうか分からないから。
教室は、今日も赤松さんの話で持ちきりだった。
今度は、犯人であるはずの彼女の靴が盗まれたというのだ。自分から疑いを逸らせる為の狂言ではないかという人もいた。靴が盗まれたことが分かってから、彼女を見た生徒はいない。姿をくらませていることこそ、彼女自身が犯人である証拠だということらしい。
私は特に危機感を覚えることもなく、教室を出た。彼女の靴を盗んだのは私ではないけれど、本当はまた靴を切りたいと思っていたし、赤松さんが身代わりになっている今もやめる気はなかった。でも、今日は無理だ。
無責任な噂話を耳にしながら昇降口へ向かう。溜息を吐きながら靴に履き替えようとした時だった。凄い勢いで昇降口へ駆け込んできた人がいた。その人物は、私の後ろで立ち止まった。
私は振り向かなくとも、それが彼であることが分かった。何故なのかは分からない。でも、とうとうその時が来たのだと、頭のどこかで悟っていた。
「杉本、話があるんだけど」
彼の呼びかけに、私はゆっくりと振り向いた。
杉本瑞葉はゆっくりと振り向いた。
ぼくはざっと辺りを見まわした。昇降口には、いくつかの集団がまだ帰る様子もなく話し込んでいる。田口もぼくを追っているはずだ。
「ちょっと、こっち」
ぼくは彼女を急ぎ足で南校舎まで引っ張っていき、視聴覚室に連れ込んだ。この教室は防音になっているので、人に聞かれたくない話をするには好都合だった。
「何? 話って」
杉本が静かに問いかけてくる。ぼくは一呼吸置いてから答えた。
「思い出したんだ。中学の時のこと」
ぼくが中腰の姿勢で田口のスカートの裾を見た瞬間、手の先にあった紙くずは、レーシングカーのシールが剥げかけているカッターナイフに変貌した。ぼくはやはり見ていたのだ。あの時の犯人を。
あの残暑の厳しい放課後、ぼくはクラスメートの盗まれた靴を探していた。地面に伸びる影が、とても濃い色をしていた。探していたというのは形ばかりで、ぼくは適当にほっつき歩いているだけだった。
ところが、涼しそうだと思って入って行った体育館の裏手で、懐かしいものを見てしまったのだ。
それは二年前に失くした宝物だった。
顔をあげると、ぼくより少しだけ背の低い女子生徒が、無残に切り裂かれた靴を持って立っていた。
「靴泥棒の犯人の顔とか?」
杉本の声が光のない空間に響く。
ぼくと杉本は、教室の電気を付けることさえせず、向き合っていた。遮光カーテンを閉めた部屋はほとんど闇に近い。
「いや、顔はぼんやりとしか覚えてない。でも、間違いなく犯人は女子で、カッターを持ってた」
「だから?」
「それで、犯人が誰だか分かったんだ」
杉本が体を震わせたのが分かった。しかし、彼女は次の言葉を穏やかに発した。心なしか、いつもの突っかかってくるような感じも少ない気がする。
「誰? 犯人って。私の知ってる人?」
「ああ。あんただ」
「私?」
「そう。犯人の持ってたカッターには手で擦って貼り付けるタイプのシールが貼ってあった。あんたは知らないかもしれないけど、あれは俺のものだったんだ」
カーテンの隙間から弱い光が入って、杉本の体が薄闇に浮かぶ。彼女はスカートのポケットに左手を入れようとしていた。ぼくは続けた。
「俺はずっと、あのカッターはどこかで落としたと思ってた。でも違った。そう思い込もうとしてただけだったんだ。本当は、あれは盗まれたんだよ。中一の時に」
当時、ぼくはクラスの連中から総無視をくらっていた。要するに、地味にいじめられていたわけだ。それは本当に無言の攻撃で、面と向かって殴りかかられるようなことはなかった。しかし、一度だけ盗難という別の形を取られたことがあるのだ。
ぼくがレーシングカーのシールを貼ったカッターを大事にしていたことは、同じ小学校の出身者はみんな知っていることだった。それと同じくらい、ぼくの傍若無人ぶりも知れ渡っていたので、いじめはそういった小学校で一緒だった連中から始まったようだった。
そして無視だけでは飽き足らなくなった彼らは、ぼくの宝物を盗んでクラスの女子のペンケースに隠すことを思い付いた。それも一番人気のある女の子を選んで。
何故ぼくがそれを知っているのか。誰かが気の毒に思って教えてくれたわけではない。彼らが聞こえよがしに話していたからだ。
ぼくはそれを聞いてピンときた。そのようにぼくに聞かせるということは、ぼくがカッターを取り戻すために、彼女に話しかけるよう仕組もうとしているのだと。
きっと彼らは、ぼくが彼女に話しかけたら分不相応だと言って冷やかそうと思っていたのだろう。何せ相手はクラスだけでなく、学校中から可愛いと噂されている少女だ。嫌われ者が声をかけられる存在ではない。
「あの時奴らが話していた女子の名前は、杉本、あんたの名前だった」
中学一年の時、杉本とぼくは同じクラスだったのだ。
ぼくはもちろん、彼女に声をかけなかった。カッターは盗まれたのではなく失くしたのだと諦めた。物を盗まれたということが、いじめがひどくなることを示唆しているようで、認めたくなかったのも事実だ。
そしてぼくは、自分の記憶を改ざんした。それに関係する全てのことをも忘れることにした。ちょうど今の赤松のように。記憶の抽斗に鍵をかけて。
「あなたはそれで、私がそのカッターを持っているから犯人だと思ってるのね。でも、本当に私が持っている確証はないじゃない。彼らは口では私の名前を出していても、他の人のペンケースに入れていたかもしれない」
「いや、俺はあんたがペンケースからカッターを見付けて首を傾げてるのを見てたんだ」
「でも、私から他の人の手に渡ってるかもしれないわ。加奈子とか」
「田口は違う」
「どうしてそんなに即答できるの?」
「中学の犯人は、左足の腿に大きな傷があったんだ」
杉本の表情は見えない。ぼくは続けた。
「見たのは一瞬だったし、前も言ったように俺は次の日には忘れてた。おまけに事故で一生消えない傷ができた女子がいるって聞いたのはあのかなり後だったから、その時は事件の犯人とは結びつきもしなかったんだ。田口は確かに事故に遭ってた。でも、彼女の足には傷がない。さっきも会ったけど、あれだけ短いスカートを穿いていたら、あの傷は見えてるはずなんだ。だけど、彼女の足には痣すらなかった」
そう。先ほど焼却炉の前まで来て踵を返した足には、どこにも傷などなかった。今まで長いスカートを穿いていたせいで、ほとんど日焼けもしていない白い足。
ぼくは遠ざかろうとする田口を呼び止め、杉本の居場所を訊いた。
「瑞葉なら、まだ教室にいると思うけど。どうかしたの?」
ぼくは余程恐ろしい顔をしていたのだろう。田口は完全に怯えていた。
「ちょっと話したいと思って」
「何を?」
「田口には関係ない」
ぼくは怯えながらも訝しげに問いかけてくる彼女を振り切り、水溜りを飛び越えて駆け出した。
「待って!」
後ろから田口の追ってくる気配と、旧校舎の最上階の窓が開く、軋むような音がした。ぼくは構わず走り続けた。昇降口で杉本を捕まえるまで。
カーテンの隙間から斜めに差し込む弱々しい光が、ぼくと杉本の空間を分断するように床に落ちている。
「それに何より、あんたがここで俺に言った言葉が、あんたが犯人である証拠だ」
「私の言葉?」
空気が揺れた。教卓にもたれていた杉本が、姿勢を正したのだ。
「あんたは俺に、本当に犯人を覚えてないのかって聞いてきた時、『靴切り裂き事件の犯人』って言ったんだ。あの時盗まれた靴は、結局一足も見付からなかった。だから、盗まれた靴がどうなってるかなんて知ってる奴はいないんだ。なのに、あんたは靴が切り裂かれたと知っていた。俺と犯人しか知らない事実を」
杉本が息を飲む。
「それで、私にどうしろっていうの? あの時盗んだ人達に謝って回れって?」
そう問いかける声は、意外と落ち着いていた。
「いや、あの時の被害者にじゃない。藤田と赤松に謝ってほしいんだ」
「中学の時の犯人だったからって、今回の件の犯人だとは限らないじゃない。何か証拠でもあるの?」
ぼくは少し言葉に詰まった。はっきりとした証拠は何もなかった。
「・・・・・・強いて言えば、靴の切り方が似ていたってことかな」
「でも、あなたは中学の時の犯人と今回の犯人は別人だと言ってたじゃない」
「ああ、あの時点ではまだ別人しかいなかったんだ。あんたは藤田の靴しか盗んでないからね。そうだろ?」
杉本はぼくの質問には答えず、逆に問いかけてきた。
「じゃあ、もう一人の犯人は?」
「タカヨシだよ」
「え? 犬の?」
「そう。あんた気付いてなかったのか?」
彼女の頷く気配がした。
「そうか、気付いてなかったのか・・・・・・。だから赤松を犯人と思わせるようなメモを、藤田の机に入れたのか」
考えてみれば、犬のタカヨシが犯人だと知っていれば人間に罪を着せる必要はない。全て犬の仕業にしてしまえばいいのだから。
逆に人に罪を着せることは、真犯人にとって危険なことになる。もう一人の犯人が人間なら、赤松を全ての犯人にすることでそいつも盗みを止めるかもしれないが、噂を理解できない犬が犯人では、犯行が続く可能性が高いからだ。そうすると、赤松犯人説はいつか崩れることになる。
「証拠はそれだけ?」
「あとは赤松だ。最初俺は、タカヨシを庇うために、あいつが罪を被ることにしたのかと思った」
タカヨシは保健所送り寸前になったことがある。そんな犬が生徒の靴を自分のコレクションの為に持って行ってしまっていることが教師達にバレたら、きっと今度こそ無事では済まないだろう。だから赤松は、タカヨシがやっていることを誰にも気付かれないようにしようと思った。そして、タカヨシのやっていることに気付いてからは、盗まれた靴をこっそり返していたのだ。
最近タカヨシが赤松に攻撃的なのは、餌をくれる人から自分のコレクションを盗んでいくとんでもない輩へと、認識を改めたせいだろう。
ゴミ集積場の裏には直径五十センチ、深さ一メートルくらいの穴があり、タカヨシのコレクションが放り込まれていた。そのほとんどは赤松によって回収されていたようで、今朝は二・三足しかなかったが、不思議と片方だけの靴はなく、左右両方ともを咥えてきているようだった。サイズがまちまちながらも小さめの靴ばかりが消えていたのは、運び易かったからだろう。
あの日、赤松の鞄から盗まれた靴が出てきたのは、彼女がそれらを昇降口に並べようと穴から持ち出してきていたからだったのだ。
「でも、赤松が庇ってたのは、タカヨシだけじゃなかったんだ。あいつは友達少ないから、自分のせいで親しい人間に害が及んで迷惑を掛けることを心底恐れてる。だから、タカヨシの為だけに自分が全部の罪をひっかぶるようなことはしない」
助けなければならない対象がタカヨシだけなら、保健所に連れて行かれないように飼い主を探すとか引き取るとか、もっと別な方法を取るだろう。
「じゃあ、どんな奴なら友達まで白い目で見られても庇うか。その友達自身が犯人だった場合だ」
「それでどうして私なの? 前科者だから?」
「赤松が今現在大切に思っている友人といったら、あんたと田口だろうと思ったんだ。あいつは犯人だと言われた時、真っ先にあんたらの反応を見たからな。あの時、田口は挑発的な表情をしてたけど、あんたは怯えたような顔をしてた。さっきあんたが中学の時の犯人だって思い出して、これはおかしいと思ったんだ。他の奴ならともかく、あんたの場合は過去に自分もやってたことだ。靴を切るくらいの人間なんて、怖くもなんともないだろう。それで思い当たったんだ。あんたが怯えてたのは赤松じゃない。自分のやったことがバレてしまうことだったんじゃないかって」
「赤松さんは、どうして私だと思ったのかしら」
杉本が力なく呟く。左手はスカートのポケットに入れたままだ。
「さぁ? ゴミ集積場の裏手で靴を回収してた時にでも、あんたが焼却炉の前でしてたことを見たんだろう」
「赤松さんがそう言ったの?」
「あいつは何も言わない。それどころか、俺まで泥棒の仲間だと思われるから自分に近づくなってさ」
ドアの上部に嵌めてあるすりガラス部分から、四角い光が落ちている。いつの間にか廊下の蛍光灯がついたようだった。薄ぼんやりと見える杉本の表情は、少し困惑しているように見える。
「何でまた靴なんて切ろうと思ったのか知らないけど、そこまでして庇おうとしてくれるような人間に罪を着せて、良心痛まないわけ?」
「あなたにはあるの? 良心」
「一グラムくらいはあるつもりだけど」
「あなたのせいよ」
「は?」
急に話が飛んだような気がして、ぼくは聞き返した。
「靴を切ろうと思った理由」
「え?」
今度は自分の耳を疑った。なんでぼくのせいなんだ。
「何で俺のせいなわけ?」
ぼくは思ったままを口にした。
「あなたが忘れていたから。あの時、あの中学の焼却炉の前であなたに見付かった時、私はもう終わりだって思った。でもあなたは誰にも言わないでいてくれた」
「それは・・・・・・」
「分かってる! 忘れてたからでしょ?」
杉本が、今日この教室に入って初めて、感情のこもった声を発した。いつもの冷静さや穏和さをかなぐり捨てた激しさが、そこにはあった。
ぼくは黙って頷いた。忘れてたから。忘れるほどに興味がなかったから。それに、思い出したくない過去の鍵があの現場にはあったから。全ての理由は心の中だけで打ち明けた。
「でも、私はそんなこと知らなかったから、庇ってくれてるのかと思ってた。許されたって思った。守られてるって。それからずっと、あの出来事を支えにしてきた。まさか次の日には忘れられてるなんて思ってもみなかったから・・・・・・。私は周りからしっかりしてるとか優しいとかって言われてるけど、そういう自分を演じてるにすぎいわ。本当の私はあんなに醜いのに。親でさえ、演技してる私が本当だって思ってる。私は必死に演技してるのに、それにも気付かないで勝手に離婚して。でも、あなただけは醜い私も受け入れてくれたんだって思ってた。それが・・・・・・。やっぱり誰も私の支えになんてなってくれないのよね。本当の私なんて・・・・・・」
ただ、思い出して欲しかったの・・・・・・。震える声でそう呟く杉本を、ぼくはただ見ていることしかできなかった。
そのうちに見ているのも辛くなり、四角い光の影へと視線を落とした。時折、廊下を通る人の影で、床に落ちた明かりが点滅する。カーテンの隙間から入っていた外の光は、もう薄明るい筋を落としてはいなかった。
「でも、私じゃないわ」
しばらくの沈黙の後、彼女が言った。
「え?」
先ほどとは打って変わって、あまりに静かな声音に、ぼくは一瞬聞き逃しそうになった。
「あのメモを藤田君の机に入れたのも、切った靴を赤松さんのロッカーに入れたのも私じゃない。切った靴は、焼却炉に入れたんだもの」
「じゃあ誰が・・・・・・」
言いかけてぼくはハッとした。そうか、そうだったんだ。
「なんだ、いるじゃん」
「え?」
今度は杉本が戸惑う番だった。ぼくは勢い込んで宣言した。
「俺なんかを支えにしなくても、本当のあんたを知って、なおかつ庇おうとしてる人間が、あんたの傍にはちゃんといる」
- つづく -
© Rakuten Group, Inc.