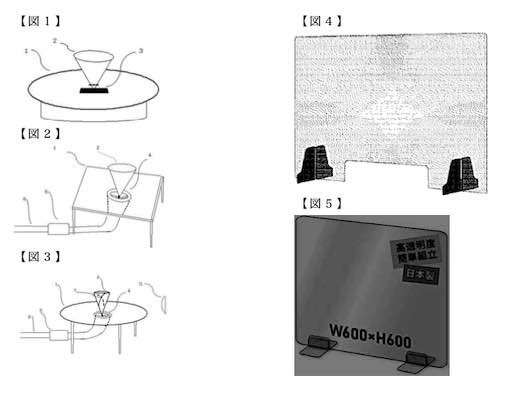2
ある日の出来事 2
くらくらする頭を抱えて、ぼくは必死に数分前のことを思い出そうとしていた。
友人とは、銀行の自動ドアの所で別れた。
「暑いから中入る?」
「ううん。お客さんも少ないみたいだし、すぐ終わるだろうからここで待ってるよ」
彼女はぼくの自転車を駐輪場に停めてくれながらそう言った。
「じゃあ、すぐ戻るから」
彼女と自転車をその場に残し、ぼくは某大銀行の支店へと足を踏み入れた。この支店は小さいので、入り口は一つしかない。入ってすぐ左手にATMがあり、入り口からまっすぐ進むと窓口のある広いロビーに続くようになっていた。
ぼくは順番を待っている間、ぼんやりと自動ドアから外を見ていた。外を見るといっても、透明ガラスの自動ドアには、ちょうど大人の目線あたりに銀行のロゴ大書してあり、かがみこまないと外からは中の、中からは外の様子はよく見えない。仕方がないので、ぼくは下の方に視線をさまよわせていた。
店内の床はよく磨きこまれており、ドアから入る太陽の光を受けて、てかてかと輝いている。一方、ガラス越しの景色は少し揺らいで見えた。焼けたアスファルトから煙が立ち昇っているかのようだ。
入り口の向かいにある駐輪場に友人が立っているのが見える。とりたてて太くも細くもない足が、日影を求めて歩き回っている。視界の端には、黒いズボンを穿いた男性のものらしい足もあった。入る時には気付かなかったが、警備員だろうか。こちらは暑いのに、じっと日向に立ったまま動かない。仕事とはいえ、ご苦労様だ。
ぼくの前でATMを使っていた男性が、象のように重い足取りで機械の前から離れた。図体もデカイので、本当に象が歩いているようだ。彼は沈痛な面持ちで通帳に見入っており、なかなか出ていこうとしなかった。首筋にある大きな黒子までもが、心なしか悲しそうに見える。
ぼくはネズミのように素早く機械の前に陣取り、画面の『お引き出し』を指で押した。機械アナウンスに従ってカードを入れる。暗証番号に続いて金額を入力し、確認ボタンを押したところで、自動ドアが開いた。
ぼくは先程の象男が出て行ったのだろうと思っていたが、どうやらここで入ってきたのが、今窓口でがなっている男であるらしい。そういえばあの時、ATMの上に設置してある鏡に、一瞬黒いジャンパーが映ったような気がしたのだ。この暑いのにジャンパーを着込むようなイカレタ人間がいるわけがない、きっと目の錯覚だと思っていたのに。
あの時、彼女も男と一緒に入ってきていたのか。
ぼくの口中に苦いものが込み上げてきた。
悪夢だ。きっとあまりの暑さに頭が湧いて、変な白昼夢を見てるんだ。隣のおばさんの頭を叩けば、目が覚めるかもしれない。
しかし、たとえ夢でも、善良な一市民であるぼくにそんなことができるはずもなく、この夢は一向に覚める気配を見せない。
窓口では、何故か友人が行員に詫びていた。そして犯人に「余計なことを言うな」と怒鳴られ、周りの同情と非難を一身に浴びている。
ぼくは自動ドアの下方に視線を移した。先程見えていた警備員の足は、どこかに消えていた。異変に気付いて、警察でも呼びに行ったのだろうか。ひょっとしたら、犯人が入る前に、気絶でもさせられたのかもしれない。
そうこうしているうちに、支店長と名乗る男性が大きなジュラルミンケースを抱えて登場した。犯人の要求は、窓口のお金の他に旧札で一千万円。あの中身がそうなのだろう。
犯人は人質の女の子、つまりぼくの友人に、窓口の女性から受け取った現金入りのずた袋を持たせ、果物ナイフを閉じてケースの中身を確認した。
友人はずた袋をしっかりと両手で抱きしめていたが、その姿は、お金というようりも赤ん坊を恐々と抱きかかえているかのようだ。しかし、袋には赤ん坊のように手足の引っ掛かりがない。よって、今にも腕の間からズルズルと落ちていきそうだった。
ぼくは心の中で、落ちるぞ、落ちるぞ、落ちても知らないぞ、と犯人に語りかけていたのだが、目出し帽なんぞ被った男に超能力者でもないぼくのテレパシーが通じるはずもなく、犯人がジュラルミンケースを閉じると同時に、友人はずた袋を取り落とした。
ずだーんっ!
袋が床に落ちて、派手な音を響かせた。紐で縛っていただけの口が開いて、中から札束が転がり出る。ロビーにいた人達の間にどよめきが走った。
友人は小さくなって、「ごめんなさい」を連呼している。
彼女が抱えていたのが本物の赤ん坊でなくて良かった。
そう思ったのも束の間、袋を拾い上げようとした友人を引っ張って、犯人が走り出した。左手でナイフとジュラルミンケースを持ち、右手で友人を引きずるようにして、ぼくのいる入り口の方へ向かってくる。
足をもつれさせながら引きずられてくる友人を見て、ぼくは捨てようとしていたレシートを、咄嗟に床にばら撒いた。更に、ATMの横に置いてあるお金を入れる封筒と預金案内などのパンフレットも取り出して、その辺に投げ散らかす。そして、隣のおばさんの手から、花柄のスカーフをひったくると、突進してくる犯人達へ投げつけた。
スカーフはこちら側にいる友人の顔にかかり、彼女は床に散乱している紙に足を滑らせてすっ転んだ。それに引きずられて、犯人も右側から倒れこむ。
頭から突っ込んでくる少女と、右肩を突き出してくる犯人に、まだ入り口付近で固まっていた象男が、泡を食って逃げ出そうとした。しかし、その辺にはぼくがばら撒いたレシートや封筒が散らばっており、それに足を取られた彼は、二人もろとも背中から床に沈んでいった。
どったーん!
床に穴が開いたかと思うような激しい音の後には、入り口の前に折り重なるように倒れこんでいる三人の姿があった。彼らの体をセンサーが感知し、自動ドアが開く。
途中まで降りたシャッターの向こうには、行員達が呼んだと思しき警官達が群れをなしており、犯人はあっという間に御用になった。
ぼくは警官に許可を取って、まだスカーフを被ってふがふが言っている友人の傍に腰を下ろした。
「大丈夫か? 赤松」
友人の赤松は、なんとかスカーフを顔から外すと、今度は咳き込み始めた。ぜんそくの発作かと思うような苦しげな咳の間に、何やら呻いているようだ。
「重かったよう。臭かったよう」
やっと咳が治まってくると、彼女はそんなことを連呼していたのだと分かった。
重かったのは当然だろう。象男こそ彼女の下敷きになっていたが、上にいた犯人はジュラルミンケースを抱えたままだったのだから。
赤松の言葉が聞こえたのか、倒れていた象男がさっと立ち上がって身を縮めた。
「す、すいません。ぼ、僕、腋臭なんです!」
「ああ。あなたじゃないと思いますからお気遣いなく」
ぼくは、未だ苦しげな赤松の代わりに、男に笑いかけた。それから、彼女に被さっていたスカーフを持ち主のおばさんに渡す。
「お嬢ちゃん、大丈夫? 怖い目に遭ったわね」
おばさんは、赤松を気遣うように身をかがめてきた。すると、赤松はまた咳き込み始める。ぼくはおばさんをやんわりと遠ざけた。
赤松が咳き込んでいるのは、きっとおばさんの香水のせいなのだ。スカーフにもそのにおいが染み付いていた。一瞬ひっつかんだだけのぼくの手にも、そのにおいはハッキリと残っている。きっと高価な香水なのだろうが、その香りはどう嗅いでも、キンチョールのそれなのだ。つまり今の赤松は、キンチョールを顔に吹き付けられたような状態の中にいるのだった。
「そ、それじゃあ、僕はこれで・・・・・・」
そう言って立ち去ろうとする象男を、警官の一人が引き止めた。
「すみませんが、まだお聞きしたいことがありますので、いましばらく・・・・・・」
そこまで言って、警官の表情が変わった。象男を引き止めたまま、他の警官を呼んでいる。二人がこそこそ話し合っていると、キンチョールのおばさんが象男に向かって叫んだ。
「あなた! この前の銀行強盗犯の手配写真の人じゃないの!?」
ほっと一息ついていた客達も、行員も警官も、みんなぎょっとした。一斉に息を飲む音が聞こえるようだ。
「ほら、体格なんかも指名手配のポスターに書いてあったのとぴったり合うじゃない。特徴として挙げてあった首筋の大きな黒子もあるし」
おばさんは周りの様子に構わず、得意気に続ける。
「あたくし、ああいう手配ポスターって、ちゃんと細部まで覚えておくようにしてるのよ。だって、犯人逮捕を手伝うのは市民の義務ですものね。今回だって、あたくしのスカーフが・・・・・・」
悦に入って演説を続けるおばさんを尻目に、警官の一人が象男に言った。
「すみません。ちょっと、お話を聞かせていただけますか?」
その声音は、優しく、しかし有無を言わせないものを持っていた。
「え、あ、その、あの・・・・・・」
象男はしどろもどろになりながらも、勢いよく走り出そうとした。しかし、そこらにはまだ紙片が散らばったままで、またもや店内には地響きのような墜落音が鳴り響いたのだった。
- つづく -
くらくらする頭を抱えて、ぼくは必死に数分前のことを思い出そうとしていた。
友人とは、銀行の自動ドアの所で別れた。
「暑いから中入る?」
「ううん。お客さんも少ないみたいだし、すぐ終わるだろうからここで待ってるよ」
彼女はぼくの自転車を駐輪場に停めてくれながらそう言った。
「じゃあ、すぐ戻るから」
彼女と自転車をその場に残し、ぼくは某大銀行の支店へと足を踏み入れた。この支店は小さいので、入り口は一つしかない。入ってすぐ左手にATMがあり、入り口からまっすぐ進むと窓口のある広いロビーに続くようになっていた。
ぼくは順番を待っている間、ぼんやりと自動ドアから外を見ていた。外を見るといっても、透明ガラスの自動ドアには、ちょうど大人の目線あたりに銀行のロゴ大書してあり、かがみこまないと外からは中の、中からは外の様子はよく見えない。仕方がないので、ぼくは下の方に視線をさまよわせていた。
店内の床はよく磨きこまれており、ドアから入る太陽の光を受けて、てかてかと輝いている。一方、ガラス越しの景色は少し揺らいで見えた。焼けたアスファルトから煙が立ち昇っているかのようだ。
入り口の向かいにある駐輪場に友人が立っているのが見える。とりたてて太くも細くもない足が、日影を求めて歩き回っている。視界の端には、黒いズボンを穿いた男性のものらしい足もあった。入る時には気付かなかったが、警備員だろうか。こちらは暑いのに、じっと日向に立ったまま動かない。仕事とはいえ、ご苦労様だ。
ぼくの前でATMを使っていた男性が、象のように重い足取りで機械の前から離れた。図体もデカイので、本当に象が歩いているようだ。彼は沈痛な面持ちで通帳に見入っており、なかなか出ていこうとしなかった。首筋にある大きな黒子までもが、心なしか悲しそうに見える。
ぼくはネズミのように素早く機械の前に陣取り、画面の『お引き出し』を指で押した。機械アナウンスに従ってカードを入れる。暗証番号に続いて金額を入力し、確認ボタンを押したところで、自動ドアが開いた。
ぼくは先程の象男が出て行ったのだろうと思っていたが、どうやらここで入ってきたのが、今窓口でがなっている男であるらしい。そういえばあの時、ATMの上に設置してある鏡に、一瞬黒いジャンパーが映ったような気がしたのだ。この暑いのにジャンパーを着込むようなイカレタ人間がいるわけがない、きっと目の錯覚だと思っていたのに。
あの時、彼女も男と一緒に入ってきていたのか。
ぼくの口中に苦いものが込み上げてきた。
悪夢だ。きっとあまりの暑さに頭が湧いて、変な白昼夢を見てるんだ。隣のおばさんの頭を叩けば、目が覚めるかもしれない。
しかし、たとえ夢でも、善良な一市民であるぼくにそんなことができるはずもなく、この夢は一向に覚める気配を見せない。
窓口では、何故か友人が行員に詫びていた。そして犯人に「余計なことを言うな」と怒鳴られ、周りの同情と非難を一身に浴びている。
ぼくは自動ドアの下方に視線を移した。先程見えていた警備員の足は、どこかに消えていた。異変に気付いて、警察でも呼びに行ったのだろうか。ひょっとしたら、犯人が入る前に、気絶でもさせられたのかもしれない。
そうこうしているうちに、支店長と名乗る男性が大きなジュラルミンケースを抱えて登場した。犯人の要求は、窓口のお金の他に旧札で一千万円。あの中身がそうなのだろう。
犯人は人質の女の子、つまりぼくの友人に、窓口の女性から受け取った現金入りのずた袋を持たせ、果物ナイフを閉じてケースの中身を確認した。
友人はずた袋をしっかりと両手で抱きしめていたが、その姿は、お金というようりも赤ん坊を恐々と抱きかかえているかのようだ。しかし、袋には赤ん坊のように手足の引っ掛かりがない。よって、今にも腕の間からズルズルと落ちていきそうだった。
ぼくは心の中で、落ちるぞ、落ちるぞ、落ちても知らないぞ、と犯人に語りかけていたのだが、目出し帽なんぞ被った男に超能力者でもないぼくのテレパシーが通じるはずもなく、犯人がジュラルミンケースを閉じると同時に、友人はずた袋を取り落とした。
ずだーんっ!
袋が床に落ちて、派手な音を響かせた。紐で縛っていただけの口が開いて、中から札束が転がり出る。ロビーにいた人達の間にどよめきが走った。
友人は小さくなって、「ごめんなさい」を連呼している。
彼女が抱えていたのが本物の赤ん坊でなくて良かった。
そう思ったのも束の間、袋を拾い上げようとした友人を引っ張って、犯人が走り出した。左手でナイフとジュラルミンケースを持ち、右手で友人を引きずるようにして、ぼくのいる入り口の方へ向かってくる。
足をもつれさせながら引きずられてくる友人を見て、ぼくは捨てようとしていたレシートを、咄嗟に床にばら撒いた。更に、ATMの横に置いてあるお金を入れる封筒と預金案内などのパンフレットも取り出して、その辺に投げ散らかす。そして、隣のおばさんの手から、花柄のスカーフをひったくると、突進してくる犯人達へ投げつけた。
スカーフはこちら側にいる友人の顔にかかり、彼女は床に散乱している紙に足を滑らせてすっ転んだ。それに引きずられて、犯人も右側から倒れこむ。
頭から突っ込んでくる少女と、右肩を突き出してくる犯人に、まだ入り口付近で固まっていた象男が、泡を食って逃げ出そうとした。しかし、その辺にはぼくがばら撒いたレシートや封筒が散らばっており、それに足を取られた彼は、二人もろとも背中から床に沈んでいった。
どったーん!
床に穴が開いたかと思うような激しい音の後には、入り口の前に折り重なるように倒れこんでいる三人の姿があった。彼らの体をセンサーが感知し、自動ドアが開く。
途中まで降りたシャッターの向こうには、行員達が呼んだと思しき警官達が群れをなしており、犯人はあっという間に御用になった。
ぼくは警官に許可を取って、まだスカーフを被ってふがふが言っている友人の傍に腰を下ろした。
「大丈夫か? 赤松」
友人の赤松は、なんとかスカーフを顔から外すと、今度は咳き込み始めた。ぜんそくの発作かと思うような苦しげな咳の間に、何やら呻いているようだ。
「重かったよう。臭かったよう」
やっと咳が治まってくると、彼女はそんなことを連呼していたのだと分かった。
重かったのは当然だろう。象男こそ彼女の下敷きになっていたが、上にいた犯人はジュラルミンケースを抱えたままだったのだから。
赤松の言葉が聞こえたのか、倒れていた象男がさっと立ち上がって身を縮めた。
「す、すいません。ぼ、僕、腋臭なんです!」
「ああ。あなたじゃないと思いますからお気遣いなく」
ぼくは、未だ苦しげな赤松の代わりに、男に笑いかけた。それから、彼女に被さっていたスカーフを持ち主のおばさんに渡す。
「お嬢ちゃん、大丈夫? 怖い目に遭ったわね」
おばさんは、赤松を気遣うように身をかがめてきた。すると、赤松はまた咳き込み始める。ぼくはおばさんをやんわりと遠ざけた。
赤松が咳き込んでいるのは、きっとおばさんの香水のせいなのだ。スカーフにもそのにおいが染み付いていた。一瞬ひっつかんだだけのぼくの手にも、そのにおいはハッキリと残っている。きっと高価な香水なのだろうが、その香りはどう嗅いでも、キンチョールのそれなのだ。つまり今の赤松は、キンチョールを顔に吹き付けられたような状態の中にいるのだった。
「そ、それじゃあ、僕はこれで・・・・・・」
そう言って立ち去ろうとする象男を、警官の一人が引き止めた。
「すみませんが、まだお聞きしたいことがありますので、いましばらく・・・・・・」
そこまで言って、警官の表情が変わった。象男を引き止めたまま、他の警官を呼んでいる。二人がこそこそ話し合っていると、キンチョールのおばさんが象男に向かって叫んだ。
「あなた! この前の銀行強盗犯の手配写真の人じゃないの!?」
ほっと一息ついていた客達も、行員も警官も、みんなぎょっとした。一斉に息を飲む音が聞こえるようだ。
「ほら、体格なんかも指名手配のポスターに書いてあったのとぴったり合うじゃない。特徴として挙げてあった首筋の大きな黒子もあるし」
おばさんは周りの様子に構わず、得意気に続ける。
「あたくし、ああいう手配ポスターって、ちゃんと細部まで覚えておくようにしてるのよ。だって、犯人逮捕を手伝うのは市民の義務ですものね。今回だって、あたくしのスカーフが・・・・・・」
悦に入って演説を続けるおばさんを尻目に、警官の一人が象男に言った。
「すみません。ちょっと、お話を聞かせていただけますか?」
その声音は、優しく、しかし有無を言わせないものを持っていた。
「え、あ、その、あの・・・・・・」
象男はしどろもどろになりながらも、勢いよく走り出そうとした。しかし、そこらにはまだ紙片が散らばったままで、またもや店内には地響きのような墜落音が鳴り響いたのだった。
- つづく -
© Rakuten Group, Inc.