10
5
翌日もぼくは、学校のある町まで電車で来ていた。クラスメイトが学校付近の書店でバイトを始めたというので、茶化しに行こうと出てきたのだ。
書店は広い店内にちらほらと人が立ち読みしている程度で、レジにいたクラスメイトは暇そうにしていた。ぼくは彼に乞われるまま、彼のバイトが終わるまで暇潰しに付き合った。ぼくとしても、暑苦しい家にいるより、冷房の効いた場所に居られるほうがありがたかった。
三時過ぎにバイトが終わり、彼と一緒に駅まで戻った。昼飯を食べていたにもかかわらず、駅の中のセルフのうどん屋でうどんを奢ってもらい、ホームへ向かう。彼も帰る方向が同じなので、乗る電車も一緒だった。
「そういえば、今朝お前が来る前に赤松さんが来たよ」
ホームへの階段を登りきったところで、クラスメイトが言った。
ぼくは向かいのホームに気を取られていて、彼の言葉を聞き取るのが少し遅れた。
向かいのホームでは、ぼくの家とは反対方向に行く電車が入ってきているところだった。そのホームに、片岡がいたような気がしたのだ。その姿はすぐに電車で見えなくなったが、それらしい人影が車内に立つのを見たような気がした。
しかし、本当の片岡は、今日も朝からこの町にある塾でカンヅメになっているはずだ。まだ受験は来年だというのにご苦労なことである。
「え? 何? 赤松?」
ぼくは反対方向の電車を見送ってから聞き返した。
「うん。赤松さんが今朝うちの店に来たんだ。残念だったね。もう少し早く来れば会えたのに」
ぼくは、ふーん、とだけ言っておいた。彼もぼく達の仲を勘違いしている人間の一人かもしれない。
ぼくが相槌しか打たないでいると、クラスメイトは勝手に続きを喋りだした。
「でも、彼女変わってるね。処方薬事典買ってくなんてさ」
ぼくはまた一瞬遅れて彼を見た。ショホウヤクジテンを頭の中で漢字変換するのに時間がかかったのだ。
「専門書コーナーにある分厚いやつ。何千円もするのをひょいと買ってくんだもんな。家に病気の人でもいるのかな。それとも看護学校にでも進むつもりかな」
彼は考えながら喋っていたが、急に思い出したように苦い顔になった。
「あ、お客さんの購入したものって、本当はあまり人に教えちゃいけないらしいんだよね。俺が喋ったのは内緒にしといてくれよな。彼女はずっと下ばかり見てて、俺に気付いてなかったみたいだし」
クラスメイトは顔の前で両手をあわせた。ぼくは曖昧に頷いた。
どうせ、いつも俯いて、人の噂話など耳に入れないように感覚を閉じて生活している赤松は、彼のことなど知らないのだ。顔を見ても、同じ学校の生徒だということにすら気付かないだろう。
電車が来るというアナウンスが入り、かすかな地響きが聞えてくる。風圧とともに現れたのは貨物列車だった。列車はホームの全てを吹き飛ばすような轟音を響かせて、スピードを緩めないまま目の前を通過していく。
ぼくは貨物列車のコンテナの数を数えながら、昨夜の赤松との会話を思い出していた。
昨日、ぼくはディスカウントストアで手にしていたジュースを赤松の買い物袋に入れたまま帰ってしまい、家に帰って気付いた彼女から電話があったのだ。
赤松は、まだ白石久美子の件にこだわっている様子だった。
「わたし、片岡君には白石さんが助かったから良かったって言ったけど、それって本当に白石さんにとって良かったことなのかな」
「どういう意味?」
「自殺を決心するのって、並大抵のことじゃなかったと思うんだ。死にたくて死にたくて、やっと意識を失うことができたのに、生き延びてしまったと気付いた時の彼女の気持ちって、どうだったんだろうと思って」
白石さんが自殺だったらの話だけどね。赤松はそう付け加えた。
自殺しようとした人間が目覚めた時の気持ち。それはもちろん安堵や歓喜などではなく落胆だろう。命と引き換えにしてまでこの世の苦痛からの脱出を試みたのに、またもや死にたいと思うような現実に引き戻されてしまうのだ。どんな苦痛からも逃れることは許さないと。矛盾しているようだが、脱走した死刑囚が刑務所に連れ戻される時の気持ちと似ているかもしれない。
それに白石久美子には、彼女の覚醒を待っている人間もいなかった。赤松から聞いた話では、友人や知人が見舞いに来るようなこともないらしい。しかも言語障害というオマケまでついてしまっているのだ。ある程度は治るということだが、完治するかどうかは分からないらしい。
倒れた時、これで連れ合いの元へ行けると思っていたとしたら、現在の彼女の絶望は計り知れないものだろう。
底のない孤独。暗い現実。希望の光など見出せるはずもない。
「たしかに自殺だったなら、明るい気持ちじゃなかっただろうね。だけど、赤松は彼女が生きていて良かったって思ったんだろう? だったらそれでいいじゃん」
考えとは裏腹に、ぼくは楽観的な調子で言った。
「そうだけど・・・・・・」
「一度、見舞いにでも行くか」
「え?」
「一人でも自分が生きてることを良かったって思ってくれる人間がいれば、白石久美子も少しは救われるんじゃない? それに、この件に関しては俺の意見に従うんじゃなかったっけ」
赤松は暗い声を一転させて、そうだねと言った。
「うん。この件は全部きみの言うとおりにする」
それなのに朝っぱらから処方薬事典を買っていったとは。まだあの薬のことを調べようとしているに決まってる。これ以上、何をどうしようっていうんだか。
「ったく、あの馬鹿」
「え? 何?」
思わずぼくの口をついて出た悪態に、電車に乗り込もうとしていたクラスメイトがギョッとして振り向いた。
いつの間にか貨物列車は行ってしまい、目の前には、銀色の車体が口を開けて停まっていた。
「や、何でも」
ぼくは蒸し暑い駅のホームにいることを思い出し、急いで電車に飛び込んだ。
- つづく -
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ニュース
- 今日から健康保険証の新規発行停止
- (2024-12-02 18:36:52)
-
-
-

- つぶやき
- ガパオライスとチーズかぼちゃ餅、お…
- (2024-12-03 00:00:26)
-
-
-
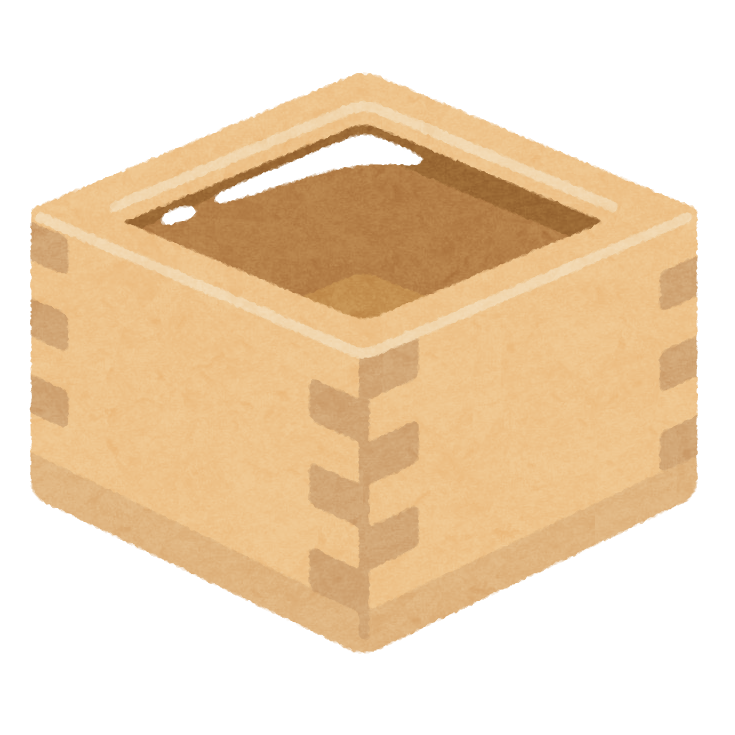
- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 【感想あり】給油所で「レギュラー“…
- (2024-12-03 00:00:12)
-
© Rakuten Group, Inc.



