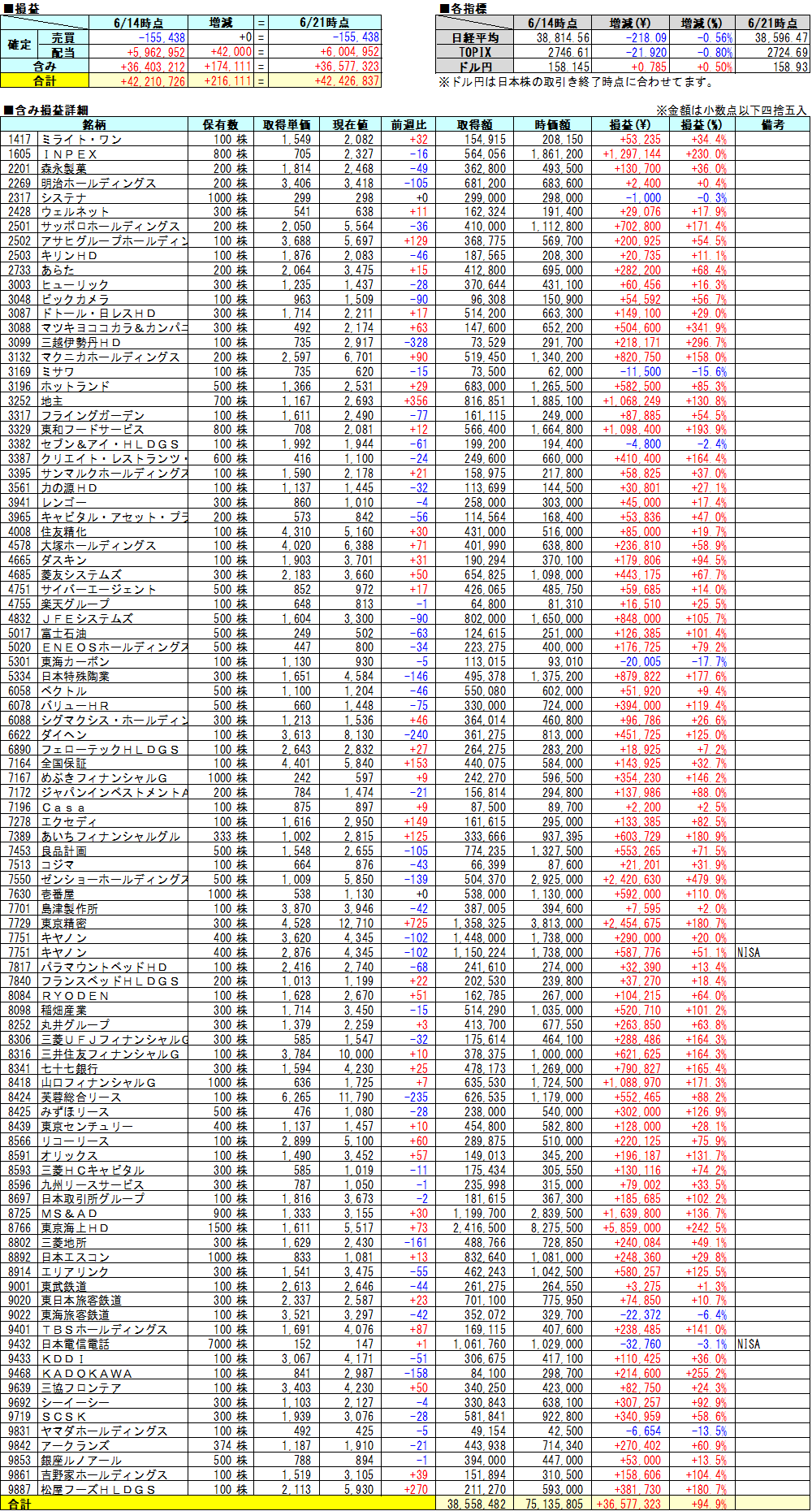14
6
片岡は欠伸を一つして話し始めた。
白石久美子のアパートに行った日、彼は部屋の中を一通り見させてもらったらしい。その時、親父さんと白石久美子の薬を発見した。
片岡が薬袋の散乱しているキッチンのテーブルの前に立っていると、白石久美子がトイレに入っていった。
部屋にエアコンはなく、親父さんの遺影のある和室で、扇風機が物憂げに回っていた。
「たしかに俺は、お前の言うとおり、あの女の薬と親父の薬を入れ替えた。でも、ピルケースには入れていない。ヒートのまま薬袋に入れ替えたんだ」
「え? じゃあ、彼女は・・・・・・」
ぼくは少なからず驚いた。白石久美子は全て承知で飲んだということか。
片岡がその考えを裏付けるように後を引き取った。
「自分の意思で飲んだんだよ。俺はあの部屋では、ピルケースなんて見てもいない」
赤松の言葉が脳裏に蘇った。
ゆるやかな自殺。
彼女は愛する者の服用していた薬で、少しずつ少しずつ自分の体を蝕んでいったのだ。自分自身の意思で。
片岡は一人になると、いつの間にか薬の入った袋を手に取っていた。そして、ほとんど無意識のうちに袋の中身を入れ替えていたのだった。
「無意識と言っても、似たような色のものを選んで入れ替えていたらしい。入れ替えたのは、ベージュの降圧剤とピンクの糖尿病薬だったんだからな」
片岡には、二つの薬がどういう薬でどんな作用を及ぼすものなのかという知識は、この時点では全くなかった。
「俺があの女を映画に誘ったのは、半分はお前の考えたとおり、あの女がどうなったのかを確認するためだ。でも、それよりも、あいつがどんな反応をするかを見てみたかった。俺が薬を入れ替えたことに気付かないはずはなかったから、飲んでいるとは思ってなかったよ」
白石久美子は、片岡が親父さんとそっくりだと愛しそうに言ったという。そんな、愛する者にそっくりな子供に殺意を抱かれていると気付いた時の彼女の反応を、片岡は見たかった。彼女がどんな表情をするのか、どんな風に彼に振舞うのか。その中には、絶望や焦燥が見えるのではないか。
約束の日の前日、白石久美子から片岡に連絡があった。彼女は至って元気そうで、明日を楽しみにしていると、うきうきした声で伝えてきたそうだ。片岡の気持ちは揺れた。愕然とする彼女を見たかったのに、白石久美子は嬉しさに声を弾ませていたのだ。
本当に殺意を抱いたのはこの時かもしれないと、片岡は言った。
「俺は、あの女の家にあった薬のことを調べて計画を立てた。あのグレープフルーツジュースはお前の想像通り、あの女に飲ませて降圧剤の副作用を引き出させようと思って持っていったものだ。さすがに殺せるとまでは思ってなかったが、せめて俺に悪意があることを、あの女に気付かせたかった」
「一つ、聞きたいことがあるんだけど」
ぼくは片岡の話を割るように言った。
「何だ?」
「片岡が赤松の本を踏めないと言ったのは、あの映画館ではお前が悪いことをするはずがないって、暗に俺に思い込ませるためだったのか?」
これはぼくがずっと引っ掛かっていたことだった。
ぼくが片岡に疑惑を抱いたのは、昨日、従兄の持ってきたグレープフルーツジュースを見た時だ。しかし、あの言葉がなかったら、もっと早い段階から彼を疑っていたかもしれない。
以前のぼくなら、こんな非日常的なことは考えもしなかっただろう。でも赤松と出会ってから、犯罪というものがあまり遠い世界の話ではなくなったような気がする。
あいつが歩くとたいてい人にぶつかる。そしてその中には、低い割合ではあるが、普通の人が出会うよりは高い確率で犯罪者も紛れている。
片岡には、赤松の作品を傷つけるようなことはできない。
この固定観念がどこかにあったから、ぼくは昨日まで片岡を疑うことがなかったのだ。
「そう思うのか?」
質問に質問で返され、ぼくはしばし沈黙した。
「・・・・・・正直、思いたくない」
片岡はクスリと笑った。それは、どこか眠たげな笑いだった。
「お前が素直な発言すると気持ち悪いな」
「俺も鳥肌が立ってるよ」
「あれは本当だ。実際に、あの映画館では俺は何もしていない」
「本当に?」
「ああ。あの映画の製作には赤松さんはノータッチだったけど、やっぱりあそこで人を苦しめることなんて出来なかったよ。たしかに俺はあの日、あの女にグレープフルーツジュースを飲ませようと思っていた。でも、それは映画館でじゃない。映画を観終わって、外に出てからのつもりだったんだ」
片岡は映画館を出て街をぶらぶら歩いている時にでも、喉が渇いたふりをして自分が飲み、白石久美子にもさり気なく勧めるつもりだった。もちろん、彼女が喉が渇いたから何か飲もうとでも言えば、それこそ好都合だと思っていた。
今年の夏は、去年の冷夏の貸しを取り戻すかのような猛暑だ。自販機のある学校にも、お茶やジュースを凍らせたり魔法瓶に入れたりして持ってきている奴もいる。だから水筒にジュースを入れて持ち歩くことは、別に不自然なことではなかった。
あの日は特にそういうことをするにはおあつらえ向きな天気で、ビルや道路までもが水分を欲しているようだった。
しかし、片岡はそうすることができなかった。それは、彼女が映画館を出る前に倒れたからではない。彼は館内にいる時、既にそんな気を失くしていたのだ。
「エンドロールで赤松さんのペンネームを見た時、俺は何やってんだろうって思ったんだ」
赤松の本は、そんなに売れているわけではない。ぼくはよく知らないが、大きな書店でも一冊置いてあるかどうかといったところらしい。そんなわけで、彼女の副業を知っている人間はわずかしかいない。赤松自身もそれをひた隠しにしているようなところがあり、中学生の頃から印税を稼いでいたとはとても思えないほど、彼女は地味で目立たないどころか、暗いとさえ噂されるような学生生活を送っている。
それでも、彼女の書いたものを気に入って、映像化したいという人間がいた。そしてわずかだが、それを観に来た人達も。その中には、彼女の書いた話だから、その話が好きだからという人間だっていたはずだ。
自分と同い年のどうしようもなく内気な女の子が、少しずつ少しずつ、自分の中の何かを育てようとしている。学校では柱の影に隠れるように小さくなっていて、友人さえいない彼女が、全くの他人に認められようとしている。
それなのに、自分は何をしようとしているのだろう。
片岡は、自分が恥ずかしくなった。
「それで、あの女がトイレに入ったのをいいことに、俺は逃げるようにして映画館を出た。でも、まさかあそこで倒れるなんて・・・・・・」
片岡の声は、かすかな後悔を含んでいた。
きっとそれは、彼の最大の誤算だったのだ。あそこで白石久美子が倒れなければ、片岡はぼく達に彼女との関係を話すことはなかった。ぼく達は彼の過去を知ることもなければ、彼がやったことに気付くこともなかっただろう。
片岡は、ぼく達に自分のしたことがばれてしまうリスクを負っても、赤松に謝罪せずにはいられなかったのだ。
それは彼の几帳面な性格のせいでもあり、相手が赤松だったせいでもあると思う。
「そうやって一度は思いとどまったのに、どうしてまた」
ぼくは訊かずにいられなくなって、口を挟んだ。
実際には、白石久美子はあの薬を飲んでいたわけだが、ここまでなら、片岡のしたことはまだ人の道を外れていないような気がする。それを逸脱させてしまったものは、一体何だったんだろう。
「俺、あの女の手紙、本当は受け取ってたんだ」
「え? でも、おばあさんは・・・・・・」
「ああ、ばあさんが拒んだのは本当だ。でも、次の日、じいさんが病院まで出向いて貰ってきた。あの手紙は俺へのものなんだから、ばあさんや自分が勝手に受け取り拒否していいもんじゃないってな」
おじいさんは片岡に手紙を渡して言ったそうだ。
――私達にとっては、白石久美子もお前の父親も、娘を不幸にした悪の権化みたいな存在なんだ。勝手に拒否してしまったばあさんを許してやってくれ。
片岡は自分も受け取る気はないからいいと言った。しかし、おじいさんは、彼の親父さんを悪く言ったことを謝り、彼に封筒を押し付けた。
――私達がそうだからといって、お前まで彼を嫌う必要はないんだ。たった一人の父親なんだから。これは、その父親を看取った人の手紙だ。読まなくてもいいし、破り捨ててもいい。でも、自分の意志で、自分の手でするんだ。そして、後悔するような扱いだけはするな。
おじいさんの顔はとても穏やかだったが、目は厳しさを湛えていた。
「それで、お前は読んだんだな?」
「ああ。お前に内容を聞かれた時は、まだ読んでなかったんだけどな。捨てようかどうしようか迷ってる最中だったから」
「何が書いてあったんだ?」
いつも沈着冷静な片岡に、再び殺人の衝動を起こさせる何かが、そこには書いてあったのだ。ぼくはつばを飲み込んだ。
- つづく -
© Rakuten Group, Inc.