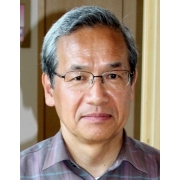PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
またまた花は6月も…
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん
季節の花 シャクジ… New!
himekyonさん
New!
himekyonさん
菜園ニュース:久々… ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん季節の花 シャクジ…
 New!
himekyonさん
New!
himekyonさん菜園ニュース:久々…
 ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 山野草と樹木と野鳥たち
☆冬の間は、随時「自然観察の振返り」を掲載しています。テーマは、名前の由来です。
☆ウォーキングの途中、大きめの鳥が見えたので、近づいてみました。獲物を捕らえたオオタカでした。オオタカは、日本全土の平地から山岳地帯に生息しているタカ科ハイタカ属の留鳥ですが、一部は越冬のため南下するそうです。(2013年10月9日撮影)。

☆体長は、カラスより大きい印象で、全長がおよそ50センチメートル位だったでしょうか。オオタカは、タカ科に属し、日本のタカの代表的な種で、鷹狩りに使われていたそうです。オオタカ(大鷹)の名は、他のタカ科の羽色が褐色なのに対して、オオタカの羽色が青灰色なので「蒼鷹(アオタカ)」と呼ばれ、それが転じてオオタカになったという説があるそうです。奈良時代には「あをたか」、平安時代には「おほたか」と呼ばれ、それがオオタカにつながっているという説明もありました。「蒼い」とは、本来は灰色がかった白色ということなので、アオサギ(蒼鷺)の名と同じ由来になるようです。(2013年10月9日撮影)。

☆なお、「鷹」の名は、「高(タカ)く」飛ぶからという説、「タカヒドリ(手飼鳥)」の意味という説、「タケキ(猛)」の意味からという説、凡鳥でないので「気高し(ケタカシ)」の意味という説などがあるそうです。
☆オオタカは飛翔能力が高く、ハト・カモなどの鳥類やネズミ・ウサギなどの小型哺乳類を空中や地上で捕えます。食物連鎖の頂点に位置するので、生態系の自然が健全でないと生息できないそうです。
◎三鷹の地名―鷹狩を行なった鷹場の村々が集まっていたことと、世田谷領・府中領・野方領にまたがっていたことに由来する(三領の鷹場)
☆三鷹の地名は、江戸時代は鷹狩りが盛んで、徳川将軍家及び御三家が鷹狩を行なった鷹場の村々が集まっていたことと、世田谷領・府中領・野方領にまたがっていたことに由来する(三領の鷹場)と言われています。北は前橋、熊谷など、西は武蔵野、三鷹など、南は藤沢、小田原まで、東は葛西あたりまで、江戸を取り囲む周辺は全て徳川の「御鷹場」であったそうです。
☆1889年の市町村制施行により各村の合併で「三鷹村」、1940年に町制施行により「三鷹町」、1950年に市制施行により「三鷹市」になったそうです。(2013年10月9日撮影)。

◎クマシデ(熊四手)―シデの仲間では果穂が最も大きいので「熊」の名
☆2014年は、クマシデの果穂が例年になく鈴なりになっていました。秋には、黄緑色から茶色く色づきいちだんと目立つようになりました。果穂とは、種子を抱いた果苞(葉が変形したもの)が房状になったものです。クマシデの果穂は、果苞が密で太いのが特徴です。(2014年10月8日撮影)。

☆クマシデ(熊四手)の名は、シデの仲間では果穂が最も大きいので「熊」の名がついたそうです。四手(紙垂)は、しめ縄や玉串などにつける細長く切った紙のことで、花が枝に垂れ下がる様子から。(2014年10月8日撮影)。

◎クマノミズキ(熊野水木)―三重県熊野地方に産するミズキで地名「熊野」から

☆クマノミズキは、本州、四国九州の山野の林内に生えるミズキ科ミズキ属の落葉高木です。クマノミズキ(熊野水木)の名は、三重県熊野地方に産するミズキに由来しますが、西日本に広く分布しています。ミズキ(水木)の名は、早春に枝を切ると樹液がしたたり落ちることに由来しているそうです。(2014年6月13日撮影)。

☆なお、地名の「熊野」の名は、神武天皇が大熊に会ったためという説、うっそうたる森林に覆い隠されているためという説、出雲国の熊野の名が移されたという説もあるそうです。
◎クマツヅラ(熊葛、生薬名:馬鞭草)―馬の鞭の材料であった「クマツヅラ」が「馬鞭草」の鞭の意味となり、クマツヅラが馬鞭草の和名となった
☆2014年、東伊豆で多く見かけたのはランタナの花です。ランタナは、中南米原産で世界中に帰化しているクマツヅラ科シチヘンゲ属(ランタナ属)の常緑小低木です。(2014年11月17日撮影)。

☆ランタナは、小さな花が集まった散形花序で、開花後時間がたつと次第に花の色が変わるそうです。
☆ところで、クマツヅラ科の「クマツヅラ(熊葛)」の由来を調べてみると。クマツヅラの全草を刈り取り日干しにして乾燥したものを、生薬名で「馬鞭草(ばべんそう)」と呼び、腫れ物、打撲傷、打ち身などの外用に用いるそうです。平安時代の初期頃までは、「クマツヅラ」は馬の鞭の材料であったクマヤナギ(熊柳)であったそうです。馬の鞭の材料であった「クマツヅラ」が、いつの間にか馬の鞭の代名詞(鞭=クマツヅラ)として使われ「馬鞭草」の鞭の意味となり、クマツヅラが馬鞭草の和名となったと云う説があるそうです。(2014年11月17日撮影)。

☆なお、コムラサキやムラサキシキブは、以前のクロンキスト体系ではクマツヅラ科ムラサキシキブ属に分類されていましたが、現在のAPG植物分類体系ではシソ科ムラサキシキブ属に分類されています。
☆ウォーキングの途中、大きめの鳥が見えたので、近づいてみました。獲物を捕らえたオオタカでした。オオタカは、日本全土の平地から山岳地帯に生息しているタカ科ハイタカ属の留鳥ですが、一部は越冬のため南下するそうです。(2013年10月9日撮影)。

☆体長は、カラスより大きい印象で、全長がおよそ50センチメートル位だったでしょうか。オオタカは、タカ科に属し、日本のタカの代表的な種で、鷹狩りに使われていたそうです。オオタカ(大鷹)の名は、他のタカ科の羽色が褐色なのに対して、オオタカの羽色が青灰色なので「蒼鷹(アオタカ)」と呼ばれ、それが転じてオオタカになったという説があるそうです。奈良時代には「あをたか」、平安時代には「おほたか」と呼ばれ、それがオオタカにつながっているという説明もありました。「蒼い」とは、本来は灰色がかった白色ということなので、アオサギ(蒼鷺)の名と同じ由来になるようです。(2013年10月9日撮影)。

☆なお、「鷹」の名は、「高(タカ)く」飛ぶからという説、「タカヒドリ(手飼鳥)」の意味という説、「タケキ(猛)」の意味からという説、凡鳥でないので「気高し(ケタカシ)」の意味という説などがあるそうです。
☆オオタカは飛翔能力が高く、ハト・カモなどの鳥類やネズミ・ウサギなどの小型哺乳類を空中や地上で捕えます。食物連鎖の頂点に位置するので、生態系の自然が健全でないと生息できないそうです。
◎三鷹の地名―鷹狩を行なった鷹場の村々が集まっていたことと、世田谷領・府中領・野方領にまたがっていたことに由来する(三領の鷹場)
☆三鷹の地名は、江戸時代は鷹狩りが盛んで、徳川将軍家及び御三家が鷹狩を行なった鷹場の村々が集まっていたことと、世田谷領・府中領・野方領にまたがっていたことに由来する(三領の鷹場)と言われています。北は前橋、熊谷など、西は武蔵野、三鷹など、南は藤沢、小田原まで、東は葛西あたりまで、江戸を取り囲む周辺は全て徳川の「御鷹場」であったそうです。
☆1889年の市町村制施行により各村の合併で「三鷹村」、1940年に町制施行により「三鷹町」、1950年に市制施行により「三鷹市」になったそうです。(2013年10月9日撮影)。

◎クマシデ(熊四手)―シデの仲間では果穂が最も大きいので「熊」の名
☆2014年は、クマシデの果穂が例年になく鈴なりになっていました。秋には、黄緑色から茶色く色づきいちだんと目立つようになりました。果穂とは、種子を抱いた果苞(葉が変形したもの)が房状になったものです。クマシデの果穂は、果苞が密で太いのが特徴です。(2014年10月8日撮影)。

☆クマシデ(熊四手)の名は、シデの仲間では果穂が最も大きいので「熊」の名がついたそうです。四手(紙垂)は、しめ縄や玉串などにつける細長く切った紙のことで、花が枝に垂れ下がる様子から。(2014年10月8日撮影)。

◎クマノミズキ(熊野水木)―三重県熊野地方に産するミズキで地名「熊野」から

☆クマノミズキは、本州、四国九州の山野の林内に生えるミズキ科ミズキ属の落葉高木です。クマノミズキ(熊野水木)の名は、三重県熊野地方に産するミズキに由来しますが、西日本に広く分布しています。ミズキ(水木)の名は、早春に枝を切ると樹液がしたたり落ちることに由来しているそうです。(2014年6月13日撮影)。

☆なお、地名の「熊野」の名は、神武天皇が大熊に会ったためという説、うっそうたる森林に覆い隠されているためという説、出雲国の熊野の名が移されたという説もあるそうです。
◎クマツヅラ(熊葛、生薬名:馬鞭草)―馬の鞭の材料であった「クマツヅラ」が「馬鞭草」の鞭の意味となり、クマツヅラが馬鞭草の和名となった
☆2014年、東伊豆で多く見かけたのはランタナの花です。ランタナは、中南米原産で世界中に帰化しているクマツヅラ科シチヘンゲ属(ランタナ属)の常緑小低木です。(2014年11月17日撮影)。

☆ランタナは、小さな花が集まった散形花序で、開花後時間がたつと次第に花の色が変わるそうです。
☆ところで、クマツヅラ科の「クマツヅラ(熊葛)」の由来を調べてみると。クマツヅラの全草を刈り取り日干しにして乾燥したものを、生薬名で「馬鞭草(ばべんそう)」と呼び、腫れ物、打撲傷、打ち身などの外用に用いるそうです。平安時代の初期頃までは、「クマツヅラ」は馬の鞭の材料であったクマヤナギ(熊柳)であったそうです。馬の鞭の材料であった「クマツヅラ」が、いつの間にか馬の鞭の代名詞(鞭=クマツヅラ)として使われ「馬鞭草」の鞭の意味となり、クマツヅラが馬鞭草の和名となったと云う説があるそうです。(2014年11月17日撮影)。

☆なお、コムラサキやムラサキシキブは、以前のクロンキスト体系ではクマツヅラ科ムラサキシキブ属に分類されていましたが、現在のAPG植物分類体系ではシソ科ムラサキシキブ属に分類されています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[山野草と樹木と野鳥たち] カテゴリの最新記事
-
「アオ」の名がつくアオキ、アオゲラ、ア… 2015.01.28 コメント(2)
-
昨年10月に種を蒔いて育ててきたパンジー… 2014.02.05
-
アオサギを久しぶりに見かけました。ウォ… 2013.05.19
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.