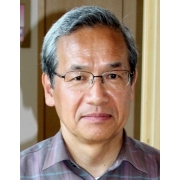PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
我家で咲く花たち!…
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん
上高地へ 2日目 New! himekyonさん
用水路~K川散策日記… ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん上高地へ 2日目 New! himekyonさん
用水路~K川散策日記…
 ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 楽天写真館(354986)
カテゴリ: 山野草
☆自然観察ブログ「しろうと自然科学者の自然観察日記」を始めて6年9カ月、連載は連続2,400回を超えました。そこで、「自然観察の振返り」を随時掲載しています。【自然観察の振返り[13]】はキジカクシ科(クサスギカズラ科:Asparagaceae)の植物です。キジカクシ科は、従来の分類(新エングラー体系、クロンキスト体系等)ではユリ科に含められていました。第4回は、ツルボの花です。(2016年8月15日撮影)。

☆ツルボは、北海道西南部以南の日本全土の山野の日当たりの良いところに生えるキジカクシ科ツルボ属の多年草です。(2015年8月28日撮影)。

☆ツルボの葉は、春と夏、年に2回出ます。春には5~10枚の春葉が出て夏草が茂る頃には枯れ、初秋に2~3枚の葉が出て葉の間から花茎を伸ばして花穂をつけるそうです。葉は倒披針状線形で先が尖り、長さ10~25センチ、幅4~6ミリ、表面は浅くくぼみ、厚く軟らかいそうです。写真では、花茎の両側に2枚の葉が見えます。(2016年8月15日撮影)。

☆ツルボの花期は8~9月で、高さ20~50センチの花茎の先端に総状花序をつけます。(2012年9月4日撮影)。

☆ツルボは、花序に長さ3~6ミリの花柄がある花が密に付き、花穂の下から順に咲いていきます。花穂の先端の蕾は緑色で、次第に淡紅紫色に変わり、花が咲いていく様子がわかります。(2015年8月24日撮影)。

☆ツルボの花は斜上向きに咲き、ツルボの花のつくりは、淡紅紫色の花被片が6枚(外花被片3枚と内花被片3枚)、雄蕊が6本、雌蕊が1本です。花被片の中央には、紫色のスジが見えます。(2012年9月4日撮影)。

☆6本の雄蕊は花被片とほぼ同じ長さで、花糸の先端の葯は2つに分かれています。子房は3室に分かれており、子房から伸びる雌蕊花柱は紫色です。(2012年9月6日撮影)。

☆花序の下の方で花が終わったものは、果実ができ始めています。ツルボの果実は蒴果で、熟すると裂開して黒い種子が散布されます。蒴果(さくか)とは、乾果(乾燥果)で裂開する果実のことです。(2013年8月22日撮影)。

☆ツルボ(蔓穂)の名は、球根の外皮をとると、つるりとした坊主頭に似ているので、「ツルボウズ」からツルボになった説などがあるようです。また、「ツルイイボ(蔓飯粒穂)」が略されてツルボになったという説がありました。「ツル(蔓)」は長く連なることや長く伸びることを表す言葉、「イイ(飯粒)」は飯粒(めしつぶ)で「イイボ(飯粒穂)」は飯粒状のものが花穂を作っていることだそうです。「ツルイイボ(蔓飯粒穂)」が「ツルイボ」になり、そしてツルボ(蔓穂)になったという説です。(2016年8月15日撮影)。


☆ツルボの別名はサンダイガサ(参内傘)で、公家が内裏に参内するときに従者に持たせた長い柄がある傘をたたんだ形に、ツルボの花序の形が似ているため名づけられたそうです。

☆ツルボは、北海道西南部以南の日本全土の山野の日当たりの良いところに生えるキジカクシ科ツルボ属の多年草です。(2015年8月28日撮影)。

☆ツルボの葉は、春と夏、年に2回出ます。春には5~10枚の春葉が出て夏草が茂る頃には枯れ、初秋に2~3枚の葉が出て葉の間から花茎を伸ばして花穂をつけるそうです。葉は倒披針状線形で先が尖り、長さ10~25センチ、幅4~6ミリ、表面は浅くくぼみ、厚く軟らかいそうです。写真では、花茎の両側に2枚の葉が見えます。(2016年8月15日撮影)。

☆ツルボの花期は8~9月で、高さ20~50センチの花茎の先端に総状花序をつけます。(2012年9月4日撮影)。

☆ツルボは、花序に長さ3~6ミリの花柄がある花が密に付き、花穂の下から順に咲いていきます。花穂の先端の蕾は緑色で、次第に淡紅紫色に変わり、花が咲いていく様子がわかります。(2015年8月24日撮影)。

☆ツルボの花は斜上向きに咲き、ツルボの花のつくりは、淡紅紫色の花被片が6枚(外花被片3枚と内花被片3枚)、雄蕊が6本、雌蕊が1本です。花被片の中央には、紫色のスジが見えます。(2012年9月4日撮影)。

☆6本の雄蕊は花被片とほぼ同じ長さで、花糸の先端の葯は2つに分かれています。子房は3室に分かれており、子房から伸びる雌蕊花柱は紫色です。(2012年9月6日撮影)。

☆花序の下の方で花が終わったものは、果実ができ始めています。ツルボの果実は蒴果で、熟すると裂開して黒い種子が散布されます。蒴果(さくか)とは、乾果(乾燥果)で裂開する果実のことです。(2013年8月22日撮影)。

☆ツルボ(蔓穂)の名は、球根の外皮をとると、つるりとした坊主頭に似ているので、「ツルボウズ」からツルボになった説などがあるようです。また、「ツルイイボ(蔓飯粒穂)」が略されてツルボになったという説がありました。「ツル(蔓)」は長く連なることや長く伸びることを表す言葉、「イイ(飯粒)」は飯粒(めしつぶ)で「イイボ(飯粒穂)」は飯粒状のものが花穂を作っていることだそうです。「ツルイイボ(蔓飯粒穂)」が「ツルイボ」になり、そしてツルボ(蔓穂)になったという説です。(2016年8月15日撮影)。


☆ツルボの別名はサンダイガサ(参内傘)で、公家が内裏に参内するときに従者に持たせた長い柄がある傘をたたんだ形に、ツルボの花序の形が似ているため名づけられたそうです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[山野草] カテゴリの最新記事
-
キツネノカミソリの花が咲き始めました。… 2023.07.31 コメント(2)
-
花の終わりの時期のタカオスミレ。春のス… 2023.04.08
-
キジョランの花、初めて出合ったシオデの… 2022.07.31 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.