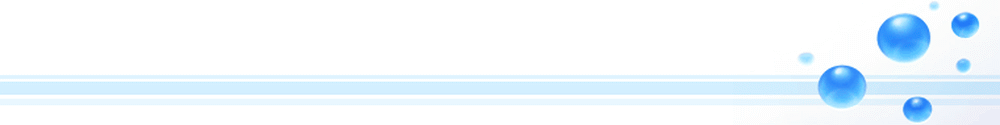其の二十~三十七
「るろうに剣心小説(連載3)設定」
必ず上記設定、特に注意事項にご了承頂けた方のみ本編をお読み下さるようお願い致します。
『いとけない君の願い事』目次
『いとけない君の願い事』
其の二十「昼過ぎの街」
昼過ぎの街を、剣心は歩く。橋を渡る。弥彦と初めて会った橋。薫が死んだと、弥彦がうつむいていたという橋。弥彦はあの夜ここで、何を思っていただろう。薫がいない道場に、誰もいない道場に、独り帰る十の子供。暗い夜。初めてその人と会った場所でうつむいて……。
泣いていたのだろう、と、剣心は思った。当然だ。それでも、一人きりになるまで、我慢していたのだろう。そして泣くときも、声を押し殺し、震える肩を必死で止めようと頑張ったのだろう。
『なんで弥彦君はあんなに涙こらえてるんですか!』
新市の言葉が突き刺さる。
弥彦は平気なわけではない。泣くのを我慢しているだけだったのか。
『泣くことを絶対に許していないんですか!?』
もちろん、そんなわけはない。ただ、間接的に、そうしてしまっていたとしたら。
泣かなくて当然だと、そういう風に接してしまったから。
『弥彦君は怖いと言いませんでしたよ!』
あんなに強くなった弥彦が、それでも今、集英組に怯えている。
怖いと言わなくても、いろいろなことが本当は……怖かったのだろうか。
弥彦に対する認識が、一瞬で変わった気がした。
今回のことでもやもやしていた、見落としていた重大なことを、今やっと見つけた気がした。
どんなに剣が強くても、心が強くても、関係ない。弥彦が数え年十の子供であるのは、まぎれもない事実――
とたんに、今までのことが雪崩のように、疑問となって押し寄せる。
京都での闘い後、褒めてあげただろうか。縁との戦いは? 鯨波のときは? 済まぬ、さみしかっただろうと、辛かっただろうと、独りにして済まなかったと、抱きしめてあげただろうか。いや、そんなことは一度もなかった。何故なら、弥彦はそれが平気なのだと思っていたし、望んでいたと思ったし、当たり前だと思っていたから。弥彦は、子供扱いされるのを極度に嫌い、一人前と認めればうれしがったから。それは、弥彦がそうありたかったから、なりたい自分に近づけたことへの喜びだったには違いない。けれどそうあるためには、どれくらいの苦しみと引き替えであったのだろう。どれだけの気持ちに耐えてきたのだろう。あるいは殺してしまったのだろう。きっとそれは、見当もつかないほど大きい。
そういえば……自分が十の頃は? まだ死闘を経験したことなど、あるわけもなかった。
弥彦は、どんなに怖かっただろう。どんなに、辛かっただろう。怖いに決まっている。褒めてもらいたかったに……抱きしめてもらいたかったに、決まっていたのに……。
神谷家へ帰った剣心は、その足で道場へ向かう。今度は躊躇せず、ガラリと戸を開けた。うずくまっていた弥彦は、恐怖の目で顔を上げ、ビクッとする。気付かれたことに、激しく動揺したのだろう。うろたえた表情で、座ったまま後ずさりする。着物は、吐いたものでどろどろに汚れている。床にも、たくさん流れて……。それに気付き、弥彦はガクガク震え出す。
「ごめ……」
はぁはぁと苦しげに息をしながら、小さく泣きそうな声であやまり、弥彦は懐から布きれを取り出す。
剣心は、あわてて床を拭こうとする弥彦の手をそっとつかみ、首を振った。剣心を見上げる、吐いた床の上にペタンと座り、袴も着物も汚れている――その弥彦を剣心は躊躇することなく、抱きしめた。弥彦はほんのわずかに目を見ひらき、剣心……と漏らしたが、息ばかり漏れて声にならなかった。剣心は何も言わずに、弥彦をただぎゅっと抱きしめていた。弥彦は訳が分からないまま、体を固くしたまま、けれど涙が一筋、頬を伝い流れ落ちた。
其の二十一「黄色い葉」
それから、弥彦を診療所の恵に預けると、剣心は薫と左之助を道場の居間へ呼び、今日気付いた考えを話した。
「確かにねぇ……こないだやった着物見て、俺も思ったんだ。アイツはまだガキなんだって。いくら強ぇからって、死闘を任せたりしてたのは、なんかなぁってな……」
左之助は、片手で頬杖をつき、ため息をつく。
「確かにそうだけど……でもあの子が怖がったところって、本当に見たことがないの……」
「それは多分、薫殿が女の人だからでござるよ。男が女の前で泣いたり怖がったりするわけにはいかないと、男の子は思うものでござるからな。まして弥彦は、ああいう性格でござるし……」
薫は、ハッとする。そうして考えてみれば、自分が泣いているとき代わりに頑張ってくれた弥彦を、いくらでも思い出すことが出来る。もしあのとき、本当は必死で恐怖と涙を我慢していたのだとしたら……。薫の目から、涙がにじむ。
「泣くなって、嬢ちゃん。過ぎちまったものは仕方ねぇ」
「そうでござるよ。大事なのはこれからでござる。これからのことを、ちゃんと皆で考えるでござるよ」
剣心は、そっと薫の涙を拭った。薫は、うん……と、うなずいた。
その日は、三人で弥彦を診療所へ迎えに行った。恵から診察の結果を聞き、薬をもらい、剣心は弥彦をおぶって帰った。食べられなくてふらふらの弥彦を、もう、歩かせたりはしなかった。弥彦は、おそるおそる、剣心の背中に体を預けていた。そうして、ぱらぱらと黄色い葉が落ちる銀杏並木を歩き、皆で帰った。薫は弥彦のために、りんごをすりつぶして食べやすいようにし、飯もご飯ではなくお粥にした。左之助は、その間座るのも辛そうな弥彦を、膝に乗せ抱いてやっていた。風呂もちゃんと剣心がいれてやった。今日からは三人が交代で一緒に寝ると、剣心は弥彦に告げた。
その夜は、剣心が弥彦のとなりに布団を敷き、一緒に寝た。弥彦は、警戒するように布団を頭からかぶる。けれどやがて、浅くはあるが眠りについたようであるのを見届けると、剣心は弥彦の頭をなで、自らも眠った。
けれど、その沈黙は、一刻も経たないうちにやぶられた。
「…いたい……」
うわごとのように、弥彦はつぶやく。剣心がそっと覗き込むと、弥彦はひどくうなされていた。
「痛い……痛いよぉ……」
涙をこぼしながら、あえぐように息をする。頬が赤い。そっと触ると、熱をおびていた。
「うっ……く……っ、いた…い……よぉ……」
剣心がたまらず抱きしめると、意識は夢の中のまま、弥彦は剣心の寝間着をぎゅっとつかみ、痛い痛いと泣き続けた。集英組で折檻される夢を見ているに違いない。
毎晩、独りで泣かせていた。大事なのはこれからと言った剣心が、この夜、どれだけ後悔しただろう。
其の二十二「二通の手紙」
剣心たちが弥彦に、ちゃんと子供として接するようになってからも、症状は変わらなかった。笑わないし、ほとんど喋らない。夜泣きがひどく、昼間も突然震えて吐くことが多い。このころから剣心たちは、深刻に原因を探ろうと必死になっていた。けれど、震えたとき、吐いたとき、どうしたのかと聞けばますます怖がるばかり。本当に困っていた。ただ一つ微かな回復があったとすれば、今まで麻痺していたような感情を、少しだけ取り戻してきたことだ。笑うことはないが、夜泣きのときなど、そのとき目が覚めてもそのまま泣き続けることが多くなった。今までの弥彦なら、とたんに涙を呑み込もうと必死だっただろうに。泣くのを止められないのは、夢うつつで感情の抑えがきかないせいもあるが、かたくなに閉ざされていた意識が少しだけ解きほぐされてきたのだろうと、恵は言った。
そんなある日、恵は往診のときに、由太郎からの手紙を持ってきた。恵は弥彦の病を調べるために、由太郎の父を通して、由太郎のかかりつけ医に意見を聞いていたのだ。しかしそれが、由太郎に知られてしまった。由太郎の父は、手紙で恵にあやまってきたという。
由太郎からの手紙は二通あった。一通は、弥彦が発症したばかりの頃の手紙、もう一通はその次の手紙だった。恵は、一通目が着たとき、弥彦の精神状態を考え初めは隠していた。が、少し感情の回復が見られた弥彦を見て、二通目が着たこともあり今ならば……と、思いきって持ってきたそうだ。
弥彦はそれを受け取ると、独り部屋にこもった。
弥彦は重い体を鏡台に預け、一通目の手紙を開く。そこにはたった一行だけ。馬鹿やろう、と書かれていた。弥彦はうつろな表情のまま、二通目を開く。また、馬鹿やろう、と書かれていた。けれど、今度は続きがあった。『ふざけんな』 また続く。『俺を困らせるんじゃねぇ』 うつろだった弥彦の目が、ほんの少しだけ眼差しを変える。最後の一行。『弥彦、早く元気になれ』
由太郎の父は、手紙にこう書いてきたという。由太郎は、二通目の手紙を、泣きながら書いていたと。
ふいに弥彦は、思い出す。まだ冬の終わりだったのに、太陽が強烈に降り注いでいた気がしたあの頃。まぶしかったあの頃。由太郎と一緒に、未来を夢見た。それはとても遠い場所だったけれど。けれど確かにあって、きらきらと輝いていた。強くなっていくことが、とてもうれしかった。憧れを追いかけることが、とても幸せだった。由太郎が独逸へ行ってしまってからも、それをするのは無意識のうちに心の中で由太郎と一緒だった。あの頃は確かに必死だったけれど、それでも明日は昨日よりより良いだろうと、そうあるように頑張った。明日はきっといい日だと、疑いもなく信じてた。けれど、今は……。
「由太郎……、俺、未来が見えない……!」
弥彦は鏡台につっぷし、堰を切ったように泣き出した。
其の二十三「同じ境遇」
その頃恵は、道場の居間に剣心たちと向かい座っていた。縁側の向こうに見える紅葉の葉は、もうほとんど落ちていた。
恵は、由太郎の主治医を通して学んだ知識を、剣心たちに話していく。
「心の病というのはね、弱い子がなるというものではないらしいの。むしろ弥彦君のように、普段立派にしている子がなる例も多いらしいわ」
三人がうなずくと、恵は今度は、症状について語り始める。
「まず、突然震えて吐く症状。あれは、過去に起きた強烈な出来事が、突然頭の中によみがえる症状なの。頭の中と言っても、本人にとっては実際その場に戻されて再体験しているのと同じ状態に思えるらしいわ。弥彦君の場合は、急に意識が飛んで、集英組に折檻された場面に引き戻されるの。だから、怖くて震えたり、受けつけなくて吐いたり、耐えきれなくて気を失ったりするのね」
剣心、薫、左之助は、恵の話を真剣に聞く。
「次に、木刀を持てない訳。これも同じような理由よ。集英組の折檻で一番多く使われたのが、恐らく木刀のはず。だから恐怖で、体が受けつけないの。発症の頃、あなたが木刀で攻撃すると言ったときその症状が起きたのも、木刀で打ち付けられるのが怖かったから……」
薫は、湯呑みを包むように両手で持ち、少しうつむく。
「ただ、何故怖いのに無理矢理木刀を持とうと道場にこもるのか、分からないけれど……」
「弥彦の、剣術にかける思いは、すごく強いでござるから……」
剣心の言葉に、考えつつもうなずき、恵は続ける。
「夜泣きも、症状の一つ。いつも集英組の悪夢を見ている……。表情が乏しくなったのも、笑わなくなったのも、過剰に怯えるのも、そして未来像の喪失も……すべて心の病のせい……」
でも、と、恵は少しだけ表情を和らげた。
「最近、感情は少しだけ回復してきている……。笑ったり怒ったりはないけれど、夜泣きで起きたとき泣き続けているのは良い傾向よ。みんなの、弥彦君に対する接し方や行動が、気持ちとなり伝わって、弥彦君が少し安心してきたからだと思うわ」
三人は、少し表情を曇らせる。本来なら、もっと早くそうしてやるべきだった。
「だから、今が好機よ。弥彦君の口から、何故集英組に怯えるようになったのか、聞き出すの。確かに自分からは怖くて話したがらないから難しいけれど、怯えないように、安心させてあげれば、どうにか話してくれると思うの」
そこが、最大の山場だという。原因さえつかめてしまえば、後はその原因を解消させてあげるだけだ。
「あと、自分と同じ境遇の人に対して申し訳なくなり、なんとかしてあげたいという気持ちも表れるらしいわ。もしそれらしき症状に気付いたら、それは弥彦君の境遇ということだから……」
そこまで言って、恵はハッと口をつぐむ。
「どうしたってぇんだ」
左之助が、恵の顔を覗き込む。
「実は……恥ずかしい話なのだけれど……」
恵はしばらく言いづらそうにしていたが、茶を一口すすると、続きを語り始めた。
「弥彦君に、言ったの。剣さんたちと家族である君が、うらやましいって……」
それはみんなに心を開いてもらいたくて言ったことだが、本心でもあったのだと、恵は決まり悪そうに目をそらした。が、やがてまた皆の方を向く。
「そうしたら弥彦君、一生懸命に言ってくれたわ。恵は家族だって。みんな恵を大切に思ってくれてるって。うれしかったわ……けれど……」
それがもし症状の一つなら。弥彦にとって剣心や薫は家族ではなく。弥彦は今も独りだと思っていることになる。
其の二十四「細い腕」
弥彦は、道場での行いを続けていた。剣心と薫は、それだけは止めなかった。いや、止めることが出来なかった。何故なら、二人は剣を持つ者だったから。剣を握れないことが、どれだけ辛いか知っていたから。
けれど、左之助は違った。いつも通り、震える体で木刀を睨む弥彦のそばに座り、静かに言った。
「なぁ……こんなこと、もうやめろよ……。今から、そんな強くならなくても、いーからよ。な?」
弥彦は、左之助を見つめた。そんな風に誰かをしっかりと見ることは、久しぶりだった。けれど弥彦は、すぐに目をそらし、うつむくと、弱々しく首を振った。木刀のそばに戻ろうとした弥彦の腕を、左之助は荒々しくつかむ。
「なにも病気んときに、無理するこたねぇだろ? 治れば、お前ならまたいくらでも強くなれるんだからよ」
励ますつもりで言った。けれど、つかんだ細い腕から伝わってきたのは、震えだった。
「……なんで俺を見て怯えんだよ……」
左之助の、弥彦の腕をつかむ力が強くなる。
「いい加減にしろよてめぇ……!」
左之助の怒鳴り声に、弥彦はのけぞるように身体をそらせ、そのままペタンとしりもちをついた。思わず手を離すと、震えながら、縮こまり、頭を抱えている。左之助はハッとした。
「……悪ぃ」
左之助は、再び弥彦に手を伸ばす。弥彦は、ビクッとする。
「何もしねぇから……。ぶたねぇから……。大丈夫だから……」
低く告げ、そっと弥彦の腕をどける。着物の袖で隠れていた弥彦の目に、涙がたまっていた。怯えの中に、悲しい色が混じった目をしていた。
其の二十五「静かな午後」
季節は、いつの間にか冬を迎えていた。雪が降った。弥彦はそれを、縁側の柱に寄りかかり、独りぼんやり眺めていた。
ガタガタ震えているのは、常におびている熱のせいだろうか。寒いせいだろうか。いや、それだけでなく……。
静かな午後。紅葉の木は葉をなくし、枝には雪が積もる。雪は、しんしんと降り続く。弥彦の意識はまた、集英組での中にいた。こごえる雪の日も、凍てつく吹雪の日も、スリに行かされた。かじかむ手で、財布をスッた。傷だらけの体で。腹を空かせた体で。時に病気の体で。しくじって、スッた相手に気を失うまで殴りつけられたこともあった。鉄の棒で、骨が折れるまで叩かれたこともあった。何度も、死にかけた。このまま死んでしまえたら良かった――
ハッと弥彦は、現実に引き戻された。
このまま死んでしまえたら――
『もう、苦しまなくてすむ』
”だけど……剣心も薫も左之助も、優しくしてくれるよ……”
『それでもお前はまだ、昔のあの日々が怖くてたまらないんだろう』
”早く治りたいよ。けど、治らないのはお前のせいだ”
『なんでだよ』
”お前は恵の言うことを全然聞かない。子供に戻ろうとしない。俺はお前なんだって認めない”
『けど……』
”あのときの剣心の手を、取らない……”
『今更、遅いよ……』
”そうだ。もう遅い。けれど……”
『もう一度手を差し伸べてくれたなら、今度こそ……』
”その手をつかむことが出来るのか?”
『分からない……』
”俺は、すごく怖いよ……”
『お前は甘いことばかり言うくせに、本当は剣心たちを信じていないからな』
”……それが事実だと、思うだけだよ……”
『だから結局、もう一つの怖さが消えない。いつか……』
”いつかを待つのは、怖くてもう耐えられない”
『もう……終わりにしよう……』
「弥彦っ!」
真白い雪の上に、小刀がさくりと落ちた。赤い血が少し、まわりを染めた。
「なにやってんのっ!?」
薫に小刀を奪われた弥彦は、呆然と、手首から滴る赤い血を見ていた。
「自分が何をしてたか、分かっているの!?」
激しく肩を揺すられる。弥彦は、ゆっくりと首を振る。
「……覚えて、ないの……?」
微かに、うなずく。薫の手から、徐々に力が抜けていく。
薫は、すぐに薬箱を持ってくるからと、走っていってしまった。
弥彦は、意識がはっきりしないまま、ぼんやりと流れる血を眺める。
「なんか……落ち着く……」
薫は、包帯を巻きながら、泣いていた。
耐えきれないように、嗚咽していた。
何故、と、何度も独り繰り返した。
其の二十六「手近な布」
”薫を泣かせてしまった……”
『心配してくれたわけじゃない。面倒を見るのが疲れたんだ』
”それでも、抱き付いて泣いたら良かったんだ”
『そんなことしたら俺は――』
”どうせもう長くない。剣心がだまっちゃいねぇだろ”
『だからこそこれ以上薫に甘えたら、余計に剣心は――!』
”嫌だ怖い! そんなんなるくらいなら俺――”
『……なら、決心しろ……』
”……分かった。お前、最後まで俺の言うこと、聞いてくれなかったな……”
『……もう、行くぞ……』
半ば無理矢理布団に寝かせた弥彦を、ずっと見守っていた薫。ごめんね、ごめんね、と何度も繰り返し泣きながら、そのまま眠ってしまったのは薫の方だった。弥彦はふらりと起きあがり、手近な布を薫の肩にかけてやる。剣心がまだ買い物から帰ってきていないことを、気配で確認する。
「あやまるのは、俺の方だ……。ごめんな、薫。それから、ありがとう……」
弥彦は、薫を起こさないように、そっとそっと、薫に抱き付いた。
「薫のこと、本当は大好きだったよ……」
涙が、にじんだ。それを袖でぐしと拭うと、弥彦は寝間着そのままの格好で、神谷家を後にした。
静かな午後の街を、弥彦は独り、ふらふらと歩く。雪は静かに降り続いていた。弥彦の肩に、雪がはらりと落ちては、着物に染みこんでいった。着物に落ちた涙が、ゆっくりにじんでいくのに、似ていた。
小国診療所の窓から、そっと中をのぞいた。恵はこんな雪の日でも、忙しそうに患者を診ている。邪魔は出来ないと思った。
恵だけだった。表面上の立派な自分にではなく、心の中の子供な自分に話しかけてくれたのは。
さよなら、と、小さな声でつぶやき、去った。
其の二十七「突然の来訪者」
左之助は、突然の来訪者を、あわてて長屋に入れた。
「何やってんだよ弥彦! 傘もささねぇで! 独りできたのかオイ」
手ぬぐいで、荒く弥彦の頭を拭く左之助。
「歩いてきたのか!? なんて無茶すんだよ! 俺に用があるなら道場で待ってればいいだろが! これから行くところだったんだからよ」
左之助は今日、家に戻っていたのだ。ここのところ弥彦の世話で道場に泊まり込みだったが、長屋に住んでいる以上、たまには帰って所用を済ませなければならない。
「左之助に…怯えたわけじゃないんだ……」
弥彦は、手ぬぐいで隠れた顔のまま、小さな声で言った。けれど、どこか必死で伝えているような気がした。左之助は思わず手を止め、手ぬぐいをかき分け、弥彦の顔を覗き込む。
「そんなことを、わざわざ言いにきたのか?」
「ごめん……」
「そんな小せぇこと、俺がいつまでも気にするわけねぇだろう?」
左之助は、弥彦の頭に大きな手を乗せる。
「だから、そんな顔すんな……」
左之助は、そのまま弥彦の頭を引き寄せ、胸に押し当てた。左之助の胸に、弥彦はしばらく、静かに抱かれていた。心の中で、弥彦は語りかける。左之助、俺、あのとき、強くならなくてもいいって言われて、少しだけ心が楽になったよ。その言葉が、本心ではないって、分かってはいたけれど……。
左之助は、ふいに言う。
「戦いがあっても、お前はもう、闘わなくていいよ……。もう、闘わなくて、いい……」
それは左之助の、せいいっぱいの、労りだった。その気持ちは、弥彦の胸をいっぱいにさせた。うれしくて……。けれどそれ以上に、打ちひしがれた。左之助は、微かな、最後のよりどころであったのに。
やがて、左之助が道場に戻ろうと言うと、弥彦は首を振った。
「帰りは……剣心が……おぶってくれるんだ……」
「へ?」
「行きも……途中まで……連れてきてくれたんだけど……、一人で行きたいって……我が侭を言って……だから、濡れたんだ……傘、一本しか……なかったから……」
そうして、草履を履くと、弥彦は左之助を見上げた。
「弥彦……?」
「左之助……」
しばらく左之助を見つめていた弥彦だったが、やがてうつむき、静かに言った。
「ありがとう」
肩が、わずかに震えていた。
「や――」
「じゃあな……」
弥彦はすっと戸を閉めた。そうして静かに、涙をこぼした。
其の二十八「蜜柑味の金平糖」
弥彦は、おぼつかない足で、ぼんやり街を歩いた。雪が降り続く、白い街。家も木々も、空気さえも白くて。積もり始めた雪の上を歩いても、足音は吸い込まれ。ただ、小さなあしあとだけが続いていった。凍てつくような寒さなのに、その感覚はどこか遠いところにある。ただ、吐く息が白く繰り返し漏れるのを見ながら、今日はきっととても寒い日なのだろうと思った。
無意識のうちに向かった先は、あの橋の上だった。剣心と、薫と、初めて出会った橋。弥彦は、手すりに寄りかかり、流れる川を見下ろす。雪は降り続く。寝間着からのぞいた、手首の包帯にも、舞い降りてじんわりとけた。
どこにも行くところがなかった。行く気力も残ってなかった。ふいに、父上母上のところへ行こうかと思った。父上は、誇り高く生きることが出来なかった自分を、許してはくれないだろう。けれど母上なら、許してくれるかもしれない。無条件に、愛してくれたから。
夜になり、人気がなくなったら、行こうと思った。川の水は、雪より冷たいかもしれないけれど。それまで、思い出を並べて時を過ごそう。
一番最初の時。橋を渡る、赤い着物の剣客が見えた。その背中が、温かそうだった。だから思わず、スリとしては初歩技である当て身を使ってしまったのだ。その剣心の背中を、ずっと追いかけていくことになるなんて、そのときはまだ思いもしなかったけれど。
剣心にも、最後に会いたかったと思った。剣心は、絶望の世界にいた自分に、希望を与えてくれた人。とても大切な存在だった。けれど、それを抜きにしても、大好きだった。
優しい剣心。今朝、相変わらず飯を受けつけない自分に、何か食べたいものはないかと聞いてくれた。なんでも作ってやるからと、言ってくれた。ぼんやり思いつくままに、蜜柑味の金平糖が食べたいと、言ってみた。母上が、生活が苦しい中無理をして、一度だけ買ってくれた菓子だ。甘くて、とてもおいしかった。剣心は、金平糖は作れないでござるなぁと、済まなそうに笑った。それで蜜柑味の金平糖というのはどこに売っているのかと聞かれたが、もう店はつぶれたしそこにしか売っていなかったと答えた。本当は、昔母上と暮らしていた近くに今でもその店はあるのだが、ここからでは遠すぎる。けれど剣心のことだ。きっと嘘に気付いただろう。今は降り続くこの雪が解けて、明日晴れたら、蜜柑味ではなくても色とりどりの綺麗な金平糖を買ってきてくれるつもりだったのかもしれない。
剣心には、もう会えない。剣心はきっと、見抜くから。そうして、告げられる言葉が怖かった。とても怖くて、怖くて仕方なくて、だからもう会えない。
だから、優しいままの剣心を思い出に、行こう。
其の二十九「闇色の水」
辺りが暗くなってきた。雪は未だ、しんしんと降り続ける。先程から既に人気がない。忘れていた。この辺りは、わりと町外れなんだ。
それなら、もういいか。ここにいる意味は、一つも残っていない。
弥彦は、おそるおそる、身を乗り出した。闇で染まった、黒い川。そうだ、このまま、闇に吸い込まれてしまえばいい。なにもかも、もう忘れて……。かじかんで、既に感覚のない手で手すりをつかみ、もう少し体を乗り出す。どくどくと流れる、闇色の水。それなのに、移ったように見えたのは何故か、みんなの笑顔。その温かい輪の中に、幸せそうな自分がいる。
帰りたかった。本当は。けれどもう遅すぎる。他に行く場所もない。
弥彦は、さらに身を乗り出す。そのまま、下を見下ろしたまま、しばらくじっとしていた。やがて、弥彦は手すりを強くつかむ。
最後に、一つだけ賭けてみようと思った。それは、祈りにも似た、願いだった。振り返ったとき。もしも大好きな人が迎えに来てくれたなら。そうしたら。
ゆっくりと、振り向いた。
奇跡かと思った。
舞い散る雪の中で、ホッとしたような笑みを浮かべた剣心が、立っていた。
「良かった……。道場に帰ったらお主がいなくなっていた故、さがしに来たのでござるよ」
「けんし――」
その情景は、弥彦には、やけにゆっくりと見えた。馬車が、剣心の横を通り過ぎ、自分の横を通り過ぎていった。そのとき、車輪にはじき飛ばされた。手すりの隙間から、体が下へ落ちていく。それは本当は、一瞬の出来事だった。
其の三十「差し伸べられた手」
「弥彦――!!!」
頭の中が真っ白になった。
けれど、気がついたとき、弥彦は川に落ちる途中でとどまっていた。
橋を支える柱の出っ張りに、弥彦の襟の合わせは引っかかっていた。
弥彦は完全にぶらさがる格好になっていた。
けれど、体重の軽い弥彦であっても、襟の引っかかりは今にも外れそうで。
少しでも動いたら、真っ逆様に落ちる状態だった。
「弥彦!」
見上げると、剣心が、手を差し伸べてくれていた。
手を伸ばせば、ぎりぎり届く距離だ。
『もう一度手を差し伸べてくれたなら、今度こそ……』
「つかまれ! 弥彦!!」
”その手をつかむことが出来るのか?”
弥彦は、追いつめられた表情で、いやいやをするように首を振った。
「弥彦!!」
『分からない……』
”俺は、すごく怖いよ……”
『お前は甘いことばかり言うくせに、本当は剣心たちを信じていないからな』
”……それが事実だと、思うだけだよ……”
『だから結局、もう一つの怖さが消えない。いつか……』
”いつかを待つのは――”
「怖い……!」
恐怖の表情で、震える。
「大丈夫でござるよ。弥彦の手を、絶対離したりはしないでござるから」
「嘘だっ!」
剣心の目が、大きく見ひらかれる。
「いつか突きはなすくせに……!」
震える声で。
「結婚して子供が出来たら俺なんか邪魔なくせに……!」
涙声で。
「剣が振るえない俺なんていらないくせに!」
涙をぼろぼろこぼしながら。
感情を爆発させてしまってから、激しい震えがきた。ガクガクと、冷たい汗を流しながら、全身を震わせた。息が上手く吸えない。涙で視界がぼやける。
そうだと言われるのが怖かった。否定して欲しかった。けれど、否定されたところで何が救われるというのだろう。だってそれは、剣心の優しさなのだから。愛情とは、違うのだから。
いらないと言われるのが、怖かった。
それはきっと、剣心の手を振り払ってしまったあのときから――
其の三十一「十歳の子供」
まわりの者は皆、弥彦が子供だということを忘れてしまっていた。
あるいは気付いていても、弥彦なら平気と思ってしまっていた。
弥彦は十歳で死闘に立とうが、褒められなかろうが、抱きしめられなかろうが、それが当然の世界にいさせられた。
しかも存在理由が「神谷活心流一番門下生」と「剣心が見込んだ者」だったから、それを裏切るわけにはいかなかった。
何故なら、そうしなければ、居場所がなくなってしまうから。
あの日、橋の上で出会ったあのとき、剣心たちと弥彦が当然のように別れていったように。
拾われたのは、志の強さを見せて、剣心に見込まれたから。
薫は、門下生として、住み込みを許した。
そうして、剣心と約束をした。強くなるという、約束を。
神谷活心流門下生。未来をになう剣士。
神谷活心流道場を再建させ次の世へ伝える後継者。日本一の剣客が振るう不殺の剣と信念の跡継ぎ。
二つの大切な役目を背負った、破ることの出来ない、約束を。
その意味も知らずに、してしまった。
まわりの期待はどんどん大きくなり、裏切るには、あまりにも重くなっていく。
答えるしかなかった。ここにいるためには。
だから、強く在らねばならなかった。甘える子供でいることは、許されなかった。立派でなくてはならなかった。怖いなんて言えるわけがなかった。だけど本当は怖かった。今だって怖い。守って欲しかった。抱き付いて、泣いて、怖いよって言って、当然のように守って欲しかった。
けれど、自分には、許されない。これからも、どんなに怖くても、苦しくても、悲しくても、平気なふりをしなければならない。できるだろうか。今までは、気を張って、張りつめて、夢中で、必死で、がむしゃらで……けれど、ゆるんでしまった。ふと、平和なことに気付いて、一度心がゆるんでしまった。本当はまだ、集英組の連中でさえ、怖いのに。「あんなの敵じゃない」と、簡単に倒して見せなければならないのだ。出来るだろうか。自分に……。
そうして弥彦はあの日、平和な午後の縁側で、初めて吐いて気を失った。残酷な過去に、引き戻されて……。
そうして剣を握れなくなった。
そうして存在価値を失った。
そうして出ていかなければならなくなった。
其の三十二「雪と流れ星」
「弥彦! とにかく手を……!」
剣心は、腕をめいっぱい伸ばす。けれど、弥彦の体がすりぬけた手すりも、大人の剣心には抜けることが出来ない。これ以上前にのめり込むことは無理だった。
「見抜いたんだろ? 薫は俺のせいで追いつめられて限界だって……!」
震えが止まらないまま、残る力の、ありったけの声で怒鳴る。責めるような口調は、本当は自分に対してだろうか。剣心にとって、最愛の薫を追いつめた。今まで、いらなくても置いてくれていた。けれどもう、限界だろう。いつか、を、今日にしてしまったのは自分だ。剣心は「目に映る弱い子供」を助けてくれるだろう。橋の上に引き上げてくれるだろう。けれどその後に、きっと告げる。元気でな、と。その言葉の中に、さよなら、と、いらない、と、出ていけ、という意味を込めて。
きっと剣心は、懸命に良い処を探してくれるだろう。良い養子先を探してくれるだろう。けれど、もう二度と、自分と会おうとはしないだろう。薫にも、会わせないだろう。左之助は、わざわざ会いに来たりしないだろう。
「お前なんかいらないってことを、言いにきたんだろ!?」
「弥彦――!」
弥彦の体が、ほんの少し下がる。ずる…と、引っかかりが落ちてきたせいだ。
「なんで大丈夫なんて言って笑うんだよ! なんで手なんか差し伸べるんだよ! そういうの偽善っていうんだよ!」
「早く手を――!」
「五月蠅い!」
剣心は、差し伸べてくれた手を、引っ込めた。
”もう一度手を差し伸べてくれたなら、今度こそ……”
最後の希望が、消えていった。
弥彦の体が、またずるりと下がる。
そのとき、ガラガラと崩れる音が、静かな橋に響いた。
そっと見上げると、剣心が逆刃刀で手すりを斬った音だった。
そこから剣心は、半身を乗り出して、さらに手を伸ばした。
「ばっ……やめろ剣心落ちるっ!」
「大丈夫だから――」
剣心はさらに前のめりになる。こわれそうな両脇の手すりにつかまるわけにはいかず、地面の床を片手でつかみ体重を支えている。常人にはとても出来ない。それをやってのける剣心も、そうそう長く続くわけがない。
「馬鹿剣心っ! お前には薫がいる! 生まれてくる子供だって!」
弥彦は必死で叫ぶ。
「同情や偽善で大切な人たちを悲しませるのか!? それとも何? それがお前の信念だから? そのせいで薫が自害でもしたらどーすんだよ!? 薫はお前がいなきゃ生きていけねーんだぞ!」
「弥…彦……!」
剣心はそれでも、体を乗り出してくる。さすがに、きついらしい。苦しげに、左手で地面をつかむ。それで全体重を支えているのだから、痛々しい。
「もうやめろって!!」
泣き叫んで見上げたそのとき――
舞い落ちる雪と一緒に、降ってきたのは、たくさんの流れ星――
其の三十三「あたたかな光景」
流れ星に見えたそれは、金平糖だった。
剣心の懐からのぞいた袋は、確かに母上と行った、あの店の袋だった。
蜜柑味の金平糖が、袋から、ぽろりぽろりと落ちてきて。
外灯を浴びて、流れ星に見えたんだ。
剣心は、雪の降る中、あんなに遠い街まで行ってくれたのだろうか。
蜜柑味の金平糖を、探してくれたのだろうか。
血の繋がらない、もういらないはずの、子供のために――
流れ星が落ちる前に、願い事をしよう。
それは弥彦の中に眠っていた、純粋な子供の心。
「………………ように」
小さな、小さな声で、願い事をした。
ずるりと襟が抜け、弥彦の体が落ちていった。
「弥彦――!!!」
剣心が、めいっぱいに手を伸ばす。
それは綺麗で、あたたかな光景だった。夢みたいだった。
雪が舞い、星が降り、その中で差し伸べてくれる手があった。
『ねぇ弥彦君。それは君にとって、とても怖いことなのかもしれない』
うん。とても怖いよ、恵。
『だけど、ちゃんと受けとめて。ね……』
母上。どうか、受けとめられる勇気を下さい。
自分がまだ、子供なのだという事実を。
落ちる刹那、差し伸べてくれた剣心の手を、ぎゅっとつかんだ。
其の三十四「願った事」
橋の上で、二人はしばらく座り込み、息を切らしていた。
少しして、まだはぁはぁしている弥彦の頬を、剣心はぱちんとぶった。
弥彦は思わず、剣心を見上げた。
それは、ただ何かを伝えるためだけの、儀式みたいな感じだった。剣心は、睨んでいる風もなく、ただじっと弥彦を見つめていた。だから、怖くはなかった。頬も、そんなに痛くはなかった。ただ、心が痛かった。集英組の連中に殴られたときより、何十倍も、痛かった。ぶたれた理由が、十分に分かっていたから。そして、愛情が、こもっていたから。
「剣心……」
弥彦は、震える手で、そっと剣心の袖をつかむ。
今なら、きっと言える。流れ星に願い事をした、純粋な自分である今なら。本当の自分に、きっと戻れる。
「俺はまだ……子供で……怖いことも……分からないことも……一人では出来ないことも……たくさんあって……」
弥彦の肩が震える。今まで懸命に、かたくなに守ってきた「大人であろうとした自分」が、それを認めることは、とても怖くて辛いことなのだろう。けれど、弱い自分を認めようと思った。そうでないと、先に進むことが出来ないと思ったから。
「大人と対等なつもりだった……。俺すごいうぬぼれてた……。だけど俺、今日道場を出て、どうしたらいいか全然分からなかった……。俺は……一人じゃ……生きていけない……」
声が震える。
「集英組の連中が……今でも怖い……。忘れられなくて、剣が握れない……。こんな弱い子供な俺は……いらないって……言われるのかと……思ってた……」
いつの間にか、涙声。
「今まで、信じることが出来なくて、ごめん」
弥彦の、剣心の袖を握りしめる力が、ぎゅっとなった。
「弥彦」
剣心は、弥彦の頭をぽんと叩いた。
「流れ星に、何をお願いしたのでござるか?」
弥彦は、答えようとして……目にいっぱいの涙をためた。
「弥彦?」
「また……みんなと一緒に……、仲良くご飯が食べられますように……って……」
涙が頬を伝う。
「かっ…、叶う…かなぁ……っ、うっ…うっく……っ」
弥彦は、袖で涙を拭う。それでも涙はあとからあふれ、止まらない。剣心は、袋にたった一つだけ残っていた金平糖を、弥彦の口に入れてやった。それはとても甘くて、ほっとして、心をとかしてしまいそうで……。
「叶うでござるよ。今晩すぐに。だから一緒に帰ろうな」
剣心が優しく笑いかけると、弥彦はうなずき、肩をひくっと震わせた。抱きしめてやると、弥彦はどうしようもなくなり、思いきり声を上げて泣いた。剣心にぎゅっとしがみつき。剣心は弥彦を抱きながら、うれしそうな、済まなそうな顔をした。
其の三十五「夢の中」
雪降る中を、剣心におぶさり、帰る。包帯から少し血がにじみ、白い寝間着にもついていた。生きていることを、実感した。それはとても幸せなことなのだと、知った。
道場に帰ると、薫が笑顔で迎えてくれた。昼間、泣き疲れて眠った間に弥彦がいなくなっていて、血の気がひいた。帰ってきた剣心にあわてて事情を話すと、剣心はすぐに飛び出していった。少し出ただけで帰ってくるかもしれないからと、薫は道場に残された。心配で、いても立ってもいられなかったところに、夕方左之助がやってきた。剣心に連れられて長屋に来たという話を聞いて、剣心が見つけたのだと思い、安心して待っていたらしかった。
仕事を終えた恵も、往診に来てくれた。
皆で一緒に夕飯を食べた。弥彦はまだ笑うことは出来なかったけれど。頬を紅潮させて。炊きたてのご飯を、一口だけ食べることが出来た。
弥彦は、疲れたのだろう。夕飯が済むと、うつらうつらし始めた。左之助が布団へ連れていき、添い寝をしてやった。弥彦はずっと、左之助の胸に顔をうずめていた。袖をぎゅっとつかんで離さなかった。いつも寝るときには警戒して、独り布団をかぶっていただけに、驚いた。けれど左之助は、弥彦が眠るまで、抱いてやっていた。
「左之助……」
寝たのかと思った頃、静かに弥彦はつぶやいた。
「どした? 眠れねぇのか?」
抱いたまま、弥彦の顔を覗き込む。
「俺が怯えたのは、左之助が怒鳴ったのが怖かったからじゃなくって……。お前は強くなれるって言われて……、期待に答えられなかったらって考えたら……怖くなったからなんだ……」
「そうか……」
「それと……」
嫌われると思ったから、と、消え入りそうな声で言った。
「馬鹿」
左之助が優しく返すと、弥彦は再び左之助の胸に顔をうずめた。
やがて弥彦がすぅと眠ったのを確認すると、その頭をぽんぽん叩き、布団をかけ直した。そっと行こうとして、袖をつかまれた手がそのままなのに、気がついた。
「さの…すけ……」
寝言だろうか。目をつむったまま、小さくつぶやく弥彦。左之助は、弥彦の顔を覗き込む。
「たすけ……て……」
閉じたまぶたから、涙を頬に伝わせる弥彦。
「……またいつもの夢、見てんのか?」
けれど、少しだけ違う気がした。激しく怯え、震え、痛がり、ひどく泣く、いつもの夢の弥彦は、独りぼっちなのだろうと思う。けれど今日は、夢の中に、左之助がいるらしいのだ。
「けん…しん……」
剣心もいるようだ。
「こわい……よ……」
夢の中で、助けを求める弥彦。
「大丈夫。大丈夫だ。ちゃんと守ってやるから。だから安心して眠んな」
背中を何度も、なでてやった。
其の三十六「泣いている声」
その後弥彦はまたひどい夜泣きを起こしたが、やっとちゃんと眠ると、左之助は皆のところへ戻った。剣心たちは、居間で待っていた。もう真夜中だった。
左之助が弥彦の様子を話した後、今度は剣心が、今日の出来事を皆に話して聞かせた。皆に愛情を注いでもらっていることを、信じていなかった弥彦。分からせるために、剣心は弥彦の頬を叩いたという。
「けれど、弥彦をそんな風に思わせていたのは、拙者の落ち度でござろうな……」
剣心の目は、こころなしか伏し目がちになる。
「拙者にとって、弥彦は憧れの存在だったから……。強くて、真っ直ぐで、決して間違えたりしない。その生き様は、拙者の比ではない。精神的な強さは初めから拙者を越えていたし、剣の強さもすぐに並の大人以上になった。だから平気で過酷なことをさせた。当然のようにそれを見ていた。心のどこかで泣いている声に、気付いてもやれずに……」
そう――手を差し伸べたのは初めだけ。集英組から助けたあのときだけ。小さな手で、けれど力強く振り払われたあのとき、本気で見くびってしまったと思った。観柳邸での戦いに連れていった。燕を狙う士族崩れに木刀の嵐を食らっていたときも、助けなかった。真剣を持つ男――長岡幹雄と一対一で戦わせた。それでも、そのときまでは、まだぎりぎり助ける用意があった。剣の腕が、まだ未熟だと思っていたから。だが、その感覚も、だんだん麻痺していく。雷十太に人質に取られたとき、助けようともしなかった。京都にいたっては、志々雄兵と戦って欲しいと命じたのは自分だった。それが十本刀と戦うことになったと知ったのは後からだったが、無事と聞いて良かったと思っただけだった。血だらけの乙和戦では、信念を預けて戦えと命じた。鯨波戦で弥彦を瀕死にさせたのは、自分が落人群にいたから。そうして四神戦では、当然のようにその一人を弥彦に任せた。十の子供が、棍を頭から叩きつけられ、腹に食らわされ、血を吐いた。平気で見ていた。そしてどのときも、それが当たり前でありこれからも進む道だという態度をとった。
弥彦を追いつめたのは自分だ――なのに弥彦は、金平糖を買ってきてやった、たったそれだけで、心を許してくれた。頬を叩いた。大切だと思う気持ちを伝えたくて。みんなが大事に思っているのに、信じなかった弥彦に、分かってもらいたくて。けれどその原因は自分にも多々あったのだから、弥彦は反抗しても良かったはずなのだ。けれど、弥彦は責めるどころか、自分が悪かったのだと、そればかり反省し、ひどく泣いた。あんなに苦しめて、悲しませて、追いつめたのに――
「剣心……」
気がつくと、薫が剣心の手を取り、心配そうにその顔を覗き込んでいた。
「だって……剣心が考えすぎるのは……悪い癖だから……」
薫は、言い訳するように小さな声でいい、顔を赤らめそっと手を引っ込めた。左之助と恵もいたので、恥ずかしかったようだ。
「済まぬ、薫殿……。薫殿は、ちゃんと弥彦が子供であることを、忘れずにいたでござるな……。それは当たり前のことなのかもしれないが、拙者にとってはとてもすごいことだと思えるでござるよ」
剣心は優しく笑ったが、薫は、ううんと首を振る。
「私、弥彦には怒ってばかりだったもの……。生意気なところばかりが目について……」
「そりゃあ当然でぇ嬢ちゃん。アイツは実際生意気だからな」
左之助は、冗談めかして笑った後、ふっと真顔になる。
「俺が、一番いけねぇこと言っちまった……」
ふうと、ため息をつき。
「弥彦に、剣心と嬢ちゃんは近いうちに結婚してガキが出来んなぁって。お前はお邪魔虫だねぇって。冗談のつもりで。からかうように何度も言っちまった。アイツは、笑ってた。それでいいんだって、いつでも出ていけるよう準備はもう出来てるんだって、早く幸せになって欲しいって、笑ってた。だから、気付かなかった。いざとなりゃあ俺の長屋に住ませりゃいいと、軽く考えてた。しかも養ってやるとか考えなかった。俺は狭い東京から出て、どっか行くのもいいねぇなんて考えてた。弥彦なら自分の食いぶちくらい自分で稼げると思ったし。それくらいアイツは完璧な大人だと思ってた。けど実際アイツは今日、行くところすら分からなかったんだ……」
もう一度、ふぅと息を吐き。なんとなく皆は恵を見る。
「結局、恵殿だけでござったな。弥彦に、完全に十の子供として接していたのは」
恵は、ただ静かに笑っていた。恵は、大人の女性だった。子供の弥彦に気付いたのは、恵が本当に大人だからだろうと、皆は思った。
其の三十七「本当の自分」
とにもかくにも、弥彦が何故集英組に怯えるようになったのか、その理由がやっと分かった。今までばらばらだったことが、一つに組まれていくように。弥彦は、本当の自分は子供で、怖いことも一人では出来ないこともたくさんあると言った。そして、いらないと言われるのが怖かったと言った。今まで、それらを必死で我慢してきたのだろう。以前恵が言った、平和になる前の弥彦が緊張状態にあったというのは、こういうことだったのだ。小さな体で、懸命に闘い、必要な存在であるように必死で……。
だから、きっかけは、平和になって気がゆるんだから。戦いの日々から解放され、強く立派に振る舞っていた緊張状態が、一時的にゆるんだから。抑えていたさみしさや、悲しさや、苦しみがあふれすぎて、恐怖となり、集英組の記憶を揺り起こしてしまったのだろう。
恐怖は、弥彦から剣を奪い、存在意義を見いだせなくなった弥彦を悲しみが襲い、悲しみは捨てられるのだという恐怖となり、どうにか剣を取り戻そうと木刀を握ろうとするのだけれど、いっそのことと恐怖の根元である組を倒しに行こうとするのだけれど、耐えられないほど残酷な過去の記憶が襲い、拒否反応で吐くばかりで、皆の重荷になっていくことで、いついらないと言われるだろうと、さらなる恐怖と悲しみを生んで……悪循環を繰り返し――病は悪化していったのだろう。
そして、病の根本的原因は、今までずっと追いつめたから――。
無意識にではあっても、追いつめていたのなら、これからは安心させてあげよう。剣の成長は、もっとゆっくりで良いのだと。怖いときやさみしいときは、泣いても良いのだと。無条件に、ここにいても良いのだと。みんな、大切に思っているのだと。なにもかも、伝えよう。言葉だけではなくて。そうして、みんなで弥彦を守り生きていこう。それは義務でも同情でも偽善でもなんでもない。弥彦は大切な家族なのだから。
前ページへ 次ページへ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…
- (2024-11-30 06:19:29)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…
- (2024-10-04 21:52:45)
-
-
-

- お勧めの本
- おきざりにした悲しみは [ 原田 宗典…
- (2024-11-30 11:19:53)
-
© Rakuten Group, Inc.