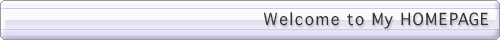Will Kemp Interview
ウィル・ケンプ「カー・マン」インタビュー2001年10月
An Interview with Will Kemp
by Ed Lippman
October 2001
「ダンス界のジェームス・ディーン、ウィル・ケンプ」
エド;何日か前にマシューにインタビューしたとき、彼はダンサーは踊るのがうまいやつより、演技がうまいやつを雇うね、と言ってたんだけど。それで君に聞いてみたいんだけど、「カー・マン」は(ダンスより)演技のほうが大事なのかな。
ウィル;「カー・マン」は特にね。マシューの趣味もあるんだけど、芝居の比重が大きいと思います。「白鳥の湖」は3人か4人の人物キャラクターしか出てこなかったから特に演技の面がこれほど重要というわけじゃなかった。振り付け的にも「白鳥の湖」はよりクラシック・バレエにつながるもので、僕にとっても主役の白鳥をやるには、バレエの技術が要求されました。「カー・マン」は登場人物のキャラクター付けがすごいんだ。どこから来たやつで、何て呼ばれていてどういう人間関係なのかとか決まってないやつは一人もいない。だから「カー・マン」では自分が誰で、どうしてそこにいるのか、考えなくてはならない。だから振り付けの多くも、自分がどんな人物像を演じているかによって違ってくる。つまり、こういうことになるんだ、まず人物像が先にありきでそれによってそいつはどういう動きをしてどうしてそんな行動するのかが決まるんだ。
エド;君にとっては「カー・マン」はクラシックバレエの作品とはどう違ったのかな?
ウィル;僕が純粋にクラシックバレエの作品といえるものを経験したのは、ロイヤルバレエ・オペラ学校での授業だけだったので、今より7、8年前のことになるかな。そこで大事なことは隣に並んでるやつと全く同じに見えるようにすることで、正しく拍子に合わせて正しく動くこと、個性的でありすぎてはいけないんだ。振り付け通りにやらなかったらたちまちアウトだ。僕の乏しいクラシックバレエの経験から言えばそこには正しいことと、間違ったことしかない。白黒はっきりしてるんだ。ところが僕らが今作り上げている最中の作品では、正しい正しくないという考え方はほとんど存在しない。つまり、自分の人物像にあったふうに演じれば、それは大概オーケーになるってこと。別の言い方をすれば、そんなガチガチの体制じゃないダンスカンパニーに居れば、どう演じるかについて何通りもの考え方が出来るということだ。ここ(AMP)では、ひどく間違ってさえいなければ、自分が作り上げたやりかたで演じていいんだ。
エド;「カー・マン」に比べれば、クラシック・バレエの作品を踊るほうが、君にとっては易しいことなのかな。
ウィル;どっちが難しくてどっちが易しい、っていうふうには僕は考えません。僕にとってここ(AMP)は天国です。クラシックのバレエ団にいたら、こんな作品や役柄にめぐりあうことはほとんどなかったろうし、自分についてこんなに学ぶということもなかったろうし。こんなことになってなかったろうし。クラシックバレエのカンパニーにいたら自分はこんなに成功できなかっただろうと思います。もっと難しかったでしょう。だからといってここでやってることが簡単だというわけではないんですけど。
(中略)
エド;「白鳥の湖」だけど、全く違うお話になっているよね。マシューが話してくれたんだけど、バリシニコフがリハーサルを見に来て、この物語の印象が未来永劫に変わってしまったと言ってたんだって。君にとってはどう?印象が変わってしまったのかな?
ウィル;もちろん。「白鳥の湖」はぼくが1995年にカンパニーに入って最初にやった作品なんだ。ロイヤルバレエ学校を出たてのほやほやでね、学校時代にすでに10何回もこの作品は見てたんだけど、実際によくわかったのはカンパニーでリハーサルを見てからだね。僕らは部屋でクラシック音楽を聴きながら、白鳥について、白鳥がほんとはどんなに力強い動物かってことを話し合った。マシューが白鳥役を男にした本当の理由は、白鳥の中に潜む男らしさや、攻撃性、力強さ、強大さ、それであっても優美な資質を失わないこと、などを引き出したかったからなんだ。全くもって、もっともなことだよ。
リハーサルのときを思い出すと、僕がクラシック音楽を目を閉じて聴いていて、目をあけるとそこは、白鳥を、攻撃的な力強い白鳥を表現するために飛び回っている野郎どもでいっぱいだった。これは本当にうまくいった。このやり方は本当に心を打ったし、音楽を「白鳥の湖」の真の意味合い、つまり白鳥と白鳥と王子との関係に結びつけるものだと思う。AMPの「白鳥の湖」では、明らかなことだけど、毎日同じことを繰り返し、同じような服装をして、同じように振舞わなくてはならない王子が、実は心の中では、自分自身から逃げ出して自由を得たいと思っているんだ。あげくの果てに王子は白鳥という力強く、圧倒的に自由な生き物にその願望を投影してしまった。AMPの「白鳥の湖」ではこれはまったくもってはっきりしていることだ。
伝統的な「白鳥の湖」ではいろんな要素があいまいにされているけれども。僕らの考え方がすっごく真実をついているということはもうずっと前の早い段階からわかっていたことだよ。
ほんとに興味深いのは、「白鳥の湖」の音楽こそが、驚くべきものであるということだ。情熱的で、実際に体を揺さぶられ、別世界へと運ばれていく。個人的にはぼくはめったに伝統版の「白鳥の湖」ではそうなることはないんだけど。僕らの「白鳥の湖」では、自分の思い入れのできる人物像を見るだけで、音楽を新たな形で聴き直して、宮殿へと、公園へと、誘われていくんだ。
エド; おっしゃることはよくわかります。それは僕もこないだ「ジゼル」(ABTのサンディエゴ公演)を見ながらずっと考えていたことなんだ。すばらしい作品なんだけど、音楽に比べて物語の方がお粗末だと感じるときもあるなと。
ウィル; つまりこういうことだよ。「白鳥の湖」のようなとんでもなくすばらしい音楽を聴くときには、一般的にいって人生で2回ぐらいはみんな聴いたことがある音楽なわけで。作品を見るときも、もう既に知っているものだったらいつも比較してしまうものだよね。舞台を見るときに、「これはオリジナルにはなかったよ。これはここだけの特別版だね。」となってしまう。観客に、今までに見た他のあらゆるヴァージョンを振り捨てて、この作品だけをいいと思ってついてきてくれるように仕向けないと、そうしないと、いつも観客は「これはオリジナルと違うよ!」となってしまい、それじゃ本当にお客をつかまえたとはいえない。お客は他に流れてしまう。
(ここで話がわき道にそれて、時には悪夢でもある映画の撮影についての話になった。その話を切り上げて、僕は自分のやったショーのおもしろい体験談を話し、ウィルは大いに気に入ってくれた。それはほんとにひどい体験だったけど、それでもその全ての過程が自分にとって特別なものだったのだ。ぼくはウィルにはそんな経験はないかと聞いてみた。)
ウィル;「白鳥の湖」が全くそんな感じだったよ。
(中略)
エド; このあいだ、AMPのレッスンの様子を半分ぐらい見学させてもらったんです。わたしは舞台でのあなたの動きに感銘受けていたので、まるであなたの内面にある何かが突き動かしているような動きにね。レッスンでさえも、あなたから目をそらすことが出来なかった。だからどうしても聞いてみたいんですけど、どうしてあなたは踊るのかな?
ウィル; んー、それは難しい問題だね、そこに純粋に個人的な何かを見出さない限り、どうしてそれを究めたいと思うだろう! それがすごく難しくなって、競争が激しくなれば、捜し求めてるものの本当の姿がだんだんわかってくる、それは自分自身に結び付けられる何かであり、そうして初めて、自分のものにすることができる。僕は子供の頃からそれを探し始めた。9歳頃まではダンスというものを知らなかったんだ。僕は感情的な性格で恥ずかしがり屋だったので人とコミュニケートするがいつも苦手だった。でも、今言ったような、自分の特別な場所、そこに集中できればコミュニケートできることがわかったんだ。そこにいれば気持ちよくて、すみずみまで完全に理解することが出来る場所だ。僕が正直な真の自分自身でいることを許してくれる。僕、なんかおかしいことを言ってるかな?
エド; いや、そんなことはないよ。
ウィル;つまり、自分をほんとの自分にするものをみつけるということです。(It’s about finding what really, really makes you you. )それを見つけたら、自分の中のその部分を大切に育て、絶対失わないようにすることです。
(中略)
エド;特に好きなダンサーとか、役のモデルにしてる人は?
ウィル;役のモデルとかは特にないけど、ぼくは素晴らしいダンサーといっしょに仕事する恩恵に浴しているので。特に「白鳥の湖」の初期の頃のね。アダム(クーパー)はほんとに素晴らしくて、彼から多くを学んだんだ。
エド;好きなダンス映画は?
ウィル;(ダンスを映画にするのはほんとに難しい)その中でも唯一そのエッセンスを捕らえることができたと思った映画は 子供だけど、何だと思う?「ビリー・エリオット(邦題;「リトル・ダンサー」)」だよ。僕は我慢して観ていたけど、しまいには我を忘れて怒っていた。「どうしてビリーはこんなに(がんばれるんだ)!」自分の子供時代を思い出すと。「ビリーはなんて賢い子なんだ!」こんな気持ちになるのはきっと僕だけだと思ったよ。僕にとってはそんな映画です。
エド;舞台上での最高の瞬間は?
ウィル;いろいろあるけど(中略)最近では「カーマン」の2幕でアンジェロが刑務所から戻ってくるところ。こんなぞっとするようなことが起こった。パートナーはエッタ・マーフィットだったけど、僕が体をねじって、彼女があとずさって僕を引きずる、というシーンなんだけど、彼女が3歩ぐらい下がったところで僕の体ごと倒れてしまった。そこの床に僕は死んだように寝ているシーンなので彼女は客の方に向かって僕の上に転がってきた。そしてあとの8分の3は即興さ。こんなことはありがたいことにめったに起こらないけど、同時に、とてもありうることで、お客がいるわけなので、間違ってしまったら、なんとかその分取り戻さなきゃいけない。舞台ではこんな貴重な出来事が山のようにあるから気を引き締めなきゃいけないんだよ。
エド;舞台上での最悪の瞬間とは?
ウィル;若い頃、14歳のときに経験したね。ぼくは1年の間、演じることも振付を覚えることも出来なかった。もうこんな先生と母のお決まりのジョークのネタになってしまったぐらい「頼むから、何ヶ月もスタジオでやったことを忘れないでね。」 僕はもちろん集中してやるべきことをやるんだけど、観客席の暗闇を目にすると途端に自分が何をやってたか忘れてしまい、勝手に自分でアドリブで踊ってしまうんだ。さも自信ありそうなふりで、飛び跳ねて、振付の途中からは自分流のステップで踊っていた。観ていた観客は「これはいいねえ」と思い、途中から「何だ、こりゃ?」と思ったに違いないよ。
play with= ~を軽視する、軽くあしらう
rigid= 厳格な、融通性のない
masculinity = 男らしさ
bloke= 英略式=guy 野郎
phenomenal= 驚くべき、並外れた
digress = 脱線する、わき道へそれる
sit through = sit out = 耐える、最後まで座っている
keep--on one’s toes = (人の)気を引き締める
a can of worms = 複雑で解決困難な問題
come home to = 完全に理解される 痛切に感じられる
まるでマシューのセリフを聞いてるみたい。あまり冗談も言わないし、まじめな人なのね、ウィルって。そして、頭いいよね。マシューワールドを完璧に理解し、言葉にすることが出来てる。
そしてウィルはまるで首藤さんのように、子供の頃からシャイで人とコミュニケートできなくて、唯一の“what really makes you you”が、真実の自分でいられる場所こそが、ダンスであったと告白している。うー感涙! そしてビリーエリオットに感情移入してしまう彼の姿。アラン・ビンセントなんか、ダンス始めたのは「女にもてそうだから~」なわけで、この違いに笑ってしまうね!
このインタビューのURL
ttp://www.criticaldance.com/amp-la2001/wkemp0110.html
(without top "h")
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ハロプロあれこれ
- ユニット名は ロージークロニクル
- (2024-06-17 09:28:40)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪筒井あやめ『のぎおび◢』S…
- (2024-06-18 06:54:45)
-
-
-

- 音楽のお仕事♪
- ダンカン林 2024年 6月~7月スケジュ…
- (2024-06-13 20:24:37)
-
© Rakuten Group, Inc.