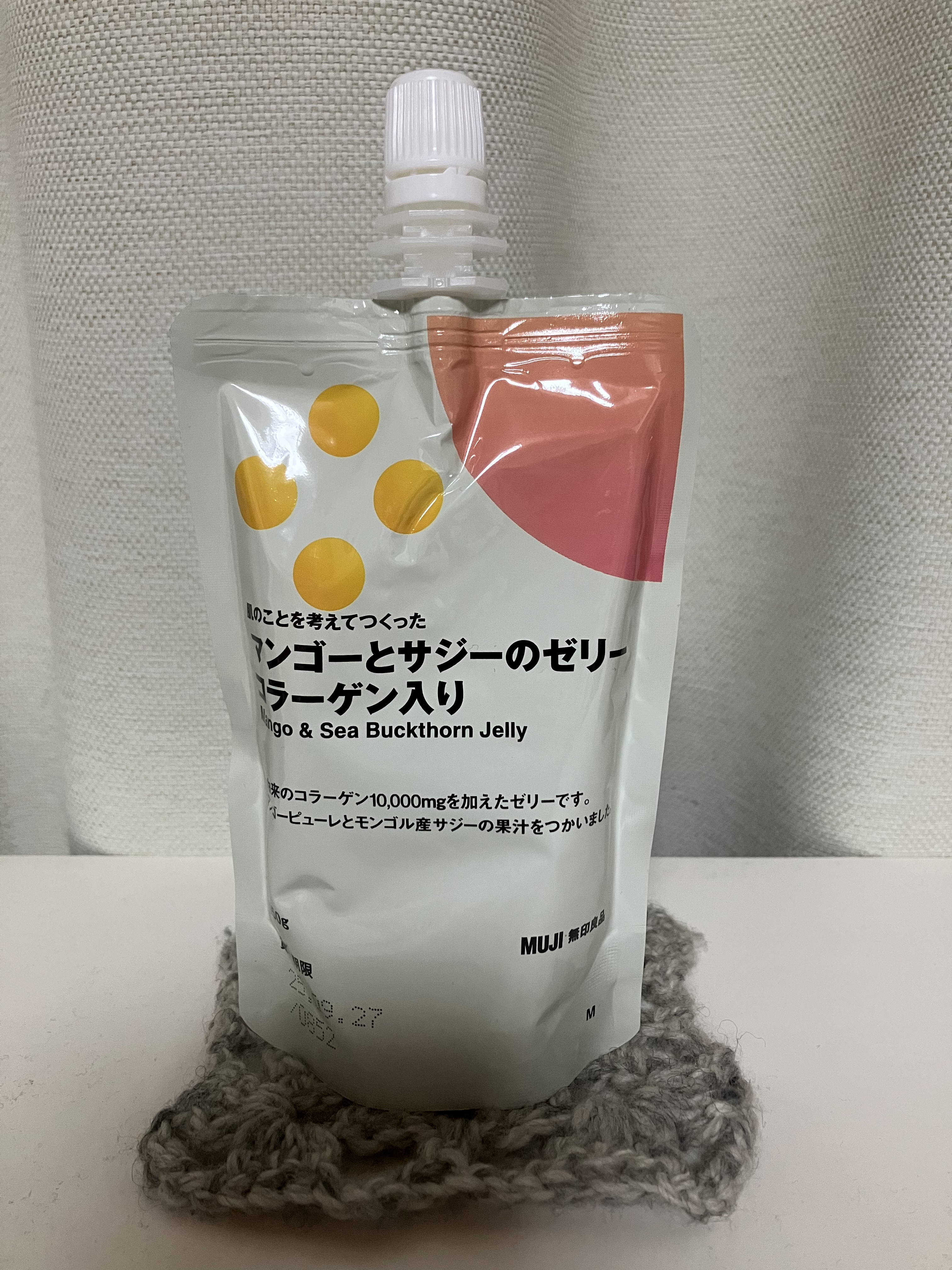雑誌に紹介していただきました。


ゼロから無農薬の米づくり
「大室自然農園」を営む大室一宏さん
広島県の山あいにある世羅郡世羅西町の農業、大室一宏さん(41)は、サラリーマン家庭に育ちながら、9年前に現在の土地に入植、「大室自然農園」として無農薬の米づくりを目指して奮闘を続けています。
大室さんを通して、農業にかける生産者の思いを聞きました。
在学中に出会った
農家の人に感動
大室さんは瀬戸内、広島県音戸町の生まれ。広島市内の県立高校を卒業後、同志社大学文学部に進みました。
大学では歴史を学びましたが、室内にこもって史料をひもとくというよりも、現場に出てフィールドワークをするのが好きというタイプで、民俗学の研究で地方を訪ね歩いていろいろと聞き書きをするうちに、農家への興味がわいてきたと言います。
考古学を専攻した関係で、遺跡のそばで生活をしながら発掘作業にかかわったこともありました。その時、発掘の手伝いに来ている地元の農家の人たちが、現場近くのありあわせの材料であっという間に仮設のトイレやかまどをこしらえるのを見て、びっくりしました。
作業の合間に、田んぼの話を生き生きと交わす農家の人たちの姿も、大室さんには「カッコイイ」と映りました。農家のお母さんたちには食事の世話をしてもらい、ふだんは朝食なしの学生生活でしたが、ご飯と味噌汁、お茶だけの朝ご飯がとてもおいしく感じられたといいます。
アラスカでハンド
メイドの家に驚く
やはり考古学の調査でアラスカに行った時には、大学の先生の自宅を訪れ、その先生から「この家は自分で建てた」と聞いて、また大きなショックを受けました。
ログハウス風のロフトのある三階建ての立派な建物でしたが、住む人が自分の家を建てるのは、アラスカでは珍しくなく、先生は「みんなそうしている」というのです。
手造りの家にあった白黒テレビや真空管を使っているようなオーディオは、大室さんの当時の学生生活から見ても粗末なものでしたが、かたや狭い四畳半でかび臭い水に我慢しながらの下宿生活と、かたやリスが駆け回るような森の中で家族と住む暮らしでは、「どっちがぜいたくなんだろう」と思ったと言います。
自然の中で家族一緒にシンプルに。「こういうのが本当の生活だなあ」と感じた大室さんでしたが、日本でそんな暮らしをするのは定年退職してからかなと漠然と考えていました。
山林3千坪を購入
自力で家を建てる
大学を卒業後、やはり田舎や農業へのあこがれから、東京にある出版社・農文協
(社団法人・農山漁村文化協会)に入社。関東一円を営業で訪れるかたわら、農家の生活をつぶさに見て回り、農業で生活していくことの厳しさなどを学びました。
それからは、大阪府内の市役所で、文化財の発掘調査にあたる教育委員会の嘱託技師を経て、広島市内の共同作業所の運営にかかわっていた時に、農業を始めることを決意しました。
ちょうど十年前に、縁があって現在地の山林三〇〇〇坪を購入することができ、当時、農業を学ぶために住んでいた山間部から毎日一時間をかけて通い、木の伐採から土地の造成までを行いました。
地元の新年会に顔を出した時に、「ジャングルジムでも造っているのか」とからかわれながらも、自力で掘っ立て小屋の母屋を建て、造成から半年近くがたった頃には何とか家族を呼び寄せて引っ越しを終え、苗づくりをスタートさせました。
ところが、その苗を植える田んぼはなかったのです。
苗はつくっても
「田んぼがない!」
田舎は後継者不足や高齢化で田んぼが余っている、だから新しく就農した人は歓迎されて田んぼもすぐに確保できて米づくりが始められる―そう一般には思われがちです。
しかし少なくとも大室さんの場合、現状は違いました。
いざ実際に農業を始めようとすると、よそから来た人間に貸してもらえるような田んぼはなく、あっても栽培には条件の悪い田んぼがちょこっとあるだけ。
なかなか田んぼが決まらない中、米づくりへの意欲と自信を芽生えさせていた大室さんは、意地になって五反分の苗をつくり始めました。
結局、地元で世話をしてくれた人が自分が受けていた中から五反分を提供してもらい、事無きを得ました。こうして最初の年は順調に米づくりができました。
大室さんによると、同町内では、定年退職した人が就農する例が多いので、休耕田や荒廃田はほとんどないそうです。逆に、田んぼをどんどん増やして大規模な農業をしたいという意欲がある人が多く、田んぼが不足しています。
近所の人「昔のきれいな
お米を思い出す」
大室さんは、地元では珍しい有機無農薬栽培の米農家。なぜ?という問いに対して、
「もともとは自分の子どもにちゃんとした食べものを食べさせたいと思い、自分でつくりたいというあこがれがありました。
わざわざ外からやって来て、ふつうの慣行農業をするくらいなら、しなくていい。
地元の人はそうは言わないですけど、先祖代々のこの土地の農家ではないということがずっとついて回るから、その中で僕にできることは何なのかといつも考えています。
人がやるよりは僕がやった方がいいというのは何なんだろうと。無農薬でっていうのはそうなんですよ。
(無農薬の米づくりは)
地元のほかの人たちよりも僕の方がやりやすい。(農業を)大規模でやろうというのは、僕が狙うことじゃないんです」。
ただ、大室さんが行っている米づくりに関心を寄せる地元の人は多いそうです。
「偉いねえ」と言う人から、「なんぼ儲かる?」と聞く人もいるようです。
大室さんのホームページでは、昨年の米づくりの様子が写真付きで紹介されています。
その中で、稲刈りのシーズンが来て田んぼを見回る大室さんに、近所のおばさん
が「きれいな米だ」と声をかけたことが書いてあります。
さらに続いてそのおばさんは「うちのおばあさんが、大室さんとこの米を見ていると、昔の本当のきれいな米を思い出すといつも言っています」と言い、
「僕にとっては最高のほめ言葉」と、大室さんを感激させました。
リスク回避のため
除草剤使う田も
現在、大室さんは全部で約一ヘクタールの田んぼで米づくりをしています。
基本的には無農薬栽培ですが、雑草が生えると稲の生育が悪くなり収量が極端に低下する危険性(リスク)があまりに大きく、実際に一昨年などは自家米の確保も難しいほど収量が落ち込んだこともあり、今では「リスク回避のため」除草剤を一回だけ使う田んぼもあります。
一般の農家の慣行農業に比べ、完全無農薬の場合は除草機を押すなどその四~五倍の労力がかかるといいます。
しかし、お米の値段にその差をそのまま反映させることは難しいのが現状です。
しかし一回だけ除草剤を使うとしたら、完全無農薬に比べて栽培の手間が格段に少なくなり、価格もそれほど高くはなくなります。
「(除草剤を使うのは)ある程度(自分に米づくりの)力がつくまではそれでもいいのではと考えています」と大室さん。
家族の生活がかかっているだけに、リスクの大きい完全無農薬にこだわりすぎるというのは、逆に農家としての未来をなくしかねません。
さらに田んぼの質という問題もあります。
同町の農業委員会は、お米がたくさんできやすい順に、上田、中田、下田と分類しています。大室さんの田んぼのある一帯は、構造改善(ほ場整備)が行われたにもかかわらず、中田です。
トラクターの歯が飛ぶほど田んぼには石が多く、「石の上に土が載っているだけ。ここは“ざる”ですよ」。
また、大室さんが“ざる”と呼んだ田んぼでお米をつくり始めて八年になる昨年の秋にはイノシシが現れ、田んぼの中で大立ち回りを演じました。しかも無農薬栽培をしていた田んぼの方で。その前年までは全くイノシシの被害がなかったのに、予期せぬ出来事でした。
自然相手の農業では、何が起きるかわかりません。
味噌づくりを広げ
情報発信も続ける
つくったお米は、自家米のほかは、農協に出荷せずすべて販売しています。
妻の美佐子さんと、中学一年の耕作君を頭に四人の子どもの六人家族で、一カ月で四〇キロ近くのお米を食べます。
種もみを水につけるところから始まり、さまざまな作業や手順、そして大小の苦労を経て収穫したお米を慈しむ気持ちは、もちろん人一倍。家族がご飯を残したりお米を粗末に扱うと「本気で腹が立つ」というのもうなずけます。
最近は味噌づくりにも力を入れており、自家製の麹と地元産大豆、五島の塩だけでつくる「父ちゃんの手前味噌」は「おいしい」と好評です。
「将来は味噌づくりを一つの事業にして、地域の雇用につなげることができれば」と夢を広げます。
十一月から翌年の五月にかけては、都会の人などを募って味噌づくり体験の催しを開いています。
決して順調でも平坦でもない、全くゼロから有機農家の歩みを始めた大室さんは、つい最近まで農業をやめようかと思っていたと打ち明けます。
でもここで自分ができることを考えていくうちに、味噌づくりを広げ、情報発信(「大室自然農園」のホームページはhttp://www.10chan.com)を続けていくといったことに力を入れていこうと決めました。
大志をいただきつつも無理をしない、そうした地に足のついた生き方が、まさに農業や米づくりには欠かせないことなのでしょう。それはもちろん、私たち一人ひとりの生き方にも通じるものがありそうです。
マクロビオテックマガジン 「むすび」 2004年6月(No537) 正食協会発行より。
© Rakuten Group, Inc.