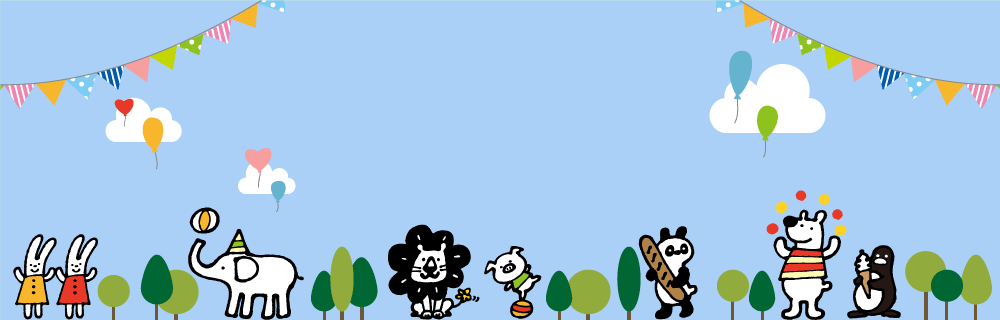第一次世界大戦(67)~(完)
第一次世界大戦と中国
英・仏等の連合国は、戦争が長引くに連れて、中国の参戦をも求めるようになります。しかし、日本政府は中国の参戦に強く反対しました。ドイツの山東における利権の継承を目指している日本にとって、中国が対ドイツ戦の戦勝国の一員として、講和会議に出席する事態は避けたかったのです。
こうして中国は、日本の反対によって、中立を維持することになりました。1916年6月に袁世凱が死去すると、政治の実権は段祺瑞に移ります。欧州の戦争はなおも続き、アジアに対するヨーロッパ列強の圧力が弱まってきていました。この機に中国南部では、戦争の継続を自成的な経済発展の好機と捉えて、道半ばに終った孫文の革命運動の再現としての国民革命を目指す国民党が勢いを増し、北京の中央政府は南からの革命の危機と、継続中の財政危機を克服するために、参戦と引き換えに借款を得ようと画策していました。
1917年2月に、アメリカがドイツと断交して、参戦への準備を進め始めた時、段祺瑞の政府も参戦に積極的になり、連合国に対して、義和団事件に関わる賠償金の支払い延期、関税引き上げの承認、その他財政上の支援を、参戦の代償として求めました。
この時、今まで中国の参戦に反対していた日本は、参戦支持に立場を変え、対独参戦に舵を切りつつあったアメリカが、逆に中国の参戦にブレーキをかける立場に回ったのです。
開戦から4年、ヨーロッパ列強の国力の疲弊は目立ち、彼等は太平洋や中国の事態に精力を割く余裕を失っていたのです。そのため、これら地域における日米両国の地位は、相対的に高まっていました。
日米両国は戦地を遠く離れた有利な条件の下で、ヨーロッパの戦争による特需を満喫して、海運、造船業などを中心に飛躍的な経済発展を続けて、世界経済に占める地位を大きく向上させていたのです。
ここに日米両国は、共に中国に狙いを定めた資本主義列強として、互いに譲らず相対峙するにいたっていたのです。
第一次世界大戦(68)
続・第一次世界大戦と中国
財政的に窮乏状態にあった中国政府に対し、日米両国は財政支援を通じて中国政府に対する影響力を強めようと競い合うことになりました。
中国駐在の米国公使館は、中国の参戦を自国に有利に運ぼうと、財政支援を約束し、本国へもその旨を申し送ったのですが、時あたかも米国内で参戦ムードが高まっていた時であったため、米国政府は公使館の動きにブレーキをかけ、中国への働きかけも急速に弱められたのです。
ヨーロッパの戦争へ介入する決意を固めた米国にとって、その第1の関心は、ドイツの打倒であり、そのための財政支援は連合国への援助ということになるのは、いわば当然の成行きでした。こうして大戦末期、中国を巡る情勢は、帝国主義の観点から見るとき、明らかに日本に有利な形勢になっていったのです。
1917年1月以降、西原借款の名で知られる日本の対中借款は2億円に達していました。大戦開戦時の借款は全部で1億円程度でしたから、急増振りが分かります。
日本が中国の参戦を支持するようになったのは、大戦の過程で圧倒的に有利な地歩を築くことができたことに依るものだったのです。西原借款は段祺瑞政府のによる、反国民革命路線での中国の武力統一を支援することで、中国における日本の優越的地位の確立を目指したものでした。しかし、借款の返済を保障する確実な担保は何もなく、日本国内にも強い批判を残すものでしたし、諸列強からは侵略政策だとして、強い非難を浴びましたが、日本の本格的な対外投資の最初のケースだったことも事実です。
しかし、日本の本格的な中国との接触が、中国の有識者を中心とする民衆の願いである、国民革命政府の樹立を妨げる、反革命勢力の支援と形をとったことは、日本にとっても、中国にとっても不幸なことであったと指摘せざるをえません。「日中両国の国民にとって不幸な過去の1時代」がまさに本格的な幕を開けようとしていたのです。
第一次世界大戦(69)
日本艦隊地中海へ
英・仏・露ら連合国からのたっての要請を断り続け、頑なに陸軍の欧州への派遣を拒みつづけた日本も、遂に1917年2月、駆逐艦よりなる第2特務艦隊を地中海に派遣するに至りました。
それは、イギリスの海上封鎖にあって、物資の欠乏に悩むドイツが、無制限潜水艦作戦に訴えてきたことに鑑み、地中海を通じて西部戦線に移送するインド兵、エジプト兵、モロッコ兵などの輸送船団の安全確保が大きな課題として浮上した時期でした。
兵士のみならず、インドやエジプト等の物産の輸送も深刻な問題となっていました。潜水艦の襲撃を避けるために、船団は常にジグザグのコースをとるため、必然的に航路は長くなります。その上、寄港地への出入りは最も潜水艦に狙われやすくなりますから、寄港回数は出きるだけ少なくする必要があったのです。
こうした戦争の新しい段階において、大輸送船団を護衛するには、太平洋という最も大きな海洋を航海するために、乗組員の生活条件の犠牲の上に、長い航続距離を達成した日本の駆逐艦の性能が、高く評価されたからでした。
ヨーロッパでの戦争を想定したため、航続距離に難のある英・仏の駆逐艦に比べ、日本の駆逐艦が断然歓迎され、重宝がられたのでした。
こうして、第2特務艦隊は、積極的にヨーロッパの戦争に協力することになったのです。勿論、日本政府は参加と引き換えに、山東省におけるドイツ権益の確保や、赤道以南のドイツ領南洋群島の割譲を認める秘密条約を結ぶことに成功していました。
後日談があります。日本との秘密条約の存在を知らされて、激怒したアメリカのウィルソンに対し、イギリスのロイド=ジョージは「当時は、日本の駆逐艦の援助を受けることが、どうしても必要だったのだ」と弁明していることです。ヨーロッパの長期戦は俄然日本有利の様相を呈していたのです。
第一次世界大戦(70)
講和会議とアジア問題
第一次大戦末期、中国や太平洋を巡る情勢は、日本に有利に展開していたことは、前回の記事に記しました。
しかし、ドイツが降伏して大戦が終了すると事情は変わってきます。イギリスとフランスは、日本に遠慮しなければならない事情がなくなり、自らの対中国利権の保全に何が有利かを、先ず考えるようになります。日本と満蒙を分け合う方針に転換していた帝政ロシアは、革命によって消滅してしまっています。そして欧州の戦争に全力を傾注して,アジアのことを横においていたアメリカは、日本を強く牽制するようになっていたのです。
さらに、ヨーロッパにおける戦争の長期化で、欧州列強の中国に対する圧力が大きく減じた結果、ようやく中国は経済発展のチャンスを掴み、江南地方を中心に民族資本が成長し、産業の近代化が進みました。こうした背景の下に、中国でも民族自決への期待が高まり、知識人を中心に民族の誇りと独立への意欲が大きく成長していたのです。
こうした情勢の変化で、英仏との秘密条約があったとしても、日本の要求がそのまま認められるわけもなく、講和会議の席では、1つ1つ審議する必要に迫られたのです。ドイツ領南洋群島については、イギリスがその赤道以南の領有を欲したため、赤道以北の領有を望む日本の要求も,委任統治という形で,比較的スンナリと認められました。
しかし、山東の利権については、中国代表の激しい抵抗もあり、アメリカも強硬に反対を続け、難航を極めたのですが、最終的には日本の要求が認められることになりました。この決定に抗議して中国代表はヴェルサイユ条約への調印を拒否して帰国してしまいます。事情を知った中国の知識人や学生は、激しい反日独立運動を繰り広げます。中国の革命と独立を目指す運動の新たな転換点となった五四運動は、こうして起こりました。
アメリカもまた議会の反対にあって、ヴェルサイユ条約に調印しませんでした。こうして、アメリカは中国を巡っての日本の最大のライヴァルとなって行くのです。
第一次世界大戦(71)
第一次世界大戦とインド
第一次世界大戦の項も終りが近づいてきました。最後にインドの関わりを取り上げたいと思います。
この大戦におけるインドの役割は、とかく我々が忘れがちになっている、第二次世界大戦における韓国というか、朝鮮半島の役割ととてもよく似ているからです。
先ずインドは、沢山の国民をイギリス軍の兵士として、ヨーロッパの戦場に送りました。しかしインド代表が、パリ講和会議に招かれることはありませんでした。それはインドがイギリス領インドとして、大英帝国の1部に組み入れられ、イギリス国王をインド皇帝に戴き、イギリスのインド総督が皇帝の代理として実権を振るう、100%イギリスの植民地になっていたからです。
開戦と同時に、国家主権を失っていたインドは、自動的に自分と関係のない戦争に巻きこまれていたのです。当時大英帝国最大の陸軍兵力を要するインド軍(将校の大部分はイギリス人、兵士の全てはインド人)は、すぐに2個師団を西部戦線に送ることになりました。この時のイギリス本国軍は4個師団でした。
以後、次々と増員を命じられ、最盛期には120万人が兵員としてヨーロッパへ送られていたのです。
第一次世界大戦(72)
第一次世界大戦のインド兵
第一次世界大戦におけるイギリスは、ヨーロッパの西部戦線のみではなく、自国の権益を守るために、バルカン半島、メソポタミア(現在のイラク)。エジプトなどにも、兵を派遣する必要がありました。
そのための兵士の供給がイギリス領のインド帝国軍(以下英印軍と略記)に求められたのです。この時イギリス政府は、協力の代償として戦後における自治権の賦与や、さらには独立まで仄めかしていたのです。
インドの知識層はこれを真に受け、積極的な協力を惜しまなかったのです。下士官や兵士が100万人、戦場その他での雑役に20万人というのが、およその比率でした。最下位カーストの出身者が雑役を担当したのです。そしてインド軍の費用は、そのほとんどがインドの負担でした。
戦争中のインドは、20世紀に入ってから大きな対英抗争の原因となったベンガル分割(この点は後述します)反対闘争の経験を封印してまで、イギリスの戦争に協力を惜しまなかったのです。
しかし、問題もありました。19世紀後半からのインドにおける反英闘争の主力がヒンドゥだったことに鑑み、インド兵の主力はイスラムの兵士だったのです。そして、当時のイスラムにとっては、オスマン帝国のスルタン=カリフこそ、教主であり、教父だったのです。そして、オスマン帝国は14年の11月に、ドイツ側に立って参戦したのです(既述)。
オスマン帝国の参戦と同時に、英印軍はシャットル・アラブ河の河口域を抑え、12月にはバスラを落とし、翌年にはバクダッド近くにまで進出しました。またエジプトに派遣された3万人近い部隊は、ヨーロッパとインド(アジア)とを結ぶ大動脈、スエズ運河防衛の大任を負っていたのです。
こうした矛盾を抱えた英印兵だったため、イスラム兵は対オスマン帝国との戦いを喜ばず、イギリスに対する不振の目を崩しませんでした。そのためイスラムの兵士をヨーロッパ戦線に送り、その地に派遣されていたヒンドウの兵士といれ替えることまでして、ようやく事無きを得たのでした。
こうした状況の中で、第一次世界大戦は終了を迎えたのです。革命ロシアの提起した民族自決のスローガンは、インド国民にとっても勇気を鼓舞される性格のものでした。
第一次世界大戦(73)
世界大戦直前のインド
ここで、大戦前のインドの様子を駆け足で概観しておきたいと思います。
イギリスのインド支配は、東インド会社に支配の一切を委ねるスタイルで行われていましたが、1857年~59年にかけての第1次インド独立戦争を経て、イギリス政府による直接統治に切りかえられました。
インドの最初の独立運動は、イギリスに依る力の鎮圧に敗れ去り、残虐な報復が行われました。やがて、力のみに頼る支配には限界のあることを知ったイギリスは、ナオロジーらの努力によって始められたインド国民会議の創設を認め、ヒンドゥとイスラムの宗教間対立を煽ることで、独立運動の狼煙が強まらないように、細心の注意を払っていました。
厳しい弾圧と、イスラム教徒とヒンドゥ教徒を対立させる策動で、しばらく大きな流れを見失っていたインドの反英闘争は、1905年に出されたベンガル分割法への怒りから、再び大きな流れを取り戻したのです。
この法は、東インドのベンガル地方を2つの州に分離するという法律でした。ベンガル地方の東部にはイスラム教徒が、西部にはヒンドゥ教徒が多いという事情を計算に入れて、相互の対立を煽り、対英独立運動の旗頭である、ベンガルの民族運動を弱めようという露骨な狙いを持っていました。
この露骨な分割統治政策に対し、インド各地は激しく反発しました。それでもベンガル分割を強行したイギリスに対する反発は、火に油を注いだかのように、インド各地に燃え広がっていったのです。
第一次世界大戦(74)
続 世界大戦直前のインド
イギリスのインド総督府が実施した、ベンガル分割法は、イスラムとヒンドゥの対立を煽る、「分割統治」政策の露骨な現れでした。
この分割に反対する声はインド各地で広がりましたは、総督府は分割を強行しました。抗議の集会、行進、断食などが次々に行われました。
こうした運動の中から、ベンガルを先頭に、先ずスワデーシー(イギリス商品の不買と国産品の奨励)運動が広がってゆきます。
そこでは「商売がダメになるということは、正義がどうのこうのよりも、商人の国イギリスの骨身に堪えるに違いない…」これが、スワデーシー運動の考え方でした。急進派のティラクは、ここにスワラージ(自ら治める)を加え、スワデーシー・スワラージ運動を展開すべきだと、熱弁をふるい、穏健派の支持をも獲得したのでした。
翌1906年には、運動は全インドに広まりました。狙いはベンガル分割法の取り消しのただ1点でした。スワラージ運動の展開のために、民族教育の推進という目標も掲げられました。追い詰められたイギリスは、ここでも再び、分割統治の原則に立ち帰り、少数派のイスラム教徒を優遇する事で、運動の分断を図ったのでした。
その後、今度は穏健派と急進派の対立を利用して、穏健派への譲歩を仄めかして、急進派との分断をはかったのです。大英帝国からの完全独立を希求する急進派に対し、穏健派は大英帝国に留まりながら、自治領となること(カナダ並の自治)を目指していたからです。
やがて国民会議派は、急進派と穏健派に分裂します。こうして、イギリスとの対立抗争によって、インドにはいくつもの分裂が生じたのですが、悪名高かったベンガル分割法そのものは、1911年のジョージ5世のインド訪問を記念して、取り消されたのでした。
紆余曲折はありましたが、インドの独立運動が、イギリスから勝ちとった最初の成果が、このベンガル分割法の撤廃だったのです。
第一次世界大戦(75)
大戦後のインド
1911年のベンガル分割法の撤廃後の小康状態の下で、イギリス領インドは、インド国民自身の意志とは無関係に、イギリスの意志で第一次世界大戦に巻き込まれました。そしてインドのインテリは、その戦争に積極的に参加しました。戦後における独立とか、自治権の賦与といった口約束を信じて…。
大戦中、イギリス経済の混乱から、インドへの綿布の輸入は途絶し、その結果インドの綿工業は大きく成長しました。ここにインドの民族資本も成長のきっかけを掴んだのです。
こうして経済的な足腰の強化を背景に、戦時中にアジアからアフリカにかけて広まった「民族自決」の声の高まりを受けて、インドの独立を求める声も大いに強まっていました。
イギリスもまた、インドに対する一定の譲歩の必要は感じていました。こうして戦争中の1917年、高級官僚の1部にインド人を登用する道を開き、インドにおいても高等文官試験(上級職国家公務員試験)を実施しました。イギリスから見れば、確かに譲歩でしたが、しかし、独立意識に目覚めたインドの人々にとっては、この譲歩は小さ過ぎました。
イギリスに協力的な親英的な団体のインド奉仕協会ですら、見かえりとしての自治権要求の旗を掲げ、この程度の譲歩では譲歩と言えないとソッポを向いたままでした。
こうした背景の下に、大戦末期にアメリカの参戦で勝利の感触を掴んだイギリス政府が、戦後のインド支配の構想としてまとめたのが、次ぎの3点でした。
(1)官吏ではないインド人を、州政府に参加させる道を開く
(2)高級官僚に,より多くのインド人を採用する
(3)州議会に、任命に依らない、より多くの被選挙議員を加える
しかし戦争末期の国際情勢の動きは、もっと急でした。イギリスはインドに自治政府の約束をせざるを得ないところに、追い詰められたのです。しかし、ここからがイギリスの巧妙な二枚腰ともいえる,うまさでありずるさでした。
第一次世界大戦(76)
大戦後のインド …2
イギリス政府のインド大臣モンタギュとインド総督チェムズファドの名を合わせて、モンファド改革と呼ばれ、両頭政治とも呼ばれる改革がここから始まったのです。
インドは戦勝国イギリスの植民地でしたから、インド問題はパリ講和会議の話題にはなりえません。いかにインドの人々が民族自決権を拠り所に、イギリスの独立を訴えても、それは聞き入れられないものでした。その点で、日本の支配からの独立を望む朝鮮の人々にとっても同じでした。中国にはドイツ利権が存在しましたが、インドや朝鮮は別だったのです。
モンファド改革は、1919年2月のインド統治法に繋がりました。ここでは(1)中央政府はイギリスが握ったままとする。(2)地方行政の1部をインド人に任せる。の2点です。教育・農業・地方自治などの管理はインド人の、選挙で選ばれた州議会に任せましょうというのです。
しかし、その奥にイギリスの狙いが隠されていました。元々地方分権の考え方は、19世紀の後半に反英闘争の過激化に手を焼いたイギリスが、地方の保守層に権力の1部を分与して、親英勢力による州政府を作ろうとしたところから、生まれた考え方でした。地方名望家層をイギリス支配の一端に組み込み、彼等に地方行政を預け、中央権力は従来通り維持しようという狙いがそこに、見え見えでした。
そして、他方では、悪名高いローラット法を制定して、独立運動は徹底的に弾圧しようとしたのです。この法は、裁判なしに被疑者を無期限に拘束出きるという、厳しい弾圧法でした。令状なしの逮捕、正規の裁判なしの禁固刑など、形振り構わぬ弾圧法でした。
1面で譲歩する姿勢を見せながら、他方であくまでインドを支配下に置きつづけようという、意志を露骨に提示したのでした。
インド統治法に1ヶ月遅れ、19年の3月に施行されたローラット法は、インド人の尊厳を無視するものでした、しかも大戦終了後の経済不振のただなかにありましたから、インド国内は騒然とした状況となり、不穏な情勢が急速に広まったのです。
新しいタイプの独立運動の指導者、ガンディーが登場したのは、丁度このような状況の時でした。彼の下で,運動の規模は何層倍にも大きくなっていったのです。
第一次世界大戦(77)
ガンジーの登場…1
ここで、マハトマ=ガンジー(1869~1948)について、触れておきたいと思います。
マハトマとは偉大なる魂を意味し、彼を敬愛するインド国民によって、つけられたガンジーへの尊称です。
ガンジーは、当時インドに多数存在した藩王国の宰相の子に生まれました。日本でいえば、さしづめ小藩の城代家老の息子といったところでしょうか。
ロンドンに留学して弁護士の資格を取り、その後曲折を経て、1893年南部アフリカの会社の顧問弁護士となります。
ここには、4万人以上のインド人が年季奉公人(日本で言えば、人身売買で売られ、自由のない奴隷的境遇の労働者ということになります)がおりました。
ガンジーはこうした年季奉公人に対する白人の侮蔑的待遇に心を痛め、その待遇改善運動のリーダーになります。彼が非暴力抵抗運動(サティヤーグラハ)という抵抗の方法を編み出すのは、この南部アフリカでの待遇改善運動の中だったのです。
第一次世界大戦(78)
ガンジーの登場…2
さて、ガンジーの運動は、断食、菜食主義、不殺生、非暴力などを組み合わせることで、力を得て行きました。
こうしたガンジーの理念が、最も良く反英の意志を示したのが、非暴力抵抗運動でした。
この運動は、暴力で立ち向かって来る権力に対して、非暴力で立ち向かうという、聞いただけでも身体に痛みが走りそうな運動です。行進の最中に棒で殴る蹴るの暴行を加える官憲に対し、無抵抗の人々が頭を割られ、血を流して倒れる傍らを、同じように無抵抗の人々が、同じように殴られ蹴られるために、我が身を晒して進むのです。この人々もまた倒れ、さらに後の人々が、また同じように暴力に対して、無抵抗の身を晒すのです。そして誰も退こうとはせずに、一指乱れぬ行動を続けるのです。
不気味さを感じた官憲が、暴力を揮い続けることが出来なくなるまで、この非暴力の抵抗運動(サティヤーグラハ)は続けられるのです。ガンジーの運動は、ある意味では,徹底的に身体に拘った運動でした。彼は言います。空腹とか、痛みとか、休みたいとか、性欲とか、人間の基本的な欲求を基礎として、考えたり行動したりする時には、あまり大きな間違いはしないものだと。
ガンジーは、こうした肉体的な感覚で、近代ヨーロッパ文明に対抗しようとしたのです。そして身体を拠点として、権力にまつわる問題を提起し始めたのでした。
そもそも、18世紀末以降の、とりわけ産業革命以降のイギリス人は、インド人並びにインド社会を、非理性的で暴力的で無知であり、疫病に満ちていると考えていました。それに対して、西欧社会やヨーロッパ人は、理性的かつ市民的であり、文明的で知的であると考えていたのです。
1905年当時のインド総督カーゾンが、カルカッタ大学の卒業式で、「真理の最高の理想は、だいたい西洋の概念であります」と演説していることを、考え合わせる時、ガンジーが非暴力運動を組織し、それにサティヤーグラハ(直訳は真理を保つ力)と名付けたことが、いかに西洋流に対して挑戦的であったか、お分かりいただけると思います。
第一次世界大戦(79)
ガンジーの登場…3
非暴力の運動で、南アフリカにおけるインド人年季労働者の待遇改善運動を勝利に導いたガンジーは、1915年大戦に参加させられていたインドに戻ります。
1度イギリスにわたり、そこからまたアフリカに戻って、インドに帰ったのです。このイギリスからアフリカに戻る船中で、一機に書き上げたのが、彼の代表作『ヒンドゥ・スワラージ』です。
彼は記します。
『インドはイギリスに政治的に支配されていることが問題なのではない。ただイギリスを追い払って、日露戦争後の日本のように富強の独立国を作り、強い軍隊を持つのが良いというのなら、それはイギリス人のいないイギリスを作るだけではないか。問題はそこにはない。真の問題は近代文明にあるのだ。』
『近代文明とは何か。……西洋近代の基本問題は、肉体的欲望を解放した事にある。無制限の生産を称え、無制限の消費を歓迎した。出来るだけ手足を使わずに遠くまで行く事、出来るだけ多くの種類の食べ物を食べること、出来るだけ多くの種類の衣服を着ること、こうした肉体的欲望を出来るだけ満足させる事を進歩だと考える思想では、真の独立はありえない。』
『我々が打ちたてるべきインドの自治とは、真の文明なのであり、真の文明とは、徳のありかという意味である。即ち真の文明とは、肉体的欲望の自制に基づくものでなければならない。人間は知っている技術を、必ずしも全て使うべきではない。その事を、インド古来の文明は教えている。』
アジアが近代文明に向おうという、まさにその時に、早くも近代文明を真っ向から批判する観点から、民族運動を展開しようとするのが、ガンジの辿りついた地平だったのです。
イギリス人が、インド人は我々に比べてずっと劣っているから、いろいろと教えてやろうという態度をとっていた時に、ガンジーはインドの文明の方が遥かに優位で、近代を超えているのだから、変わっていくのは、ヨーロッパ文明の方だと考えていたのです。
非暴力抵抗運動は、こうした思想の下で、考えられた運動だったのです。ガンジーは、この時点で西洋文明の問題点を見抜き、西洋の近代を超克する視点を、20世紀の早い段階で獲得していたのです。
第一次世界大戦(80)
ガンジーの登場…4
ガンジー以前にも、インドの独立運動を指導する優れたリーダーはキラ星の如くおりました。社会の混乱期には、平時に数倍する優れたリーダーが輩出されることは、中国でも、日本でも、アメリカでも、西欧でも洋の東西を問わず、全く同一のように思えます。
しかし、そうしたリーダー群像の中でも、ガンジーはまさに異色のリーダーでした。ガンジー以前のリーダーは、いずれもインド人の官僚を任命せよとか、植民地課税を軽減せよといった、政治権力に関する要求に力点をおいていました。それがガンジーにおいては、近代文明を批判する観点から民族運動が構築されていくのです。とてもユニークで先見性が際立っていました。
ガンジーはヒンドゥとの関係が悪化していたムスリム(イシラム教を信じる人々)に対しても、その権利を擁護し、彼等の運動を支持しました。ムスリムの指導者で、後にパキスタン建国の父と称えられるジンナーもまた、この時点ではガンジーと手を組むのです。
非暴力という抵抗運動が射落とすべき標的は、近代国家そのものでしたから、ムスリムもまた敵ではなく,共に行動すべき仲間だったのです。ガンジーの運動は,国家というものに対する根源的な批判でした。
それは近代国家の本質が、まさに暴力の独占にあったからです(日本における秀吉の刀狩は、その最もドラスティックな実現形態でした)。そしてそれを主権と称して、何物にも妨げられずに行使することが許されているのです。20世紀は、その最も露骨な暴力の時代でした。
この暴力志向の問題性は、非暴力による抵抗という、反暴力の運動を対置して見るとき、実に見事に暴き出す事が出来ます。叩かれても,叩かれたも、やり返さずに、ひたすら叩かれるために行進する人々の群、追い散らすことの出来ない集団に怯えるのは、暴力を振るう方なのです。ここには精神的優位がどちらにあるかを、明確に示されています。
こうしてガンジーの運動は、インドのみでなく、全世界で、そして宗主国イギリスにおいてさえ、人々の支持を獲得したのです。
第一次世界大戦後期にインドに戻ったガンジーは、大戦後の独立運動を指導する指導者として、期待されていたのです。
第一次世界大戦(81)
大戦後のインド…3
イギリスがインド統治法と共にローラット法を施行した時、インドの人々はインド統治を手放す意志を持たず、支配の継続にかけるイギリスの強い意志を感じ取りました。
穏健派の人々も、従前のような請願運動では事態の打開が出来ない事を感じ取りました。しかし、他方には弾圧法に強く反発して、力による独立に走りそうな暴力肯定派もおりました。
しかし、何といっても大切なのは、インド国民の力を分散せずに、分断統治を狙うイギリスの策謀に乗らず、統一した多数の運動とする事でした。そのためには、ようやく行動に踏み出そうとする穏健派が、安心してついてこられる運動であって、しかも暴力肯定派をも納得させる運動でなければなりません。
この難問に答え、非暴力の抗議行動として、インド人の独立運動を纏め上げたのがガンジーでした。ガンジーは大衆に信頼され、熱狂的な支持を受けました。インド統治法でイギリスは地方の政治をインド人に委ね、大きく中央の支配を続けようとしました。そのイギリスに対抗して,ガンジーは地方別の運動体を束ね、インド人の独立運動を全国化しました。
ガンジーはいかなる贅沢をも拒否して、自ら腰布の外には何も纏わず、鉄ブチめがねと木の下駄の外には何も持たず、菜食主義を貫くなど、徹底した簡素な生活を貫く事で、貧富の隔てなく、全インドの人々の尊敬と支持を集めたのです。貧しき民衆は、ガンジーの中に自分達の苦しみに共感を持って接してくれる、偽善のない指導者を感じ取りました。
そして武器を持たない民衆は、非協力や断食のような非暴力の闘争が、部分的とはいえ勝利を達成するのを見て、自分たちの団結による力を知って、無力感から解放されたのです。ガンジーによって、はじめて指導者と大衆の一体感が築かれ、両者の間の垣根は取り払われたのです。
そしてまた,ガンジーはロンドンで学んで弁護士資格を持つという、国際性をも身につけていました。ガンジーは,インドの現状を欧米の知識人に訴える術も知っていました。こうして彼は晩年のトルストイや、ロマン=ローラン、チャップリンなど、欧米世界に影響力を持つ知識人の支持を得て、欧米世界にインドの独立を働きかけるアンテナも持っていたのです。
第一次世界大戦(82)
大戦後のインド…4
それでは、ガンジーの非暴力・抵抗運動とはどのようなものだったのか。ガンジーは語ります。
「これは長い戦いになる。どんな危険に際しても、決して暴力を用いない、非暴力の戦いに徹すること。」
「運動の中で、生命・人格・財産に対する暴力は、絶対に慎まなければならない。その上で、インド政庁の悪法に従う事を拒否しよう。」
これがガンジーの訴えでした。それはスワデージー(イギリス商品の不買)から、議員自粛による議会ボイコット、村長らイギリスを利することしか知らない人達に、村長職の辞職を促します。官吏のボイコット、そして子弟の教育施設ボイコットと続きます。最後に税の不払いを宣言します。
運動は全インドへと広まり、農村部にまで広がりを見せました,驚いたインド政庁は、ガンジー逮捕に踏み切ります。1919年4月9日のことでした。敬愛するリーダーの逮捕を知って、激興した民衆は暴力に走ろうとしますが、獄中のガンジーに止められます。「暴力に訴えるなら、運動は中止する」と。
こうしてガンジーは、イギリスに対する非協力を貫き、ジリジリとイギリスを追い詰めて行くのです。一歩また一歩と。派手ではない、ガンジーの運動が大きな実をつけるには、なお時間が必要でしたが,ガンジーは一歩また一歩と,着実で堅実な歩みを続けていったのです。
こうして植民地インドでもイギリスの力は、少しづつ少しづつ,蝕まれていったのです。
第一次世界大戦に関する連載は、今回を持って終らせていただきます。
ご愛読有難うございました。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 京都 紅葉と食べ物語り 6 東福寺 …
- (2024-11-28 08:17:17)
-
-
-

- ニュース関連 (Journal)
- 懐の深い方だと思う。
- (2024-11-26 05:59:16)
-
-
-

- 楽天写真館
- クリスマス飾りとオキザリスと多肉ち…
- (2024-11-28 08:10:10)
-
© Rakuten Group, Inc.