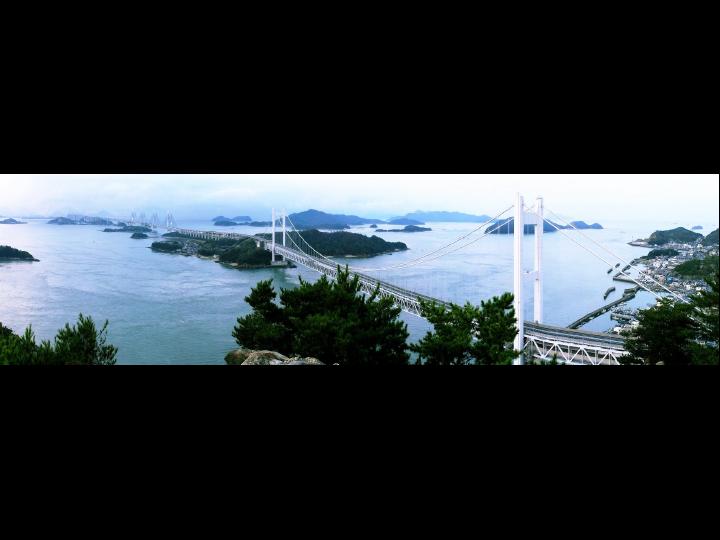創作秘話 「干潮 祭りの夜」
これを書いたのはもう四十年も前になる。
当時、全国青年祭なるものが国の行事で毎年東京を開催地として行われ、勤労青年の文化と運動を競うものがあった。
倉敷の青年たちはスポーツの分野では出場していたが、文化、演劇では出場、地方の審査で最優秀に輝くことが出来ずにいた。何回か挑戦したがそこまでの物は出来なかった。
どうにか東京で公演してプロの審査を受けたいものだと言う声があり、台本を依頼された。
私は倉敷を故郷としない、いわば外部者、其の目で倉敷をくまなく歩いた。
当時は「文化の町倉敷」とうたっていた。其の名前がこの町にふさわしいのかと言う思いがあった。この町は大原美術館を創設した大原家の権威は浸透していた。それに抗う事はゆるされないと言う不文律があった。また、美観地区は伝統建造物保存地区として保護されていた。それらは倉敷の文化の萌芽を邪魔していると思った。古いものだけに依存するのではなく、その上にこの町独特の新しい文化はどうしたら出来るだろうかと考えた。
この作品を書くに及んで早朝のまだ明けやらぬ倉敷の街を歩き、石橋に寝転んで暗さが溶けてゆく町の推移を確かめようとした。空気は漆黒から深い緑に変わりわずかずつ太陽が照らし出す頃には灰色になり現実の静けさを作っていた。石橋は露に濡れ、川面に垂れる柳は水面にしずくを落としていた。路地は入り組んだ家屋に繋がり、其の日の一日を告げていた。
私はこの倉敷の営みを五十分に切り取ることにした。
阿智神社の、秋の祭りの夜を書こうとした。この町の親子の在り方を倉敷ならではの物として書きたいと思った。父親と娘、其の誤解と錯覚により現われる断絶、それは果たしてなにを物語っているのか。行き違う心は何処に起因しているのか、大きな愛と言うものに対しての勘違いではなかろうか。
焼き物しか知らない父と、母に対しての愛情に飢えた娘、そして、父と母の愛の深さを見ることが出来なかった娘。
それは伝統と言う仕組みの中にうごめいて縛られている倉敷市民の姿を私は思った。ここに大きな隔たりがありはしないかと、親子の確執がすなわち今の倉敷ではないのか。其の理解は何かを作りそれを市民が盛り上げる、其の民度の高目る事に問題があるのではないのか。娘が父を理解しょうとしないと同じように相互の思惑の違いで発展の基礎をなくしていると感じた。
父は娘に、幼かった頃の姿を克明に語る。病に伏す母を思い倉敷川を一杯に流れる桜の花びらを母に見せようとて 牛乳瓶に入れて持ち帰り見せる。その行為は誠の娘が母を思う行いであり、その思いを持っていた頃に帰るように諭す。
古来家庭に受け継がれている茶器は使う人の心で色を変える。それは女が使い、その歴史を刻み次に託すという生き方なのだと訴える。この茶器、茶碗を、母が母の生き方で色を変えたものを今度はおまえが生きて感じた色に変える番なのだ、武骨な父は言う。
父の弟子と、其の恋人、娘の友達、母の幼馴染の友達、それらの人達が祭りの夜になにを感じなにを望んでいるかを書きすすめた。
「伝統だけの町、それにしがみ付いている人達、新しいものを何も生まない倉敷、こんな街にはうんざり、二度と帰らない。もう倉敷のことなど考えてやるものか」
そういい捨てる娘の友達の台詞に書き手は何を託したかは、みなさんの思いに任すしかない…。
この作品は、目黒公会堂で公演され、最優秀舞台美術賞、優秀演技賞を貰って帰倉したが・・・。
倉敷に帰って倉敷を批判したとして文句を言われたという落ちがついている…。
また、倉敷の青年たちに出会い、青年の純真な心に触れ、楽しい夢を見せてもらい、思い出を貰ったことに感謝をしている。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天ブックス
- 最強の詩 5 (ジャンプコミックス)…
- (2025-02-19 10:06:49)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【初めての“老い”を上手に生きる…
- (2025-02-19 00:00:25)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…
- (2024-09-12 00:00:14)
-
© Rakuten Group, Inc.