黒澤明アンソロジーR2
<黒澤明アンソロジーR2>図書館で『黒澤明、天才の苦悩と創造』と『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』という本を同時に借りたが・・・・
双方に『トラ・トラ・トラ!』から黒澤監督途中降板の真相が載っていて、興味深々でした♪
で、この際、黒澤明について集めてみました。
・『コピペと捏造』
・『黒澤明の世界』
・巨匠のメティエ・黒澤明
・黒澤エピソード満載の本
・『トラ・トラ・トラ!』から黒澤監督途中降板
・伝説の映画美術監督たち×種田陽平
・黒澤明 夢のあしあと

R2:『コピペと捏造』を追記
<『コピペと捏造』>
図書館で『コピペと捏造』という本を、手にしたのです。
どこまでコピペは許されるのか?、どうしたらパクリになるのか?・・・
わりと気になるので、この本を借りたのです。

第1部「あらゆる分野にはびこるコピペとパクリ」から黒澤さんの映画の例を、見てみましょう。
<黒澤明> p70~72
黒澤明監督の作品は海外でしばしば翻案されています。菊島隆三が脚本を書き、三船敏郎と仲代達也が出演した『用心棒』は、筆者の大好きな時代劇の傑作ですが、クリント・イーストウッドの初のマカロニ・ウェスタン『荒野の用心棒』に翻案されました。
二組のならずものの対立に巻き込まれた一匹狼が途中瀕死の目にあいますが、最後に奇想天外な復讐をとげるというストーリーはまったく同じです。この場合は『用心棒』を製作した東宝がイタリアの映画社に抗議しました。東宝によれば、イタリア側のプロデューサーから事後承諾を求める連絡があったことからも盗作の意図は明らかだとしています。
これについてはイタリアのジョリイ・フィルム社が侵害の事実を認め、日本・台湾・韓国での公開権を黒澤・菊島両氏が保有すること、ジョリイ社は賠償金を払うほか、配給利益の15%を両氏に支払うことで合意しました。
しかし、そもそも一匹狼がならずものたちの紛争に巻き込まれるというアイデアは、ダシール・ハメットの『血の収穫』が最初のように思われます。コンチネンタル探偵社のコンチネンタル・オブは対立する4組のならずものについたり離れたりしながら抗争を引き起こし、最後はならずものたちを全滅させます。
プロットのディテールはかない違いますが、黒澤明監督も『黒澤明語る』(福武書店)において、「『用心棒』の場合はハメットの『血の収穫』ですね」という聞き手・黒田真人の指摘にたいして、「そうそう、あれはそうですよ。ほんとは断らなければいけないぐらい使っているよね」と答えています。
しかし『血の収穫』を読んでみるとわかりますが、この小説は、一部銃撃戦のシーンなどもありますが、けっしてビジュアルではないと思います。黒澤監督の凄いところは、この小説をビジュアルで衝撃的なものに変えたところです。『黒澤明語る』では、映画の冒頭の有名な犬のシーンがどうして生れたかについても語られています。
また、同じ黒澤明監督、仲代達也主演の『天国と地獄』は推理小説作家エド・マクベインの『キングの身代金』の翻案ですが、映画のヤマとなる身代金の受け渡しの部分は脚本の菊島隆三のまったくの創作と語っています。
このプロットを作家三好徹が『乾いた季節』(河出書房新社)で盗用したと、映画を製作した東宝が発表しました。これに反発し三好は菊島隆三らを名誉毀損で逆告訴しました。さらに日本文芸家協会が、一方的な非難だと抗議しています。
この事件は最終的には和解したようですが、『乾いた季節』はそのままお蔵入りとなり、再版はされていないようです。
【コピペと捏造】

時実象一著、樹村房、2016年刊
<「BOOK」データベース>より
【目次】
序 どこまで許されるのか(パクリと創造の境界/パクリとパロディ、オマージュの違い ほか)/第1部 あらゆる分野にはびこるコピペとパクリ(歴史上に見られる盗用/小説に見られる盗用のパターン ほか)/第2部 バレないと困るパロディの世界(裁判になったパロディ事件/贋作もあるデザインのパロディ ほか)/第3部 怪しい捏造と改竄(結論ありきのテレビの捏造/ドキュメンタリーの捏造と真実の境界 ほか)/おわりに 厳しいだけではない寛容さを求めて(病理としてのコピペと捏造/むずかしいノンフィクションにおける判断 ほか)
<読む前の大使寸評>
どこまでコピペは許されるのか?、どうしたらパクリになるのか?・・・
わりと気になるので、この本を借りたのです。
rakuten コピペと捏造
<『黒澤明の世界』>
『黒澤明の世界』というムックを、ゲットしたのです。
【黒澤明の世界】
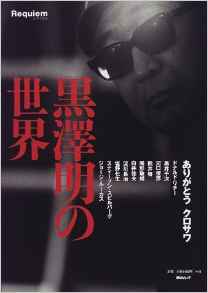
ムック、毎日新聞社、1998年刊
<「MARC」データベース>より
映画のカットや、撮影現場の写真、スタッフ、出演者等の裏話、スピルバーグや淀川長治らのメッセージなどを交えながら、黒沢明の仕事を年代順に整理し、作品の魅力、また監督の人物像を立体的に追う。
<大使寸評>
このムック本を2016年4月のひょうご大古本市で500円で買ったが、お買い得やで♪
Amazon 黒澤明の世界
<『巨匠のメティエ・黒澤明』>
図書館で『巨匠のメティエ・黒澤明』という本を手にしたのです。
黒澤天皇を支えたスタッフ、俳優たちへのインタビュー集であるが・・・まさに黒澤レジェンドという感があるのです。
【巨匠のメティエ・黒澤明】
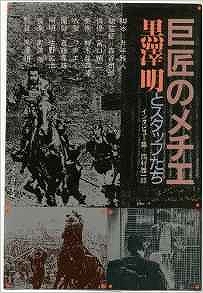
西村雄一郎著、フィルムア-ト社、1987年刊
<「BOOK」データベース>より
古書につき、データなし
<読む前の大使寸評>
黒澤天皇を支えたスタッフ、俳優たちへのインタビュー集であるが・・・まさに黒澤レジェンドという感があるのです。
rakuten 巨匠のメティエ・黒澤明
大使としては美術が気になるので、美術の村木与四郎さんのところを見てみました。
p150~162
<村木与四郎>
Q:『蜘蛛巣城』の城門にしても、とてつもなく大きいですものね。
村木:実際、あんな巨大な門なんかありませんよ。黒澤さん何しろ大きいのや、太いのが好きみたい(笑)。
Q:それは、黒澤さんの視点を考えるうえで面白い事実ですね。
村木:『乱』でも、酒を注ぐ白磁の銚子を型にとらせて、実際焼かせて作らせたんです。それも、実際のよりかなり大きくて、図太い(笑)。
Q:そうすると、黒澤作品の場合でも、ずいぶん、史実と異なることがあるんですか?
村木:あります。大いにあります。『用心棒』の宿場の道の幅も、スクリーンがワイドだから、あれほど、広くしなければならなかったのです。『赤ひげ』の小石川養生所のセットにしても、実際の患者の部屋は少ないんですが、本に合わせて、部屋数を多くして、自由に出入りできるようにしたのです。養生所の制服も、まるっきり創作したもので、ああいう御仕着せ的なものがあったわけじゃない。その後、テレビの『赤ひげ』で、あのままの形で着せてましたけどね。手術台のセットにしても、当時は油紙を敷いて、手術していたんですが、それだと絵的に面白くないから、あんな形になったんです。
Q:つまり、視覚的にいかに写るかが優先するわけですね。
村木:そうです。
Q:クソリアリズムじゃない。
村木:それだと動きがとれないですよ。『蜘蛛巣城』の城郭にしても、清水寺のような長い束柱に支えられた舞台が面白い、と採用になったんです。
Q:『影武者』でも、天守閣がいろいろ出てきましたが、黒澤さんは、「天正年間の城は、山城で、平城の天守閣は本当はなかったが、それでは映画として面白くない」と、さかんにおっしゃってましたね。それが、封切られると、平城はおかしいと批判される。だから、時代考証家が実際とは違うと批判するのは、ナンセンスだという気がしますね。だけど、黒澤映画の場合、スクリーンに写ってしまうと、それが現実に存在したんじゃないかと思うくらいに説得力がある。これは、なぜですか?
村木:それは、理論的な裏づけができているからですよ。さっきもいったように、全くかけ離れたところから想像したものでなくて、
Q:その意味では、黒澤さんは一流の批評家でもありますね。
村木:そういうことです。
Q:じゃあ、黒澤さんは、相当な資料を持っておられるんですか?
村木:ものすごいですよ。美術書なんか、専門の僕でもかなわない。
Q:ユニークな発想も、それだけ資料を読みこなした上での発想なんですね。黒澤映画は、どこ切っても、黒澤さんの教養が出てますものね。
村木:なにしろ、黒澤さん、何かやり出すと、趣味でなくなっちゃいますからね。多摩川の鯉釣りやり始めたら、潜って鯉の道筋まで描いたりする(笑)。その時、スイス製のリールを使ったことから、『七人の侍』の矢のアイデアが出てきたんですよ。矢が刺さる所に板を隠しておいて、その板と射る矢を透明なテグスで結ぶんです。矢の中は空洞になっていて、その間にテグスを通す。矢はテグスを伝わっていくわけだから、確実に狙った所に届くんです。つまり、黒澤さんは、自分の趣味を、実にうまく映画に利用するんです。
Q:黒澤さんは何か、無意識のうちに、やっていることすべてを、映画に結びつけているって感じがしますね。
(中略)
Q:『用心棒』は舞台は上州?
村木:そうです。空っ風が吹くところという設定なので、むこうの家屋を参考にしてます。倉のつくり方、汚し方も、ずいぶん調べました。映画では一方の親分が、最初はお米屋だったんです。でも、僕の親父が酒問屋の番頭やってましてね。小さい時から造り酒屋へ行ってたものですから、そっちのイメージのほうがいいんじゃないかって黒澤さんに話したら、「じゃあ、酒屋にしよう」とOKが出たんです。でも、そこまでは良かったんですが、両方の親分の組が、お互いのものを壊しあう時に、酒樽から酒が飛び出すシーンがあるでしょう。あの時、「酒樽が小さい。倍ぐらい大きいものを作れ!」って(笑)。でも、あんな巨大な樽なんて日本にないでしょう。だから、樽をたがねるタガがなくて作るのに大変でした。この印象的なカットも、実際より、ビジュアルに写るほうを優先させた例ですね。
Q:桑畑三十郎が酒を飲んでる時のとっくりは、黒澤さんが所有されてる骨董品だそうですね。
村木:あれ、京都で買ったんですよね。小物の場合は、黒澤さん骨董が好きだから、持ってるもの使うんです。『七人の侍』の木賃宿の時使ったお米の壷は、鎌倉時代の物なんですよ。
Q:『用心棒』で、空っ風が吹いているのを現わすのに、埃を利用されてますね。それを散らすのに大扇風機を回してるんですが、実際の撮影の時は、ものすごい轟音だったそうですね。
村木:そうそう、あれ飛行機のプロペラで回してるんですよ。昔のものだから、もううるさくってね。あれは、西部劇で草の固まりがころがるシーンがあるでしょう。あれからヒントを得たんじゃないのかな。
<村木与四郎>
Q:『蜘蛛巣城』の城門にしても、とてつもなく大きいですものね。
村木:実際、あんな巨大な門なんかありませんよ。黒澤さん何しろ大きいのや、太いのが好きみたい(笑)。
Q:それは、黒澤さんの視点を考えるうえで面白い事実ですね。
村木:『乱』でも、酒を注ぐ白磁の銚子を型にとらせて、実際焼かせて作らせたんです。それも、実際のよりかなり大きくて、図太い(笑)。
Q:そうすると、黒澤作品の場合でも、ずいぶん、史実と異なることがあるんですか?
村木:あります。大いにあります。『用心棒』の宿場の道の幅も、スクリーンがワイドだから、あれほど、広くしなければならなかったのです。『赤ひげ』の小石川養生所のセットにしても、実際の患者の部屋は少ないんですが、本に合わせて、部屋数を多くして、自由に出入りできるようにしたのです。養生所の制服も、まるっきり創作したもので、ああいう御仕着せ的なものがあったわけじゃない。その後、テレビの『赤ひげ』で、あのままの形で着せてましたけどね。手術台のセットにしても、当時は油紙を敷いて、手術していたんですが、それだと絵的に面白くないから、あんな形になったんです。
Q:つまり、視覚的にいかに写るかが優先するわけですね。
村木:そうです。
Q:クソリアリズムじゃない。
村木:それだと動きがとれないですよ。『蜘蛛巣城』の城郭にしても、清水寺のような長い束柱に支えられた舞台が面白い、と採用になったんです。
Q:『影武者』でも、天守閣がいろいろ出てきましたが、黒澤さんは、「天正年間の城は、山城で、平城の天守閣は本当はなかったが、それでは映画として面白くない」と、さかんにおっしゃってましたね。それが、封切られると、平城はおかしいと批判される。だから、時代考証家が実際とは違うと批判するのは、ナンセンスだという気がしますね。だけど、黒澤映画の場合、スクリーンに写ってしまうと、それが現実に存在したんじゃないかと思うくらいに説得力がある。これは、なぜですか?
村木:それは、理論的な裏づけができているからですよ。さっきもいったように、全くかけ離れたところから想像したものでなくて、
Q:その意味では、黒澤さんは一流の批評家でもありますね。
村木:そういうことです。
Q:じゃあ、黒澤さんは、相当な資料を持っておられるんですか?
村木:ものすごいですよ。美術書なんか、専門の僕でもかなわない。
Q:ユニークな発想も、それだけ資料を読みこなした上での発想なんですね。黒澤映画は、どこ切っても、黒澤さんの教養が出てますものね。
村木:なにしろ、黒澤さん、何かやり出すと、趣味でなくなっちゃいますからね。多摩川の鯉釣りやり始めたら、潜って鯉の道筋まで描いたりする(笑)。その時、スイス製のリールを使ったことから、『七人の侍』の矢のアイデアが出てきたんですよ。矢が刺さる所に板を隠しておいて、その板と射る矢を透明なテグスで結ぶんです。矢の中は空洞になっていて、その間にテグスを通す。矢はテグスを伝わっていくわけだから、確実に狙った所に届くんです。つまり、黒澤さんは、自分の趣味を、実にうまく映画に利用するんです。
Q:黒澤さんは何か、無意識のうちに、やっていることすべてを、映画に結びつけているって感じがしますね。
(中略)
Q:『用心棒』は舞台は上州?
村木:そうです。空っ風が吹くところという設定なので、むこうの家屋を参考にしてます。倉のつくり方、汚し方も、ずいぶん調べました。映画では一方の親分が、最初はお米屋だったんです。でも、僕の親父が酒問屋の番頭やってましてね。小さい時から造り酒屋へ行ってたものですから、そっちのイメージのほうがいいんじゃないかって黒澤さんに話したら、「じゃあ、酒屋にしよう」とOKが出たんです。でも、そこまでは良かったんですが、両方の親分の組が、お互いのものを壊しあう時に、酒樽から酒が飛び出すシーンがあるでしょう。あの時、「酒樽が小さい。倍ぐらい大きいものを作れ!」って(笑)。でも、あんな巨大な樽なんて日本にないでしょう。だから、樽をたがねるタガがなくて作るのに大変でした。この印象的なカットも、実際より、ビジュアルに写るほうを優先させた例ですね。
Q:桑畑三十郎が酒を飲んでる時のとっくりは、黒澤さんが所有されてる骨董品だそうですね。
村木:あれ、京都で買ったんですよね。小物の場合は、黒澤さん骨董が好きだから、持ってるもの使うんです。『七人の侍』の木賃宿の時使ったお米の壷は、鎌倉時代の物なんですよ。
Q:『用心棒』で、空っ風が吹いているのを現わすのに、埃を利用されてますね。それを散らすのに大扇風機を回してるんですが、実際の撮影の時は、ものすごい轟音だったそうですね。
村木:そうそう、あれ飛行機のプロペラで回してるんですよ。昔のものだから、もううるさくってね。あれは、西部劇で草の固まりがころがるシーンがあるでしょう。あれからヒントを得たんじゃないのかな。
<黒澤エピソード満載の本>
図書館で『天気待ち』という本を手にしたが・・・
黒澤さんに影のように付き添ってきた著者が、黒澤さんと、その映画作りを語っています。
黒澤エピソード満載の本やないけ♪・・・ということで借りたのです。
【天気待ち】
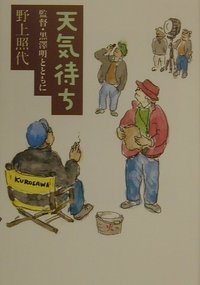
野上照代著、文藝春秋、2001年刊
<「BOOK」データベース>より
本書は、1991年7月から97年10月までの6年に亘り“キネマ倶楽部”というビデオ販売機構の会報に連載された「天気待ち」というエッセイが中心になっている。『羅生門』以来黒沢組にかかわる著者の、巨匠の逸話満載。
<読む前の大使寸評>
黒澤さんに影のように付き添ってきた著者が、黒澤さんと、その映画作りを語っています。・・・・黒澤エピソード満載の本やないけ♪
rakuten 天気待ち
著者インタビュー「黒澤映画の秘密」の一部を紹介します。
黒澤天皇と言われた由縁がわかるし、この本のキモみたいなところでしょうね。
<編集でみせる集中力>p312~316
Q:野上さんにとって、黒澤映画のユニークなところ、また黒澤さんの映画監督として余人をもって代えがたい才能というのは、何であるとお考えでしょうか。
野上 :それはまず、監督としての異常なほどの“集中力”。成瀬さんの話に繋がるけど、特に編集の時の集中力はすごい。話しかけても何も聞こえない。記録のわたしの立場からいえば、撮影よりも何よりも編集作業ほど大変なものはない。なにしろ撮った材料が多いから。
Q:編集作業に立ち会うのは何人ですか。
野上 :作品によって違うけど、わたしと編集技師とその助手さんの三人くらい。『乱』から後はイタリア人の助監督ヴィットリオ・ダレ・オーレ君も付いてたけど。
Q:編集は監督が一人でされるわけですか。
野上 :そう。とにかく編集は部屋が凍りつくぐらいの緊張です。いつ何が起こるかわからない。
(中略)
Q:聞いているだけで鬼気迫るものがありますね。
野上 :とにかく黒澤さんの場合は、それが最終的な一番大事な演出だから。黒澤さんの演出というのは、いつもおっしゃっていまっすが、「まず編集の材料を撮る」ということなんです。わたしは、これを『羅生門』のころからずっと毎回聞かされている。「材料を撮るために撮影している」って。
要するに、撮影のときは画を作って、録音のことはあとまわし。それで悪いところがあれば、音は音で何とかする。それで、監督にとっては最終的にたった一人で一番本当の演出をするのが編集作業なんですよ。
全部の材料をすべて手にして、最近になると音楽のテープまで持って、とにかく一から百までの全部ができるのが編集だから。われわれはとにかくそばにいて、コトリとでも音を出さない。邪魔をしないかぎりはいいわけよ。でも、邪魔をしてはじめて存在がわかるんだけどね(笑)。
『羅生門』のモノクロ映像の美しさについても触れています。
<太陽を撮る>p78~81
いまさら感心するのも妙な話だが、黒澤さんは実にキャメラのことをよく知っている。キャメラマンと相談しながらにしても、どのカットもぜんぶ自分でファインダーをのぞいて構図を決めるし、レンズのサイズまで選択するほど、それは詳しい。だからキャメラに収まる画面の範囲なども明確に頭に入っているようである。
たとえば雪の日の撮影の時などスタッフは、うっかり足跡でもつけたら大変とヒヤヒヤしながら作業をするのだが、黒澤さんは平気で、ずかずかキャメラの前に出て行く。周囲が「ああっ、あんなでっかい足跡を・・・」という顔をすると「大丈夫だよ、こんなところは入ってねえよ」と自信たっぷりである。よくわかるものだなあ、と私などはそれだけで参ってしまう。
だから普通のキャメラなどもさぞ好きだろうと思われがちで、外国などへ行くと超一流のキャメラをおみやげにもらったりするのだが、実はこっちの方にはまったく興味がない。一度もシャッターを押したことがないという珍しい人である。
黒澤さんが、『七人の侍』以後、複数のキャメラを使うようになったことは知られているが、それまでは1台のキャメラだったから『羅生門』も当然、1台だった。
宮川一夫さんは、いったんキャメラが据わったら最後、ファインダーをのぞきっぱなしの人である。そのわきに体を寄せて黒澤さんが座り込み、二人でファインダーの取り合いのかっこうで、いつもどっちかがのぞいていた。撮影助手の平さん(本田平三)が「わしら、のぞく時あらへん」と、ぼやいていたほどである。
黒澤さんが今でも助監督たちを怒鳴ることのひとつは「キャメラをのぞけ!」である。「キャメラをのぞいてみろ。そんなところに通行人おいたってキャメラからは見えないだろ。無駄なことするな!」とくる。
助監督さんだってキャメラをのぞきに来ないわけではない。しかし黒澤さんのように構図を正確に頭に入れるのはなかなかできないことなのだ。
前置きが長くなったが、『羅生門』の美しさは、あの構図のシンプルさと光と影の絶妙の感覚だと思う。
盗賊の三船敏郎が大木の下で眠っている時、通りかかった馬上の女を見る。
「あの風さえ吹かなければ」という一陣の風が女を見送る盗賊の胸の葉影を揺らす。あの不吉な美しさ。
(中略)
黒澤さんは、太陽が好きである。自著『蝦蟇の油』にも『羅生門』の太陽について書いている。
「この作品の大きな課題の一つは、森の中の光と影が作品全体の基調になるから、その光と影をつくる太陽そのものをどのように捕まえるかという問題があった。私は、その問題を、太陽をまともに撮る事で解決しようと思った。」―そのころは、まだキャメラマンも太陽をじかに撮るのは恐れていた。太陽光線がフィルムを焼くとさえ考えられていたそうだ。しかし宮川さんは大胆にもキャメラを太陽へ向けて振り上げ、梢越しに輝く太陽をとらえた。
盗賊が女を抱いて無理矢理、接吻するあの場面は色々なアングルから撮った。二人をイントレ台(組み立て式の台。D・W・グリフィス監督『イントレランス』で使われたことからできた名称)の上に載せ、梢ごしの太陽をバックに仰角のカットも撮った。
著者は記録係(スクリプター)として、黒澤監督と関わったのだが、記録係の作業が語られています。
<記録>p108~111
遅まきながら記録係とは何者なのかを説明しておこう。近ごろではスクリプターと呼ぶのが普通だ。外国でいうスクリプトガールから来たものだろうが、ガールにはほど遠いオバさんが大勢を占めている。
(中略)
こうして撮影されたフィルムは現像所でネガ・フィルムになり、NGという不要部分を除き、初めてカット・ナンバーの順にOKだけがポジ現像される。どれがNGでどれがOKかは記録係の“送り”という伝票を見ないと分からない。それには撮影の時のカット・ナンバーに一回毎の秒数と、OK、NGが記されている。音の方も6ミリ・テープから35ミリ・シネテープにOK分だけを転写してネガ編集部へ渡す。そこで画と音を合わせたラッシュ(急ぎの)プリントが出来上がるのである。
この音と画を合わすために、なくてはならぬのがあのカチンコだ。板切れにはこれから撮影するカットのシーン、カット、テイクの番号をチョークで書いて、ど頭にこのカットの“固有名詞”を焼きつける。編集部はフィルムに写っている拍子木の合わさった瞬間と、テープに録音されているカチン!という音を合わせさえすれば、その後はすべて自動的にせりふと口の動きがピッタリ合うことになっている。別にカチンコじゃなくても頭をたたいたって音がでりゃ合わせられる理屈である。
黒澤監督の編集は世界中のだれも真似ができない特別な天才だから例外だ。記録の“送り”なんか見るどころか、何もかも自分で記憶しているから、まったく歯が立たない。
大使にとっては美術監督の仕事が興味深いのである。
<美術>p119~121
美術監督の村木与四郎さんは、1948年の『酔いどれ天使』で松山崇さんの助手について以来の黒澤組古参兵である。村木さんの造るセットは雄大である。コセコセしていない。どかん、としているところが黒澤さんの好みに合ったのだろう。
黒澤さんと村木さんがセット・プランの平面図を中心に対峙している様子はまさに名人戦だ。工事現場のヘルメットの小父さんが見るような青い図面を黒澤さんは、よく読めるものだといつも感心して見ていたが、これが分からなくちゃ監督は務まらぬ。
<『トラ・トラ・トラ!』から黒澤監督途中降板>
図書館で『黒澤明、天才の苦悩と創造』という本を手にしたが・・・・
パラパラめくると・・・・
監督の描いた絵コンテ(カラー写真)や『トラ・トラ・トラ!』のシナリオ、『トラ・トラ・トラ!』から黒澤監督途中降板の真相、『七人の侍』演出ノートなどが載っていて、これは見所満載である♪
【黒澤明、天才の苦悩と創造】
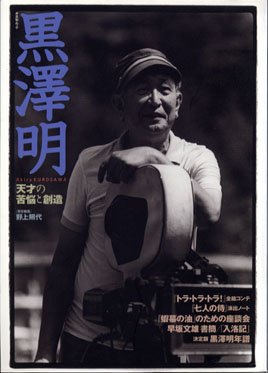
ムック、キネマ旬報社、2001年刊
<「MARC」データベース>より
黒沢明の創造の軌跡を演出ノート、絵コンテ、関係者の談話、座談会などから探り、塩野七生、キアロスタミ、池辺晋一郎、井上ひさし等がその魅力を分析する。貴重なスナップも多数掲載。
<読む前の大使寸評>
監督の描いた絵コンテ(カラー写真)や『トラ・トラ・トラ!』のシナリオ、『トラ・トラ・トラ!』から黒澤監督途中降板の真相、『七人の侍』演出ノートなどが載っていて、これは見所満載である♪
Amazon 黒澤明、天才の苦悩と創造
ところで『トラ・トラ・トラ!』という映画は、どんなだったか・・・・先ず、過去の日記から映画評を見てみましょう。
このときは、黒澤監督途中降板など知らずに観たんですが。
【トラ・トラ・トラ!】

リチャード・フライシャー監督、1970年米制作、H24.7.30観賞
<goo映画解説>より
太平洋戦争の火ぶたを切った真珠湾奇襲作戦の全貌を描いた大型戦争映画。製作総指揮はダリル・F・ザナック、製作は「ブルー・マックス」のエルモ・ウィリアムス。監督は、アメリカ側が「ミクロの決死圏」のリチャード・フライシャー、日本側が「スパルタ教育・くたばれ親父」の舛田利雄と「きみが若者なら」の深作欣二。ゴードン・W・プランゲの「トラ・トラ・トラ!」とラディスラス・ファラーゴの「破られた封印」を基に、アメリカ側はラリー・フォレスター、日本側は菊島隆三と小国英雄が共同脚色。
<大使寸評>
戦争オタク必見の映画でんな♪ 冒頭、軍楽隊が「海ゆかば」を演奏するところで、おもわず涙する大使であった。
とにかく膨大な数のカーティスとカタリナ飛行艇の実機が爆破されたが、さすがアメリカ映画の物量には驚いたのだ。そして、こんな国と戦争した無謀さを実感。
goo映画 トラ・トラ・トラ!
この本では、黒澤監督途中降板の顛末が多くの関係者によって語られているのだが・・・・
そのなかで、佐藤純ヤ監督とのインタビューを見てみましょう。
p38~41
佐藤監督は、『トラ・トラ・トラ!』で第2班監督として携わる。北海道でのロケーション撮影は行うが、黒澤監督が降板すると同時に、この映画から手を引く。その直後白井佳夫氏によるインタビューが行われ、「黒澤明集成3」(小社刊)に収録されているが、今回は改めて回想してもらい、また新たな証言をお聞きすることができた。(聞き手:野上照代)
Q:佐藤さんはB班監督だった訳ですが、黒澤さんと一緒に降りられたんですね。
佐藤:そうです。アメリカのプロデューサーに呼ばれて、(黒澤監督降板後を)全部引き受けろと言われたんですが、黒澤さんと一緒に仕事がしたくて引き受けたので、黒澤さんが辞めるなら僕も辞めますと言ったんです。
僕は、黒澤さんと別れたのは、68年12月30日に、黒澤さんが東京へ引き上げるというんで、松江さんや村木さんや7人くらいで一緒に帰って。ちょうど「七郷都落ち」みたいな気がしてきましたね。
その時以来、黒澤さんとは何年もお会いしていなくて、ある時、黒澤さんの何かの作品の試写に行ったらお会いして、それが最後でした。「元気かい?」とおっしゃって、随分懐かしがってらっしゃいましたね。
Q:最初に青柳哲郎プロデューサーから頼まれて、B班つまりセカンド・ユニットということだったんですね?
佐藤:そうです。黒澤さんは、ロケーションはしんどいので北海道のロケは全部任せるとおっしゃって、「僕はセットをやるから」と。
北海道は、駆逐艦に海上給油するところ、それから連合艦隊がハワイへ向けて出発するのを見送る地元民というところの何カットかです。黒澤さんの描いた絵コンテを持って行きました。海上給油の、駆逐艦と給油艦の間にロープを張って作業中に水兵が海に落っこちるというところは、たまたま嵐が来て撮れたんです。3,4カットあったと思いますが、艦隊の出発を地元民が見送るところは雪待ちでした。
実際にカメラを回したのは多分2日ぐらいだったと思います。あとは雪待ちで、毎日朝起きるとピーカンで、2週間ぐらいは今日は洞爺湖へ行こうとかどこへ行こうとか、遊んでいました。カメラマンは植木等さんの兄弟の佐藤忠さんでした。
(中略)
黒澤さんがしょっちゅう言っていたのは、黒澤プロダクションとしてアメリカと契約しているということを本当に気にしていました。逆に言えば、毎晩、哲ちゃんにそれを吹き込まれていたということでしょうが。でも、実際には、黒澤プロの社長としての立場と、監督・黒澤明としての立場はものすごくギャップがあったということでしょう。いろいろ言われて節約しなきゃと思っても、監督として思う存分やりたいし、金勘定がわかる訳ではないし、辛かったと思いますよ。
それに輪をかけたのが、俳優として素人を起用したということでしょうか。
選んだのは黒澤さん自身ということなんですが。結局、いろいろもめて照明部がストライキということで1週間休みを取って、その間に、松江さんたちと、素人に演技指導をした訳です。
Q:とは言っても、なかなか難しいでしょう。みんな年齢がいっているし、社会人として地位のある方なので怒れないし
佐藤:海軍将校たちも、みな海兵経験者から選んだ訳ですが、実際の海軍の人たちの行動と黒澤さんのドラマとしての動きがズレてくるんですね。そうすると、段々テンションが上がってきて・・・・。亀田さんという実際に真珠湾攻撃に参加された人がアドバイザーとして参加してまして、「亀田さん、実際にはこうかもしれないけど、ドラマにはならないから変えてもいいかな」なんて聞きまして。そうすると、こんどは俳優の人たちが動けないんです。それでまた爆発したりして。
(中略)
見ていて、僕は金輪際やるまいと思ったのは、やはり、プロデューサーと監督兼任というのは絶対だめですね。コッポラみたいに自分の金でやって、自分の金なんだから文句言うなということなら別ですが、人の金でやる場合はね。
Q:プロデューサーが一緒に戦ってくれるんならいいんですが、青柳プロデューサーは最初からアメリカ側だったらしいし。それに(黒澤さんは)言葉ができないということもあって、外国語のできる人を信用するしかない訳ですし。
(2001年9月19日)
佐藤監督は、『トラ・トラ・トラ!』で第2班監督として携わる。北海道でのロケーション撮影は行うが、黒澤監督が降板すると同時に、この映画から手を引く。その直後白井佳夫氏によるインタビューが行われ、「黒澤明集成3」(小社刊)に収録されているが、今回は改めて回想してもらい、また新たな証言をお聞きすることができた。(聞き手:野上照代)
Q:佐藤さんはB班監督だった訳ですが、黒澤さんと一緒に降りられたんですね。
佐藤:そうです。アメリカのプロデューサーに呼ばれて、(黒澤監督降板後を)全部引き受けろと言われたんですが、黒澤さんと一緒に仕事がしたくて引き受けたので、黒澤さんが辞めるなら僕も辞めますと言ったんです。
僕は、黒澤さんと別れたのは、68年12月30日に、黒澤さんが東京へ引き上げるというんで、松江さんや村木さんや7人くらいで一緒に帰って。ちょうど「七郷都落ち」みたいな気がしてきましたね。
その時以来、黒澤さんとは何年もお会いしていなくて、ある時、黒澤さんの何かの作品の試写に行ったらお会いして、それが最後でした。「元気かい?」とおっしゃって、随分懐かしがってらっしゃいましたね。
Q:最初に青柳哲郎プロデューサーから頼まれて、B班つまりセカンド・ユニットということだったんですね?
佐藤:そうです。黒澤さんは、ロケーションはしんどいので北海道のロケは全部任せるとおっしゃって、「僕はセットをやるから」と。
北海道は、駆逐艦に海上給油するところ、それから連合艦隊がハワイへ向けて出発するのを見送る地元民というところの何カットかです。黒澤さんの描いた絵コンテを持って行きました。海上給油の、駆逐艦と給油艦の間にロープを張って作業中に水兵が海に落っこちるというところは、たまたま嵐が来て撮れたんです。3,4カットあったと思いますが、艦隊の出発を地元民が見送るところは雪待ちでした。
実際にカメラを回したのは多分2日ぐらいだったと思います。あとは雪待ちで、毎日朝起きるとピーカンで、2週間ぐらいは今日は洞爺湖へ行こうとかどこへ行こうとか、遊んでいました。カメラマンは植木等さんの兄弟の佐藤忠さんでした。
(中略)
黒澤さんがしょっちゅう言っていたのは、黒澤プロダクションとしてアメリカと契約しているということを本当に気にしていました。逆に言えば、毎晩、哲ちゃんにそれを吹き込まれていたということでしょうが。でも、実際には、黒澤プロの社長としての立場と、監督・黒澤明としての立場はものすごくギャップがあったということでしょう。いろいろ言われて節約しなきゃと思っても、監督として思う存分やりたいし、金勘定がわかる訳ではないし、辛かったと思いますよ。
それに輪をかけたのが、俳優として素人を起用したということでしょうか。
選んだのは黒澤さん自身ということなんですが。結局、いろいろもめて照明部がストライキということで1週間休みを取って、その間に、松江さんたちと、素人に演技指導をした訳です。
Q:とは言っても、なかなか難しいでしょう。みんな年齢がいっているし、社会人として地位のある方なので怒れないし
佐藤:海軍将校たちも、みな海兵経験者から選んだ訳ですが、実際の海軍の人たちの行動と黒澤さんのドラマとしての動きがズレてくるんですね。そうすると、段々テンションが上がってきて・・・・。亀田さんという実際に真珠湾攻撃に参加された人がアドバイザーとして参加してまして、「亀田さん、実際にはこうかもしれないけど、ドラマにはならないから変えてもいいかな」なんて聞きまして。そうすると、こんどは俳優の人たちが動けないんです。それでまた爆発したりして。
(中略)
見ていて、僕は金輪際やるまいと思ったのは、やはり、プロデューサーと監督兼任というのは絶対だめですね。コッポラみたいに自分の金でやって、自分の金なんだから文句言うなということなら別ですが、人の金でやる場合はね。
Q:プロデューサーが一緒に戦ってくれるんならいいんですが、青柳プロデューサーは最初からアメリカ側だったらしいし。それに(黒澤さんは)言葉ができないということもあって、外国語のできる人を信用するしかない訳ですし。
(2001年9月19日)
なるほど、黒澤プロの社長そして、監督・黒澤明としての葛藤に、アメリカとの文化摩擦が加わったのか・・・・
黒澤天皇でなくても、切れてしまうんじゃないでしょうか。
<伝説の映画美術監督たち×種田陽平>
図書館で『伝説の映画美術監督たち×種田陽平』という本を手にしたが・・・・
この本に『トラ・トラ・トラ!』の黒澤監督降板劇の真相が載っていて、興味深々でんがな♪
【伝説の映画美術監督たち×種田陽平】
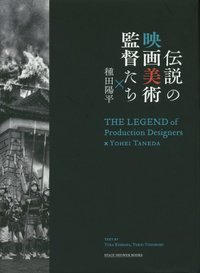
種田陽平著、スペースシャワーネットワーク、2014年刊
<「BOOK」データベース>より
映画監督・種田陽平が聞く13人の映画美術の巨匠たち。
【目次】
木村威夫/横尾嘉良/間野重雄/水谷浩/西岡善信/朝倉摂/池谷仙克/竹中和雄/井川徳道/森田郷平/村木与四郎/ワダエミ/ダンテ・フェレッティ
<大使寸評>
村木与四郎さんとの対談で、『トラ・トラ・トラ!』の黒澤監督降板劇の真相が出てくるのだが・・・・
日米の交渉スタッフが映画作りの部外者だったので、黒澤監督がおかんむりだったようですね。
rakuten 伝説の映画美術監督たち×種田陽平
『トラ・トラ・トラ!』の黒澤監督降板劇の真相あたりです。
p177~180
06年6月に行われた対談に際し、村木は当時刊行されたばかりの「黒澤明vsハリウッド―『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて」(田草川弘著)を用意して種田を待っていた。この本は60年代後半、黒澤明が20世紀フォックス資本で撮るはずだった映画『トラ・トラ・トラ!』の監督降板劇の真相を探ったものである。
村木:この本は、日本側に関しては事実と違う記述も見受けられるけど、20世紀フォックス側のデータはよく調べてある。これを読むと、日本側のプロジューサーだった青柳哲郎がおかしなことを言っているのがよく分かります。要するに、それまで1回も映画の現場で揉まれたことのないスタッフが、英語ができるだけで重要な交渉の場に立ってしまったから話がこんがらがっちゃった。クロさんも思い込みが強いから、脚本は全部自分で書いて、その通りに撮れると思っていた。
種田:最近でこそハリウッドとのやり方が日本側も分かってきたけれど、当時の考え方のギャップがあまりにも大きかったんでしょうね。
村木:間違いの種は、フォックス側が何かにつけてクロさんに安請け合いしたこと、例えば向こうは一度、零戦が奇襲するハワイ島・真珠湾のミニチュア模型を、日本のスクリーンの3倍の大きさで作れると言ったんだ。ところがしばらくして、「そこまでサイズが大きいと、ライティングの光量が足りなくてピントが合わない」と言い出した。要はアメリカ側も映画を知らない人間が交渉の場に立っているから、できるできないの判断が付かず、それが現場に降りてきて揉めてしまう。
種田:黒澤監督は『トラ・トラ・トラ!』の前、66年にアメリカのエンバシー・ピクチャーで「Ranaway Train」を撮ることになっていましたが、このときはどうだったんですか?
村木:『暴走機関車』は機関士が心臓発作を起こし、機関車が逆方向に暴走する話だけれど、この際もアメリカ側は鉄道の運行を止め撮影すると言っていたんです。逆走し始めた機関車と、それを知らずに進行してきた機関車がぶつかる直前ですれ違うシーンも、実物を動かして撮ろうと、今考えればそんな危険な撮影、許可なんて下りるわけないんだけど。クロさんは始末に負えないほど人が好くてね。出来ると言われるとすぐに信じちゃうんです。うまく行くと批評家は「凄い」と褒めるけど、そうじゃないときは『トラ・トラ・トラ!』になってしまう。
種田:例えば『羅生門』(50)では黒澤さんのビジョンがうまく映像化したわけですが、その違いは何なのでしょう?
村木:敗戦直後の東宝争議で、クロさんは山本嘉次郎さん、成瀬(巳喜男)さん、谷口千吉さんと東宝を退社して「映画芸術協会」を設立するでしょう。それで49年、大映に赴いて『静かなる決闘』を撮るんだけど、大映の方も監督の扱い方が分かって、次の『羅生門』では永田雅一社長を始めスタッフがうまくクロさんを乗せた。
種田:セットが大きくなるのは、静岡の御殿場で撮るようになってからですか?
村木:御殿場は、ロケ先で野次馬に騒がれるようになったのも大きい。だったら人が簡単には来られらない場所にセットを組もうという発想になった。ただ、『七人の侍』の頃からすでに、セットが大規模になる傾向があって、1年以上の制作期間中、3回ぐらい途中で撮影がストップしたんだけど。
種田:むしろ3度止まっても完成できたのが凄いなと。
村木:クロさんは狙って撮影を途中で止めるんですよ。一番いい場面のチャンバラの手前で撮影を止めて、そこまでのラッシュ映像を製作陣に見せる。そうすると話は面白いし、「もうちょっとで終わりだから・・・」と製作側もお金を出す。そしたら、より大きく作り直しちゃう。
種田:でも、そのスケールの大きさが黒澤さんの持ち味なんですよね。例えば『羅生門』にしたって、脚本に具体的説明はなく、ただ一言「門」とあるだけ。それが映画になると、巨大なモニュメントのようにそびえ立っています。村木さんが手掛けた『隠し砦の三悪人』(58)の石段にしても、日本映画では見たことがないほどのスケール感ですよね。
村木:『隠し砦』の石段は、他の作品よりは小さいですよ(笑)。まあ、僕はいつも一回り大きく作るからね。
種田:それはなぜですか?
村木:そうしないと、クロさんから必ず何か言われて癪だからね。ただ、本当を言うと僕は脚本に合わせて作るのが上手いんだ。東宝でも最も安い美術製作費で作られた『小象物語 地上に降りた天使』(86)も僕、あの映画は夜の話ですから、さすがに象舎だけは作りましたが、あとは撮影所内の建物に金網なんかをあしらって檻っぽく見せた。
種田:なるほど、村木さんの場合は小さく安くもできるけれど、黒澤作品に限っては一回り大きくなっちゃうと(笑)。
村木:そういう意味では、僕のやっていることは大体インチキなんです。『夢』(90)では珍しく、クロさんが幼少期を過ごしたという本郷近くの家の門を本物らしく再現したら、「僕のうちの門は近所でも有名なくらい大きかった」とくる(笑)。そういう人なんだよ。だから、『椿三十郎』では部屋の隅っこに茶室を作った。その手前の庭に椿の木を置いて、それを一番端から望遠で撮ると、とても奥行きが出るからね。
種田:普通の日本人が見ている風景よりも大きい世界観は、黒澤さんの肉体の大きさの反映ですか?それとも村木さんの志向性?
(中略)
村木:結局、映画美術なんて、現実の借り物である映画のさらに借り物だからね。借り物だけが独立して、大きく発展するなんてありえない。大きい企画を生み出すプロジューサーが現れないと、次世代のクロさんは生まれないんじゃないかね。僕はそう、思いますね。
06年6月に行われた対談に際し、村木は当時刊行されたばかりの「黒澤明vsハリウッド―『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて」(田草川弘著)を用意して種田を待っていた。この本は60年代後半、黒澤明が20世紀フォックス資本で撮るはずだった映画『トラ・トラ・トラ!』の監督降板劇の真相を探ったものである。
村木:この本は、日本側に関しては事実と違う記述も見受けられるけど、20世紀フォックス側のデータはよく調べてある。これを読むと、日本側のプロジューサーだった青柳哲郎がおかしなことを言っているのがよく分かります。要するに、それまで1回も映画の現場で揉まれたことのないスタッフが、英語ができるだけで重要な交渉の場に立ってしまったから話がこんがらがっちゃった。クロさんも思い込みが強いから、脚本は全部自分で書いて、その通りに撮れると思っていた。
種田:最近でこそハリウッドとのやり方が日本側も分かってきたけれど、当時の考え方のギャップがあまりにも大きかったんでしょうね。
村木:間違いの種は、フォックス側が何かにつけてクロさんに安請け合いしたこと、例えば向こうは一度、零戦が奇襲するハワイ島・真珠湾のミニチュア模型を、日本のスクリーンの3倍の大きさで作れると言ったんだ。ところがしばらくして、「そこまでサイズが大きいと、ライティングの光量が足りなくてピントが合わない」と言い出した。要はアメリカ側も映画を知らない人間が交渉の場に立っているから、できるできないの判断が付かず、それが現場に降りてきて揉めてしまう。
種田:黒澤監督は『トラ・トラ・トラ!』の前、66年にアメリカのエンバシー・ピクチャーで「Ranaway Train」を撮ることになっていましたが、このときはどうだったんですか?
村木:『暴走機関車』は機関士が心臓発作を起こし、機関車が逆方向に暴走する話だけれど、この際もアメリカ側は鉄道の運行を止め撮影すると言っていたんです。逆走し始めた機関車と、それを知らずに進行してきた機関車がぶつかる直前ですれ違うシーンも、実物を動かして撮ろうと、今考えればそんな危険な撮影、許可なんて下りるわけないんだけど。クロさんは始末に負えないほど人が好くてね。出来ると言われるとすぐに信じちゃうんです。うまく行くと批評家は「凄い」と褒めるけど、そうじゃないときは『トラ・トラ・トラ!』になってしまう。
種田:例えば『羅生門』(50)では黒澤さんのビジョンがうまく映像化したわけですが、その違いは何なのでしょう?
村木:敗戦直後の東宝争議で、クロさんは山本嘉次郎さん、成瀬(巳喜男)さん、谷口千吉さんと東宝を退社して「映画芸術協会」を設立するでしょう。それで49年、大映に赴いて『静かなる決闘』を撮るんだけど、大映の方も監督の扱い方が分かって、次の『羅生門』では永田雅一社長を始めスタッフがうまくクロさんを乗せた。
種田:セットが大きくなるのは、静岡の御殿場で撮るようになってからですか?
村木:御殿場は、ロケ先で野次馬に騒がれるようになったのも大きい。だったら人が簡単には来られらない場所にセットを組もうという発想になった。ただ、『七人の侍』の頃からすでに、セットが大規模になる傾向があって、1年以上の制作期間中、3回ぐらい途中で撮影がストップしたんだけど。
種田:むしろ3度止まっても完成できたのが凄いなと。
村木:クロさんは狙って撮影を途中で止めるんですよ。一番いい場面のチャンバラの手前で撮影を止めて、そこまでのラッシュ映像を製作陣に見せる。そうすると話は面白いし、「もうちょっとで終わりだから・・・」と製作側もお金を出す。そしたら、より大きく作り直しちゃう。
種田:でも、そのスケールの大きさが黒澤さんの持ち味なんですよね。例えば『羅生門』にしたって、脚本に具体的説明はなく、ただ一言「門」とあるだけ。それが映画になると、巨大なモニュメントのようにそびえ立っています。村木さんが手掛けた『隠し砦の三悪人』(58)の石段にしても、日本映画では見たことがないほどのスケール感ですよね。
村木:『隠し砦』の石段は、他の作品よりは小さいですよ(笑)。まあ、僕はいつも一回り大きく作るからね。
種田:それはなぜですか?
村木:そうしないと、クロさんから必ず何か言われて癪だからね。ただ、本当を言うと僕は脚本に合わせて作るのが上手いんだ。東宝でも最も安い美術製作費で作られた『小象物語 地上に降りた天使』(86)も僕、あの映画は夜の話ですから、さすがに象舎だけは作りましたが、あとは撮影所内の建物に金網なんかをあしらって檻っぽく見せた。
種田:なるほど、村木さんの場合は小さく安くもできるけれど、黒澤作品に限っては一回り大きくなっちゃうと(笑)。
村木:そういう意味では、僕のやっていることは大体インチキなんです。『夢』(90)では珍しく、クロさんが幼少期を過ごしたという本郷近くの家の門を本物らしく再現したら、「僕のうちの門は近所でも有名なくらい大きかった」とくる(笑)。そういう人なんだよ。だから、『椿三十郎』では部屋の隅っこに茶室を作った。その手前の庭に椿の木を置いて、それを一番端から望遠で撮ると、とても奥行きが出るからね。
種田:普通の日本人が見ている風景よりも大きい世界観は、黒澤さんの肉体の大きさの反映ですか?それとも村木さんの志向性?
(中略)
村木:結局、映画美術なんて、現実の借り物である映画のさらに借り物だからね。借り物だけが独立して、大きく発展するなんてありえない。大きい企画を生み出すプロジューサーが現れないと、次世代のクロさんは生まれないんじゃないかね。僕はそう、思いますね。
<黒澤明 夢のあしあと>
図書館で『黒澤明 夢のあしあと』というムック本を借りたが・・・
数多くの現場写真に添えて、俳優・スタッフの苦労話が載せられていて興味深いのです。
特に、大使の関心は映像美術にあるのだが、この本はその関心にバッチリはまっています♪

『七人の侍』のなかで、この雨中の攻防シーンは圧巻である♪
このシーンが厳冬期に撮影されたそうだが・・・
ここに映画制作にかけては、血も涙もない(笑)黒澤監督の厳しさが表れているようです。
俳優たちはカット終了までは歯の根も合わず死ぬ気で頑張ったそうで、カットの合図が出ればたらいのお湯をかぶったそうです。
【黒澤明 夢のあしあと】
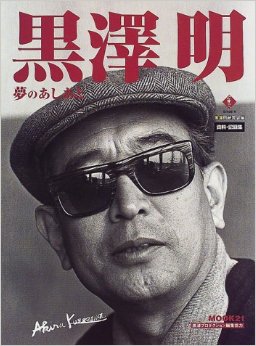
ムック、共同通信社、1999年刊
<「MARC」データベース>より
88歳の生涯を映画に捧げた黒沢明。映画30作品のみならず、遺されたシナリオ、絵コンテ、文章、言動の記録から、その生涯を振り返る。黒沢映画に関わった俳優・スタッフを集めた人名辞典を巻末に収める。
<大使寸評>
数多くの現場写真に添えて、俳優・スタッフの苦労話が載せられていて興味深いのです。
特に、大使の関心は映像美術にあるのだが、この本はその関心にバッチリはまっています♪
Amazon 黒澤明 夢のあしあと
この本では『七人の侍』の撮影エピソードに多くをさいているが、黒澤映画のベストでもあり、当然の扱いなんでしょうね。
<七人の侍ロケ地探訪、静岡県堀切> よりp168
黒澤映画の編集は、オプチカルの多用、マルチカメラ、徹底したアクション・カットによるつなぎ、などによって、水の流れるような独特の映像言語を形成している。そのうちのアクション・カットは初期作品から一貫している手法だが、『七人の侍』から徹底するようになる。これは私見だが、村のロケ地が分散しているので、異なったロケ地とのつなぎ目が鑑賞者に悟られぬようアクション・カットを多用したと思われる。
離れ家の炎上シーンでは、マルチカメラと、1台のカメラで撮られたフィルムが交互編集されている。
「離れ家の炎上シーン」の現場におられたスタッフの方々(斉藤孝男・撮影、村木与四郎・美術、浜村幸一・火災調整、堀川弘通・監督助手)にお会いして、お話を伺ったが、幾度も撮り直した水車小屋の炎上シーンと比べて撮影はスムーズに行われ、一回でOKになったとのこと。しかし、それまでの黒澤作品で、最も大がかりな撮影ではなかったか。三台のキャメラが回されるのは初めてである。
<村木与四郎の話、柱でもなんでも焼き板に> よりp172
私の場合は中学の時から、木材の方の学校におりまして、実際に漆ですとか普通の塗りもやったのが、ある程度功を奏したみたいなことで・・・それから塗り屋の人に大変優秀な人がおりまして、会社でその人を入れない時に、黒澤さんが会社に行って塗り屋さんを社員に入れろと言ったわけですね。そういう話があったくらいに一人そういうふうに造詣の深い人がおりますと、夢中になるんですね、黒澤さんは。(その人が)よそに獲得されなかったということは、うちのセットが良くなった元だと思いますね。『七人の侍』から、柱でもなんでも焼き板にしましてね。塗りで古さを出す仕上げを始めたわけです。
<志村喬の話、途中から「みぞれ」が> よりp176
2月の雨の中の戦闘シーン、途中から「みぞれ」が降ってきました。歯の根が合わないというか、ほんとうに合わないのです。カチカチカチカチ。それでも「用意」の声がかかると、このカチカチが止まるのです。カットの声を聞くとトタンに又カチカチ。おかしいやら寒いやら、それに膝を没する泥の中の戦闘で皆ころびました。しかし今ふりかえってみて懐かしさだけが残っています。我が田に水を引くようですけれど、とにかく面白いのです。
 映画『デルス・ウザーラ』をいま思う
より
映画『デルス・ウザーラ』をいま思う
より『デルス・ウザーラ』をまだ観ていないのだが、この本を読んで「観てみたい」と思ったのです
<『デルス・ウザーラ』は30年前からの夢だった、黒澤明> よりp281
『デルス・ウザーラ』の映画化は、ぼくが30年も前から考えていたことでした。まだ助監督だったころ、たまたま探検記が好きで、『デルス・ウザーラ』の原作を読んで、デルスという人物がとても好きになったわけです。ぜひ映画にしたいと、『白痴』(51年)を終えたあとだったと思いますが、いちど久板栄二郎さんに話してシナリオを書いてもらったのです。そのころは勿論ソビエトで撮るなんて考えてもみなかったから、舞台も人物も置き換えてやったのですが、できたシナリオがどうもおもしろくない。しょせん日本ではうまくいかないのです。
その後、1971年2月、ソビエトのセルゲイ・ゲラーシモフ監督が来日したとき、ソビエトで一本撮る気はないかという話があり、それからその年のモスクワ映画祭に特別出品として「どですかでん」を持って、ぼくがソビエトに行ったとき、向こうからあらためて一本撮らないかという話がでたのです。
日本に来たことのあるレフ・クリジャーノフ監督と会って話していたとき、『デルス・ウザーラ』をやってみたいと言ったのです。すると向こうは、びっくりして「『デルス・ウザーラ』を知っているのか」と言うわけです。「いやあ、30年も前からずっと考えていた」と言うと、「それならそれがいいじゃないか。実は、すでにソビエトで撮った『デルス・ウザーラ』があるけれども、それはとてもつまらない、黒澤さんが撮るなら勿論、全然違うものができるだろう、それがいい」と、けっきょく『デルス・ウザーラ』を撮ることに決まったのです。
アルセーニエフという人は陸軍幼年学校を出て、もともと軍人だったが、子どものときから動物学、植物学、地理学、地質学に大変な興味を持っていた。それで若い士官として極東に派遣され、はじめ軍の戦略的研究から探検を始めたのですが、やがて本格的なシベリアの学術調査をやることになる。
その後、8年間もハバロフスク博物館の館長をつとめたこともある。軍人、探検家というより、地理学者であり文学者です。だから、今でもとても尊敬されていて、ハバロフスクには勿論、亡くなったウラジオストックにも大きな銅像が建っている。
<『デルス・ウザーラ』の時の黒澤さん、ユーリー・サローミン> よりp283
監督との最初の面接にスタジオに出かけたとき、私がどんなに興奮していたか、2回も途中から引き返したことなどについても語るまい・・・。とにかく、私は、ついに偉大な日本人に会うことができたのだから、私が想像していた通り、彼はすらっと背が高く、エレガントで、賢い手、賢い口元、彼の存在のすみずみにハーモニーがゆき渡り、余計なものが何一つなかった。恐らく大自然は、自分の創作にさぞ満足しているだろう。
撮影現場で、黒澤さんがロシア語で叫んでいた。「用意! モーター! 始め!」の号令は、一生私の記憶に残るだろう。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ◆◎◆韓国ドラマ・映画◆◎◆大好きヽ(^◇…
- スノードロップ☆19話その②あらすじ☆…
- (2024-11-23 07:37:07)
-
-
-

- 有名・芸能人
- 齊藤なぎさ・原菜乃華・あのちゃん、…
- (2024-11-23 18:12:02)
-
-
-

- 宝塚好きな人いませんか?
- やっと宝塚のチケット 抽選に当たり…
- (2024-11-08 19:40:24)
-
© Rakuten Group, Inc.



