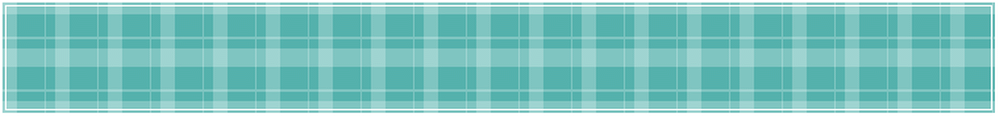脳・こころ
『脳はなにかと言い訳する』池谷裕二『「夜ふかし」の脳科学』神山潤
『救急精神病棟』 野村進
20世紀末の、脳科学の飛躍的な発展に伴い、見逃されてきた心の障害の理解や精神病治療についても、飛躍的に進歩してきた感がある。まさしく21世紀は脳と心の時代。
今まで、収容・隔離、長期入院当たり前とされていた精神科医療に、開放化、短期入院という新たな動きが生まれている。(なかなか広がっていかない苦労はあるが)
それに取り組んでいる、千葉県精神科医療センター(精神科救急)のドキュメンタリー。
従来の、精神病院に対する、何も知らないが故の偏見・マイナスイメージはこれを読めば払拭されるのではないだろうか。誤解されやすかった治療法についての納得できる説明、開放され、社会復帰を前提として考えられた施設設備、患者さんの意思に配慮した入院。
社会からはじき出された形の患者さんやその家族達に向ける医師や看護師達のあたたかなまなざし。迷いやいらだちが生じることもあるが、それを乗り越えて治療に専念する方々には頭が下がる。
センター長のことばに目頭が熱くなった。
まともな治療なんてない時代に“たまたま”精神科医になったと言うセンター長。
「そういう精神病院の内情はずいぶん知っていたから、もうちょっとましな商売にすべきじゃないかとは思った。治療によってお金をもらえる、まっとうな商売にね。世のため人のためにいいことをしたいなんていう使命感なんかじゃないんだよ。世のため人のためなんて思わない方がいい。患者さんを救うことで自分も救われるんだなんて言うことも考えない方がいいな。おれなんか、『精神医療は本当に役立ってるの?』と平気で言っちゃうし、そもそも医学は半分くらい悪いこともしてきたと思ってるしさ」
「じゃあ何だってこんな商売やってるんだというと、ここに運び込まれるまでぐじゃぐじゃになっちゃった人たちをほっとけないだろう?ほっといたら死んじゃう人たちを、みすみす見逃せないだろう?こんな人たちをほっとくのは『人類社会』とはいえないもん。えらそうに『文明社会』なんていえないよな。そこに疑問の余地はない。それなら誰かがやんなきゃならない。じゃあしょうがねえからしぶしぶやるよ、というのがおれのここでの『理屈』さ。使命感じゃなくて、しぶしぶということ。だから、ここでは救急治療を要する精神病状態という、誰の目にも明らかな、ほっといたら死んじゃうかもしれない人たちを中心に診る。その点にも疑問の余地はないわけだよ」
精神病患者とその治療に関する日本の歴史は、惨憺たる有様。人権すら配慮されない、医師や看護師達や病院経営者の態度、国のお粗末な政策。
でも一番罪深いのは、地域住民。私たちの精神病患者や精神障害者に対する意識、無知による偏見なのであろうと感じた。
人によっては、100人に1人は精神病患者であると言われる。鬱病などがマスコミで取り上げられるようになり、その種の本が多く出版されている。精神科に通うことも、一般社会に認知されるようになってきている。「精神病は、治せる」その信念で医療に携わる皆さんに、エールを送りたいと思う。
『呪の思想』 白川静・梅原猛 平凡社
中国関係は私の守備範囲外のため、注釈まで読んでいたら、やたらと時間がかかってしまいました。
漢文・中国思想は高校以来・・・。忘れちゃってましたね~。
でもそんな知識がなくてもいろいろ勉強になりました。
よく見る漢字の成り立ちが出ていて、それがけっこう血なまぐさい成立のしかただったり、多くは祭祀関係からできてきたり。(才や裁などの文字の成り立ちのページはとてもおもしろい)
古代の死んだ妊婦の埋葬のしかたがアイヌのばあちゃんの説明でわかるとか、古代の「死」と「再生」の思想とか、征服した民族を、滅ぼしてしまって敵にするよりも、その神様を祀って残し(御霊信仰)、自分たちの祭りに吸収してしまう方が支配するのに都合がよいとか、中国と日本の精神的な文化史のつながりが少しわかりました。
日本の仏教がなぜ「葬式仏教」なのかというと、日本では縄文の昔から、「葬い」というのがとても重要視されていて、仏教がその形式を引き継いだから、というのがなるほど、と思いました。
マニアックな内容ですが、漢字の好きな人は読んでみるとおもしろいと思います。
『宗教練習問題』 ひろさちや 新潮文庫
この方の著作を読むと、目から鱗の宗教論で、宗教についてのいろいろな誤解が解けてきます。この本は、練習問題を出して、その答を解説する方式で展開していくので、けっこう考えさせられ、でもおもしろく読めます。(特にイスラム教については、ぜひ読んでおいた方がいいかと思いました)
神の思し召しと思って自然にまかせようとすることがホンモノの宗教の態度。ホンモノの宗教は、「世間の奴隷」にならず、「自由人であれ」と説いている。ホンモノは、先祖供養をしないと不幸になるなんて脅さない。
また、宗教と道徳とは別物。道徳は結果で判断する。なので、道徳は罰金などを科すと、うまくいくようになる。「ゴミを落とすな」は道徳だが、宗教は、「ゴミを気にするな」である。
これらのくわしいところは、読んでいただけるとなるほど、と理解できると思います。
ところで採点もできるようになっていて、私がやってみたら181点(250点満点)で、著者によると、良識派ということでした。まあ合格点をいただいたかな。
ひろさちやさんは、自分のことを「へそ曲がり」とおっしゃっていますが、この本を読むと、ホンモノの宗教者は、みんなへそ曲がりなのでは・・・と思いました。(一休さんもそうですね・・・)
『自閉症だったわたしへ』
原題『NOBODY NOWHERE』ドナ・ウィリアムズ 河野万里子訳 新潮文庫
自閉症のお子さんを持つ親御さんや、精神科医・小児科医の方の自閉症に関する本はけっこう見かけますが、自閉症と診断された本人による本というのは、なかなか見られないと思います。
この本は自閉症という心の障害を持ちながら、懸命に生きてきた著者の叫びなのだなと、読み終えて改めて感じました。
自分の殻の中で生きていた幼少時代。母親からの虐待。家族の崩壊。
「外」となんとかコミュニケーションを取ろうという気持ちを持ってはいるが、なかなかうまくできない、そしてまた自分の中に入ってしまうことの繰り返し。
キャロルとウィリーという二つの仮面を付けることで、外との折り合いをつけることを覚えていくドナ。
男達に翻弄された十代。ある精神科医との出会いによって影響を受け、学び直すことを決意して以降は、今までに欠けていたものをもぎとるような勢いで成長していく。
一人でオーストラリアを出て、ヨーロッパへ旅をするまでの強さ、そして、もう仮面をつけなくてもいい、自ら「生きる」力を、身につけていったドナの姿に、感動を覚えました。
ドナの視点による母親の記述からは、娘に対する屈折した感情が表れてきますが、でも娘を虐待しても嫌っても、どこか捨てきれない母親の姿もちらりと伺えるのがちょっと心に残りました。
自閉症の特有の行動などに関して、こういう心の表現なのだ、こういう意味なのだという示唆もあり、心にとめておきたいと思いました。特に、直接交流を図るよりも、間接的に、物を媒介としていくのがよいということには、なるほどと思いました。
自閉症も、個々により違いはあり、ドナもまた一つの事例かと思いますが、少しだけ、自閉症の子どもたちの心の中がのぞけたような気がするし、彼らを理解する助けになるような気がしています。
『梅原猛の授業 道徳』 梅原猛 朝日新聞社
中学生向けに講義した道徳の授業を起こしたものであるので、読みやすく、わかりやすい。梅原さんは仏教の人なので、宗教を説明した上で、そこから道徳について説明している。キリスト教やイスラム教やユダヤ教などの宗教についても語られていますが、私は日本人のせいか、やはり神道(注:多神教としての神道であって、国家神道ではない)と仏教の考え方が一番しっくり来る。
全体的な内容としては、日本の道徳教育がどのように行われたかという話、「殺してはいけない」「嘘をついてはいけない」「盗んではいけない」という3つの戒律の話、人生をよりよく生きるために必要な徳の話で構成されている。
初めて知って驚いたのが、サルは同族を殺す風習がある(新ボスが、旧ボスの子を殺し、母ザルもそれを止めない)ということ。そうならばサルの進化型であるヒトが殺人をおかすのは、サルから受け継いだ遺伝なのか?とちょっと考えさせられた。
「殺してはいけない」という戒律の話はあったけれど「なぜ殺してはいけないのか」というのが話されていなかったのがちょっと残念。自分の中ではそれに対する答えは一応持っているのだけれど、梅原さんがどう言うのか知りたかったな。
「いただきます」「ごちそうさま」の精神が今一番欠けているとの話。この言葉が道徳を簡潔に表しているかな・・。
そして梅原さんの言う、道徳の根本とは、「母の愛」だそうです。
『進化しすぎた脳』 池谷裕二
中高生向けの講義をおこしたものなので、とても読みやすいです。
その証拠に、一日もかからず一気に読んでしまいました。
脳について、いろいろと考えを改めさせられる部分があり、「へぇ」の世界でした。
細かい説明は、読んでもらうととてもよくわかるのですが、たとえば、
従来は、脳は体をコントロールするものだと考えられていたけれども、むしろ身体が脳をコントロールしているということ。もちろん脳は身体をコントロールしているけれど、それと同時に身体も脳をコントロールしているということ。
だから脳と身体は切り離すことはできないということ。
脳というのは意外にあいまいなものであるということ。
脳は覚えなければいけない情報を有用化して保存するために、事象を一般化する「氾化」ということをしている。その氾化をするために、脳はゆっくりと、あいまいに情報を蓄えていくということ。 あいまいさと学習の遅さが重要。正確無比な記憶というのは応用できないから役に立たない、ということ。
神経細胞のはたらきについてのところで、ひとつだったらわかる、2つでもかろうじて実験できる、でも3つになったら何が起こるか予測できない、という「三体問題」とか「複雑系」とかの部分もおもしろいと思いました。(特に魚の群れの説明がよかった)
マウスとかサルとかウサギとか、いろいろな実験台になっていて、それが人間の脳の働きを知るために役立っているということも忘れてはならないですね。
池谷さんは、アルツハイマー病の治療に関する研究にも携わっています。ずいぶん進んできた脳科学が、病気の治療にも役だっていることは、とても心強いものです。(2004.12.30)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- おすすめの絵本、教えてね♪
- 「うしのもーさん」おおきなおおきな…
- (2025-03-06 18:30:09)
-
-
-

- 中学生ママの日記
- 英検対策セットが10%ポイント還元
- (2025-03-05 07:32:39)
-
-
-

- 子供服セール&福袋情報★
- 【500円CP対象】【95%セール】アンパ…
- (2025-03-05 07:30:09)
-
© Rakuten Group, Inc.