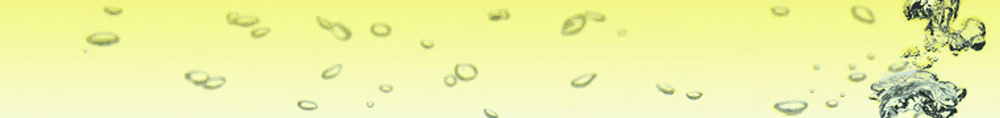小説 BLACK POST 1
それは、相手が心の扉を開いていないからだ。
だから、あなたもその人の想いが入る扉を開ければ
きっとその人の想いが伝わるよ。
第一章
1 二つの死で始まる物語
わたしが小学生になる前の年、十一歳年上の兄が死んだ。
死因は交通事故による頭部の強打。兄は交通事故にあって、死んでしまったのだ。
その時は夏の時期。事故が起こったときは夕闇だった。薄暗くて、恐ろしい夕闇。わたしは幼稚園に迎えにきてくれた兄と手をつないで歩道を歩いていた。隣の車道はあまり車が通らない道だった。
わたしは二歳くらいの時に父も亡くしている。前からの心臓の持病だったらしい。
父が死んだ時、病院に母と兄と弟の秋(しゅう)とわたしの四人で向かった。着いた時、母は抱っこしていた秋を近くにいたナースにあずけ、ベッドで寝ている父の顔をさすって酷く泣き続けていた。まだ二歳だったのに、その場面はとてつもなく覚えている。
その時、わたしの隣にいた兄はわたしと同じくらいの高さにしゃがんで、手を強くにぎった。その手はとても熱かった。
兄の顔を見ると、目には涙を溜めていて、その雫は頬にすっと伝って、落ちていった。泣いている。
「今度は俺が・・・今度は俺がお前たちを父さんの代わりに護ってやるからな。お前たちが大人になっても、ずっと護ってやるから・・・!」
今まで優しい口調だった兄が、このセリフだけはちがう人に見えた。わたしは兄の想いが伝わったのか、泣いてしまった。
その時、兄は十三歳だった。
それから三年が経った。
兄は十六歳。わたしは五歳。父が死んでから、兄がわたし達の二人目の「お父さん」だった。兄は毎日毎日、わたしと秋を幼稚園に迎えにきてくれた。迎えに来てくれない日なんて一日もなかった。
父が死んでから、母は働きに出た。その間、兄がわたし達のお世話をしてくれた。
中学に入った時、父が死んだあと、今まで大好きだったサッカーをやめて帰宅部になり、一度も友達と遊ぶこともなくわたし達をお世話してくれた。そして高校は入らず、家計を支える為にきついアルバイトをしていた。そして、迎えに行き、家に着いたらご飯を作り、食べた後は遊び相手をしてくれた。そしてわたし達が寝るまで見守っていてくれた。今思えば、兄はきついアルバイトで疲れているのに、その後もわたし達の相手をし、一日が終わった時はとても疲れているはずなのに、兄はいつも笑顔でわたし達に接してくれた。
もう、何度お礼を言ってもたりないほど・・・。
事故が起こったときは夕闇だった。薄暗くて、恐ろしい夕闇。幼稚園に迎えに来てくれた兄がわたし達の真ん中にいて、そして手をつなぎ、道を歩いていた。隣の車道はあまり車の通らない車道だった。いつも、わたし達はここを通って家に帰っていた。その日もいつも通りに兄に幼稚園であったことを話していた。
いきなりだった。急に兄は手をわたし達から離し、車道へと歩いていった。車道の真ん中には茶色い長い髪の女性が立っていた。
そこからよく顔は見えなかったけど、でも兄の方に顔を向けていた。
「お、おにいちゃん・・・?」
わたしは兄に話しかけたけど、振り向いてくれなかった。どんどんわたし達から離れていってその女性へと近づいて行った。よくわからないけど、わたしは車道は出て、兄の後を追おうとした。でも、わたしの服の袖を秋が掴んだ。
「どこに行くの?おねえちゃん。」
秋の目はまるでお兄ちゃんとわたしがいなくなってしまうんではないかという不安な目していた。わたしは秋の手をはじき、そのまま兄の方へと走った。
わたしにもよくわからなかった。何でわたしは兄を追っているのか、今思えばわたしは予感していたのかもしれない。兄がいなくなる事を・・・。わたしは思わず叫んだ。
「おにいちゃん・・・!」
その時、兄はこっちを向いた。その時、その目はぬれていた。また泣いている。その直後、兄はふっと横を見た。そして、血相を変えてまたこっちを見て
「春!戻れ、危ない!」
そんな顔をした兄を見たのは初めてで驚きのあまり立ち止まってしまった。その時、まぶしい光がわたしの顔を照らした。一台のトラックがこっちに走ってきた。まだ小さかったわたしの姿を運転手は全然気づいてないようだ。平然とした顔で運転したいた。そして、トラックがわたしの体にぶつかりそうになった時、急に目の前が真っ暗になった。それと同時に足が浮かんだような気もした。
目を開けるとわたしは道路に寝転がっていて、わたしの上には誰かが、わたしを抱いているような格好でのっかっていた。その頭からは、どす黒い液体が流れ続け、ぴくりとも動く様子がない。わたしは一体それが何なのかさえ、思うヒマもなく、そのまま気絶してしまった。その後だった。女性の声でお兄ちゃんの名前を呼ぶ声がずっと聞こえていた。
気がついたらわたしは病院のベッドで寝ていた。わたしはよく今の状況がわからないまま、しばらくぼーっとしていた。するといきなり視界に秋の顔が出てきた。その顔をよく見ると、何か言いたげな顔をしていた。
「秋・・・?どしたの?」
「おにいちゃんが・・・死にそう・・・。」
その言葉を聞いたとき、目の前が真っ白になった。ベッドから飛びあがって隣のベッドのカーテンを開いた。ベッドに寝ているのは頭に包帯が巻いており、体の隅々まですり傷がある兄だった。その周りには医者とナースがうろうろしていた。兄の口には酸素マスク、その周りはピッピッと音がなる色々な機械。わたしは一体どうなっているのかわからなかった。その時だった。急に兄の手がわたしの手を握った。
兄の顔を見るとその目は細くなっていて、瞳が曇っているように見えた。そして、兄は口についている酸素マスクをとって、わたしにこう言った。
「春、ケガしてないか?」
ピ――――――
かん高い音とともに兄はわたしの手を離した。いっきにその温もりを失ったわたしは泣き始めた。この手にかすかに残っているお兄ちゃんの温もりを離さぬようずっと手を握りしめた。
やっとわかった。何でわたし達がここの病院にいるのかを。それはわたしをかばった兄があのトラックに引かれたからだ。あの時わたしの上にのっかっていたのは兄だったのだ。わたしをトラックから護るためにかばったのだ。そして、自分が死にそうなのに最後の言葉はわたしへの心配の言葉だった。
その後、医者の低い声がした。
「1993年、八月二十日、午後八時二十五分。森泉冬季様、ご臨終でございます。」
その時、花火の音が聞こえた。その花火は兄の死を喜んでいるようだった。
兄の死から十三年経った。
~つづく~
© Rakuten Group, Inc.