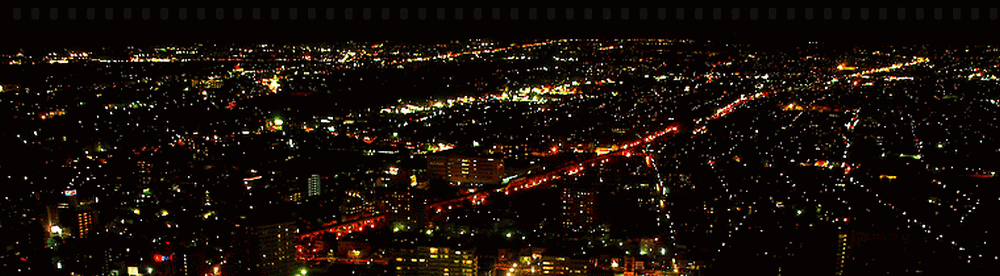過去の日記より~ザ・ビートルズ編2
2003・11・13 ザ・ビートルズの『新譜』である『LET IT BE...NAKED』
ザ・ビートルズの『新譜』である『LET IT BE...NAKED』が日本で世界に先駆けて明日(一部では既に今日...)発売となる。別段このアルバムに<新曲>が収録されている訳ではないが、ボーナス・ディスクには未発表のセッションの曲が収録されている。曲名が出ていたけどどういう形での収録かの情報が一切発表されていないから、買った時のお楽しみだ。アンソロジー3のバージョンとどれだけ違うのかな?。
このアルバムは明日買う予定だけど買ったら早速聴いて、ここに印象を書いてみたい。
でもこれってやっぱりCDショップで売れまくるんだろうね。
2003・11・14 ...NAKEDを聴いての感想
今日は ザ・ビートルズの『LET IT BE...NAKED』 を早速買ってきた。印象としてはそれらの曲で若干違うけどフィル・スペクターのミックスを一端全部カットしている。既に海賊盤とかで聴いていた印象とは若干違っていたのも事実。...NAKEDとは<裸、素のまま>とかの意味が含まれるけど、今回のリリースは<裸>というニュアンスとは若干違う。オリジナルのアルバムでは曲間のおしゃべりがあったけど、今回はこれらは全てカットされた。その代わりにボーナス・ディスクに一連のセッションでの会話が納められている。中身は、ライヴ再開への話し合いが中心で合間に未発表の曲やセッションの断片が収録されている。
それでは各曲の印象を自分なりに記してみたい。
1.GET BACK(LENNON-McCARTNEY)
このアルバムの本来のタイトルは是だったし、今回のアルバムのタイトルもこれが相応しいと思う。すでに収録されているのと大差は無い。オリジナルと比べると最後の部分のF.O.(フェード・アウト)が若干早いのが分かる。
2.DIG A PONY(LENNON-McCARTNEY)
ルーフトップでのセッションで演奏されたのがベースになっている。これも大差は無い。出来ればイントロの演奏の後にポールが<ALL I WANT IS~>と言ってから曲が始まる部分も加えて欲しかった。映画でもその部分は紹介されているのにね、何故かな?。
3.FOR YOU BLUE(GEORGE HARRISON)
これはオリジナルではよく聴けなかったジョージのアコギがはっきりと識別できる。ジョージのギターが好きな人にはこのテイクの方が納得すると思う。この演奏は映画でも披露されていて、ポールがピアノをジョンが洋子のリップスティックでスティール・ギターを弾いている。
4.THE LONG AND WINDING ROAD(LENNON-McCARTNEY)
この曲のアレンジをめぐってポールとフィル・スペクター(殺人事件で公判中)が対立。是が解散の一因とも呼ばれている。既に映画やアンソロジー3で是に近いテイクが演奏されているからさほど驚かないと思う。最近のポールのライヴでもこれに近い形で歌っているのでポールもこのテイクで満足だろう。仰々しいオケや女性コーラスはやはり不要だと思う。ポールのピアノもいい味出しているけど、中間でのビリー・プレストンのオルガンの間奏もこの曲にアクセントを付けている。映画でのテイクがそのまま使用されているから聴き慣れているテイクだ。オリジナルと比べて若干歌詞の一部が違ったり、YEAH YEAH YEAHと言ったラストもここには無い。この曲のアレンジはこれでいいと思う、これでポールも満足なのではないでしょうかね?。
5.TWO OF US(LENNON-McCARTNEY)
これはオリジナルと比べて目立った変化はなくて、若干ジョージのベースの音が上がっている?位かな。映画でもジョンとポールのアコギによる演奏とボーカルが聴ける。アコギの音もオリジナルよりはこちらの方が若干強調されている様にも感じるのと、こちらの方がF.O.の口笛が少し早いのが違い。ポールは今年になってからライヴで披露しているが、相手は当然ジョンではなくてバンドのギタリストと。青春の一ページかの様な歌詞も見事にはまっている。映画『I AM SAM』でもカバーが披露されている。
6.I’VE GOT A FEELING(LENNON-McCARTNEY)
ルーフトップでの2つのテイクを細かくつなぎ合わせて作ったテイク。これって本当にNAKEDと言えるのかな?。違いはビリー・プレストンのオルガンの音が強調されていてスピーカーからもはっきりと聞き分けられる。これで一層ライヴ感が協調されている。元々はポールの曲にジョンの未完成の部分を一つにして強引に完成させた曲。今回のアルバムでは一番手を加えられた曲だ。ジョージのギターもオリジナルとは若干違うのが分かる。
7.ONE AFTER 909(LENNON-McCARTNEY)
オリジナルとは同じテイクらしいが、こちらの方のギターが寄り一層協調されている。元々はジョンがリバプール時代に作曲して1963年に録音したがボツになっていた。そのテイクはアンソロジー1で聴ける。曲の最後がいきなりやって来るような編集に変えられた。オリジナルはラストにおしゃべりがあったけど今回はカットされているので、その影響かも知れないがチョッと唐突に感じる。
8.DON’T LET ME DOWN(LENNON-McCARTNEY)
オリジナルには含まれていなくてシングル『GET BACK』のB面としてリリースした洋子への愛を語った曲。オリジナルと違いこれはルーフトップでの演奏。ビリー・プレストンのオルガンとギターがスタジオ盤に比べて強調されている。
9.I ME MINE(GEORGE HARRISON)
ザ・ビートルズが1970年の年始に録音した最後の録音曲。映画でもスタジオでの演奏が披露されている。オリジナルはフィル・スペクターがオケを加えて彼らしいサウンドに仕立てている。コーラスはジョージとポールが担当している。タイトルは自我を押し立てるポールへのあてつけと言われている。編集で曲は録音時より長くなって発表された。
10.ACROSS THE UNIVERSE(LENNON-McCARTNEY)
元々はホワイト・アルバムでのセッションで録音されてチャリティー・アルバムに収録された。このセッションで再度引っ張り出されて収録されたが、ここでもフィル・スペクターによりオケと女性コーラスが加えられた。チャリティー収録盤はイントロとアウトロに鳥の鳴き声のS.E.が入りコーラスではファンの二人の女性が飛び入りで入り加えられたので、このテイクとは違う。アンソロに収録バージョンもこれらとは異なるから今回で都合3つの異なるバージョンが存在することになる珍しい曲。歌詞は、洋子を通じて松尾芭蕉に影響を受けたとも生前語っていた。今回のバージョンではオリジナルよりはこっちがアコギでの演奏が強調されている。バックで流れるウイ~ンという音がする楽器はタンブーラというインド楽器。
11.LET IT BE(LENNON-McCARTNEY)
ここでの演奏は映画で披露されたジョージが間奏でギターソロを弾くバージョン。最後のパートのリンゴのドラムスがここでは異なるし、フィル・スペクターが加えたオケも無い。ギターの入り方も微妙に違うのがここでも良く分かる。この曲もシングル、オリジナル、今回とすべてテイクが微妙に異なる。
オリジナルとの違いをメインに書いて見たが、オリジナルを聴いた事がある人は当然多いけど曲順も違うのにはきずいたかな?。後は、DON’T LET ME DOWNがシングルB面だったのがここではアルバム入りしている。逆に、『DIG IT』『MAGGIE MAE』や曲間のおしゃべりがカットされた。『DIG IT』には本来のダラダラとした長いバージョンがあるのに何故かカットされている。それに、このアルバムは当初は『GET BACK』で発売される予定になっていて何度もデモ・バージョンが制作されたがその都度却下された。その中には 『TEDDY BOY』 も含まれていた。オリジナルにも結局最終編集時点でカットされてジョージの『I ME MINE』と差し替えられた。この曲はその直後のポールの最初のソロ・アルバム『McCARTNEY』にバージョンを替えて収録された。ザ・ビートルズのこの曲は結局はアンソロジー3で一部をカットして収録して陽の目を見た。今回の構想でもカットされていたのは不思議だ。アンソロジー3でも今回の...NAKEDと同様にゲット・バック・セッションのリハを収めてあるが、ある意味ではこちらの方が...NAKEDかも知れない。
ジョンとジョージが既に鬼籍に入って仕舞いリンゴとポールが音頭を取ってこのプロジェクトを完成させた。なかでもポールが主導権を握っていたのは間違い無いだろう。盛んにザ・ビートルズの新作と歌っている宣伝文句が見られるけど、厳密には違う。<再編集盤>とでも言った方が適切かな。フィル・スペクターの過度な装飾を排除して今回のアルバムが登場した訳である。ポールもリンゴも今回の結果には満足している(だから出したんだよね)そうだが、果たしてこのアルバムを聴く事が出来ない二人がいたら果たして今回のプロジェクトは成り立ったかな?。特に、ジョージはあらゆる意味でこのセッションには嫌な思い出しか残っていないだろうから。この映画の方のDVD化も間もなく実現するのでそれが決まればこのセッションも30年を越えてやっと終わりを告げる事になる。
日本では、この盤はCCCD(PCでのコピーが出来ない)で発売するそうだ。これは、音質の劣化を招くしPCを傷める可能性がある代物なので発売前から大ブーイングの荒らしが吹き荒れている。何を隠そう自分もこの後に輸入盤も買う積りです。それに、もう一つ2枚組ではなくて1枚で出して欲しかった。2枚で60分を切る収録盤なのだから本盤とボーナス部分に空白を入れればオリジナリティーも保てると思うな。
今回の発売に合わせてCDショップでも大キャンペーンを張っているし(ビートルズには不要?)、TVでも盛んに是を取り上げている。そういっている今もTVで放送しているよ。このアルバムもやはり世界中で売れまくるのは間違いないし、是をキッカケにまた爆発的に新たなファンが増えるのに違いない。こうしてザ・ビートルズはどの世代にも存在するし、世代を超えての交流にも一役を買っている。更に国籍、人種、肌の色に関係なくレコードが発売されている国なら何処にでもファンは存在する。少し飛躍して彼らの売り上げの多さから言って世界中に英語が広がる事にも貢献したのでは無いかな?。彼らのサウンドや曲を理解したいが為に英語を学んだ人達も少なくない筈だ。
ザ・ビートルズは20世紀だけではなくてこの地球上が生んだ財産であり、一つの文化であると断言したい。21世紀になっても彼らの肉体が例え滅びても人々の心の中には残り続ける。そしてかれらは ロックというジャンルを飛び越えて『THE BEATLES』という名のジャンルを築いた不滅のスーパー・スターである。彼らの音楽に出会えた自分は幸せだ。

2003・11・15 ザ・ビートルズ交遊録VOL.1~ERIC CLAPTON
エリック・クラプトンとビートルズのメンバーとは個々のレベルにおいても結び付きが強い。元は、ジョージ・ハリスンを通しての付き合いで『WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS』でのゲスト参加が最初の競演だった。ビートルズは原則としてその演奏は外部の音楽家達を招かずに制作してきた。外部の音楽家はごく限られた範囲で、メンバーの担当楽器外のクラシック系のアレンジを施す際に起用された程度だ。『FOR NO ONE』やジョージがインド音楽に傾倒していた時代にインド音楽の専門家が招かれた事はあった。そういった一部のゲスト以外はプロデューサーのジョージ・マーティンやマネージャーのマル・エバンスを駆り出したりして凌いでいた。特に、ジョンはキーボード関係をこなすしポールに至ってはドラムスもこなせるからこれで充分だったと思う。
そんな中でジョージによってスタジオに招かれたクラプトンの緊張感は想像が付く。最も彼位の実力の持ち主ならビートルズのメンバーの演奏力には負けない筈だけどね。彼の起用はビートルズ内部にもいい意味での緊張感を持ち込んだことは認めているし、クラプトンにも有意義なセッションだったそうだ。
ビートルズが解散してからは主にジョンやジョージとの交流が盛んになった。特に、ジョージとは後に妻のパティとの交流も積極的に?行った結果ジョージから奪う形になってしまう。その過程でできたのが彼の代表作『LAYLA』であるのは有名な話だ。しかし残念な事にパティはこの二人のロック・スターに愛され名曲も数多く贈られながらも、子供を宿す事は無かった。それが原因かは知らないがやはりクラプトンもジョージも子供は欲しかったそうだ。皮肉な事にそれぞれパティとは離婚して、その後に結婚した女性との間には子供が出来たのだった。妻を奪われても二人の交流は絶える事無く続き(結婚式にもジョージは出席した)、お互いのアルバムでの競演も常に続いた。曲での競演は『BADGE』が二人の共作名義で発表されているし、ジョージも『RUN SO FAR』を提供している。
クラプトンは現在来日中で精力的に1ヶ月をかけてコンサートをこなす予定だ。前回の来日中にはその盟友ジョージの死の報をコンサート前の楽屋で知ったそうだ。暫く黙ってしまったクラプトンは、悲しみをこらえてステージをこなす。観衆はそんなクラプトンの気持ちは知る由も無かったはずである。そして、ステージ上ではいまでも彼のコンサートでは度々披露される『BADGE』を歌った。その際には『THIS ONE IS FOR GEORGE!』と短く言ってから曲に入っていった。この科白を聞き逃したファンも多かったと思うがTVではしっかりと聞き取れた。
クラプトンにとってはジョージは年の近い兄のような存在だったとも伝わっている。ジョージがライヴから遠ざかっていた時に、クラプトンが多くの人達からジョージはどうしていると尋ねられていたそうだ。そんな優しいクラプトンの気持ちがジョージにやっとの思いで伝わった。ジョージはソロになってから1974年に北米をツアーで回ったが、レコーディングで喉を傷めて必ずしも好評ではなかった。この評判がジョージをライヴに対して臆病にさせていたのだ。そこで、クラプトンは比較的プレッシャーの少ない本国や米国ではない日本を選んだ。日本のファンの気質を熟知しているクラプトンはジョージに自分のバンドをバックに従えることを提案した。バンドを持たないジョージに対して見せた気遣いだった。何度か心の葛藤があって弱気になりかけていたジョージの背中を押して、遂に二人での来日コンサートが実現してライヴ盤まで制作した。
残念ながら自分はそのコンサートには行っていないけど、ライヴ盤でもその雰囲気は伝わってくる。その後は再びライヴ活動を封印したまま亡くなったジョージだからこの音源は貴重だ。そして、今再びジョージの追悼コンサートの(去年行われた)CDとDVDが今月末に発売される事になった。またこの模様は劇場でも公開される事になっている。このプロモーションの一環としてオリヴィア未亡人が日本に来ているらしい。クラプトンも現在日本でツアー中だし彼もこの追悼コンサートでは重要な参加者だからもしかしたら、この二人で何かしらの行動があるのかな?。
ジョージのパートが長くなってしまったがジョンとも一時期密接な関係があった。まだ、ビートルズに在籍していた当時に既に解散の方向性を打ち出していたジョンが彼に接近。トロントで行われたライヴに参加するために急遽呼ばれた。何とまともなリハーサルは行われずに、飛行機の中で簡単な打ち合わせをリハとしてやって望んだそうだ。この模様はライヴ盤にもなって収録されている。
リンゴはクラプトンから曲の提供を受けたりアルバムに参加したりして、ジョージ同様に長い付き合いを今でもしている。ジョージとの共作『BADGE』ではクレディットこそ無いがリンゴも歌詞の一部を提供している。『RINGO’S ROTOGRAVURE』というアルバムにはクラプトン作の『THIS BE CALLED A SONG』が収録されているが、ハードなブルースではなくてどこかカントリー・タッチの香りがする曲だ。1982年には『OLD WAVE』のなかの1曲で共作もしている。最新のアルバム『RINGO RAMA』にも参加している。
ポールとは唯一アルバムの中での競演は無いが、ポールとクラプトンはチャリティー・コンサートなどで度々一緒に参加している。その際のバックにクラプトンが付いてギターを披露する事は珍しい事ではない。先述したジョージの追悼コンサートでもこの二人は『SOMETHING』『WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS』で一緒に演奏している。前者では途中からはクラプトンがボーカルを取っているそうだし、後者ではクラプトン自らボーカルを取っている。このパターンは女王陛下の即位50周年記念コンサートでも見られたのでその再現だ。これはNHKの衛星(総合は?)でも放送していた。
以上がビートルズのメンバーとクラプトンとの交友関係を語る事実だ。メンバーの一部と関係はあっても全員とセッションを行ったのは珍しいパターンだと思う。それだけ彼の人柄とギターの実力が高く評価されている証拠だといえる。こうしてビートルズの音楽だけではなくて、そこに関わる人達の音楽を知ることも重要な事だと思う。何故、ビートルズが関係を持ったのか知ればビートルズの違った側面を覗く事も可能なのだ。自分はクラプトンも大好きで永年の彼のファンでもあり、武道館に観に行ったことも一度ある。是非、彼の音楽やバックボーンにも興味を持って欲しいと願う。
P.S.クラプトンは大の格闘技マニアで度々日本で開催される、イベントを観戦するために私的に何度も来日している。格闘技の試合を見ていると良い席で観戦しているクラプトンが一瞬写ることがある。英国人である彼が格闘技に興味が有るのは今までは知らなかった。ライヴでも10回以上来日しているので私的な訪日も含めれば一体何度来ているのかな?。今年の大晦日にもK-1と猪木祭りが有るので来るかな?。
■後日談1/10 年末の格闘技番組を見ていた限りでは彼の姿は無かった。流石の彼も若いカミサンを何時までも米国に残すわけには行かなかっただろう。それとも夫人同伴の日本ツアーだったのかな?。
2003・11・19 ザ・ビートルズ交遊録VOL.2~DAVID FOSTER
グラミー賞受賞経験者の超大物プロデューサーであるデビッド・フォスターが、かつてはジョージ・ハリスンが主宰するDARK HORSE RECORDと契約してキャリアをスタートさせた事は意外と知られていない。そのグラミー賞を1984,1991,1993年でプロデューサー部門で3度受賞しているのは流石だ。
彼は1949年にカナダの西海岸のヴィクトリア出身で今では、制作の方で名が知られているが当時はピアノの演奏の方でもセッションに参加していた。
ジョージ・ハリスンのアルバムには『EXTRA TEXTURE』(邦題:ジョージ・ハリスン帝国)(1975)で始めて参加した。ここではオルガン、ピアノ、ストリングスを担当している。 そして翌年の1976年には早くも幻と言われていた初プロデュース作の『JAYE P.MORGAN』を担当。インディー系のレコード会社からの発売であった為に、発売から間もなく店頭から姿を消し何時の間にか人知れず廃盤となった。その後にフォスターがビッグネームになってこのアルバムの存在が知れるようになった。ところが何時まで経っても再発されるずに2000年になってDREAMSVILLE RECORDから日本で再発された。一部ではかなりの高額で(5万円以上とも)取引されていたこの作品が遂に陽の目をみた。このアルバムでは後の盟友ジェイ・グレイドンも参加している。まだ27歳だったフォスターだが、このアルバムは全体的に彼のセンスが遺憾なく発揮されている。主人公の<ジェイ・P・モーガン>の存在よりは、フォスターの抜群のアレンジ能力によるAORテイストの満載のこのアルバムの<質>の方に注目が集まっていたようである。
フォスターはこの時のセッションにも参加している、JAY GRAYDONとコンビを組んで多くのアルバムの制作を引き受けた。二人でユニットを組んでミュージシャンとしても『AIRPLAY』を発表し高い評価を受けている。この二人が組んで制作して数々のAORの名作を世の中に送り込んだ。ジェイ・グレイドンの最近の活動は一切伝わってこない。フォスターは 最近の仕事では同郷のセリーヌ・ディオンのアルバムで曲の提供や制作にも手を出している。セリーヌの大ヒット『THE POWER OF LOVE』の制作もフォスターが担当して、セリーヌに初の全米1位をもたらした。 この曲はオーストラリア出身のエア・サプライも発表していたが、当時はアルバムの中の1曲として埋もれていた。そのアレンジとセリーヌのバージョンを比べると明らかに違う。ボーカルもエア・サプライは男性のラッセル・ヒッチコックが高音で歌うのに対して、セリーヌはドラマチックに歌い上げる。そんなセリーヌのボーカルをより一層引き立てたフォスターのプロデュースは見事の一言にに尽きる。 セリーヌが是ほどまでの地位を築いたのには、フォスターの力も大きく作用している。
他には、 シカゴの『素直になれなくて』、EW&F『アフター・ザ・ラブ・イズ・ゴーン』、ホイットニー・ヒューストン『オールウェイズ・ラヴ・ユー』、ボズ・スキャッグス、ナタリー・コール、ホール&オーツなど数え切れないほどの名曲やヒット曲に関わって来た。
ザ・ビートルズのメンバーとの関わりでは ポールとも関係がある。1984年の12月に4曲のセッションをポールと一緒にこなして、キーボードの演奏と共同制作者として名を連ねた。その中の1曲が1987年に発売された『FLOWERS IN THE DIRT』の中の収録曲『WE GOT MARRIED』だ。この曲はポールのライヴでも取り上げられた多少古い感じのロック調の曲で、この曲のギターはピンク・フロイドのデイヴ・ギルモアが弾いている。
リンゴや生前のジョンとの関係は今のところ確認されていない。
最近のフォスターの活動は一時ほど名前が取り沙汰されるケースが減ってきた。しかし、昨今の日本でのAORアルバムの再発ブームで彼のプロデュース作品もその中に多く含まれている。フォスターは特にスケールの大きなバラード・タイプの曲のプロデュースや曲作りに定評がある。ジョージがこの若き時代のフォスターを自分のアルバムに起用していた時代は、AOR調のタイプの曲調が目立っていたのは単なる偶然では無いだろう。ジョージは解散直後はスワンプやブルースに傾倒していたが、1975年を過ぎた辺りから1980年位の期間はAORに興味があった期間だ。ストリングスを配したアレンジをさせれば彼の右に出るものはいないだろう。彼の仕事によってその地位を確立したアーチストは数知れない。セリーヌ・ディオンとの仕事が落ち着いて、今度はどんなアーチストを我々に紹介してくれるのかが楽しみだ。
もし、AORのアルバムで何を買うか迷っている人がいたらプロデューサーの名前を見て<デビッド・フォスター>の名前があったら迷わず買って下さい。絶対間違いは無い。
2003・11・23 ザ・ビートルズ交遊録VOL.3~JEFF LYNNE
ジェフ・リンは1972年の8月にレコード・デビューしたELECTRIC LIGHT ORCHESTRA(略してE.L.O.)の中心メンバーとして活躍してきた。E.L.O.はそのコンセプトがロックバンドにクラシックのシンフォニーの要素を加えたものとしてスタートしていった。時代の変遷と共にそのサウンドは微妙に流行色を取り入れながらも、独自のすぐそれと分かる者を確立して来た。それは、ストリングスの導入と打楽器や鍵盤楽器との融合を目指したサウンド。複雑に音を重ねながら分厚いサウンドを利かせる、他には真似の出来ないシステムを作った。その中でもジェフ・リンは中心的な役割を演じてきて、作詞作曲やアレンジ等の全てを担当するに至り徐々にE.L.O.イコール<ジェフ・リン>となってきた。曲自体は取り立てて複雑ではなくて、むしろポップなイメージさえあるもののこの独特のアレンジでそれを発展させた。その結果単なるポップスも別の次元の曲となり独自のステータスと名声を獲得した。
70年代のDISCOブームもあってE.L.O.のサウンドもそうした時代の流れに見事に乗った。その結果6曲のベスト10ヒットを生み出して、更にオリヴィア・ニュートン・ジョンとの共作『XANADU(ザナドュ)』のサントラ制作でも主題歌がトップ10ヒットになった。当時売れっ子だったオリヴィアとE.L.O.との共作は大いに話題を提供した。
しかしシンセサイザーの発達と同時に当初のシンフォニー的な、楽器を沢山使っての演奏が意味を成さなくなってきた。80年代に入り徐々に勢いも失せて来たE.L.O.はメンバー・チェンジもあって、ジェフ・リンの個人プロジェクトの意味合いが強くなってきた。
ジェフ・リンとザ・ビートルズのメンバーとの最初の音楽的な関わりは、ジョージ・ハリスンの1987年のアルバム『CLOUD NINE』の制作をジョージと共同で行ってからだ。 1980年代に入ってアルバム『SOMEWHERE IN ENGLAND』の中の曲『ALL THOSE YEARS AGO』がヒットを記録して以来発表したアルバムは商業的には成功しなかった。そこでジョージは親交のあったDAVE EDMUNDSの紹介でJEFF LYNNEを呼んだ。ジョージは若いプロデューサーが自分の過去の栄光に敬意を払わないで、最新のテクノロジーを用いる事に抵抗感を感じていた。その点ジェフ・リンは自分の憧れの元ザ・ビートルズのメンバーとの競演を強く望んでいた。そんな彼ならきっと上手く行くと踏んで組んだのだった。
狙いは見事に当たりこのアルバムからは『GOT MY MIND SET ON YOU』というナンバー・ワン・ヒットをもたらした。これはルディー・クラークなる人物のカバーだが、彼はこのナンバーを独自のアレンジも取り入れてみせて見事に大ヒットに結び付けた。このアルバムからは『WHEN WE WAS FAB』もシングル・カットされてここでもストリングスを巧みに導入した。ジョージの得意とするインド音楽の演奏を最後に持ってきて、そのキャリアに敬意をさり気無く評しているしこの曲は『I’M THE WALRUS』風に料理されているのも彼の功績だ。このアルバムのシングルの発売にあたって、B面として新たに曲をレコーディングすることになりゲストには大物スター達が呼ばれた。ここから発展して生まれたのが 『TRAVELING WILBURYS(トラベリング・ウイルベリーズ)』 である。このグループはジョージ、ジェフ、トム・ペティ、ロイ・オービソン、ボブ・ディラン達が変名で組んだスーパー・プロジェクトだ。この中でロイ・オービソンは結成直後に亡くなってしまったのが悔やまれる。このメンバーで結局アルバム2枚と1曲が制作されて、そのPRODUCEにはジェフ・リンが大きな力を発揮した。このグループとしてツアーを行う企画もあったそうだが、前述したようにロイ・オービソンが亡くなったりレコード会社の利害関係などが絡んだのか結局幻となった。もし実現していたら大変な反響を呼んだことだろう。
このアルバムは翌年のグラミー賞で『最優秀ロック・グループ(グループ・デュオ部門)』賞を見事受賞した。
昨年のジョージの命日に行われた追悼コンサートにも参加。この企画は盟友エリック・クラプトンが、ジョージに縁のある人達に声を掛けて実現した。クラプトンは音楽監督として、ジョージの一粒種ダーニを含めてポール、リンゴ、ビリー・プレストン、ゲーリー・ブルッカー等が参加した。ジェフ・リンは『GIVE ME LOVE(GIVE ME PEACE ON EARTH)』でリード・ボーカルを披露している。ハウス・バンドとしてはギターでも参加して、CDのPRODUCERとしても名を連ねている。
このアルバムでの仕事振りがジョージと同じくアルバムに参加していたリンゴの信頼を得て、1995年からのザ・ビートルズのアンソロジー・プロジェクトの際に再び呼ばれた。ここではジョンが残した未発表のテープ『FREE AS A BIRD』に、残った3人が演奏や詞を加えて完成させるPRODUCEを一緒に任された。
ポールとはこの時が初対面だったが、その仕事振りを気に入ったポールがアンソロジーの仕事が終わった後の自分のアルバムのプロデュースを依頼してきたほどだ。その結果は1997年の『FLAMING PIE』で聴く事が出来る。彼の得意とする分厚い音を重ねる手法は控えめだが、随所に彼らしさも散りばめられているし丁寧な仕事は評価されるだろう。
リンゴとはジョージの先述のアルバムが初対面だと思う。その後は、アンソロジーのプロジェクトで再度一緒になったしポールの先述のアルバムでも一緒だった。
ジェフ・リンは2001年にE.L.O.名義で久し振りにアルバムを発表して、そこでもジョージとリンゴはゲストで参加している。ジョージはその年の11月にガンで亡くなっているのでこれは貴重なセッションとなった事だろう。
JEFF LYNNEはこう振り返ると生前のジョンとの直接の交流こそ無いが(テープではある)、3人とは交流がある数少ない音楽家である。アーチストとしてよりはプロデューサーとして3人の信頼を得た。彼の力なくして晩年のジョージは無かったと思うし、ビートルズのプロジェクトでも大きな力となった。是非、彼の足跡を辿る場合はE.L.O.の全盛期のアルバムを聴いて思いを巡らして欲しい。
2003・11・28 ザ・ビートルズ交遊録VOL.4~ERIC STEWART
エリック・スチュワートはウェイン・フォンタナ&マインドベンダーズのギタリストとしてレコード・デビューを果たした。このグループはその名が示すとおりにWAYNE FONTANAがリーダーとなったバンドではあるが、1965年に『THE GAME OF LOVE』が全米1位を獲得した。その後はヒットは出せずフォンタナはバンドを辞めてしまった。残されたメンバーで活動を続行して『A GROOVY KIND OF LOVE』が翌年に全米で2位を記録。バンドは解散後この時のメンバーだったERIC STEWART,GRAHAM GOULDMAN(グレアム・グールドマン)がコンビを組んで後に知り合ったKEVIN GODLEY(ケヴィン・ゴドレー)とLOL CREME(ロル・クレーム)と一緒に結成したバンドが 10CC だ。
1973年にレコード・デビューを果たしたバンドは順調に活動をスタートさせて、1975年には最大のヒットでロック史にも残る名作『I’M NOT IN LOVE』を発表した。この曲は全米で2位を獲得するヒットを記録して、度々カバーもされている。中でも1991年にウイル・トゥ・パワーによる現代的なアレンジによるカバーはトップ10に食い込んだ。
しかし、グループは徐々にその方向性を巡って意見の対立が表面化した。結局スチュワート&グールドマンのコンビは10CCに残留し、ゴドレー&クレームは離脱した。後者は80年代に入って映像分野で偉大な足跡を残し、数多くのアーチストのおPVを手がけた。どれも当時は斬新なイメージで作られていて、MTVなどを通して視聴者の度肝を抜いていった。
さて本題のエリック・スチュワートは1979年に交通事故で重傷を負い長期入院を余儀なくされた。ザ・ビートルズの中ではポールが10CCのメンバーとは密接に関係があったようだ。10CCが考案した実験的楽器<ギズモ>にポールも関心を持ち、<LONDON TOWN>のセッションでも用いて実際に演奏までもした。そして、ポールはウイングスが解散後にソロ・アルバムの制作に着手した。固定メンバーを失ったポールは親交のあったエリック・スチュワートを呼んだ。彼も10CCの活動は開店休業状態だったので、ポールのレコーディングに参加した。
参加したのは 『TUG OF WAR』~『PIPES OF PEACE』~『GIVE MY REGARD TO BROAD STREET』~『PRESS TO PALY』+アルバム未収録のインスト・ナンバー1曲の期間だ。一方ポールはエリックの10CC名義のアルバムには『...MEANWHILE』、『MIRROR MIRROR』に参加。 前者は1曲提供しただけで、その曲は『PRESS TO PLAY』での共作曲で未発表になった曲にグレアムが歌詞を追加したものだ。後者では2曲で参加してうち1曲は共作している。
ポールにとって70年代はウイングスのデニー・レインが常に脇役で支えてきた。80年代は中盤まではエリック・スチュワートが右腕となって支えてきた。最初に三作では演奏とコーラスでの参加だったが、『PRESS TO PLAY』では半分以上の8曲を共作して支えた。しかしこのアルバムはポールの80年代の中でも、結果的には商業的にも音楽的にも振るわなかった。エリックにとってポールは、自分が音楽的に憧れていた人物であり曲調も似ていた。ポールはエリックにジョンのようなパートを求めていたのだろうが、エリックには出来なかった。しかし別にこれをもってエリックの才能が否定されたわけでは決して無いと思う。
当初の二作では曲作り以外のほぼ全ての曲でギターやコーラスに参加。そして何とPVの『SO BAD』ではポール夫妻とリンゴ・スター、エリック・スチュワートのスタジオでの演奏シーンが観れる。このPVは似た内容の二つのバージョンが有るが、演奏するバックにはリンゴとポールの写真とともにエリックのもある。PVでは他に『PRESS TO PLAY』の中の『ONLY LOVE REMAINS』でのスタジオでの演奏でアコギを弾いている姿が映る。
ザ・ビートルズのメンバーとの交流では、自分が知る所ではポールとが一番親交が深いだろう。ポールとは’60年代のビートルズ時代から親交があったとも言われている。リンゴとはポールのアルバムで一緒にセッションをしているが、リンゴのソロ・アルバムには参加してはいないと思う。ジョージとの交流関係は不明だし、ジョンとの交流も無いものと思う。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天イーグルスにアツいエールを送ろ…
- 2004年に発生した中越地震から10月23…
- (2024-10-24 00:22:47)
-
-
-

- テニス
- テニスと恋愛は似ていると思う
- (2024-11-28 15:37:27)
-
-
-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…
- ★今朝の道路状況★
- (2024-11-29 07:14:53)
-
© Rakuten Group, Inc.