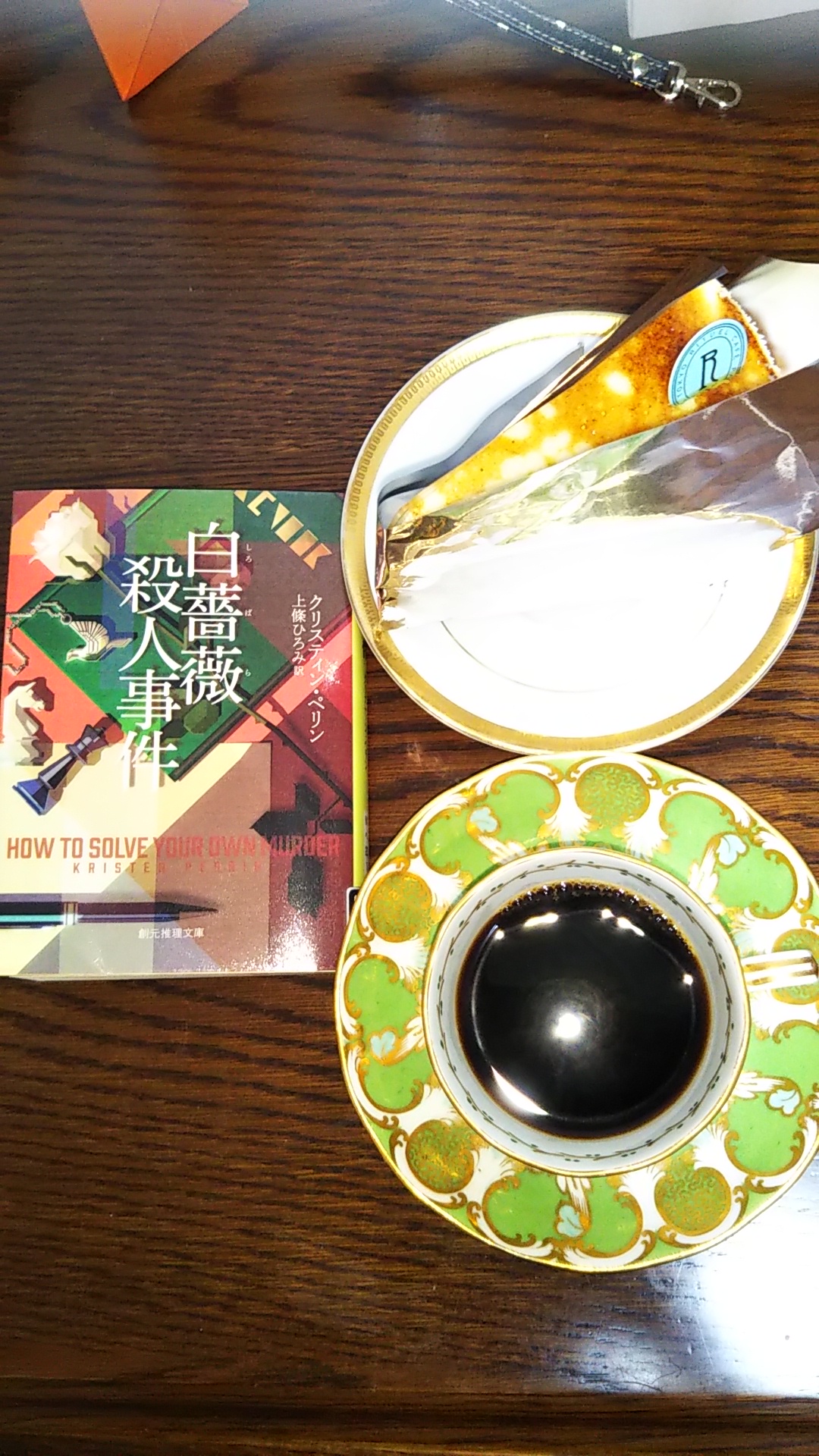星を統べるもの5
『私たちは、本能でその星の王を嗅ぎ分けるの。』
犬みたいなエイリアンだな。
『この星中を探し回って、やっとあなたを見つけたの。』
だから、俺は、王でも長島でもないんだってば。
『青き星の力を持つ、星の王。』
ちょっと待て!
『星の力って?』
まさか・・・あのときの・・・。
目の前の青い目がすっと細くなって、天使のような容姿には不自然な光が、ちらと見えた気がした。
艶のある唇がわずかに開いて、小さな呟きが漏れる。
『えっ?』
聞き取り損ねて、問いただそうとした瞬間、俺の顔面にガンと衝撃が訪れた。
目の前に、星が飛び散った。
『イカタコノミヤキ食べたい~~~っ!』
もう一匹のエイリアンをすっかり忘れていた。
(こいつらいわく)王様の顔面を足蹴にして、ベッドの上に仁王立ちになって雄たけびを上げるとはいい根性だ。
そもそもそれは、イカ焼きか?たこ焼きか?お好み焼きか?
『あれ?ここどこ?』
きょろきょろと、辺りを見渡す前に、おまえの足の下をまず見て欲しい。
バチコーン!!
ひどく景気のいい音がした。
さすがはエイリアンだ。いったいどこから、そんな大きなはりせんを出したんだろう?
『お行儀が悪いわよ!ケイロォーン!』
足癖の悪いエイリアンの名は、ケロヨンというらしい。
『ひどいよ。ミーア。』
みーみーと泣きながら、ケロヨンは頭を抑えてうずくまる。俺の上にだ。
『改めて紹介いたしますわおとうさま。私はミーア。これは弟のケイロン。どうぞよろしく。』
どいてくれたのはありがたいが、ベッドの上で三つ指つかれてもなぁ。
姉に押さえつけられて、無理やり頭を下げさせられたケロヨンは、上目づかいで俺を見上げながら、馬鹿にしたようにふ~んと声を漏らした。
『これが地球の王様かぁ。顔は良いけどなんか弱そう。なぁミーア。こんなんでほんとにだいじょうぶふう!』
弟の頭を押さえていた手のひらを肘に変えて、ほほほとミーアは微笑んで見せた。
・・・この姉弟の力関係が良くわかった。
『おまえら異星人だろ?なんだって、地球の王様とやらが、おまえらのお父様なんだよ?』
『あら。私たちを導き、育ててくださるんですもの。そういう存在を地球ではおとうさまというのでしょう?』
それとも、おかあさまだったかしら?
俺は、前のめりにベッドに沈んだ。
『由紀~っ!ご飯よォ。』
そのとき、のん気なおふくろの声が、階下から響いた。
とたんに、びょんと、ケロヨンが復活する。
『ごはん~っ。』
すかさず足払いをかけようとした、姉の攻撃を今度はひらりとかわし、ケロヨンは部屋を飛び出していってしまった。
『お、おい待て。』
とたとたと軽い足音が遠ざかる。
ふらふらと俺は立ち上がった。くそう。頭痛ぇ。
『おとうさま。だいじょうぶ?』
青い瞳がうるうると俺を見上げた。
ほだされちゃダメだ。いくら見かけが可愛い女の子でも、相手はエイリアンなのだ。
地球を侵略しに来たのかもしれない。
台所に下りていった俺が見たのは、食卓を侵略しつつあるエイリアンの姿だった。
中華どんぶりを抱えて、がうがうと犬食いをしている。
すでに空になった丼や皿が、幾つもテーブルの上に積み重ねられている。
『あらあら。ケイちゃん。やけどするわよ。』
おふくろがエイリアンの顔をふきんでぬぐっている。
『あう?』
金色の前髪についているのは、ごく細の縮れ麺だ。
『どうでい?美味いだろう?』
俺の特製だからなと、上機嫌で親父が、新しいどんぶりを持って現れた。
『おっ。おまえらも食うか?』
ミーアは、いただきますと言って、にっこりと食卓につく。
親父が渡した、ラーメンを上品につるつると、フォークに巻き付けて食べ始めた。
俺はわなわなと震えた。
『由紀。いつまで立ってんの?』
瑞希が、かに玉を取り分けながら、おれに向かってあごをしゃくった。
『なんで?なんでこいつら、なじんじゃってるの?こいつらエイリアンなんだぞ!?』
俺が唾を飛ばしてわめくと、お袋は汚いわねえと、眉をしかめた。
『なんだ由紀。異星人差別は良くないぞ!』
親父がぐりぐりと、ケロヨンの頭を撫でながら言う。
『異星人差別って・・・親父はなんとも思わないのかよ?こいつら変な力持っているし、どんなに危ない奴らか・・・。』
『俺のラーメンを食う奴に悪い人間はいない。』
きっぱりと、親父は言う。
だからこいつらは、人間じゃないんだってば。
『おかわり!』
ケロヨンが、ぐいとどんぶりから顔をあげた。
ま、まだ食うつもりか?
しかも親父のあのラーメンを・・・。
親父はといえば、ほいほいとうれしそうに、新しいラーメンを作りに消えてしまった。
『お父さんうれしいのよ。』
お袋がおれの前に、茶碗を置きながら言った。
『初めて、お父さんのラーメンを美味しいと食べてもらえたから。』
親父は、3年前までは普通のサラリーマンだった。
それも結構大きな商社の部長だった。
それが、なにを思ったのか、いきなり辞職。ラーメン屋を始めたのだ。
『夢だったんだ。』
だったらなんで、サラリーマンやっていたわけ?
おれの問いに、親父はにわか仕込みの怪しい江戸弁で、
『人生、いろいろあらぁな。』
と、呟いただけだった。
よくわからないが、ひとつだけ俺にもわかることがある。
それは・・・親父のラーメンが、とんでもなく不味いってことだ。
常連客は、けっしてラーメンを頼まない。
それでも、そこそこ店が人気が出たのは、お袋が作るラーメン以外の料理のおかげだろう。
一度、その人気を勘違いをした雑誌が『人気のラーメン店』と、うちの店を紹介したため、大量の犠牲者を出したことがあったが。
ともあれその後、店の暖簾が『王様らーめん』と名を染め抜かれていても、親父が朝の4時から汗水たらして仕込む、ラーメンを食べてくれる客は、たまたまふらりと入ってきた何も知らない哀れな子羊だけだった。
『ほらよ。』
親父が、大きなどんぶりをケロヨンの前に置く。
『大盛りにしてやったからな。』
はあ。こんなにうれしそうな親父は、初めて見るかもしれない。
『話を聞けば、まだ小せえのに、親元を離れて遠い星まで、修行にやって来たなんて偉いじゃねえか。由紀。お前も男ならこいつらの面倒を見てやんな!』
『そうよ由紀。この子達は、学校で貧血を起こして倒れたあなたを、家まで送ってきてくれたのよ。優しい子達じゃない。』
俺がぶっ倒れたのは、こいつらのせいだぞ。
『姉ちゃんは?』
なんとなく、聞く前から答えが、わかっているような気がしけれども、おれはほんのひと筋の救いを求めて瑞希を見た。
『だって・・・可愛いじゃない♪』
肩を落とした俺に向かって、由紀も可愛いわよと言われても少しもうれしくない。
『これからよろしく。おとうさま。』
『あぐうく。おごおはま。』
こうして、おれは16歳にして、二人の子持ちになってしまったのだった。
『星を統べるもの』6 に続く
© Rakuten Group, Inc.