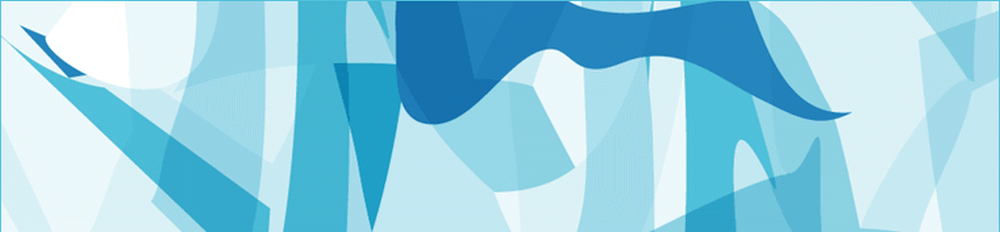『トリエステの坂道』 須賀敦子

素材がみつかりませんでしたが、新潮文庫から文庫でもでています。
日記にもチラッと書きましたが、書きたいことは巻末の解説に、非常にうまく書いてありました。とほほ。ということで、またもや分析はやめて単なる感想文をば書いてみたいと思います。
約12編のエッセイですが、それぞれが上質な短編を読むような味わいがあります。これはほとんどの須賀敦子の本にいえることですが。
内容は主に二つの事柄からなっています。敬愛する詩人や作家の話と、若くして亡くなったイタリア人の夫の家族のエピソード。
作家の文体のスピードと自分の呼吸があってくると、本を読んでいるというよりはその話の中に入り込んでリアルに体験しているような気がしたり、映画でも見ているように情景が生き生きとうかびあがったりすることがあります。滅多にない体験ですが、須賀敦子を読んでいる時にはよくあります。
たとえば「ふるえる手」。
ナタリア・ギンズブルグという女流作家の家を何度か訪問する、彼女の死後それを回想するという形で話は進んでいきます。
彼女の生前の家の前を通りかかったとき、須賀敦子の心に突然喪失感が広がります。最後に訪問したときのことがおもいだされます。
(引用)コーヒー沸しの柄が熱いので、彼女は着ているカシミヤの黒いセーターの袖をひっぱって、それを鍋つかみのようにして手をくるんでいた。ふちなしの黒い帽子を思い出しながら、私は手伝おうか、どうしようかとためらっていた。
前後の文章とあわせて読むと、彼女と作家の距離、その時の作家の状態までがこの一節に凝縮されていることがわかります。注ぎそこねたコーヒーがソーサーにたまっていく様子が、私の目にも見えるようです。黒いセーター、コーヒーといったモノトーンの描写にもかかわらず、「色鮮やかに」という表現がぴったりなくらいに。
類まれな観察力が女性らしい洞察力で瞬時に本質を探り当て、確かな文章力で表現されていて、読んでいて「読書の幸せ」という言葉がうかんできます。60歳をすぎて、初めて小説を書こうとして、その途中で亡くなったそうで、読んでみたかったな~と心から残念でなりません。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『冷徹社長の執愛プロポーズ~花嫁契…
- (2024-12-02 00:00:18)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 先生は患者としては良い?悪い?
- (2024-12-02 11:57:58)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…
- (2024-11-30 06:19:29)
-
© Rakuten Group, Inc.