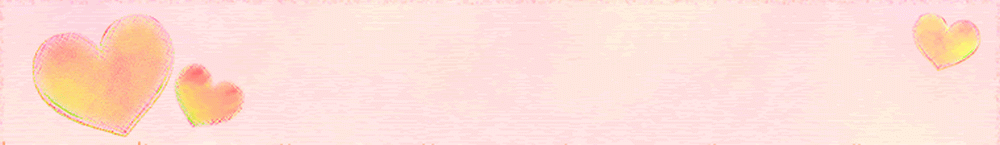三歳児神話
そうなの、子育て支援に関わる立場としては、一度ちゃんと知っておきたかったことなので、本当に「待ってました~」と大向からかけ声かけたかったくらいの内容。
しんどくて、短大を休みたいくらいだったけど、この講義の続きを聞きたかったから、頑張って学校に行こうと思わせる、
私にとってはそういう力のある(興味関心のある)ことでした。
掻い摘んで言うと、
「三歳児神話」とは、
「子どもが小さいうち(特に三歳まで)は、母親が側にいて育児に専念すべき、という考え」のことで、
1950年代半ばから言われ始めた。
1950年以前は、「大家族・地域社会」による子育てだった。
3世代に渡る大勢の家族メンバーたちは、手間のかかる農作業に励んでおり、母親=若い嫁は、農作業労働力として期待され、子育てはそのあいまになされるものだった。
すなわち、多くの母親は「働く母親」であり、母親だけでなく、祖父母や兄弟なども手伝って、子どもは育てられていた。
地域共同体として地域の人々のつながりが強く、子育てにもそれらの人々の関わりが欠かせないものであった。
家父長制のもと、夫や家長の「三くだり半」によって、当時の日本の離婚率は世界有数の高さだった。
子育ては母親以外の家族メンバーや地域社会の人々の目と手がかけられており、今は力を失った「血縁・地縁による、自然発生的な子育て支援」が、実は昔からなされていたのである。
しかし、
1950年代半ば~1970年代半ばにかけて、
「子育ては、家庭・母親責任論」が展開された。
経済の高度成長期を境にして、
大都市圏に移り住み、企業の雇用労働者(サラリーマン)が急増する。
この時代、妻は、
夫の長時間労働を支え(夫の家庭家事育児の時間も全て企業に差し出すため)、家事と育児に専念するように求められた。その時代に言われ始めたのが、
「子育ては母親こそが行うべき。母親は子育てのみを行うべき。」という「子育ての家庭・母親責任論」である。
特に、三歳児未満の子どもには母親による育児が絶対のものであるとする「三歳児神話」が強調されていた。
企業・国からのこのような期待に応え、多くの母親が専業主婦の道を選び、
「サラリーマンの妻で専業主婦」である女性の数もまた、
1955年の517万人から1970年の903万人へと倍増した。
「三歳児神話」が作られたときの論拠として使われたのは、3つの内容である。
1.乳幼児期が人間にとって非常に大切な時期である。
2.それほど大切な乳幼児期であるから、母親が不可欠である。
3.なのに、乳幼児期に母親が育児に専念しないと、子どもは将来心の傷を残す危険性が高い。
というもので、
実は、1は確かにそうであるが、
2.3.は、「別に、DNA的つながりの母親である必要はなく、愛着形成が持てる大人との親密な関わりであればよい」のであるが、
そこを無視して論理に飛躍がある。
1970年代に、ボルヴィーによって、
「発達の遅れや異常の原因は母親不在が原因している」という説が唱えられ、(本来これは、別に「DNA上の母である母親不在」ではなく、「愛着形成の相手としての母親役割を担当する人物の不在」を意味していたはずなのだが……。)この説が利用された。
それらの考え方によって、
日本の政府は、1970年代、
「保育所を作ると、母親が育児を怠ける」として、福祉予算を削減した。
1970年代後半から、子育て困難社会。
この時期になると、「育児不安」が話題になり始めた。
高度経済成長により都市化が進み、孤立した家族の中だけで地域社会の支えもなく、母親のみが子育てに専念する形態は、
近所づきあいの希薄さ、
夫の育児参加の少なさ、
母親になるまでの子育て経験の乏しさ、
などの要因もあり、
育児不安に関する心理学的研究も盛んに行われるようになった。
「育児不安」とは、
子どもの成長発達状態に悩みを持ったり、
自分自身の子育てについて迷いを感じ、
結果的に、
子育てに適切に関われないほどの不安を抱いている状態をいう。
今では、
そんなの当たり前にあるよね~、みんな不安だよね~、その中で何とかやってるんだよね~、私もそうよぉ~。って言えちゃうそんな状況も、
「育児不安」という単語で呼んで貰えるようになったのは、
実は1980年代以降で、
1980年代以前には、このように感じるのは「特別におかしい女性」で、まともな人間ではないので、奇異な目で研究材料として見られる感じがあり、その頃は、母たる女性がそのような感情を感じることがある場合、
そのような状態を
「母親失格」とか「母性喪失」という単語で呼ばれていた。
しかし、研究が進む中で、
そうではなく、
「血縁・地縁による、自然発生的な子育て支援」の機能しなくなった中で、
「近所づきあいの希薄さ、
夫の育児参加の少なさ、
母親になるまでの子育て経験の乏しさ、
などの要因があり」、
高度経済成長という経済上の便宜の為の、企業と国にとって都合良く動くための論理に煽られた中で追い詰められた当然の結果としての
「育児不安」の発生であることが見極められ、
またそういった視野狭窄の母親に囲い込まれた状態で育つしかない子どもの、経験不足による社会性や人間関係力の弱さも問題になってくる。
その結果、
「高度経済成長により都市化が進み、孤立した家族の中だけで地域社会の支えもなく、母親のみが子育てに専念すること」は、決して子どもにとっても育ちやすい環境では無かったことが明らかになったのである。
1990代~子育ての深刻化と「子育て支援社会」
行政側が、それまでの「母親育児責任論」の誤りを認め、方向を転換したことを、はっきり表明したのは、
1991年に発表された「健やかに子どもを産み育てる環境づくりについて」においてであった。
その具体化として、
1994年に「エンゼルプラン」
1999年に「新エンゼルプラン」
2003年に「次世代育成支援対策推進法」「少子化社会対策基本法」が施行された。
ねえねえ、みんな。
子育てしていてイライラすることって、あるよねぇ?
そんなの、誰だって普通だよね。
自分の体調だってあるだろうし、色々な要因が重なることだって、
タイミングの問題もあるだろうし、さ。
子育てしていて「イライラ」なんて、誰だって体験してる筈だと思うのは私だけ?
厚生労働省の「児童環境づくり等総合調査研究事業」(平成13年3月)の中にあるデーターでね、
「育児を巡る母親の意識」て言うのの中に、母親の意識比較があって、
「イライラすることが多いか」という質問にたいする答えのパーセントが出てるの。
1981年は、
「はい」……10.8%
「どちらともいえない」……41.8%
「いいえ」……46.8%
2000年は、
「はい」……24.6%
「どちらともいえない」……48.8%
「いいえ」……25.8%
この「はい」の増加と「いいえ」の低下を見て、
ほらね、育児不安が増加してるでしょ、ってこの数字を読む人も多いけど、
私すごく切なくなっちゃったよ。
1980年代初めのデータでしょ。
それまでは、育児不安の感情を感じたことがあるって告白する人は、
「母親失格」とか「母性喪失」という単語で呼ばれていたわけでしょ。
思っても「はい」なんて答えられないよね。
もしかしたら、
そんな風に「疲れた」とか「辛い」とか「不安だ」とか、思うことさえ自分に許せない女性も多かったんじゃないかと思うと、
切なくて、悔しくて、たまらなかったよ。
チャップリンのモダンタイムスじゃないけどさ、
高度経済成長のコマ(歯車)である労働者を、
猛烈サラリーマンとか、企業戦士とかって、持ち上げてさ、
長時間労働を可能にさせることを
企業・国から期待されて、
その期待に応える形の「子育ての『家庭・母親』責任論」と、
その期待に応えざるを得ない脅迫のような「三歳までは母親による育児絶対論(三歳児神話)」の風潮に丸め込まれて、
女性も子どもも夫(労働者)も利用されたんだ。
で、それで誰が一体幸せになったというの………、
と思うと、
ものすごーーーーーーーーーーく悔しくて、
授業中後ろの方の席で
「くそぉー!!! ばかにするな! ふざけやがって。悔しい~」
と、小さな声でブツブツ言いながらノートを取っていた私。
ちょっと、マジで目が涙目だったわ。
見直ししていないので、誤字脱字ご容赦。
また、時間のある時に直します。
取り急ぎ、書いておきたかったので。
もう、PC切り上げなくっちゃ。
明日も早いぞ。
明日も長いぞ。
うりゃ~。お休みなさい。
(2006.05.13ブログ)
© Rakuten Group, Inc.