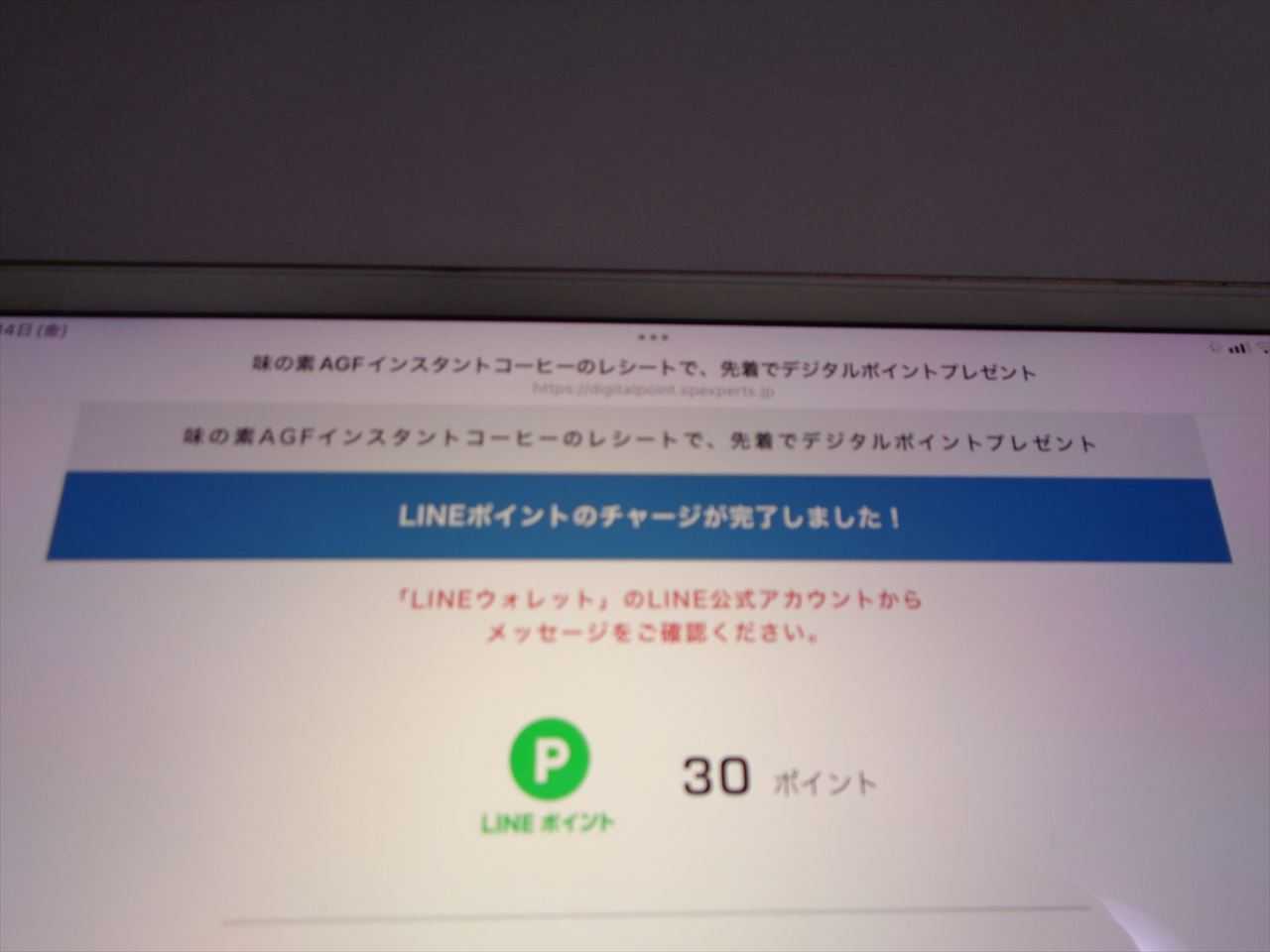幸せですか?
幸せですか?
携帯が鳴った。出るといきなりドスのきいた怒鳴り声である。
「コノヤロー! 金返さんかい!」
「はい? おかけ間違いじゃございませんか?」
「コノヤロー! 梨田の女房だろがっ、早よう返さんかい! このアマ! 耳揃えて返さんと、今すぐそっち言って暴れるぞ! バカヤロー!なめんじゃないぞ!」
あいつと結婚しなかったら、絶対に耳にしないで済んだ言葉であったろう。俗に言う『090金融』の暴力的な取り立てである。彩には身に覚えのないことだ。
「一体、いつお借りしたお金ですの?」
馬鹿丁寧な言葉になるのは、彩(あや)が興奮している証拠である。もしくは、とても不快なときに、必要以上の丁寧な言葉遣いをしてしまう。
「調子こくなっ!三ヶ月で返す約束だったじゃないか!」
呆れた。数年前から、居場所も知らない奴の借金なのだ。三ヶ月前に借りた金か。
「梨田とは十年前に離婚しておりますし、どこにいるのかも存じませんのよ」
「な、なにィ~? 十年前? おまえ、ナシダって名前だろ?」
「そうですけど」
「別れたら、同じ名前を名乗るな! ややこしい!」
聞けば、借金するのに連絡先として女房の携帯の番号を押さえたらしい。まあ、担保みたいなものだ。ちょっと無理をすれば作れる額を高利で貸して、家族を脅して取り立てる。返済金を踏み倒して逃げているため、消費者金融からも借り入れの出来ない人間に金を貸す。貸すのは五、六万。家族を脅せば十万が戻る。違法ではあるが、目先の金が欲しい人間がいくらでも飛びついてくるので儲けは上がる。
「梨田丈雄はあらゆる消費者金融のブラックリストに載っているはずですわ。どこに居るのかも存じませんよ。そちら様の方がご存知でしょうに」
「ご、ごぞんじもへったくれもあるかいっ! ひどい奴だ、あんたの亭主は!」
はんぱな裏社会の人間にまで同情される始末か、と、彩はため息をつく。
その男は、梨田丈雄の携帯番号と住所まで、彩に告げた。
「知ってもどうしようもないでしょう?」
彩がそう言うと、そこに電話をかけて「払ってくれないと、私がひどいめに合うから、早急に返してくれ」と言って欲しいと言うのだ。
「あなたの名前は?」
「リョウってんだ」
「リョウで分かるのね?リョウさんに返してと言えば良いのね?」
「ああ、頼んだぜ」
もっと不快なことをされるのかとおぞましくおもったが、そんな程度でリョウはひきさがった。必ず電話してくれよと念を押して。
遠くに住んでいるのかと思えば意外に近い。嫌な感じだ。
コール音、三回で相手は出た。
「結婚していたということまで後悔させるような真似はやめてちょうだい!」
「もうそっちに連絡が行ったのか?」
逃げ回って電話にも出なかったら、当然のように矢はこっちへ飛んでくる。馬鹿じゃないかと彩は思う。息子の名前まで担保にするような奴は親じゃない。裏社会は表の金融機関では担保にならないモノを担保にする。脅しのための担保なのだから。彩は、自分のした行動に後悔をしない主義だ。だから、この時までは結婚していたことを後悔してはいなかった。自分の人生には必然の悪だと思っていたのだ。
「宏の名前まで教えてお金を借りるなんてひどいわ。私と宏が取り立ての矢面に立たされるのよ。子供が可愛かったら、普通、隠すでしょう? 養育費なんか要求したこともないし、私の息子よ! あんたに親の資格なんかないわ!」
奴の言い訳けなんて聞きたくもないから、彩は速攻に電話を切った。そして、受信と発信に記録された「リョウ」と「丈雄」の番号を着信拒否に設定をする。
持って行き場のない怒りを抱えて、大きな窓越しにベランダの向こうの空を見る。天まで半ベソをかいている。女の私がこうしてまともに社会に向き合って生きているのに、なんて奴だろう。そういう奴と見抜けないで結婚した自分も悪い。
「ああ、やめた! 後悔するなんて、何の役にもたたない!」
途端に、また携帯の着信音が鳴る。表示は『公衆電話』である。出ないでおこうかと思った。着信拒否をされた丈雄が公衆電話から掛けてきた可能性がある。うるさいと思ったが、彩は逃げるのが嫌いな性格だ。いつもちゃんと向き合って生きることを常としている。気負って電話に出てみれば、見知らぬ女の声であった。
「由紀がお世話になっております。由紀の母でございます」
その声はとても恐縮した様子である。
「お待たせしました」
一面ガラス張りの喫茶店の中から、不安そうに外を見つめているその女性は、彩と同じくらいの年齢に違いない。
「由紀さんのお母さんですね。『美月』の梨田です」
もしかしたら、ものすごく遅刻するかもしれないからよろしくと、店のスタッフである美緒に連絡をした。彩はその日の出勤前に、『公衆電話』の声の主と会って話をする約束をしたからだ。
一見して『夫人』という風のその女性は、地味ではあるが質の良い、品をたたえた和装であった。彩は水商売のミズをくぐり抜けたあでやかさで、生活感のない着物姿である。同じ着物姿でもまるで違う。初めて会う二人は、自分の特徴を電話で伝え合っていた。
「着物を着ておりますから」
「あら、私も着物の女ですから、すぐに分かりますわ」
彩が約束の時間よりも早く着いたのに、すでに随分長いこと待っていたらしい。
由紀の母だというその女性は、夫の名刺を差し出す。大手企業の常務の肩書きだ。裏に自宅住所と電話番号が手書きされてあった。彩も名刺を渡そうと懐から名刺入れを取り出すと、名刺はすでに由紀から貰ったと、夫人が言う。
「ここに勤めているから安心して」と、由紀がそう言って渡したそうだ。由紀が彩の店に勤めることになった時、携帯の電話番号を書き入れて由紀に渡した名刺であった。
「それで電話をくださったのですね」
「ええ、あの子は、私がママさんと会っているとは知りません。ですが、もうママさんに相談するしかないのです」
由紀の部屋に上がれば、それはひどい暮らしが分かったという。
彩も由紀の事情を多少は聞いて知っていた。妻子を養うという感覚に欠落した男のために水商売に身を入れたのだろう。彩も似たようなものであった。おなかが空いたと泣く子供のために、手っ取り早かったからだ。
「分かりましたわ、お母さん。由紀さんと話してみます」
事情によっては、逆にこの親を説得することにもなるかも知れない。連れて帰りたがる母親に、私は大丈夫だから心配しないでねと、由紀は言ったそうだ。
「七年前に家を出ましてね、戸籍の付表を調べていたら、子供が生まれたときに入籍をするので居場所が分かったのですが、主人がね、そのうち泣きついて来るだろうから見守っていてやろうって言ったのです。勝気な娘ですから、反対すればするほど、また何処かに逃げて行くからって。今度もしばらく行方が分からなくなっていたのです。最近、また戸籍の付表が動きましてね。子供を幼稚園に入れるために住民票の登録をしたのです。そういうことでもなければ、住民票を移動できないような暮らしをしていたわけですよ」
「お母さんは、もう限界だとおっしゃるのですか?」
「ええ、七年間もあれば分かります。この先、あの男が由紀に幸せを与えるとは思えません。あの子も思い知っているはずなのに、今更、泣きつけない性格なのです。母親の私が一番良く知っております」
「男と女には傍から分からない幸福というのもありますよ」
「いいえ、あの子はこのままでは道を外します。母親だから分かるのです」
道を外すか、水商売への偏見だろうと、そのときはそう思った。夫に庇護されて生きてきた夫人には分かるはずもないと。だが、その日、店に遅れて入った彩の目は由紀の様子がいつもと違うのを感じ取った。由紀の母親に会ったからか、いや、それにしても妙だ。
その日は、「オーさんに送って貰いなさい」とは、言えなかった。
客の小鹿野が執拗だったし、それより由紀が変だ。
「オーさん、今夜は定時で閉店してからミーティングするから、悪いわね。アフターは無理よ」
「何だ、ママ、焼きもちか?邪魔するなよ」
「はいはい、ミーティングですからね。オーさんだってうちの経営の邪魔をしないでね」
やれやれと言って帰る小鹿野を最後に送り出して店を閉めた。
「美緒、悪いけど今日は先に帰って。由紀ちゃんと話があるから」
「え?私たち、ミーティングに残らないで良いのですか?」
一瞬美緒はとまどったが反射的に察して、他のスタッフと一緒にそそくさと店を出て行った。
「帰ろ、帰ろ。お疲れ様でした~」
察しが良い娘だと、いつも感心させられる。
由紀と二人だけになって、店のボックス席で向き合った。
「あんたの目は、オーさんとヤケで付き合うか、そういう目をしている」
「………」
「店外恋愛に口を挟む気はないけど、ヤケで付き合うのなら必ずお客さんを失うからね」
「……申し訳ありません」
「お金なの? ダンナさんはちゃんと働いているの?」
「ごめんなさい、ママ。少し前借りできませんか?」
訳を聞けば、夕方に由紀の母親が話したことが道理に思える。どうしても、由紀と孫を連れて帰りたいと由紀の母が言った。彩は、説得しなくてはいけないのはむしろ由紀の方にだと気が付いた。
「由紀ちゃんは実家を頼る気はないの?」
由紀の不安げな美しい顔がひくつく。黒目がちの目だけが異様に光っている。この娘が自分の美貌を武器に、器用に世間を渡っていける人間なら、それはそれでもかまわない。だがその美貌は、十年後には確実に嫌味で陰惨なものに変わるだろう。
「ダンナさんと別れたくないんだ?」
「実家は……別れるのが条件で、援助すると……」
「当然でしょうよ!」
彩は、とうとう今日の昼間の自分の出来事を話した。彩の母から電話が入る前の一件だ。自分の恥なぞ誰に話す気もなかったが、この娘の心を割るには、自分の恥から話さねばなるまい。
「何が一番大事?」
「子供です!」
由紀は迷わず即答をした。
「あなたのね、お母さんと私、同じ年なの。あなたが自分の子供が大事なように、あなたのお母さんもあなたが大事なの。よく分かるわ。若い頃の私とあなた、似たような苦労をしているもの。おかしいわね。さっき話した通り、ダメ男は何十年経ってもダメなままなのよ。今度こそ頑張るって、必ず言うでしょ?そして、ウソついて働くふりしてバレたら、言うでしょ?君に心配かけたくなかったからだって」
由紀はひどく驚いた顔をする。
「お母さんとこに帰りなさい。子供を連れて。お金は明日、用意するわ。お昼の二時ころ、うちのマンションに来てくれる?」
「実家に帰ることは考えてみます。前借りは、今夜は出来ませんか」
今夜のタクシー代もないのだろう。
「今夜は私がタクシーで送る。明日、タクシーで子供を連れていらっしゃい。二時ね。いただき物のケーキがあるわ」
マンションの地図を書き、タクシーチケットと共に由紀に渡す。
「明日はこのチケットを使って、必ず子供を連れてくるのよ」
翌日、時間通りに由紀がマンションを訪ねてきた。小さい人が二人、
めずらしい物を見るように、きょろきょろしながら後に続く。
「すみません。いたずら盛りで、ご迷惑をおかけすると思うので、ここで失礼しよ
うと思います」
由紀は玄関から上にあがろうとしない。
「ケーキが用意してあるわ。ほら、上がって、上がって」
子供たちがケーキをほおばるのを世話しながら、やっと由紀が白状をした。
「本当は私……死のうと思ったんです。でも子供たちの顔見たらそんなこ
ととても出来なくて……あの、それで小鹿野さんに相談してみようと思っ
たんです。いつも、困ったことがあったら、相談に乗るからって言われて
いたし……」
「それって、身体と引き換えにって意味よ!」
「ええ、覚悟はあります。だって私、うちの人にお家賃の支払いを頼んでいたのに、昨日大家さんから請求があって、もう三月も払ってなかったって。その上、うちの人、娘の幼稚園のために用意したお金まで持ち出してしまってて、何に使ったのか聞いても黙っているばかりで話してくれない……」
「だからもう、実家にお帰りなさい」
「出来ません、絶対に。そら見たことかと笑われるわ」
「で、他の男に甘えて生きていこうと思ったの?しかも不倫で?」
「………」
「そういうことになるのよ。実家に帰ることは、ある意味負けたみたいで辛いかもしれないわ。あなたの気持ちもよくわかる。人生はね、平坦な道ばかりじゃない。私だって、昨日あなたに話したように、次から次にトラブってる。でも、ちゃんと乗り越えて振り返れば、乗り越えたこと自体が幸せなのよ。乗り越えても、また次の山があるわ。でも、山はね、必ず頂上があるの。登るかぎりは一生、頂上にたどり着けないなんてことはありえないから。登り詰めたら、後は下りるだけよ。下りても、また山があるけど、人が生きるって多かれ少なかれそういうことじゃない? ただ、由紀ちゃん、あなたは少し怪我をして山を越える力が弱っているの。そんな時に手を差し出してくれた親ごさんに、頼るのは良くないことかしら? 今の由紀ちゃんにとって本当の家族は、ダンナさんじゃなくて、実家の方の人たちじゃないの? 家族に甘えて怪我の手当てが済めば、またあなたは山に向かえるわ」
我慢していたものが堰を切って溢れ出したのだろう。由紀のほほに流れるものがベランダから差し込む光で反射する。
「おばちゃん、おかあしゃんをいじめないで!」
いじらしい応援団だ。
「おばちゃんはね、お母さんをいじめているのじゃないのよ。大人が泣くのは悲しいときだけじゃないんだから」
小さい人たちに説明していると、チャイムが鳴った。
「由紀ちゃんのお母さんがお迎えにいらしたわ。勝手にお呼びしてごめんなさい
ね。このままいったん実家にお帰りなさい」
彩は、白い封筒を、たよりなく細い由紀の手に渡した。
「お給料を清算してあるわ」
「また遊びに来ても良いですか」と、何度も頭を下げながら、由紀は母親と帰って行った。穏やかな小春日和の午後である。何もかもを知り尽くしたようなやさしい日差しの中。
結局、彩が説得をしたのは母親ではなくて由紀の方であった。これから暮れに向かう時節に、人手がたくさん欲しいというのに馬鹿な経営者だなと自嘲する。
「由紀ちゃん、実家に帰ることになったから」
その夜、彩は、経営するバー『美月』でスタッフの皆に伝えた。
「ママ、せめて今年いっぱいでも居てもらうよう説得できなかったのですか?これから忙しくなるというのに……」
美緒が不服を言う。
「う~ん。勤めて貰うことが、却ってトラブルになるという私の判断。納得でき
ない?」
「いえ、私たちは、何も……」
バーテンのロクさんがあわてて口を利いた。寡黙なロクさんにしてはめずらしい。
「さて、美緒。だれか勤めてくれる人いないかな? ほら、前によく飲みに来てくれたあの子、絵美ちゃんとか言ったっけ? 美緒の隣の部屋だって子。最近来ないけど、どうしてる? 元々、あの子の誘いで水商売に入ったって言ってたじゃない」
「……自殺しました。あの子、一年くらい前からソープで働いていたんです。」
「ええっ」
驚いた。ちょっと、あてにしてたのに。明るい娘だったし。彼女は山に登り損ねたということか。
その年の暮れは、知り合いのショットバーのマスターに頼み、臨時のアルバイトの娘で何とか人手をつなげることになったのだった。
携帯が鳴った。出るといきなりドスのきいた怒鳴り声である。
「コノヤロー! 金返さんかい!」
「はい? おかけ間違いじゃございませんか?」
「コノヤロー! 梨田の女房だろがっ、早よう返さんかい! このアマ! 耳揃えて返さんと、今すぐそっち言って暴れるぞ! バカヤロー!なめんじゃないぞ!」
あいつと結婚しなかったら、絶対に耳にしないで済んだ言葉であったろう。俗に言う『090金融』の暴力的な取り立てである。彩には身に覚えのないことだ。
「一体、いつお借りしたお金ですの?」
馬鹿丁寧な言葉になるのは、彩(あや)が興奮している証拠である。もしくは、とても不快なときに、必要以上の丁寧な言葉遣いをしてしまう。
「調子こくなっ!三ヶ月で返す約束だったじゃないか!」
呆れた。数年前から、居場所も知らない奴の借金なのだ。三ヶ月前に借りた金か。
「梨田とは十年前に離婚しておりますし、どこにいるのかも存じませんのよ」
「な、なにィ~? 十年前? おまえ、ナシダって名前だろ?」
「そうですけど」
「別れたら、同じ名前を名乗るな! ややこしい!」
聞けば、借金するのに連絡先として女房の携帯の番号を押さえたらしい。まあ、担保みたいなものだ。ちょっと無理をすれば作れる額を高利で貸して、家族を脅して取り立てる。返済金を踏み倒して逃げているため、消費者金融からも借り入れの出来ない人間に金を貸す。貸すのは五、六万。家族を脅せば十万が戻る。違法ではあるが、目先の金が欲しい人間がいくらでも飛びついてくるので儲けは上がる。
「梨田丈雄はあらゆる消費者金融のブラックリストに載っているはずですわ。どこに居るのかも存じませんよ。そちら様の方がご存知でしょうに」
「ご、ごぞんじもへったくれもあるかいっ! ひどい奴だ、あんたの亭主は!」
はんぱな裏社会の人間にまで同情される始末か、と、彩はため息をつく。
その男は、梨田丈雄の携帯番号と住所まで、彩に告げた。
「知ってもどうしようもないでしょう?」
彩がそう言うと、そこに電話をかけて「払ってくれないと、私がひどいめに合うから、早急に返してくれ」と言って欲しいと言うのだ。
「あなたの名前は?」
「リョウってんだ」
「リョウで分かるのね?リョウさんに返してと言えば良いのね?」
「ああ、頼んだぜ」
もっと不快なことをされるのかとおぞましくおもったが、そんな程度でリョウはひきさがった。必ず電話してくれよと念を押して。
遠くに住んでいるのかと思えば意外に近い。嫌な感じだ。
コール音、三回で相手は出た。
「結婚していたということまで後悔させるような真似はやめてちょうだい!」
「もうそっちに連絡が行ったのか?」
逃げ回って電話にも出なかったら、当然のように矢はこっちへ飛んでくる。馬鹿じゃないかと彩は思う。息子の名前まで担保にするような奴は親じゃない。裏社会は表の金融機関では担保にならないモノを担保にする。脅しのための担保なのだから。彩は、自分のした行動に後悔をしない主義だ。だから、この時までは結婚していたことを後悔してはいなかった。自分の人生には必然の悪だと思っていたのだ。
「宏の名前まで教えてお金を借りるなんてひどいわ。私と宏が取り立ての矢面に立たされるのよ。子供が可愛かったら、普通、隠すでしょう? 養育費なんか要求したこともないし、私の息子よ! あんたに親の資格なんかないわ!」
奴の言い訳けなんて聞きたくもないから、彩は速攻に電話を切った。そして、受信と発信に記録された「リョウ」と「丈雄」の番号を着信拒否に設定をする。
持って行き場のない怒りを抱えて、大きな窓越しにベランダの向こうの空を見る。天まで半ベソをかいている。女の私がこうしてまともに社会に向き合って生きているのに、なんて奴だろう。そういう奴と見抜けないで結婚した自分も悪い。
「ああ、やめた! 後悔するなんて、何の役にもたたない!」
途端に、また携帯の着信音が鳴る。表示は『公衆電話』である。出ないでおこうかと思った。着信拒否をされた丈雄が公衆電話から掛けてきた可能性がある。うるさいと思ったが、彩は逃げるのが嫌いな性格だ。いつもちゃんと向き合って生きることを常としている。気負って電話に出てみれば、見知らぬ女の声であった。
「由紀がお世話になっております。由紀の母でございます」
その声はとても恐縮した様子である。
「お待たせしました」
一面ガラス張りの喫茶店の中から、不安そうに外を見つめているその女性は、彩と同じくらいの年齢に違いない。
「由紀さんのお母さんですね。『美月』の梨田です」
もしかしたら、ものすごく遅刻するかもしれないからよろしくと、店のスタッフである美緒に連絡をした。彩はその日の出勤前に、『公衆電話』の声の主と会って話をする約束をしたからだ。
一見して『夫人』という風のその女性は、地味ではあるが質の良い、品をたたえた和装であった。彩は水商売のミズをくぐり抜けたあでやかさで、生活感のない着物姿である。同じ着物姿でもまるで違う。初めて会う二人は、自分の特徴を電話で伝え合っていた。
「着物を着ておりますから」
「あら、私も着物の女ですから、すぐに分かりますわ」
彩が約束の時間よりも早く着いたのに、すでに随分長いこと待っていたらしい。
由紀の母だというその女性は、夫の名刺を差し出す。大手企業の常務の肩書きだ。裏に自宅住所と電話番号が手書きされてあった。彩も名刺を渡そうと懐から名刺入れを取り出すと、名刺はすでに由紀から貰ったと、夫人が言う。
「ここに勤めているから安心して」と、由紀がそう言って渡したそうだ。由紀が彩の店に勤めることになった時、携帯の電話番号を書き入れて由紀に渡した名刺であった。
「それで電話をくださったのですね」
「ええ、あの子は、私がママさんと会っているとは知りません。ですが、もうママさんに相談するしかないのです」
由紀の部屋に上がれば、それはひどい暮らしが分かったという。
彩も由紀の事情を多少は聞いて知っていた。妻子を養うという感覚に欠落した男のために水商売に身を入れたのだろう。彩も似たようなものであった。おなかが空いたと泣く子供のために、手っ取り早かったからだ。
「分かりましたわ、お母さん。由紀さんと話してみます」
事情によっては、逆にこの親を説得することにもなるかも知れない。連れて帰りたがる母親に、私は大丈夫だから心配しないでねと、由紀は言ったそうだ。
「七年前に家を出ましてね、戸籍の付表を調べていたら、子供が生まれたときに入籍をするので居場所が分かったのですが、主人がね、そのうち泣きついて来るだろうから見守っていてやろうって言ったのです。勝気な娘ですから、反対すればするほど、また何処かに逃げて行くからって。今度もしばらく行方が分からなくなっていたのです。最近、また戸籍の付表が動きましてね。子供を幼稚園に入れるために住民票の登録をしたのです。そういうことでもなければ、住民票を移動できないような暮らしをしていたわけですよ」
「お母さんは、もう限界だとおっしゃるのですか?」
「ええ、七年間もあれば分かります。この先、あの男が由紀に幸せを与えるとは思えません。あの子も思い知っているはずなのに、今更、泣きつけない性格なのです。母親の私が一番良く知っております」
「男と女には傍から分からない幸福というのもありますよ」
「いいえ、あの子はこのままでは道を外します。母親だから分かるのです」
道を外すか、水商売への偏見だろうと、そのときはそう思った。夫に庇護されて生きてきた夫人には分かるはずもないと。だが、その日、店に遅れて入った彩の目は由紀の様子がいつもと違うのを感じ取った。由紀の母親に会ったからか、いや、それにしても妙だ。
その日は、「オーさんに送って貰いなさい」とは、言えなかった。
客の小鹿野が執拗だったし、それより由紀が変だ。
「オーさん、今夜は定時で閉店してからミーティングするから、悪いわね。アフターは無理よ」
「何だ、ママ、焼きもちか?邪魔するなよ」
「はいはい、ミーティングですからね。オーさんだってうちの経営の邪魔をしないでね」
やれやれと言って帰る小鹿野を最後に送り出して店を閉めた。
「美緒、悪いけど今日は先に帰って。由紀ちゃんと話があるから」
「え?私たち、ミーティングに残らないで良いのですか?」
一瞬美緒はとまどったが反射的に察して、他のスタッフと一緒にそそくさと店を出て行った。
「帰ろ、帰ろ。お疲れ様でした~」
察しが良い娘だと、いつも感心させられる。
由紀と二人だけになって、店のボックス席で向き合った。
「あんたの目は、オーさんとヤケで付き合うか、そういう目をしている」
「………」
「店外恋愛に口を挟む気はないけど、ヤケで付き合うのなら必ずお客さんを失うからね」
「……申し訳ありません」
「お金なの? ダンナさんはちゃんと働いているの?」
「ごめんなさい、ママ。少し前借りできませんか?」
訳を聞けば、夕方に由紀の母親が話したことが道理に思える。どうしても、由紀と孫を連れて帰りたいと由紀の母が言った。彩は、説得しなくてはいけないのはむしろ由紀の方にだと気が付いた。
「由紀ちゃんは実家を頼る気はないの?」
由紀の不安げな美しい顔がひくつく。黒目がちの目だけが異様に光っている。この娘が自分の美貌を武器に、器用に世間を渡っていける人間なら、それはそれでもかまわない。だがその美貌は、十年後には確実に嫌味で陰惨なものに変わるだろう。
「ダンナさんと別れたくないんだ?」
「実家は……別れるのが条件で、援助すると……」
「当然でしょうよ!」
彩は、とうとう今日の昼間の自分の出来事を話した。彩の母から電話が入る前の一件だ。自分の恥なぞ誰に話す気もなかったが、この娘の心を割るには、自分の恥から話さねばなるまい。
「何が一番大事?」
「子供です!」
由紀は迷わず即答をした。
「あなたのね、お母さんと私、同じ年なの。あなたが自分の子供が大事なように、あなたのお母さんもあなたが大事なの。よく分かるわ。若い頃の私とあなた、似たような苦労をしているもの。おかしいわね。さっき話した通り、ダメ男は何十年経ってもダメなままなのよ。今度こそ頑張るって、必ず言うでしょ?そして、ウソついて働くふりしてバレたら、言うでしょ?君に心配かけたくなかったからだって」
由紀はひどく驚いた顔をする。
「お母さんとこに帰りなさい。子供を連れて。お金は明日、用意するわ。お昼の二時ころ、うちのマンションに来てくれる?」
「実家に帰ることは考えてみます。前借りは、今夜は出来ませんか」
今夜のタクシー代もないのだろう。
「今夜は私がタクシーで送る。明日、タクシーで子供を連れていらっしゃい。二時ね。いただき物のケーキがあるわ」
マンションの地図を書き、タクシーチケットと共に由紀に渡す。
「明日はこのチケットを使って、必ず子供を連れてくるのよ」
翌日、時間通りに由紀がマンションを訪ねてきた。小さい人が二人、
めずらしい物を見るように、きょろきょろしながら後に続く。
「すみません。いたずら盛りで、ご迷惑をおかけすると思うので、ここで失礼しよ
うと思います」
由紀は玄関から上にあがろうとしない。
「ケーキが用意してあるわ。ほら、上がって、上がって」
子供たちがケーキをほおばるのを世話しながら、やっと由紀が白状をした。
「本当は私……死のうと思ったんです。でも子供たちの顔見たらそんなこ
ととても出来なくて……あの、それで小鹿野さんに相談してみようと思っ
たんです。いつも、困ったことがあったら、相談に乗るからって言われて
いたし……」
「それって、身体と引き換えにって意味よ!」
「ええ、覚悟はあります。だって私、うちの人にお家賃の支払いを頼んでいたのに、昨日大家さんから請求があって、もう三月も払ってなかったって。その上、うちの人、娘の幼稚園のために用意したお金まで持ち出してしまってて、何に使ったのか聞いても黙っているばかりで話してくれない……」
「だからもう、実家にお帰りなさい」
「出来ません、絶対に。そら見たことかと笑われるわ」
「で、他の男に甘えて生きていこうと思ったの?しかも不倫で?」
「………」
「そういうことになるのよ。実家に帰ることは、ある意味負けたみたいで辛いかもしれないわ。あなたの気持ちもよくわかる。人生はね、平坦な道ばかりじゃない。私だって、昨日あなたに話したように、次から次にトラブってる。でも、ちゃんと乗り越えて振り返れば、乗り越えたこと自体が幸せなのよ。乗り越えても、また次の山があるわ。でも、山はね、必ず頂上があるの。登るかぎりは一生、頂上にたどり着けないなんてことはありえないから。登り詰めたら、後は下りるだけよ。下りても、また山があるけど、人が生きるって多かれ少なかれそういうことじゃない? ただ、由紀ちゃん、あなたは少し怪我をして山を越える力が弱っているの。そんな時に手を差し出してくれた親ごさんに、頼るのは良くないことかしら? 今の由紀ちゃんにとって本当の家族は、ダンナさんじゃなくて、実家の方の人たちじゃないの? 家族に甘えて怪我の手当てが済めば、またあなたは山に向かえるわ」
我慢していたものが堰を切って溢れ出したのだろう。由紀のほほに流れるものがベランダから差し込む光で反射する。
「おばちゃん、おかあしゃんをいじめないで!」
いじらしい応援団だ。
「おばちゃんはね、お母さんをいじめているのじゃないのよ。大人が泣くのは悲しいときだけじゃないんだから」
小さい人たちに説明していると、チャイムが鳴った。
「由紀ちゃんのお母さんがお迎えにいらしたわ。勝手にお呼びしてごめんなさい
ね。このままいったん実家にお帰りなさい」
彩は、白い封筒を、たよりなく細い由紀の手に渡した。
「お給料を清算してあるわ」
「また遊びに来ても良いですか」と、何度も頭を下げながら、由紀は母親と帰って行った。穏やかな小春日和の午後である。何もかもを知り尽くしたようなやさしい日差しの中。
結局、彩が説得をしたのは母親ではなくて由紀の方であった。これから暮れに向かう時節に、人手がたくさん欲しいというのに馬鹿な経営者だなと自嘲する。
「由紀ちゃん、実家に帰ることになったから」
その夜、彩は、経営するバー『美月』でスタッフの皆に伝えた。
「ママ、せめて今年いっぱいでも居てもらうよう説得できなかったのですか?これから忙しくなるというのに……」
美緒が不服を言う。
「う~ん。勤めて貰うことが、却ってトラブルになるという私の判断。納得でき
ない?」
「いえ、私たちは、何も……」
バーテンのロクさんがあわてて口を利いた。寡黙なロクさんにしてはめずらしい。
「さて、美緒。だれか勤めてくれる人いないかな? ほら、前によく飲みに来てくれたあの子、絵美ちゃんとか言ったっけ? 美緒の隣の部屋だって子。最近来ないけど、どうしてる? 元々、あの子の誘いで水商売に入ったって言ってたじゃない」
「……自殺しました。あの子、一年くらい前からソープで働いていたんです。」
「ええっ」
驚いた。ちょっと、あてにしてたのに。明るい娘だったし。彼女は山に登り損ねたということか。
その年の暮れは、知り合いのショットバーのマスターに頼み、臨時のアルバイトの娘で何とか人手をつなげることになったのだった。
© Rakuten Group, Inc.