「眠れない墓」(一)
眠れない墓
THE UNQUIET GRAVE
(一)
「こんな女性と一緒になれるなら、わたしも人生をやり直したい」
男はしみじみと呟いた。
大理石の回廊に一人、少女が立つ。彼女は男が知る誰よりも美しかった。白い天井は境目無く青い空に変わり、その空も遠くにいくほど紅くなり、果てには星のまたたく夜空があった。よく見れば、柱の影にもう一人が隠れ、彼女をじっと見つめている。『眠らぬジューン・あるいは永遠の回廊』、長い題だが、すんなりと頭に入った。
週末の美術館で、男はその絵を覧た。
四十の手習いで絵画教室に通いだした妻は、たちまち覧る方にも熱をあげた。休日ごと、男は運転手がわりに、あちこちの画廊や美術館に連れ回された。
その好むところも、はじめはモネ、スーラなど男も良く知る印象派の絵ばかりだったが、月日が経つにつれ、舌を噛みそうな名前の画家が描いた意味不明な幻想絵画に移っていった。
今日もそうだった。男は、狂人の妄想じみた世界の羅列にいささかうんざりしていた。
「ロビーで煙草の煙と遊ぼうか」
立ち止まる妻の背中を追い越した時、ちょうど彼女の見入っていた絵が彼の目をひいた。全体の印象ではない。描かれた女性の、あまりにはかなげな姿に胸を打たれたのだ。
「あなたは芸術より、女の人に興味がお有りのようね」
皮肉たっぷりに妻が言った。
「女なら誰でもって訳じゃない。この少女は理想の初恋の相手だよ。年齢に関係なく、男なら皆、そう思うよ」
「四十の中年男が初恋だなんて、この絵も迷惑ですよ」
つまらぬ事で喧嘩は御免だ。男はむかつきを抑え、口をつぐんだ。
彼らは街外れに住んでいた。隣の家まで車で五分、野中の一軒屋だった。
子供の無い夫婦二人、多少不便でも静かな場所を。つねづね思っていた彼は、父母が死んだあと弟夫婦に元の家を譲り、格安で手に入れたこの土地に小さな平屋の家を建てた。
妻もここが気に入っていた。南側は、街に続く路と家庭菜園。残る三方は、芝生のような短い草が茂る丘と、その彼方、広葉樹の森が広がっていた。
夏でも北向きの小窓を開ければクーラーはいらない。そよ吹く風は部屋の空気と甘く溶け合い、快適な眠りを約束した。
午前零時。すでに妻は眠り国の住人に、男もその入口付近でまどろんでいた。
とんとん、とんとん――誰かが男の肩を軽く叩いた。
「ううん」男は迷惑そうに寝返りをうった。
とんとん、とんとん――「起きてください。わたしがまいりましたよ」
男はたまらず目を開けた。
「うるさいな、寝かけたところなのに」とつぶやく彼の目に映ったのは、あきらかに妻の姿ではなかった。
光沢を持つ白い布地が視界を覆う。おそらく絹と思われる襞の流れを見上げていくと、そこには見慣れぬ女性の顔が有った。高い鼻、金色の髪に青い瞳、日本人の顔ではない。
「せっかくわたしがまいりましたのに、つれないおことば」
「はあ、どうもすいません」
男はつい、卑屈な調子で謝った。
――これは夢の中だ。きっとそうに違いない。眠ってまで人に頭を下げるとは、自分も情けないもんだ。
固くまぶたを閉じてから、もう一度ひらいてみた。女の姿は消えなかった。いたずらっぽく微笑んで小首をかしげ、こちらの顔をのぞき込んでいた。
ここで男は初めて驚いた。自分が覚醒しているという事実と、女のこの世のものとは思えぬ美しさに。
乱れた思考を収拾するため、男は寝ぼけかかった頭を必死にはたらかせた。
――わたしに西洋人の知り合いはいないし、付き合いで行く飲み屋でも女にもてたためしがない。ひょっとしたら妻の絵の仲間だろうか。
「妻にご用ですか。隣で寝てますが、起こしましょうか?」
「いいえ、あなたに会いたくてまいりました」
「わたしに? どこかで約束しましたかね」
「なにをおっしゃいます。恋人同志にとって毎日が約束、恋しい時、会いたい時に相手のもとへ駈けつけるのが二人の約束でしょう」
「恋人…こんな中年男が、あなたのような美女の?」
「中年男なんてとんでもない。あなたは若く、美しい方ですわ。嘘だとお思いになるのなら鏡をごらんになって」
男はベッドを立ち、姿見に自分を映してみた。
男は目を見張った。今はアルバムの中にしかない、細く鞭のようにしなやかな身体を持つ若い日の彼がいた。思わず自分の腕を摩った。たしかに細くなっている。脂ぎっていた肌が、蟻が滑るほどさらさらになっている。
どんな金持ちでも諦めざるを得ないものが有る。失われゆく若さだ。これこそ神が定めた絶対平等の原理だ。しかし彼はその法則にさからい、年齢の逆行を自らの肉体で体験した。
「これでお分かりになったでしょう。ここでは落ち着きません。外を散歩しながらお話しましょう」
二人は真夜中の丘へ出た。月の光は、霜のように白く野づらをおおう。虫たちは宴たけなわに、たがいの音色を受けとめては投げ返す。
二人は丘の中腹に置かれた丸太に腰を降ろした。
「説明しておくれ。君は誰だ、なぜ、わたしは若返った」
女は男の視線から顔をそらし、夜空を見あげた。
「理由は問わずとも天に星はまたたき、月は満ち欠けをくり返しながら空を巡ります。人もまた同様、赤子の頃から、誰に教えられるでもなく自分以外の温もりを求めるもの。すべてを知る事が必ずしも大事とは思いません。あなたとわたしがいる、それだけで充分ではありませんの」
そう言うと、女は男の肩にもたれかかった。
――そうかも知れない。何事にも理由付けしないと気が済まぬ。それはわたしだけでなく、現代に生きるもの皆が患う病なのだろう。
男はしぜんと女の肩を抱き、ともに夜空を見上げた。アルクトゥールスをはじめ、月光をのがれた星々の光が、黒い梢の上で息づいている。
――限りない時空をへだてた星達を介し、若さを取り戻した自分が絶世の美女とたがいの温もりを共有する。・・・・・・これ以上の何を望む――彼は迷いを捨て、幸福感にひたった。
女が、ささやくように歌いはじめた。柔らかく、やや哀しみを帯びた古風な旋律だった。歌詞は英語だが、昔風の詩句や言い回しらしく意味は解らない。男はまぶたを閉じ、歌声に聴き入った。やすらぎが綿の海のように彼を包んだ。男は女にもたれたまま、ふたたびまどろみの中におちていった。拡散する意識の底で声が響いた。
「明日の夜もまいります。北の窓を必ず開けておいて下さい」
朝、男は自分のベッドの上で目を覚ました。いそいで鏡を見た。だがそこに見たものは、相変わらず肉のたるんだ中年男の容貌だった。
「やはり夢だったのか」
落胆しながら、彼は何気なくパジャマのズボンを見た。
その裾は青い草の汁に染まっていた。
二章へ
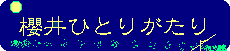
© Rakuten Group, Inc.






