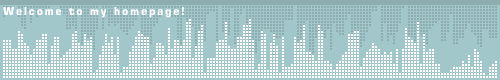音円盤アーカイブス(10,11月)

今、3曲目の「FORGIVNESS,AN ALIBI」を聴いている。
ギターのボッサリズムに導かれてテーマが吹奏されるが、サウダージ感溢れるメロディーで、秋の今ごろの季節に聴くには最適だ。
このアルバムのリーダー、SIGURD KOHNについては実は、あまり知らない。
SJの輸入盤コーナーにアート・ペッパーのそっくりさんがいると紹介されていて、興味をもって大阪に帰省していた時、ワルツ堂EST
1店で購入。
確かに一曲目はもろペッパーのコピーで、細かいニュアンスまでよく再現したなぁとまず驚く。曲名も題名通り「MORE PEPPER,PLEASE」。
今になってアルバムのクレジットを見て気がついたのだが、ベースがなんとINGEBRIGT HAKER FLATEN.
見事、ベン・タッカーの役割を演じている。
2曲目の「WHITE COFFEE」もウエストコーストの当時のフレーバーを再現した気品あふれる一曲。
4曲目の「NO WORRIES」もアップテンポの曲調にペッパーライクなSIGURDのアルトサックスが快調に飛ばし、トランペット、ピアノとソロが受け継がれる。ピアノは、DAG ARNESEN.
ドラムは当時のものより録音のせいもあるがややロックテイストかな?
3曲目や10月の空を流れる雲を連想させるような曲調の5曲目「OCTOBER」、ギターやパーカッション、などで色付けされたラテンスパニッシュな6曲目「BINGO」など曲が進むにつれ、アルバムは次第に50年代のウエストコーストから現代のノルウェーの音楽シーン(時代性、地域性を超越したグローバルな音楽性)で活躍する若手ミュージシャンによる新たな解釈が試みられる。
SIGURDの音色は以前紹介したアラン・メスキダをすこし肉太にした感じで、私の好きなアルトの音。
この一枚しか持っていないが、気になるミュージシャンだ。
きっと音楽性は幅広く多岐にわたるのが、推測される。
それにしても、ベースがINGEBRIGT FLATENなのには、驚いた!
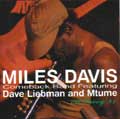
大阪は扇町プールでその来日コンサートは開かれた。
阪急東通り商店街を通り抜け、開場まで歩いていったんじゃなかったっけ? H野さんとS田君といったような気がする。
開場につくと売店で来日記念グッズとしてマイルスのロゴが印刷されたとスェットシャツを売っていたので、嬉々として買う。
銀色に鈍くライトに照らされて反射するプールを隔てたところに設置されているステージを、見ながらまだか、まだかと待ちわびる。
6年以上の長い沈黙を破って、シーンにカムバックした最初の来日コンサートが決定して以来この日を待ちわびていた。
夜になるとさすがに着込んでいても寒くなってきた。
何十分待ったのだろうか?
ついに帝王マイルスがステージに・・・
メンバーのイントロに導かれて最初の一音。
思わずズッコケタというか、H野さんと顔を見合わせた。
「こりぁ、あかんわぁ!」
最初の一音というかワンフレーズは確かにうわずって、音程が狂い音にもパワーがなかったと思う。
マーカス・ミラーのファンキーでねばりのあるベースやでぶっちょマイク・スターンのロックテイストのギターはそれなりに新鮮に聴こえたのを覚えている。サックスのビル・エバンスは生徒が先生の前で必死に演奏している感じ。ソプラノを足の間にはさんで下をむいて吹いている姿が今でも目に焼きついている。
肝心のマイルス。次第に演奏はリップコントロールも落ち着きマイルスらしい、いやマイルスにしかできない音の芯といったものを断片的にではあるが、聴けるように・・・
おそらく体調は最悪だったのだろう。
最後までステージをつとめあげ抱きかかえられる様にして退場したのではなかったか?
しかしである、演奏は確かにベストではなかった、いやむしろマイルスにしてはショボかった。
でも、感激した。強烈な印象を残した。
最初から最後まで完全にマイルス・デイビスの音楽だった。
マイルス・デイビスのステージだった。
ステージがはねてから、すぐに裏のバックヤードへ駆けつけたがすでにマイルスは移動した後だったのか、見れずじまい。
記憶のなかでは、あとのメンバーがのったリムジンバスの窓の中からアル・フォスターが手を振ってくれたことになっている。
最後になってしまったが、このブートレッグはマイルスがカムバックして、「キックス」「エイブリー・フィッシャー・ホール」とステージをこなしもう一度NYのファンにライブをという事で急遽くまれたライブ録音。もちろんオーディエンス録音。
大阪の時よりは好調だが、正直いってあの時見たライブを思い出させる演奏である。
しかし、マイルスはマイルスである。
他の誰でもない。
中山さん風に、
「マイルスを聴け!」

ジャズを聴きだした頃から、スイングジャーナルの日本のジャズ欄なんかでこの女流ジャズフルーティストの事は、結構取り上げられて名前を早くから知っていた。
今でこそ女性の管楽器奏者は増えたが、70年代はピアノ、ボーカルを除いては、ほとんどシーンの中央に名前が出てこなかった。
そんな時代にコルトレーンの曲なんかをレパートリーの中心にして、真摯にジャズ演奏の活動をくりひろげていたのが、小宅珠実。
私が80年代初頭、初めて新宿PIT INNを訪れた時もステージ横のミュージシャン席に黒の皮ジャンに細身のジーンズ姿の小宅珠実の姿を目にした。
遠目に見ても、24時間ジャズという感じが漂っていて、近寄りがたかったのを覚えている。
でも、凄くかっこよかった。
社会人になり、82年の春に広島にきて、テレビを見て驚いた。
ポエム(漢字なのだが)という広島のお菓子屋さんのCMに音楽と本人が出演していたのだ。
確認はしていないが、たぶん間違いないと思う。
学生気分の抜けきらない新社会人にとって、一人暮らしのボロアパートに疲れて帰って、その疲れを癒してくれるのが、一本の缶ビールとジャズレコードだった。
少ない給料の中から(学生の頃より買う枚数が減った)やりくりして買ったのが、この一枚。
1982年5月、発売されたときに確か買ったはず。
古沢良治郎曲集。
実に素朴で暖かいメロディーを、集まったミュージシャンが各自の持ち味を最大限にいかして料理している。
小宅のフルートはナイーブな面もみせつつ、曲によっては、むしろ男性的で、ハードな面もみせ、女流フルートの概念を覆す。
このセッションに集まったメンバーは、
小宅珠実(FL)板橋文夫(P)吉野弘志(B)小山彰太(DS)
初山博(VIB)古沢良治郎(DS,VO)広木光一(G)
いい曲ばかりだが、どれか一曲となると、やはり「EMI」だろう。
ギターのイントロに導かれて出てくる小宅の吹く甘く切ないメロディーはまさに永遠のメロディー。
今聴いても遠いあの日々のことを思い出させてくれる。

3年前の夏も今年と同じで、猛暑だった。
慣れない仕事から疲れて帰ってきて部屋のクーラーを付けて、
このCDを少し大きめの音量で鳴らすのが、日課になっていた。
TAKIS BARBERISはギリシャのギタリストだ。
このアーティストを知ったのは、ネットサーフィンをしていて
偶然XAVIER RECORDSという通販専門のお店のホームページを見たのがきっかけ。
ザビエルレコードのサイトは、ほとんど知らない未知のアーティストの作品が紹介されていて、試聴も一部できるのだ。
そこに、このTAKIS BARBERISも紹介されていて、試聴してすぐに気に入ったので、購入した次第。
サウンドはパット・メセニーのサウンドに、エスニックな風味を増して、プログレッシブロックの要素を取り入れたサウンドと言えばわかるだろうか。
曲によっては、地中海から中近東のあたりのフレーバーが強い音のものがあり、新鮮に響く。
TAKISはオールラウンドなギタープレイヤーらしくメセニーライクなプレイからロックテイストの強いプレイ、クラシカルなプレイと縦横無尽に活躍。
タブラやシタール奏者との息もバッチリで、目を閉じて聴くと、体が浮いて、どんどん高みに登っていく様な浮遊感覚を味わえる。
すこしトランス状態というか、トリップさせてくれるサウンドである。
全然馴染みのないギリシャのミュージシャンばかりで作られたCDなので、偶然耳にすることがなければ一生耳にすることが、ひょっとするとなかったかもしれない。

あれは、NHKのゴールデンジャズフラッシュという番組だった。
ディスクジョッキーは本多俊夫。軽音楽(ハワイアンからジャズ)全般のベースプレイヤーとして活躍した後、元ベーシストとしての観点からジャズ評論、ラジオ番組などに出演。
当時高校生だった私は、そのわかりやすい解説、明快な口調のプロフェッショナルな番組進行にすっかりファンになっていた。
番組の特集である日「ベースプレイヤ-特集」の日があった。
レイ・ブラウン、ダグ・ワトキンス、ポール・チェンバース、ロン・カーター、スコット・ラファロ、ミロスラフ・ヴィトウス、ジャコ・パストリアス、などとともに偉大なベーシストとして紹介されたのが、レッド・ミッチェルの新譜だった。
「スケアポート・ブルース」と題された新作をオンエアしたのは、息子本多俊之のレコーディングデビュー作紹介の意味もあったに違いない。若手新鋭アルト奏者本多俊之がフィーチャーされたレッド・ミッチェルの新作は確かに、本多の明るくさわやかで、つややかなアルトサックスも聴き物だったが、一番気をひいたのが、やはりリーダー、レッド・ミッチェルのベースプレイと音色、統率力だった。
レッド・ミッチェル自体のプレイはハンプトン・ホーズのレコードなどでよく耳にしていたのだが、最近のプレイは聴いたことがなかった。
まず、ベースの音色が全然他のベースプレイヤーと違うのである。
一音、一音が粒だっていて、明瞭なトーン。音に伸びがあり抜群に唄うベースプレイ。ソロでもバックでも存在感のあるワンアンドオンリーな音。
この事は本多俊夫の解説によってすぐにわかった。
通常のベースの調弦をセロの調弦に変え、猛練習の末独自の運指法をあみだした云々・・・
それ以来、好きなベースプレイヤーの一人になった。
このCDは1992年に岡山のLPコーナーで買ったもの。
ピアノがケニ-・バロンだったことも購買意欲をそそった。
ケニ-のRESERVOIRの新作の「フラジャイル」がお気に入りだったので、このレッドの新作でもケニ-のピアノプレイにも期待感がたかまった。
このCDは「EL SUENO」がベスト。
ケニ-・バロンの粒立ちのよいピアノがとるシンプルだが、哀感溢れる蒼い色調のメロディーに、耳を奪われる。
レッド・ミッチェルのユニークなベースソロに続き倍テンポでケニ-の歌心溢れるスインギ-なアドリブプレイが最高。
トリオの一体感が最もでた一曲だと思う。
他の曲もグルービーでスイング感溢れた曲が収録されており、聴いていて楽しい一作になっている。

去年の年末、アマゾンで検索してみたら、あったのですぐに注文して入手した。
93年10月にCD化されたものが、まだ残っていたみたいだ。
リイッシュ-された時買おうと思っていたのが延び延びになって買い逃していた一枚。
この作品はヘレン・メリルの4度目の来日の時に録音された企画盤。
1967年3月26,31日 東京録音
アレンジは前田憲男と渡辺貞夫がわけあっている。
40前の女盛りのヘレンが唄うボサノバの名曲を聞きたかったのも事実だが、一番の理由は日本語で唄う「夢は夜開く」と「信じていたい」を聴きたかったからと正直に告白しておこう。
よくも悪くも日本の60年代後半の情景が走馬灯のように浮かぶようなサウンド。
高度経済成長、所得倍増計画、新幹線開通、高速道路、高層ビルの建設、・・・クリスマスのバカ騒ぎ、夜のグランドキャバレー、
あの頃は日本人が皆希望に燃えていたのだろう・・・
昨日より今日、今日より明日と・・・
たぶん日本語をあまりわからなかったであろうヘレンが日本人以上にその当時の日本文化の断片を当時の流行歌という形で鮮やかに描写して見せたことにやはり只者ではないことを感じる。
ボサノバもポップスの名曲も先程の歌謡曲も統一したカラーで唄われているのもこのアルバムを評価できる点。
ブラジルでいうところの「サウダ-ジ感覚」が全編にわたり醸しだされている。
アメリカ人であるヘレンが日本、ブラジルという異文化を巧みに消化し、自己を表現した裏名盤ではないかと思う。
それにしてもCDのインナースリーブの裏ジャケにうっているヘレンの麗しいことよ!

今と違って通信販売の手順も大変だった。
大阪の「ライトハウス」からその頃は毎月買っていた。
毎月20日過ぎになると30ページのディスクリポートが配達され、その月の商品案内が写真とコメント付きで掲載されているのだ。
予算にうまく収まる様やりくりして目ぼしいものをチェック。
月に7,8枚は注文してたか?
往復はがきで在庫確認。返事が戻るまで、約1週間。
書留で送金。2,3日で配達、漸くブツが届くといった按配。
今から考えると気の遠くなるようなめんどくさい手順を踏んで買っていたものである。途中からFAX注文に変わったが、どちらにせよ現在のネット注文とは、月とスッポンの違いである。
このCDもその頃1992年の初めにライトハウスの通販で入手。
充実したラテンタッチを加味したハードバップセッションである。
1曲目はマイケル・カービンの歯切れの良いリズムワークの元にセシル・ブリッジウォーター(TP)ソニー・フォーチュン(AS)
クラウディオ・ロディッティ(FLH)がノリノリのソロを展開。
アルバムの出来のよさを期待させる仕上がり。
ロディッティをフューチァーした「IT MIGHT AS WELL BE SPRING」でクールダウン。
3曲目クレア・フィッシャーの「MORNING」は哀愁のメロディー。
ちょっと松岡直哉を感じさせるメロディー。名曲だ。
ちょうど今ごろの秋の晴れ渡った青空が拡がっている朝に聴くと気持いいかも。ソロは、ロディッティ-(TP)フォーチュン(FL)サイラス・チェスナット(P)の順。
4曲目の「EFFI」もケニ-・バロンの「サンシャワー」に似たメロディーで、ソロはブリッジウォーター(TP)フォーチュン(AS)。
作曲はスタンリー・カウエル。
5曲目の「THABO」はマイケル・カービンのスティック捌きが聴き物の一曲。ロディッティが快調なソロで飛ばす。
6曲目「BODY AND SOUL」はソニー・フォーチュンのASがフューチャー。
全部で8曲。
いぶし銀の中堅ミュージシャン(チェスナットだけ若いが)が集まって繰りひろげた好ハードバップセッションの一枚。
参加メンバーは、MICHEL CARVIN(DS),CLAUDIO RODITI(TP,FLH)
CECIL BRIDGEWATER(TP)SONNY FORTUNE(AS,FL)CYRUS CHESTNUT(P)JHON HICKS(P)DAVID WILLIAMS(B)
録音は1989年12月12日 ヴァンゲルダースタジオで行われた。
CDジャケの裏側にはカービンのバックにツインタワーが写っている。

ジャズ批評ピアノトリオVOL.2(1990年)に掲載されていて気になっていたのが、このデビー・ポーリス・トリオ(TIMELESS)。
仕事中に寄った岩国の「WESTCOAST」というレコード屋さんで入手。今は移転して経営者のTさんは広島の店に常駐されている。
Tさんは以前は岩国で「ライフタイム」というジャズ喫茶を経営されていて、ライブも盛んに主催されていた。自身もドラムを叩かれる。
Tさん主催のコンサートで最も印象深いのが、アート・ブレイキー・ジャズ・メッセンジャーズのコンサート。
メンバーはブレイキー(DS)ビリー・ピアース(TS)ドナルド・ハリソン(AS)テレンス・ブランチャード(TP)ピアノとベースが記憶が定かじゃない。
全員ピシッとしたスーツに身をまといやや緊張した面持ちでフロントのハリソンやブランチャードがソロを吹いた後、後方のブレイキーに一礼するのが可笑しかった。
演奏自体旧来のレパートリーを当時の新鋭が斬新な切り口で解釈するスタイルで満足いくものだった。
しかし、客の入りが悪かった。
Tさんは、大赤字をだしたらしい。しかし、当の本人は念願のブレイキーを岩国に呼べて大満足、後悔は全くなかったらしい。
私も帰りの東京行きの夜行列車(広島に止まる)のなかでモーニンを頭の中で反芻していたのを思い出す。
最近といっても2年前だが、クアトロでやったアーチ-・シェップ・カルテットがTさん主催で、楽屋で久々に元気な顔を拝見した。
そうそう、デビー・ポーリスの話だった。
オランダの当時は(1982年)若手ピアニストだったポーリスも活躍していたら、中年のいい歳になっている。残念ながら消息を全くきかないのだが・・・
この当時はまだまだ今の様に女流ピアニストの数が多くなかった。
そんな中、デビューしてリーダ-アルバムのリリースとなったのが、1984年、録音自体は1982年11月21,22日に行われている。
スタイル自体はごくオーソドックスでケリーからエヴァンスを消化したうえハンコックからの影響も見え隠れするか?
特に強烈な個性は感じられないけど、味がある折にふれて棚から取り出してついついかけてしまうピアノトリオ盤。
こういう普通のピアノが結局長い年月にわたって聴き続けるのだなぁ。
メンバーはベースがHEIN VAN DE GEYN,ドラムが、HANS EYKENAAR
曲が今、SWEET GEORGIE FAMEになった。
GEYNのベースソロに寄り添うようにつま弾くPORYESのピアノは、可憐でプリティー。
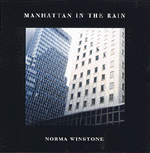
MANHATTAN IN THE RAIN・・・雨のマンハッタン
最初は題名に惹かれた。ノーマ・ウィンストンという名前にも・・・
1998年の年末だった。スイングジャーナルをパラパラ自室でやっていたら、キャットフィッシュレコードの広告に載っていたのだ。
なんとなく良さそうな気がして、全くの勘で注文。
年末のギリギリに宅急便が届き、一年の締めくくりに聴いたような・・・
文字通り、マンハッタンの高層ビルのラウンジで聴いているかのような、自分がワンランク、グレードアップしたかのような上品な音楽。 バックは結構アグレッシブなこともやっているが・・・
アジムスでのボーカルを聴いたことがないので、比較しようがないのだが、この人スタンダード唄わせても非常にうまい。
基礎がしっかりしていて、決して声量があるほうではないが、語り口に詩情があり、ウィットネスに富んでいて説得力がある。
ノーマのボーカルにTONY COEのクラリネットが絡んで、ベタツキ感の無い叙情味が醸しだされている。
まだ、比較的早い時間帯の最上階のバーラウンジ。
バーテンダーはグラスをピカピカに磨き上げ、ウェイターは蝶ネクタイのチェックに余念がない。
陽が沈み、あたりの景色が群青色に染まり、イルミネーションがひときわ美しく見える時間帯。
まだ、お客はまばらだけど、その日のファーストステージが始まった。
外は雨らしい・・・窓枠についた雨雫で景色が滲んで見える。
MANHATTAN IN THE RAIN
今、歌手はジョビンのRETRATO EM BRANCO E PRETOを唄いだした。
いい唄だ。 もう一杯ギムレットをお替りしよう。
NORMA WINSTONE/MANHATTAN IN THE RAIN(ENOCD)
NORMA WINSTONE(VO)STEVE GRAY(P,SYNTH)
CHRIS LAURENCE(B)TONY COE(TS,CL)
1997年3月録音

その頃はフランス盤のCDはべらぼうに高かった。
LPコーナーの通販で買ったはずだが、確か3000円以上したはず。
しかし、値段以上の満足感を味わったCDも少なくない。
当時IDAから出ていたものは、バルネ・ウィランをはじめとして、結構力作が多くてこのエディー・ヘンダ-ソンも当たりの一枚。
トランペットのワンホーン物で、バックのミュージシャンもよいし、ウェイン・ショーターの曲を2曲吹いているのが、購買動機となった。
70年代にハンコックのグループで活躍後、自身のアルバムもフュージョン路線のやや中途半端な作品が多く、一時忘れ去られた存在だったエディーは、スティープルチェイスにリーダー作を発表しはじめ、メインストリーム路線にカムバックした頃だった。
録音は1990年3月7,8日
先ごろ亡くなったデビッド・ベイカーが手がけている。
さすがベテランらしい味を発揮していて、硬軟使い分けた柔軟なプレイに終始。曲の芯どころを捕らえた経験と風格からかもし出されるジャズ度に聞き惚れるばかり。
バラードでは、甘すぎないセンチメンタリズムを、アップテンポではスリルを。
メンバーはEDDIE HENDERSON(TP,FLH)
LAURENT DE WILDE(P)IRA COLEMAN(B)LEWIS NASH(DS)
EVERYTIME WE SAY GOODBYE,OLD DEVIL MOON,GOODBYE,EL GAUCHO,FLEURETTE AFRICAINE,ARMAGGEDON,FOR ALL WE KNOW,YOU`VE CHANGED 全部で8曲収録されている。
マンハッタンの秋の景観をとらえたジャケット写真も悪くない。

昨日グルーヴィン本店でカーリー・サイモン「TORCH」を買う。\1200だった。深津純子「CATCH THE RAIBOW」こちらは、\790。
このアルバム、福井県出身のN目さんがポピュラーパートの研究会でかけたのではなかったか?
FM放送でもよくオンエアされていたはず。
このカーリー・サイモン以外にリンダ・ロンシュタットやリッキー・リー・ジョ-ンズなんかもジャズスタンダードを唄った作品を発表した。
ジャズパートの研究会よりポピュラーパートでこの辺のアルバムはかけられていたような気がする。
当時の印象はカーリーの唄より一曲目のサンボーンのイントロやマイク・マイニエリのバイブソロが残っていて、どちらかというと色眼鏡で見ていたような気がする。
今、聴き直して見ていいんだなぁ、これが!
うーん・・・やはりジャズではない。
あくまでもポピュラー畑の歌手がスタンダードを唄ったアルバム。
でも、印象に強く残る。訴えたいメッセージが唄を通じてダイレクトに伝わってくる。
凛とした色気も伝わってくる。独自の個性が発揮されている。
そして艶やかさも持ちあわせている。
それ以上何が必要なんだろう?
インストと違ってボーカルに関してはジャンル分けの必要がないと昔から思っている。
唄は唄。たかが唄、されど唄・・・
人間の最も根源的で肉体的な「唄う」という行為にジャンルわけして囲いこんでも仕方ないと思っている。
だから、ボーカルに関しては、好き嫌いで聴いている。
どんな偉人、天才でも嫌いなものは嫌い。
たとえばビリー・ホリデイ・・・一枚ももっていない。
それでいいと思っている。

数年前、仕事中によく訪れていた岡山、表町のレコードショップ「ディスクトランス」で見つけて入手したもの。
その頃から、このLABEL BLUEやACT,ENJA,ECMなどヨーロッパのジャズレーベルの品揃えに力を入れていて、珍しいものもよく入荷していた。
このCDも買い逃していた一枚。
ナナ・ヴァスコンセロスの土着的でありながら洗練されていてスタイリッシュなパーカッションとスティーブ・ローダーの織り成すシンセの絨毯をアンディー・シェパードのソプラノサックスが飛翔する一曲目からぐいぐいと音楽に引き込まれる。
サウンド的にはパット・メセニーやウェザーリポートからの影響を感じさせるが、幾層にも連なる音のタペストリーを彼らは、3人で
表現している。
パットやウェザーと共通している点は牧歌的なサウンドで、テクノロジーを使いこなしてヒューマニティ溢れる音造りを為し遂げている点。
無国籍性・・・色々な音楽の要素を感じさせるのだが、そのどの要素も際立っているわけでない・・・ジャンルや国、民族性の垣根を越えた汎地球的な音楽。
それこそ、彼らが指向した音楽であろう。
INCLASSIFICABLE : 「分類できない」
まだまだ音楽の発展性を予想させるグループだけにこの一枚だけに終わるのはもったいないと感じるのは私だけだろうか?
再結成、新作を望みたいグループである。

1980年代の終わりから1990年初めにかけてほぼ毎月一枚くらいのペースでJAZZ CITYレーベルから新人中心の新作CDがリリースされてよく買っていた。
プロデュースは増尾好秋。
なら春子もその時すぐに買った一枚。
画像は2001年に再発された時のもので、最初のものは、雨に濡れそぼる大都会の道路を行きかう車の往来をとらえた写真でそっちの方が気にいっている。
一曲目のタイトルは「夢」。
硬質なトーンのピアノのイントロに導かれてケニ-・ギャレットのサックスが優しく入ってくる。
トム・スコットがタクシードライバーのテーマを吹いたのと同じ様な感じで、幾分サブトーン気味のギャレットの音色はいつになくメローな気分をかもし出している。
なら春子の硬質に録音されたピアノの音との対比がいいアクセントになっている。
この一曲目でこの作品は個人的名盤になったといっても過言でない。それほどこの曲は気に入っている。
2曲目はがらりと雰囲気が変わって、4ビートの明るく楽しくスイングする曲。なら春子とギャレットのアドリブもノリがよく、聴いていて楽しくなる。ロニ-・プラキシコとマーヴィン・スミティ・スミスのコンビネーションも良好。
マイ・フェバレット・シングスはコンピューター・プログラミングされたキーボードとケニ-のアルトとのデュオ。
4曲目の「ラベル」も「夢」にひけをとらない名曲。
ならの作品は当時の最新のテクノロジーを導入しながら、とてもヒューマンなタッチを感じさせ、陰影感溢れた曲になっていてオリジナリティに優れていると思う。
作風は師匠の鈴木良雄にどことなく似ていると感じるのは私だけだろうか?
どことなく遠くを見るような、そして懐かしさを感じる曲調といえばわかるだろうか?
作曲のことばかり書いたが、ピアニストとしてもならの技量は「MY ROMANCE」や「HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON」などのスタンダードで証明されている。
決してテクニックをひけらかすタイプではないが、しっかりと自分の言いたいことを表現できるピアニストと聴いた。
録音は1989年3月と6月
なんとそれ以来録音が途絶えている。
なにやってんだ!日本のレコード会社!
こんな素晴らしい才能の持ち主のリーダー盤吹き込みしなくてどうする!新人のピアニストばかり発掘しないでもっと周りに目を向けろと言いたい!

東京出張の折新宿のタワーかHMVかその辺で買ったもので、バーゲンのコーナーで発見。値段も安かったから買ったのだと推測される。その頃CECILIA SMITHなんて名前知らなかったし、バックにロニ-・プラキシコの名前があるのと、曲がFALL,COME SUNDAY,BLUE IN GREEN,などジャズオリジナルとNIGHT AND DAY,TENDERLY,HERE`S THAT RAINY DAYなどスタンダードをカルテットで演っているので、悪くはないだろうと買い上げたのだろう。
これが、正解、良かったのである。
むろんミルト・ジャクソンやボビー・ハッチャ-ソンなんかと比べたらまだまだ食い足りない点もある。
彼らのプレイはまさにワンアンドオンリー、個性のかたまりである。そしてその独自のスタイルで何十年と演奏してきて、ある意味
スタイルが確立されすぎて悪く言えばマンネリ、手垢にまみれた演奏になる危険性もはらんでいる。
セシリアというと、このアルバムはファースト作で圧倒的な個性がない反面、曲を隅々まで把握して丁寧に演奏していると言えよう。
カルテットのメンバー全員が一致団結してチームプレイに徹しているといった感じ。
もちろん、ソロプレイでは各人見せ場をつくっている。
ただ、圧倒されるプレイではないのだが、それが逆に爽快感、さわやかさを生んでいて曲の本質が聴き取れる。
BROWNSTONEレーベルにあと3枚リーダー盤があり、3361BLACK
から香取良彦との共演盤がでている。
今9曲目のオリジナル「MEDITATION FOR A SPACE FLIGHT」がかかっている。
ラテンタッチのスペーシーな良曲。
作曲もなかなかやるじゃないか。
ここ最近リーダー盤のリリースが途絶えているのだが、こういうアーティストこそ、日本のレコード会社が契約してもいいのでは?
ピアノトリオのCDばかりだしてる場合でもないと思うのだが・・・

RATKO ZJACA???なんて読むんだろう?
未だに名前の読み方がわからない。
バックのミュージシャンで買った一枚。
ベースがレジ-・ワークマン、ドラムがアル・フォスターのギタートリオ。曲もスタンダード何曲かやってるし、こうしてCDでるのだから全く聴けないこともないだろう。
おぅ!GENTLE RAINやってるやんか! 買うぉっと。
好きな曲が入っているとそれが駄目押しになって買った例の一枚。
RATKO ZJACAはアコースティック、エレキギター双方を駆使して極めてオーソドックスなプレイを繰りひろげる。一曲目のオリジナル作「SONG FOR SHARON」から基礎のしっかりしたプレイヤーなのが実感できる。オーソドックスな奏法の陰に70年代以降のプレイヤー、ジョンスコ、パット・メセニー、マイク・スターンらの影響もちらっと見え隠れする。
4曲目「LONNIE`S LAMENT」ではパット・マルティーノのように真摯に淀みないソロを繰りひろげ、途中からギターシンセにスイッチ。
7曲目がお目当て「GENTLE RAIN」。
ややアップテンポのジェントルレイン。
アコギでよく唄うソロをとっている。
でもそれ以上に唄っているのがドラムのアル・フォスター。
なんて素晴らしいプレイなんだろう。サポートしながらソロをやっているようかのプレイ。
このアルバムを通して様々なリズムフィギュア-を見せてくれていて、それが何とも音楽的でツボにはまっている。
テクニックを披露と言うわけではなく必然的にそうなったと思わせる熟練の技。
ベテランの妙技というものをまざまざと見せつけてくれる。
アルのスネアやシンバルワークの音がこんなによく録音されているCDはあまりないんじゃなかろうか?
レジー・ワークマンの事を書かなかったが、黒人のベースプレイヤーにしては、珍しくピッチが非常に安定しているプレイヤーで相変わらず堅実なサポート。
RATKOは故郷ザグレブでティーンの頃、マイルスとコルトレーンのグループをそれぞれ見て、ひとつの夢を持ったらしい。
このグループのメンバーといつか一緒にプレイしてレコーディングすると・・・
夢がかなったのである。
2000年4月16日に。
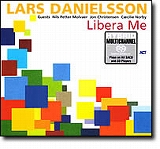
まずインナーのジャケに写っている顔写真を見て以前の風貌とだいぶイメージが変わったと感じる。DRAGON盤の「POEM」のジャケットなどとだいぶ違う感じ、最も12,3年経過しているので無理もないか。
LARSのリーダーアルバムは結構もっているが、ほとんどがトリオ、カルテット中心のスモールコンボだったのに対し、本作は様々なミュージシャンとの多様な編成によるラルス・ダニエルソンの音楽を多角的に紹介しようという意図がみてとれる。
一曲目は一番したの娘に捧げた曲で、叙情的であり、北欧の乳白色の空の様に陰りをおびているニールス・ペッタ-・モルヴェルのTPがフィーチャーされる。
3曲目はベースの師、ANDERS JORMINに捧げていて、自身のベースソロをフィーチャー。エストニアの作曲家、ARVO PARTにインスパイアされてかいた6曲目「SHIMMERING」でもペッタ-・モルヴェルがソロをとる。弦楽器の絨毯の上を幻想的なメロディーが奏でられる。
8曲目はジョニ・ミッチェルの「BOTH SIDES NOW」を自身のベースでカバー。ちょっとした小品という感じか。
表題曲「LIBERA ME」は自身のベースと長年の仲間デイブ・リーブマンのソプラノサックスが余情的なソロをとる。
ジョニ-・ホッジスがソプラノを吹いたらこんな音になるのではないかと連想させるような膨らみのあるマイルドなソプラノの音。
7曲目はそのまま映画の主題歌に使えそうな一大叙事詩。
ラストのボーナストラックはサンプリングがもちいられていてコンテンポラリーな要素が最も強く感じられる。
モルヴェルのTPの音が最もはえるシチエーションであろう。
とにもかくにも、
ACTレーベルの新しいシリーズの第一作はラルス・ダニエルソンの今日の多彩な音楽性を収録した成功作といっていいだろう。

ディスクユニオンに注文するが、売り切れでHMVが出荷まで7日から15日になっていたが、すぐに到着。
今、3回目を聴いているところ。
懐かしい感じを抱かさせるサウンド。
木漏れ日、秋の森の中から射す太陽の光、雨に濡れた落ち葉の匂い、木々の中をたわむれる小鳥達、・・・
秋の一日をゆったりと自然の中で過ごすようなリラックスしていて少し懐かしさ、卿愁を感じさせるサウンド。
アコーディオン、バンドネオン、クラリネット、アコースティック・ギター、パーカッションなどの組み合わせが、そういうイメージを抱かせるのに一役かっていると言えよう。
全体的に柔らかく極め細やかな繊細なアレンジ、かといって軟弱なのではなく一本芯の通った骨太な精神性も感じさせる音楽。
CHRISTOPHE WALLEMMEはこれまでPRISMのベーシストとしてしか認識がなかったが、どうしてどうしてユニークでオリジナリティ溢れる音楽性の持ち主であるのがこのアルバムを通してわかる。
NOCTURNEレーベルはムタン兄弟、ピエリック・ペドロン、リック・マーギッツァなどの諸作を最近リリースしていて、それらも結構力作なのでこれからも期待したい。

今からちょうど4年前の事。このCDには辛い思い出がある。
約20年間勤めた会社の日本市場撤退の説明会を大阪へ聞きに行った帰り、一人梅田まで出てワルツ堂EST1店で購入したもの。
ちなみに全員解雇。
口では言い表せない将来への漠然とした不安感、暗黒の暗闇が心の中にじわじわと広がっていく感じか?なんとなく重苦しい気分だったのは確か。
帰りの新幹線の中で聴いたのだ。何枚か買ったうちの一枚だったのだが、偶然この一枚をポータブルCDプレイヤーで聴きだした。
これが良かったのである。そんな気分のときでも、いい音楽を聴くと耳が素直に反応してしまう体質になってしまっているのだろう。
結局広島に着くまで、結局2回聴き通した。
新幹線を降りる時には大阪をでる時より少し心が軽くなったような気がした。
あれこれ悩んでても、しょうがあれへん。なるようにしかならんわぁ!
一時的にせよこのCDが嫌なことを忘れさせてくれた。
むしろ、元気づけてくれ勇気をくれたと言っても過言でない。
この事でこのCDの出来はあまり説明する必要もないかもしれない。
内容は特別変わった事をやっているのではない、普通のジャズ。
老練のマルコ・ディ・マルコのメロディアスなピアノがリードするオーソドックスなメインストリームジャズ。
メンバーは
MARCO DI MARCO(P)ADAM KOLKER(TS,SS)HARVIE SWARTZ(B)
RON VINCENT(DS)MEMO ACEVEDO(PER)
1998年11月9,10日 NY SYSTEM TWO RECORDING STUDIOSで録音
ジャケットの後に写っているのはツインタワーだろうか?
マンハッタンの紅葉する木々の前で佇むマルコ。
ここにマルコ・ディ・マルコのオータム・イン・ニューヨークが完成した。
SUMMER NIGHT,COME RAIN OR COME SHINE,JUST FRIENDSなどのスタンダードとTURNAROUND,SOLAR,VERY EARLYなどジャズオリジナルをバランスよく配合し自身のオリジナルを数曲加えるといった構成。
マルコのオリジナル作が聴き物。
4曲とも良曲だが、個人的には一曲目の「QUANDO」が一押し!
ラテンフレイバーのきいたサンバタッチの名曲。
3曲目の「MR.BILL」もサウダ-ジ感覚溢れる美しいメロディー。
4曲目は題名通り詩的なバラード作。
きっとマルコにとってこのニューヨークでの録音は快心の演奏旅行であっただろう。

レコードの神様って存在すると思う。
レコード屋でエサ箱を漁っていて一枚のレコードを引っ張りあげた時、体が凍りついたことはないだろうか?
それまでほしくて、ほしくて夢にまで出てくるくらいずっとほしかったレコード。
突然出会うのである。 ある日突然に・・・
私の場合はこのレコード。チック・コリアの「日輪」。
1993年の春先だったと思う。
常宿にしていた倉敷のホテルから歩いて300メートル程のところに中古屋がオープンしたのである。経営はGREEN HOUSE。
屋号はそのものズバリ「レコード屋」。
オープンの日に早速いってみた。
2階の店内に結構な在庫を置いていてJAZZコーナーの棚を1時間以上かけてチェック。
うーん!期待が大きすぎたのか今一歩、何が何でも即買いのこの一枚のレコードがなかった。
地方のショップの品揃えはこんなもんかぁと半ば諦めの心境になっていた矢先、目の下に二つダンボールのケースが置いてあった。
JAZZの表示があったので念の為チェックしておこうと漁りだした。
一枚、一枚引っ張り出していく。
最初は夢か幻でも見ているのかと思った。
頬っぺたをよくやるようにつねってみた。
痛かったのがこんなに嬉しかったことはなかった。
ついに出遭ったのだ。
幻の名盤読本でしっていたし、ジャケ違いで再発もされたのも刷り込み済みだった。でも、どうしてもオリジナルのジャケットでほしかったのだ。元WAVEの瀧口さんのエッセイでも素晴らしい内容なのは察知された。
内容についてはまたの機会にかこう。
このレコードは手に入れたことで私の中では自己完結しているのだ。
こういう体験をこれまでに数回経験している。
夢でみたレコードが一ヵ月後か、数ヵ月後か、3年後か、数年後か、数十年後か・・・いつか出遭うのである。
レコードの神様はいるのだ。
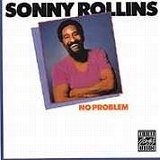
ロリンズに対しては、いまだに特別な感情を抱いている。
1976年1月に、「BLUE SEVEN」を聴いて衝撃を受けそれ以来ジャズを聴き続けている次第で、今聴いてもロリンズの天才が発揮された一曲だと思う。
このアルバムは初任給で買った思いで深い一枚。
「サキ・コロ」に比べれば、ロリンズもやっぱり人間だったんだと思わせるような演奏だが、(70年代以降)曲が結構良くてロリンズにしてはチームワークがとれた演奏になっており何時にまして暖かいプレイが聴ける一枚。
85年に広島でコンサートがあった時、急に見に行こうと思って当日券売り場に並んだ時チケット買いませんかと声をかけられた。
チケットを見ると一列目。私より若干若く見える大学生風の男から額面通りの金額で買ってあげた。
至近距離、約2メートル手前でみるロリンズ。
演奏はやはりロリンズの独壇場であった。
御得意のサーキュラーブレス奏法で延々と音を伸ばしやがてカデンツァに持っていく見せ場もあった。
ゲストのボビー・ハッチャーソンも目まぐるしいスティックさばきでバイブを叩きまくった。
クリフトン・アンダーソンもパワフルなトロンボーンを披露した。
でも圧倒的な印象、オーラを生じているのはソニー・ロリンズだった。
そのプレイに天才性は感じなかったが、肉体の強靭性、鍛錬と節制による集中力、持久力を体感した。
ロリンズの70年代以降の演奏を聴くとジャズは筋力だ、最終的には体力だと思えてしょうがない。
このアルバムはそのコンサートとメンバー編成が違うが今でもよく聴く一枚。
SONNY ROLLINS(TS)BOBBY BROOM(G)BOBBY HUTCHERSON(VIB)
BOB CRANSHAW(B)TONNY WILLIAMS(DS)
1981年12月9~15日録音
昨日N山さんにCDRに焼いてもらったAL GAFA/LEBLON BEACH(PABLO)を聴いています。
これなんか多分リリースされた時見向きもされなかった一枚だと思うのですが、今日の耳で聴き直すと実に良いですねぇ。
はっきりいって甘口。
でもさわやかな風が吹いてきます。
一曲目「BARCELONA」ケニー・バロンのエレピとアル・ガファのギターがソロとテーマを分け合う。
バルセロナのオレンジ色の陽光を浴びながら海岸べりを歩く女性の後姿が見えてきます。
2曲目「ABRE ALAS」いやぁ、まいったなあ・・・
俗に陥る一歩手前というか、ほんと名曲です。
哀愁とペーソスの百花繚乱。
ガファとバロンのソロも実に乗っています。
ここで似たレコードを思い出しました。
今田勝/アンダルシアの風 これは80年くらいの発売のはずだから
ひょっとしてもとネタだったのかもしれない。
アル・ガファ(渡辺香津美)ケニー・バロン(今田勝)結構テイストが似ていると思う。
5曲目「AFFIRMATION」ジョージ・ベンソンのバージョンを耳だこになるほど聴きましたが、それに勝るとも劣らない名演!
同じ頃こんな演奏があったとは・・・28年目にして初めて知りました。
ガファのプレイは決して超テクニックのあるギターではないがアジのあるいぶし銀のプレイ。楽曲のよさを生かすいわゆる音楽を膨らませるタイプのミュージシャンという意味で、ケニー・バロンと同じタイプのミュージシャンだと思う。
アルバムは当時のガファの親分ディジー・ガレスピーの「CON ALMA」で終る。
メンバーは
AL GAFA(G)KENNY BARRON(P)BEN BROWN(B)
AL FOSTER(DS)AZZEDIN WESTON(PER)
1976年4月8日 NY録音
今から20年くらい前の夏によく聴いた一枚。
その頃山陰地方の営業担当だったので海岸沿いを夏、車で走りながらよく聴いたっけな。
夏の白兎海岸の青い空と白い雲を思い出す。
吉田和雄と坂井紅介、通称ベニタマコンビの歯切れのいいリズムが
気持ちいい。小宅珠実や向井滋春、キーボードの小林修も歌心溢れるソロをとっていてブラジル音楽の楽しい雰囲気がよくでている。
このアルバムで中村善郎のボーカルもはじめて聴いた。
当時からベルベットボイスで今のスタイルは確立されていたようだ。
ピアノがメロディーを弾くULTIMA BATUCADAやトッキーニョのESCRAVO DA ALEGRIA,中村が唄うVINHO ESQUECIDOなどリラックスしていて(今で言うとマッタリ)まどろんでしまいそう。
レイラ・マリアの唄やANTI CALYPSOなど楽しく活きのいいナンバーも用意されていて選曲面でもメリハリがある。
最後は波の音がインポーズされたジョビンのLOOK TO THE SKYで幕を閉じる。
夜明け・・・海岸の地平線上から少しずつ朝日が昇ってきて生命の鼓動を感じさせるような一曲。波の音が最後に3回・・・
今でも続くブラジリアンフュージョンバンドの20年位前の力作。

ESTATE・・・初めて聴いたのは、約四半世紀前、ビリー・ヒギンズのRED盤「ONCE MORE」だったと思う。ボブ・バーグのテナーはこの曲にあまりマッチしていなかったようで印象に残らなかった。
いい曲だなと思ったのはチェット・ベイカーの演奏を聴いてから。
それ以来この曲に目がない。
ピアノトリオのものやボーカルもこの曲聴きたさに購入したものは、少なくない。
このMATTHIEU MICHELのTCB盤も出た時からずっと気になっていて
2000年12月に倉敷の「レコード屋」で中古で入手。
メンバー全員が同じテイストの音楽性なのを感じる。
音楽に対してはったりがなく派手なプレイはないが、聴いていてとても心に残るメッセージを伝えてくれる。
ESTATEをはじめとして、リッチー・バイラークのLEAVING、NEVER LET ME GO,トム・ハレルのSAIL AWAYなど名曲揃い。
ティエリー・ラングのワルツ曲もRICHARD GALLIANOのアコーディオンが実に異国情緒をかもし出していて秋の晴れ渡った午後、公園のベンチに座って聴きたい一曲。
途中からMATTHIEU MICHELのフリューゲルホーンが入ってきてガリアーノとのアコーディオンとの絡んで官能的に盛り上がる。
8曲目CARUSO(LUCIO DALLA)のバラードナンバーは映画のテーマ曲のような情熱的な愛を感じさせるナンバー。
歌心溢れるミュージシャンがサウダージ感覚いっぱいにプレイした
名曲集といえる。
秋の一日に聴くをお薦めしたい一枚。

今知ったのですがピート・ジョリーが亡くなったらしい。
冥福を祈って、愛聴盤のリトルバードを聴いてみます。
昔、この辺の白人ピアニストの諸作を熱心に集めていた時期があった。ピート・ジョリーはルー・レヴィーと並んで特によく聴いたピアニスト。
このAVA盤はH野さんに以前聴かせてもらってその素晴らしさは認知していた。
VSOPから再発盤が出た時すぐに入手した。
もう一枚の「SWEET SEPTEMBER」とともにこの「LITTLE BIRD」はピート・ジョリーのたくさん出ているアルバムの中でも最も上位にはいる一枚だと思う。
実に端正できらびやかにスイングできる才能溢れるピアニストだった。
このアルバムではCHUCK BERGHOFERのベースとLARRY BUNKERのドラムスとの鉄壁なリズム隊を率いて軽快にスイングするピート・ジョリーのピアノが満喫できる。
個人的にはやはり一曲目の表題曲「LITTLE BIRD」に最も愛着がある。
白人ジャズのいいところとして推薦したい一作。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 人気歌手ランキング
- ランキングの入れ替日
- (2024-11-24 10:01:24)
-
-
-

- Jazz
- 菊陽町でBOK三昧!
- (2024-11-19 16:30:35)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- John Wetton - An Extraordinary Life
- (2024-11-29 00:00:16)
-
© Rakuten Group, Inc.