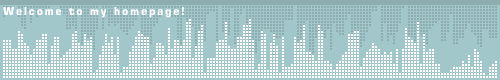音円盤アーカイブス(2,3月)

最近新作が出ないなぁと思っていたらどうやらこのSHAIレーベル倒産してしまったらしい。フランスのメインストリームジャズで活きのいい作品をリリースし続ける会社だっただけに残念でならない。
このOLIVIER RENNEも2001年に仙台のDISK NOTEから通販でローラン・フィッケルソンのピアノトリオと一緒に購入したもの。
TS,ASのツーサックスにスリーリズム、ゲストとして3曲にステファン・ベルモンドがTPで参加している。ピアノはローラン・フィッケルソンが担当している。
ドラムがリーダーで楽器編成からもトニー・ウィリアムス・クインテットを連想してしまうが、バンド自体を自らのドラム捌きでしっかりコントロールして、鼓舞するところなど似ていると言えるかもしれない。
1曲目はステファン・ベルモンドの切れ味鋭いアドリブに続きテナーのYANNIC KRIEUとフィッケルソンのピアノソロはどちらともモーダルでフリーな展開も含ませつつやや抽象度高めのプレイ。
12分強の演奏がとても短く感じられる充実した演奏。
2曲目の「CHANT DU NIL」でのフィッケルソンのピアノソロはハンコック以降のピアノスタイルを消化したスタイルでとても美しい。
後期コルトレーンのような曲。
3曲目は口笛とドラムの共演の小品。
4曲目はステファン・ベルモンドが再び参加して活きのいいモードジャズが展開される。やや地味な感じで低音中心のサックスソロからベルモンドの輝かしいトランペットに引き継がれた瞬間、音楽のギアが何段か切り替わったようにボルテージが上がったように感じた。このCD、ベルモンドを全曲参加させたほうがより出来が良くなったかもしれない。速、陽、鋭のベルモンドと二人のサックス陣との対比がでてサウンド的にもメリハリがよくついて面白いと思うのだ。
肝心のリーダー、OLIVIER RENNEだが、トニーやエルビンみたいな圧倒的な個性はないが、各プレイヤーの個性を活かすフレキシブルな感覚をもったドラマーでバンドの統率力も秀でているのではないか。そして作曲能力、このアルバムラストの「夜は千の目を持つ」を除いて全て自作曲。昔からドラマーの書く曲に名曲多しと言ったものだがここでも例外ではない。
8曲目のバラード作もいい感じに仕上がっている。
最後は夜千でもって大円団を迎える。
録音は2000年6月5,6日 RARIS

テナー奏者にエリック・アレキサンダーが入っていたので購入した。最近は追いかけるのを止めてしまったが、デビュー以来エリックの参加作品はできる限りフォローしていた。
エリックのテナーを実は久しぶりに(と言っても1,2ヶ月ぶりだが)聴くのだが、ひとつの確固たるスタイルを確立したなぁと実感した。初期の頃のデクスター・ゴードンの影響が色濃くでたスタイルから脱却して伝統的でよく歌うフレージングの持ち味はそのままに、コルトレーンやジョージ・コールマンのスタイルをブレンドさせた重厚であるが、スムースさも感じさせる二律背反のスタイルを確立したのではないか。
速いフレーズを吹いても決してセカセカした印象を受けない。
バラードでは甘いだけではないハードボイルドな表現も難なくやってのける表現力の幅を身につけた。
音楽をスイングさせ、歌うことについてはこれ以上学ぶことはないのではないかと思わせるくらいエリックのテナーの吹きっぷりは素晴らしいものがある。
しかしだ、ここからが問題なのだ。
エリックの最近の演奏にはサプライズが薄くなってはしないか?
聴く前からこの曲だったらこういう音色でこう解釈するのではないかと悟られてしまうような演奏。
それがひとつの確固たるスタイルだと逆に言えないこともないだろう。
でも、このままのスタイルでずっといってしまうと意外と早く我が国のファンからもソッポを向けられるような気がしないでもない。
契約したレーベルがあのVENUS。
今のエリックに最も最適というか、最悪というか、最も安住の地というか、心配である。このレーベルにいる限り自分の殻を打ち破るようなレコーディングセッションは組まれないであろう。
エリック・アレキサンダーよ、まだまだ若いのだからもっと冒険してくれぃ! チャレンジしてくれぃ!
今日は何時になく検事的な耳で聴いてしまったのであった。
というのも正統派テナーでそれだけエリックを買ってのこと。
あえて苦言を呈した次第。
ところでこのCD、決して悪い出来ではない。
フィンランドのベーシストがリーダーの快適な4ビートセッション。
メンバーは、ERIC ALEXANDER(TS)PETER MIHELICH(P)
ATRO "WADE" MIKKOLA(B)JOE FARNSWARTH(DS)
録音は1995年10月2日 BROOKLYN NY
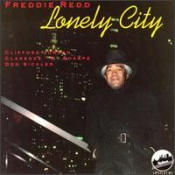
1989年に「ライトハウス」の通販カタログを見てこれは直ぐに買わねばと注文したレコード。メンバーの中に伝説のアルトサックス奏者クラレンス・C・シャープの名前を発見したからだ。
フレディ・レッドの楽曲をドン・シックラーがアレンジを施している。
1曲目から歯切れの良いニューヨークのダウンタウンのクラブでいかにも鳴っていそうなコクのあるバップサウンドが響き渡る。
ベン・ライリーのドラムが今まで聴いた事がないくらい歯切れの良いリズムを刻んでいてこんなに素晴らしいドラマーだとは思わなかった。
2曲目のファーストソロでお目当てのC・シャープのアルトソロが聴ける。
正直言って「???」なのだ。 わざと外して吹いているのではないかと思うくらいピッチが悪い音。実際、歯に問題を抱えていてアルトサックスを通常のアンブシュアーで吹くことはできなかったらしい。テナーのクリフォード・ジョーダンはそれに比べてややテナーにしたら高い音使いでまっとうなソロを展開している。
で、どちらが印象に残るソロなのかといえば、これが圧倒的にクラレンス・シャープなのがジャズ演奏の面白いところ。
フレディ・レッドの楽曲は躍動感に富んだジャズの楽しさを教えてくれる良曲揃い。
レッドのピアノ演奏が記録されているレコードでは50年代初頭にレコーディングされたメトロノーム盤がそれまで一番の愛聴盤だったが、このアルバムを入手してから同じ割合で聴くようになった。
4曲目は「THESPIAN」フレディ・レッドの楽曲の特徴が色濃くでた作品だと思う。
5曲目はアルバム表題曲にして一番の聞き物。
レッドの天上の調べの様に美しいピアノのイントロに導かれて哀愁度高めのテーマが奏でられる。そしてクラレンス・C・シャープのアルトソロ。
短いけれど抜群の存在感をもったワン&オンリーな「くさや」のようなソロ。
演奏しているミュージシャンの心がひとつになったかのようにジャズマインドを最高に感じ取れる1曲。
ラストは曲名通りタッド・ダメロンの作風を思わせるこれまた良い曲だ。
メンバーはCLIFFORD JORDAN8TS)CLARENCE`C`SHARPE(AS)
GERRY CAPPUCCIO(BS)DON SICKLER(TP)FREDDIE REDD(P)
GEORGE DUVIVIER(B)BEN RILEY(DS)
録音は1985年1月18,19日 ENGLEWOOD CLIFF, NJ

1994年に倉敷の「レコード屋」で中古盤で入手したCD。
マイケル・コクレーンといえばそれまでハンニバル・マーヴィン・ピーターソンのサイドマンなどで名前は知っていたが、そのピアノプレイを本格的に聴いたのはこのCDが初めてだった。
いぶし銀のプレイとはこういうプレイのことを言うのだろう。
こんなに味があってよく歌うピアノはその頃新譜で買ったCDで聴いたことがなかった。
それ以来コクレーンの新作が出ると追いかけ続けている。現在、STEEPLE CHASEと契約していて年に一枚のペースで新作がリリースされ続けている。
最近はピアノトリオよりテナーにボブ・マラックを迎えてカルテットでの吹き込みが多くなってきているが、コクレーンのピアノを堪能したいファンには勿論ピアノトリオ作品の方がよいだろう。
このアルバムはSOULNOTEから1993年にリリースされた最初の頃のリーダーアルバムで、いぶし銀のプレイに瑞々しさも感じられてコクレーンのピアノがとても新鮮に響く。
実際コクレーンのピアノはそんなにアクの強いスタイルでもないし、テクニシャンでもない。圧倒的な個性の持ち主でもない。
でも、そんなことがどうしたと言うんだ?
好きな曲やオリジナル作品を真心込めて精一杯の自分のジャズを演奏する。
自分も楽しんでファンも楽しませる。考えてみればエンターテイメントの基本である。
この人のオリジナル作品は実際ラテンフレイバーのイイ曲が結構ある。
ケニー・バロンがこれだけ評価されているのなら、その何分の一かマイケル・コクレーンのも目をかけて欲しいものだ。
メンバーはMICHAEL COCHRANE(P)MARCUS MCLAURINE(B)ALANNELSON(DS)
録音は1992年11月22,23日 NY

今年になってはまっていることがある。
晩酌の時に芋焼酎をお湯割りか水割りで飲んでいる。
今まで全く関心がなく飲むとしたらワインかウイスキーで色々試してきたが焼酎がこんなに美味しいものだとは知らなかった。そして、これも奥が深い。酒の種類が変わるとそれに合う料理も必然的に変わってくるわけで、すっかり和食中心の食生活になってきた。
のっけからジャズに全然関係ない話になってしまったが、焼酎キングとの異名をとるジャズミュージシャンが我らが高橋知己なのだ。
命名したのはこのアルバムが捧げられた亡きエルビン・ジョーンズだという次第。
2000年にリリースされた前々作「NOTHING LIKE YOU」にその「HE CALLS ME SHOW-CHEW KING」という由来の曲が収められている。
このアルバムはエルビンとの度重なる共演を経験しソウルブラザーといっての良い旧知の仲の高橋知己が、昨年のエルビンの死から間もない8月にエルビン縁の曲をつづった最新作で先月リリースされたばかりのもの。
レギュラーカルテットによる演奏なのでどの曲もバンドとしての統一したサウンドが出ていて成熟したカルテットの演奏が楽しめる。
そして一番の聴きどころなのは、知己のテナーサウンドなのは言うまでもない。
柔らかいんだが音に芯があって厚みがあり、どっしりと座った安定したテナーの音色、
ハードボイルドな表情のなかに無類の優しさも覗える包容力もその音は表出するようになったのではないか?
全部で9曲収録されているが、「THREE CARD MOLLY」「SIMONE」「MR.JONES」「CRESCENT」の4曲がとくに気に入っている。
なかでもフランク・フォスターの「SIMONE」は出色の出来で繰り返し繰り返し聴いている。この曲のベストと言ってよいバージョンだと個人的に思っている。
メンバーは高橋知己(TS,SS)津村和彦(G)嶋友行(B)小松伸之(DS)
録音は2004年8月23,24,25日 アケタの店で収録
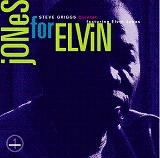
実はこのCD、昨日高橋知己の最新作をアップしていた日に駅前の「グルーヴィン」で中古盤で発見したもの。エルビン・ジョーンズにちなんだアルバム紹介が続くがこれもなんかの因縁だろうから早速紹介しよう。
HIP CITYというレーベルはこのSTEVE GRIGGSのアルバムばかり出しているので自費出版のレーベルなのが分かる。エルビン・ジョーンズと共演するのが夢だったのだろう。
買ったのはVOL.1だが、実際VOL.2も発売されている。
トランペットにはJAY THOMASが参加。
シアトル在住のミュージシャンと3日間で16曲収録が行われたそうで、彼らにとって最高の時間だったことが察せられる。
エルビンの縦横無尽のドラミングが音楽をグイグイ引っ張っているのは紛れの無い事実でそれにGRIGGSら4人のメンバーがついていっている感じは否めない。
役者が違うとはこういうことを言うのだろう。
しかし、GRIGGSはオリジナル作品を2曲を除いてアルバムの為に書き下ろし、テナーを精一杯吹奏する姿勢には好感が持てる。
ミュージシャン全員のジャズに対する取り組み方やエルビンへのリスペクトがレコーディング全体から滲み出ているようで悪い気はしない。
オリジナル作品も変化に富んでいて佳作揃いで、エルビンの様々なドラミングが楽しめる仕掛けがなされている。
メンバーはSTEVE GRIGGS(TS,SS)ELVIN JONES(DS)MILO PETERSEN(G)
PHIL SPARKS(B)JAY THOMAS(TP)
録音は1998年5月19-21日 WOODINVILLE

4日の朝から更新が遅れていたのですが、実はインフルエンザにやられてしまいまして39度ほどの熱が出て寝込んでいたのです。
さっき計るとだいぶ熱も下がり楽になってきたので更新しております。
いやはや、36時間ぶっとうしで寝続けていたので頭がまわりません。
このMARLENE ROSEMBERGのCDも昨日紹介の盤と一緒に駅前グルービンで買った。
国旗のシールが貼られていたのでLPコーナーの倒産流れ品だと思う。
こんな冴えないジャケなのに何故買ったかというと、テナーカルテットによる演奏でメンバーがJAVON JACKSON(TS)CEDAR WALTON(P)だったから・・・
JAVON JACKSONというテナー奏者CRISSCROSSから当時出た初リーダーアルバムを大阪のLPコーナーで\3400もの高値で買った記憶がある。その共演者がエルビン・ジョーンズだった絡みもあり、出来に期待していたのだが見事に外してくれた。
ジャズ批評誌でこぶ平が、「ジャボンのテナーはザボン」と言いえて妙な表現をしていたのを思い出す。この人リーダーアルバムよりサイドメンで演奏しているアルバムに意外といい演奏しているものが多い。小島勉カルテットしかり、TIMELESSのスーパーカルテットしかり。このアルバムでもそんな次第で適度に力が抜けたリラックスしたジャクソンのテナーが聴ける。
4曲目はピアノトリオで、演じられるダークな印象をうけるスローナンバー。
ローゼンバーグのベースソロとシダー・ウォルトンの神妙なソロが聴けるナンバー。
5曲目がやはり最大の聞き物であろう「HOLY LAND」。
寺島さん的に言えば、「この1曲の為に、このアルバムの価値はあがった」と言えよう。
後半はピアノトリオによる演奏でローゼンバーグのベースソロとシダー・ウォルトンのピアノソロがばっちり楽しめる仕掛けになっている。
メンバーはMARLENE ROSENBERG(B)CEDAR WALTON(P)JAVON JACKSON(TS)
GEORGE FLUDAS(DS)
録音は1999年 CHICAGO

2ヶ月くらい前に注文していたCDがHMVからようやく到着。
勿論、ボッソ絡みで購入したもの。
ボッソとイリオ・ディ・パウラとの前作は素晴らしいボサノバデュエット集だったが、この作品はストレートなジャズ作品になっている。
1曲目「WHAT IS THIS THINGS CALLED LOVE」は名刺代わりの1曲とういか、ボッソの躍動感溢れるトランペットソロに続くイリオ・ディ・パウロのギターソロがバップの香りに溢れた巧みなソロワークで聴き物。
2曲目はボッソはFLHを使用。アレンジがロック風でこんな「BLUE BOSSA」もありなのかなぁと言う感じで、ややミスマッチの感は否めない。もっと普通に演奏した方が原曲が素晴らしいのでより大勢にアピールできるのでは?
3曲目は「枯葉」ボッソが吹くと枯葉じゃなくて5月の青葉繁れる瑞々しい新緑の若葉になったような演奏に聴こえる。マイルスのミュートとは対極的ともいえるミュートトランペットだが、現状の勢いを感じさせるソロワークが聴けると思う。
5曲目「チュニジアの夜」はスローテンポで演奏される。この曲はやはり血肉湧き踊るようなソロが爆発するようなアップテンポで聴きたかった。
ボッソやパウロのソロは素晴らしいのでご安心を・・・
6曲目「I REMEMBER APRIL」。そうそうこのテンポが聴きたかったのだよ。
上り調子のミュージシャンに小細工はいらぬ。ただ素材と最適なテンポを与えたら名演が生まれる実例じゃないかな?
「ジョーンズ嬢に会ったかい?」をはさんでラストはソニー・スティットの「LOOSE WALK」。ファーストソロはパウロ、タッチの強いきつめのピッキングでよくこれだけ流麗なソロが取れると思う。ボッソも持ち前の味を発揮してアルバムは幕を閉じる。
全体の印象、ジャムセッションでの人気曲をボッソが快演したアルバム。しかしこのアルバム、ハプニングがなかった、予定調和の世界に収まっている。それでも充分に素晴らしいのだけれどボッソクラスになると要求のハードルも高くなるもので、全曲「I REMENNBER APRIL」のようなはりきりプレイをもっと聴きたかったのが本音のところ。
メンバーはIRIO DE PAULA(G) FABRIZIO BOSSO(TP,FLH)MASSIMO MORICONI(B)
MASSIMO MANZI(DS)
録音は2003年1月15日 MILANO

オーストリアのQUINTONレーベルのHPで試聴してそのサウンドが気にいってDUから通販で買ったのが2002年の春先のこと。
店頭で見ただけだったら見向きもしていなかっただろう一作。
楽器編成はフレンチホルン、ギター、ベースにゲストのドラムやクラリネット奏者が絡むといった趣向。
2曲目「PRESENTE TO MOSCOW」でその美旋律に耳を奪われた。
乾いた抒情性というのか、ジャズのソロ楽器として決して向いているとは言えないフレンチホルンの音色が東欧のブラジルというか、サウダージ感溢れたメロディーを奏でるのだ。
4曲目「BACHIADO」も哀愁度高めの歌謡性に富んだメロディー。
フレンチホルンとアコースティックギターのブレンドされた音がこれほど調和がとれてしっくりくるサウンドを作り出すとは思わなかった。
5曲目「VINDOBONA」も大きく打ち寄せる波の満ち引きを連想させるような、地球的リズムからなる自然賛歌。牧歌的な雰囲気に聞き惚れてしまう。
6曲目はこのアルバム中最もキャッチーなメロディーをもつこれまた名曲「AMIGO DE INFANCIA」。ALEGRE CORREAのギターが特に活躍する。
晴れ渡った湾岸道路を車で疾走するイメージか?
7曲目は情熱的なラテン性を感じさせる躍動感に溢れた曲。
8曲目「MANHATTEN」でARKADY SHILKLOPERのフレンチホルンの超絶技巧ぶりが聴ける。
もっともジャズテイストの強い曲。
ラストは「FUNK ROG」途中4ビートになってスキャットまじえながらスイングするところなんか滅茶苦茶かっこイイ!
録音は2001年1月28-30日 VIENNA

このアルバムを初めて耳にして、全編日本語で唄われている事に驚いた。
FM番組「ソニーミュージックスコープ」か「気まぐれ飛行船」で紹介されたのを聴いたのだと思う。
このアルバムがリリースされた1977年は「ジャズライフ」誌が創刊された年でちょうどこの「TOKYO SPECIAL」もレビューが載っている。
この年の夏に開催された第1回LIVE UNDER THE SKYには、笠井紀美子、ジャズ・オブ・ジャパン、V.S.O.P.クインテットが出演。当時の笠井紀美子人気がうかがわれる。
実際このアルバム相当ヒットしたはずで、10年以上経ってから渋谷の「CISCO」だったか?\300で入手した。
笠井紀美子は一度だけ観た事がある。広島のジャズフェスに1985年だったか出演した時のこと。私は夕方からビールを飲みまくり、酔い覚ましにフェスティバルの会場ゲート付近をうろついていた時、一台のタクシーが止まった。そこから降りてきたのが笠井紀美子。
目と目が合って日頃ならそんな勇気ないはずなのを、酔いにまかせて喋りかけたのだ。
少しビックリしたようだったが、応対してくれた。その日はピアノトリオをバックにスタンダードを歌ったはず。
このアルバム、70年代の自由な空気が一杯詰まった真の意味でのフュージョンミュージックに今の耳で聴き返しても成っていると思う。
ジャズ、クロスオーバー、ブラックコンテンポラリー、ニューミュージック、R&B、様々な音楽のテイストが感じられるが、1本芯の通ったストーリーが笠井の語り口から感じられるのだ。
プレイヤーズの全身コルゲンバンド時代のバックの演奏も最高にイイ。
いまだにA面は個人的にヘビーローテーションの一枚だ。
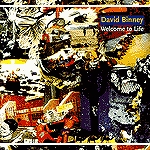
デビッド・ビニーの最新作、去年の秋AMAZONから通販で購入。
ビニーの名前を初めて知ったのは、約10年前。スコット・コリーのFREELANCE盤を買った時メンバーとして参加していて、印象に残るアルトサックスを吹いていたので記憶に残った。
アクトからでた作品とほぼメンバーが一緒だが、このメンバーのラインナップがお気に入りのミュージシャンばかりで、頬が自然と緩む。
デイブ・ビニーのアルトサックス、クリス・ポッターがテナー、クレイグ・テイボーンがピアノ、アダム・ロジャースがギター、スコット・コリー、ベース ブライアン・ブレイド、ドラムスといった現代ジャズ精鋭部隊によるアルバム。
コリー、ブレイドの骨格のしっかりしたそれでありながらある種の揺らぎも感じさせるビートの上をソロイストが独自のサウンドアプローチを展開していくと言った図式だが、
彼らのソロに共通して流れているコンセプトはクール、揺らぎ、浮遊感覚といったもの。
彼らブルックリン派若手ミュージシャンのサウンド指向の特性が如実に現れた一作と言っても良いと思うが、勿論ソロイストとしてのオリジナリティーの追求といったジャズアーティストとしての本能的な部分もあるわけで、その当たりのバランス感覚、揺らぎ度合いが丁度いい具合に均衡を保っているのではなかろうか?
一人一人がサウンドメイキングの重要な担い手でありながら、それぞれが存在感のあるインプロバイザーである。これって、昔ウェザーリポートが70年代に結成した時指向した音楽的スローガンじゃなかったっけ?
ブルックリン派の若手ミュージシャンの動向は今後も目が話せない。
録音は ブルックリン システムツーサウンドスタジオ

岡山のLPコーナーから通販で買ったレコードで、カルテットというのは、ビル・エヴァンスとラファロをいれてカルテットであって、実際はラリー・コリエルとミロスラフ・ビトウスのデュオレコーデイング。
最初は淡々と繰りひろげられるデュエットであるが、2人のエバンス~ラファロに対する敬愛の念が、曲が進むに連れてどんどん滲み出てきて次第に演奏に引き込まれていくのだ。
録音が良いことも特筆できよう。
ビトウスのベースがこんなにアコースティックで木の質感をともなって録音された音源を他にあまり聴いた事がない。
4曲目「CORCOVADO」ではビトウスのアルコが聴ける。
ジャズでのアルコ奏法はあまり好きではないが、ビトウスのアルコは例外で、聴き入ってしまう。大きな体に似合わず繊細で複雑なラインを縦横無尽に弾きまくるビトウスのアルコソロは昔一回生演奏を見たことがあるが、本当に迫力があった。
ラリー・コリエルはゲイリー・バートンのグループやイレブンハウスなどのロックテイストの強い演奏しかそれまで聴いた事がなかったのだが、このアルバムでジャズギターの伝統性を踏襲したオーソドックスなプレイに認識を新たにした次第。
ラストはジミー・ロウルズの名曲「THE PEACOCKS」。
名手2人による解釈はこの曲のもつ陰影感に富んだ幽玄の美とでも言おうか、曲調をよく理解した演奏で聞き応えがあるバージョンとなった。
録音は1987年5月13日

2000年12月倉敷の「レコード屋」で\990で買ったCDで、テナーにマイケル・ブレッカーのそっくりさんと言われているOVE INGEMARSSONが参加しているのを、クレジットを見て発見して「はて、どんなものか聴いてみよう」と買ったのだ。
聴いてみてマイケル以上にマイケル・ブレッカーに似ているというパラドックスのような解答がでてくるほど、このオーべ・インゲマルソンというテナー奏者、そっくりなのだ。
1曲目「MIRROR」の最初のテナーの出だしの音からマイケル・ブレッカー本人が吹いているのでは?と思わずクレジットをもう一回見るくらい細かいニュアンスまでそっくりなテナーサウンド。EWAN SVENSSONはアコースティックギターを使ってしなやかなプレイを披露。
2曲目はややテンポアップして温度感もやや上昇傾向の曲調で、オーべのテナーもよりアクロバティックなマイケルらしい複雑でありながら数学の方程式のような理路整然としたソロパフォーマンスを展開。EWANのギタートーンはパット・メセニーライクか?
3曲目「MONDAY AFTERNOON」オーソドックスな4ビートで演じられる曲だが、テーマ、アドリブともマイケル・ブレッカー~パット・メセニーのスタイルに代表される現代ジャズ奏法のモデルケースとも言える語法にて語られる。
オーべ・インゲマルソンのリーダーアルバムもその後DRAGON盤を最初に入手したが、このアルバムと同じくマイケル・ブレッカー・スタイルの作品であった。
2003年にスパイス・オブ・ライフから日本でのライブ作をリリースしたが、その作品ではマイケル一辺倒のプレイから脱却してコルトレーンの影響も感じさせるプレイだったので、本人の個性というものはまだまだこれから発揮するテナープレイヤーかもしれない。
テナーのテクニック的な点ではこのアルバムの吹き込まれた1994年の時点で完成されていて、ケチのつけるところの無い完成度を身につけていると言える。
まだまだ吹き込みもそんなに多くないので、これからもライブにレコーディングに活躍して欲しいテナープレイヤーである。
6曲目「APRIL WALK」などもマイケルのアルバムを聴いているような錯覚に陥りそうなくらいだ。
録音は1994年11月24,27日 KUNGALV

このCDを買った1994年当時はジェリー・バーガンジィーに目が無かった。
1992年から94年くらいにかけてバーガンジィーの参加した作品は結構そんな訳で買っていたがこの「NAPOLI CONNECTION」もそうした一枚。
バーガンジィーのプレイを初めて聴いたのは、彼がまだデイブ・ブルーベックのバンドの一員だった頃のレコードだったが、その頃はこの頃に比べてスタイルがまだ確立されてなくて印象がちょっと薄かった。
88年頃REDからリリースされた「JERRY ON RED」を聴いてそのエグミ成分の多い激シブテナーに一辺にノックアウトされた。
それ以来バーガンジィーのクレジットを見つけたらCDを買い上げる日々が暫らく続いた。
RED,ENJA,LABEL BLEU,MUSIDISC,NUBA,FREELANCE色々なレーベルの様々なミュージシャンのCDを買った。リーダー作でもサイドメン参加作でもプレイのクオリティーが一緒で、決して手抜きのプレイをしないのも魅力のひとつで、この時期のバーガンジィー参加作にハズレなしといっても過言でないと思う。
この人の場合長い下積み時代を経て、ソロイストとして様々なレコード会社からアルバムをリリースするようになった時点で既に自己のスタイルを完全に確立していたわけで、その人生経験に裏打ちされた酸いも甘いも噛み分けたいぶし銀のハードボイルドテナーは最近の若手テナー奏者では出せない味。
そして作曲家としても評価できると思う。
このアルバムでも大半がオリジナル曲だが、メロディーが美しかったり聴きやすい曲では決してないけれども、ジャズ喫茶の暗い空間や夜中1人で聴いていると思わず聞き惚れてしまう通受けする渋い曲が多いと思う。
で、このアルバムで一番の聞き物は何かというとBRUNO MARTINOの名曲「ESTATE」なんですけれどもね。バーガンジィーのテナーの入り方がこれまた滅茶苦茶渋いのであります。
メンバーは TRIO IDEA VALERIO SILVESTRO(P)TONY RONGA(B)SALVATORE TRANCHINI(DS) JERRY BERGONZI(TS)
録音は1992年3月12日 NAPOLI

1988年、センチュリーレコードから期待の新鋭グループがデビューした。
名付けてMG4(マンハッタン・グラフィティー・フォー)。ケニー・ギャレットに藤原清登が結成したグループなので、発売日に直ぐ買ったのを覚えている。
1曲目のマーチ曲「DA NIRO」の少し変なメロディーをケニー・ギャレットが情熱的に吹きつづっていくところから、彼らのこのレコーディングにかける熱意が伝わってきて鑑賞にも身が入った。アブストラクトなピアノソロ、藤原清登のアルコソロに続き再びケニー・ギャレットに戻される構成
2曲目も藤原の作品で、テーマはギャレットによってサブトーン気味に吹かれる淡い雰囲気のバラードナンバー。
3曲目もメロディーが1曲目と同様に少し抽象的な面白い曲で、題名通り、ケニーのアルトが活躍するナンバー。モンクの「PANNONICA」マッコイの「PASSION DANCE」と続いて
6曲目がこのCDのなかで一番のお気に入り「BOY AND BEAUTY」。
藤原作の優しい感じのバラードナンバーで、ニューヨークという大都会に暮らす若いミュージシャンの苦悩と明日への希望といった雰囲気を感じさせる曲。
7曲目は「ON GREEN DOLPHIN STREET」藤原のベースがアルコ奏法でテーマを奏で、途中からピッチカートに転換。今でこそベースマスターの域に達している藤原だが、この頃から既にテクニック的には完成していたことが覗えるトラック。ケニーはお休み。
短い超アップテンポの8曲目をはさんで、9曲目もこのグループの特徴がよく出たナンバー。
ラストは一捻りしたクールな感じのピアノトリオによる「枯葉」で幕が閉じられる。
このレコーディング時点でケニー・ギャレットはOTBに参加しており、既に売れっ子の仲間入りを果たしつつあったが、若手の不遇時代切磋琢磨した音楽仲間のために喜んでレコーディングに参加したというケニー・ギャレットの人間性もうかがわれる作品。
録音は1987年10月3,4日

10数年来のファンである中村善郎のセカンド作。
このアルバム1曲目が「春(PRIMAVERA)」という曲で文字通り、春の雰囲気たっぷりの明るくほんわかした楽しい曲。中村善郎と橋本一子のデュエット。
デビューアルバムは発売日に買ったが、この2作目は買い逃したままで、そのまま廃盤になってしまっていたのだが、近所のスーパーマーケットの中古CD市で偶然発見して入手した。1995年のこと。
中村の歌に選ばれているテーマは「失恋」「傷心」「孤独」「出会い」「別れ」などがキーワードになっていることが多い。
深刻に歌うと重苦しくなりすぎるテーマをあのベルベットボイスで淡々と決して軽い調子でもなく、まるでもう1人の自分が傍観者のようにクールでシニカルな視線で見つめているかのようなイメージで伝わってくる。
そして歌われるメッセージは確実にじわじわと遠赤効果の様に骨身にしみてくるのだ。
ピエール・バルーと一緒に歌われる「出会い」。
このアルバムのエポックメイキングだろう。
この頃の中村のアルバムはブラジル音楽を切り口にしているのは、間違いないのだが
無国籍性というか、ヨーロッパの石畳の裏通りやバールの風景、サウダージから地球半周戻って日本の「侘び」「寂び」の概念まで感じとるのは私だけだろうか?
アルバムのライナーに書かれている中村自身の文章を引用しよう・・・
エトランゼ・・・。孤独。
僕は一人で見知らぬ街角を彷徨ってきた。
ホテルやレストランで短い言葉を交わす事はあったが、
人と口をきく事もまれな日々が続いた。
もちろんどの街にも友と呼べるものはなかった。
寂しさが胸の中で疼く。
しかしそれは心地良い痛みでもある。
僕は誰でもない、僕自身でいられるから・・・。
旅はいずれ終わりが来る。
そうすればあのくすんだ、そして湿った空気の街に帰って行く事になる。
友と再会し、見慣れた毎日が始まるだろう。
しかい僕は胸の中にエトランゼを抱き続けるだろう。
僕はいま痛感している。
誰もが人生という旅を通り過ぎて行く。
孤独なエトランゼでしかない事を・・・。
(中村 善郎)
録音は1991年1,2月

1月にDUから購入。フランスの若手テナー奏者STEPHANE GUILLAUMEがどんな音楽をやっているのか興味が湧いて注文した。
柔と剛、両方を持ち合わせたプレイヤーだなぁと聴いた瞬間悟った。
自らは各種サキソフォン、クラリネット、フルートを操り、綿密に編曲されたハイブロウな曲を見事なリーダーぶりでサイドメンを牽引していく。
曲作りに知性が感じられる、かといって頭でっかちなのではなくて、プレイは結構肉体派の部分もあって感覚派の要素が感じられるのだ。
知性と本能的な部分が微妙なバランスで釣り合って自己のサウンドを形成しているのがこのステファン・ギョームなのではないか?
曲や編曲面では、ウェイン・ショーターやギル・エバンスの影響が感じられない事もない。
抽象派、印象派といった言葉がしっくりくる曲もあるし、カレイドスコープを覗き込んだようなサウンドコラージュの様な曲もある。
リードプレイヤーとしての実力があるので、どんな展開であろうと音楽自体にパワーがあり、説得力が生まれている事はこの人の大きな武器だろう。
おそらく伝統的な4ビートでも、フリージャズでも、フューチャージャズやエスニック系音楽でもオールラウンドに素晴らしい演奏ができるプレイヤーではないか?
このCDを聴いているとそう思わずにはいられない音楽家としての土壌の広さとプレイヤーとしての卓越性を感じ取るのだ。
フランスの新たな才能を感じさせるマルチリード奏者の誕生を喜びたい。
録音は2003年6月

デンマークの無名の若手テナー奏者のリーダーアルバム。バックのKURT ROSENWINKEL,
PAUL MOTIANの名前に惹かれて2000年に岡山「ディスクトランス」で買った。
1曲目モンクの「ASK ME NOW」から現代のブルックリン系ともいえる響きのするサウンドが流れ出す。テナー、ギター、ベース、ドラムのカルテット編成のフォーマットが中心になると言ってもよいと思う。もちろんこれの変化形もあるのだが、和声的に自由でサウンドに膨らみや揺らぎ、タイム感覚の伸縮性を感じさせる要はこの編成なのだろう。
マーク・ターナー、ビル・マクヘンリー、クリス・チーク、シーマス・ブレイク、ノア・ベッカー、ダニー・マキャスリン、そして御大ジョー・ロバーノらがギター勢このカート・ローゼンウィンクル、ベン・モンダー、アダム・ロジャース、スティーブ・カルディナス、御大ビル・フリゼルら絡んでいるレコーディングは思いのほか多くて一つのサウンド指向としての明白な方向性を示していると言っていいような気がする。
そしてそのサウンドの元祖ともいえる音楽家がこのアルバムにも参加しているポール・モチアンなのだ。
80年代からジョー・ロバーノ、ビル・フリゼルを加えたユニークなバンド活動を実践し
90年代以降からエレクトリック・ビーバップ・バンドを結成。先のブルックリン派の多くがこのバンドでの演奏経験がある事は紛れもない事実として認識されよう。
現代ジャズの一つのサウンドモデル、雛型を形成した創始者的存在としてポール・モチアンというミュージシャンは後年歴史的評価が今よりももっともっと上がるような気がする。
ブルックリン派のこういうサウンド指向、即興演奏面では一言でいえば「クール」が合言葉になっているプレイスタイルはこうして現代ジャズシーンにおいて確固たる位置を築きつつあると言って良いと思うが、かってのビバップがそうであったようにスタイルの推進、蔓延がオリジナルなジャズ、音楽といった面で閉塞的状況を生み出す危惧も同時に出て来る訳でそうした問題を、各々ミュージシャンがどうやってクリアしていき独自のサウンドをつくりだしていくのかこれからも見守っていきたい。
このアルバムの事にあまり触れなかったが、好調なセッションの記録として充分鑑賞に耐える作品で、テナー奏者としてもJAKOB DINESENは今後に期待できる有望株だと思う。
メンバーはJAKOB DINESEN(TS)KURT ROSENWINKEL(G)ANDERS CHRISTENSEN(B)
PAUL MOTIAN(DS)
録音は1999年5月13日 SOUND ON SOUND STUDIO NY

アルゼンチンのテナー奏者RICARDO CAVALLIの前作で2003年の今頃仙台のDISK NOTEから通販で購入したCD。
CAVALLIのテナーの音色はアルゼンチンという地域性が関係しているという事もないだろうが、暖色系で力強い音でフレーズを明確に吹き上げるタイプ。
低域は黒人っぽい音色で、(ジョニー・グリフィン+ボブ・バーグ)÷2みたいな感じを思い浮かべてもらったらいいかな?同じく南米テナーのデビッド・サンチェスにも少し似ているか?
3曲目「LA ENTREGA」などデクスター・ゴードンのような後のり具合で、マッタリとスローバラードを吹き上げるところなんか、「お主、なかなかやるわい!」といった感じでテナー奏者としての実力を覗わせる。
NYの若手テナーのような新感覚は薄いのだけれど、自身の信念に基づいた明確なフレーズを力強く吹き綴っていくところは、颯爽とした思い切りのよさを感じさせ、聴いていて気持ちいい。
作曲にも長けている。リズムの変化に富んだ色彩感豊かな曲が多く、自身のこってり系のテナーサウンドがよく映える曲調といえばよいか、全編リズムセクションとともに気合の入った演奏になっている。
反面、注文もある。音色、作編曲、演奏、一流のジャズには必ずといっていいほどある、ミステリアスな部分、聴いて分りづらい謎の部分といったものが、やや希薄なのである。
音と音との行間になにかサムシン・エルスを表現するような、演奏せずに無音のところが逆に音楽になっている「間の芸術」の様な変化球玉のような表現力を今後身につけたら、
RICARDO CAVALLIは、より創造性に溢れた独自の演奏スタイルを持つより大きな演奏家になるであろう。
メンバーはRICARDO CAVALLI(TS,SS)GUILLEMO DELGADO(B)DIEGO LUTTERAL(DS)
GUILLERMO ROMERO(P)
録音は2002年 ARGENTINA

去年の今頃、休日にレコードを物色しに駅前まで出かけたとき、グルービン本店の2Fのレコードコーナーでこのアーデルハルト・ロイディンガーのECM盤を格安で発見。
ジャズを聴きだした頃、山下洋輔や坂田明絡みで、アーデルハルトの名前はよく耳にしたし、山下の本で、物理学者で研究にいきづまるとベースをかき鳴らし、演奏ツアーに出かけることも読んでいた。
日本にも山下とのデュオツアーが組まれたはずで、FMラジオでライブレコーディングを聴いた記憶がある。
当時そんなふうに聴いたアーデルハルトのプレイは怒涛の勢いで高速ベースをかき鳴らす
超人ベースプレイヤーといった印象であった。
このレコードを聴くまでは・・・
超絶テクニックを誇る速弾きベーシストとしての印象しかもっていなかったのが、このレコードの1曲目からそういった先入観を根底から覆された。
幻想的な女性のボイスとハインツ・ザウアーのテナーの絡みとバックのバイブラフォンやパーカッション、ギターの効果音的使用が有機的にブレンドされて極上のサウンドコラージュを形成している。もちろん自身のベースプレイもフューチャーされている。
2曲目はベースをオーバーダビングによって一人二重奏が繰りひろげられる。
メロディックなアプローチが存分に聴けるソロワークが冴え渡っている。
3曲目も1曲目のテイストで、定型的に繰り返されるシークエンスの上を各ソロイストが順次ソロを展開していき曲が進むに連れて多層的に絡み合った音の絨毯がどんどん高みに舞い上がっていき天上へ突き抜けていくのである。
現代音楽風チェンバー暗黒ジャズロックとでも言ったらなんとなく分かってもらえるでしょうか?
4曲目はドラムが定型ビートを刻んでいるので、、1,3曲目よりジャズっぽい演奏になって
いるが、音楽の独創性は維持されている。
5曲目のALNA KEMANISのボイスは天使か悪魔かどちらの声なのだろう?
ボイスとギターとバイブが有機的に絡み合う音絵巻。
6曲目ラストも全員のソロがフューチャーされながら、幻想的でありながら躍動感溢れる
サウンドコラージュのスパイラルを作り上げていく綿密な作業が繰りひろげられている。
いずれにしてもアーデルハルト・ロイディンガーの独創性、特異性が見事に展開された
名盤だと思う。
メンバーはADELHARD ROIDINGER(B)HEINZ SAUER(TS)BOB DEGEN(P)
HERRY PEPI(G)WERNER PIRCHNER(VIB)ALNA KEMANIS(VO)MICHAEL DIPASQUA(DS,PER)
録音は1981年11月

2003年の夏頃、HMVの広告で知って直ぐに注文したベテラン歌手の最新作。
ピンキー・ウィンターズのレコードは、ヴァンテージ盤「PINKY」と湖畔のジャケットの「LONELY ONE」を持っていて、どちらも愛聴していたが、最近の録音は全く聴いた事がなくて、新作はなんとなく昔のベツレヘムレーベルを彷彿させるような感じの良いジャケなので、長年の勘で買う事を決めたのだ。
50年代に20代であったなら21世紀の現在は60歳から70歳の間なので、声の衰えが気になったがこれは、全くの危惧に終った。
いや、逆に今が歌手としての全盛期を迎えているのじゃないかと思うくらい、見事な歌いっぷりで感激した。
声の衰えは微塵もなく、むしろ若い頃より正確なピッチで低域のパワーも格段に出ている。そのパーフォーマンスにはある種のたくましさを感じるくらい。
マッチョとか肉体的なたくましさではなくて、人生経験を積んだ女性らしい可憐さをともなった人間としてのたくましさがそのまま歌となって表現されていると言ったらよいだろうか?
語り口はあくまでも柔らかいのだが、そこには人生の機微を感じさせる深い情緒に支配された本当の歌が表現されている。
引き出しも多いので、様々な表情をもった歌を満喫できるが、どの歌にも押しつけがましくないピンキー印のペーソスがブレンドされていて、この人の歌を聴いてよかったなと思わせる本物の歌手の姿が現れているのだ。
全部で14曲、有名、無名曲を問わず安定した技量でもって一気に聴きとおすクオリティーを持ったアルバムだと思う。
どれか1曲選べと言われたら12曲目「NO MORE」を私は選ぼう。
メンバーはPINKY WINTERS(VO)RICHARD RODNEY BENNET(P,ARR)BOB MAIZE(B)
録音は2001年9月5,6,7日 HOLLYWOOD ,CA
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪12/23『日経エンタテイン…
- (2024-11-26 13:07:15)
-
-
-
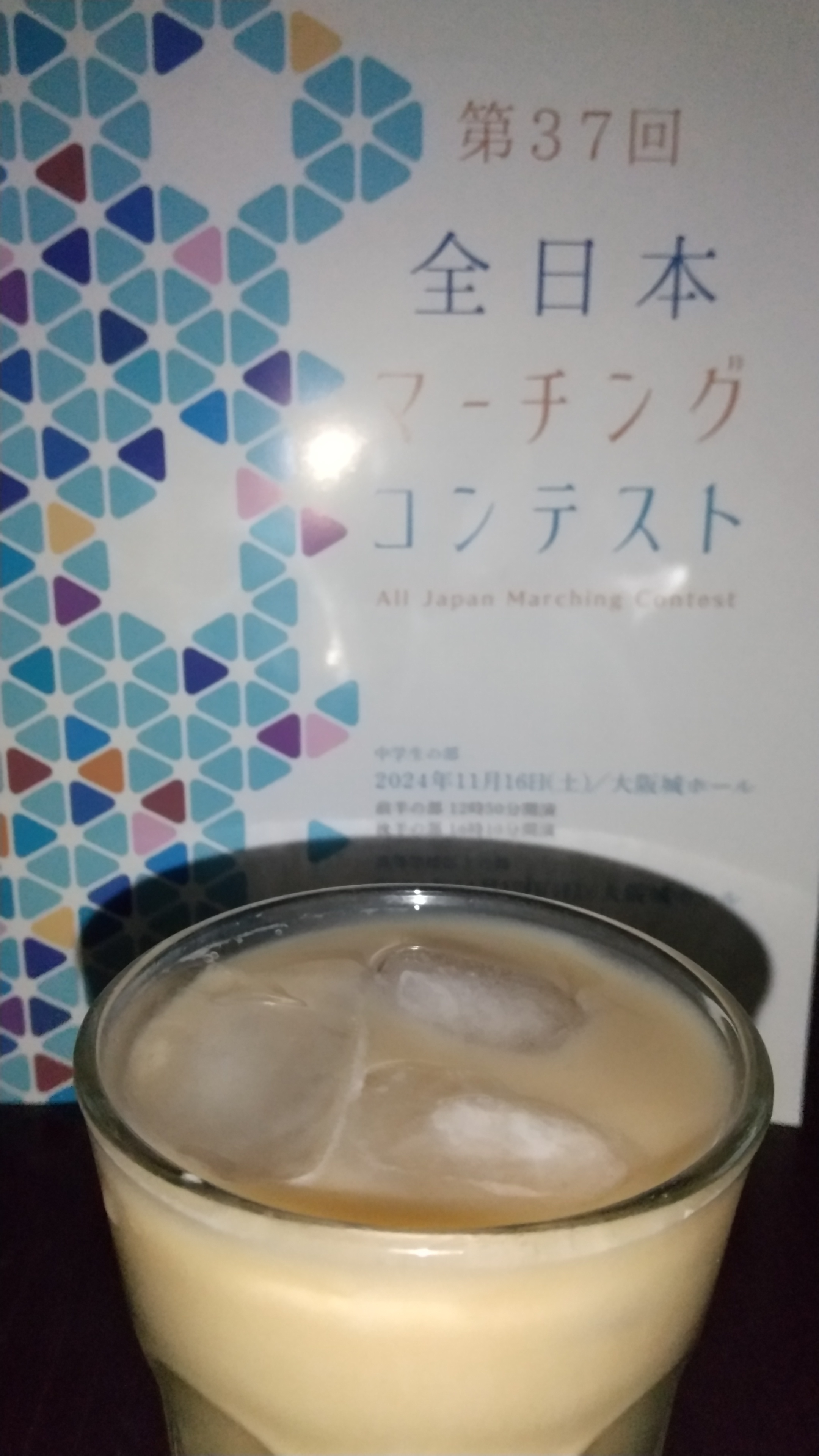
- 吹奏楽
- マーチング全国大会 金賞
- (2024-11-25 06:27:11)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
© Rakuten Group, Inc.