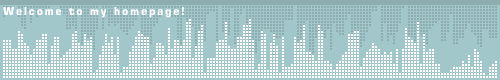音円盤アーカイブス(4月)

HPで試聴して全く知らないギタリストだったが、目の覚めるようなギターワークに即買いを決めてすぐに福岡のキャットフィッシュレコードに通販申し込みのメールを送ったのが2001年の春先だった。
1曲目「MR.P.C.」に気合を感じた。脇目も振らず猪突猛進の如くギターを掻き鳴らすNICOLA MINGOに一聴好感を抱いた。続くアントニオ・ファラオがそれ以上の実力を感じさせるファインプレー。
2曲目「FOUR ON SIX」もウェス・モンゴメリーの熱くうねりのあるプレイを彷彿させるかのようなノリのよいプレイを展開。もちろんウェスの様な天才性は感じさせないのだけれど、ジャズへの情熱、リスペクトが存分に感じ取れ聴いていて爽快で楽しい気分にしてくれる正統派ジャズギターと言えばよいだろうか。
3曲目のジョージ・ラッセル「EZZ-THETIC」を取り上げたところに、NICOLA MINGOのやる気を感じたのは私だけではないだろう。アントニオ・ファラオも卓越したテクニックに裏打ちされた起伏に富んだスリリングなプレイを披露。
自作「BLUES FOR GRANT GREEN」では活きのいいイタリア人とは思えないブルース感覚を表現し、非凡なところを顕にする。
ニコラ・ミンゴは1963年ナポリ生まれで、ジョー・パス、ジム・ホール、ケビン・ユーバンクス、マイク・スターン、ジョン・スコフィールド、ジョン・アバクロンビーらジャズ史に名を連ねる偉大なギタリストを研究し、1986年から1990年にかけてはウルブリアジャズ祭に参加してテレンス・ブランチャード、シダー・ウォルトン、ビリー・ヒギンズらとジャムを経験する。1993年にはエディー・ラング・ギター・コンペティションでファイナリストとなって、1994年には初リーダーアルバムを吹き込むに至る。
骨太なギタートーンでその音楽的バックボーンは明らかにビ・バップからハードバップなのだけれど、それだけには留まらない新しさも完成形ではないのだけれど見え隠れするこれからの成長がまだまだ楽しみなギタリストだと思う。
メンバーはNICOLA MINGO(G)ANTONIO FARAO(P)JOSEPH LEPORE(B)LUCA BULGARELLI(B)
AMEDEO ARIANO(DS)
録音は2000年10月14,15日 ROME
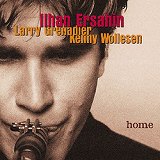
ILHAN ERSAHINはトルコのテナー奏者で、近年はニューヨークで活躍していてこのCDは、LARRY GRENADIER(B)とKENNY WOLLESE(DS)のトリオで吹き込まれた最もジャズ度の高い作品の一枚。
2001年の秋、DUから通販で入手したもの。
テナー1本で骨太な演奏をおこなうILHANのプレイは、NYに在住して以来、様々なミュージシャンと共演し切磋琢磨しているのが、その音楽を通してこちら側によく伝わってくる。
NYのシーンを通じて日々影響され、吸収してきたものを、迷いなく自己のフィルターを通して信ずる音楽にフィードバックしているのがこのCDからは覗える。
作品の中には中近東のモードを意識したテーマをもつものもあるが、あくまでもアドリブする為のテーマといった扱いで、音楽自体、極端に民族性を強調したものではなく、テナートリオというフォーマットでいかに自分流の自由な演奏ができるかという事にフォーカスされている。
NY、ブルックリン派との相互影響からなのか、演奏中のサウンド指向の側面を感じ取るかと思えば、フリーキーなトーンで結構感情移入して咆哮しまくるフリー度高めなトラックなどもあってひとつのワクにおさまりきらないところがユニークだと思う。
LARRY GRENADIER,KENNY WOLLESENとのチームワークも適度な緊張感をもちつつ、ユルメのところはとことんユルメのサウンドでその辺の緩急のつけ方が絶妙のバランスで均衡を保っているので、飽きることもない。
ただ、外に向かって発散、開いていくより自己の内面にむかって投影されていくようなスタイルなので、万人受けするような演奏ではない。
ILHANのテナーは連続した運動性を常に感じさせる持続力のある情念のようなものを感じさせ、そこがユニークだと思う。
録音は1997年3月10日 NY

新進女性ドラマーSYLVIA CUENCAの初リーダーアルバムで2000年の年末に福岡のキャットフィッシュレコードから通販で入手したCD。
サポートメンバーの豪華さと演奏曲目に惹かれて買いました。
EDDIE HENDERSON(TP)VINCENT HERRING(AS)SEAMUS BLAKE(TS)DAVID KIKOSKI(P)
ESSIET ESSIET(B)が主なメンバーでジョー・ヘンダーソン、ジョージ・ケイブルス、ウェイン・ショーター、チック・コリア、ジョビンの曲を演奏。
女性ドラマーと言えば最近ではシンディー・ブラックマンやテリ・リン・キャリントンなんかが有名だが、このシルビア・クエンカも歯切れのよいタイトなドラムを叩く若手女性ドラムの有望株と言えるだろう。
クラーク・テリーのバンドの一員としてヴィレッジヴァンガードやブルーノートに出演し、ジョー・ヘンダーソン・トリオのドラマーとして世界中のジャズフェスを廻った経歴の持ち主で、1992年のセロニアス・モンク・ジャズ・ドラム・コンペティションのセミファイナリストでもある。
1曲目ジョーヘンの「GRANTED」ハーリング、ヘンダーソン、ブレイクとソロが廻されるが、特にヘンダーソンの張り切った活きのいいプレイが耳に残る。
最近のNYの若手のような捻りは全くなくて60年代のBULENOTEの様な直球一本槍のプレイを全員が披露。2曲目のケイブルス作「THINK OF ONE」ではシーマス・ブレイクが短いがグルービーなテナーソロを、続くヘンダーソンのTPはベテランらしい上手さを感じさせるプレイ、ハーリングも情熱的な熱いアルトソロを展開、誰が聴いても分かりやすく、いいジャズを聴いたなぁという満足感を味わえるトラックが多いのがこのアルバムの特徴。
サンバで演奏される「FAVELA」も楽しさに溢れたトラックでミュージシャンの笑みが見てとれる様な出来映え。
5曲目はヴィンセント・ハーリングが吹くショーターの「INFANT EYES」が聴ける。
力技に頼らないいつになく神妙なハーリングの吹奏が新鮮。
全7曲 深夜ジャズクラブで繰りひろげられるジャムセッションのような普段着のプレイが楽しめるモードジャズ直球盤。
録音は1998年10月14,15日 NEW JERSEY
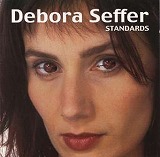
DEBORA SEFFERはフランスの女流バイオリニストで、日本で言えば寺井尚子の様な存在か? 初めて聴いたのは、ザビエルレコードから2001年の夏に通販で購入した90年代初頭の作品で、ロック色強めだったが切れ味鋭いパワフルなプレイにその時から注目した。
このアルバムは2003年の秋にシャレオで開催されていた中古レコード市で入手したもので、アコースティックなカルテットによる演奏で、題目もジャズマンオリジナルで固められている。
メンバーはDEBORA SEFFER(VLN)KEN WERNNER(P)RAY DRUMMOND(B)BILLY HART(DS)
1曲目は「ALL BLUES」ドラモンドとハートが繰り出すリズムの絨毯の上をSEFFERとWERNERが歯切れよく疾走するイメージでソロを展開。
SEFFERのヴァイオリンは専門家が聴くとあまり音程が良くないそうだが、あまり気にはならない。そもそもジャズではピッチや音色の問題に関してはクラッシックと違って許容範囲が比べ物にならないくらい広いので好みの問題もあろうかと思う。
もちろん、オーネット・コールマンの様なソロを延々ととられたら辛いものがあるだろうが、SEFFERのプレイはいたって正統派なのでご安心を・・・
3曲目は「SCRAPPLE FROM THE APPLE」寺井尚子も演っているので聞き比べをしてみたらよいかも知れない。
このアルバムではケン・ワーナーが力演しており、改めてこのピアニストが実力者であることを認識した。
「NAIMA」はこの曲がもつ崇高で優美なイメージがそのまま保たれて最後までだれることなしに演奏される。モンクの「THINK OF ONE」に続く「OLEO」は一気果敢にアップテンポで完奏。
ビリー・ハートとレイ・ドラモンドのベテランコンビはN山さんが2000年に主催した東広島でのティム・アマコストのコンサートで生演奏を見ていて、打ち上げにも同席した。
レイ・ドラモンドの白いベースケースを終演後の後片付けで運んだのもいい思い出だ。
アマコストは日本語ペラペラなので大分話しをさせてもらったが、二人のことを気遣って尊敬しているのがはたで見ていてうかがえた。
打ち上げの席で話題が何故かハリー・スイーツ・エディソンのことに及んだ時にビリー・ハートが感慨深げに「昔、一緒に演奏した事がある。」と言っていたが懐かしい。
このアルバムに戻って、8曲目がベストトラックであろうマッコイ・タイナーの「PASSION DANCE」。SEFFERのソロも一段とノリのよい切れ味深い爽快さを感じさせるプレイを展開。
他にはシルバー「SONG FOR MY FATHER」 、エリントン「IN A SENTIMENTAL MOOD」、エヴァンス「LAULIE」などが演奏されている。
ラストは彼女のオリジナル作品で締めくくられる。
実際、スタンダードをベテランとプレイするのは挑戦だったのかも知れない。
最後のプレイは水を得た魚のように飛び跳ねるピチピチした軽快で伸び伸びした演奏を披露する。
1999年 フランス作品

RODRIGO DOMINGUEZはQUINTETO URBANOのサックス奏者として活躍しているが、これは彼のオルガン、ドラムスからなるテナートリオ編成によるリーダーアルバム。
このCD、sh2oさんがHPで紹介されていたので知って興味をもち昨年末、中南米音楽から通販で入手したもの。
RODRIGOのテナーはQUINTET URBANOの時のプレイより自由度高めのユニークな演奏を繰りひろげており、時にはウェイン・ショーターのテイストやNYブルックリン派の若手テナー奏者との共通項も見出せるのではないかと思える演奏を展開している。
ERNESTO JODOSのハモンドB-3もエレガントで色彩感に溢れた素晴らしいプレイ。
前にも書いたかもしれないが恐るべきアルゼンチンジャズの世界だ!
プレイに奥行きがありスリルに満ちている。先に何が飛び出してくるか分からない期待と不安が交錯して、聴いていてワクワク、ドキドキの興奮を味わえるのだ。
ドラムのSERGIO VERDINELLIも千手観音型オクトパスドラマーで、機動力、爆発力を備えた将来が楽しみなドラマーだ。
この三人のミュージシャンが有機的に結合して自由な表現を繰りひろげる。
デジャブーのように一つの演奏風景が幻視される・・・実際あったわけではないが、ポール・ブレイ、ジミー・ジュフリー、ポール・モチアンが現代において若手ミュージシャンならば、さも演奏していそうな音楽がアルゼンチンのブエノスアイレスで現実に鳴り響いているのだ。
録音は2003年12月22,23日 BUENOS AIRES

DUの沼田順(当時)の推薦CDコーナーでネット通販予約を受け付けていたので、2001年だったか直ぐに予約したのだが、連絡なしにいつまで経っても届かなかったCDで、昨年2月倉敷の「レコード屋」で\790で中古で入手したといういわくつきのもの。
JAGA JAZZISTというノルウェーの若手音楽集団が数年前から台頭してきていて、ヨーロッパを初めとしてアメリカ、日本でもCDリリースされ認知度が高まりつつあるのだが、(ちなみに某SJでは完全に黙殺、蚊帳の外扱い)彼らの音楽を一言で説明するとエレクトロニカ~ブレイクビーツ~テクノ~フューチャージャズ~プログレッシブロック・・・
様々な音楽的要素を内包した恐ろしく音楽的レベルの高いカッコいいミュージックと言ったらよいだろうか?
ちなみに私は2002年に日本盤で入手して以来はまりました。
この4月に新作がリリースされたばかりで、JAGAの音楽を未聴のかたは一度是非聴いてみることをお薦めする。目から鱗なことうけ合いです。
ちなみにこのCDはそのJAGA JAZZISTのテナー担当JORGEN MUNKEBYとピアノのMORTEN QVENILDが結成した純アコースティックジャズグループの第1作目。
ドラムのTORSTEIN LOFTHUSのスナップの効いたパルシッブなシンバルワークが素晴らしい。JORGENのテナーは時々グロウルを織り交ぜてクールなんだけれどその音楽的嗜好の先には60年代アメリカのフリージャズシーンを意識したものがあると感じられる。
今のアメリカのブルックリン派に代表される若手テナーと明らかに違いを感じさせるプレイ指向の部分が見受けられ、音楽的支柱となっている部分も60年代ジャズがもっていた叫び、混沌、熱さといった部分を彼らの音楽の要素の一部分として私には感じ取れるのだ。
SHININGは第2作を2003年JAZZLAND ACOUSTICからリリースして、最近3作目が発売されたと聞く。
まだ未聴なのだが、過去の2作とは大幅に音楽性の変化が見受けられるサウンドになっているそうである。
録音は2001年5月 OSLO
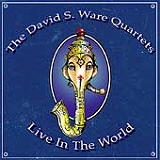
デビッド・S・ウェアの最新作で3枚組のボリューム、2週間前アマゾンから\2750で入手した。CD1が1998年12月スイスでのライブ、CD2,3が2003年、イタリアのTERNIという場所とミラノでのライブがそれぞれ収録されている。
ドラムがスージー・イバラ、ハミッド・ドレイク、ギレルモ・E・ブラウンが各CDにそれぞれ別に参加しておりドラミングの違いを聴くことができる。
全部通して聴くと当然の事ながら相当体力を消耗して疲れる。
3時間半くらい時間を要するので、いつかはまとめて聴くことにトライしようと思っているが今日はCD2のイタリアTERNIでのライブを聴いている。
そもそも、デビッド・S・ウェアを知ったのは大学の研究会で確かO本君だったと思うが、
セシル・テイラー「DARK TO THEMSELVES」をかけた時だった。
その音量、体力に驚き暫らくその轟音が耳から離れなかったのを覚えている。
デビッドで凄いミュージシャンがマレイと並んでもう一人いることがインプットされたのはその時だった。
その後、東京へ初めて行った時、ディスクユニオン新宿店で買ったのが、DAVID S.WAREの初リーダー作「FROM SILENCE TO MUSIC」(PALM)。
衝撃を受けた。聴いているのが辛くなるような一音一音に魂が宿っているというか情報量の多い音に軽いめまいがしたのを覚えている。
それからウェアのCDを買い続けている。
ウェアの凄さは一言でいって音楽に対する集中力と持久力が絶妙なバランスで保っている点だと思う。そして、どんな状況に陥っても信念を曲げないハートの強さ、精神の強靭さだと考えている。
この作品でもそんなウェアのレギュラーグループの一丸となった演奏がありのまま捕らえられていて、録音状態も良いので大変聴き応えのあるものとなっている。
マシュー・シップはピアノを熱狂的に変幻自在なスタイルで弾きまくっているし、ウィリアム・パーカーもブイブイとベースを掻き鳴らしている。
ハミッド・ドレイクはパルスを叩き続け理想的ともいえる環境の中でウェアのテナーが咆哮し続けるのであった。
録音は2003年 ITARIA TERNI

ジャズを聴きだした比較的初めの頃からラウル・ジ・スーザの名前はその頃にでたブラジリアンフュージョンのレコードなどで知ってはいたが、ちゃんと聴くのはこのCDがはじめてだった。
1999年の岡山の「ディスクトランス」で買ったもので、ジャケットにフューチャリングCONRAD HERWIGと入っていたのも大きな理由。
ツートロンボーン、テナー、アルトサックス(ソプラノやフルートの持ち替え有)の4管にピアノ、ベース、ドラム、パーカッションといった編成でラウル・ジ・スーザ以外のブラジルのミュージシャンで名前の知っている人はいないけれども、全員一体感のある熱演で、演奏を盛り立てている。TSのFELIPE LAMOGLIAはブレッカーを少し不良にしたようなプレイで結構聴き物。3曲目のOSCAR CASTRO NEVESの「CHORA TUA TRISTEZA」ではスーザとハーウィッグのトロンボーンバトルが聴ける。ファーストソロがスーザ、セコンドがハーウィッグだと思うが確証がなく、今一歩自分の耳に自信がない。
4曲目ジャヴァンの「NAO DEU」はVINICIUS DORINのソプラノサックスが全面的にフューチャーされた曲。どちらかと言うとスーザの方が音が太く音量も大きめで、ネイティブなものを感じ、ハーウィッグのホーンは倍音成分の多いモダンなフレーズが聴き取れる。
ソロ云々と言うよりも、ジャージーに編曲されたロベルト・メスカネル、ジャヴァン、ジョニー・アルフ、トム・ジョビン、トッキーニョ・オルタらの素晴らしい楽曲をブラジルの腕利きミュージシャンが、好演していて聴いていてウキウキした開放的な気分を味わえるCD。
それだけであれやこれや言わなくてもいいのではないか・・・そんな一枚。
録音は1998年2月 SAO PAULO

スティーブ・グロスマンが参加したフランスのドラマーSIMON GOUBERTのリーダーアルバム。何日か前にグロスマンの悪口を書いたので罪滅ぼしにこのアルバムを紹介しよう。
今はなき六本木WAVEで1994年5月、入手した。
今になって気が付いたのだけれどピアニストにLAURENT FICKELSONが参加している。
結論から言いますとこのアルバムでのグロスマンは相当いいです。
「マイ・フェバレット・シングス」かと勘違いするようなフィッケルソンのイントロから
始まる一曲目「TAKE FIVE」。グロスマンはソプラノを用いていて、アルトのJEAN-MICHAEL COUCHETと息のあったコンビネーションを見せる。
モーダルに処理した編曲がグロスマンの活気溢れたアドリブを生み出す原動力になったのか、ピアノソロを挟んで展開されるグロスマンの何かに取りつかれたかのような鬼気迫るソプラノソロは70年代を彷彿させる見事な出来映え。
こういうグロスマンをずっと待ち望んでいたのだ、私は。
アルトのCOUCHETも悪くはないのだが、如何せんグロスマンとは役者が違いすぎる。
本当にやる気を出した時のグロスマンほど怖いものはない。
一音一音、言霊が宿っているかのような重く激情的で刺激性のある音。
2曲目グロスマンの「RIVERBOP」でも好調さは維持される。
テナーから滝の様に溢れ出てくる激情の嵐、サウンドの洪水を浴びれる幸せに浸る。
3曲目はコルトレーンへの祈りともいえる「NAIMA」。
まさにグロスマンの独壇場だと思う。好調時にこういう曲を演れば・・・
ラストはSIMON GOUBERTの作品、アルバム表題曲「HAITI」。
ベースのイントロからモーダルな展開で進んでいき、フリーな局面へ突入していく所など、コルトレーン~ファラオ・サンダースを彷彿させる場面もあって、ここ最近のグロスマンのプレイで最も激しく自由度の高い怒涛のプレイが記録されている。
結論として、私的にはグロスマンが活きるのは「コルトレーン」なのだ。「ロリンズ」ではない。
録音は1991年2月10,11日 フランス

初めて聴いたのは今から約22年前、松江のジャズ喫茶「ばん」。
マスターがこの女性ボーカリストは素晴らしいと当時日本盤がでたフィル・ウッズが参加した「LITTLE JAZZ BIRD」をかけた時だった。
まだまだ当時はボーカル入門仕立で、アーネスティン・アンダーソンやダイナ・ワシントンなんかを、白人ボーカルだと、ヘレン・メリル、日本人では金子晴美、大野エリなどを良く聴いていた。
今から思えばボーカルの深遠な世界がよく見渡せておらず、自分の好みも確立していなかった
状態でインストのほうが圧倒的に興味の対象だったので、はっきり言ってその時はメレディスの良さが分からなかったのだと思う。
「ばん」のマスターが与世山澄子の「WITH MAL」の中の「THAT`S LIFE」をかけた時も何故そんなに感激しているのかあまり良くわからなかったのが正直なところ。
それから、黒人女性ボーカルは好みじゃないのが分かって一時、フレッシュサウンドから再発される白人金髪系ボーカルや寺島さん推薦のジョニ・ジェイムスなどを結構買った。
暫らくしてそれらのレコードはほとんど中古屋に売り飛ばしてしまった。
結局気にいったのは、アン・フィリップス、ドナ・ブルックス、ピンキー・ウィンタースなどだった。その頃新譜ででたメレディスの「THE COVE」(リー・コニッツがサイドマンで参加しているという理由で買った)とメデリーン・イーストマンのMAD-KAT盤も買ったのだがまた、過ちをおかしてしまうのだ。
金に困った時に再び処分してしまったのである。
結局本当にメレディスやメデリーンの良さを心の底から好きになったのはこの「KISS OF ECHO」を買った1998年ぐらいからの様だ。
アイリーン・クラールを頂上にこの3人で私的ジャズボーカルのトライアングルが現在は形成されている。
ジャズ以外ならボサノバ歌手で好きなボーカリストはたくさんいるが・・・
以前にも書いたがボーカルに関しては完全に個人の好みで判断している。
好き嫌いで判断して許されるのがボーカルの世界ではないか?
いつも言っているが「それでいいのだ。」と思っている。
好き嫌いに理由はいらないので、このCDに関してもあれこれ言わない。
一言、「LISTEN!」。
メンバーはMEREDITH d`AMBROSIO(VO)MIKE RENZI(P)JAY LEONHART(B)TERRY CLARKE(DS)
録音は1998年8月11,12日 NY
P.S. メレディスの絵って光と影の使い方が素晴らしいと思いませんか?

全身を黄緑色の人民服で身をおおった姿が今でも瞼に焼き付いている。
初めてというか、最初で最後の武田和命の姿を見たのは、約四半生記前の合歓JAZZ INNでの事だった。
山下洋輔カルテット(国仲勝男、小山彰太、武田和命)がそれぞれ違う色の人民服を着ていたはずなのだが、何故か武田の黄緑色の人民服だけが強烈に記憶に残っているのだ。
クラブの皆で見に行ったのだが、その中にこのアルバムを録音した島田正明氏(今までS田氏と表記していたが、彼はジャズ業界の住人、プロとして生業にしている人だから実名で勝手に表記してもいいだろう。)もいたはずで、その島田氏が録音した武田和命の等身大の演奏が記録されたCDで、発売後直ぐに買った。
確か岡山のLPコーナーから通販で買ったと思う。
武田のリーダーアルバムはこれ以前はFRASCOから出た「GENTLE NOVEMBER」だけであり、この2枚目がリリースされた時、既に武田の姿はこの世になかったのである。
武田の演奏も良いが、島田の録音も良い。
そういえば、大学の頃から、オーディオに関してはクラブ一詳しく、音への執着、ポリシーを明白に持っていた。
自分の理想とする音のイメージを持っていてその為には寝る間を惜しんで食うものも食わずアルバイトに精をだしていたのを思い出す。
苦労して手に入れた島田の4畳半の下宿に据えられたオーディオは確かに素晴らしい音がした。
紛れもない本物のジャズの音がしていた。
島田が言った一言を覚えている。「ピアノの音だけはJOKE(いきつけのジャズ喫茶)に負ける・・・」
実際島田の下宿にはよく遊びに行った。
私がアルト、彼がトランペットでコールマン~ドン・チェリーの真似事のような練習もしたのを思い出す。
卒業後一度だけ電話をくれたことがある。
来月、SJのゴールドディスクで「ドナルド・ハリソン~テレンス・ブランチャードクインテット」が自分が勤めているレコード会社から出ると・・・
実際は出なかった。何故ならその前に会社が倒産してしまって幻のGDに終わったのだ。(後にキングから無事発売される。)
このCDを聴くと走馬灯のようにこんなことが思い出されるのだ。
今日は思い出話に終始してスミマセン。
島田はその後「アケタの店」に就職。
「アケタ」にいなくてはならない存在として多岐にわたって活躍されている。
島田とは大学卒業後、一度も会っていないのでなんかの拍子に乱入して驚かせてやろうと企んでいる。
メンバーは武田和命(TS)吉野弘志(B)古沢良二郎(DS)
録音は1989年1月26日 「アケタの店」 島田正明 録音

2003年秋シャレオ地下の中古市で物色中に発見した一枚で、JESSE GREENの名前は全く知らなかった。ジャケ下にクレジットされていた名前で即買いを決めた。
DAVE LIEBMAN 、 CHRIS POTTER 、 PHIL WOODS うわぁー!好きなミュージシャンばかりやん!
こういう思いがけない遭遇があるので、中古盤漁りはやめられない。
3人のサックス奏者が全員で共演しているのはラストの1曲だけで、1曲目がポッターとウッズの共演となっている。後はそれぞれリーブマンが1曲、ポッターが1曲、ウッズが2曲ソロフューチャーされていて、いささか拍子抜けの感があるが、聴いてみた。
1曲目「EXTREME SPORTING」ウッズとポッターのユニゾンでテーマが奏でられる。
ウッズの容姿はさすがに年老いたがプレイは30歳の青年の様なつややかで張りのある瑞々しい音色で思わず聞き惚れる。ポッターはいつもと違いバッピッシュでごつごつした感じのテナーを披露。JESSE GREENのピアノのリズム感に優れた勢いの感じられるピアノプレイで聴いていて爽快感がある。
2曲目はピアノトリオでジェシーの歯切れのよいタッチが楽しめるワルツ曲。
3曲目はデイブ・リーブマンがソプラノで参加したカルテットによる演奏。
スローテンポで幻想的で厚く垂れ込めた雲のような陰鬱なイメージを受ける曲でやや冗長か?4曲目はJERRY HARRISの唄う「I`VE GOT YOU UNDER MY SKIN」でこの曲でけ1999年10月のライブ録音。ウッズの歌伴が聴けるが、アルバムの統一性の見地からはこのトラックは要らなかったかもしれない。
5曲目アルバム表題曲も力演だが、13分半は少し長すぎやしないか?
クリス・ポッターのソプラノは音色的に少しショーターに似ている。
6曲目はレイ・ブライアントで有名な「GOLDEN EARINGS」。リラックスしながらも歯切れの良い軽快なジェシーのピアノが聴ける。オリジナルでも肩の力を抜いてこんな感じでやったらよかったのではないかな?
7曲目「BETTE」はウッズのアルトサックスがフューチャーされるペーソス溢れたバラードナンバー。いい曲です。
ラストは3人のサックス奏者が会して大円団を迎える。
ソロオーダーはジェシー・グリーン(P)クリス・ポッター(TS)フィル・ウッズ(AS)デイブ・リーブマン(TS)。ポッターもリーブマンも結構ゴリゴリ、グキョグキョに吹いていて、それでも二人のテナーの個性の違いが分かって面白い。
録音は2001年5月18,19日

出張から帰ってきていつもの様に自分のブログをアップした後、ネットサーフィンしていて、ペデルセンが亡くなった事を知った。享年58歳 心臓発作だったそうだ。
今日は同じベーシストのBEN ALLISONのリーダー作をアップ予定だったのですが、変更してNIELS-HENNING ORSTED PEDERSENを追悼したいと思います。
私にとってペデルセンはジャズ喫茶のひとで、それこそケニー・ドリューとのトリオやデュオ、ポール・ブレイとのデュオ、サム・ジョーンズとの共演盤を「JOKE」でよく聴いた。
レコードも持っていたけど自宅よりジャズ喫茶で聴いた記憶の方が多いのだ。
そんな中でこの「DANCING ON THE TABLE」はLPコーナーで大学時代にメンバーを見て直ぐに買って繰り返し繰り返し聴いたペデルセンの中で最も思い入れの強い一枚。
NIELS-HENNIG ORSTED PEDERSEN(B)DAVE LIEBMAN(TS,SS)JOHN SCOFIELD(G)
BILLY HART(DS)という実に魅力的なメンバー。
クラブの研究会でもかけて好評だったのを覚えている。
勿論、1曲目「DANCING ON THE TABLE」。
テナー~ギターカルテットの編成は現代のブルックリン派によく見受けられる編成だが、彼らのように曲やリズム、ハーモニー面で変化球というか、屈折したというか、浮遊感覚溢れた雰囲気のものは、なくて剛直球ストレート一本やり。(ハードバップの時代や60年代に比べればもちろん、サウンド面で斬新さは感じます。)
それが全員の熱気溢れたプレイでジャズを聴いたなぁという満足感とフレッシュな爽快感の両方を味わえるのだ。
デイブ・リーブマンもジョン・スコフィールドもこの頃は現在より悪く言えば、ひねくれてないというか、まだまだ素直さが残るプレイで逆に言えばまだまだ青さの残っている演奏といえばいいのだろうか?ジャズへのひたむきさが感じ取れるプレイ。
ペデルセンのベースは今と本質的に何も変わっていない。すでに完成形のベースプレイで
ソリッドの一言。ミスが無いところがミスとしかケチのつけようがない全てのベーシストがお手本にする演奏といえるだろう。
ペデルセンのプレイや言動について、唯一欠点があるとすれば完璧主義者でやや柔軟性に欠けるところだろうか?
雑誌のインタビューで黒人ベーシスト全般の音程の悪さ(実名でロン・カーターやレイ・ブラウンまでも)を挙げていた。
本当のことだから、ありのままの発言しただけのことだろう。
音楽感の違いだけの話で、ジャズ音楽の場合、サウンド的にいけていたらその演奏は素晴らしい演奏だと私的には思うのですが・・・
録音は1979年7月3,4日 8月30日
どちらにせよ、ジャズ界はまた一人、巨匠を失ってしまったのである。
冥福をお祈りします。

2000年に名前は忘れてしまったが松山の商店街の裏通りにある中古レコード屋で入手したもの。
このアルバムはリーダーであり、ベーシストのBEN ALLISONが1992年に設立したミュージシャンによる非営利団体JAZZ COMPOSERS COLLECTIVEの 中心メンバーによって演奏されたCD。
COLLCTIVEの設立は現在の音楽産業やクラブシーンに一石を投じ、自らの音楽を創造し、演奏し、レコーディングできる環境を実現することを目的としたもので、この作品以外にたくさん作品がリリースされるに至っている。
メンバーはBEN ALLISON(B)MICHAEL BLAKE(SAX)TED NASH(SAX,FL)TOMAS ULRICH(CELLO)JEFF BALLARD(DS)FRANK KIMBROUGH(P)RON HORTON(TP,FLH)
1曲目「SPY」4ビートと無調の部分が巧みに連動した魅力的なテーマを持つ曲。
ツーテナーで最初の主題部は演奏され、MICHAEL BLAKEのサックスはファラオ・サンダースの様な響きを発し、端正なTED NASHとの対比が秀逸。ソロイストは楽器を持ち替えながらバラエティーに富んだサウンドが展開される。
2曲目でもマイケル・ブレイクが大々的にフューチャーされる。バックで鳴り続けるピッチカートベースと弓弾きのチェロが効果的な音を生んでいる。
3曲目はNYという都会が発する様々な音響を音楽で表現する事を試みた曲で、観念的な部分と実際の鳴っている音楽、芸術性の部分でミスマッチを生じている部分があると思うのだがどうだろう?この曲ではテッド・ナッシュとジェフ・バラードがフューチャーされる。
4曲目「APOSTLES OF THE UGLY」はロン・ホートンの思索的なトランペットとナッシュがフューチャーされた漂うような雰囲気のバラード。
ここまでで半分だが、曲やアレンジに凝っていて意図していることはわかるのだが実際音楽、作品として魅力的かと問われれば、少し消化不良の部分が問題として残っていると、この作品が吹き込まれた1997年の時点では言わざるいえない。
どちらにせよ、クリエイティブな演奏活動を自らの手で働きかけるシステムを作り上げ、現在もそれが続いているJAZZ COMPOSERS COLLECTIVEの動きを見守っていきたい。

2000年5月大阪出張の時、ワルツ堂EST1店で購入したもので、SJ輸入盤欄でチェックしていたので、少し期待して買ったはず。
ウェイン・ショーター「JUJU」や「AFRO BLUE」の2曲以外は全てリーダーMANUEL HERMIAのオリジナル作品でまとめられている。
1曲目からHERMIAは興奮剤でも使用しているのではないかと思うほど、テンション高めのプレイで、これは結構いいぞと身を乗り出してスピーカーを覗き込んだ。
アルトの音に厚みがあり、音量も大きめでグイグイとリズムセクションを引っ張っていくタイプの奏者とみた。ちょっとエキセントリックなところも感じられてそこら辺が、70年代のスティーブ・グロスマンがアルトサックスを吹いているようで気に入っている。
勿論パワー一本槍の演奏ではなくて全体の構成も計算にいれた知的な計算も当然していると推測されるのだけれど、受ける印象は全般的にアドレナリンがビンビンに体中を駆け巡るといった様な印象なのだ。
今の時代、こういう存在は貴重なのではないか?
サウンド指向の強いクールな演奏をするプレイヤーが多い中メインストリームジャズシーンでMANUEL HERMIAみたいなアルト奏者はあまり多くないからだ。
1曲目「NO DOUBT」4曲目「YOU KNOW WHAT? I'M HAPPY」などのオリジナルもアップテンポの直球モード曲で自身のスタイルが映えるイイ曲を書き下ろしている。
リズムセクションも健闘していて、特にBRUNO CASTELLUCCIの切れ味のあるドラミングは賞賛に値する。個人的にスネアの音はあまり好きじゃないが・・・
5曲目ではソプラノを披露。ソプラノの音もパッショネイトな音色で情報量が多い。
7曲目「AFRO BLUE」はそれこそ大学のジャズ研のようなベタな選曲だけど、いいんですねぇ。これが。ERIK VERMEULENがしっかりマッコイやってます・・・
HERMIAにいたっては、言わずもがな。なりきってますコルトレーンに。
アンプのメモリを思わず上げてしまう演奏と言っておこう。
8曲目はほの暗いやや瞑想的なバラードで締めくくられる。
MANUEL HERMIA,覚えていても良い欧州サックス奏者の逸材だと思う。
メンバーはMANUEL HERMIA(AS,SS)ERIK VERMEULEN(P)SALVATORE LA ROCCA(B)
BRUNO CASTELLUCCI(DS)
録音は1999年9月

先週のシャレオ地下、中古市で見つけたもので、ジャケ裏のクレジットを見るとなんと、「CURBITS」を再演しているではありませんか!
しかもメンバーがHERB GELLER(AS)BERNT ROSENGREN(TS)RED MITCHELL(B)と有名どころも参加。\1050だった事もあって他の一枚と一緒に買ったのです。
名盤「SAX APPEAL」から何年経つのだろう?ちなみに本作は1979年の録音。
オリジナルとは違って新たに編曲し直していてピアノのイントロから始まる「CURBITS」だけど、サックスのユニゾンで奏でられるあの甘美なメロディーが流れてくると思わず聴き入ってしまいます。
ハーブ・ゲラーのアルトは50年代より幾分肉付きのよいバッピシュなフレーズが聴かれるが、これはこれでいいのではないかな。曲の途中で新たに編曲で加えられたセカンドメロディーもなかなか良いと思う。
2曲目「STORM WARNING」も春の柔らかな陽射しを思わせる様なフルートによるユニゾンでテーマが奏でられサックスのソロが続くのだが、テナーがコルトレーンマナーなのが可笑しい。曲自体は北欧の哀愁が感じられる魅力的なメロディー。
3曲目はボーカル入りなのだがクレジットがない。作曲はリンドバーグとレッド・ミッチェルの共作なので、ミッチェルの可能性が高いと思う。
4曲目はハーブ・ゲラーがソプラノサックスを吹いていてこういうところもオリジナルが吹き込まれた時代との隔たりを感じる。
5曲目もスウェーデン民謡かと思うようなリンドバーグのオリジナル作品
日の当たる時間が短い冬の夕暮れを思わせる様な物悲しいメロディーをサックスが綴っていく。
6曲目「INVERSION」は各人のサックスが忙しく入れ替わり立ち代わり交錯するモダンなテイストのする曲で、アルバムの中ではやや異質な感じがしないでもないが、意外とこのアルバムが吹き込まれた1979年当時ニ-ルス・リンドバーグが最も演りたかった事はこんなことだったのかもしれない。
メンバーはHERB GELLER(AS,SS,FL)CLAES ROSENDAHL(TS,FL)BERNT ROSENGREN(TS,AS,FL)LENNART ABERG(BS,FL)ERIK NILSSON(BS,FL)NILS LINDBERG(P)
RED MITCHELL(B)RUNE CARLSSON(DS)
録音は1979年5月23日 STOCKHOLM


2年ほど前にOWLからでたCDを買っていてそのアルバムもデイブ・リーブマンが参加していたが、当作品もリーブマンが参加しており、1993年の正月に梅田ロフトの中にあったWAVEで買ったもの。
1曲目はいかにもウディ・ショウが演奏しそうなモーダルな曲で、小気味よいフレーズ自体も小型版ウディを連想させると言える。
2曲目はゲイリー・バートンのグループに在籍していた70年代の頃と少しも変わっていない独特のギターの響きを持っているミック・グッドリックのイントロから始まる。
リーブマンのソプラノ、サラスのフリューゲル、グッドリックのギターとソロが続くが、
グッドリックが持つある種の懐かしさを感じさせるギターの音色が最も印象深く、曲のテイストを位置付けていると思う。
リーブマンとサラスのフリーフォーミングなデュオから始まる3曲目。
ハービー・シュワルツのベースがリズムパターンを出して、サラスとリーブマンがソロをとるが、ここはリーブマンの緩急自在でダイナミクスに富んだソロに軍配が上がるだろう。
ED SARATHはライナーによるとミシガン大学でジャズインプロビゼーションの上級クラスの講座を受け持っている先生だという。
どうりで端正なフリゅーゲルホルンを吹くはずで、リーブマンの奔放なサックスと好対照を成しているが個人的にはもう少し羽目を外したバーンアウトしたプレイも聴きたかったというのが本音のところ。
アルバム全体が1曲目のようなガッツ溢れる勢いが感じられる調子でまとめられていたら
もっと良かったかもしれない。
メンバーはED SARATH(FLH)DAVID LIEBMAN(SS)MICK GOODRICK(G)HARVIE SWARTZ(B)
MARVIN "SMITTY"SMITH(DS)
録音は1991年12月22,23日 NY
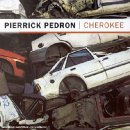
2001年6月にDUから通販で入手したもので、ピアノにバプティステ・トラティニョンの名前を発見したからだ。
テナー奏者に比べアルト奏者は現代ジャズシーンにおいて、実際調べたわけではないが、出てくる新人の数は少ないように感じる。テナー人口の方が多いのだろうか?
たぶんそういう訳ではないような気がする。人間の肉声に最も近いトーンをもつアルトサックスという楽器特性上、かましが効きにくく、奏法上の差別化が音色も含めてあまりにも完成され過ぎてしまっている為個性的な人材がテナーほど見つかりにくいというのが現状なのではないかという気がする。
あくまでもテナー奏者と相対的に比べての話なのだけれど思いつく80年代以降の奏者の名前をあげていったらある程度納得いただけるのではないだろうか?
そんなアルトシーンにおいて、フランスからいたって正統派のアルト奏者として2000年にELABETHレーベルからリーダーアルバムをリリースしたのがPIERRICK PEDRON。
オリジナル作品や曲のリズムアレンジメントには創意工夫が感じられるのだが、アドリブプレイはいたってオーソドックスでストレートなのである。
決して悪い意味で言っているのではなく、クールでサウンド指向の新人プレイヤーが多い中実直で悠然と自身の信じるストレートジャズを演奏するPEDRONのアルトサックスは説得力があり、小気味よい力強さが感じられる。
50年代チャーリー・マリアーノが録音したのと同じ様に、作為性無しにリアルタイムの音楽として「ニューヨークの秋」を切々と謳い上げるPEDRONに私は本物を見た。
もちろん現代のプレイヤーなのでこれだけがPEDRONのやりたい事ではないだろうが、フェイクなしに時代の空気感を現代に蘇らせる説得力のあるアルトサックスに才能の片鱗を見出した次第。
昨年にストリングス入りのニューアルバムを出したはずだが、未聴なのでなんとも言えないが数少ない正統派アルト奏者として大成するのを期待したい。
メンバーはPIERRICK PEDRON(AS)BAPTISTE TROTIGNON(P)VINCENT ARTAUD(B)
FRANCK AGULHON(DS)
録音は2000年2月24,25日 PARIS

先週の土曜日、ザビエルレコードさんのHPで試聴して、一辺に気にいって月曜日に注文、昨日CDを受け取って聴いている。
あまりにもツボにはまった素晴らしいサウンドなので、感激しているのだけれど、あまり頻繁に聴いていると楽曲がメロディアスなので飽きが早く来ないように、意識して少しづつ聴くようにしている。バルネ・ウィランに「SANCTUARY」(IDA)を聴いた時のように・・・
JOEL XAVIERは1974年、リスボン生まれ。
リスボンというと「リスボン特急」という映画を思い出す。
アラン・ドロンとカトリーヌ・ドヌーブが共演したギャング映画だったはずだけど、内容はあまり覚えていない。サントラのEP盤を買ってエレピによるイントロが好きで繰り返し聴いたのを思い出す。ジャズを聴きだす前の話。
最近ではマスターカード(だったか?)のCFで夜のポルトガルの街のように思える景色の映像が流れていたが、私にとって未知の文化圏でありよく分からない。
妹夫妻がスペインに昔数年住んでいた時、ポルトガルに旅行したらしい。
隣の国なのに、スペインに比べポルトガルは貧しく、町並みも汚かったそう。
人々は瞼の奥底に哀しみの表情をひめているような印象をもったそうだ。
明るく情熱的なラテン気質そのもののマドリッドに比べてリスボンの町は妹にそんな印象を抱かせそれ以来二度とポルトガルに旅行しなかったらしい。
このCDを聴いて直ぐにそんな身内のエピソードを思い出してしまったのだけど、JOEL XAVIERの音楽はそんなポルトガルの市井の人々の思慮深く、心に皆、ある種の悲しみを宿したような深い情緒を感じさせる音楽だ。
薄暗い石畳の道路に降りしきる雨、裏通りの何処からともなく聴こえてくるファドの響き、港の停泊場の上空を鳥群が飛び交っている。
そんな情景がこの音楽を聴いていると浮かんでくる。
ギターの腕前はぴか一だ。
17歳で初リーダーアルバムをリリース以来、LARRYCORYELL,PAQUITO D`RIVERA,MICHAEL CAMILO,ARTURO SANDOVAL,CHUCHO VALDES,BIRELI LAGRENE,RICHARD GALLIANO,JOEY DEFRANCESCOら著名ミュージシャンと共演、レコーディングした素晴らしい経歴の持ち主。
このアルバムでは2曲目にTOOTS THIELEMANSも参加しており、ツボにはまった素晴らしいプレイを聴かせてくれる。
JOELXAVIERは、共演者や個々のプレイ云々より楽曲の素晴らしさ、トータルなコンセプトで感銘をリスナーに与える素晴らしいギタリストだと思う。
試聴もできるので聴いてみて欲しい。
http://www.joelxavier.com/
録音は2002年11月12-15日 LISBOA
最新アルバムではなんとロン・カーターとのデュオアルバム。
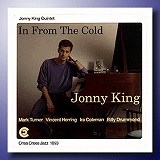
クリスクロスのCDを買うのは周期があって、今はあまり買っていないかなぁ・・・
このCDがでた1994年の秋頃はポロポロと新作を買っていた。
このJONNY KINGもその頃レコーディングデビューした新進ピアニストの作品だったので、他の作品と一緒に岡山の「グリーンハウス」で買ったと思う。
ライナーノーツによると、このレコーディングがおこなわれた1994年当時、JONNY KINGは29歳で法律家とミュージシャンの二束のわらじをはく忙しい人間だったようだ。
ビリー・ピアース、ケニー・ギャレット、ボビー・ワトソン、グレッグ・オズビー、ラルフ・ムーア、ジョシア・レッドマン、ビリー・ドラモンドらと共演したことがあり、オリジナル作品がビリー・ピアース、ビリー・ドラモンド、トニー・リーダスにレコーディングされた経歴の持ち主。
そんな彼の初リーダー作がこの作品なのだが、なるほど聴いてみて演奏と作曲を比べてみた場合圧倒的にプレイヤーとしてより作曲家、音楽家としての質が高いのがわかるはずだ。
リズムやハーモニー面で一捻りした工夫がなされていて、楽曲とアレンジメントがうまくかみ合っていて独りよがりなところがない点が評価されると思う。
あまりにも曲を弄り回して聴いていて浮いてしまっていて少しも楽しくなかったり、その逆に曲自体に魅力がなかったり、あまりにも単純な曲過ぎて飽きてしまったりという事がミュージシャンのオリジナル作品には往々にしてあるのだけど、このジョニー・キングのコンポジションは丁度リスナーのピンスポットを上手く突いているというか、魅力的な楽曲揃いなのである。
実際、CDを聴いた後もピアニストとしての印象は強く残らず、マーク・ターナーの高域中心のフレーズ使いや相変わらずマッシブでパワフルなヴィンセント・ハーリングのアルトサックス、ビリー・ドラモンドの機敏で歯切れよいドラミングが印象深い。
その後ジョニー・キングはENJAから2作品アルバムをリリースしたが、近況をきかない。
ジャズピアノの本を出版したそうだけど、ミュージシャンとしてはどうしているのだろうか?
メンバーはJONNY KING(P)MARK TURNER(TS)VINCENT HERRING(AS,SS)IRA COLEMAN(B)
BILLY DRUMMONDO(DS)
録音は1994年1月2日 NYC
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- John Wetton - An Extraordinary Life
- (2024-11-29 00:00:16)
-
-
-
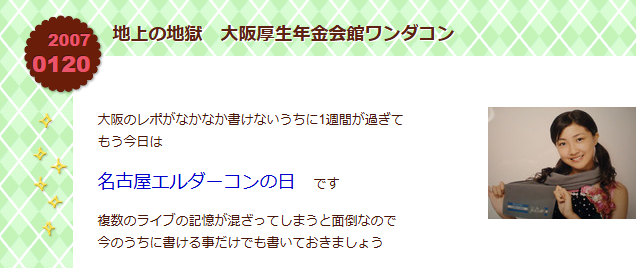
- LIVEに行って来ました♪
- 始原本家 70年史 2007年1月
- (2024-11-24 10:29:27)
-
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- あさって、ジンのI’ll be there 楽し…
- (2024-10-23 23:53:52)
-
© Rakuten Group, Inc.