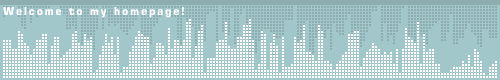音円盤アーカイブス(2005年7月)

初リーダーアルバムのトーラス盤を買って感心したアルトサックスのヤングライオン(当時25歳だった)JON GORDONのCHIAROSCURO盤。
師匠ともいえるアルトサックスの重鎮フィル・ウッズとのツーアルト構成となっている。
GORDONのアルトはハリのある艶やかな音色で、高音部へフレーズが駆け抜けていくところなどは、フィル・ウッズにとても良く似ている。
フレーズ面では、さすがに若手ミュージシャンなので、ビバップ一辺倒ではなく、モード以降の様々な奏法の片鱗が見受けられる。
ピアノのKEVIN HAYSも、やみくもに弾きまくるのではなく、よく練られた意味のあるフレーズを紡ぎだして素晴らしいサポートをおこなっている。
3曲目「EVIDENCE」でフィル・ウッズの登場。「WHAT'S NEW」「MY SHINING HOUR」とウッズのオリジナル1曲、全部で4曲ジョン・ゴードンと競演している。
ウッズが入るとゴードンがまだまだ青く感じるほど、スムースで音色のニュアンス、太さ、艶やかさで勝る点がある。
まだまだ若い者には負けられぬと言ったところだろう・・・
GORDONがウッズに勝っているところがある。
勿論、若さである。瑞々しさ、新鮮さ、何か新しいことをやってくれるのではないだろうかという期待感、実際そう期待させるに値する音楽的にしっかりした才能とセンスを持っている。
「MY SHINING HOUR」では、互角の勝負ではないかと思わせるフレッシュで溌剌としたプレイをおこなっていて、師匠ウッズも弟子の成長に目を細めながら共演を楽しんだに違いない。
メンバーはJON GORDON(AS,SS)KEVIN HAYS(P)SCOTT COLLEY(B)BILL STEWART(DS)PHIL WOODS(AS)
録音は1992年3月8日 SAYLORSBURG

2002年にCD復刻されるまで、幻の名盤だったソニア・ローザのデビュー作(CONTINENTAL盤)。リイッシューの報を知った時は飛び上がって喜んだ。
ストリングスやウッドウィンズの響きとソニアの刻むボッサギター、個人的にはとろけそうになる甘いウィスパーボイスに、何も言う事はありません。
ただ、黙ってひたすら聴いていたい作品ってありませんか?
それが、私にとってソニア・ローザとジョアン・ジルベルトになります。
だいたい、ジャズと違ってブラジル音楽のことは、あまりとやかく言う気がしない。
ただ、黙って聴いていたい音楽なのです。
一言だけ言うなら、ここには、来日後のよりソフィスティケイトされた和製ボッサのソニア・ローザよりもっとプリミティブでナチュラルな姿が捕らえられている。
勿論どちらのソニアも好んで聴いている。渡辺貞夫や大野雄二とコラボレーションして生まれた作品もブラジル時代の10代の頃の録音の当作品も、可憐でキュートで、少しオキャンで舌足らずなソニアの素晴らしい歌声が聴けるだけで幸せなのだ・・・
今年の夏は長い間行っていない海に行ってみようかな・・・
録音は1967年

10年以上前、WIZ WONDERLANDの催事会場で広島レコードマーケットで手にいれたもので、ジャケ裏に新宿「木場」のスタンプと通し番号がついている
ジョー・チェンバースがおそらく自費出版でリリースしたもので、ウェイン・ショーターの「RIO」をどう料理しているのか聴きたかって買ったのだろう。
アルバムのテイストで似ているものを挙げたらアル・フォスターの「MIXED ROOTS」だろう。マイルス、テオ・マセロ、経由のニューヨークサウンドと言えばよいのか、複雑にリズムが交差したり、バンプが設けられたマイルス風の曲作り、電化ロックサウンド(エレピ、エレキギターの多用)、など相当JOE CHAMBERSも気合の入れてこの作品の録音にのぞんだ事が推測される。
何より、1曲目からのドラムの叩き方からして尋常でない。こんなアグレッシブでパワフルなジョーのドラミングは聴いた事がない。
3曲目がお目当ての「RIO」。このアルバムでは、「WAYNE SHORTER'S BOSSA NOVA」と題されている。PAUL METZKEのロックテイストのギターとエレガントでスノッブなEDDIE MARTINESのエレピ、DICK MEZAのサックスがクールで少し変なショーターの曲を上手く解釈していて結構聴かせるトラックになっていると思う。
HERB BUSHLERとJOE CHAMBERSのリズムの抜け具合も絶妙だ。
4曲目はハンコック「BLOW UP」で、前曲とうって変わってちょっと俗っぽい感じがしないでもないが、悪いものではない。
アルバムのどこにも録音年月日のクレジットがないのだが、ジョー・チェンバースの顔写真とサウンドから70年代後半だと推測される。
メンバーはJOE CHAMBERS(DS,MARIMBA,VIVES)EDDIE MARTINEZ(ELP)HERB BUSHLER(ELB)OMAR CLAY(PER)PAUL METZKE(G) DICK MEZA(TS,SS,FL)REY MANTILLA(PER,CONGA)

先々週、久しぶりに休日街中に出かけた時、閉店間際の「GROOVIN'袋町店」で買ったCD。テナーのKRSTER ANDERSSONの名前は知らなかったけど、ピアノにはCARL-FREDRIK ORRJE、ベースにはPER-OLA GADDが参加しているので、買いました。
いやぁーー。思わぬ拾い物でした。このCD。
テナーのKRISTER ANDERSSONは若干音が軽いけどテクニシャンで節回しの上手いところをみせて納得のプレイをしている。CARL-FREDRIK ORRJEもハンコックばりの早弾きフレーズを連発させたかと思えば、オーソドックスで歌心溢れた熟練の技も冴えており引き出しの多いところを披露している。PER-OLA GADDは所々、ギシギシとベース弦がきしむパワフルなプレイ、ドラムのBENGT STARKもキレの良いドラミングでカルテット全体がとてもよくスイングしていて聴いていて楽しい気分になる。
曲調も変化に富んでいて、モード曲、明るいテーマをもつ4ビート、ちょつと変わったテーマのスローブルース、物悲しいバラード、ストレートにスイングするアップテンポ曲、ビーバップ調などを演奏していて飽きがこない。
いい意味でのエンターテイメントの精神がバンド全体にゆきわたっているのだと思う。
ジャズは聴衆に媚びたらお終いだと思うが、こんな具合に絶妙なバランスで発揮されるエンターテイメントの精神は歓迎だ。
メンバー全員の高い音楽性が結実した素晴らしいグループだと思う。
メンバーをもう一度、KRITER ANDERSSON(TS,CL)CARL-FRERIK ORRJE(P)PER-OLA GADD(B)BENGT STARK(DS)
録音は1996年1月6日 SWEDEN

2週間前DUから購入したばかりの新着CD。ELLERY ESKELLINが参加していることとアメリカの古い漫画のようなストレンジなジャケットに興味をそそられたのだ。
「骸骨二丁拳銃ガンマン、墓場に現る」といった風情のユーモア溢れるジャケット、私は好きですね。ジャズはあまり感じないけど・・・
1曲目、単調なフレーズをBOB PRICEが繰り返す中、一聴、皆がバラバラに好き勝手やっているように聴こえるが、事実そうで、ESKELINは抽象的で浮遊感溢れるメロディーを吹きだしていくし、JOEY BARONは別のタイム感覚で自由奔放なリズムをたたき出す。ベースのTREVOR DUNNも独自のラインを弾いているように聴こえる。それが次第に一点に向かって収束しこれから何か起こるのかなと思っていたら結局何も起きずにやがてフェードアウトする。
2曲目はタランティーノ監督の「キル・ビル」を見ているかのような、不思議な感覚を味わえる曲。パラレルワールドのような別の世界でのジャズがあったとしたらこんな感じなのかもしれない。3曲目もそういう雰囲気が続いてまさにこのジャケットの絵のフィーリングをそのまま音にトランスレートした感じ。ROB PRICE、ひょっとして只者ではないかもしれない。菊地成孔が「デキュタシオン」でやったようわざと音楽のコアの部分をすくいとってカスタマイズした様に、次の4曲目なども1:45という短い時間で題をつけるとしたら「墓場への行進、ロックンロール風味仕立て」みたいな似たような事をやっていると取れなくもない。
アルバムを通してそんなユーモアや比喩の精神が感じ取られ音楽自体もいきいきとこちらに迫ってくるところを大いに評価したい。
メンバーは、ROB PRICE(G)ELLERY ESKELLIN(TS)TREVOR DUNN(B)JOEY BARON(DS)
録音は2004年3月、4月 BROOKLYN NYC

1993年に「LPコーナー岡山店」で買ったCDで、この頃は出るバルネのCD、復刻のLPをほとんど全て追いかけていました。
IDA,ALFA JAZZ、VENUSから出る新譜CDに、フレッシュサウンドから復刻される50年代のものを愛聴していたそんな折、このCDを発見した。
ある意味その頃思い描いていたバルネのお洒落でアンニュイでいかしたジャズマンというイメージを覆すかのようなちょっと過激でエキセントリックな音に途惑ったのを覚えている。これは、自分の好きなバルネではない・・・それ以降あまり聴いていなかった。
中古屋に売り飛ばしそうになったこともある。
今、久しぶりに聴いてみて、これが滅茶苦茶いいのですねぇ!
あの時売り飛ばさなくて良かった。
レース場のエンジン音で始まる1曲目から、フルスロットルでバルネとラバが吹きまくる。ライブ盤なのでソロが長めで聴き応えがある。
今まで聴いてきたバルネはそのほんの一面の部分を切り取ったものに過ぎなく、バルネ・ウィランというミュージシャンはもっと幅広く奥の深い音楽性の持ち主だという事がこのアルバムによって再検証できる。
60年代は実際アフリカを放浪し、フリージャズやニュージャズにも傾倒したバルネのこと、聴く側のこちらの一方的な思い込みに過ぎなかったわけでバルネ自身が決して変わったわけではないのだろう。
このアルバムの音楽はハイブロウなんだけど、60年代のような独りよがりの部分がなく、
成熟した前衛性を秘めながらも外に向かって開かれたオープンマインドの音楽である点が
バルネのミュージシャンとしての成熟を表すものだろう。
JAZZにおいて、本当の意味での「自由な音楽」がここで展開されているのだ。
バルネのことばかり書いてしまったがラバも渋いソロやオブリガードを吹いていてカッコいい!集められたミュージシャン全員がカッコいい!
メンバーはBARNEY WILEN(TS,SS)ENRICO RAVA(TP)PHILIP CATHERINE(G)BALTHASAR THOMASS(P)PALLE DANIELSSON(B)PETER GRITZ(DS)SEGE MARNE(PER)
録音は1992年5月28日
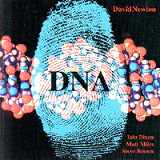
5月末、広島駅地下で催されていた中古市で買ったCDで、DAVID NEWTONはLINNレーベルからの初リーダーアルバムを持っていたが、その一枚だけしか持っておらず最近の演奏はほとんど聴いていなかった。最もこのCDも大分前の演奏だけど・・・
CANDIDからの作品で、ピアノトリオではなく、IAIN DIXONというサックス奏者を加えたカルテット作品。
IAIN DIXONのサックスはちょっとくすんだ音色でオーソドックスで歌心豊かなプレイで、デビッドのピアノといいバランスを保っている。
ソプラノを吹いたら少し丸みを帯びた音色で、感覚的にテナーより新しい新鮮な演奏をするみたいだ。
DAVID NEWTON初め、メンバー全員が日本では余り知られていない馴染みのない名前かもしれないが、メンバー全員が協調性溢れた音楽性の高い演奏をおこなっていて納得させられた。DAVID NEWTONのピアノはタッチがとてもよくて表情が豊かなので、弾いている音に無駄がなく伝わってくる情報量がとても多いのに感心させられる。
作曲能力にも非凡なものがあって今後の活躍をますます楽しみにしたい。
すこし地味な性格なのか、素晴らしい才能を持っているのだからもっと自分をアピールして前へ出てきてもよいピアニストだと思う。
メンバーはDAVID NEWTON(P)IAIN DIXON(TS,SS)MATT MILES(B)STEVE BROWN(DS)
録音は1996年11月20,21日 SUSSEX ,ENGLAND

初めてJESSE DAVISのサックスを聴いたのはCONCORDから「タナ・リード」のファーストアルバムだった。そのアルバムの録音を聴いたCONCORDのオーナー、カール・ジェファーソンがジェシーの才能に驚嘆し、すぐさま契約を持ちかけたという逸話が残っている。そして数ヵ月後ファーストアルバムがリリースされそのアルバムも手に入れたが、ジャケットがそれまでのコンコードレーベルのイメージから大分変わったなという印象をもった。派手になったのだ。
最もジャケットが派手になっただけで、ジェシーのサックススタイルは決して地味ではないが、実直でどちらかというと玄人受けするタイプのミュージシャンだと思う。
一般受けするようなフレーズやクリシェを使わず、その恵まれた体格、肺活量を生かしたファットなビッグトーンで自身の納得したフレーズしか吹かない。
マイペースなのである。マイペースだから他人のことを気にしない。
音楽がセコセコしていないのだ。セコセコしていないから早いフレーズを吹いてもゆったりと聴こえて一音一音のニュアンスがよく聴き取れる。
常に余裕を感じさせるプレイをするので、聴いていて危なげがない。
決してジャズ的なスリルに乏しいわけではない。むしろ一音一音に表情があるので、パッションが感じられ音のニュアンスも多彩で、色々なカラーを感じるのだ。
オーソドックスな演奏をする若手プレイヤーの中では人気は別にして実力は三本指に入るアルトサックス奏者だと思う。
もう少し本人に売り込む意欲があれば、もっと人気がでるプレイヤーだとおもうのだけど・・・
最新作は2001年にコンコードを離れマイナーレーベルからリリースしたもの。
実力は充分すぎるほどの持っているので、アルバム作りももう少し一般受けする曲を織り交ぜて作ったらもっとアピールして売れるのにと思う。
本人が、そんなことに関心が無いのだろう。
このアルバムもある意味(アルバム作りという意味)不器用なジェシーのファンタスティックなサキソフォーンが収録されたアルバム。
メンバーも素晴らしいので、聴いてみる価値は充分あると思います。
メンバーはJESSE DAVIS(AS)PETER BERNSTEIN(G)BRAD MEHLDAU(P)DWAYNE BURNO(B)LEON PARKER(DS)
録音は1995年3月24,25日 NY

このCD,最近リリースされた物なのに何故かなかなか入手できず、つい最近DUに再入荷したのか、通販で買うことができました。
勿論、マーク・ターナーがサイドメンでほぼ全曲参加しているのが買った理由。
インナーのジャケを見るとスキンヘッドだったマーク・ターナーがショートアフロのような髪型に変わっているではありませんか?
そんな事はどうでもいいのだけど、このアルバムでもいつもの様に変幻自在の浮遊感に飛んだサックスを吹いていて、高音部からフラジオで駆け抜ける複雑なフレーズをいとも容易く吹いてしまうテクニックはとても素晴らしい。
ERIK STEPHENSはトム・ハレルばりに音色の柔らかなトランペット、フリューゲルを吹く逸材で、マーク・ターナーのサックスとのバランスも大変良い。
リーダーのEMMANUEL VAUGHAN-LEEがこのアルバムをレコーディングするきっかけは子供が生まれ父親になるという感情がインスピレーションの源らしい。
なんとなく優しげで穏やかな曲調が多いのはそのせいか?
6曲目はSTINGの曲で、ラテンフレーバーのするそこはかとない哀愁漂うメロディーをALBERT SANZとEMMANUELが好演。美メロ曲だ。
EMMANUEL VAUGHAN-LEEは基礎のしっかりした素晴らしいベースプレイヤーだが、それ以上に作曲能力に新しい才能を感じさせる。
このレコーディングでも集まった素晴らしいミュージシャンの個性を殺さずに自分の伝えたいメッセージを全員が同じフィーリングで表現していて、その音楽性が100%ダイレクトにこちら側に伝わってくる手腕が特に秀でていると思った。
メンバーは、MARK TURNER(TS)ERIK JEKABSON(TP,FLH)ALBERT SANZ(P,ELP)
EMMANUEL VAUGHAN-LEE(B)FERENC NEMETH(DS)
録音は2004年5月26,28日 BERKELEY,CA

スウェーデンのベテランドラマーFREDRIK NORENのハードバップエンターテイメント作で、5月末中古市で入手した。
テナーには、自身のリーダー盤では結構過激でラウドな吹奏ぶりが評判のJONAS KULLHAMMARが参加しているのが目を引く。
選曲は、「SIDEWINDER」「BOHEMIA AFTER DARK」「BLUES MARCH」などいささかベタなものも含まれるが、わざとらしいところが感じられず、マンハッタン・ジャズ・クインテットみたいな人工的な雰囲気はないので、違和感なく自然に聴き進んでいける。ついでに曲を並べておくと、「FRIED BANANA」(D.GORDON)「WALKIN'」「UNITED」(SHORTER)「YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS」[GINGERBREAD BOY」(J・HEATH)「SOY CALIFA」(GORDON)「AFRO BLUE」(M・SANTAMARIA)「IT TAKES TWO TO TANGO」の全11曲。
JONAS KULHAMMARもここではいたって正統派の歌心溢れたプレーに専念していて、アップテンポ、バラードどちらも素晴らしい説得力のある演奏を展開している。
「YOU DON'T KNOW」などのバラード解釈にテナー奏者としての力量を感じる。
トランペットのNILS JANSONとの二菅編成のフロントはバランスもよい。 このアルバムが現代ジャズの一面を切り取った作品かと問い詰められると返答に困るのだが、
そんな堅いことは抜きにして理屈ぬきにモダンジャズの名曲をストレートに楽しく演奏するというこのアルバムの主旨をそのまま楽しんだらそれで良い作品なのではないか?
メンバーはFREDRIK NOREN(DS)NILS JANSON(TP)JONAS KULHAMMAR(TS)DANIEL TILLING(P)TORBJORN ZETTERBERG(DS)
録音は2001年6月16,17日 STOCKHOLM

ちょうど一昔前、梅田にあったワルツ堂EST1店のバーゲンコーナーで見つけたもの。名前を見たら買わずにおられない大好きなテナー、BOB ROCKWELLのクレジットを発見したから。
1曲目から活きのいいサウンドが飛び出してくる。
この頃のBOBは前へ前へとライブと言う事もあるのか、いつにましてストレートにスイングする直球で勝負しているようだ。ストレスがまったくないスムースで流暢なフレーズの展開にこの日のBOBのやる気をみた。
ANDERS BERGCRANTZもBOBに負けじと素晴らしいフレーズを矢継ぎ早に綴っていく。ライブ録音なので1曲が10分以上のものが少なくないが演奏が充実しているので冗長に聴こえる事はない。全員の一丸となった音楽へのアプローチと個々の充実した個人技がいいバランスで展開されていて聴いていてとても充実感、満足感を味わえる作品になっている。そこは、このアルバムのリーダー、JAN KASPERSENの統率力によるものだろう。
3曲目はBOB ROCKWELLのバラード演奏。ビタースウィートでハードボイルドなテナーの音色に思わず聞き惚れてしまう。
このサックス奏者に最近ようやく日本のジャズジャーナリズムも関心がいくようになったみたいだけど、もっともっと記事に取り上げてよいミュージシャンだと思う。
メンバーはANDERS BERGCRANTZ(TP)BOB ROCKWELL(TS)JAN KASOERSEn(P)PETER DANSTRUP(B)OLE ROMER(DS)
録音は1991年8月5日 COPENHAGEN

最初、映画のワンシーンの様なジャケットに目がいって、知っているミュージシャンは、NATHALIE LORIERSだけだなぁと思っていた。裏ジャケの曲が購買動機になった。「FEE.FI.FO.FUM」「ELM」「THINK OF ONE」「NEFERTITI/OFF MINOR」「EVIDENCE」「YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS」。モンク、ショーター、にバイラーク、これこれという感じでレジに持っていったのだろう。
JEANFRANCOIS PRINSの作曲によるアルバム表題曲「N.Y.STORIES」はダウン・トゥ・アースな雰囲気な循環ものだけど、全員の充実したソロが聴かれアルバムの冒頭に相応しいこれから何か起こるぞと期待させるに足る幕開け。
PRINのギターはソロになると、太い音でぐいぐい引っ張っていく結構正統派の音作りで、聴かせるものを持っている。バックに回ったり、曲調によっては、繊細な音つくりもバッチリでこんなところからもルネ・トーマを彷彿させる。
NATHALIE LORIERSはバックでもソロでも様々なカラーを感じさせる表情豊かなサウンドを提供しており、アルバムに幅を出す要になっていると思う。
どちらかと言うと剛のソロイストのPRINに対し、柔のLORIERSが柔軟なバッキングをつけているという構図で、同じコード楽器のぶつかり合いを上手いこと避け、むしろ相乗効果でアルバムのサウンドに幅を持たせることに成功している。
サックスのERWIN VANNは大きな個性はこの録音当時まだ感じさせないが、テナー、ソプラノとも真っ直ぐで嫌味のない吹奏は好感が持てる。
ベルギーのヤングミュージシャンがベテランのリズムセクションにサポートされて出来上がった充実した作品だと思う。
メンバーはJEANFRANCOIS PRINS(G)NATHALIE LORIERS(P)ERWIN VANN(TS,SS)JEAN-LOUIS BAUDOIN(B)FELIX SIMTAINE(DS)
録音は1991年4月

今年のGW,注文していたCDが入荷したという連絡をもらい「ノルデック・サウンド・ヒロシマ」という本当は北欧クラッシック専門の店に取りにお伺いした。
インターホンを鳴らしオートロックの扉を開けてもらいエレベーターに乗って目指す部屋へ・・・マンションの一室のこの場所で既に7年も営業しているというではないか。店長がとてもフレンドリーな方で、初対面で専門外の音楽なのに、色々応対してくれ、その時にカタログを見せてもらって注文したのがこのPALLE DANIELSSONと明日書くつもりのRED MITCHELL盤。
聞けば、北欧のジャズにも週2回のデリバリーを利用してこれから力を入れていきたいとの事。
PALLE DANIELSSONのこの作品はジャズ批評のベース特集号でジャケを見て以来興味を持っていた。
DANIELSSONはそれこそ70年代のキースのヨーロピアン・カルテットの頃から馴染みのベーシストで、サイドメンで参加している作品は結構持っていると思うけど、このアルバムが何と初リーダーアルバムらしい。
リーダーアルバムだからといって自身のベースが極端にフューチャーされる事もなくサックスのJOAKIM MILDERやピアノのRITA MARCOTULLIの個性を上手く活かした音楽としてバランスのよい作品に仕上がっている。
全体的に思索的で洞察力の深い、そして一般的に北欧的なイメージというとECMレーベルに代表されるひんやりした、部屋の温度が何度か下がりそうな清涼感溢れるサウンドが展開されている。
もちろん演奏内容は低血圧の青白い顔してプレイしたものではなくて、内にメラメラと情熱を秘めてアクティブにプレイされたものなのは言うまでもない。
表現したい音楽が単にそういうサウンドを志向しているだけの話。
メンバーはPALLE DANIELSSON(B)JOAKIM MILDDER(TS,SS)RITA MARCOTULLI(P)
ANDERS KJELBERG(DS)GORAN KINGHAGEN(G)
録音は1994年5月30,31日6月1日 RAINBOW STUDIO OSLO

このアルバムも「ノルディック・サウンド・ヒロシマ」でその時注文して手にいれたものなんですが、少し因縁めいたエピソードがある。
「LUSH LIFE」というHPを随分前から主宰されているBARNEYさんのサイトをネットサーフィン中偶然発見したのが4月だったか?
そのBARNEYさんが、5月初めに、よりジャズに特化したブログ、「HOME SUITE」を立ち上げられた時、そのネーミングのもととして一番最初に紹介されたレコードがこのRED MITCHELL盤という訳。
ネット上のREDの「HOME SUITE...」の画像を暫らく眩しげに見つめていた私。
ちょうど翌日に「ノルディック・サウンド・ヒロシマ」へ行ったのです。
そこで店長が、初対面にかかわらず「こんなものが、うちでは入荷しますよ。」とカタログを指差したCDが、当作品RED MITCHELLの「HOME SUITE...」だったのだ。
長い間レコードやCDを聴いていると時々こういうめぐり合わせというか、不思議な経験をすることがありますよね。
前にも書いたけど、「初山博/SMILE」や「チック・コリア/日輪」なんかがそれに当たる。
ところで、「HOME SUITE...」の内容だけど、さすが、BARNEYさんがブログタイトルにしてるだけあって、ほんと聴けば聴くほど味が出てくるスルメ盤です。
REDが日当たりの良い自室で、気のむくまま好き勝手楽器と戯れているといった風情で、
リラックスしていて、スローライフな雰囲気が全編を通して漂っているのだけど、
それが決して緩い感じではなくて一本筋が通っていて、ジャズ的な緊張感はずっと
保っているのだ。
それでいて、ユーモアやペーソス、おおげさに言ってしまえば人生や哲学までも感じさせてしまうRED MITCHELLというベース奏者の存在の大きさが分るしかけになっている。
深夜にでも、REDの音楽との戯れを目を閉じて聴いてみて欲しい。
RED MITCHELL(SOLO BASS,PIANO,VOICE)
録音は1985年1月16、17日

今から15年くらい前に、心斎橋商店街の「三木楽器」で買ったレコード。
その当時は今はどうなのか知らないけど、各国の輸入盤レコードが結構置いてあったはず。新譜を「三木」で見て、「MUSIC MAN」と「MT.KISCO」で中古をチェック、難波まで歩いて「LIGHT HOUSE」と「BIG PINK」に行くというのがミナミのレコ掘り定番コースでした。
その頃はまだまだエンリコ入門仕立てで、このレコードも現物見て初めて知ったくらい。メンバーを見て勿論即買いを決めたのは言うまでもありません。
アート・ファーマーがいつもより元気よく、アグレッシブにハードバッピッシュに吹いている。一方のマッシモ・ウルバーニのほうは、当時のリーダーアルバムなどと比べて幾分押さえ気味で、暴走はしない。
リーダーのエンリコの指示なのか、ファーマーとウルバーニが二菅でフロントをとる作品ではそういう塩梅で、微妙なバランスを保っている。
ただ、2人は本質的にはタイプが正反対のミュージシャンだと思う。
ファーマーが全体の和を重んじてどちらかというと静的なプレイをおこなうのに対し、ウルバーニはあくまでも個を重視し、動的なプレイに存在意義を生み出すと言ったら短絡過ぎるだろうか?
エンリコには、どちらのミュージシャンが合うのかだって?
音楽的テイストではファーマーの方がしっくりくるでしょう。現にファーマーをフューチャーしたワンホーンカルテットの方が完成度の高さを感じる。
かといってツーホーンのものが良くないというわけではなくて、スタイルの異なるミュージシャンがお互いの音を聴きながら音楽性を擦り合わせていき作品を作っていこうというドキュメントが見受けられて興味深い部分があるのだ。
こういうところが、個性を重んじるジャズのジャズたる所以だと思う。
最後にエンリコのピアノはこの頃から眩い輝きを発していて非凡なところを既に発揮していると記しておきたい。
80年に録音されたヨーロピアンハードバップの貴重なドキュメンタリー。
メンバーはART FARMER(FLH)MASSIMO URBANI(AS)ENRICO PIERANUNZI(P)FURIO DI CASTRI(B)ROBERTO GATTO(DS)
録音は1980年2月9,11日 ROMA

アマゾンから5月に購入した新作で、オーストラリアのピアニストPAUL GRABOWSKYがニューヨークのトップミュージシャンと繰り広げたセッション盤。
BRANFORD MARSALISがソプラノ、JOE LOVANOがテナーを吹いていておまけにドラムスがJEFF TAIN WATTSときたので、飛びついて「注文する」のところをクリックしてしまったのである。
ジェフ・ワッツの素晴らしいドラムに乗って、トランペットのSCOTT TINKLERがフリーブローイングな大胆でありながら良くスイングしたソロを披露したかと思えばブランフォードもそれに触発されたのか負けじとソプラノで長く複雑なフレーズを吹き続け、気合の入っているところを見せる。
2曲目はパースペクティブな風景が目の前に広がっているような少し幽玄な響きもする曲で、後半に展開されるジョー・ロバーノのソロが書道の大家が一筆書きで記した作品のように自由でありながら美しさを感じさせる芸術作品のようにテナーマスターとして完成の域に達した様をみせつける。
4曲目もジョーがメロディーを吹くのだけど、一吹きしただけで、音楽がジョーのカラーに染まり、メロディーが原曲以上に膨らんでいってより深い意味をもったメーセージが発せられるのだ。
PAUL GRABOWSKYの曲は詩的なイメージを感じさせる作風が多くて、ソロイストの感じ方によって、原曲を自由に解釈して発展させることができる許容度だ大きい柔軟性に富んだ作品が多い。逆にプレイヤーに力量に負うところが多いともいえるのであるが・・・
この作品には、エスタブリッシュなメンバーが揃っているのでGRABOWSKYの狙いは見事当たったといえるのではないだろうか?
メンバーはPAUL GRABOWSKY(P)BRANFORD MARSALIS(SS)JOE LOVANO(TS)SCOTT TINKLER(TP)ED SCHULLER(B)JEFF"TAIN"WATTS(DS)
録音は2003年4月24-27日 AVATOR STUDIOS NYC

BRAMBUS RECORDSのHPでこのROLF HASLERのCDも試聴できて、いつか買おうと思っていたのですが、昨日袋町グルーヴィンでGET。
デックス系のオーソドックスな本当にテナーサックスらしい音色で、スタイルも豪放で男性的、おおらかなスイング感を持ち合わせた良く唄うフレージングが魅力的である。
サイドメンも皆無名だが、リーダーの意図することをよく飲み込んだプレイに終始しており、特にピアノのJEROME DE CARLIはチャーミングなきらりと光るソロが素晴らしく、将来楽しみな人材(と言っても写真を見ると結構ベテランのよう)だ思う。ピアノトリオによる作品を聴いてみたいと思わせる逸材。
ROLF HASLERは、中庸のよさを全面に押し出していくスタイルというか、はっきり言ってあまり冒険をおこなわない。 70年代以降の複雑なフレーズを使用せずに地にどっしり足をついた前向きにスイングすることを最大の目標にしている。
そこに迷いが無い。迷いがないので、説得力があるし、音楽が完全に自分のものになっているので、聴いているこちら側も首を縦に振らざる得ない。
スタイルではなくて、様はそのミュージシャンの心の奥底から発されている等身大の音楽が表現できているかどうかなのだと思うのだ。
ただしソプラノを吹けば、コルトレーンの影響が幾分強くなる。
チェンジオブペースだと思えば、悪くは無い。
後半はスタンダードを3曲。「NEVER LET ME GO」「EASY TO LOVE」「I'M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU」。
サックス奏者の力量が推し量れるトラックだと思うが、ROLFの素晴らしい実力が表れたナンバーだと思う。
メンバーはROLF HASLER(TS,SS)JEROME DE CARLI(P)GIORGIOS ANTONIOU(B)PETER HORISBERGER(DS)
録音は2003年4月8,9日 FRIBOURG
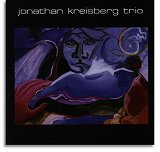
今はNY在住の若手実力派ギタリストの仲間入りを果たしたといえるJONATHAN KREISBERGの1996年作品で、最も初期の録音だと思われる。
CRISS CROSSの様な雰囲気を期待していたのだけど、この頃はロックミュージックからジャズへ転進して間もない頃だからか、スタイル的にはフュージョン的な要素がとても多いサウンドになっている。
マイク・スターン、ジョン・スコフィールド、アラン・ホールズワースのスタイルをミックスしたようなサウンドで、勿論ジミ・ヘンに代表されるロックギターのテイストが色濃く出ている部分もある。
この頃はまだまだ自分のスタイルを作り上げる過渡期だったのであろう、音に求心力がないというか、聴いていてこちらが身を乗り出すような、インパクトや説得力にはっきり言ってまだまだ欠けると言わざる得ない。
持っている語彙の少なさも気にかかるところ。引き出しが多いだけで、器用貧乏なのも困るけど、臨機応変に様々の音楽の状況に柔軟に対応していきつつ、個性をその中で出せるのが一流のジャズミュージシャンだと思う。
オリジナル作品において、いい瞬間が1分くらい続く時もあるのだけど、持続性がない。途中で焦点が曖昧になってしまって音が分散してしまうのだ。
CRISS CROSSレーベルでの最近のストレートアヘッドな集中力と持続力のある快調なプレイを聴くにつれ、この当時、ジャズギタリストとして修行を相当積んだことが推測される。
メンバーはJONATHAN KREISBERG(G) JAVIER CARRION(ELB)VINCENT VERDERME(DS)
1996年作品
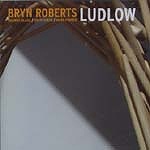
このCDも最初アマゾンに頼んでいた物が入荷せず、DUから暫らくして入手したもので、最近何故かFSNTの新譜が手に入りにくくなっていると感じるのは、私だけだろうか?
BRYN ROBERTSという新人ピアニストのリーダー作品なのですが、テナーにSEAMUS BLAKEが参加しているので買いました。
このアルバムはBRYNの第2作目で、デビュー作は2001年にリリースされていて、それにもSEAMUS BLAKEが参加している。
ピアノの師匠はフレッド・ハーシュで、どうりで繊細でありながら明確な意志が伝わってくるようなニュアンスが師匠譲りだと感じる。
2001年にモントリオールからニューヨークに移って「BLUE NOTE」「BIRDLAND」「FATCAT」「the 55 BAR」などの有名ジャズクラブで様々なミュージシャンと演奏して、キャリアを積んでいる。
このアルバムが録音されたのは、26歳だった模様。
作曲のスタイルは、一聴、捉えどころの無いようで、よく聴くと様々な仕掛けやストーリー性を発見することが多く、プレイヤーに最大限の自由を与えるような調子の曲が中心となっていて、こういう作曲手法はこのFSNTがリリースしているブルックリン派中心の流行となっているように感じる。
こういうムーブメントの中から時世に残る名曲が生まれてくることに期待したい。
BRYNのピアノは音数で勝負するようなテクニシャンではないが、師匠譲りの写実的な表現や陰影のつけ方などに秀でた情感を伝えるのが得意なピアニストと見た。
まだまだ初々しいところも見受けられるので、ピアニスト、コンポーザーとしての今後の成長に期待したいピアニストの一人だと思う。
SEAMUS BLAKEはいつも通り、素晴らしいテナーサックスを吹いていることを付け加えておきたい。
メンバーはBRYN ROBERTS(P)SEAMUS BLAKE(TS)DREW GRESS(B)MARK FERBER(DS)
録音は2003年6月30日 MONTOREAL,CANADA

今だと馴染みのあるメンバーの名前もこのCDを入手した1998年頃は、誰一人知ってるメンバーがいなかった。
今見るとイタリアジャズ界に確固たる地位を築き上げているメンバーが名を連ねている。
FABRIZIO BOSSO,GAETANO PARTIPILO,GIANLUCA PETRELLA,STEFANO BOLLANI,GIUSEPPE BASSIなど。
アンドリュー・ヒル「MIRA」サム・ジョーンズ「UNIT7」デューク・ピアソン「AMANDA」リー・モーガン「MR.KENYATTA」とボラーニ、パーティピロ、バッシらメンバーのオリジナルからなる構成。
SCHEMAというレーベルカラーからクラブシーンに向けてのジャズ作品という点はある程度否めないし、曲調もそういうフロア受けしそうなアップテンポの快適な曲が多く収録されている。
これが、悪くないんだなぁ。
今一歩、気分が乗らないときこのCDを聴けば、そんな鬱気分も吹っ飛ぶ滋養強壮剤のような働きをしてくれ「元気ハツラツ!」になること受け合い。
成功の要因は、選曲の勝利とイタリア若手勢の音楽的技量におうものが多いと思う。ソロイストではやはり、FABRIZIO BOSSOとSTEFANO BOLLANIの2人が頭ひとつ飛び出した存在か?
他のメンバーも水準の高いプレイをおこなっていて、彼らのジャズ的成熟度と若々しいフレッシュな感性が見事に結実して爽やかな風を呼び起こせていることが勝利の最大の要因であろう。
メンバーはFABRIZIO BOSSO(TP)GAETANO PARTIPILO(SAX)STEFANO BOLLANI(P)GIUSEPPE BASSI(B)FABIO ACCARDI(DS)
録音は1997年6月2,3日 MILANO

2000年に倉敷「GREENHOUSE」で買ったCD。
JEFF GARDNERはPANレーベルのエディ・ゴメスとのピアノトリオ作やゲイリー・ピーコックとのデュオ作品が、素晴らしい出来だったのでそれ以来ファンとなったのだけれど、寡作なアーティストの様で、忘れた頃に新作がリリースされるといった感じで、このアルバムも店頭で見つけて直ぐに買い込んだ。
ガードナーにしては珍しく菅入りの作品で、サックスにはRICK MARGITZA,トランペットにはINGRID JENSENが参加している。
JEFF GARDNERがPAUL AUSTERの小説に感銘を受け、そこからインスパイアされて作曲された作品が演奏されている。
さすがはジェフ・ガードナー、全編詩的なストーリー性、抒情性を連想させつつジャズ的な躍動感が織り込まれたコンポジションになっているのだ。
本人の硬質でありながらビターテイストな叙情性を感じさせるピアノプレイはもとより、サイドメンの個性を殺すことなしにその音楽的力量を最大限に発揮させて自身の音楽を表現しきっているところが素晴らしいと思う。
RICK MARGITZAは元来器用なミュージシャンだと思うがここでも、その役割を充分果たしていてこの作品のカラーバリエーションを高めていると言えよう。
DREW GRESSとTONY JEFFERSONとのピアノトリオは最高のコンビネーションを発揮していてフレキシブルな演奏によるベルベットの絨毯の上を二菅のフロント陣がスムースに滑走するような様は、ガードナー自身してやったりと言うところだろう。
ポール・オースターの小説を読んだ事はないのだけど、このアルバムのタイトル「精霊」「偶然の音楽」「月の場所」「草の街」「夜の旅」を見ていたら読んでみたくなってきた。
メンバーはJEFF GARDNER(P)INGRID JENSEN(TP)RICK MARGITZA(TS)DREW GRESS(b)TONY JEFFERSON(ds)
録音は1999年6月 NYC

アルゼンチンのユニークなピアニスト、ERNESTO JODOSの2001年作品。
通常のトリオフォーマットではなくて、チェロ、パーカッションでのピアノトリオという点がERNESTOらしい。
ERNESTOがこの作品で表現している音楽は、いわゆるオーソドックスなジャズピアノトリオではない。パウエルやエヴァンス、キースのような一般的なピアノトリオとはテイストが根本的に違うのだ。
ポール・ブレイが最も近い存在かもしれない。
通常のジャズ演奏におけるアドリブ志向の部分より、全体のサウンドを有機的に自身の考え思い描いている「絵」に近づけ、響かせることを優先していると思うのだ。
勿論、ERNSTOのピアノの技量は素晴らしく繊細で様々の光を発することのできる表現力に長けた存在なのだけれど、そういう各論的な(という言葉が適当かどうか分からないが)ことより、音楽全体の響き、融合性みたいな総論的なことが重視されている様に思えてならない。
アルコによるチェロの調べにERNESTOの色彩感豊かで煌びやかなピアノのフレーズやコードが乗っかり、それはやがてピッチカートによるリズムを発しだしたリズムにパーカッションのカレイドスコープのような装飾音とともに三本の違った糸が自然発生的に絡み合いやがて有機的に結合して太い一本の糸になるかのような印象を与える。
演奏する前からその「音」があったかのようなプリミティブなサウンド、それはあたかも湖上の白鳥が一見優雅に泳いでいるように見えて、水の下では猛烈に足を漕いでいるのと同じ様に、ナチュラルで美しい響きを編み出す為に3人のミュージシャンのテレパシーと言ってもよいほどの音楽的交感に裏づけされたものによるものだと・・・
メンバーはERNESTO JODOS(P)MARTIN LANNACCONE(CELLO)SERGIO VERDINELLI(PER)
録音は2000年12月 BUENOS AIRES

今から4年前にリリースされたスウェーデンのテナー奏者KARL MARTIN ALMQVISTの作品。
それより何年か前にリリースされたMATHIAS LANDAEUSの「BLABETE」での好演を記憶していたこともあり、リーダー作はどんなものか聴いてみようという気になったのだ。
ピアノにはJAN LUNDGRENが参加していることも購買意欲をかきたてた。
ALMQVISTのサックスは鋭角的でメタリックなトーンではなくどちらかと言うと木の温もりがするマイルドでまろやかな幾分ハスキーな成分も含んでいる音色で、その音色を武器にスローナンバーは、思索的で北欧的な叙情感も漂わせながらプレイするかと思ったら、アップテンポでは、モーダルなコルトレーンライクなマナーでコニッツ流のクールネスを加味しつつ鋭角的なフレーズをマイルドなトーンで吹き綴っていくところなど強烈な個性に欠けるとはいえ有能ぶりを見せつける。
ただ、アルバムの中で一番個性的で、印象に残るプレイをしているのは、JAN LUNDGRENだと思う。JAN LANDGRENのまるでマッコイ・タイナーが乗り移ったのではないかと思わせるような鬼気迫る演奏を聴いたのは初めてだ。
もともと、唄ものやハードバップスタイルのスインギーでチャーミングなフレーズをまじえつつ良く唄うプレイが特徴のLUNDGRENが、こういうモードプレイでも非凡なところを披露するのを聴いて改めてこのピアニストの才能を見直したほど。
どんなスタイルでも素晴らしいピアノを弾けるのだ。
ただ、本人の売りのスタイルがハードバップスタイルなのだ。
1曲だけオリジナル以外のナンバーが演奏される。
タッド・ダメロンの名曲「ON A MISTY NIGHT」。
ウォーン・マーシュを彷彿させるクールな吹奏ぶりにところどころジョー・ロバーノの現代的なフレーズが混じって、全体的にはほのぼのした雰囲気にまとめ上げているところなど、聴いていて中々良いのではないかと思う。
メンバーはKARL-MARTIN ALMQVIST(TS)JAN LUNDGREN(P)FILIP AUGUSTSON(B)SEBASTIAN VOEGLER(DS)
録音は2000年8月31日9月1,2日
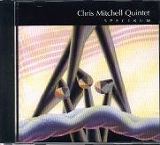
カナダのサックス奏者CHRIS MITCHELLのネオ・バップ作品。
ピアノレスでサックス2本トランペットの3菅編成で音に厚みがあり迫力がある。
メンバーの知名度はリズムセクションの方が有名だろう。
ベースがNIEL SWAINSON,ドラムスがJERRY FULLERの2人が担当している。
CHRIS MITCHELLのバリトンは音圧があってゴリゴリ、バリバリ吹くところなんか、ペッパー・アダムスやニック・ブリグノラを彷彿させ1曲目から迫力のあるところを見せる。テナーのKIRK MACDONALDもコルトレーン以降の伝統的なテナー技法を消化したスタイルで軽快なアクション技を交えつつ活きのいいプレイを展開。
3曲目はゲストのLORNE LOFSKYのボッサリズムのイントロから始まるマクドナルドの佳曲。LOFSKYはジム・ホールのようなトーンの音色で奥ゆかしい歌心のあるプレイをして印象に残る。テナーとアルトで奏されるテーマが結構いけてると思う。
4曲目はダークな雰囲気のするスローナンバーで、STEVE MCDADEのミュートトランペットが活躍する。
バンドのメンバーで誰一人スターはいない。にもかかわらず聴いていて飽きがこないのはメンバーの音楽的技量の足並みが揃っていることと、バラエティー豊かな曲調、チームワークの良さ、そしてベース、ドラムのリズムの要がとてもしっかりしているからであろう。
地味で、目立たない作品だけれども、良いアルバムだと思う。
メンバーはCHRIS MITCHELL(BS,AS,SS)KIRK MACDONALD(TS)STEVE MCDADE(TP,FLH)NIEL SWAINSON(B)JERRY FULLER(DS)
録音は1999年11月19,20 MONTREAL

今から4年前の夏、「サニーサイド・レコード」から手に入れたドイツのORGNIC MUSICからリリースされたハードバップ作品。
リーダーのJOHN MARSHALLの名前は以前ジェシー・デイビスを迎えたMONS盤を持っていて馴染みがあり、それが結構良かったのでこの作品も買う気になったのだ。
メンバー全員がハードバップを愛しているのが分かる演奏。
愛があるから、そこに喜びがある。演奏するのが楽しくて楽しくて仕方ないといった雰囲気に溢れている。そういう演奏だから音にまやかしがなくて説得力があるのだ。
リーダーJOHN MARSHALLは中音域がぶ厚く音に張りのある典型的なハードバップタイプのトランペッターだと思う。セコセコしていなくて大きく歌うことのできる職人気質のプレイヤーとみた。テナーのFERDINAND POVELとの相性もよく楽曲が活きるフロントを形成している。ピアノのTARDO HAMMERはこの当時はまだ知る人ぞ知る存在だったとはずだけど、才能の片鱗は充分に見受けられる滋味深いプレイを披露している。選曲も凝っていてビリー・ストレイホーンの珍しいバラード「BALLAD FOR VERY SAD AND VERY TIRED LOTUSEATERS」なんてマニアックな曲を取り上げていたりする。TADD DAMERON3曲、GILLESPIE1曲、DORHAM1曲に「SO IN LOVE」や「SWEET AND LOVELY」などスタンダードを数曲あわせた構成。
マニアも初心者も一緒になって楽しめる現代ハードバップの秀作だと思う。
メンバーはJOHN MARSHALL(TP,FLH)FERDINAND POVEL(TS)TARDO HAMMER(P)JOHN LDSBY(B)DOUG SIDES(DS)
録音は2000年8月2,3,4日
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- 一般投票で選ばれた35曲 ZARD Best …
- (2024-11-14 00:31:45)
-
-
-

- 人気歌手ランキング
- ランキングの入れ替日
- (2024-11-24 10:01:24)
-
© Rakuten Group, Inc.